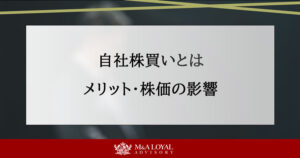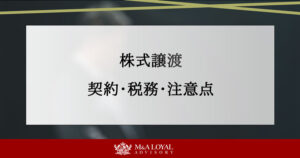株式譲渡承認請求書とは?書き方や手続きの流れ、注意点を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
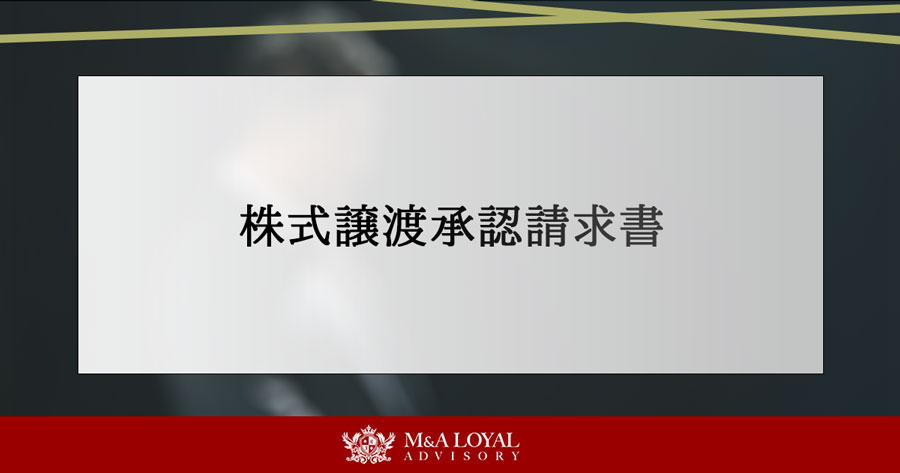
株式譲渡承認請求書とは、会社の株式を第三者に譲渡する際に必要となる重要な書類です。特に非公開会社では、株主が自身の株式を他者に譲渡する際、会社の承認を得るためにこの請求書を提出することが求められます。株式譲渡承認請求書は、適切な書き方や手続きが求められ、これを怠るとトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、株式譲渡承認請求書の書き方、手続きの流れ、注意点など中小企業の経営者向けに詳しく解説します。
目次
株式譲渡承認請求書の基本知識
株式譲渡承認請求書は、譲渡制限株式を第三者に譲渡する際に必要となる書類です。まずは、この請求書が必要となる背景や法的位置づけについて理解しましょう。
株式譲渡承認請求書とは何か
株式譲渡承認請求書とは、譲渡制限株式を保有する株主が、自分の株式を第三者に譲渡したい場合に、会社に対して譲渡の承認を求めるために提出する正式な文書です。特に非公開会社(株式譲渡に制限を設けている会社)では、株主の意図しない第三者の参入を防ぐために、この承認プロセスが重要な役割を果たします。
この請求書は単なる形式的な書類ではなく、会社法上の株主権利行使手段であり、承認プロセスの起点となる文書です。株主はこの請求書を提出することで、会社に対して承認・不承認の判断を法的に求める権利を行使します。
なぜ株式譲渡承認請求書が必要なのか
株式譲渡承認請求書が必要となる理由は、会社法の基本原則と非公開会社の特性に関係しています。会社法第127条では「株式の譲渡自由の原則」が定められており、本来、株主は自由に株式を譲渡できるとされています。
しかし、非公開会社では、定款で「譲渡制限株式」を発行することを定め、株式の譲渡に会社の承認を要する旨を規定することができます。これにより、会社は望まない第三者の株主としての参入を防ぎ、経営の安定や会社の独立性を守ることができるのです。
株式譲渡承認請求書は、この「譲渡制限」と「株式譲渡自由の原則」のバランスを取るための法的手続きであり、株主の権利と会社の利益を両立させる重要な仕組みとなっています。
法的根拠と関連条文
株式譲渡承認請求書の提出と承認プロセスは、会社法に明確な法的根拠を持っています。以下に主要な関連条文を整理します。
| テーマ | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 株式譲渡自由の原則 | 会社法第127条 | 株主は株式を自由に譲渡できる基本原則 |
| 譲渡制限株式 | 会社法第107条1項1号、第108条1項4号 | 譲渡制限株式の発行・設定に関する規定 |
| 承認請求権 | 会社法第136条 | 株主が会社に対して株式譲渡の承認を請求できる権利 |
| 承認機関 | 会社法第139条 | 承認の決定は取締役会(または株主総会)が行う |
| みなし承認 | 会社法第145条 | 請求から2週間以内に通知がない場合や不承認後の手続きを怠った場合の自動承認 |
| 不承認時の救済 | 会社法第140条 | 不承認の場合、会社または指定買取人による買取義務 |
| 価格決定 | 会社法第144条 | 買取価格の協議・決定方法 |
これらの条文が複合的に機能することで、株主の権利保護と会社の利益保護のバランスが保たれる仕組みとなっています。株式譲渡承認請求書はこの法的枠組みの中で、プロセスを正式に開始するための文書として位置づけられています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式譲渡承認請求書が必要となる場面
株式譲渡承認請求書は特定の状況下で必要となります。どのような場面で請求書を提出する必要があるのか、また、どのような会社で必要とされるのかを理解しておきましょう。
非公開会社における株式譲渡
株式譲渡承認請求書が必要となるのは、非公開会社の株式を譲渡する場合です。非公開会社とは、定款で株式の譲渡制限を設けている会社を指し、多くの中小企業や同族会社がこれに該当します。
非公開会社では、株主構成の安定性維持のため、株式の第三者への流出を防ぐ承認制度が中核となっています。株主が持株を他者に譲渡したい場合、まず会社に対して承認請求書を提出し、会社(取締役会または株主総会)の判断を仰ぐ必要があります。
具体的には、以下のような場面で株式譲渡承認請求書が必要となります。
- 事業承継のために同族内で株式を移転する場合
- 資金調達や戦略的提携のために外部投資家に株式を売却する場合
- 株主が個人的な資金需要から株式を現金化したい場合
- 相続により取得した株式を第三者に譲渡する場合
公開会社と非公開会社の違い
株式譲渡承認請求書の必要性を理解するためには、公開会社と非公開会社の根本的な違いを把握することが重要です。
公開会社とは、株式の譲渡制限を設けていない会社であり、株主は原則として自由に株式を譲渡することができます。上場企業はもちろん、未上場でも株式譲渡に制限を設けていない会社は公開会社に分類されます。このような会社では、基本的に株式譲渡承認請求書は不要です。
一方、非公開会社は定款で「株式を譲渡により取得するには、会社の承認を要する」旨を定めています。これにより、会社は株主の変動をコントロールし、意図しない第三者の経営参加を防ぐことができます。中小企業の多くはこの非公開会社の形態を採用しており、株式譲渡には会社の承認が必要となります。
事業承継・M&Aにおける重要性
株式譲渡承認請求書は、事業承継やM&Aのプロセスにおいても重要な役割を果たします。中小企業の経営者が事業承継や会社売却を検討する場合、株式譲渡の手続きは選択肢の一つとなります。
事業承継においては、現経営者から後継者(家族や従業員など)への株式移転が必要となりますが、非公開会社の場合、この移転にも会社の承認が必要です。特に複数の株主が存在する場合は、他の株主の意向も反映される承認プロセスが重要になります。
M&Aには、会社売却を実行する手法として株式譲渡があります。買収側は対象会社の株式を取得することで経営権を獲得しますが、非公開会社の場合、この株式取得には会社の承認が必要です。M&Aのスキームや交渉過程によっては、株式譲渡承認請求書の提出とその承認が取引完了の重要な条件となることもあります。
また、M&Aの過程で株主間の利害調整が必要となるケースでも、株式譲渡承認プロセスが重要な役割を果たします。特に不承認となった場合の買取手続きや価格決定は、売り手と買い手の交渉に大きな影響を与えることがあります。
株式譲渡承認プロセスの流れ
株式譲渡承認請求書の提出から始まる承認プロセスには、明確な流れと法定期限があります。このプロセスを正確に理解することで、スムーズな株式譲渡を実現できます。
承認請求書の提出から決議まで
株式譲渡承認プロセスは、株主による承認請求書の提出から始まります。この段階では、譲渡を希望する株主が正式に会社に対して承認を求める意思表示を行います。
承認請求書が会社に到達すると、会社はその内容を確認し、承認するかどうかの判断を行います。この判断は、取締役会設置会社であれば取締役会で、取締役会を設置していない会社であれば株主総会で行われるのが原則です(ただし、定款で別段の定めがある場合はそれに従います)。
会社法上、会社は承認請求を受けてから2週間以内に、承認するかしないかの決定と、その旨の通知を株主に行わなければなりません。この2週間という期間は非常に重要で、この期間内に通知がなされないと「みなし承認」となり、会社が承認したものとみなされます。
承認決議のポイントは以下の通りです。
- 取締役会での決議は過半数の賛成で可決(定款で別段の定めがない限り)
- 株主総会での決議は普通決議(議決権の過半数の賛成)で可能
- 定款で承認機関や決議要件を別途定めることも可能
- 決議の際は、譲受人の属性や譲渡の目的、会社への影響などを総合的に判断
承認された場合の手続き
会社が株式譲渡を承認した場合、株式譲渡を完了させるためにいくつかの手続きが必要となります。承認通知を受けた後、株主と譲受人は以下の手続きを進めます。
まず、株式譲渡契約を締結し、株式の対価の支払いなど契約上の義務を履行します。契約内容や対価の決定は当事者間の合意によりますが、適正な価格設定が重要です。
次に、株式の名義書換手続きを行います。これは株主名簿上の記載を変更するもので、譲渡人から譲受人へと株主の名義を書き換える手続きです。この手続きには、一般的に以下の書類が必要となります。
- 株式名義書換請求書
- 株式譲渡承認通知書(会社からの承認通知の写し)
- 株式譲渡契約書(写し)
- 譲渡人・譲受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 株券(株券発行会社の場合)
名義書換が完了すると、譲受人は正式に株主としての地位を取得し、株主権を行使できるようになります。株主名簿に記載されることで、配当金の受領や株主総会での議決権行使などが可能となります。
不承認の場合の対応策
会社が株式譲渡を承認しない決定をした場合、株主は株式を譲渡できなくなるわけではありません。会社法では、譲渡制限株式の株主保護のために、不承認の場合の救済措置が設けられています。
不承認通知を受けた株主には、以下の選択肢があります。
第一に、会社自身に株式を買い取るよう請求することができます(株式買取請求権)。会社が不承認を通知する際には、会社自身が買い取るか、他の買取人を指定するかを株主に通知する必要があります。会社が自ら買い取る場合、特別決議など必要な手続きを経て、適正な価格で買い取りを行います。この場合、不承認の通知から40日以内に会社は買取通知を行うことが義務付けられています。
第二に、会社が指定する「指定買取人」に株式を売却することができます。指定買取人は不承認通知の日から10日以内に株主に対し通知を行う必要があります。
買取価格について当事者間で協議が整わない場合、不承認通知から20日以内に裁判所に対して価格決定の申立てを行うことができます。この申立てがない場合は、純資産額×買取株式数で価格が算定されます。
なお、会社が不承認の通知をしたにもかかわらず、その後の買取手続きを法定期間内に行わなかった場合は「みなし承認」となり、当初予定していた第三者への譲渡が承認されたものとみなされます。
みなし承認とは何か
「みなし承認」とは、一定の条件が満たされた場合に、会社が明示的に承認していなくても法律上は承認したものとみなされる制度です。これは株主保護のための重要な仕組みで、会社側の不作為によって株主の株式譲渡の権利が不当に制限されることを防ぐ役割を果たします。
みなし承認が発生するケースは主に以下の2つです。
第一に、株主からの承認請求書提出後、会社が2週間以内に承認・不承認の通知を行わなかった場合です。この場合、2週間の経過により自動的に承認されたものとみなされます。
第二に、会社が不承認の通知をしたにもかかわらず、その後の法定手続き(会社自身による買取りや指定買取人の指定など)を適切に行わなかった場合です。具体的には、不承認通知後に会社が買い取る場合は40日以内に必要な手続きを完了する必要があり、これを怠ると「みなし承認」となります。
みなし承認は会社側にとってリスクとなる場合があります。会社が望まない第三者が自動的に株主となる可能性があるためです。そのため、承認請求書を受け取った会社は、法定期限を意識して迅速に対応することが重要です。特に中小企業では、日常業務に追われて期限管理が疎かになりがちですが、カレンダーやリマインダーを活用して確実に対応することが求められます。
株式譲渡承認請求書の作成方法と書き方
株式譲渡承認請求書を作成する際には、必要事項を漏れなく記載し、適切な書式で提出することが重要です。ここでは、具体的な作成方法と記載すべき内容について解説します。
基本的な記載事項
株式譲渡承認請求書には、譲渡の意思表示と承認を求める旨を明確に記載する必要があります。基本的な記載事項は以下の通りです。
まず、文書のタイトルとして「株式譲渡承認請求書」と明記します。次に、請求日(文書作成日)を記載し、宛先として対象会社の正式名称と代表取締役名を記入します。
請求者(譲渡株主)の情報として、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、住所、連絡先を記載します。また、保有している株式に関する情報として、株式の種類、数量、株券番号(株券発行会社の場合)などを明記します。
そして、「下記の通り株式を譲渡したいので、会社法第136条に基づき承認を請求します」といった承認請求の趣旨を明確に記載します。株式の譲渡先に関する情報として、譲受人の氏名(法人の場合は名称と代表者名)、住所、連絡先を記入します。
また、譲渡予定日や譲渡の条件(譲渡価額など)についても記載することが一般的です。最後に、請求者の記名・押印(実印が望ましい)を行います。
株式譲渡承認請求書のひな形と記入例
以下に、株式譲渡承認請求書のサンプル書式の主要項目を示します。このフォーマットを参考に、自社の状況に合わせてカスタマイズすることができます。
| 項目 | 記入例 | 備考 |
|---|---|---|
| 文書タイトル | 株式譲渡承認請求書 | 中央上部に大きく記載 |
| 日付 | 2023年10月1日 | 請求日を記載 |
| 宛先 | 株式会社○○ 代表取締役 ○○○○ 殿 | 会社の正式名称と代表者 |
| 請求者情報 | 住所:東京都○○区○○1-2-3 氏名:○○○○ 印 | 法人の場合は法人名・代表者名 |
| 請求趣旨 | 私は、下記の通り所有株式を譲渡したいので、会社法第136条に基づき貴社の承認を請求いたします。 | 承認請求の法的根拠を明示 |
| 株式情報 | 1. 譲渡株式:普通株式 100株 2. 株券番号:第○○号~第○○号 | 株式の種類・数量を明記 |
| 譲受人情報 | 住所:東京都△△区△△4-5-6 氏名:△△△△ | 譲受人の正確な情報を記載 |
| 譲渡条件 | 1. 譲渡予定日:2023年11月1日 2. 譲渡価額:金○○○○○円(1株あたり○○○円) | 必要に応じて記載 |
| 不承認時の意向 | 本請求が不承認の場合は、会社法の規定に基づき、貴社または貴社の指定する者による買取りを希望します。 | 任意記載事項 |
実際の記入に際しては、自社の状況や譲渡の具体的な条件に合わせて、必要な情報を過不足なく記載することが重要です。また、会社によっては独自の書式を指定している場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
添付書類の準備
株式譲渡承認請求書を提出する際には、請求書本体に加えて、いくつかの添付書類が必要となることもあります。これらの書類は、譲渡の真正性を証明し、会社が適切な判断を行うための重要な資料となります。
一般的に必要となる添付書類は以下の通りです。
まず、譲渡人(請求者)の印鑑証明書が必要です。これは請求書に押印された印鑑の真正性を証明するもので、発行後3ヶ月以内のものが望ましいとされています。特に実印を使用する場合は、この印鑑証明書が重要な証明書類となります。
次に、譲受人の住民票または印鑑証明書が求められることがあります。これは譲受人の身元確認のための書類で、特に個人間の譲渡の場合に重要です。譲受人が法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要となる場合もあります。
また、株券発行会社の場合は、譲渡対象となる株券の写しを添付することもあります。これにより、譲渡対象株式の確認が容易になります。
さらに、譲渡の背景や目的を説明する「株式譲渡理由書」を添付することで、会社の判断材料となる情報を提供できます。特に戦略的な理由や事業承継などの背景がある場合、これを明確に説明することで承認の可能性を高めることができます。
なお、会社によっては独自の添付書類を求める場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。特に譲受人が外国法人や外国人である場合、追加の身元確認書類が必要となることがあります。
押印と本人確認の重要性
株式譲渡承認請求書の作成において、押印と本人確認は特に重要な要素です。適切な押印と本人確認が行われないと、請求の有効性に疑義が生じる可能性があります。
押印については、法律上は実印の使用が絶対的に必要というわけではありませんが、多くの会社では実印の使用を求めています。これは、株式譲渡が重要な財産権の移転を伴うためであり、本人の意思確認を確実に行うためです。実印を使用する場合は、印鑑証明書との照合によって本人確認が行われます。
一方で、近年のデジタル化の流れを受けて、電子署名による株式譲渡承認請求も認められつつあります。電子署名法に基づく電子署名は、一定の条件を満たせば手書き署名や押印と同等の法的効力を持つとされています。ただし、会社側がこの方法を受け入れる体制が整っているかどうかを事前に確認する必要があります。
本人確認は不正な株式譲渡防止に重要です。高額取引や経営権に関わる譲渡では、厳格な確認が一般的です。実印と印鑑証明書の組み合わせに加えて、対面での確認や公的身分証明書の提示を求められることもあります。
また、法人間の株式譲渡の場合は、譲渡の意思決定が適切な社内手続きを経ているかどうかの確認も重要です。取締役会議事録や株主総会議事録などの提出を求められることもあります。
株式譲渡承認請求書作成・提出時の注意点
株式譲渡承認請求書を作成・提出する際には、いくつかの注意点があります。これらを事前に理解し、適切に対応することで、スムーズな株式譲渡プロセスを実現できます。
記載内容の正確性
株式譲渡承認請求書の記載内容の正確性は、承認プロセスの円滑な進行と法的有効性を確保するために不可欠です。不正確または不十分な記載は、承認の遅延や無効化のリスクを高めます。
特に重要なのは、譲渡株式の正確な特定です。株式の種類(普通株式、優先株式など)、数量、株券番号(株券発行会社の場合)を正確に記載する必要があります。株式数や種類の誤りは、承認後の名義書換時に問題を引き起こす可能性があります。
また、請求書の日付は重要な起算点となるため、実際に会社に提出する日付を記載することが望ましいです。事前に作成した場合は、提出時に日付を修正するか、提出日を別途明記することを検討してください。
会社側の対応と準備
株式譲渡承認請求書を受け取った会社側も、適切な対応と準備が求められます。特に中小企業では、このような請求を受ける機会が少ないため、事前の準備と理解が大切です。
まず、請求書を受け取ったら、受領日を明確に記録し、2週間の法定期限を確認します。その上で、取締役会(または株主総会)の開催準備を進め、承認・不承認の判断を行うための資料を準備します。判断の際は、譲受人の属性や譲渡の目的、会社への影響などを総合的に検討します。
承認・不承認の決定後は、速やかに通知を行う必要があります。通知書には決定内容と日付を明記し、不承認の場合は、会社が買い取るか指定買取人を指定するかの意向も明記します。通知は確実に相手に届く方法(配達証明付き郵便など)で送付することが望ましいです。
また、株式譲渡承認請求に関する一連の文書(請求書、決議書、通知書など)は適切に保管し、後日の紛争を防止するための証拠として管理することが重要です。
まとめ
株式譲渡承認請求書は、非公開会社における株式譲渡の第一歩となる重要な文書です。この請求書を起点として、会社による承認判断、承認後の名義書換または不承認時の買取手続きへと進むプロセスが展開されます。
非公開会社の株主が株式を第三者に譲渡したい場合、まず会社に対して承認請求書を提出し、会社の判断を仰ぐ必要があります。株式譲渡請求が行われた場合、会社は2週間以内に承認・不承認の判断と通知を行わなければならず、これを怠ると「みなし承認」となり、請求を承認したものとなります。
請求書作成時には、譲渡株式の正確な特定、譲渡人・譲受人の情報、譲渡条件などを正確に記載し、適切な押印と本人確認を行うことが重要です。また、承認プロセス全体を通じて、複数の法定期限を適切に管理することがトラブル防止の鍵となります。
株式譲渡は事業承継やM&Aにおける手法の一つであり、このプロセスを理解し適切に対応することは、中小企業の経営者にとって経営戦略上の重要な知識となります。専門家のアドバイスを適宜受けながら、慎重かつ計画的に進めることをお勧めします。
会社売却や事業承継の際には、株式譲渡だけでなく様々な法的・税務的な検討が必要となります。専門家に相談することで、最適なスキームの選択や適正な価値評価、手続きの適切な進行などのサポートを受けられます。M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。