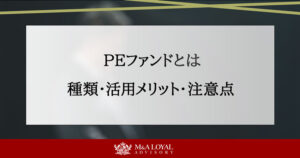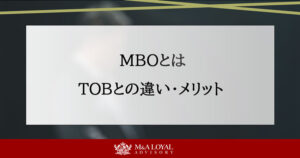株式非公開化とは?目的やメリット、事例、株はどうなるかなど解説!
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
株式非公開化は、企業戦略として注目されていますが、その目的やメリットを詳しく知る人は少ないかもしれません。本記事では、株式非公開化の基本的な定義や背景、そして株の行方について解説します。上場企業が非公開化を選択する理由には、経営の自由度向上や株主からの圧力軽減がありますが、デメリットも存在します。この記事を通じて、非公開化の成功事例や失敗事例を学び、企業や株主に与える影響を把握し、最適な判断を下すための指針を提供します。株式非公開化のプロセスを知ることで、ビジネス判断に新たな視点を加えてみましょう。
目次
株式非公開化とは?
株式非公開化とは、上場企業が株式を市場から引き上げ、非公開企業として運営することです。本項では、株式非公開化の基本について解説します。
意味と実施される背景
株式非公開化とは、上場企業が株式市場から撤退して、株式を一般の投資家が売買できない状態にすることです。これにより、株主が限られた人や団体に絞られ、経営陣が株主への対応を減らし、長期的な経営に集中できるようになります。また、外部からの買収リスクを減らし、経営権を強化する目的でも行われます。簡単に言えば、会社を「みんなで持つ」から「特定の人たちで持つ」に変える仕組みです。
特に、市場が不安定だったり、規制コストが重荷になったりする場合、経営陣は迅速かつ柔軟な意思決定を求められます。このような状況で非公開化が選択されることが多いのです。また、プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)や経営陣自身が会社を完全に所有したい場合にも、株式非公開化が実施されます。
非公開化により、企業は株主の多様な利害関係を調整する必要がなくなり、特定の投資家や経営陣のビジョンに沿って成長を目指せるようになります。しかし、非公開化には買収資金の調達や既存株主との交渉が必要で、プロセスは複雑です。そのため、企業は法的および経済的な要因を考慮し、慎重に計画を立てることが重要です。株式非公開化は、企業にとって重要な戦略的決断の一つとなります。
上場と上場廃止の違い
株式の上場と上場廃止は、企業の株式が市場で取引されるかどうかを示す分類です。上場とは、企業が株式を公開して、投資家が自由に売買できるようになる状態のことです。上場により、企業は資金を調達しやすくなり、知名度や信用度も向上します。ただし、上場するためには、証券取引所の厳しい基準を満たさなければならず、一例として財務の透明性やガバナンスの強化などが求められます。
一方で、上場廃止とは、企業が株式を市場から引き上げることです。上場廃止によって、企業は経営の自由度を高められるほか、長期的なビジョンを達成するための再編成の一環として行われることがあります。また、規制や基準を満たせない場合も、上場廃止の原因となります。上場廃止後、企業は非公開企業となり、株式の売買は一般の投資家には難しくなります。しかしその分、株主との関係が密接になり、長期的な視点で経営ができるのです。
上場と上場廃止のどちらを選ぶかは、企業の資金調達や経営方針に大きな影響を与えます。その選択は市場の状況や企業の成長戦略によって異なりますが、どちらも企業の未来にとって重要なステップであることに変わりはありません。
非公開になった株はどうなる?
株式非公開化とは、企業が株式を市場で自由に売買されない状態にすることです。この変化により、株主には大きな影響があります。
まず、非公開化が決まると、企業は既存株主に株式を買い取る提案をします。買い取り価格は通常、現在の市場価格よりも高く設定される場合が多く、株主はその提案を受け入れるか拒否することができます。このプロセスにより、企業は既存株主から株式を回収し、株主を限定的な人々に絞り込みます。
次に、非公開化されると、企業の株を持つ人は経営陣や特定の大株主などに限られるようになります。これにより、企業の意思決定が迅速化する可能性がありますが、情報公開や透明性が減少する傾向があります。また、従来のように株式市場で自由に売買することはできなくなるため、株の流動性が低下します。
さらに、非公開化後の株式は、売買が非常に制限されます。基本的には株主間で個別交渉を行う形が一般的であり、市場での取引はほぼ不可能になります。そのため、株主は株式の流動性や価値の変動を慎重に考慮して判断する必要があります。
これらの点を理解することで、株式非公開化が企業や株主に与える影響をより深く考えることができます。
株式非公開化の目的
株式非公開化にはいくつかの目的があります。企業が公開市場から撤退するのは、経営の柔軟性を高めたり、短期的な株主のプレッシャーを軽減したりするためです。ここでは、株式非公開化が選ばれる主な目的について詳しく説明します。
企業が実施する理由とメリット
企業が株式を非公開化する理由とメリットはさまざまですが、主に以下のようなものがあります。
株主の影響を減らしたい
上場企業は株主の利益を最優先に考える必要がありますが、これは短期的な利益を追い求める圧力につながることがあります。株式を非公開にすることで、経営陣は長期的な視点で会社の戦略を立てやすくなり、持続可能な成長を目指せます。ただし、非公開化後も特定の株主(創業者や主要投資家)が存在する場合があるため、完全に株主の影響がなくなるわけではありません。
株価の変動を避けたい
上場企業は市場の動きに大きく影響され、企業の本当の価値が正しく評価されないこともあります。非公開化することで、市場の影響を受けずに、企業の実力に基づいた経営が可能となります。
経営情報の保護
上場企業は決められた情報を公開しなければなりませんが、これが競争相手に有利な情報を与えることがあります。非公開化することで、必要な情報だけを開示し、企業の競争力を守りやすくなります。
コストの削減
上場企業は報告書の作成などに多額の費用をかける必要があります。非公開化によって、これらのコストを削減し、他の重要な分野にリソースを当てることができます。ただし、非公開化に伴う上場廃止手続きには一定の費用が発生する点も考慮する必要があります。
企業の再編を容易にする
非公開化することで、株主の承認を得ずに迅速に組織変更ができ、競争力を高めるための施策を迅速に実行できます。例えば、子会社化や事業売却などの再編がスムーズに進む可能性があります。
これらの理由により、企業は株式非公開化を検討することがあります。
課題やデメリット
株式非公開化にはいくつかの課題やデメリットも存在します。
時間とコストの負担
株式を非公開化するプロセスは時間とコストがかかります。法的手続きや株主への説明、同意取得など、多くのステップを経る必要があり、そのための準備や実施には資金と時間が必要です。
資本調達の制限
非公開化後は資本調達の手段が制限されます。上場企業は株式市場を通じて資金を調達できますが、非公開企業になるとその選択肢が狭まり、外部からの資金注入が得にくくなる可能性があります。
透明性の減少
透明性の減少も懸念されます。上場企業は定期的に財務状況や経営方針を公開する義務がありますが、非公開企業になるとその義務が軽減されるため、情報の非対称性が生じやすくなります。これにより、ステークホルダーとの信頼関係が損なわれるリスクがあります。
株価評価と株主対立
非公開化に伴う株価の評価や、株主からの買い取り価格の設定が難航することもあります。株主が納得する価格を設定するためには、公正な評価が求められますが、それが難しい場合、株主との間で対立が生じる可能性があります。
経営陣の自己利益優先のリスク
企業の経営陣が非公開化を主導する際、マネジメント・バイアウト(MBO)などで自己利益を優先する行動を取るリスクも考慮すべきです。このような行動は、残りの株主や従業員にとって不利に働く可能性があるため、慎重な判断が求められます。
以上のように、株式非公開化は企業にとって戦略的な選択である一方で、多くの課題とデメリットを伴うため、実施に際しては十分な検討と準備が不可欠です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式非公開化の流れ
株式非公開化は、企業が株式を上場市場から撤退させ、非公開企業として再スタートを切るプロセスです。このプロセスは慎重に計画され、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、その基本的な流れを解説します。
一般的なプロセス
株式非公開化とは、企業が株式市場から上場を廃止し、一般の投資家から株式を切り離すプロセスのことです。このプロセスにはいくつかのステップがあります。
まず、企業は非公開化する意図を発表し、株主にその理由や計画を説明します。この際、非公開化による企業の戦略的な利点を強調することが重要です。
次に、非公開化に必要な資金を調達します。通常、銀行からの融資やプライベートエクイティから資金を得て、株式を買い戻すために使います。この段階では、資金調達の条件や返済プランをしっかりと考える必要があります。
その後、企業は株主に対して株式の買い取りを提案します。ここでは、買い取り価格が適正であることを確認するために、第三者の評価機関が価格の評価を行うことが一般的です。株主は提示された価格を元に、株式を売却するかどうかを決めます。
次に、企業は株式市場からの上場廃止を申請します。証券取引所の規定に従って必要な手続きを終えると、正式に上場が廃止されます。この過程では、規制当局とのしっかりしたコミュニケーションが求められます。
最後に、非公開化が完了すると、企業は新しい所有構造での運営を開始します。この段階では、非公開企業としてのガバナンス体制を整え、長期的な成長戦略を立てます。これにより、企業は市場の短期的な圧力から解放され、より柔軟な経営を行うことが可能になります。
マネジメント・バイアウト(MBO)とは?
マネジメント・バイアウト(MBO)は、企業の経営陣が自社の株式を買い取り、会社を非公開化する手法の一つです。これは、経営陣が会社の所有権を取得し、株式市場から撤退することで、長期的な経営戦略を柔軟に実行できる環境を整えることを目的としています。MBOは通常、外部投資家や金融機関からの資金調達を伴い、経営陣が主導権を持ちながらも、投資家の利益を考慮する必要があります。
この手法が選ばれる背景には、会社の成長戦略や再編成に伴う外部の短期的な利益圧力からの解放を目指すケースが多く見られます。また、株式市場のボラティリティ(価格の変動幅や不安定さのこと)や外部からの敵対的買収のリスクを避けるためにも利用されます。マネジメント・バイアウトを実施することで、経営陣は株主の意向に左右されずに、独自のビジョンに基づいた企業運営が可能となるのです。
しかし、マネジメント・バイアウトにはリスクも伴います。まず、経営陣が自身の資金や借入金を用いて株式を買い取るため、財務負担が増加する可能性があります。また、外部投資家との間で利益分配や経営方針に関する意見の相違が生じることもあります。さらに、マネジメント・バイアウト後の経営が期待通りに進まなければ、企業価値の低下や財務問題に直面するリスクもあります。
このように、マネジメント・バイアウトは経営陣が自らのビジョンを実現するための強力な手段である一方、慎重な計画とリスク管理が求められる手法でもあります。企業がこの方法を選択する際には、長期的な戦略と財務状況の分析が重要となります。
株式非公開化の事例と影響
ここでは、株式非公開化の具体的な事例を挙げ、その影響について詳しく解説します。企業がなぜこのような決断をするのか、そしてそれがどのような結果をもたらすのかを見ていきましょう。
過去の成功事例と失敗事例
成功事例:株式会社すかいらーくの場合
株式非公開化の代表的な成功事例が、株式会社すかいらーくです。同社は2006年に上場廃止を決定し、経営の自由度を高めるために非公開化を選択しました。これにより、店舗運営の効率化や事業の再編に集中することができ、財務状況が改善されたのです。その後の2014年に再上場を果たし、企業価値をさらに向上させることに成功しています。この事例は、株式非公開化が経営改革や成長戦略において有効な手段となることを示しています。
失敗事例:株式会社西友
株式非公開化の課題が浮き彫りになった事例のひとつが、スーパーマーケットチェーンの株式会社西友です。同社は2008年に親会社である米国ウォルマートによって完全子会社化され、株式が非公開化されました。ウォルマートは効率的な経営再建を目指して非公開化を進めましたが、日本国内の競争激化や市場環境の変化により、業績不振から抜本的な改革を進めることが難しい状況に陥りました。
その後、事業再建に取り組みましたが十分な成果が得られず、2020年にはウォルマートが西友を売却する決断をしています。西友の事例は、非公開化が万能の経営手法ではなく、競争環境や市場動向への適応が不可欠であることを示すものです。
これらの事例は、株式非公開化が企業に与える影響を考える上で重要な教訓を提供しています。成功するためには、明確な戦略と市場環境への適応力が不可欠です。
株式非公開化後の企業と株主への影響
株式非公開化が行われると、企業と株主にはいくつかの影響があります。
企業側の影響
まず、企業にとっては経営の自由度が増します。上場企業では、四半期ごとの報告や株主総会での意見に対応する必要がありますが、非公開化によりこうした義務が軽減され、長期的な戦略に集中できるようになります。また、株式市場の変動に左右されにくくなり、経営の安定性が期待できます。ただし、株式市場を通じた資金調達手段が失われるため、銀行融資やプライベートエクイティファンドなど、他の資金調達方法を活用する必要があります。
株主側の影響
株主にとっては、株式を自由に売ることが難しくなるデメリットがあります。非公開化により、株式市場での売買ができなくなるため、現金化が困難になる場合があります。また、売却するタイミングを逃したり、提示された株価が適正でないと感じるリスクもあります。ただし、非公開化によって企業の成長が実現し、将来的に買収や再上場を通じて株主に利益がもたらされるケースもあります。
株主構成の変化
非公開化では、企業が特定の投資家や経営陣に買収されることが一般的です。このプロセスでは、既存の株主が決められた価格で株式を売却し現金化することになります。これにより企業の所有者が変わり、経営方針にも影響が出る可能性があります。また、非公開化後に株主として残る投資家がいる場合、その役割は経営の意思決定に大きな影響を与えることがあります。
総じて、株式非公開化は企業と株主の双方にさまざまな影響を与えるプロセスです。企業にとっては長期的な視点での経営が可能になる一方、株主にとっては流動性の低下やリスクも伴います。こうした影響を十分に理解し、企業の長期的なビジョンと株主の期待が一致するかを慎重に検討することが重要です。
株式非公開化とM&Aについて
株式非公開化とM&A(企業の合併・買収)は、企業戦略として密接に関連しています。企業が非公開化を選択する際、M&Aがその一環として利用されることが多くあります。特に、前述のマネジメント・バイアウト(MBO)やプライベート・エクイティ・ファンドによる買収は株式非公開化を促進する手段として用いられます。これらの手法により、企業は短期的な株式市場のプレッシャーから解放され、長期的な成長戦略を追求するための柔軟性を得ることができます。
株式非公開化によるM&Aは、企業価値向上を目的として行われることが多く、経営陣は市場からの干渉を最小限に抑えつつ、事業の再構築や新たな投資機会を実現することが可能になります。これは、非公開化後の企業がより迅速に意思決定を行い、効率的に資源を再配分することができるためです。
一方、株式非公開化とM&Aにはリスクも伴います。買収資金の調達や、買収後の企業統合プロセスの複雑さ、そして企業文化の統合が課題として挙げられます。これらのプロセスがうまく進まない場合、企業の財務負担が増し、最終的に企業価値が低下する可能性もあります。そのため、株式非公開化とM&Aを成功させるには、事前の綿密な計画と実行後の継続的な管理が不可欠です。
このように、株式非公開化とM&Aは、企業の成長を促進するための戦略的手段であると同時に、リスクを伴う複雑なプロセスでもあります。企業はこれらの側面を慎重に検討し、適切なタイミングと方法で実行することが求められます。
まとめ
株式非公開化は企業が直面する多くの課題を解決するための一つの戦略です。経営の自由度を高め、株主からのプレッシャーを減らすことで、企業は長期的な視点での成長を目指すことができます。しかし、非公開化には資金調達の難しさや透明性の低下といったデメリットも存在します。これらのメリットとデメリットをしっかりと理解し、企業の状況に応じた最適な判断をすることが重要です。
もしあなたが投資家であれば、非公開化のニュースを受けた際には、企業の目的や将来的な計画を確認し、投資判断を見直す機会とするのが良いでしょう。企業で働く方や経営者であれば、非公開化のプロセスや影響を深く理解し、会社の未来に向けた戦略を考えることが求められます。ぜひ、この記事を参考にして、株式非公開化についての理解を深め、新たなビジネスチャンスやリスク管理に活かしてください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。