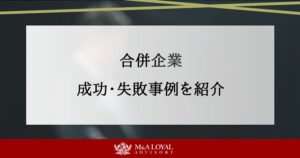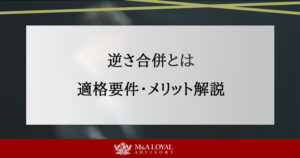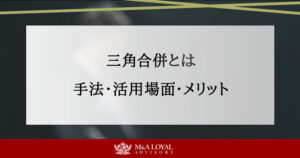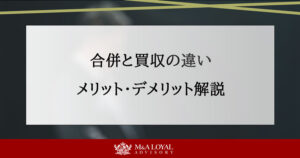簡易合併とは?要件や手続き、できない場合、略式合併との違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
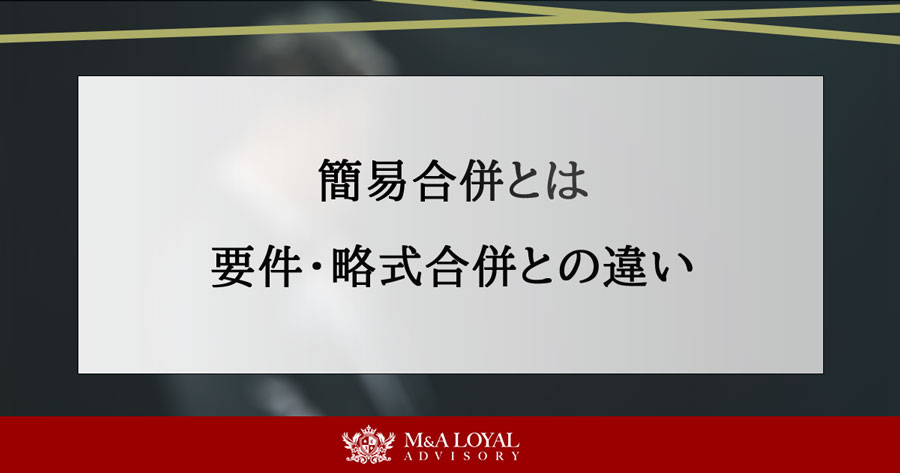
企業同士が合併を行う際、通常は株主総会の承認が必要ですが、一定の要件を満たせばこの手続きを省略できる制度が「簡易合併」です。
煩雑な株主総会を省略することで、組織再編のスピードを大幅に高められるため、多くの企業で活用されています。
本記事では、簡易合併の定義や適用要件、略式合併との違い、注意点や具体的な手続きの流れまでを詳しく解説します。
目次
簡易合併とは
まず、簡易合併に関する基本的な知識について解説します。
簡易合併とは関係手続きを一部省略できる吸収合併のこと
簡易合併とは、吸収合併において、一定の要件を満たすことで存続会社における株主総会の承認決議を省略できる制度です(会社法796条2項)。
通常、合併には株主総会の特別決議が必要ですが、簡易合併が適用されると、株主総会の開催を回避でき、合併手続きの迅速化が図れます。
簡易合併と略式合併との違い
略式合併とは、消滅会社が存続会社の「特別支配会社」である場合に、存続会社の株主総会決議を省略できる制度です(会社法796条1項)。
簡易合併と略式合併は、いずれも株主総会の承認を省略できる点で共通しています。ただし、略式合併は支配関係が前提となり、主に親子会社間での統合に限定されるのに対し、簡易合併はより多様な相手との合併に適用可能です。
なお、一定の要件を満たせば簡易合併と略式合併を併用できます。その場合、存続会社・消滅会社の双方において株主総会の承認が不要です。
略式合併の詳細な要件や具体的なメリットについては、後述します。
合併の種類
企業合併は大きく「吸収合併」と「新設合併」の2種類に分類されます。簡易合併および略式合併は、いずれも吸収合併において活用できる制度です。
吸収合併
吸収合併とは、一方の会社(存続会社)が他方の会社(消滅会社)を取り込み、消滅会社の全ての権利義務を承継する手法です。
手続きが比較的簡便で、実務でも多く採用されています。特に子会社の整理や経営不振企業の統合に適しており、既存の許認可や契約関係、上場資格などを引き継げる点が利点です。
ただし、統合の形式によっては、企業間に優劣があるという印象を与えることもあります。
新設合併
新設合併は、複数の会社が解散し、新たに設立した会社に全ての権利義務を承継させる手法です。対等な関係にある企業同士が統合する場合に用いられ、公平性やブランド刷新を目的としたケースで多く見られます。
一方で、新設会社には新たな許認可の取得や上場手続きが求められるため、行政上・実務上の負担が大きい点が課題です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



簡易合併の要件
簡易合併の要件について解説します。
要件は対価が純資産の5分の1以下であること
簡易合併を適用するためには、「消滅会社の株主に交付する対価の帳簿価額の合計額」が「存続会社の純資産額の5分の1以下」であることが要件です(会社法796条2項)。
合併により交付される対価が小さい場合、存続会社の株主に与える影響も限定的であると考えられ、株主総会の承認を省略できます。なお、対象となる「対価」には、株式のほか、社債や新株予約権、金銭などが含まれます。
また、存続会社の定款で「5分の1」よりも厳しい基準(例えば10分の1など)を定めている場合には、その定めが優先されます。
計算方法
簡易合併の適用判断における計算は、形式的な数値だけでなく、帳簿価額を基準とした慎重な算定が必要です。
「消滅会社の株主に交付する対価の帳簿価額の合計額」と「存続会社の純資産額の5分の1以下」の計算方法について、それぞれ解説します。
消滅会社の株主に交付する対価の帳簿価額の合計額
簡易合併の要件判定において、消滅会社に関する交付対価の帳簿価額は、次の三つの項目の合計です。
- 消滅会社の株主に交付する株式の数に、1株当たり純資産額を乗じた金額
- 交付される社債や新株予約権などの帳簿価額の合計
- 現金など株式以外の財産の帳簿価額の合計
これらの合計が、存続会社の純資産額の5分の1を超えないことが必要です。交付される資産の性質に応じて計算方法が異なるため、帳簿価額に基づいた正確な算定が求められます。
存続会社の純資産額
存続会社の純資産額は、まず次の六つの項目の合計額を算出します。
- 資本金
- 資本準備金
- 利益準備金
- 剰余金
- 評価・換算差額
- 新株予約権の帳簿価額
次に、これらの合計から「自己株式と自己新株予約権の帳簿価額の合計」を控除します。
この純資産額は、原則として合併契約を締結した日の財務データに基づいて計算されます。ただし、合併契約で別の日を基準とする定めがある場合は、その日を基準とします。
簡易合併のメリット
簡易合併のメリットとして次の二つの点が挙げられます。
- 株主総会での承認がいらない
- 事業再編がスピーディーに進む
それぞれについて解説します。
株主総会での承認がいらない
簡易合併の大きなメリットは、存続会社における株主総会の承認が不要な点です。通常の合併では、存続会社と消滅会社の双方で特別決議による承認が必要となり、多数の株主の賛同を得るために準備と調整が不可欠です。
また、株主総会の開催には、日時・場所の設定や招集通知の発送、議案の説明など、法的にも実務的にも煩雑な手続きが伴います。特に株主数が多い企業や上場会社では、調整負担が大きく、開催までに多くの時間とコストを要します。
一方で、簡易合併では、合併の影響が軽微であると見なされるため、こうした承認手続きを省略できます。これにより、承認取得のための根回しや説明責任の軽減が実現し、合併手続き全体の効率化とコスト削減に寄与します。
事業再編がスピーディーに進む
簡易合併を活用することで、事業再編を迅速に進められます。通常の合併では、株主総会の開催準備や承認取得に一定の期間が必要となり、その結果、企業再編の進行が遅れがちです。
特に株主数が多い会社では、招集通知の送付や出席の調整に時間がかかり、株主総会の開催自体が困難になるケースもあります。こうした場合、合併の実行までに数カ月を要することも珍しくありません。
簡易合併を利用すれば、存続会社側の株主総会が不要となり、意思決定から実行までのプロセスが大幅に短縮されます。例えば、完全子会社の吸収合併や、小規模会社の整理統合では、簡易合併を選択することで、事業再編に伴う手続きの負担を軽減し、スピード感のある経営判断を可能とします。
簡易合併ができないケース
簡易合併は、存続会社が消滅会社に交付する合併対価の総額が存続会社の純資産額の5分の1以下である場合に、存続会社の株主総会を省略できる制度です。しかし、以下のような条件を満たさない場合、簡易合併の適用が認められません。
- 存続会社が交付する合併対価が純資産額の5分の1を超える場合 簡易合併の適用条件は、存続会社が交付する合併対価(現金、株式など)の総額が存続会社の純資産額の5分の1以下であることです。この条件を超える場合、存続会社の株主総会での承認が必要となります。
- 株主保護措置が適切に講じられていない場合 簡易合併では株主総会を省略するため、株主保護措置を適切に実施することが求められます。これには以下が含まれます。
- 株式買取請求権:合併に反対する株主が、公正な価格で株式を買い取るよう会社に請求できる権利。
- 十分な情報開示:合併契約の内容、対価の算定方法、合併後の影響など、株主が適切に判断できる情報を提供する必要があります。
株主保護措置が不十分である場合、手続きが無効となる可能性があります。
- 合併契約が会社法の要件を満たしていない場合 合併契約の内容が会社法の規定に準拠していない場合、または必要な手続きを適切に実施していない場合、簡易合併を進めることはできません。 具体的には、合併契約書に記載すべき内容(会社法第749条)や、債権者保護手続きが不十分な場合、手続きの適法性が問題となる可能性があります。
補足情報:誤解されやすいケースについて
以下のケースについては誤解されやすいですが、簡易合併の適用そのものを制限する条件ではありません。
- 合併差損が生じる場合合併によって存続会社に合併差損が発生したとしても、簡易合併の適用条件を満たしていれば実施は可能です。ただし、経営判断としてその影響を慎重に検討する必要があります。
- 譲渡制限株式が合併対価となる場合 合併対価として譲渡制限株式が交付されること自体は、簡易合併の適用を妨げるものではありません。ただし、譲渡制限株式を受け取る株主にとって不利益となる場合があるため、事前に適切な情報開示と説明が求められます。
簡易合併の注意点
簡易合併は、株主総会を省略することで手続きを迅速化し、コストを削減できるメリットがあります。しかし、以下の点に注意が必要です。
- 株主や債権者の権利保護:省略される手続きに代わる保護措置を確実に講じること。
- 適法性の確保:会社法の規定に基づいた正しい手続きを行うこと。
法務や会計の専門家の助言を得ることで、手続き上や法的リスクを回避することが推奨されます。
簡易合併における注意点
簡易合併は、一定の要件を満たす場合に存続会社の株主総会を省略できる制度です。ただし、この制度を適用する際には、以下の点に注意が必要です。
1. 株主総会以外の手続きは省略できない
簡易合併では、存続会社の株主総会を省略することが認められますが、それ以外の手続きは通常の吸収合併と同様に行う必要があります。
- 取締役会での承認 合併契約の締結は会社の重要事項であり、取締役会設置会社では会社法第362条第4項に基づき、取締役会の決議が必要です。この権限を取締役個人に委任することはできません。 取締役会非設置会社であっても、取締役の過半数による同意が求められます。
- その他の手続き 合併契約の交渉・締結、書類の公告・備置き、債権者保護手続きなど、通常の吸収合併で必要な手続きは簡易合併でも省略できません。
注意点: 簡易合併は株主総会の省略を可能にする制度であり、その他の法定手続きが簡略化されるわけではありません。
2. 簡易合併では消滅会社の株主総会は省略できない
簡易合併は、存続会社の株主総会を省略できる制度ですが、消滅会社については原則として株主総会の承認が必要です。
- 例外: 消滅会社が略式合併の要件を満たしている場合(存続会社が消滅会社の議決権の90%以上を保有している場合)、消滅会社の株主総会を省略することが可能です。
- 適用ケース: 親子会社関係にない場合や、消滅会社に一般株主が存在する場合には、消滅会社側で株主総会を開催する必要があります。
3. 存続会社の株主は株式買取請求ができない
簡易合併では、存続会社の株主に株式買取請求権は付与されません。
- 理由: 2014年の会社法改正により、簡易合併において存続会社の株主に与える影響が限定的であると判断される場合、株主総会の承認が不要とされ、これに伴い株式買取請求権も付与されないことが明文化されました。
- 株主保護の仕組み: 存続会社には、合併契約の概要を公告または株主に通知する義務があります。これにより、株主が情報に基づいて判断を行う機会が確保されています。
補足情報:簡易合併の適用条件と注意点
適用条件
簡易合併が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 存続会社が消滅会社に交付する合併対価の総額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であること。
注意点
- 株主保護の必要性 合併による株主への影響が小さい場合に適用される制度ですが、株主保護のための情報開示や公告を適切に実施する必要があります。
- 法的リスク 手続き上の不備がある場合、合併手続き自体が無効となる可能性があるため、法務面での慎重な対応が求められます。
ポイント
簡易合併は、株主総会を省略できることで手続きを迅速化し、コスト削減を図ることができる制度ですが、以下の点に注意が必要です。
- 株主総会以外の手続き(取締役会の承認、債権者保護手続きなど)は通常通り行う必要があります。
- 消滅会社の株主総会は省略できないため、略式合併の要件を満たしているか確認する必要があります。
- 存続会社の株主には買取請求権が認められないため、適切な情報開示を行い株主の理解を得ることが重要です。
これらの注意点を踏まえ、法的要件を正確に理解し、適切な手続きを進めることが求められます。
簡易合併の手続きの流れ
吸収合併において、存続会社側での一般的な手続きの流れは次のとおりです。
- 事前準備・交渉
- 合併契約の締結
- 合併契約に関する書面の事前の備置き
- 株主総会における承認決議
- 反対株主・新株予約権者への通知または公告
- 債権者に対する官報公告および各別の催告等
- 吸収合併の効力発生
- 吸収合併に関する書面等の本店備置き
- 登記申請
簡易合併の場合、四番目の「株主総会における承認決議」を省略できます。
事前準備・交渉
吸収合併の実施に先立ち、当事会社間で基本的な条件の調整を行い、合併の可否や目的、手続きスケジュールなどについて協議します。
その後、各社の取締役会で合併契約の締結と株主総会の招集に関する承認を得ます。取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数による決議が必要です。
合併契約の締結
合併を実施するには、当事会社間で合併契約を締結する必要があります。
契約書には、商号や所在地、合併の方式、効力発生日、対価の内容などの法定事項を記載します。契約の締結後は、合併の具体的な手続きに移行し、次に掲げる各種開示・公告の準備が始まります。
合併契約に関する書面の事前の備置き
合併契約を締結した会社は、合併に関する重要書類(契約書や貸借対照表など)を、株主総会の2週間前から合併の効力発生日から6カ月が経過する日まで本店に備え置く必要があります(会社法794条)。
これは株主や債権者が合併内容を確認し、適切な判断を下せるようにするための措置です。なお、書類は書面または電磁的記録による形式で提供可能です。
株主総会における承認決議
通常の吸収合併では、株主の利益に重大な影響を及ぼす可能性があるため、特別決議による株主総会での承認が必要です。
株主総会は、取締役会の決議に基づき招集され、議決権の3分の2以上の賛成がなければ合併を承認できません。
前述のとおり、簡易合併の要件を満たしている場合には、この承認手続きが省略できます。
反対株主・新株予約権者への通知または公告
合併に反対する株主や新株予約権者には、買取請求権を行使する機会を与える必要があります。そのため、合併効力発生日の20日前までに通知または公告を行い、手続きの詳細と権利行使の期限を明示します。
なお、公告手段は官報や日刊新聞などが一般的です。
債権者に対する官報公告および各別の催告等
吸収合併により存続会社が債務を承継する場合、債権者保護のための手続きが必要です。具体的には、合併効力発生日の1カ月前までに官報で公告を行い、併せて判明している債権者に対して個別催告を実施します。
この期間中に異議を申し立てた債権者には、弁済や担保の提供などの対応が求められることがあります。
吸収合併の効力発生
合併契約書に記載された効力発生日に、合併の効力が発生します。この時点で、消滅会社の全ての権利義務が存続会社に包括的に承継され、消滅会社は法的に解散・消滅します。
効力発生日そのものには特段の行為は不要であり、効力発生日の午前0時をもって合併の効力が自動的に発生します。ただし、効力発生日後には以下のような手続きが必要です。
- 登記手続き: 存続会社における「変更登記」と、消滅会社における「解散登記」を法務局で行います。
- 契約や許認可の確認: 消滅会社が保有していた契約や行政許認可が存続会社に承継されるかどうかを確認し、必要に応じて行政機関での承認手続きを進めます。
吸収合併に関する書面等の本店備置き
合併の効力が発生した後も、株主や利害関係者の閲覧のために一定の書面を本店に6カ月間備え置く必要があります。
備え置く書面には、合併契約書や最終事業年度の財務諸表などがあります。
登記申請
合併の効力発生日から2週間以内に、法務局にて合併登記を行う必要があります。存続会社は合併の実施に伴う登記事項の変更を申請し、併せて消滅会社については解散登記を行います。
これを怠ると罰則の対象となる可能性があるため、期限内の正確な申請が求められます。
簡易合併にかかる税務について
簡易合併にかかる税務について解説します。
適格合併と不適格合併について
合併は税務上、「適格合併」と「不適格合併」のいずれかに分類されます。
適格合併とは、法人税法上定められた要件を満たすことで、資産や負債の移転に伴う課税が繰り延べられる合併形態です。これにより、合併に起因する譲渡益課税や繰越欠損金の消滅といった負担を回避できます。
一方、不適格合併はその要件を満たさないため、移転資産は時価で評価され、帳簿価額との差額に法人税が課されます。さらに、繰越欠損金は引き継がれず、被合併法人の税務上の損失は消滅します。
適格合併の要件
適格合併の要件は、合併当事会社間の資本関係に応じて異なります。大きく分けて、「完全支配関係」「一定の支配関係」「支配関係がない場合(共同事業型)」の3つに分類され、それぞれに応じた要件が設けられています。
1. 完全支配関係の場合
完全支配関係とは、親会社が子会社の発行済株式を100%保有している状態を指します。この場合、合併前後で経済的実体がほとんど変化しないと考えられるため、税務上の要件は比較的緩やかです。
必要な要件は以下の2つです:
- 金銭等不交付要件: 合併対価として株式以外の資産(現金など)を交付しないこと。
- 継続保有要件: 合併後も交付された株式を継続して保有する見込みがあること。
この形態は、企業グループ内の再編で最も一般的に利用される方法です。
2. 一定の支配関係の場合
一定の支配関係とは、親会社が子会社の過半数の株式を保有している状態を指します。この場合、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 金銭等不交付要件
- 継続保有要件
- 事業移転要件: 被合併法人の従業員のうち80%以上が合併後も存続会社の業務に従事すること。
- 事業継続要件: 被合併法人の主要な事業が、合併後も継続して営まれること。
3. 支配関係がない場合(共同事業型)
両法人に資本的な支配関係がない場合でも、共同事業を目的とした合併であれば、適格合併と認められる可能性があります。ただし、以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 金銭等不交付要件
- 継続保有要件
- 事業移転要件
- 事業継続要件
- 事業関連性要件: 合併当事会社の事業に相互の関連性があること。
- 選択要件: 以下のいずれかを満たす必要があります。
- 同等規模要件: 両社の売上高、従業員数、資本金などが一定の範囲内であること。
- 双方経営参画要件: 合併後の会社で、両社の役員が共に経営に関与すること。
税金の種類
法人税
適格合併であれば、被合併法人の資産や負債は帳簿価額で存続法人に引き継がれ、譲渡益による課税は発生しません。反対に、非適格合併では、資産を時価で評価して引き継ぐため、時価と帳簿価額との差額に法人税が課されます。
特に含み益のある資産を多く保有する会社の合併では、この税負担が大きくなる可能性があり、合併後の資金繰りにも影響を及ぼす恐れがあります。
登録免許税
合併登記には登録免許税が課され、税額は増加資本金の1,000分の1.5(最低3万円)です。例えば、合併によって資本金が2億円増加した場合、登録免許税は30万円です。
さらに、合併により不動産の所有権を承継する場合には、その名義変更登記にも登録免許税が発生しますが、この場合には軽減措置(評価額の1,000分の2)が適用されることがあります。
消費税
消費税法上、吸収合併は「資産の一括譲渡」とされ、原則として課税対象外です。例えば、合併によって棚卸資産や設備、不動産を引き継いだ場合でも、その全体が一括して承継されるなら、消費税の課税は生じません。
ただし、合併に伴って資産の一部のみを分離して第三者に譲渡したようなケースでは、その取引部分に対して課税される可能性があります。非課税であっても、仕入税額控除の調整が必要になる場合があり、会計・税務の整合性を確保するための事前確認が求められます。
不動産取得税
不動産取得税は、通常の売買や贈与と異なり、合併による取得は原則として非課税です。これは、吸収合併が包括承継であり、財産の取得形態が個別の譲渡ではないという性質に基づきます。
ただし、合併が実質的に不動産の売買とみなされる特殊な事例では、課税対象となることがあります。そのため、不動産を多く保有する子会社の合併などでは、各都道府県の判断や税理士の見解を踏まえて慎重に対応すべきです。
印紙税
合併契約書の作成にあたっては、印紙税が課されます。会社法に基づく合併契約書については、1通当たり4万円の印紙税が必要です。
その他、金銭の授受や不動産譲渡を伴う契約書(事業譲渡契約書や借用証書、不動産譲渡契約書など)についても、契約金額に応じて印紙税が発生します。例えば、契約金額が1,000万〜5,000万円であれば1万円、5,000万~1億円であれば3万円が課税されます。
印紙の貼付がない、または金額が不足している場合には過怠税が科されるため、契約書の種類と記載金額に応じた確認が不可欠です。
出典:印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)
簡易合併の国内事例5選
吸収合併において、簡易合併の制度を活用した国内事例をいくつか紹介します。
ソフトバンクの簡易合併
通信事業を展開するソフトバンク株式会社は、2022年3月に完全子会社であったLINEモバイル株式会社を吸収合併しました。この合併は、ソフトバンクを存続会社とする簡易合併の形式で実施され、LINEモバイルの法人格は消滅しました。
合併の背景には、ソフトバンクが新たに展開したオンライン専用ブランド「LINEMO」において、LINEとの連携を一層強化するという狙いがありました。LINEモバイルが手掛けていたMVNOサービスの知見を取り入れつつ、契約手続きの完全オンライン化や「LINEギガフリー」などの独自機能を導入し、利便性の高いサービス基盤を整えることが目的とされました。
現在、LINEモバイルの新規受付は終了しており、「LINEMO」ブランドとしてサービス提供が継続されています。
はごろもフーズの簡易合併
はごろもフーズ株式会社は、2021年3月、ギフト製品の製造・販売を担っていた100%子会社・はごろも商事株式会社を吸収合併しました。合併は、はごろもフーズを存続会社とする吸収合併方式で行われ、これによってはごろも商事は法人格が消滅しました。
今回の合併は、会社法上の簡易合併および略式合併の手続きに該当し、株主総会の承認を経ることなく実施されました。
目的は、経営資源を本体に集約し、業務の効率化と意思決定の迅速化を通じて事業全体の競争力を高めることにあります。グループの内部機能を統合することで、企業価値の向上を図っています。
日本製鉄の簡易合併
日本製鉄株式会社は、2020年4月1日付で完全子会社の日鉄日新製鋼株式会社を吸収合併しました。簡易合併方式により、日本製鉄が存続会社となり、日鉄日新製鋼の法人格は消滅しました。
日新製鋼は2017年に日本製鉄の子会社となり、2019年に完全子会社化されていましたが、その後の経営環境の悪化や自然災害、事故などの対応を背景に、本格的な一体運営体制の確立が求められました。
この合併により、経営資源の適正な配分や間接部門の統合によるコスト削減を進め、グループ全体の競争力向上を目指しました。また、将来的な設備の最適化も視野に入れた柔軟な事業運営体制の構築を図っています。
なお、日本製鉄は、2012年に新日本製鐵と住友金属工業の合併によって誕生した新日鐵住金株式会社を前身とし、2019年に現在の社名に改称しています。
さらに、2025年には、米国の老舗鉄鋼メーカーであるUSスチールの完全子会社化を成功させ、国内外の業界関係者から高い関心を集めています。
エディオンの簡易合併
エディオン株式会社は、2002年にデオデオとエイデンが共同で設立した持株会社を母体として誕生しました。その後、2005年にはミドリ電化を子会社化し、2009年にはデオデオとミドリ電化を合併しています。
さらに、2010年にはエディオンEASTおよびエディオンWESTの吸収合併により、本体への統一を実現しました。これにより、効率的な経営体制の構築が進みました。これらの再編では、簡易合併方式がたびたび用いられています。
2012年には、店舗ブランドの統一も実施され、「イシマル」「エイデン」「ミドリ」「デオデオ」などのブランド名を「エディオン」へ一本化しました。併せて、情報システムや物流体制の再編により、企業としての競争力を高めました。
以降も、リユースや物流、通販、不動産、スポーツ、運輸といった多様な事業分野での合併や子会社化を通じて、事業領域を着実に拡大しています。
日本調剤の簡易合併
日本調剤株式会社は、2021年1月1日付で100%子会社の株式会社ライムを吸収合併しました。合併形式は、日本調剤を存続会社とし、ライムを消滅会社とする吸収合併方式(簡易合併制度を利用)で行われ、ライムの法人格は消滅しています。
ライムは、同社グループの一員として、全国で薬局を運営し、地域に密着した医療サービスを提供してきました。今回の合併は、グループ内の調剤薬局事業を本体に統合することで、事業運営の一元化を図り、業務管理やオペレーションの効率化を目指すものです。
また、経営資源を集約するとともに意思決定の迅速化を進めることで、変化の激しい医療業界に機動的に対応し、地域医療へのさらなる貢献を実現する体制の強化が図られました。
略式合併とは
簡易合併と同様に、株主総会を省略できる制度である略式合併について解説します。
概要・要件
略式合併とは、特別支配関係にある企業同士が合併を行う際、被支配会社の株主総会での承認を省略できる制度です。
通常、合併には株主総会の特別決議が必要ですが、議決権の90%以上を支配会社が保有している場合には、実質的に支配関係が確立していると判断され、承認手続きを省略できます。この制度は、2006年の会社法施行により明文化されました。
略式合併が適用されるのは、主に親子会社間や完全子会社間など、明確な支配関係が存在する場面です。
略式合併のメリット
略式合併の最大の利点は、簡易合併同様、株主総会を開催する手間を省ける点にあります。
例えば、存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合、消滅会社側の株主総会を開かずに合併が実行可能です。
なお、存続会社側の株主総会を省略する目的で、簡易合併と併用されることも少なくありません。
略式合併の注意点
略式合併は、特別支配関係に基づき株主総会を省略できる制度である一方、いくつかの制約や留意点があります。
まず、要件を満たしていても常に適用できるわけではなく、新設合併や新設分割、株式移転など、新会社の設立を伴う再編には利用できません。
また、合併対価として譲渡制限株式が交付される場合は、株主の権利に影響を及ぼす恐れがあるため、例外的に株主総会の承認が必要となることがあります。
さらに、略式合併は少数株主への配慮が不十分になりやすく、不利益が懸念される場合には差止請求が認められることもあります(会社法784条の2)。
加えて、会計上の「逆取得」に該当する場合には、例外的な処理が必要となるため、実務上の検討事項も少なくありません。
簡易合併に関するQ&A
最後に、簡易合併に関するよくある質問とその回答を紹介します。
吸収合併にはどんなデメリットがあるか
吸収合併には手続きの簡便さや許認可・契約関係の承継が可能であるといった利点がある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
最大の問題は、合併当事会社間の上下関係が表面化しやすい点です。吸収される側が「取り込まれた」という印象を受けやすく、従業員の士気低下や社内統合の難航といった人事・文化面での摩擦が生じやすいです。
また、吸収合併では一方の法人格が消滅するため、契約当事者の変更や顧客対応における説明責任も発生します。さらに、合併に伴う会計・税務上の調整や、のれんや合併差損が発生する場合の影響も見逃せません。
特に合併対象企業に債務超過や簿外債務がある場合には、リスクを全て引き継ぐことになるため、事前のデューデリジェンスが不可欠です。
無対価合併とは
無対価合併とは、吸収合併において消滅会社の株主に対して対価(株式や金銭など)を交付しない合併方式を指します。代表例として、100%親子会社間の合併や、完全子会社同士の合併(いわゆる兄弟合併)などが挙げられます。
親会社が子会社の株式を全て保有している場合、親会社が自社株を交付する必要がないため、法律上も対価の交付は認められていません(会社法第749条)。無対価合併は、資本関係が明確である企業間で行われるため、手続きが簡素化される特徴があります。また、合併契約書には対価を交付しない旨を明記する必要があります。
簡易合併に関してどの専門家に相談すべきか
簡易合併を進める上で、複数の専門家への相談は不可欠です。専門家と連携することで、法務や財務、税務といった多角的な視点から簡易合併を円滑かつ確実に進められます。
例えば、M&A仲介会社やフィナンシャルアドバイザーは、合併の戦略立案から交渉、スキーム構築まで、M&Aプロセス全体のマネジメントをサポートします。
また、弁護士は、合併契約書の作成・レビューや法務デューデリジェンス、株主総会決議の要件確認、そして合併に関連する各種法的手続き全般についてアドバイスを提供してもらえます。
公認会計士または税理士からは、財務デューデリジェンスや合併後の会計処理、そして税務上の影響などについて専門的な助言がもらえます。
簡易合併と目的が共通するM&A手法はあるか
簡易合併は吸収合併の一種であり、会社を一体化させるM&A手法です。ただし、同様の目的を達成できる手段として、株式譲渡や株式交換があります。
- 株式譲渡 株式譲渡は、買収側が対象会社の株式を取得することで経営権を獲得する手法です。この手法では、対象会社の法人格を維持したまま支配関係を変更できる点が特徴です。手続きが比較的簡便で、許認可の承継が不要な場合も多いため、柔軟に用いられることが多いです。ただし、特定の業種では許認可が必要となる場合があります。
- 株式交換 株式交換は、存続会社が消滅会社の株式を全て取得し、完全子会社化を実現する手法です。対価として存続会社の株式が交付されます。この手法では、対象会社の法人格が維持されるため、法人格を残したままグループ内の再編を行いたい場合に適しています。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
株主総会の承認決議を省略できる「簡易合併」は、組織再編のスピードを大幅に高められるため、多くの企業で実施されており、合併を検討している場合は有効的です。
合併・買収や経営課題に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。