株主間契約を成功させるための秘訣:メリット・デメリットとその対策
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
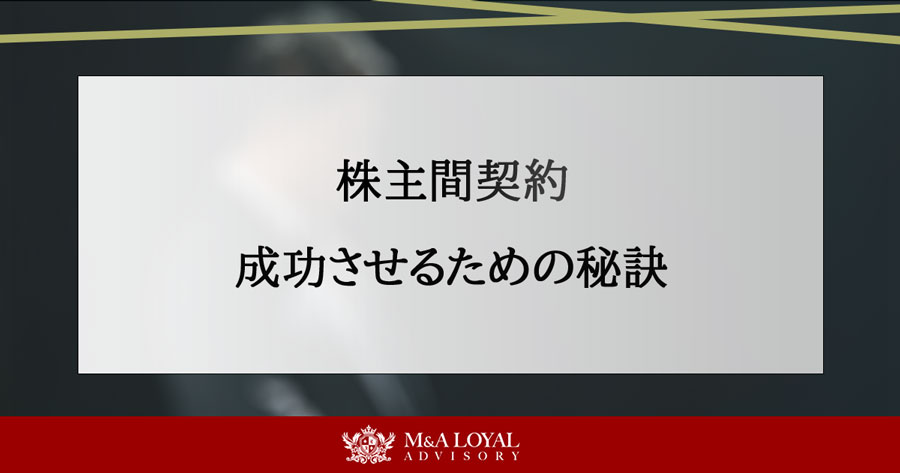
株主間契約は、企業経営において非常に重要な役割を果たす契約形態です。しかし、その複雑さから、多くの経営者が株主間契約の適切な締結方法や運用に悩んでいます。
本記事では、株主間契約の基本からメリット・デメリット、具体的な条項の解説、そして成功させるための秘訣を詳しく紹介します。これにより、事業を円滑に進めるための実践的な知識を得ることができ、法的なリスクを最小限に抑えることが可能となります。
株主間契約を適切に活用することで、事業の安定性と成長を支える強固な基盤を築いていきましょう。
目次
株主間契約(株主間協定)とは?
株主間契約とは、企業の株主間で締結される、企業の運営や株主間の関係を明確にする契約で、「株主間協定」と呼ばれることもあります。この契約は、会社法などの法令に基づく定款とは異なり、株主間の合意に基づく個別の取り決めを詳細に定められる点が特徴です。
通常、株主間契約は会社の設立時や資本参加時、またはM&A(合併・買収)に関連して締結されることが多く、企業の状況や目的に応じて柔軟に内容を設定できます。
株主間契約の目的と役割
株主間契約の主な目的は、株主の権利や義務を明確にし、将来的な紛争を未然に防ぐことにあります。これにより、株主間での信頼関係を構築し、企業の安定した成長を促進することが期待されます。例えば、株式の譲渡制限や議決権の行使に関するルールを定めることにより、予期せぬ経営の混乱を回避することができます。
また、この株主間契約は、株主の利益を保護し、企業の経営方針が株主の意向に沿っていることを確保するための手段ともなります。株主間契約は、特定の株主に特別な権利を付与したり、取締役会の構成を規定したりすることも可能です。これにより、重要な経営判断が株主の意図に反することなく進められるようにします。
株主間契約の内容の策定は各当事者のニーズを十分に反映し、後のトラブルを防ぐためには、弁護士などの専門家の助言を仰ぐことも大切です。これにより企業は株主の多様な意見を尊重しながら、持続可能な成長を目指すことが可能になります。
株主間契約の締結対象
株主間契約の締結対象は、基本的に企業の全株主を含みますが、特定の株主グループ間で締結されることもあります。特に、企業の設立者や主要な投資家が主な当事者となることが多く、株主間契約の内容は、それぞれの立場や影響力に応じて調整されます。これにより、株主間での誤解や対立の発生を未然に防ぎ、企業の安定した運営をサポートします。
さらに、株主間契約は、企業の方向性や戦略に対する株主の意向を反映させる手段です。たとえば、企業が成長する過程での出資や経営方針の変更に関して、株主間契約を通じて合意を形成し、共通のビジョンを共有することができます。なお、株主間契約には、会社法のような強制力はありません。
株主間契約の主な利用シーン(創業、M&A、資本参加など)
株主間契約は、企業における重要な合意形成の手段として、多岐にわたるシーンで活用されています。この契約は、企業の安定した運営を支えるために、各株主の権利や義務を明確にし、潜在的な紛争を未然に防ぐ役割を果たします。
契約が交わされる場面としては、「創業期」「M&A時」「資本参加時」などがあります。
創業期
株主間契約は創業時において、共同創業者間での役割や資本構成についての合意を形成するために用いられます。これにより、経営方針や利益分配に関する不一致を未然に防ぎ、企業のスムーズな成長を促進します。
M&A
M&Aの際には、株主間契約が企業統合プロセスを円滑に進めるための重要なツールとなります。この契約は、買収後の統合戦略や利益調整における合意形成を助け、企業価値の最大化を目指すことを可能にします。
資本参加
第三者の資本参加がある場合も、株主間契約は不可欠です。この契約を通じて、既存株主と新たな株主との間で経営方針や戦略についての共通認識を築き、新規投資家の影響力や責任範囲を明確化します。
株主間契約は、企業が直面するさまざまな局面において、株主間の利害を調整し、経営の安定性を確保するための役割を担います。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株主間契約のメリット
株主間契約のメリットとして挙げられるのは、ルールの柔軟性です。一般的な会社法の任意規定に縛られることなく、株主間契約によって独自のルールを設定できるため、企業の特性や株主の意図に応じたカスタマイズが可能です。また、株主間契約に基づく手続きの簡略化も大きな利点です。具体的には、意思決定の迅速化や、事前に決めたルールに基づくスムーズな運営が期待できます。
上場企業・非上場企業・スタートアップ企業におけるメリットを紹介します。
上場企業におけるメリット
- 特定の株主との間で戦略的な提携や合意を強化できる。
- 敵対的買収からの防衛策として機能する場合がある。
- 経営方針やガバナンスに関する透明性を確保するために利用される。
非上場企業におけるメリット
- 企業の成長段階に応じた柔軟な条件設定が可能。
- 株主間での紛争を未然に防ぎ、安定した経営環境を構築できる。
- 株式の譲渡制限や新規株主の受け入れ条件を明確にすることで、経営の意図を反映させやすい。
スタートアップ企業におけるメリット
- 初期投資家に対して特別な権利を付与し、資金調達を円滑に進められる。
- 経営陣と株主間でのビジョン共有を促し、迅速な意思決定をサポート。
- 将来の資金調達ラウンドにおける条件を事前に整備し、成長戦略を明確にできる。
株主間契約のデメリット
一方で、株主間契約にはデメリットも存在します。第一に、法的拘束力が不十分な場合があることです。株主間契約はあくまで契約であり、法的な強制力が他の法的文書に比べて弱いことがあります。そのため、契約の履行を巡り紛争が生じた場合、法廷での解決が困難になる可能性があります。
さらに、複数の株主間契約が存在する場合、それらの契約間で矛盾が生じるリスクも無視できません。特に、異なる時期に異なる目的で締結された株主間契約が競合することにより、企業運営に混乱を招く恐れがあります。
したがって、株主間契約を締結する際には、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、適切なバランスを保つことが重要です。株主間契約の効果を最大化するためには、各契約の内容を慎重に検討し、適切に管理することが求められます。
上場企業のデメリット
- 株式市場の規制と整合性を保つ必要があり、契約内容が制約される可能性がある。
- 多数の株主が存在するため、全員の同意を得ることが困難。
- 公開情報との整合性が求められ、情報漏洩のリスクが増加する。
非上場企業のデメリット
- 契約の透明性が低く、株主間での信頼関係が崩れるリスクがある。
- 株式の流動性が低いため、株主間の合意が得られない場合、資本政策に影響を与える可能性がある。
- 株主の数が少ない場合、特定の株主の意向が強く反映されるリスクがある。
スタートアップ企業のデメリット
- 経営方針の変更が多く、契約の頻繁な改訂が必要になる場合がある。
- 投資家間の意見の不一致が事業成長の妨げになる可能性がある。
- 経験の浅い経営陣が多く、契約内容の不備が発生しやすい。
株主間契約のメリットとデメリットを理解し、契約書の作成や改訂時には慎重な検討と法的専門家の助言を得ることが大切です。
株主間契約書の主な記載事項と代表的な条項
株主間契約書(株主間協定書)は、株主間の関係を明確にし、将来的な紛争を防ぐために重要な役割を果たします。その主な記載事項には、事前承認事項や情報開示の取り決めが含まれ、特定の取引や決定に関しては事前に株主の承認を得る必要があることが明記されます。
また、取締役の指名権やオブザベーションライト、企業への専念義務に関する条項も重要で、これにより株主は会社の運営に対する一定の影響力を保持します。
さらに、売渡強制条項や株式譲渡禁止、議決権拘束条項などが含まれることが一般的です。これらの条項は、株主が会社の株式をどのように扱えるか、または他の株主に対する義務を規定します。先買権や共同売却請求権の規定もあり、これにより株式の売却に関する優先権が設定されます。
デッドロックの条項は、意思決定が行き詰まった場合の解決策を提供し、ロックアップや優先関係、合意管轄の条項は株式の流動性や法的手続きの場所を制限する役割を果たします。これらの条項は、会社の安定的な運営を支え、株主間の信頼関係を強化するために不可欠です。
契約書の内容は企業や株主のニーズに応じて柔軟に設計されるべきですが、適切なリーガルチェックを受けることで、法的拘束力を強化し、将来のトラブルを回避することができます。
事前承認事項および情報開示の取り決め
株主間契約において、事前承認事項および情報開示の取り決めも重要な要素です。これらの条項は、株主間の透明性を確保し、意思決定のプロセスを円滑に進めるために設けられています。具体的には、株主が特定の重要な取引や行動を実施する前に、他の株主からの承認を得る必要がある事前承認事項が含まれます。これにより、株主間の信頼関係が深まり、無用な紛争を未然に防ぐことが可能となります。
一方、情報開示の取り決めは、会社の経営状況や財務情報などを定期的に開示する義務を定めるもので、株主の知る権利を保障します。この情報開示は、株主が会社の現状を正確に把握し、適切な意思決定を行うための基盤となります。特に、少数株主にとっては重要な保護手段となり得ます。
これらの取り決めは、会社の成長段階や市場環境の変化に応じて柔軟に調整できるよう設計されることが望ましいです。この柔軟性があることで、リスクを低減し、株主間での長期的な協力関係を築くことが可能となります。
取締役指名権・オブザベーションライト、専念義務に関する条項
取締役指名権・オブザベーションライト、専念義務に関する条項は、株主間契約書での中でも重要な役割を果たす項目です。取締役指名権は、特定の株主に取締役を指名する権利を与えるもので、企業の経営方針や戦略に直接影響を与えることができるため、企業のガバナンスにおいて重要です。この権利は、特にベンチャー企業やスタートアップにおいて、主要な投資家が経営に関与するための手段として利用されます。
オブザベーションライトは、株主が取締役会に参加する権利を持つが、議決権を持たないというものです。これにより、株主は企業の内情を把握し、情報を得ることができるため、より適切な意思決定を行うことが可能となります。この権利は、特に経営に直接関与しない投資家が、投資先の状況を適切に監視するための手段として用いられます。
専念義務は、取締役や主要な経営陣が他の競合企業に関与しないことを義務付けるもので、利益相反を防ぐために設けられることが多いです。この義務は、企業のリソースや機密情報が他社に流出するのを防ぎ、企業の競争力を維持するために重要です。
これらの条項は、それぞれが企業の経営や株主の利益に大きな影響を与えるため、株主間契約を締結する際には慎重に検討されるべきです。特に、各株主の立場や企業の将来的な成長戦略に応じて、これらの条項をどのように設計するかが、企業の成功に直結する要素となります。したがって、これらの条項を含む株主間契約を作成する際には、法的専門家の助言を求めることが推奨されます。
売渡強制条項・株式譲渡禁止・議決権拘束条項
売渡強制条項、株式譲渡禁止、議決権拘束条項は、株主間の関係を調整し、企業の安定性を確保するために使用されます。
売渡強制条項は、特定の状況下で株主が株式を他の株主または第三者に売却することを強制される規定です。この条項は、M&Aや事業戦略の変更時に、迅速かつ円滑な意思決定を促進します。例えば、株主の一部が会社の売却に反対する場合でも、売渡強制条項があれば、一部の株主の反対により取引が阻害されることを防ぐことができます。
株式譲渡禁止条項は、株主が他の株主や外部の第三者に対して株式を自由に譲渡することを制限する規定です。これにより、企業は望ましくない株主の参入を防ぎ、既存の株主構成を維持することができます。特に、ベンチャー企業や家族経営の企業においては、株式譲渡禁止条項が株主の安定性を保証するために重要です。
議決権拘束条項は、特定の事項について株主が一致した意見を持つことを求める条項です。これにより、重要な企業決定が迅速に行われることを保証し、企業の経営に一貫性を持たせることができます。議決権拘束条項は、特に経営方針や資本政策に関する重要な決定時に活用され、株主間の対立を未然に防ぐ役割を果たします。
これらの条項はそれぞれの企業の事情に応じてカスタマイズされるため、契約書作成時には慎重な検討が必要です。各条項の適用範囲や条件を明確に定めることが、株主間の信頼関係を強化し、企業の長期的な発展を支える基盤となります。
先買権および共同売却請求権の規定
先買権とは、株主が第三者に株式を売却しようとする際、他の株主がその株式を優先して買い取ることができる権利を指します。これにより、既存の株主が意思決定に関与し続けられる可能性を高め、企業の安定性を維持することができます。
一方、共同売却請求権は、ある株主が第三者に株式を売却する際に、他の株主にも同条件でその売却に参加する権利を与えるものです。この条項は、少数株主が不利な条件で取り残されることを防ぎ、株主間の公平性を保つ役割を果たします。
これらの権利は、株主間の信頼関係を維持し、予期しない株主構成の変動を事前に防ぐ手段となります。特に、ベンチャー企業やスタートアップにおいて、資本構成の安定を図るために有効です。
しかし、これらの権利は、契約に明確に規定されていない場合、法律的に強制力を持たないこともあるため、契約書の作成時には詳細にその内容を記載し、全ての株主が理解し同意することが重要です。こうした条項を適切に運用することで、企業の成長過程における株主間の調和を促進し、潜在的な紛争を未然に防ぐことが可能となります。
デッドロック、ロックアップ、優先関係、合意管轄の条項
株主間契約における「デッドロック」条項は、経営判断が行き詰まり、意思決定ができない場合の解決策を規定するものです。この条項は、例えば取締役会の票が割れた場合に、どのようにして解決策を見つけるかを具体的に示します。デッドロックの解決方法には、調停者の介入や、第三者の決定権を付与するケースもあります。
「ロックアップ」条項は、特定の期間、株主が株式を売却することを制限するものです。この条項は、特に企業が新たに資本を調達する際に、株価の安定を図るために導入されます。ロックアップ期間中は、株式の過剰な流通を防ぎ、投資家の信頼を保つ役割を果たします。
「優先関係」条項は、特定の株主が他の株主よりも先に一定の権利を行使できることを規定します。これには、株式の新規発行時に優先的に購入できる権利や、会社の重要な意思決定における優先的な発言権が含まれます。これにより、特定の株主の利益が保護され、経営の安定性が向上します。
「合意管轄」条項は、紛争が生じた場合にどの裁判所が管轄権を持つかを定めます。この条項により、紛争解決の場が明確化され、訴訟が発生した際の手続きが円滑に進むことを可能にします。
株主間契約の締結タイミングと手順
株主間契約の締結は、会社のステージや状況に応じて最適なタイミングで行うことが重要です。設立時には、創業者間でのビジョンの共有や将来の方向性を明確にするために、株主間契約を締結することが推奨されます。この段階で契約を交わすことで、各株主の権利や義務、会社運営に関する基本的なルールを明文化し、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
第三者が資本参加する際には、新たな出資者の意向や条件を反映した株主間契約が求められます。ここでは、出資者の影響力や関与度合いに応じた条項を設定し、既存株主と新規株主の間での合意を形成することが重要です。このようにして、資本参加が会社に与える影響を管理し、円滑な運営を維持することが可能になります。
また、株式売却時には、売却先の特定や価格、売却条件の調整が必要です。株主間契約により、売却に関する手続きをスムーズに進め、売却後の経営方針や株主構成の変化に対応するための準備を行います。この段階では、売却による経営権の変動を考慮し、必要な合意形成を行い、売却に伴うリスクを最小限に抑えることが求められます。
これらの手順を踏むことで、株主間契約は会社の安定的な成長を支える重要なツールとなります。各タイミングでの適切な対応が、企業運営の円滑さと株主間の信頼関係を強化する鍵となります。
設立時、第三者資本参加時、株式売却時の事例
株主間契約は、企業のライフサイクルにおいて重要な役割を果たします。設立時には、創業者間の役割や責任を明確にし、将来のトラブルを未然に防ぐために締結されることが一般的です。この段階での契約は、株式の発行条件や譲渡制限、重要な決定事項の承認プロセスについて詳細に規定されます。特に、創業メンバー間での合意形成を図るための基盤として機能します。
第三者資本参加時には、外部投資家が新たに参入することで、利益相反の可能性や経営方針の違いを調整する必要があります。この際、株主間契約は、投資家の権利や利益を保護しつつ、既存の株主とのバランスを取るために利用されます。具体的には、取締役指名権や情報開示の範囲、議決権の行使などが議論され、明文化されます。
株式売却時には、株主間の利害関係が大きく変化するため、事前に定めた契約が重要となります。この場面では、売渡強制条項や共同売却請求権に関する規定が機能します。これにより、一部株主による不当な売却や、企業価値を損なう可能性のある取引を防ぐことができます。また、売却先の選定や価格の妥当性についても、既存株主間で事前に合意を得るためのプロセスが進められます。
これらの事例において、株主間契約は企業の安定的な成長と株主間の調和を維持するための重要なツールとして機能し、各ステージにおける特有の課題に対応します。したがって、契約内容の適切な設定と柔軟な更新が求められます。
株主間契約書作成時の注意点
株主間契約書を作成する際には、いくつかの重要な注意点があります。
ひな形利用のリスクと各当事者ニーズの反映
株主間契約書を作成する際、ひな形を利用することは一見効率的な方法に思えるかもしれません。しかし、ひな形には大きなリスクが潜んでいます。ひな形は一般的な状況を想定して作成されているため、特定の企業やプロジェクトの独自のニーズを反映しきれません。それぞれの株主や当事者が持つ具体的な目的、期待、業界特有の事情を考慮しない契約書は、後々のトラブルの原因となる可能性があります。
ひな形をそのまま使用すると、特定の株主が求める議決権の行使に関する特別な取り決めや、投資家が優先的に求める情報開示の条件が不十分になることがあります。これにより、株主間の信頼関係が損なわれたり、重要な意思決定の場面でデッドロックが発生するリスクが高まります。
また、雛形ではカバーしきれない独自の条項が必要になる場合もあります。例えば、特定の株式の譲渡制限や、特定の取締役指名権に関する独自の規定は、ひな形には含まれていないことが多く、これらを考慮せずに契約を締結すると、企業の運営に支障をきたす可能性があります。
したがって、ひな形を利用する場合でも、各当事者のニーズをしっかりと反映させることが重要です。具体的には、各株主の期待を事前にヒアリングし、必要に応じて契約内容をカスタマイズすることが求められます。また、ひな形の使用によるリスクを軽減するために、経験豊富な弁護士のリーガルチェックを受けることも重要です。これにより、ひな形による契約書が各当事者のニーズを的確に反映し、将来的な紛争を未然に防ぐことが可能となります。
弁護士によるリーガルチェックの重要性
株主間契約書の作成において、弁護士によるリーガルチェックも重要です。これにより、契約書が法的に有効かつ各当事者のニーズを適切に反映した内容であることを確認できます。法律に精通した弁護士は、契約書内の複雑な条項や法的拘束力に関する問題を見つけ出し、解決策を提案することができます。特に、複数の契約や法律の間で矛盾が生じるリスクがある場合、専門的な視点からの検証は不可欠です。
また、リーガルチェックを通じて、契約の透明性と公平性を高めることができ、後々の法的トラブルを未然に防ぐことにもつながります。例えば、紛争が発生した際に契約書が明確でないと、解決に長時間を要し、企業の経済的損失を招く恐れがあります。弁護士の関与により、契約の曖昧な部分を明確にし、解釈の違いを防ぐことができます。
さらに、弁護士は最新の法改正や判例を把握しているため、契約書が現行法に準拠しているかどうかを確認することも可能です。これにより、契約の有効性を維持し、法的なリスクを最小限に抑えることができます。最終的には、弁護士の専門知識を活用することで、株主間契約が当事者間の信頼関係を強化し、円滑なビジネス運営を支える基盤となるのです。
株主間契約の専門家への相談とサポート体制
株主間契約は、企業の成長や変化に伴う複雑な状況を円滑に処理するための重要なツールです。しかし、その作成や実施においては、専門的な知識と経験が必要とされます。特に、株主間契約の内容は各企業の特性やニーズに応じてカスタマイズされるべきであり、そのためには法律やビジネス戦略に精通した専門家のサポートが欠かせません。
まず、弁護士や法務専門家への相談は、契約が法的に有効であることを保証するために不可欠です。彼らは契約書のドラフト作成やリーガルチェックを行い、法的拘束力を確保しつつ、企業の利益を最大限に守るための助言を提供します。さらに、多くの専門家は、契約が将来の紛争を未然に防ぐための予防措置を含むようアドバイスを行います。
また、会計士や経営コンサルタントのサポートも重要です。これらの専門家は、契約が企業の財務状況や長期的なビジネス戦略に与える影響を分析し、適切な資本構成や株主の利益配分を設計する手助けをします。特に、M&Aや資本参加といった複雑な取引においては、専門家の意見が企業の成長を左右することがあります。
さらに、契約の履行段階でのサポート体制も確立しておくことが重要です。契約の実行フェーズでは、専門家が定期的に契約内容を見直し、必要に応じて修正や追加を行うことで、企業が市場環境の変化に迅速に対応できるようになります。最終的に、こうした専門家への相談とサポート体制の整備は、企業が株主間契約を効果的に活用し、持続的な成長を遂げるための基盤となるのです。
株主間契約のポイントまとめ
株主間契約は、ビジネスを円滑に進めるための重要なツールです。しかし、その複雑さから、多くの経営者がどのように取り扱えば良いのか悩んでいます。本記事で紹介したように、株主間契約にはメリットとデメリットがあり、それぞれの特徴を理解し、適切に活用することが求められます。特に、契約内容の柔軟さを活かしつつ、法的拘束力不足を補うために、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
次のステップとしては、専門の弁護士やコンサルタントに相談し、自社のニーズに最適な株主間契約を作成することをお勧めします。これにより、契約の矛盾を避け、事業の安定性を確保することができるでしょう。M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。











