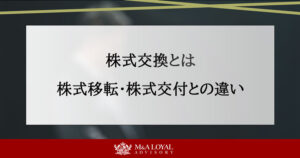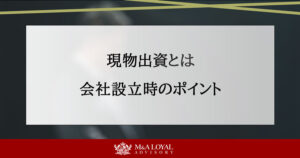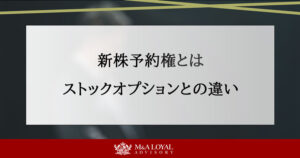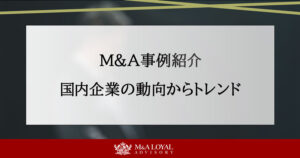株式交付とは?株式交換との違いやメリット、制度をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
株式交付とは2021年に施行された制度であり、従来の株式交換や現物出資といったM&Aスキームの課題を補完する新たな手段として注目されています。本記事では、株式交付の基本的な仕組みや株式交換・現物出資との違い、メリット・デメリット、手続きの流れについて事例とともにわかりやすく解説します。
目次
株式交付とは|制度の定義や意味をわかりやすく解説
株式交付とは、2021年3月1日に施行された改正会社法により始まった、新たなM&A手法です。株式交付制度を用いることで、買い手企業は現金を必要とせず売り手企業の株式を取得することができます。ここでは株式交付の定義や仕組み、制度創設の背景について解説します。
会社法による定義と目的
株式交付とは、取得する株式の対価として金銭を支払う代わりに、買い手が自社株式を交付することをいいます。株式交付は会社法にて次のとおり定義されています。
株式交付(会社法第2条32号の2)
| 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第774条の3第2項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。 |
会社法第2条は、会社法において使われる用語の定義を規定する条文で、他にもさまざまな用語が定義されています。また、株式交付は主に以下の目的で行われます。
- 戦略的連携と統合の促進:株式交付は、企業間の戦略的な連携を円滑に進める手段として利用されます。特にM&Aにおいて重要な役割を果たします。
- 株主の参画機会の提供:買収対象企業の株主がM&A後、新会社へ参画する機会を提供します。これにより、企業の株主構成が多様化し、両社の利益最大化を目指します。
- キャッシュフローの保護:現金を使用せずに取引を行うことで、資金流出を抑え、企業のキャッシュフローを保護します。資金調達が難しい状況でも有用です。
- 長期的な関係構築:対象企業の主要株主や経営陣と長期的な関係を築く手段としても機能し、M&A後の企業文化の融合を促進します。
- シナジー効果の引き出し:企業間の協力によるシナジー効果を最大限に引き出し、競争力を強化することが期待されます。
- 市場評価の向上:戦略的に株式交付を利用することで、株式市場における評価の向上にも寄与します。
株式交付制度の仕組み
株式交付制度は、企業が自社の株式を対価として他社の株式を取得する手法です。この制度は、現金を用いずに経営権を取得できるため、企業の資金流動性を保つ上で有効な選択肢となります。
株式交付は会社法に基づいて行われ、株主総会の承認を得た後、適切な手続きを経て実施されます。株式交付によって新たに発行される株式は、既存の株主にとっての希薄化リスクとなる可能性がありますが、成功すれば企業価値の向上が期待されます。さらに、株式交付は、現金を対価としないため、企業のキャッシュフローに対する影響を最小限に抑えることができるというメリットもあります。
また、株式交付制度の導入により、企業は市場での企業価値の評価向上や戦略的なパートナーシップの強化も期待できます。しかし、株式交付を行う際には、株式の評価や交付後のガバナンス体制の整備が重要となるため、企業は株式交付がもたらす長期的な影響を慎重に評価し、戦略的に活用することが求められます。
制度が創設された理由
株式交付制度が創設された理由として、従来のM&Aの課題解消が挙げられます。例えば、株式譲渡では株式の対価として現金を用意する必要がありました。しかし、株式交付では自社株を対価とすることで現金を使わずにM&Aを実現できるため、資金負担を軽減した企業買収が可能になります。
株式交換も株式交付と同じく自社株式を対価としたM&A手法ですが、株式交換は完全子会社化を目的に行われます。企業を買収する際は、必ずしも完全子会社化が前提ではありません。このように、100%株式を取得する必要がない場合などに株式交付が選択されます。
また、税制面でも課題がありました。株式取得では、株式譲渡益に対してかかる税金が売り手側の負担となり、M&Aの障壁となるケースが見られました。これを緩和するために、産業競争力強化法による特例措置が設けられましたが、適用要件が厳しく、実際には利用が進まない状況でした。
しかし、株式交付制度が導入されたことにより、資金負担が緩和され、M&Aがより柔軟に進められるようになりました。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式交付と株式交換、現物出資との違い
株式会社が他の株式会社を金銭ではなく株式を用いて買収しようとする場合の方法として、「株式交換」と「現物出資」があります。株式交付とそれぞれの違いについて解説します。
株式交付と株式交換との違い
株式交付と株式交換は、いずれも企業の再編やM&Aにおいて用いられる手法ですが、その仕組みや目的に違いがあります。
株式交付は、買い手企業が売り手企業の株主に対して自社の株式を交付することで、対象企業の株式を取得する方法です。現金を用いずに株式を通じて取引を行うため、資金負担を抑えることが可能です。株式交付は、迅速かつ柔軟なM&Aを進めるための手段として活用されることが多く、特に非公開企業の買収において有効です。
一方、株式交換は、企業間での株式の持ち合いを解消したり、完全子会社化を実現するための手法です。株式交換では、親会社が子会社の株式を取得し、子会社の株主に親会社の株式を交付します。これにより、子会社は親会社の完全子会社となります。株式交換は、持株会社の設立や企業グループの再編において利用されることが多く、その目的は主に企業グループ内での支配関係の明確化や経営の効率化にあります。
また、株式交換では、親会社は自社株式のほかに、金銭のみの対価でも子会社の株式を取得できます。これに対し、株式交付では原則として自社株式による交付が義務付けられており、金銭は対価の一部にしか認められていません。さらに、親会社となる企業の法人形態も異なります。株式交換では、親会社となる企業には株式会社と合同会社が認められていますが、株式交付では株式会社に限定されています。
株式交付と現物出資との違い
株式交付と現物出資は、いずれも企業の経営権取得や子会社化に活用される手法ですが、その仕組みや手続きには明確な違いがあります。
現物出資とは、会社の設立や増資時に金銭の代わりに不動産や設備、営業権、株式などの資産を出資する方法です。会社法第207条に基づき、出資物の価値が不明確な場合には裁判所選任の検査役による調査が必要になるなど、厳格な規制が課されています(例外あり)。
また、過大評価による不正を防ぐため、発起人や取締役が価値不足分を補填する義務も課せられることがあります。
一方、株式交付は、他社の株式を取得し、対価として自社の株式(必要に応じて一部現金を含む)を交付するスキームです。この制度はM&Aを促進する目的で導入され、株式交換や現物出資に比べて手続きが簡素で、企業価値を基準とした柔軟かつ合理的なスキームを組める点が特徴です。
株式交付をM&Aで用いるメリット
株式交付をM&Aで用いることで得られるメリットは次のとおりです。
- 資金調達の負担を軽減できる
- 完全子会社化が不要
- 税負担が軽減される
- 子会社の新株予約権の取得
それぞれのメリットを解説します。
資金調達の負担を軽減できる
株式交付のメリットの一つが、資金調達の負担を軽減できる点です。従来のM&Aでは、株式譲渡や事業譲渡など、買収対価として現金が必要なケースが多く、買い手企業にとって資金調達が大きな負担となることが一般的でした(ただし、株式交換や現物出資といった現金を伴わない手法も一部存在していました)。
これに対し、株式交付では買い手が自社株を対価として子会社化できるため、現金の準備が不要となります。資金に余裕のないベンチャー企業など、M&A資金の調達が難しい企業が買収を行う際に株式交付を活用するケースが増加しています。
完全子会社化が不要
対象企業を完全子会社化することなく経営権を取得できることも株式交付のメリットです。株式交換では、完全子会社化する必要がありますが、株式交付の場合は完全子会社化するか、一部を取得するかが選択できます。これにより、既存株主との意見の対立や摩擦を避けることができ、交渉や手続きにかかる時間とコストを最小限に抑えることができます。
税負担が軽減される
株式交付を活用するメリットとして、税負担の軽減も挙げられます。通常、M&Aにおいて株式を現金で買収する場合、売却益に対して税金が発生することが一般的です。しかし、株式交付を選択することで、この税負担を大幅に軽減することが可能です。
具体的には、対価の80%以上を自社株式で支払う株式交付の場合、取得した株式の評価益に対する課税が繰り延べられるため、売却時に直ちに税金が発生しないという特徴があります。これにより、企業は資金流出を抑えつつ、より柔軟に経営資源を再配分することが可能となります。税負担が軽減されることで、買収先企業の株主にとっても財務的な負担が減り、M&Aの成功確率が高まります。
子会社の新株予約権の取得
子会社の新株予約権を取得できる点も株式交付のメリットです。新株予約権とは、将来的に一定の条件下で株式を取得できる権利を指します。子会社となる企業が新株予約権を発行していた場合、親会社は株式交付によってこの新株予約権も譲り受けることができます。
これにより、親会社は子会社に対する支配権をより強固にすることができます。また、子会社が成長した場合でも、他の投資家に支配権を奪われるリスクを軽減できます。さらに、子会社の事業が成功し企業価値が大きくなった場合、新株予約権を行使することで、親会社は割安な価格で株式を取得し、利益を確保できます。
このように新株予約権を活用することで、親会社は子会社の成長に応じた柔軟な対応が可能となり、リスクを抑えつつ、将来的な利益の可能性を最大化することができます。
株式交付を用いるデメリット・注意点
株式交付にはメリットがある一方でデメリットや注意点も存在します。株式交付の主なデメリットとして以下が挙げられます。
- 対象は新たに子会社化する会社のみ
- 国内の株式会社しか子会社にできない
- 税制の優遇を受けるには条件がある
- 新制度であり活用に関する情報が乏しい
それぞれについて解説します。
対象は新たに子会社化する会社のみ
株式交付のデメリットの一つが、子会社化している会社には適用できないという点です。株式交付は新たに他の株式会社を子会社化するために行われるM&A手法です。すでに子会社(保有議決権50%以上)となっている企業の持株比率を高めたい場合には、株式交付ではなく、株式交換や現金対価での取得といった他の方法を用いる必要があります。
国内の株式会社しか子会社にできない
株式交付制度の制約の一つとして、国内の会社しか子会社化できない点が挙げられます。この制約は、日本の法律に基づくものであり、株式交付を利用して親会社が子会社とすることができるのは、日本国内で設立された企業に限られています。
この制約は、特にグローバルな事業展開を目指す企業にとっては、戦略の制限要因となる可能性があります。例えば、海外市場への進出を計画している企業が、現地企業を子会社化する際に株式交付を用いることができないため、他の手法を検討する必要が出てきます。具体的には、株式交換や現物出資といった他のM&A手法を活用することで、海外企業との取引を実現する方法を考慮する必要があります。
税制の優遇を受けるには条件がある
株式交付による税制の優遇を受けるには条件がある点にも注意が必要です。
株式交付において税制優遇措置(課税の繰り延べ)を受けるためには、子会社株主に支払う対価のうち80%以上を親会社の自社株式とする必要があります。つまり、現金など株式以外の対価を用いる場合には、それらの割合を全体の20%未満に抑える必要があります。
新制度であり活用に関する情報が乏しい
株式交付は柔軟なM&A手法として注目されていますが、制度の新しさゆえに実務上の情報や判例がまだ十分に蓄積されていません。今後、新たな論点や課題が浮上する可能性もあるため、最新情報の把握が重要です。
税務面においては、国税庁が発信する株式交付に関するQ&Aのチェックや、国税局電話相談センターなどの公的な相談窓口を活用することが推奨されます。
株式交付の手続きの流れ
株式交付を用いたM&Aは部分的な株式交換に近い性質を持つといえます。そのため、法的には異なる制度であるものの、実施にあたっては株式交換に準ずる取締役会の決議や必要に応じて反対株主や債権者への手続きが求められます。
株式交付の一連の流れを解説します。
| 1.株式交付計画を作成する 2.株主総会で承認を得る 3.株主への通知・公告 4.反対株主の株式買取請求、債権者異議手続き 5.株式交付の効力発生 6.事後開示書類を備置く |
1.株式交付計画を作成する
まず、親会社は株式交付計画を作成します。主な記載事項は次のとおりです。
- 子会社の商号・住所
- 子会社から譲受する株式数の下限
- 親会社が対価として支払う株式数と算定方法
親会社の資本金および準備金 - 譲渡人への金銭交付の有無
- 子会社が譲渡する株式や新株予約権の申込期日
- 株式交付の効力発生日
株式交付は子会社化を目的とした制度であるため、親会社は通常、対象会社の議決権の過半数以上を取得することを目指します。ただし、株式交付計画に具体的な「過半数超の株式数(議決権ベース)の下限」を明記することは、法律上の義務ではありません。
また、株式交付計画を作成後は、株主や債権者が情報を閲覧できるように本店に書面または電子記録を備え置きます。期間は備置開始日から効力発生日の6か月後までです。
備置開始日とは次のいずれか早い日です。
| ・親会社が株主に対して通知する日または公告の日のいずれか早い日 ・債権者異議手続のための公告の日または催告の日のいずれか早い日 ・株主総会の承認を受けなければならないときは、株主総会の日の2週間前の日 |
2.株主総会で承認を得る
株式交付を行う際、原則として親会社は株主総会にて特別決議による承認を得る必要があります(会社法第816条の3第1項)。これは、株式交付という重要な取引について、株主自身に内容を判断してもらうために求められる手続きです。
ただし、交付する対価(自社株など)の合計額が親会社の純資産額の5分の1(20%)以下である場合は、「簡易株式交付」として、株主総会の承認は不要です(同法第816条の4第1項)。
なお、次のようなケースでは簡易株式交付は利用できません。
| ・株式交付差損が発生する場合 ・親会社が非公開会社である場合 ・株主からの一定数の反対通知がある場合(通知から2週間以内) |
3.株主への通知・公告
親会社は株主に対して次のような通知・公告を行う必要があります。まず、自社の株主(親会社株主)に対しては、株式交付を実施する旨の通知または公告を行います。これは、株式交付の計画や影響を株主に事前に知らせるための措置です。
一方、株式交付子会社の株主に対しては、株式交付計画の内容(譲受希望株式数、対価株式数、申込期限など)を記載した通知を行い、株式を譲渡する意思がある株主を募ります。譲渡を希望する子会社株主は、申込期限までに譲渡株式数などを記載した書面を提出しなければなりません。(会社法第774条の4第1項・第2項)
また、株式交付親会社は、申込者(株式交付子会社の株主)から譲り受ける株式を株式交付計画に基づき確定し、それぞれに割り当てる株式数を決定します。そして、効力発生日の前日までにその内容を申込者に通知する義務があります。
なお、子会社化に必要な株式(過半数)を確保できない場合、株式交付は成立しません。その場合、親会社が速やかに申込者全員に状況を説明することが実務上望ましいと考えられます。
4.反対株主の株式買取請求、債権者異議手続き
株式交付において、親会社の株主や債権者が反対する場合には、それぞれ対応が求められます。まず、反対株主は親会社に対して株式の買取請求を行うことができ、親会社はこれに応じて適正な価格で株式を買い取らなければなりません。ただし、簡易株式交付の場合は、この買取請求権は発生しません。
また、株式交付の対価に金銭が含まれる場合には、債権者異議手続きが認められます。債権者が異議を申し立てた場合、親会社は債務の弁済や担保の提供などによって対応しなければなりません。
5.株式交付の効力発生
株式交付の効力発生日を迎えると、親会社はあらかじめ通知した内容に従って、自社株式を子会社株主に交付し、対価として子会社株式を正式に譲り受けます。
この時点で、申し込みを行っていた株主は、株式交付親会社に対して株式を譲渡する「譲渡人」となり、指定された株数の株式を親会社に給付します。また、譲渡人は親会社の株式の交付を経て、新たに親会社の株主として登録されます(会社法第774条)。
6.事後開示書類を備置く
株式交付の効力発生日を迎えたら、親会社は事後開示書類を本店に備え置く義務があります。これは、株主や債権者などの関係者が内容を確認できるようにするための措置であり、会社法により定められています。
事後開示書類には、次の内容を記載します。
- 株式交付の効力発生日
- 譲り受けた子会社株式の数
- 株式買取請求や債権者異議手続きがあった場合は、その経過
備置の開始時期は「効力発生日後遅滞なく」とされており、可能な限り速やかに対応することが求められます。備置の期間は効力発生日から6カ月間です。関係者からの閲覧希望があった場合には、これに応じる必要があります。
株式交付の税制措置と会計処理
株式交付に関係する税制や会計処理などについて解説します。
税制措置
株式交付は、M&Aを円滑に進めるために創設された制度であり、その普及を後押しするために税制上の配慮がなされています。
2021年の税制改正では、売り手企業の株主が保有株式を譲渡し、対価として買い手側の株式を受け取った際に発生する譲渡益に対する課税が繰り延べられるようになりました。この繰り延べの適用を受けるには、株式交付により譲り受けた親会社の株式が対価の80%以上であることが条件です。金銭などの資産も対価に含まれる場合は、その割合に注意が必要です。
また、2023年の税制改正では、この課税繰延措置の適用対象が見直され、株式交付親会社が同族会社(株主が3人以下や親族経営など)の場合には、原則として適用対象外となりました。これは、同族会社による私的な節税目的での制度利用を防ぐことが目的です。
株式交付制度は本来、M&Aを円滑に進めるための制度ですが、改正後も同族会社の範囲や過去の取引の取り扱いなど、なお検討を要する課題が残されており、今後さらなる見直しが行われる可能性もあります。
会計処理
株式交付の会計処理は、既存の「企業結合に関する会計基準」などをもとに対応します。株式交付は、株式交換と性質が類似しているため、会計上も原則として株式交換に準じた方法で処理されます。これは、企業結合に該当する場合には取得法を適用するという考え方に基づいており、取得者と被取得者の識別や対価の測定、のれんの認識などが求められる点も共通しています。
金融商品取引法との関係
株式交付は、会社法上の組織再編手段でありつつ、金融商品取引法上も多くの規制が及ぶ行為です。
株式交付には「対象会社の株式取得」と「買収会社株式の交付」という二面性があり、取引内容によって公開買付規制や有価証券届出書の提出が求められる場合があります。特に買収会社が上場企業の場合、自社株の発行は金融商品取引法上の「募集」に該当し、開示義務が課されることがあります。
また、株式交付の決定は「適時開示」の対象でもあります。売り手が上場企業の場合には、公開買付を要し、会社法や金商法上の要件を満たすスケジュール調整が不可欠です。さらに、対抗買付けが発生した場合への備えとして、買い手側は柔軟な条件変更を可能とする株主総会決議を事前に得ておくことが望ましく、制度上の柔軟な運用が今後の実務で問われます。
株式交付の事例5選
株式交付の事例を紹介します。
テクマトリックス株式会社とPSP株式会社
2022年1月、テクマトリックス株式会社は、PSP株式会社を株式交付により子会社化することを決議しました。さらに、テクマトリックスの連結子会社である株式会社NOBORIは、株式交付の効力発生を条件に、PSPを存続会社、NOBORIを消滅会社とする吸収合併を実施することも決定しました。
この統合により、医療関連ネットワークシステム分野における顧客基盤の拡大や、製品・サービスの機能強化、研究開発の加速を通じたシナジー効果を期待しており、事業領域の拡大と企業価値の向上を図る狙いがあります。
トレンダーズ株式会社と株式会社クレマンスラボラトリー
2022年2月、トレンダーズ株式会社は、株式会社クレマンスラボラトリーを株式交付により子会社化することを決議し、同社が発行する全株式(20株)を取得しました。買収対価3000万円のうち、約2165万円が現金、残りの約835万円が株式による支払いであったため、本件では株式譲渡損益の課税繰延要件は満たされなかったと推察されます。
本株式交付を通じて、トレンダーズは自社のマーケティングノウハウを生かし、美容医療・再生医療分野におけるDX支援や製品開発を推進し、業界課題の解決とグループ全体の企業価値向上を目指しています。
株式会社ソフトフロントホールディングスと株式会社サイト・パブリス
2021年11月、株式会社ソフトフロントホールディングスは、株式会社サイト・パブリスを株式交付により子会社化することを決議しました。本件は簡易株式交付手続により、株主総会の承認を経ずに実施されています。
この株式交付により、ソフトフロントホールディングスは、主力であるボイスコンピューティング関連のコミュニケーション基盤事業に加え、近接領域であるサイト・パブリスの事業を第二の柱として取り込み、経営の安定化を図るとともに、音声・動画・ウェブ分野での顧客基盤の拡大や提供価値の向上を目指しています。
GMOインターネットと株式会社OMAKASE
2021年5月、GMOインターネット株式会社は、株式会社OMAKASEを株式交付により子会社化することを決定しました。本件は、同年5月24日開催の取締役会において承認され、株主総会の決議を要しない簡易株式交付の手続きにより実施されました。
OMAKASEは、予約困難な高級飲食店に特化した予約管理サービスを展開しており、GMOインターネットは、同社の顧客基盤や予約サイト運営ノウハウが、自社のEC支援・決済事業とのシナジーを生むと判断し、グループへの迎え入れを決定しました。
本件を通じて、両社は経営資源とノウハウを融合させ、飲食店およびユーザー双方への提供価値の拡大を図るとともに、グループ全体の企業価値の向上を目指しています。
株式会社プロルート丸光とマイクロブラッドサイエンス株式会社
2021年6月、株式会社プロルート丸光は、医療機器や血液検査事業を展開するマイクロブラッドサイエンス株式会社(MBS)を株式交付により子会社化することを決議しました。
プロルート丸光は、従来の総合衣料卸売事業に加え、「美と健康」事業を新たな収益基盤と位置付けており、MBSとの提携を通じて医薬品や医療機器分野への参入を図ってきました。今回の子会社化により、MBSの製品販売ネットワークや研究機関・製薬会社との連携を生かし、OEM製造・輸出拡大といった新たな事業機会の獲得を見込んでいます。
株式交付に関するQ&A
最後に、株式交付に関するよくある質問とその回答を紹介します。
株式交付費とは何か
株式交付費とは、株式を発行または自己株式を処分する際に直接かかる費用を指し、株式交付という制度に限らず、広く株式を用いた資金調達に伴う支出全般のことをいいます。
2006年に施行された会社法により、新株発行に関する費用の範囲や取り扱いが明確化されました。これには、従来の「新株発行費」として扱われていた費用に加え、自己株式の処分に関連する費用も含まれるケースがあります。具体的には、広告費、金融機関や証券会社への手数料、目論見書や株券の印刷費、登録免許税などが該当します。これらの費用は、企業会計基準において「資本取引関連費用」として扱われることが一般的であり、通常は資本剰余金から控除される形で処理されます。
株式交付信託とは何か
株式交付信託とは、役員や従業員に対して自社株式を付与することで、インセンティブや財産形成を支援する「株式報酬制度」のひとつです。「株式給付信託」や「株式報酬信託」と呼ばれることもあります。具体的には、信託を通じて、業績などに応じたポイントに基づき株式を給付する仕組みです。
なお、本記事で解説しているM&Aにおける「株式交付」制度とは性質が異なります。株式交付信託が従業員や役員への報酬制度であるのに対し、株式交付制度は企業買収を目的とする手法であり、目的も仕組みも異なります。
株式交付がインサイダー取引に当たることはある?
株式交付は、親会社が子会社株式を取得し、その対価として自社株を交付する取引であり、「部分的株式交換」に近い性質を持ちます。ただし、株式交付が未公開の重要事実を利用して行われた場合には、金融商品取引法に基づきインサイダー取引に該当する可能性があります。そのため、取引を行う際には、情報の適法性や公開性に十分な注意が必要です。
このため、金融商品取引法では、親会社による株式交付の決定やその中止、子会社の異動を伴う株式取得、公開買付けの実施などがインサイダー取引規制の対象となる重要事実に該当します。
ただし、反対株主の株式買取請求や株式交付による株式の交付・受領については、特例としてインサイダー取引規制の適用除外とされています。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
株式交付は柔軟なM&A手法として、今後ますます注目されるでしょう。制度の活用によってメリットとデメリットがあるため、しっかり検討することが大切です。
M&Aや経営課題に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。