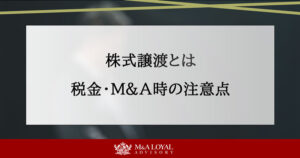不動産M&Aとは?スキーム・メリット・事例・注意点を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
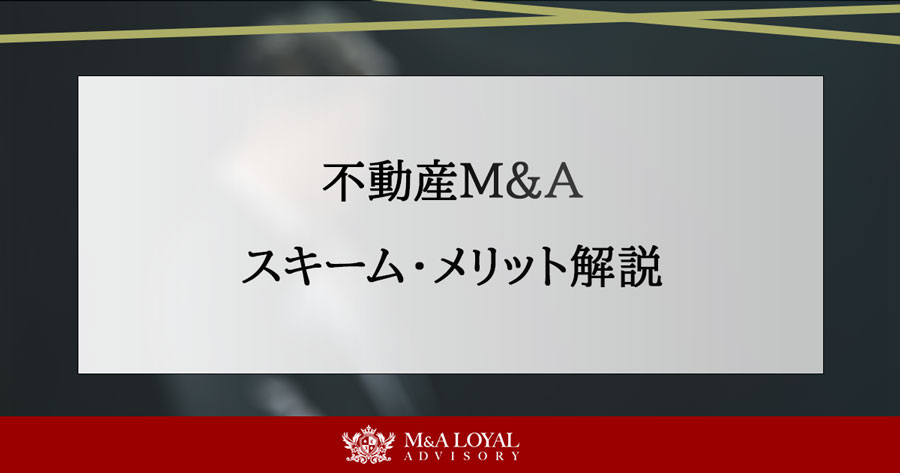
「不動産M&Aと通常の売買は何が違うの?」「税金やスキームが不安」「いつから準備すべきか分からない」そんなお悩みはありませんか。初めての方ほど用語や論点が多く、何から手を付けるか迷いますよね。
本記事では、不動産の基本定義から、不動産M&Aの仕組みや不動産売買・一般的M&Aとの違い、売り手・買い手それぞれのメリット・デメリット、代表的スキーム、税金まで徹底解説します。
ぜひ本記事を参考に、不動産M&Aに取り組む際の判断材料としてお役立てください。
目次
不動産M&Aとは
まず、不動産M&Aの定義や一般的なM&Aとの違いを解説します。
そもそも不動産とは
そもそも不動産とは、民法第86条1項で「土地及びその定着物は、不動産とする」と定義されています。ここでいう定着物とは、建物や樹木のように、継続的に土地に付着して独立して移動できないものを指します(石垣や橋なども状況により含まれます)。
一般に「不動産」は土地と家屋の総称として用いられるため、本記事でもこの通念に沿って解説します。
| 不動産 | 種類 |
| 土地 | 田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地(温泉など)、池沼、山林、牧場、原野など |
| 家屋 | 住宅、店舗、工場、倉庫などの建物 |
参照:総務省「不動産取得税」
不動産M&Aの概要
不動産M&Aは、不動産を保有する法人(資産管理会社・賃貸業など)の株式を取得し、法人ごと承継することで実質的に不動産を取得する手法です。
譲渡対象は不動産そのものではなく「不動産を所有する会社の株式」であるため、同社が持つ資産・負債・契約関係(賃貸借、借り入れ、保証等)を一体で引き継ぐ点が特徴です。
不要資産や簿外債務、係争などのリスクを伴う一方、設計次第では税務・手続き面のメリットや迅速な資金回収が見込めるため、近年は事業承継・撤退ニーズへの対応や優良不動産の機動的取得の選択肢として採用が増えています。
また、対象不動産を分社化(カーブアウト)して不要事業を切り離した上で株式を譲渡するなど、売却価値を高める構成も可能です。
不動産M&Aと不動産売買の違い
不動産M&Aと不動産売買の最大の違いは譲渡対象です。通常の不動産売買は不動産そのものを移転しますが、不動産M&Aは不動産を保有する会社の株式を移転します。
実務上は、税務や手続き、リスク分配、調査範囲が大きく異なります。
取引前の精査内容にも違いがあります。通常の不動産売買では不動産単体の調査が中心ですが、不動産M&Aでは企業全体を対象としたデューデリジェンス(買収監査)が必要です。簿外債務や訴訟リスクの有無など、弁護士や公認会計士による詳細な調査が欠かせません。
課税面にも違いがあります。詳細は後述します。
不動産M&Aと一般的なM&Aの違い
一般的なM&Aは、対象企業の経営権や事業そのものの取得を目的として行われます。対象企業が不動産を保有していても、主眼は事業の取得であり、不動産は付随的な資産に過ぎません。
これに対し、不動産M&Aは不動産の取得・活用を主目的として、その不動産を所有する企業ごと取得します。
デューデリジェンスの焦点は、一般的なM&Aでは財務・事業・人事・知財・コンプライアンスなど広範な領域に及びます。これに対し不動産M&Aでは、権利関係(登記・借地・担保)や建物・設備、環境(土壌・アスベスト)、賃貸借契約(賃料改定・解約条項など)といった不動産特有の論点が比重を占めます。
PMI(統合プロセス)にも違いがあります。一般的なM&Aは組織やシステムの統合が中心となるのに対し、不動産M&AはAM(アセットマネジメント)やPM(プロパティマネジメント)の体制の構築、リーシング、バリューアップ計画の実行が中心です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



不動産M&Aのメリット【売り手側】
不動産M&Aにおける、売り手側の主なメリットは次のとおりです。
- 高い節税効果
- 廃業コストの削減
- 従業員雇用の継続
- 相続・株式分散問題の解決
それぞれを詳しく解説します。
高い節税効果
不動産M&Aは不動産そのものではなく不動産を保有する会社の株式を譲渡するため、売主(個人株主)の課税対象は株式譲渡益です。個人の株式譲渡益は原則約20%の申告分離課税(所得税15%+住民税5%+令和19年までは復興特別所得税を加味)です。
一方、不動産売買後に法人精算を行う場合、まず法人段階で売却益に対して約30%の法人税等が課され、その後の残余財産の配当時で個人株主に最大で約55%の所得税等が課されるため、法人段階と株主段階の二重課税となりやすく、手取りが目減りしがちです。
不動産M&A(株式譲渡)はこの二重課税を回避できる場合があり、節税効果が高いとされています(個別の税率・控除・売主属性により最適解は異なります)。
廃業コストの削減
会社を清算する場合には、解散・清算結了登記や官報公告費用、不動産や設備の原状回復費、在庫などの処分費用、司法書士や税理士への報酬など、さまざまなコストが発生します。
それに対し不動産M&Aでは企業ごと譲渡するため、これらの廃業コストは不要です。
特に株式譲渡スキーム(詳細は後述します)では、手続き期間も短く、コストを抑えて譲渡を完了させられます。
従業員雇用の継続
廃業の場合は全従業員が解雇されますが、買い手が事業継続を前提として企業を子会社化する場合、従業員の雇用が維持される可能性があります。
事業承継型の不動産M&Aでは雇用と事業基盤が引き継がれるため、従業員の生活や顧客との関係を守れます。
相続・株式分散問題の解決
不動産所有会社の株式は相続を重ねることで親族間に分散し、共有状態や権利行使制限などの問題が発生します。
不動産M&Aにより早期に株式を現金化することで、相続や株式分散による経営の停滞を防ぎ、資産の有効活用を図れます。
不動産M&Aのメリット【買い手側】
不動産M&Aにおける、買い手側の主なメリットは次のとおりです。
- 取得価格の引き下げ交渉が可能
- 市場に出回らない不動産の取得
- 不動産取得関連コストの削減
- 事業展開の迅速化
それぞれを詳しく説明します。
取得価格の引き下げ交渉が可能
売り手側は株式譲渡によって高い節税効果を得られるため、譲渡価格の引き下げ交渉に応じやすい傾向があります。
これにより、買い手は市場価格よりも割安で不動産を取得できる可能性があり、投資効率を高められます。
市場に出回らない不動産の取得
自社ビルや一等地物件など、売買目的で保有されていない不動産は通常の市場に出回ることが少なく、一般的な不動産取引では取得が困難です。
不動産M&Aであれば、こうした物件を保有する企業ごと買収することで、競争相手が少ない状態で有利に取得できる可能性があります。
不動産取得関連コストの削減
不動産M&Aでは不動産の所有権は売り手企業に残るため、不動産取得税や登録免許税、印紙税などの取得関連費用が発生しません。
また、不動産仲介手数料や登記費用も不要となることもあるため、現物不動産購入に比べて初期コストを大幅に抑えられることがあります。
事業展開の迅速化
不動産M&Aでは、対象企業が所有する複数の物件や既存の賃貸契約、管理体制をそのまま引き継げます。
これにより、新規の不動産事業や再開発プロジェクトを短期間で立ち上げられ、時間的優位性を確保できます。
不動産M&Aのデメリット【売り手側】
不動産M&Aにはさまざまなメリットがある一方で、デメリットも存在します。不動産M&Aにおける、売り手側の主なデメリットは次のとおりです。
- 買い手の探索が困難
- 手続き期間の長期化
- 仲介手数料の高額化
- 節税効果の限定化
それぞれのデメリットを詳しく解説します。
買い手の探索が困難
不動産単体の売却と比べ、企業の譲渡は買い手候補が限られます。
条件面や資金力に加え、M&Aのプロセスを遂行できる体制を備えた企業を見つける必要があり、売却先の探索には時間と労力がかかります。
手続き期間の長期化
不動産M&Aでは、不動産だけでなく企業全体の財務・法務・税務などを対象にデューデリジェンスを行う必要があり、契約成立までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。
市場環境の変化によるリスクも考慮が必要です。
仲介手数料の高額化
M&A仲介手数料は不動産仲介手数料のような法的上限がなく、報酬体系も業者ごとに異なります。
そのため、不動産M&Aでは手数料負担が高額になる傾向があり、節税効果を考慮しても総コストが増える場合があります。
限定的な節税効果
対象企業に簿外債務や偶発債務が存在する場合、譲渡価格が下がることで節税効果が減少し、結果的に会社清算と手取り額が大差がないケースもあります。
特に資産規模が小さい企業や不動産以外の負債が多い企業では、想定よりもメリットが薄れることがある点に注意が必要です。
不動産M&Aのデメリット【買い手側】
不動産M&Aにおける、買い手側の主なデメリットは次のとおりです。
- 簿外債務・偶発債務の承継リスク
- デューデリジェンスの負担
- 手続き期間の長期化
- 減価償却の非適用
それぞれを分かりやすく解説します。
簿外債務・偶発債務の承継リスク
不動産所有企業を買収すると、その企業が抱える未払残業代や税務リスク、訴訟リスクなども引き継ぎます。
買収後に負債が判明した場合、予想外のコスト負担となる可能性があるため、慎重な事前調査が不可欠です。
デューデリジェンスの負担
リスク回避には、税理士・弁護士・公認会計士などによる法務・財務・税務面での徹底的なデューデリジェンスが必要です。
この調査には時間と費用がかかり、その負担は買い手側が負うことになります。
手続き期間の長期化
一般的な不動産売買は3〜6カ月で完了することが多いですが、不動産M&Aでは6〜12カ月かかることが一般的です。
不動産M&Aのスキームによってはさらに時間を要する場合もあります。
また、M&Aの交渉中に不動産市場の変化や金利の変動があれば、投資計画に影響を及ぼす可能性があります。
減価償却の非適用
株式譲渡による取得では、取得した不動産を時価で評価し直して減価償却を行うことができません。
現物不動産の購入に比べ、税務上のメリットが小さくなる可能性があります。
不動産M&Aのスキーム
不動産M&Aには、取引の目的や状況に応じていくつかの手法があります。代表的なものは次の二つです。
- 株式譲渡
- 会社分割
それぞれのスキームを分かりやすく説明します。
株式譲渡
株式譲渡は、不動産を保有する会社の発行株式を買い手が取得し、その会社を子会社化することで間接的に不動産を保有する手法です。売り手企業は法人格を維持したまま買い手グループに入り、不動産や契約、従業員、許認可などの権利義務を包括的に引き継ぎます。これにより、契約や従業員との再契約といった個別移転の手間が不要となり、手続きの簡便さが特徴です。
株式譲渡は、迅速に会社ごと引き継ぎたい場合や、売り手の税務上の優位性を生かして価格交渉の余地を残したい場合に多く採用されます。株式譲渡自体では不動産取得税や登録免許税は発生せず、不動産の名義は会社に残ります。ただし、買収後に不動産を親会社へ移転する場合には、別途課税が発生する可能性があります。
買収後は、売り手企業の事業を継続する場合もあれば、不動産の取得のみを目的として事業継続が困難な場合には、不動産を移転後に会社を清算するケースもあります。また、不動産の収益性を高めた上で売却し、その後に子会社の存続か解散かを判断するケースも見られます。
株式譲渡のメリットは次のとおりです。
- 契約・従業員・許認可を維持したまま包括的に承継ができる
- 売り手の税務メリットを生かした価格調整ができる
- 手続きが比較的簡便で短期間での取引ができる
株式譲渡のデメリットは次のとおりです。
- 負債・簿外債務・偶発債務も一体で承継するリスクがある
- リスク回避のために綿密なデューデリジェンスと表明保証・補償条項の設定が不可欠である
会社分割+株式譲渡
会社分割と株式譲渡を組み合わせた不動産M&Aは、売却したい不動産のみを譲渡するための手法です。
売り手企業はまず、会社分割によって売却対象の不動産と、それ以外の事業・資産を分離します。その後、売却対象不動産を保有する会社の株式を買い手企業へ譲渡します。
会社分割+株式譲渡のメリットは次のとおりです。
- 不動産のみを切り出しつつ、契約・従業員・許認可を包括的に承継できる
- 適格分割を活用すれば課税負担を抑えられる可能性がある
- 事業譲渡のような個別同意手続きが不要で、移転がスムーズである
会社分割+株式譲渡のデメリットは次のとおりです。
- 組織再編手続きや適格要件の確認が複雑である
- 法務・税務の事前設計に時間とコストがかかる
- 適格要件を満たせない場合は即時課税のリスクがある
不動産M&Aにかかる税金
不動産M&Aを実施する際に発生する税金について解説します。また、併せて通常の不動産売買や会社精算にかかる税金についても紹介します。
株式譲渡にかかる税金
売り手側
株式譲渡で会社ごと不動産を引き継ぐ場合、売り手の課税は「株式等の譲渡所得の申告分離課税」が原則です。譲渡益は所得税15%・住民税5%(計20%)が基本となり、さらに令和19年(2037年)分まで復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます(合計実効 20.315%)。
株式の譲渡自体は消費税の「非課税取引」に当たります(有価証券の譲渡)。
買い手側
買い手側は、株式を買う段階では特に課税は発生しません。
後に不動産を売却する際に売却益が出れば、その利益に対して法人税などが課されます。
会社分割にかかる税金
会社分割を行うと、原則として以下の税金が関係します。
- 法人税:承継される資産や負債に譲渡損益がある場合、その利益に対して法人税が課されます。
- 所得税:新設分割の対価が株主に交付される場合、それは「みなし配当」とみなされ、株主に所得税がかかります。
- 不動産取得税:不動産を新設会社に移転した場合、通常は4%の不動産取得税が課税されます。
ただし、組織再編税制の適格要件を満たす場合には、法人税や所得税は課税されず、さらに不動産取得税も一定の条件を満たせば非課税となります。
不動産M&Aの実施が税務上困難な例
短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡
譲渡対象会社の資産構成・所有期間や、特殊関係株主等による一定割合の株式譲渡に該当すると、株式譲渡であっても「短期譲渡所得(分離短期譲渡一般分)」として課税(所得税30%+住民税9%。所得税には2037年分まで復興特別所得税2.1%が上乗せ)されます。スキーム設計段階で、次の要件該当性を事前に精査することが不可欠です。
「一定の株式等の譲渡」とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
- その有する資産の総額の70パーセント以上が「土地等(その株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下等のものに限る)」である法人の「株式等」の譲渡
- その有する資産の総額の70パーセント以上が「土地等」である法人の「株式等(その株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日現在の所有期間が5年以下等のものに限る)」の譲渡
「一定の要件に該当する株式等の譲渡」とは、次の両方を満たす場合をいいます。
- その年以前3年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数または総額の30パーセント以上を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
- その年において、その株式等の譲渡をした者を含む上記(1)の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数または総額の5パーセント以上を譲渡し、かつ、その年以前3年内において、その発行法人の発行済株式等の総数または総額の15パーセント以上を譲渡したこと。
税務調査で租税回避行為とみなされる場合
組織再編税制には租税回避防止の否認規定があり、新設分割を用いた不動産M&Aも税務調査で租税回避と判断されれば否認されます。
特に、包括的否認(法人税法132条の2)は、形式要件を満たしていても法人税等の負担を不当に減少させる結果となる再編を制度乱用として否認し得るもので、否認されれば想定した繰延・非課税効果は失われます。
実務上の目安として、売却対象の不動産を含む事業が他事業に比べて小規模であれば対象側を新設会社へ移すのが自然であり、これに反して不動産M&Aのために大規模側を新設会社へ移す設計は、他に説得力のある理由が示せなければ租税回避と指摘されやすくなります。
いずれの場合も、事業再編上の必要性・経済合理性・意思決定過程を客観資料で一貫して立証できるよう準備しておくことが不可欠です。
不動産売買にかかる税金
売り手側
通常の資産売却として不動産を譲渡する場合、売り手の税負担は大きく「消費税」と「所得課税(法人/個人)」に分かれます。「所得課税(法人/個人)」はさらに詳しく分けると次のとおりです。
法人の場合は次のとおりです。
- 法人税
- 地方法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
個人の場合は次のとおりです。
- 譲渡所得税
まず消費税は、建物の譲渡が課税、土地の譲渡は非課税です。土地・建物を一括で売却する際は、鑑定評価や帳簿価額など合理的な方法で代金を区分し、建物部分のみに消費税を計算します。
所得課税について、法人は売却益に対して法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税が課され、合計でおおむね30〜34%が目安です(規模・所得水準・所在地等により変動します)。さらに、売却後の配当や清算により「みなし配当」が生じると、株主側で追加の所得課税(状況により最大約55%)が発生します。
個人が売却する場合は譲渡所得税の対象となり、譲渡所得=売却価格−取得費−諸経費で算定した所得に対して課税されます(長期・短期で税率が異なります)。
買い手側
買い手に生じる主な負担は、不動産取得税・登録免許税・印紙税です。これらに加えて、登記手続きを専門家に依頼する場合は報酬などの付随費用も発生します。
不動産取得税は、不動産の取得時に課され、課税標準は固定資産税評価額等です。税率は原則として土地・住宅が3%、住宅以外の家屋が4%で、要件を満たせば土地・住宅について各都道府県が定める軽減措置や特例が適用されます(適用要件・期限は各都道府県が公表しています)。
登録免許税は、売買による所有権移転登記に課されます。土地の所有権移転登記については、税率は原則1,000分の20(2%)ですが、令和8年3月31日までに登記を受ける場合は、時限的に1,000分の15(1.5%)へ軽減されます。課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格が用いられます。
印紙税は、不動産売買契約書が第1号文書に該当するため契約金額に応じて課税され、一部に軽減措置が設けられています。負担方法は当事者間の取り決めによりますが、折半が通例です。
会社清算に伴う税金
会社を清算する際には、まず解散登記を行い、その日を決算日として法人税・地方税・消費税の申告を行う必要があります。その後は残余財産が確定するまで「清算事業年度」として申告義務があり、通常は解散から1年以内に確定するため、多くの場合は解散事業年度と残余財産確定事業年度の2回で済みます。
法人税や地方税は利益が出れば課税、赤字なら均等割のみとなりますが、清算中に債務免除益や不動産売却益が生じれば課税対象となることもあります。残余財産を株主に分配する際は出資額までは非課税ですが、超過分は「みなし配当」として源泉徴収の対象です。
消費税についても課税事業者であれば解散・清算いずれの事業年度でも申告が必要で、不動産売却などで想定外の納税が生じる場合があります。
このように清算手続きでは法人税・地方税・消費税に加え、株主への分配に伴う課税も発生するため、税務・登記・債務整理などは税理士や司法書士、弁護士といった専門家に相談しながら進めることが重要です。
不動産M&Aの事例
ここでは、実際の不動産M&Aの事例を紹介します。
トーセイ株式会社
トーセイ株式会社は、東京都港区芝浦に本社を置く総合不動産企業で、不動産再生・開発・賃貸、ファンド・コンサルティング、管理、ホテル事業を展開しています。同社は仕入れ戦略の中核に「不動産M&A・事業承継支援」を位置付け、オフマーケットの優良アセット取得を拡大しています。
2023年1月に、不動産保有会社の全株式を取得するM&Aにより、収益マンション6棟・収益戸建2棟・区分マンション4戸の計12物件(内首都圏11物件、愛知県1物件、売上想定額約25億円)を取得しました。
2024年5月には事業承継支援を通じて千葉県内の23物件(売上想定額約95億円)を取得しました。さらに2025年には、東京都・神奈川県に所在する複合ビルや収益マンションなど6物件(2月に1物件、 5月に5物件)を取得しています。これらの取り組みにより、2025年8月現在(公表ベース)で累計94物件に達しています。
同社は原状回復やバリューアップ、リーシングによる稼働率向上などを組み合わせて資産価値を高め、売却または保有を選択するモデルで収益化しており、M&A専担組織(M&A・グループ戦略本部/部)を軸に仕入れルートの多様化を進めています。
株式会社ビーロット
株式会社ビーロットは、東京都港区に本社を置く不動産投資開発事業を主力とする上場企業です。収益性や順守性の改善余地が高い不動産の取得・再生に強みを持ち、ホテル等のオペレーショナルアセットにも積極的に取り組んでいます。M&Aを「仕入手法の拡充」にとどめず、人材やネットワークの獲得を通じた事業拡大の手段として位置付けている点が特徴です。
同社の不動産M&Aでは、2017年にカプセルホテル2棟(渋谷区恵比寿・品川区東五反田)を所有・運営する株式会社ヴィエント・クリエーションの全株式を100%取得し子会社化しました。その後、恵比寿物件は大規模リニューアルを経て高稼働を維持し、2019年11月に売却を完了しています。
また、2019年には横浜市の納骨堂「富士記念館・富士霊廟」の不動産所有・運営を目的に新設分割された株式会社横浜富士霊廟の50%を取得し、持分法適用関連会社化しました。同社は室内墓の増設や外観リフォーム、耐震工事等のバリューアップを計画しており、高齢化を見据えた新領域への展開と、オペレーショナルアセットでの再生ノウハウの活用を両立させる取り組みと位置付けられます。
これらの事例に共通するのは、株式取得によりアセットと運営機能を一体で確保し、再生・稼働改善後に売却または保有を柔軟に選択するモデルです。M&Aを起点にバリューアップを組み込み、企業価値向上へつなげる同社のアプローチが示されています。
京王電鉄株式会社
京王電鉄株式会社は、鉄道を中核に流通業、不動産業、レジャー・サービス業などを展開する企業グループで、京王電鉄本体と子会社・関連会社から構成される生活関連サービス事業者です。不動産分野でも開発・賃貸・販売の機能を有し、グループとしての不動産事業基盤の強化を進めています。
同社は2023年11月、分譲マンション開発を手がける株式会社サンウッドの完全子会社化を目的にTOB(公開買付)を実施すると発表しました。
狙いは、不動産開発の仕入・企画・設計・販売における事業協力の深化や商品企画・用地情報の相互交換、共同開発、人事交流によるノウハウ共有・人材育成などのシナジー創出で、不動産事業の基盤強化と領域拡大を図るものです。
なお、京王電鉄は2021年11月にもタカラレーベンからサンウッド株式を取得しており、今回のTOBはその延長線上での資本関係強化と位置付けられます。
株式会社DYM
株式会社DYMは、東京都品川区に本社を置く企業で、ウェブ事業・人材事業・研修事業・エグゼパート事業・海外医療事業・ウェルフェアステーション事業など多角的に展開しています。
同社は2021年3月、法人向け不動産コンサルティング・不動産仲介・オフィス移転コンサル・オフィスマネジメントを手がける株式会社エイジアトラストの株式80%を取得し、子会社化しました。
新型コロナの影響で首都圏を中心にオフィスの拡大・縮小・移転ニーズが高まる中、DYMが抱える約1万社超のクライアント需要に対応する狙いで、オフィス戦略提案や移転支援を自社グループに取り込み、店舗開拓等も含めた不動産ソリューションの提供力を強化しています。
不動産M&Aに関するQ&A
最後に、不動産M&Aに関するよくある質問とその回答を紹介します。
不動産M&Aが選ばれる主な理由は何か
主に次の四つが挙げられます。
- 買い手側で仕入れ競争が激化し、物件取得ルートと手法の多様化が必要になったこと
- 売り手側で後継者不足により不動産事業からの撤退ニーズが増えたこと
- M&A実務の成熟によりプレーヤーが増え、プロセスが確立して実行しやすくなったこと
- 現物売買と株式売買で課税関係が異なり、多くの場合は株式売却(不動産M&A)の方が売り手の税負担を抑えやすいこと
不動産賃貸業で生じる課題は、不動産M&Aで解決できるか
老朽化物件の改修負担やテナント調整、空室・賃料低下への対応、後継者不在といった課題は、運営基盤とPMノウハウを持つ買い手に事業を承継することで、解決につながります。
その結果、売り手にとっては課題解決と資産の現金化を同時に実現でき、買い手にとっても収益拡大のチャンスとなります。
不動産M&Aを検討している場合、どのくらい前から準備すべきか
不動産M&Aは、相手探索から条件交渉、デューデリジェンス、クロージングまで、手続き自体が6〜12カ月かかることがあります。
その前段でも、目的の明確化やスキーム選定、税務・法務の設計、資料整備、テナント・金融機関との調整などやるべきことが多岐にわたります。
思い立ったらまずは早めに専門家へ相談し、スケジュールと優先順位を固めることをおすすめします。早期着手は、リスクの見える化と条件の最適化、ひいては手取りの最大化にもつながります。
不動産M&Aのおすすめの相談先はどこか
まずは不動産に強いM&A仲介やFA(ファイナンシャルアドバイザリー)をハブに、弁護士や公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士とチームで進めることが基本です。
売却を急ぐ中小規模なら事業承継・引継ぎ支援センターや地域金融機関、価格最大化を狙うなら投資銀行のM&Aアドバイザリー部門、大型・複雑案件や資金調達を並行するなら信託銀行や大手デベロッパーの投資部門が適しています。初期比較にはM&Aマッチングサイトの活用も有効です。
選定時は、同種案件の成約実績や利益相反管理、報酬体系(レーマン方式/着手金・ミニマムの有無)、免許(宅建・金商)、守秘体制、案件ソーシング力とクロージング力を確認してください。
不動産M&Aで株価はどのように算定するのか
M&Aにおける企業価値評価(バリュエーション)は、大きく「インカムアプローチ」「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」の3種類に分けられます。
インカムアプローチは将来の収益を基に算定し、コストアプローチは資産や負債を基準に評価、マーケットアプローチは市場株価や類似会社との比較を用います。
M&A仲介会社はこれらを組み合わせて妥当な価格レンジを試算し、金額面での意思決定をサポートします。
まとめ
不動産M&Aは、通常の不動産売買とは異なり、会社や事業全体を対象にすることで、より複雑な法律や税金の問題が絡んでくる点が特徴です。不動産業界の変動や事業拡大を考えている方にとっては、戦略的な選択肢となるでしょう。しかし、スキームや税金の理解不足は大きなリスクを伴うため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。
不動産M&Aを成功させるためには、まずは本記事で紹介した基礎知識をしっかりと押さえ、自社の状況に適したスキームを選ぶことが大切です。さらに、具体的な計画を立てる際には、専門家と一緒にシミュレーションを行い、リスクを最小限に抑えるように心がけましょう。
不動産M&Aに関する具体的な案件やアドバイザーの選定を検討されている方はぜひ一度、M&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。