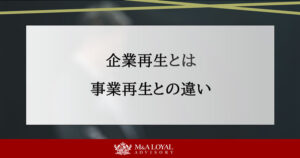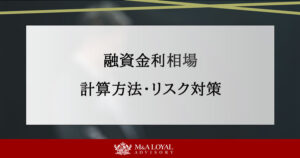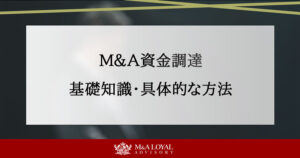プロラタ方式とは?返済の仕組みからメリット、注意点を詳しく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
プロラタとは、金融機関への返済方法の一つです。複数の銀行から借入をしている企業にとって、返済方法の設計は重要な課題です。特に事業再生や資金調達の場面では、すべての金融機関との公平な関係構築が欠かせません。プロラタ方式は、このような状況において、企業と金融機関の双方にメリットのある返済手段です。
この記事では、プロラタ方式の意味や仕組み、種類、メリット・デメリットから返済手順までをわかりやすく解説します。資金調達の幅を広げたい経営者の方に必須の知識となるでしょう。
目次
プロラタとは?その定義と基本的な仕組みを解説
プロラタとは、負担や配分を一定の基準に基づき公平に按分する手法です。特に金融の分野で、複数の債権者間で返済金額を公平に分配する際に利用されます。ここでは、プロラタ方式の基本的な仕組みについて解説します。
プロラタ方式とは
プロラタ方式とは、複数の金融機関からの借入金を借入残高や担保状況に比例して返済する方法です。この方式は、各金融機関に対して公平かつ透明性のある返済を実現できるため、金融機関との信頼関係を築きやすい特徴があります。プロラタ返済は、事業再建やM&Aの場面で資金調達を円滑に進める手法として広く活用されています。
プロラタの語源の意味
プロラタは、金融や事業再生の場面でよく使われる用語です。プロラタの語源は、ラテン語の「Pro Rata」に由来しており、「比例する」「按分する」という意味を持ちます。このことから、プロラタ方式やプロラタ返済は、複数の金融機関から借入をしている企業が、借入額に比例する形で返済額を決定することを意味します。つまり、単純に言えば「比例配分」という考え方です。
返済額を決める際の基準は複数ありますが、どの基準を採用するにしても、公平性を確保するという基本原則は変わりません。プロラタ方式では、この比例配分の仕組みにより、金融機関間の不公平感をなくし、スムーズな資金調達や返済を実現することができます。
プロラタ方式の特徴
プロラタ方式の最大の特徴は、すべての金融機関に対して公平な返済を実現することです。「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」では、事業再生計画案における権利関係の調整は、債権者間で平等であるべきとされています。したがって、返済額の配分も公平性の観点から妥当である必要があります。
例えば、ある企業がA銀行、B信用金庫、C銀行から融資を受けている場合、それぞれの金融機関の借入額や担保状況に応じて返済額を決定します。これにより、特定の金融機関だけが優遇されたり、逆に不利な扱いを受けたりすることを防ぎます。
この公平性の確保は非常に重要で、金融機関同士の争いを防ぎ、円滑な資金調達環境を整える効果があります。また、金融機関からすれば、後回しにされるリスクが減り、融資をしやすくなるというメリットもあるでしょう。
プロラタ方式が事業再生で重要視される理由
プロラタ方式は特に事業再生の場面で重要な役割を果たします。企業の業績が悪化して立て直しが必要な場合は、金融機関に対して借入金の返済を一時停止してもらう必要があります。返済の一時停止中に事業計画を策定し、借入金返済の方針も定めます。
こうしたリスケジュールを行う際、金融機関との協力関係を維持するためには、公平な返済計画の提示が欠かせません。プロラタ方式によって、借入金残高や担保状況に応じた返済計画を立てることで、金融機関からの継続的な支援を受けやすくなります。
また、債権者間の公平性を確保することは、私的整理や法的整理の場面でも重視されます。会社更生や民事再生等の法的整理の場合は、債権放棄の金額(割合)を、総債権額から担保権(別除権や更生担保権)によって担保された債権額を控除した金額を基準として、プロラタ方式により決定することが一般的です。
このように、プロラタ方式は単なる返済方法というだけでなく、企業の存続と再生を支える重要な考え方として、金融実務の現場で広く活用されています。借入金の返済に悩む企業経営者は、この方式について理解を深めることで、金融機関との関係改善や資金繰りの安定化につなげることができるでしょう。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



プロラタ方式の種類
プロラタ方式には主に「残高プロラタ」と「信用プロラタ」という2種類の方式があります。それぞれの計算方法は異なり、どちらを選択するかによって各金融機関への返済額が変わってきます。ここでは、それぞれのプロラタの特徴と計算方法の違いについて詳しく解説します。
残高プロラタとは|計算方法と具体的な返済例
残高プロラタとは、各金融機関からの借入残高をもとに返済額を決める方式です。借入残高が多い金融機関ほど返済比率が高くなるため、返済計画がイメージしやすい特徴があります。一般的に、複数の金融機関が関与する場合は公平性や透明性を重視し、残高プロラタが採用されることが多いです。ただし、担保付き債権や特定の優先順位がある場合は、他の分配方式が適用される場合もあります。
残高プロラタの計算方法は非常にシンプルで、以下の手順で行います。
- 各金融機関の借入残高を確認する
- 全金融機関からの借入残高の合計を算出する
- 各金融機関の借入残高が合計に占める割合(%)を計算する
- 毎月の返済可能額に上記の割合を掛けて、各金融機関への返済額を決定する
【具体例】 借入額が合計1,000万円、月々の返済可能額が20万円の場合
| 金融機関 | 借入残高 | 全体に占める割合 | 月々の返済額 |
| 金融機関A | 500万円 | 50% | 10万円(20万円×50%) |
| 金融機関B | 300万円 | 30% | 6万円(20万円×30%) |
| 金融機関C | 200万円 | 20% | 4万円(20万円×20%) |
| 合計 | 1,000万円 | 100% | 20万円 |
このように、残高プロラタでは、借入残高が最も多い金融機関Aへの返済額が最も多くなります。ただし実務の計算では、端数処理や優先権、法的要件などが加わる場合があるため、状況に応じた調整が必要なこともあります。
信用プロラタとは|担保の扱いと計算例
信用プロラタとは、各金融機関の借入残高のうち、担保や保証によって保全されていない「実質的な無担保・無保証部分(信用供与部分)」に応じて返済額を決める方式です 。 信用プロラタは「非保全残高プロラタ」とも呼ばれます。
信用プロラタでは、不動産担保や預金担保などの物的担保だけでなく、信用保証協会(CGC)による保証など、債権回収が保全されている部分を借入残高から控除して計算します 。これにより、担保や保証を持たない(あるいは少ない)金融機関のリスク部分が優先的に返済される形となり、これらの金融機関にとっては有利な方式となる場合があります 。
信用プロラタの返済額の計算手順は以下のとおりです。
- 各金融機関の借入残高を確認する
- 各借入に対する担保の評価額と、信用保証協会等の保証額を確認する
- 各金融機関の借入残高から担保評価額と保証額を差し引き、「無担保・無保証部分」の残高を算出する
- 各金融機関の「無担保・無保証部分」と全体の割合を確認する
- 全金融機関の「無担保・無保証部分」の合計額を計算する
- 各金融機関の「無担保・無保証部分」が合計額に占める割合(%)を計算する
- 毎月の返済可能額に上記の割合を掛けて、各金融機関への返済額を決定する
【具体例】 借入額が合計1,000万円、月々の返済可能額が20万円の場合
| 金融機関 | 借入残高 | 担保評価額 | 保証協会保証額 | 無担保・無保証部分 | 無担保・無保証部分の割合 | 月々の返済額 |
| 金融機関A | 500万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 (500-200-100) | 40% (200万円/500万円) | 8万円 (20万円×40%) |
| 金融機関B | 300万円 | 0円 | 100万円 | 200万円 (300-0-100) | 40% (200万円/500万円) | 8万円 (20万円×40%) |
| 金融機関C | 200万円 | 0円 | 100万円 | 100万円 (200-0-100) | 20% (100万円/500万円) | 4万円 (20万円×20%) |
| 合計 | 1,000万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 100% | 20万円 |
このケースでは、借入残高は金融機関Aが最も多いものの、担保と保証があるため、無担保・無保証部分では金融機関Bと同額(200万円)となり、返済額も同額(8万円)になります。金融機関Cは借入残高が最も少ないですが、無担保・無保証部分の割合(20%)に応じた返済額(4万円)を受け取ります。
なお、信用プロラタ方式を採用する場合、担保価値の評価が金融機関ごとに異なる可能性があり、その評価に対する合意形成が難しい場合があります 。そのため、計算が複雑になり、金融機関間の調整が難航するケースも存在します。
プロラタ方式を選択する場合に考慮すべき要素
プロラタ方式で、残高プロラタと信用プロラタのどちらかを選択する際にはいくつかのポイントを考慮すると良いでしょう。
担保状況の把握
まず、各金融機関の担保状況を把握することが大切です。担保付き融資が多い場合は残高プロラタが適しているケースが多いですが、無担保融資が多い場合は信用プロラタが有利となる場合があります。ただし、メインバンクが多額の担保を設定している場合、信用プロラタを提案すると反対される可能性が高くなるため、慎重な調整が必要です。
金融機関の交渉力や立場
また、各金融機関の交渉力や立場も考慮すべき要素です。特に、メインバンクとの関係が強い場合、そのメインバンクに有利なプロラタ方式を選択することで交渉がスムーズに進むことがあります。ただし、他の金融機関とのバランスや公平性を考慮し、全体の合意形成を目指すことが重要です。
リスケジュールや追加融資の可能性
さらに、リスケジュールの必要性や将来的な追加融資の可能性も検討する必要があります。プロラタ方式を導入した後は、全ての金融機関の足並みを揃える必要があるため、追加融資が必要になった場合、一部の金融機関が反対すると実現が難しくなります。
専門家の助言
最後に、専門家(税理士や弁護士)のアドバイスを受けることも重要です。彼らは企業の財務状況や各金融機関との関係性を考慮した上で、最適なプロラタ方式を提案してくれるでしょう。どの方式を選択するにしても、すべての金融機関にとって公平で透明性のある条件を設定することが成功への鍵となります。
プロラタ方式を活用するメリット
プロラタ方式は複数の金融機関との取引において多くのメリットをもたらします。プロラタを活用するメリットとして次のことが挙げられます。
- 金融機関からの信頼獲得の促進
- 金融機関との公平な取引の構築
それぞれのメリットについて解説します。
金融機関からの信頼獲得の促進
プロラタ方式の最大のメリットは、金融機関からの信頼を得やすくなることです。契約条件にプロラタ方式について明記することにより、金融機関に対する透明性を高めることができます。これにより、借入企業は金融機関から信頼を獲得しやすくなります。
特に、不測の事態や予期せぬ状況が発生した際に備えて、この方式を契約条項に事前に盛り込んでおくことは、将来的な争いを避ける上で非常に有効です。金融機関の立場から見ると、返済を後回しにされるリスクが軽減されるため、融資を行うハードルが下がります。その結果、スムーズな資金調達や融資額の増加につながる可能性が高まります。ただし、融資の可否は財務状況や担保の有無など、他の要素も含めた総合的な判断に基づきます。
取引実績のない金融機関からも信用を得やすくなるのもプロラタ方式を活用する大きなメリットです。新規の取引先であっても、公平な返済ルールを示すことで、安心感を提供し信用形成に役立つ場合があります。ただし、融資の可否は企業の財務状況や担保の有無など、他の要素も総合的に判断されます。
金融機関との公平な取引の構築
プロラタ方式を採用することで、残高や担保状況など具体的な基準に基づいて返済額が計算されます。これにより、取引期間の長短にかかわらず、すべての金融機関に対して公平な取引条件を提供することができます。
特定の金融機関を優先して返済するという不公平な状況を避けられるため、金融機関間の争いを防ぎ、円滑な資金調達環境を整える効果があります。また、取引参加者それぞれの条件に応じた公平な扱いを提供するため、金融機関からの信頼を得やすくなり、結果として継続的な支援を受けられる可能性が高まります。
この公平性の確保は、特に事業再生や資金繰りが厳しい状況においては非常に重要です。「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」でも、債権者間の公平性が重視されており、プロラタ方式はその要件を満たす有効な手段となります。
プロラタ方式で返済する際のデメリットや注意点
プロラタ方式には、いくつかの注意すべきデメリットも存在します。資金調達や返済計画を立てる際には、これらのポイントを理解した上で活用することが重要です。プロラタ方式の返済手段のデメリットは次のとおりです。
- 種類によって生じる不利益
- 全行一致でないと進められない
- 交渉や返済調整に専門知識が必要
- 融資条件の変更が難しい
それぞれについて解説します。
種類によって生じる不利益
プロラタ方式には残高プロラタと信用プロラタの2種類がありますが、どちらを選択するかによって不利益を被る金融機関が生じる可能性があります。
残高プロラタ方式は、担保なしの金融機関にとって不利な場合があります。融資先が返済途中で破産した場合、借入残高全額が回収不能になる可能性があるためです。このリスクを考慮すると、無担保で融資を行っている金融機関は、残高プロラタ方式に対して抵抗感を示すかもしれません。
一方、信用プロラタ方式は、担保ありの金融機関にとって不利になる場合があります。融資先が破産した場合、多くの借入残高が未回収のまま残ることがあるためです。また、担保評価額が期待したよりも低い場合にも不利益を被る可能性があります。
このように、どちらの方式を選択するかは、各金融機関の担保状況や立場によって意見が分かれるため、慎重な検討と交渉が必要です。
全行一致でないと進められない
プロラタ方式の大きなデメリットの一つとして、全行一致が求められる点が挙げられます。プロラタ方式を採用する場合、すべての債権者が同意しなければ手続きが進められないため、合意形成が非常に困難になることが多いです。特に、金融機関や投資家などが関与する場合、それぞれの利害関係が異なるため、全ての関係者を納得させるには多くの時間と労力を要します。
さらに、各債権者が異なる条件を求めることもしばしばであり、その調整においては、非常に高い交渉能力が必要とされます。全行一致の条件を満たせない場合、プロラタ方式自体が頓挫するリスクもあるため、最初から代替案を用意しておくことが重要です。
また、全行一致が必要なために、各債権者が個別に持つ権利や主張が複雑に絡み合い、交渉が長期化することもあります。このような状況では、債務者の負担が増加し、事業再生や資金調達のスピードが遅れる可能性が高まります。
全行一致の原則があることで、プロラタ方式の活用が現実的に難しい場合もあるため、事前に関係者間での十分なコミュニケーションを行い、可能な限り早期に合意を得るための戦略を立てることが求められます。したがって、全行一致の要件をクリアするためには、計画的かつ戦略的なアプローチが不可欠であり、この点がプロラタ方式の大きな課題といえるでしょう。
交渉や返済調整に専門知識が必要
プロラタ方式を利用する際の大きな課題の一つは、交渉や返済調整において専門知識が必要とされる点です。プロラタ方式は、複数の債権者間での公平な返済を目指すため、各債権者の残高や利率、担保状況などを考慮した精密な計算と交渉が求められます。このプロセスでは、各債権者との合意を形成するための交渉力が重要となり、交渉が不調に終わると、返済計画全体が頓挫する可能性もあります。
また、プロラタ方式は法律や金融に関する深い理解が必要であり、専門的な知識がないと、交渉の場で不利な立場に立たされることがあります。例えば、各債権者が主張する条件を理解し、それを基に適切な提案を行うには、金融商品の知識や法的な制約を熟知していることが不可欠です。
専門家の助言を受けることで、交渉がスムーズに進む可能性は高まりますが、これには追加のコストが発生します。したがって、プロラタ方式を効果的に運用するためには、交渉の経験や専門的なスキルが不可欠となります。
融資条件の変更が難しい
プロラタ方式を導入した後は、すべての金融機関の足並みを揃える必要が出てくるという点も注意が必要です。「全行一致」が原則となるため、追加融資やリスケジュールなど融資条件の変更が必要になった場合、一部の金融機関が反対すると実現が難しくなります。
リスケジュールを行う場合は、専門家(税理士や弁護士など)の助言を得て経営改善計画書などを作成し、適切な返済額を計算することが重要です。根拠のない返済額に基づくリスケジュールは、合意した計画を実行できず、見直しが必要になる恐れがあります。
また、金融機関によっては、当初の設定より返済額が少なくなり返済期間が長引くことを受け入れがたいと判断するケースもあります。そのため、導入前には各金融機関の意向をしっかりと確認し、専門家のサポートを受けながら交渉を進めることが望ましいでしょう。
このように、プロラタ方式には金融機関からの信頼獲得や公平性確保などのメリットがある一方で、方式選択による不利益や融資条件変更の難しさなどのデメリットも存在します。これらを正しく理解した上で、自社の状況や金融機関との関係性に合わせた最適な選択をすることが重要です。
プロラタ方式を成功させる5つの重要ポイント
プロラタ方式を導入する際には、金融機関との交渉がスムーズに進むよう、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、プロラタ方式での返済を成功させるための5つのポイントを紹介します。
- 借入状況を正確に把握する
- 効果的な交渉アプローチ
- 専門家の戦略的活用
- 実行可能な返済計画の策定
- 実施後の継続的な金融機関との関係維持
それぞれについて解説します。
借入状況を正確に把握する
プロラタ方式による返済を検討する第一歩は、各金融機関からの借入残高を正確に把握することです。金融機関との交渉の土台となる重要な情報であり、返済計画の根拠となるものです。
正確な借入状況を把握するためには、以下の点に注意しましょう。
- 各金融機関の借入残高を顧問税理士や公認会計士などの専門家に依頼して洗い出す
- 担保の有無や担保価値も含めて整理する
- 返済条件(金利、返済期間など)も確認する
- 現状の返済能力と照らし合わせた分析を行う
借入状況の把握が不正確だと、後の交渉段階で問題が生じる可能性があります。特に担保状況は信用プロラタを検討する場合に重要となるため、漏れなく確認することが大切です。正確な情報に基づいた交渉が、金融機関からの信頼獲得にもつながります。
効果的な交渉アプローチ
プロラタ方式の導入には、すべての金融機関の同意が必要です。そのため、効果的な交渉アプローチが成功のカギとなります。
効果的な交渉のために心がけるべきポイントは以下のとおりです。
- 一度に複数の金融機関と協議することで公平性を保つ
- 順番に交渉を始めるのではなく、同時並行で進める
- 各金融機関の立場や状況を考慮した提案を準備する
- 誠実かつ透明性のある姿勢で臨む
- 金融機関にとってのメリットを明確に示す
特に重要なのは、「一度に複数の金融機関と協議する」という点です。順番に交渉を始めると、金融機関間で不公平感が生じるリスクがあります。プロラタ方式の目的は債権者間の公平性を確保することであり、交渉の進め方自体も公平であるべきです。
また、交渉においては金融機関側のメリットを明確に示すことも重要です。プロラタ方式を導入することで、返済が後回しにされるリスクが減り、他の金融機関の動向も把握できるという安心感を提供できる点を強調しましょう。
専門家の戦略的活用
プロラタ方式の交渉には、弁護士、税理士、公認会計士、M&A仲介会社などの専門家のサポートを活用することをおすすめします。専門家を戦略的に活用することで、交渉をより有利に進めることができます。
専門家を活用するメリットには以下のようなものがあります。
- 専門家の同席により交渉力が高まる
- 経営者の精神的負担を軽減できる
- 本業に専念するための時間を確保できる
- 客観的な立場からの意見を金融機関に提示できる
- 経営改善計画書などの作成支援を受けられる
金融機関にとっても、専門家が同席することで客観的な意見を聞けるというメリットがあります。また、専門家には金融機関との交渉経験が豊富な場合が多く、その経験やノウハウが交渉を成功に導く大きな力となるでしょう。
特に、経営コンサルタントやM&A仲介会社と共に経営改善計画書を作成することは、金融機関の信頼を得るために有効です。専門家の力を借りて作成した計画書は説得力があり、金融機関に受け入れられやすくなります。
実行可能な返済計画の策定
プロラタ方式を金融機関に提案する際、実行可能な返済計画を策定することが非常に重要です。理想的すぎる計画や根拠のない返済額の提案は、金融機関の不信感を招くリスクがあります。
実行可能な返済計画を策定するためのポイントは以下のとおりです。
- 経営改善計画書などを作成し、適切な返済額を計算する
- 根拠のある数字に基づいた計画を立案する
- 自社の返済能力に見合った現実的な計画を提示する
- 金融機関が納得できる将来展望を示す
- 事業計画との整合性を確保する
特に重要なのは、「返済が滞ることなく返済できる金額を冷静に判断する」という点です。過度に楽観的な計画を立てると、後に返済が滞り、金融機関との信頼関係を損なう可能性があります。
また、金融機関ごとの返済額や返済期間を明確にし、全行一致での返済になるよう調整することも必要です。プロラタ方式は「全行一致」が原則であり、すべての金融機関に対して同時に返済を終えることを目指す必要があります。
実施後の継続的な金融機関との関係維持
プロラタ方式の導入が成功した後も、金融機関との良好な関係を維持することが重要です。特に、将来的な追加融資や条件変更の可能性を考えると、継続的な関係構築が欠かせません。
良好な関係を維持するためのポイントは以下のとおりです。
- 返済計画の実行状況を定期的に報告する
- 事業の進捗状況を共有し信頼関係を構築する
- 問題発生時には早期に相談する姿勢を持つ
- 全ての金融機関と公平に情報共有を行う
- 将来的な資金需要に備えて良好な関係を維持する
プロラタ方式導入後は、すべての金融機関の足並みを揃える必要が出てくるため、一部の金融機関との関係が悪化すると、全体に影響が及ぶリスクがあります。そのため、すべての金融機関と平等に良好な関係を維持することが重要です。
定期的な経営状況の報告や、早期の相談など、コミュニケーションを大切にすることで、金融機関からの信頼を維持・強化していきましょう。それが将来的な資金調達をスムーズにする基盤となります。
以上の5つのポイントを押さえることで、プロラタ方式の導入と運用を成功させることができるでしょう。特に専門家のサポートを受けながら、金融機関との良好な関係構築を意識することが重要です。
プロラタ方式による返済の実践的な手順と流れ
プロラタ方式による返済を実施するためには、適切な手順に従って進める必要があります。ここでは、プロラタ方式導入から実際の返済開始までの実践的な手順と流れを解説します。
プロラタ方式での返済の流れは以下の手順で行われます。
- 借入残高の確認と返済資金の算出
- 金融機関への交渉
- 返済条件の調整と合意
- 一斉返済の開始
それぞれについて解説します。
借入残高確認と返済資金の算出
プロラタ方式を実施する第一歩は、各金融機関からの借入残高を正確に把握することです。この段階では以下の手順で進めていきます。
まず、税理士や公認会計士などの専門家に依頼して、各金融機関の借入残高を正確に確認します。この際、単に借入金額だけでなく、担保状況(不動産担保、預金担保など)も合わせて把握することが重要です。特に信用プロラタ方式を検討している場合は、各金融機関の担保評価額を明確にする必要があります。
次に、自社の返済能力を分析し、毎月または毎年の返済可能額を算出します。ここで重要なのは、過度に楽観的な見積もりを避け、確実に返済できる金額を設定することです。経営状況や将来の見通しを冷静に分析し、無理のない返済額を算出しましょう。
最後に、残高プロラタか信用プロラタのどちらの方式を採用するかを決定し、各金融機関への返済額を計算します。例えば、月々の返済可能額が100万円で、A銀行(借入残高5,000万円、50%)、B銀行(借入残高3,000万円、30%)、C銀行(借入残高2,000万円、20%)からの借入がある場合、残高プロラタ方式ではA銀行に50万円、B銀行に30万円、C銀行に20万円の返済となります。
この段階で作成する資料は、今後の金融機関との交渉の基礎となるものですので、正確かつ根拠のある数字を示すことが大切です。
金融機関への交渉
借入残高と返済額の計算が完了したら、次は金融機関への提案と説得のプロセスに移ります。この段階では交渉力が問われますので、以下のポイントを押さえましょう。
弁護士やM&A仲介会社などの専門家同席のもと、借入先の金融機関へプロラタ方式での返済を打診します。この際、一度に複数の金融機関と協議することで公平性を保つことが重要です。順番に交渉を始めると、先に交渉した金融機関と後から交渉する金融機関の間で不公平感が生じる可能性があります。
交渉の場では、経営改善計画書や返済計画書を提示し、プロラタ方式を採用する理由や各金融機関にとってのメリットを具体的に説明します。ここでのキーポイントは、「すべての金融機関が公平に返済を受けられる」という点と、「返済を後回しにされるリスクが軽減される」という点です。
また、各金融機関の特性や立場を考慮した提案を行うことも重要です。例えば、担保を持つ金融機関と担保を持たない金融機関では利害が異なるため、それぞれに対する説明の仕方を工夫する必要があります。
返済条件の調整と合意
金融機関からの基本的な合意が得られたら、次は具体的な返済条件の調整と最終合意の文書化を行います。この段階では以下の点に注意しましょう。
各金融機関と相談しながら返済計画の細部を調整します。返済額だけでなく、返済期間や金利条件なども含めて協議し、すべての金融機関が納得できる内容に調整することが重要です。場合によっては、当初の計画から一部修正を加える必要もあるでしょう。
全ての金融機関との調整が完了したら、合意内容を文書化し、契約書を作成します。この契約書には、各金融機関への返済額、返済スケジュール、プロラタ方式の種類(残高プロラタか信用プロラタか)などを明確に記載します。文書化することで、後々の解釈の違いによるトラブルを防ぐことができます。
最終的に、すべての金融機関との契約が締結されたら、合意された計画に基づいて一斉に返済を開始します。プロラタ方式では「全行一致」が原則であり、すべての金融機関に対して同時に返済を行うことが重要です。
プロラタ方式による返済が始まっても、定期的に返済状況を各金融機関に報告し、良好な関係を維持することが大切です。特に、事業環境の変化により返済計画の見直しが必要になった場合は、早めに相談する姿勢を持ちましょう。
このように、プロラタ方式による返済を成功させるためには、準備段階から実施段階まで、計画的かつ誠実に進めることが重要です。専門家のサポートを受けながら、各ステップを着実に進めていくことで、金融機関との良好な関係を構築し、資金調達環境を改善することができるでしょう。
一斉返済の開始
計画に基づいて各金融機関に対して同時に返済を行います。ここで重要なのは、プロラタ方式では、全行に対して同時に返済を開始し、終了させる点です。これにより、特定の金融機関だけが優遇されることなく、公平性が担保されます。
プロラタによる返済の実行は、指定された期日に各金融機関の口座に対して同時に行われます。ここでのポイントは、事前に設定したスケジュールに基づき、遅延や不足が発生しないようにすることです。この一斉返済のステップがスムーズに進むことで、事業再生が成功に近づくとともに、金融機関との信頼関係が強化され、今後のビジネス展開においても良好な関係を維持することが可能となります。
M&Aの資金調達におけるプロラタ方式の活用法
M&Aを実行する際には、買収資金の調達が重要な課題となります。特に中小企業のM&Aでは、自己資金だけで買収金額をまかなえないケースが多く、複数の金融機関から資金調達が必要です。プロラタ方式を活用すれば、公平な返済計画を提示でき、資金調達の可能性が広がることが期待されます。
プロラタ方式を使ったM&A買収資金の効果的な調達戦略
M&A買収資金を複数の金融機関から調達する際、プロラタ方式を前提とした融資交渉を行うことで、より多くの金融機関から協力を得られる可能性が高まります。プロラタ方式では、すべての金融機関が借入金額に応じて平等に返済を受けられるため、金融機関側にとってもリスクが分散され、融資に応じやすくなるからです。
効果的な調達戦略としては、まずメインバンクと協議し、買収金額の一部をメインバンクから調達する基本合意を得た上で、残りの資金を他の金融機関から調達するアプローチが考えられます。この際、「プロラタ方式による返済を前提とする」ことを明確にすることで、新規取引の金融機関も含めて資金調達の可能性が広がります。
また、M&A特有の資金需要に対応するため、買収後の事業計画に基づいた返済計画を立案し、金融機関に提示することも重要です。買収によるシナジー効果や将来のキャッシュフローを具体的に示すことで、金融機関の信頼を獲得しやすくなります。
特に大型のM&A案件では、シンジケートローンを組成する際にプロラタ方式が採用されることが一般的です。シンジケートローンとは、複数の金融機関がシンジケート団を組成し、同一の取引条件で融資を行う協調融資のことで、一つの金融機関では対応できない多額の資金調達が可能になります。
複数の金融機関を巻き込む交渉テクニック
M&A資金調達において複数の金融機関を巻き込むためには、効果的な交渉テクニックが欠かせません。以下に、実践的なアプローチを紹介します。
まず、メインバンクを主幹事(アレンジャー)として立て、他の金融機関との調整役を担ってもらうことが有効です。メインバンクが取りまとめ役を担うことで、交渉の効率が高まり、企業側の負担も軽減されます。この際、プロラタ方式による公平な返済条件を明確に示すことで、メインバンク以外の金融機関も参加しやすくなります。
次に、各金融機関の特性や立場を考慮した提案を行うことが重要です。例えば、担保を持つ金融機関には残高プロラタのメリットを、無担保で融資する金融機関には信用プロラタのメリットを説明するなど、各金融機関にとってのメリットを強調する戦略が効果的です。
また、M&A仲介会社や弁護士などの専門家を交渉に同席させることで、専門的な観点からの説明が可能になり、金融機関の理解を得やすくなります。M&Aのスキームやシナジー効果についての専門的な説明は、資金調達の成功率を高める重要な要素です。
特に、地方銀行など地域に根ざした金融機関を巻き込む場合は、M&Aによる地域経済への貢献や雇用維持などの社会的意義も強調すると効果的です。金融機関にとっても、地域経済の活性化につながるM&Aへの融資は、社会的責任を果たす機会となります。
M&A後の返済計画におけるプロラタ方式の最適な適用方法
M&A実行後の返済計画においてプロラタ方式を最適に適用するためには、買収後の事業計画との整合性を確保することが重要です。M&A後は事業統合や組織再編などで想定外の支出が発生することもあるため、柔軟性を持った返済計画を立案する必要があります。
まず、買収後のキャッシュフロー予測に基づいて返済額を決定することが基本です。統合後の事業から得られる年間フリーキャッシュフローを見積もり、それを超えない範囲で返済額を設定します。この際、景気変動や事業環境の変化に備えて、余裕を持った計画を立てることが肝要です。
また、M&A後のシナジー効果が現れるタイミングを考慮した返済スケジュールを設計することも重要です。一般的に、M&A後のシナジー効果が本格化するのは統合から1〜2年後であることが多いため、最初の数年間は返済額を抑え、その後徐々に増加させるといった段階的な返済計画が有効です。
万が一、事業計画通りに進まない場合に備えて、返済条件の見直しについても金融機関と事前に協議しておくことが望ましいでしょう。特に、プロラタ方式を採用している場合は、条件変更には全ての金融機関の同意が必要となるため、返済猶予や条件変更の可能性についても予め話し合っておくことが重要です。
このように、M&A資金調達においてプロラタ方式を活用することで、複数の金融機関から協調して資金を調達し、買収後も安定した返済を行うことが可能になります。特に中小企業のM&Aでは、限られた資金調達手段の中で最大限の効果を得るために、プロラタ方式の特性を理解し、戦略的に活用することが成功のカギとなるでしょう。
まとめ|プロラタ方式を正しく理解して資金調達を成功させよう
プロラタ方式は複数の金融機関からの借入金を借入額に比例して返済する方法です。残高プロラタと信用プロラタの2種類があり、金融機関間の公平性を確保することを目的としています。メリットとしては、金融機関からの信頼獲得を促進し、円滑な資金調達が可能になることが挙げられます。
ただし、導入後の融資条件変更の難しさというデメリットも存在します。成功のポイントは、借入状況の正確な把握、効果的な交渉アプローチ、専門家の活用、実行可能な返済計画の策定、継続的な金融機関との関係維持です。M&A資金調達においても、プロラタ方式は有効な手段となるため、専門家のサポートを受けながら戦略的に活用し、資金調達の幅を広げましょう。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継に関するご相談を承っております。会社売却をご検討の際にはお気軽にお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。