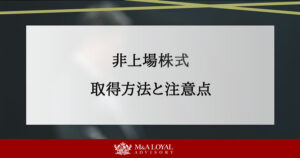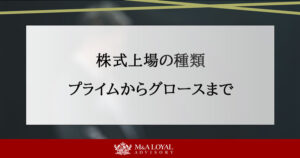非上場企業とは?特徴やメリット・デメリット、未上場との違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
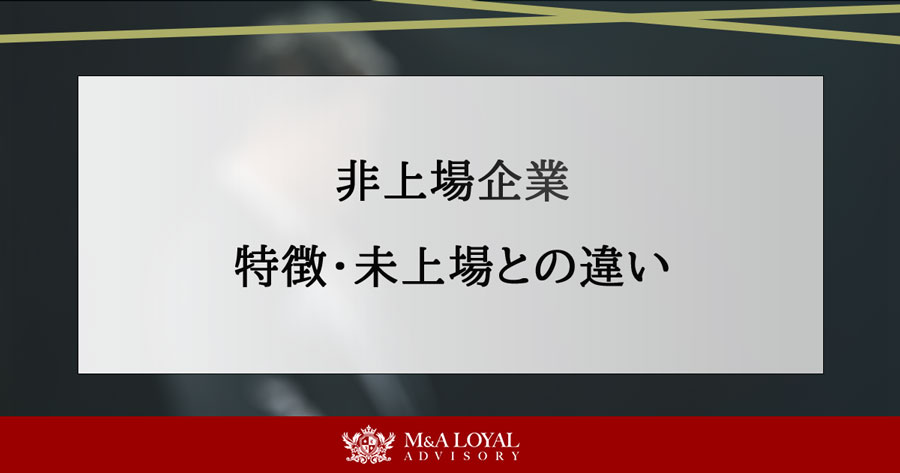
非上場企業は、株式を証券取引所に上場していない企業を指し、上場企業とは異なる経営方針や資本政策を採用していることが多くあります。
外部からの資金調達が限定される一方で、経営の自由度が高く、短期的な業績に左右されにくいといった特徴もあります。しかし、株式の流動性や企業価値の可視化といった面では課題も存在します。
本記事では、非上場企業の定義から、上場企業との違い、具体的な利点と留意点までを分かりやすく解説します。
目次
非上場企業の定義
まず、非上場企業に関する基本的な知識について解説します。
非上場企業とは
非上場企業とは、自社の株式を証券取引所に上場していない会社のことです。一般の投資家が証券会社を通じて自由に株式を売買できる市場(証券取引所)に、その会社の株式が公開されていない状態を指します。
日本企業の約99.9%が非上場企業であり、上場している企業はごく一部です。
上場とは
上場とは、企業が発行する株式を、東京証券取引所のような証券取引所で誰でも売買できるようにすることを指します。
上場することで、企業は不特定多数の投資家から広く資金を調達できるようになり、社会的な信用度が高まります。一方で、厳しい情報開示義務や監査など、さまざまな制約も課せられます。
株式会社とは
株式会社とは、株式を発行することによって出資者(株主)から資金を調達し、その資金で事業を行う会社の形態です。出資者である株主は、会社の所有者となり、株主総会を通じて会社の経営に参加したり、配当を受け取ったりする権利を持ちます。
上場できるのは株式会社のみです。合同会社や有限会社の場合、株式を発行しないため、証券取引所で売買される対象とはならず、上場できません。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



非上場企業のメリット
非上場企業であることのメリットは次のとおりです。
- 経営の自由度が高い
- 競合分析がされづらい
- 上場維持のコストが削減できる
- 買収されるリスクが低い
- 親族内承継がしやすい
それぞれについて解説します。
経営の自由度が高い
非上場企業は、外部の株主から短期的な利益追求を迫られることが少なく、中長期的な視点での経営判断が可能です。
また、証券取引所の規制や開示義務に縛られることがないため、意思決定のスピードも上場企業に比べて格段に速いです。例えば、M&Aや事業再編などの重要な施策も、社内の合意を得られれば柔軟に実行できます。
さらに、株式を外部に公開しないことで経営権を安定的に維持できる点も大きな利点であり、自社の方針に賛同する株主のみを選定することで、一貫性のある経営体制が築けます。
競合分析がされづらい
非上場企業は、上場企業と異なり財務諸表や経営戦略に関する詳細な情報を一般に公開する義務がありません(ただし、日本の会社法第440条により、非上場企業も貸借対照表の公告は義務付けられています)。
そのため、競合他社に対して自社の収益構造や事業展開の方針を知られるリスクが低く、競争上の不利を回避しやすい点がメリットです。
特にニッチ市場や技術系の企業にとって、経営上の重要情報を外部から見えにくくできることは、大きな競争力の源泉といえます。
上場維持のコストが削減できる
上場企業は、上場後も継続的に監査対応やIR活動、コンプライアンスの徹底など、多くの法的・事務的な負担を抱えます。
具体的には、四半期ごとの決算報告や株主総会の開催、開示資料の作成といった定型業務にかかる人件費・外部委託費を含めると数千万円に及びます。また、情報公開に伴うリスク管理のための内部体制の構築も必要です。
しかし、非上場企業であればこうした維持コストを削減できます。経営資源を本業に集中させやすい点が中小企業やベンチャー企業にとって大きなメリットです。
敵対的買収を受けるリスクがほぼない
非上場企業は株式を市場に公開していないため、敵対的買収を受けるリスクが極めて低いという特徴があります。
上場企業の場合、株式を一定割合以上取得した第三者が経営に介入できますが、非上場企業では経営権を意図しない外部に奪われるリスクがほとんどありません。
株式の譲渡についても、株主間契約や定款によって厳格な制限を設けているケースが多く、信頼できる関係者の間でのみ株式を保有させる形が一般的です。
親族内承継がしやすい
非上場企業は、株式の保有構造が限定的であることが多く、創業者やその家族、特定の役員に株式が集中しているケースが一般的です。このため、後継者への事業承継がスムーズに行えるという大きな利点があります。
例えば、株式を段階的に移転したり、持株会社を通じて支配権を移行するなど、柔軟な手法が可能です。また、事業承継時には外部株主の意向を調整する必要がないため、計画に沿った承継が実現しやすく、企業の文化や理念を次世代にしっかりと引き継ぐことができます。
非上場企業のデメリット
非上場企業のデメリットは次のとおりです。
- 資金調達手段が制限される
- ガバナンスが効きづらい
- 社会的な信用度や認知度が低くなる
- 客観的な企業評価が難しい
- キャピタルゲインを得られない
それぞれについて解説します。
資金調達手段が制限される
非上場企業は株式を市場に公開していないため、新株発行による資金調達の際に自ら投資家を探す必要があり、上場企業に比べてスピードや効率の面で劣ります。
市場で株価が形成されないため、企業評価は購入者との交渉によって決まり、想定よりも資金が集まらないリスクもあります。
特に成長段階や新規事業の立ち上げ時には、資金調達の柔軟性に欠けることが経営の制約となり得ます。
ガバナンスが効きづらい
非上場企業は外部株主や証券取引所からの監視が弱いため、ガバナンスが形骸化するリスクがあります。
特にオーナー経営が色濃い企業では、意思決定が少数の経営陣に集中しやすく、経営の透明性や客観性が欠ける場合があります。これらが不正や利益相反の温床になる懸念も否定できません。
健全な経営を維持するには、社内規定や監査体制の自発的な整備が求められますが、それが後回しにされやすい現実があります。
社会的な信用度や認知度が低くなる
非上場企業は、上場企業のように証券取引所による厳格な審査を受けておらず、管理体制や経営の透明性が外部から見えづらい傾向があります。
そのため、取引先や金融機関からの信頼を得るのに時間がかかり、社会的信用や知名度で劣ることがあります。
また、信用力が低いと人材確保の観点からも不利といえます。
客観的な企業評価が難しい
非上場企業は市場での株価が存在しないため、企業価値を客観的に把握することが難しいという課題があります。
財務諸表や将来性の評価に依存しますが、その妥当性は評価者によって大きく異なる場合があります。
特にM&Aや事業承継の場面では、株式の評価額に関して当事者間で認識の差が生じやすく、交渉の長期化や条件面の対立に発展することもあります。また、従業員にとっても自社株の資産価値が曖昧になるというデメリットがあります。
キャピタルゲインを得る機会が減る
非上場企業の株式は市場で売却できないため、創業者がキャピタルゲインを得る機会は売却しかありません。
上場の予定がなければ、従業員へのストックオプション制度の実現が難しく、インセンティブ設計の幅が狭まります。
たとえ企業の成長によって企業価値が上がったとしても、創業者を含めモチベーションの維持が難しいリスクがあります。
代表的な非上場企業10選
代表的な非上場日本企業を10社紹介します。有名な非上場企業であっても、実際は親会社が上場しているパターンが少なくありません。ここでは、上場していない企業に限定して紹介します。
サントリーホールディングス
サントリーホールディングス株式会社は、1899年に大阪で創業し、2009年に持株会社制へ移行した、日本を代表する総合飲料・食品メーカーです。グループ企業数は約265社、従業員は約4万人と大規模です。
創業家が所有する資産管理会社である寿不動産株式会社がサントリーホールディングス株式会社の9割近くの株式を所有しています。
サントリーHDは非上場企業ですが、上場企業と同等レベルの情報開示やガバナンス体制を自主的に整えています。ちなみに、サントリーHDの子会社であるサントリー食品インターナショナル株式会社は2013年7月3日に東京証券取引所プライム市場に上場しました。
YKK
YKK株式会社は、創業者𠮷田忠雄が東京都日本橋で設立した、世界最大のファスナーメーカーです。YKKグループの従業員は2025年3月31日現在46,305名、連結売上高は2024年度9,982億円に上ります。
YKKおよび子会社のYKK APは上場しておらず、創業者の𠮷田忠雄は株式を「事業への参加証」と捉え、社員こそ株を持つべきと考えていました。現在も筆頭株主は従業員持ち株会であり、給与に関係なく平等に株式を保有し、配当を受ける仕組みです。
社内預金や持ち株制度を通じて資金を社内に循環させ、実質無借金経営を維持しているため、上場による資金調達の必要性がありません。また、1999年には執行役員制度を導入し、ガバナンス体制も上場企業並みに整えています。
竹中工務店
株式会社竹中工務店は、大阪市に本社を構える歴史あるスーパーゼネコンで、1610年創業、1899年に法人設立された建設のリーディング企業です。2024年度の連結売上高は約1.6兆円、従業員数は約7,800名で、国内外に支店や営業所を広く展開しています。
竹中工務店は、建築を一過性の事業と捉えるのではなく、50年先、100年先を見据えた社会的・文化的資産の形成であると位置付けています。そのため、短期的な業績に左右されることなく、長期的な視点から建築の質と価値を追求できる非上場という形態を選択しています。
また、こうした理念は建築の枠を超え、現在ではまちづくりや環境保全などの分野にも広がっており、経済性のみならず社会的意義を重んじた事業活動を継続しています。
ヤンマーホールディングス]
ヤンマーホールディングス株式会社は、1912年に創業された、農業機械や建設機械を販売する大手メーカーです。グループ全体で2024年3月31日現在21,553名の従業員を抱え、連結ベースの売上高は2024年3月期で1兆814億円に上ります。
ヤンマーHDは上場していないものの金融機関から高い信用を得ており、安定的かつ低金利での資金調達が可能な体制を構築しています。また、短期的な業績への圧力から自由であることで、設備投資や研究開発といった将来を見据えた施策を実行できることをメリットとしています。
ジャパネットホールディングス
株式会社ジャパネットホールディングスは2007年にジャパネットたかたの持株会社として設立されました。1986年にたかたカメラグループより分離独立し、「株式会社たかた」を設立したことが始まりです。2024年12月期のグループ連結売上高は2725億円に上ります。
ジャパネットHDも上場の必要性を感じないとしています。既に知名度が一定あることや設備投資が不要であることなどが理由です。また、株主への配当より従業員の福利厚生を重視する姿勢を重視しています。
大創産業
株式会社大創産業は1977年に設立され、現在は100円ショップ「DAISO」を主軸に、「Standard Products」「THREEPPY」など複数のブランドを展開する大手製造小売企業です。売上高は2025年2月末現在連結で7,242億円に上り、745名の正社員を抱えています。
大創産業は以前上場準備のうわさがありましたが、現在でも非上場を貫いています。
ちなみに、上場している化学メーカーである株式会社大阪ソーダの旧社名がダイソー株式会社ですが、大創産業とは全く無関係です。
アパグループ
アパグループ株式会社は1971年に設立された、ビジネスホテル「アパホテル」の開発・運営やマンションの開発・分譲を中心に事業を展開する不動産デベロッパーです。2024年11月期連結決算は2,260億円と2年連続で過去最高を記録しました。
創業者の元谷外志雄氏は、単に資金を集める手段としての上場には否定的であり、むしろ非上場を貫くことで独自の経営スタイルを確立してきました。
同社は、自社で資産を保有しながら経営を行うことにより、強固な財務体質を築いており、外部資金に頼らずとも有利な条件で資金調達が可能としています。
講談社
株式会社講談社は1909年創業の日本を代表する総合出版社です。2025年4月現在972人の従業員を抱え、2024年度の売上高は1710億円に上ります。
出版社には非上場が多い点が特徴です。短期的な利益よりも編集方針や作家との信頼関係など、長期的視点と文化的価値を重視する経営が求められるためです。上場すると株主への説明責任や利益追求が強まり、作品の質や出版自由度に影響が出る可能性があるとしています。
また、出版業は景気変動やヒット作の有無で業績が大きく変動するため、安定した株価維持が難しい側面もあります。
DMM.com
合同会社DMM.com(DMM.com LLC)は、1999年創業の日本最大級の総合インターネット企業です。従業員数は2,584名で、2024年の売上高は3,637億円に上ります。
DMMグループの亀山敬司氏は上場維持のコストや長期的な視座で経営が行えなくなることを懸念しており、非上場を貫いています。非上場企業でありながら、2023年には社員に利益を還元するために持株会を始めたことで話題になりました。
JTB
株式会社JTBは、1912年に「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」として創業され、1945年に「財団法人日本交通公社」と改称されました。その後、1963年に営業部門が分離独立し、「株式会社日本交通公社」(現・株式会社JTB)として民間企業としての歩みを開始しました。一方、元の財団法人は観光に関する調査・研究機関としての役割に特化し、現在の公益財団法人日本交通公社へと引き継がれています。
設立時の性質や企業文化の中に根強く残る「公益性」「非営利性」が、上場を目指さない経営方針につながっていると考えられます。
非上場化の定義
次に、非上場化について解説します。
非上場化とは
非上場化とは、上場企業の経営陣が自らの意思で上場廃止を選択することを指します。
「株式非公開化」「ゴーイングプライベート」「プライバタイゼーション」ともいわれます。
上場廃止とは
上場廃止とは、金融商品取引所に上場している企業の株式が、一定の理由により取引所での売買対象から外れることを指します。
上場廃止には非公開化以外にも、取引所が定めた基準に抵触し会社の意に反する形で実施されるものもあります。
具体的な基準には、株主数や時価総額、債務超過、法的手続きの開始、不適切な合併、有価証券報告書の虚偽記載・提出遅延などがあります。
取引所は上場廃止の可能性がある銘柄を「監理銘柄」、廃止が決定した銘柄を「整理銘柄」に指定し、投資家への周知を行います。
非上場化する理由
上場企業が非公開化を決定する理由には次のものがあります。
- 上場企業であるメリットを享受できなくなったため
- 株価が低迷し思うような資金調達ができないため
- 親子上場の利益相反を解消するため
それぞれを分かりやすく解説します。
上場企業であるメリットを享受できなくなったため
非上場化の主な目的は、前述した非上場企業としてのメリットを享受することにあります。
上場企業は株主からの短期的な利益圧力や情報開示義務など、多くの制約を受けますが、非上場化することでこうした外的要因から解放され、経営の自由度が高まります。
また、上場維持にかかるコストを削減できるほか、敵対的買収のリスクも低減できます。
さらに、株式を市場に出さないことで、親族や特定関係者による円滑な事業承継も実現しやすくなります。
株価が低迷し思うような資金調達ができないため
上場の最大のメリットは、株式を発行して資金を調達できる点にあります。
しかし、株価が長期にわたって低迷している場合には、株式の流動性が低下し、株主や投資家間での売買が活発に行われにくいです。その結果、上場の意義が薄れ、上場を維持する合理性が損なわれることがあります。
このような状況において、企業が市場で適正に評価されていないと判断した場合、経営の自由度や中長期的な成長戦略の実現を重視し、非上場化に踏み切るケースがあります。
また、前述の内容とも関連しますが、株価が低いと敵対的買収の脅威にさらされるというリスクもあります。
親子上場の利益相反を解消するため
親会社と子会社が同時に上場している「親子上場」の状態では、経営判断や資本政策において両者の利益が必ずしも一致せず、利益相反が生じる可能性があります。
特に、親会社が子会社の支配株主である場合、少数株主の権利が十分に保護されないといった問題が指摘されることがあります。
こうした状況を解消し、グループ全体の経営戦略をより効率的かつ統一的に進めるため、子会社を非上場化するケースが増えています。
非上場化の手段
非上場化の手段は次の二つに大別されます。
- MBO
- 親会社による上場子会社の完全子会社化
それぞれについて解説します。
MBO
MBO(マネジメント・バイアウト)とは、企業の経営陣が自ら出資者となり、外部の投資ファンドなどと連携して株式を取得し、経営権を掌握する手法です。
MBOの実行は通常、まず公開買付け(TOB)を通じて既存株主から株式を取得する段階から始まります。TOB後、全株式を取得できなかった場合は、株式併合や売渡請求、株式交換といったスクイーズアウトの手続きによって少数株主の排除が行われます。この方法を二段階買収といいます。
これにより、最終的に買収者が全株式を保有し、企業は上場を廃止して非公開企業となります。
親会社による上場子会社の完全子会社化
非上場化の手段の一つに、親会社が上場している子会社を完全子会社化する方法があります。これは、親会社が子会社の発行済株式を全て取得し、100%出資の子会社とすることで、子会社を上場廃止に導くものです。
MBOと同じく、通常は二段階買収の方法で実施されます。
近年、上場企業による子会社の完全子会社化が増えているのは、東証による市場区分再編を契機に、コーポレートガバナンスや企業価値向上への要請が強まったことが背景にあります。時価総額や売買代金が上場維持基準を下回る子会社に対し、経営効率化や資本政策の見直しを目的とした再編の動きが活発化しています。
非上場化のリスク
非上場化には次のようなリスク・デメリットが存在します。
- 多額の資金が必要である
- 既存株主と利益相反する場合がある
- 非上場化で業績が改善する保証はない
それぞれを分かりやすく解説します。
多額の資金が必要である
非上場化を行うには、既存株主から株式を買い取るための多額の資金が必要です。
特に上場企業が一定の規模で株主数も多い場合、公開買付け(TOB)やスクイーズアウトによる株式取得には、数十億円から数千億円規模の資金を要することもあります。
資金調達が計画どおりに進まなかった場合、手続きの中断や延期といったリスクも生じるため、慎重な準備が求められます。
既存株主と利益相反する場合がある
本来であれば企業価値の向上を通じて株主の利益を守るべき立場にある経営陣が、同時になるべく安く株式を買い付けたい立場になるため、必然的に株主との間で利益相反的構造が生じるという問題があります。
経済産業省が2007年9月に公表した、いわゆる「MBO指針」(正式名称:企業価値の向上および公正な手続き確保のための経営者による企業買収に関する指針)では、MBOを実施する際には、①株主が適切な判断を行うための機会の確保、②恣意(しい)的な意思決定を排除するための手続きの整備、③買収価格の妥当性を裏付ける客観的な状況の確保、の3点が必要であるとしています。
出典:https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/MBOshishin2.pdf
非上場化で業績が改善する保証はない
非上場化は経営の自由度を高め、中長期的な戦略を遂行しやすくする手段とされていますが、それ自体が業績改善を保証するものではありません。
むしろ、上場による透明性や社会的信用を失うことで、顧客や取引先の信頼が揺らぎ、ブランド価値が毀損(きそん)される可能性もあります。
特に上場廃止がネガティブな印象で受け取られた場合には、企業イメージの低下や業績への悪影響につながるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
非上場化の事例
近年非上場化を果たした有名企業を紹介します。
大正製薬ホールディングス
大正製薬ホールディングスは2024年4月9日に東京証券取引所スタンダード市場を上場廃止となりました。経営陣によるMBOを実施し、買収総額は7,000億円超に上ったとされています。
非上場化によって意思決定の迅速化を図り、大衆薬事業の強化を目指すとしています。傘下の大正製薬では、リポビタンDなどのネット・通販販売の拡充や、アジア市場における同業他社の買収も視野に入れているとされています。
ベネッセホールディングス
ベネッセホールディングスは、創業家が欧州の投資ファンドEQTと組んで実施したMBOの一環として、2024年3月にTOB(株式公開買い付け)を成立させ、特別目的会社(SPC)を通じて非上場化を実行しました。
非上場化の目的は意思決定の迅速化と事業構造の立て直しにあり、少子化の影響で会員数が減少していた主力の「進研ゼミ」など、国内教育事業の強化を図ります。
併せてデジタル技術の活用や業務効率化を推進し、M&Aを通じて介護事業やリスキリングといった新たな分野での成長も目指すとしています。
サンスター
サンスター株式会社は、2007年にMEBO(Management and Employee Buy Out)を通じて非上場化し、経営と従業員が一体となる体制へ移行しました。同時に本社を日本からスイスへ移転しました。
その後、消費財・生産財の両事業を多角的に展開し、グローバルな事業拡大と高い自己資本比率による安定経営を実現しています。社内ポータルや年次報告を通じた情報共有を徹底し、全社的な一体感の下で長期ビジョンの達成を目指しています。
スノーピーク
スノーピークは2024年7月9日をもって上場廃止となりました。これは、米投資ファンドのベインキャピタルと組んで実施したMBO(経営陣による買収)が成立し、非上場化を進めたことによるものです。
今後は山井太社長の下、経営の自由度を高めつつ、海外事業の拡大やM&Aを活用して中長期的な企業価値の向上を目指すとしています。
永谷園ホールディングス
永谷園ホールディングスは、2024年9月27日をもって東証プライム市場での上場を廃止しました。
創業家が三菱商事系の投資ファンドと連携し、経営陣によるMBO(自社株買収)を目的としたTOB(株式公開買い付け)が成立したことによるものです。
非上場化によって意思決定の迅速化を図り、海外市場への展開を加速させる方針としています。なお、創業家である永谷栄一郎会長や永谷泰次郎社長は今後も経営に携わる予定です。
ローソン
ローソンは2024年7月24日、東京証券取引所プライム市場での上場を廃止しました。背景には、人口減少による国内市場の縮小や、円安・物価高・人手不足といった厳しい経営環境の変化がありました。
上場廃止の契機となったのは、2024年2月にKDDIが発表したTOB(株式公開買い付け)で、元々ローソンの株式の50%を保有していた三菱商事と、それぞれ50%ずつを持ち合う形で共同経営体制が確立されました。
NTTデータグループ
NTTは2025年5月、上場子会社であるNTTデータグループを完全子会社化する方針を発表しました。
現在保有している58%の株式に加え、残り42%をTOB(株式公開買い付け)で取得します。買収総額は約2兆3700億円にのぼり、買付価格には終値比34%のプレミアムが設定される見込みです。
データGはこのTOBに賛同を表明しており、手続き完了後に上場廃止となります。目的は、ITサービスやデータセンター事業の海外展開を加速させるためとしています。
非上場企業が上場する場合の市場
非上場企業が上場する場合、市場には種類があります。本記事では東京証券取引所(東証)の四つの市場区分を紹介します。
プライム市場
プライム市場は、東京証券取引所における最上位の市場区分で、主にグローバルな機関投資家を意識した設計となっています。
この市場に上場するためには、企業に対して厳格な基準が課されており、ガバナンス体制の整備や情報開示の透明性が強く求められます。また、株主との建設的な対話や、長期的視点に立った経営戦略の実行も重視されています。
具体的な上場要件としては、株主数800人以上、流通株式数2万単位以上、時価総額100億円超、流通株式比率35%以上などの基準に加え、コーポレートガバナンス・コードの厳守も義務付けられています。
プライム市場には、日本を代表する主要企業が多数名を連ねており、国際的な信頼性と競争力を備えた企業のみが参加できる市場とされています。
スタンダード市場
スタンダード市場は、一定の事業規模と経営実績を有し、安定した運営を行う中堅企業を主な対象とした市場区分です。
プライム市場に比べると上場基準のハードルはやや緩やかですが、それでも適切な企業統治体制の整備や、継続的な情報開示、安定した収益構造などが求められます。
主な上場要件としては、株主数が400人以上、流通株式数2,000単位以上、流通時価総額10億円以上、流通株式比率25%以上などがあり、さらにコーポレート・ガバナンス・コードへの一定の対応も必要です。
この市場には、成長よりも持続可能な経営や安定性を重視する企業が多く、地域に根ざした企業や歴史のある老舗企業なども目立ちます。国内の個人投資家や中小型株を好む投資家にとって、比較的なじみやすい市場といえるでしょう。
グロース市場
グロース市場は、革新性のある技術や独自のビジネスモデルを武器に急成長を目指すスタートアップ企業やベンチャー企業向けに設けられた市場区分です。
この市場の最大の特徴は、現時点での業績よりも将来の成長ポテンシャルに重きを置いて評価される点にあります。
具体的な上場要件としては、株主数が150人以上、流通株式数が1000単位以上、流通時価総額が5億円以上、流通株式比率が25%以上といった条件に加え、「事業計画とその成長可能性に関する情報開示」が必須とされています。
まだ事業が成熟していない企業も多いため、投資に際しては一定のリスクを伴いますが、その分大きな成長を見込む投資家から高い関心を集めています。グロース市場は、成長フェーズにある企業にとって資本市場への第一歩となる貴重なステージです。
TOKYO PRO Market
TOKYO PRO Marketは、東京証券取引所が提供するプロ投資家専用の市場であり、特定投資家を主な対象としています。原則として一般投資家は参加できず、資格を有するプロの投資家のみが取引の対象です。
この市場では、株主数や流通株式数、時価総額、収益といった厳格な上場要件が設定されておらず、企業は経営権を手放すことなく上場できる柔軟性を持っている点が特徴です。
ただし、上場後は監査法人による会計監査や定期的な情報開示が義務付けられており、透明性の確保が求められます。
地方の中小企業や、まだ規模は小さいものの社会的信用力を高めたい企業にとって、TOKYO PRO Marketは段階的な成長戦略の起点となる市場として活用しやすい選択肢です。
非上場企業に関するQ&A
最後に、非上場企業に関してよくある質問とその回答を紹介します。
非上場企業の決算を見る方法はあるか
会社法により、原則として非上場を含む株式会社には、決算公告の義務が課せられています。
しかし、実情はほとんど企業が実施していません。理由は、公告せずとも実際に罰則が課される可能性が低く、かつ決算公告にはコストがかかるためです。
そのため、非上場企業の決算を確認するのは難しいといえます。
非上場企業でも配当はあるか
配当金とは、会社が得た利益の一部を株主に還元するお金をいい、非上場企業でも配当金を支給できます。
しかし、実際には多くの非上場企業では配当を出していません。理由は、配当金は損金にできず、税制上のメリットが薄いためです。多くの経営者が役員報酬や賞与という形で報酬を受け取っています。
役員報酬と賞与、配当をどのような割合にすれば最も節税効果が高いかは専門的な知識を要するため、税理士や社労士、公認会計士と相談することが推奨されます。
非上場株を買う方法はあるか
非上場株式の購入は、上場株式のように証券取引所を通じて簡単に売買できるわけではありませんが、いくつかの方法で非上場株式を購入することは可能です。
具体的には、非上場企業から直接購入する以外にも、株式投資型クラウドファンディングから購入したり、非上場株を対象にした投信を購入するなどの方法があります。
しかし、非上場株式は流動性が低いため、ハイリスク・ハイリターンであることに注意が必要です。
非上場企業でも会計監査は必要か
非上場会社であっても会社法上「大会社」と定義される場合は、会計監査人監査が義務付けられます。
その定義とは、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社です。
会計監査人は公認会計士または監査法人でなければなりません。
非上場と未上場に意味の違いはあるか
非上場と未上場はどちらも「上場していない」という意味で共通しています。しかし、未上場には「これから上場する予定がある」というニュアンスが含まれます。
昨今は上場廃止を選択する企業が増えていたり、最初から上場ではなく売却という出口戦略を描く企業も多く、「非上場」という言葉を使うことが無難です。
非上場化した後に再度上場はできるか
非上場化した企業が再度上場することは可能です。
通常の上場廃止の場合は、再度上場の要件を満たせば実現可能です。しかし、MBO後の再上場にはさらに厳しい審査が行われます。
例えば、経営者が意図的に株価を下げてMBOを行い、その後業績を復活させて上場で利益を得ようとしている場合などは上場が難しいです。
非上場化した後に経営陣がほとんど入れ替わっていない場合や、MBO後極めて短期間で再上場の審査が行われた場合は、再上場が認められる可能性は低いです。
上場廃止に追い込まれた事例にはどんなものがあるか
西武鉄道株式会社は有価証券報告書等の虚偽記載が契機となって2004年12月上場廃止となりました。これまで上場廃止となったのは主に経営破綻などが原因であり、本件のような情報開示の不備を理由とするのは異例だったことで世間の注目を集めました。
カネボウ株式会社は巨額の粉飾決算が契機となり2005年6月に上場廃止となりました。2000年頃から会計基準が大きく変わり、親会社単体を重視する「単独決算」から、グループ全体を対象とする「連結決算」重視へと移行しました。カネボウはこの変化に対応できなくなった典型例といえます。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
上場・非上場は、それぞれの会社の方針などによって選ぶべき道が異なります。上場に関することはもちろん、M&Aや経営課題についてご検討している経営者の方は、ぜひ私どもM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。