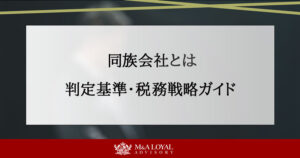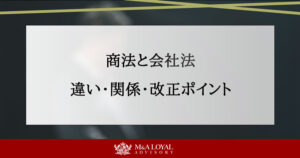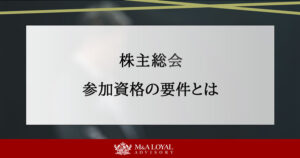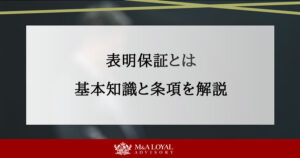名義株とは?名義変更や相続の注意点からM&A時のリスク対策を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
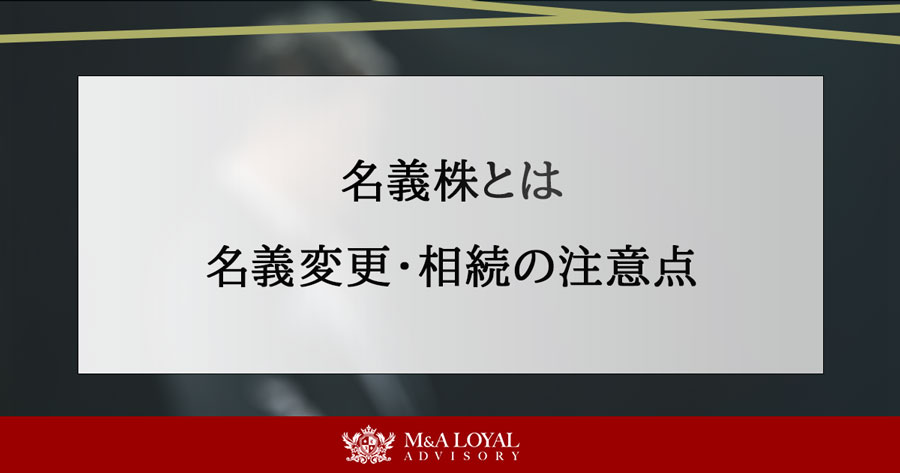
名義株とは、株主名簿に記載されている人物と実際の出資者が異なる株式のことで、特に創業から長い歴史を持つ中小企業において見られる株式です。この名義株の存在は、M&Aや相続の際に深刻なトラブルを引き起こす可能性があり、企業価値の低下や取引の中止、さらには法的紛争にまで発展するリスクを抱えています。
本記事では、名義株とは何か、発生する原因、M&A時に起こりうる具体的な問題、名義変更や相続時の注意点、そして効果的な対策方法まで、会社売却を検討される経営者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。
目次
名義株とは何か
名義株とは、株主名簿に記載されている名義人と実際に出資した真の株主が異なる株式のことを指します。名義人は形式的には株主として登録されているものの、実際には配当を受け取らず、株主総会への参加もせず、株主としての実質的な権利行使を行わない状態にあります。
このような状況が生まれる背景には、株式会社の設立や運営における様々な事情があります。特に同族会社においては、経営者が家族や従業員の名義を借りて株式を保有するケースが多く見られ、これが後の経営権承継やM&A時に重大な問題となることがあります。
名義株と実質株主の違い
名義株問題を理解するためには、名義株主と実質株主の違いを明確に把握する必要があります。名義株主は株主名簿上に記載されている人物であり、法的には株主としての地位を有しているように見えます。一方、実質株主は実際に出資を行い、株主としての権利を実質的に行使している真の所有者です。
裁判所の判例では、単に株主名簿に記載されているだけでは真の株主とは認められず、実際の出資状況や権利行使の実態を総合的に判断して真の株主を決定するとされています。この判断基準は、M&A時の株式譲渡手続きや相続対策において極めて重要な意味を持ちます。
名義株が存在する会社の特徴
名義株が存在しやすい会社には一定の特徴があります。まず、創業から数十年が経過している老舗企業や、複数世代にわたって経営されている同族会社に多く見られます。また、過去に商法改正の影響を受けた会社や、税務対策として親族間での株式移転を行った履歴のある会社でも名義株問題が発生しやすい傾向にあります。
さらに、出資者と名義人の不一致、およびその経緯が不明瞭である場合、株式の所有関係がより曖昧になりやすく、名義株問題が複雑化する場合があります。これらの特徴を持つ会社の経営者は、M&Aを検討する前に名義株の存在について詳細な調査を行うことが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



名義株が発生する主な原因
名義株が発生する原因は多岐にわたりますが、その多くは過去の法制度や税制の影響、そして経営者の個人的な事情に起因しています。これらの原因を正しく理解することは、現在の名義株問題を解決し、将来的なトラブルを防ぐために不可欠です。
特に中小企業においては、創業時の特殊事情や長年にわたる経営方針の変化により、知らず知らずのうちに名義株が生まれているケースが少なくありません。
旧商法の発起人制度による影響
名義株発生の最も大きな原因の一つは、旧商法時代の発起人制度にあります。現在は廃止されていますが、かつての商法では株式会社を設立する際に7人以上の発起人が必要とされていました。この制度により、実際には1人または少数の出資者しかいない場合でも、親族や従業員、知人などの名義を借りて発起人の人数要件を満たす必要がありました。
この名義貸しによって設立された会社では、設立後も名義人が形式的に株主として残り続けることが多く、これが現在の名義株問題の根源となっているのです。商法改正の影響により現在はこのような制度は存在しませんが、過去に設立された会社では依然として問題が残存しています。
相続税対策としての名義変更
相続対策として行われた株式の名義変更も、名義株発生の原因のひとつです。経営者が相続税の負担軽減を目的として、配偶者や子供、親族の名義に株式を移すケースがありますが、実際には経営権や配当受取権を移転せず、形式的な名義変更にとどまることがあります。
しかし、税務上は名義変更時点で贈与が成立したと見なされる可能性があり、後に税務調査で問題となるリスクがあります。また、相続時には実質的支配者判定基準(税務上、実際に株式を支配・管理している者を判定する基準)に基づいて真の株主が判定されるため、名義変更による相続税回避効果は期待できないのが実情です。
経営者の個人的事情による名義借用
経営者個人の事情により名義を借用するケースも存在します。例えば、過去の破産歴や信用情報の問題を隠すために、信用力のある第三者の名義で株式を保有する場合があります。
このような意図的な名義借用問題は、M&A時に買い手企業から大きな懸念を持たれる要因となり、企業価値の低下や取引条件の悪化を招く可能性が高いため、早期の解決が必要です。
M&A時に発生する名義株問題とリスク
M&Aを実施する際、名義株の存在は様々な深刻な問題を引き起こします。これらの問題は単なる手続き上の障害にとどまらず、取引そのものの成立を阻害したり、成立後に重大な法的リスクを生じさせたりする可能性があります。
買い手企業にとって名義株の存在は、対象会社の株主構成や経営権の所在が不明確であることを意味し、投資判断を行う上で大きな不安要素となります。
株式譲渡手続きの複雑化と遅延
名義株が存在する場合、M&Aにおける株式譲渡手続きが著しく複雑化します。まず、真の株主を特定する作業が必要となり、これには大量の資料調査や関係者への聞き取りが必要です。また、名義株主からの同意取得も必要となりますが、長年連絡を取っていない名義株主の場合、所在確認から始める必要があります。
さらに、名義株主がM&Aの事実を知ることで、これまで権利主張をしてこなかった人物が突然株主としての権利を主張し始めるリスクもあります。これにより、予定していたスケジュールが大幅に遅延し、場合によってはM&A自体が中止となる可能性があります。
組織再編における議決権不足問題
M&Aの手法として合併や株式交換などの組織再編を選択する場合、特別決議による株主総会の承認が必要となります。特別決議には議決権の3分の2以上の賛成が必要ですが、名義株の存在により実際に確保できる議決権が不足する可能性があります。
特に、発行済み株式の3分の1以上が名義株である場合、たとえ実質的な株主が全員賛成していても、法的には特別決議の要件を満たすことができない場合があります。この問題は、M&Aの実行可能性そのものを左右する重要な要素となります。
買い手企業のM&Aリスク評価
買い手企業の立場からすると、名義株の存在は対象会社への投資リスクを大幅に増大させる要因です。株主構成が不明確な会社は、将来的に予期しない株主が現れて経営に干渉してくる可能性があり、安定した事業運営に支障をきたすリスクがあります。
また、名義株問題が解決されていない会社は、買い手企業のコンプライアンス基準を満たさない場合が多く、大企業による買収対象から除外される可能性が高いのです。これにより、売却先の選択肢が限定され、結果として売却価格の低下を招くことになります。
相続時における名義株のトラブル
名義株問題は相続時にも深刻なトラブルを引き起こします。経営者の相続が発生した際、名義株の存在により遺産分割協議が紛糾したり、税務調査で重大な指摘を受けたりするケースが後を絶ちません。
特に同族会社では、経営者が家族や従業員の名義を借りて株式を保有するケースが多く見られます。これが後の経営権承継やM&A時に重大な問題となります。
遺産分割協議における争い
相続が発生した際、名義株主と実質株主の相続人との間で株式の帰属を巡る争いが生じることがあります。名義株主側は「株主名簿に記載されているのだから自分が真の株主だ」と主張し、実質株主の相続人側は「実際に出資したのは被相続人であり、名義貸しに過ぎない」と主張することで、激しい対立が生まれます。
このような争いは、最高裁判例を参考にして解決されることがありますが、具体的な解決は証拠や事実関係に依存します。証拠収集や立証活動に長期間を要し、相続手続き全体が停滞する原因となります。また、親族間トラブル防止策を講じていない場合、家族関係の悪化にもつながりかねません。
税務リスク対応と追徴課税
税務署による相続税調査では、名義株の存在が大きな問題となります。税務上は実質的支配者判定基準により真の株主が判定されるため、名義株も実質株主の相続財産として課税対象となります。しかし、相続税申告時に名義株を適切に申告していない場合、追徴課税の対象となります。
実際に、大手企業グループの事例では、名義株の取り扱いを巡って40億円もの追徴課税が課されたケースがあります。このような税務リスク対応を怠ると、相続人に予想外の税負担が発生し、事業承継計画全体に重大な影響を与えることになります。
会社設立時の注意点と現在への影響
会社設立時における名義株の発生は、数十年後の相続時まで影響を及ぼし続けます。創業者が設立時の事情を詳細に記録していない場合、後の世代が名義株の存在や経緯を把握することが困難となり、相続時に混乱を招く原因となります。
現在会社を経営されている方は、設立時の名義貸借について詳細な記録を残し、将来の相続に備えて名義株問題の解決を図っておくことが極めて重要です。
名義株問題の効果的な解決方法
名義株問題を解決するためには、複数のアプローチを組み合わせた総合的な対策が必要です。問題の発見から解決まで、段階的かつ計画的に進めることで、M&Aや相続における重大なトラブルを回避することができます。
解決方法の選択は、名義株の発生経緯、関係者の協力度、解決に要する時間などを総合的に考慮して決定する必要があります。
名義株主からの念書・確認書取得
最も確実な解決方法は、名義株主本人から名義貸与の事実を認める念書や確認書を取得することです。この書面には、「株式の名義貸与を行ったこと」「実際の出資者は別の人物であること」「株主としての権利を行使する意思がないこと」などを明記します。
さらに確実性を高めるためには、公証役場で確定日付を付与してもらうことが重要で、これにより書面の作成時期が公的に証明され、後日の争いを防ぐ効果があります。ただし、この方法は名義株主の全面的な協力が前提となるため、関係性が良好でない場合は実現が困難です。
資金拠出者の特定と証拠資料の整備
名義株主からの協力が得られない場合は、客観的な証拠資料により実質株主を立証する方法があります。具体的には、会社設立時の資金移動記録、株主総会議事録、配当金の受取履歴、議決権行使の記録などを収集・整理します。
これらの資料により一貫して同一人物が実質的な株主として行動していることを証明できれば、名義株主の協力なしでも問題解決の道筋をつけることができます。ただし、完全な解決には至らない場合もあるため、他の方法との組み合わせが必要です。
M&A契約書における表明保証条項の活用
M&Aを実行する場合の実務的な解決策として、最終契約書に表明保証条項(売主が買主に対して一定の事実を保証する条項)を設定する方法があります。この条項では、「名義株は存在しないこと」または「名義株が存在した場合の責任は売主が負うこと」を明確に規定します。
万一、取引成立後に名義株に関するトラブルが発生した場合、買い手企業は売主に対して損害賠償を請求することができ、経済的リスクを軽減する効果があります。この方法は名義株問題そのものの根本的な解決ではないため、可能な限り事前の対策と併用することが望ましいです。
専門家によるサポートの重要性
名義株問題の解決には、法律、税務、M&A実務に精通した専門家のサポートが不可欠です。問題の性質上、単一の専門分野だけでは対応が困難であるため、複数の専門家が連携して対応することが成功の鍵となります。
特に、M&Aを検討している企業経営者にとって、名義株問題は取引の成否に直結する重要な課題であり、早期の専門家相談が推奨されます。
M&Aアドバイザーの役割
M&Aアドバイザーは、名義株問題がM&A取引に与える影響を正確に評価し、最適な解決策を提案する重要な役割を担います。豊富な取引経験に基づき、類似事例での解決方法や買い手企業の懸念事項を熟知しているため、実践的なアドバイスを提供できます。
また、買い手企業との交渉において、名義株問題の説明や解決策の提示を適切に行うことで、取引条件への悪影響を最小限に抑える役割も果たします。M&Aプロセス全体を通じて、名義株問題に関する一貫したサポートを受けることができます。
弁護士による法的対応
弁護士は、名義株問題の法的側面を担当し、特に争いが発生した場合の対応において重要な役割を果たします。最高裁判例の分析や実質株主の立証方法、名義株主との交渉戦略など、法的専門知識に基づいた助言を提供します。
また、念書や確認書の作成、M&A契約書の表明保証条項の設計など、法的リスクを最小化するための書面作成も弁護士の重要な業務です。万一、訴訟に発展した場合の代理人としての役割も担います。
税理士による税務リスク管理
税理士は、名義株問題に関連する税務リスクの評価と対策を担当します。相続税や贈与税の観点から名義株の取り扱いを検討し、税務調査に備えた準備や適切な申告方法についてアドバイスを提供します。
特に、過去の名義変更について税務上の問題がないかを詳細に検証し、必要に応じて修正申告や税務署との事前相談を実施することで、将来の税務リスクを軽減します。
名義株問題の予防策と今後の対応
名義株問題を根本的に解決するためには、問題が発生してからの対処だけでなく、予防策の実施と継続的な管理が重要です。現在名義株問題を抱えていない企業においても、将来的なリスクを回避するための対策を講じておくことが賢明です。
特に、事業承継やM&Aを将来的に検討している企業では、早期の段階から計画的な対策を実施することで、スムーズな承継や売却を実現することができます。
株主名簿の定期的な見直し
株主名簿の定期的な見直しは、名義株問題の早期発見と予防において極めて重要な取り組みです。株主名簿に記載されている全ての名義人について、実際の株主としての実態があるかを確認します。
具体的には、配当金の受取状況、株主総会への参加実績などを通じて、名義株の可能性がある株式を特定します。早期発見により、関係者の記憶が鮮明なうちに問題解決を図ることができ、解決コストも大幅に削減できます。
株式移動時の適切な手続き実施
株式の移動を行う際は、必ず適切な法的手続きを実施し、名義と実質の乖離が生じないよう注意することが重要です。贈与や売買による株式移転の場合は、契約書の作成、対価の支払い、税務申告などを確実に実行し、客観的な証拠を残します。
また、相続対策として株式移転を行う場合は、税務上の適切な評価と申告を行い、将来の税務調査に備えて十分な資料を保存しておくことが不可欠です。
次世代経営者への情報継承
創業者や現経営者は、会社設立時の経緯や株式に関する取り決めについて、詳細な記録を残し、次世代経営者に確実に情報を継承する必要があります。口頭での申し送りだけでなく、書面による記録を作成し、関連資料とともに適切に管理します。
この情報継承により、将来のM&Aや相続時に名義株問題で混乱することを防ぎ、スムーズな事業承継を実現することができます。
まとめ
名義株問題は、中小企業のM&Aや相続において深刻なトラブルを引き起こす可能性のある重要な課題です。旧商法時代の発起人制度や相続税対策などにより発生した名義株は、現在でも多くの企業に潜在的なリスクをもたらしています。
M&A時には株式譲渡手続きの複雑化、組織再編の阻害、買い手企業からの信頼失墜などの問題が発生し、最悪の場合は取引自体が中止となる可能性があります。また、相続時には遺産分割協議の紛糾や多額の追徴課税リスクを抱えることになります。
これらの問題を解決するためには、名義株主からの念書取得、客観的証拠による立証、M&A契約での表明保証条項設定などの方法を、専門家のサポートのもとで適切に実施することが重要です。名義株問題でお悩みの経営者の方は、M&A実務に精通した専門家にご相談いただくことで、最適な解決策をご提案いたします。
M&Aや経営課題に関するお悩みはぜひ一度、M&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。