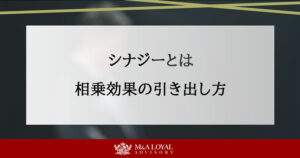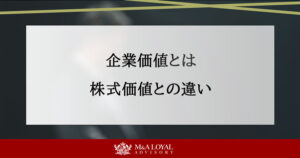居酒屋のM&A事例5選!買収・売却を成功させるポイントと注意点
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
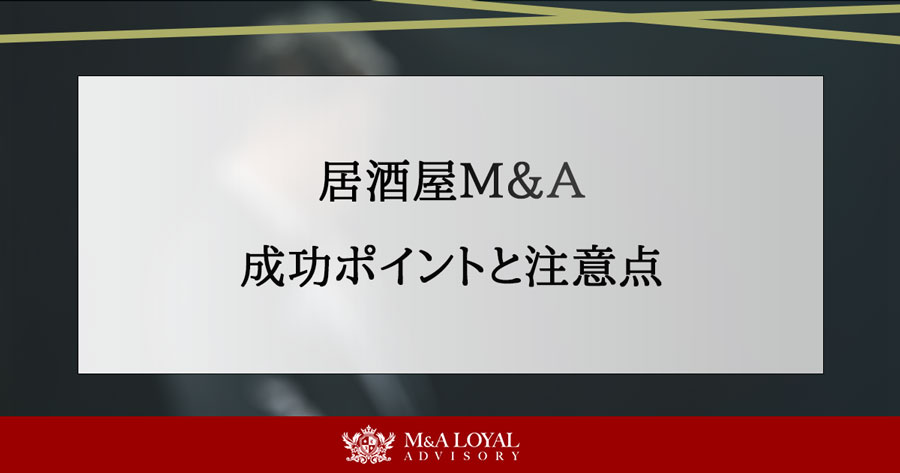
居酒屋業界のM&Aは、居酒屋を経営するオーナーにとって競争力を強化する有効な手段の一つです。物価の高騰やデリバリー、テイクアウトの拡大、宴会需要の低迷、そして若者のアルコール離れにより、外食産業にはさまざまな影響が出ています。特に居酒屋やバーでは、これらの変化に対応するために見直しを余儀なくされている店舗も少なくありません。
本記事では、居酒屋業界の現状と課題、メリット・デメリット、そしてM&A動向を事例とともに解説します。さらに、買収・売却を成功させるためのポイントや注意点も紹介します。ぜひこの機会に、居酒屋のM&Aの全貌を理解し、未来への一歩を踏み出しましょう。
目次
居酒屋業界のM&A|市場動向と現状の課題を解説
居酒屋業界のM&Aには、外食産業の市場動向が深く関わっています。居酒屋は、アルコール飲料を中心とした飲食を提供する業態であり、個人経営から大手チェーン店まで多様な形態が展開されています。
長年にわたり日本の食文化を支えてきた居酒屋業界ですが、近年はさまざまな課題にも直面しています。例えば、少子高齢化による消費者層の変化や、健康志向の高まりに伴ってアルコール飲料の消費量が減少していることが挙げられます。これらの変化に対応するため、事業の効率化や新しいビジネスモデルの導入が求められています。
ここでは、居酒屋業界の市場動向とその現状の課題について詳しく解説していきます。
居酒屋業界の市場規模と売上の推移
居酒屋業界の市場規模は、外食産業の中でも高い割合を占めています。リクルートの外食市場調査では、2025年5月の外食市場全体の売上規模は3,137億円(前年比+175億円)と増加しており、コロナ禍以降最も回復しています。なお、2025年5月の居酒屋の市場規模は617億円であり、外食産業の約19.7%をシェアしています。
■外食産業の市場規模TOP5(2025年5月)
- 居酒屋 617億円(19.7%)
- 和食料理店 482億円(15.4%)
- 焼肉・ステーキ・ハンバーグ等の専業店 325億円(10.4%)
- ファミリーレストラン・回転すし等 256億円(8.2%)
- 中華料理店 250億円(8.0%)
外食単価および外食回数を見ると、居酒屋の外食単価は3,921円であり、平均外食単価の2,924円を上回っています。外食単価が最も高い業態はフレンチ・イタリアン料理店(4,913円)であり、次いで和食料理店(4,733円)、バー・バル等(4,302円)と続いています。また、延べ外食回数に関しては、1,574万回と他の業態と比べて最も高いことが特徴です。
居酒屋が外食産業の中でも市場規模が高い理由として、ファミリーレストランと異なり、定食ではなく、複数の品数を頼むことやアルコール飲料を頼む回数が多いこと、フレンチやイタリアン料理店と比較して比較的敷居が低く、会社帰りなどに立ち寄りやすいことが考えられます。
しかし、すべての居酒屋店が売上を伸ばしているわけではありません。帝国データバンク「居酒屋倒産動向」によれば、2024年の居酒屋の倒産件数は過去最多の203件を記録し、店舗数は前年比の97.9%と減少しています。また、野村證券株式会社の資料では、居酒屋業界の2025年1月の前年比売上は2024年1月の前年比と比較すると下がっていることから、「客数」「客単価」は増加傾向にあるものの、赤字経営が4割と競争が激しい業界であることが分かります。
■2024年度の店舗売上高TOP5
- ワタミ:746億円
- エターナルホスピタリティグループ:611億円
- SFBホールディングス:346億円
- チムニー:333億円
- 大庄:300億円
飲食業界全体で見ると、特に居酒屋業界は大きな変革期にあります。大手店舗は売上を伸ばしつつも、物価高騰などのコスト増加により経営状況が厳しくなっている店舗も少なくありません。このような現状を受け、居酒屋業界では市場動向に応じた戦略の見直しが急務となっています。競争が激化する中、飲食店としての独自の魅力を打ち出し、顧客の多様なニーズに応える柔軟性が求められています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



居酒屋業界の課題とM&Aが進む背景
居酒屋業界でM&Aが選択される背景には、居酒屋業界の課題が関係しています。近年の消費者の嗜好の変化や、働き方改革による飲酒機会の減少、さらには新型コロナウイルスの影響など、居酒屋業界は多くの課題に直面しています。
特に市場に影響を与えている課題として以下が挙げられます。
- 宴会需要の低迷
- 若者のアルコール離れ
- 中食市場の拡大
それぞれの課題について見ていきましょう。
宴会需要の低迷
近年、居酒屋業界が直面している課題の一つとして、宴会需要の低迷が挙げられます。特に新型コロナウイルスの影響は、宴会を含む大人数での集まりを避ける傾向を強めました。これにより、居酒屋の売上の一部を大きく占めていた宴会需要が著しく減少し、業界全体に影響を与えています。
さらに、リモートワークの普及により、職場での飲み会や歓迎会、送別会といった従来の宴会文化が変化しつつあることも、需要減少の一因となっています。この状況は都市部に限らず、地方の居酒屋にも影響を及ぼしています。
また、消費者のライフスタイルの変化や健康志向の高まり、物価の高騰による価格高騰も宴会需要の低迷に拍車をかけています。このような状況を打破するために、居酒屋業界は新たな戦略を模索しています。例えば、少人数でも楽しめるプランの提供、食事のクオリティ向上といった取り組みが進められています。
こうした中で、居酒屋業界ではM&A(合併・買収)が注目されています。M&Aを通じて、規模の拡大や新たな市場への進出を図る企業が増えてきています。特に、地域に根ざした居酒屋チェーンが大手企業とM&Aを行うことで、ノウハウや資本を活用し、サービスの質を向上させる動きが見られます。
これらの施策は、宴会需要の低迷を補うだけでなく、新たな顧客層を取り込むための重要な手段として期待されています。居酒屋業界が今後も成長を続けるためには、M&Aを含む変化に柔軟に対応し、新しい需要を喚起するための工夫が求められています。
若者のアルコール離れ
若者のアルコール離れも、居酒屋業界が直面している課題の一つです。若年層の消費者嗜好の変化やライフスタイルの多様化により、飲酒機会が減少していることが背景にあります。このような状況下で、居酒屋業界ではM&A(合併と買収)が戦略的な選択肢として注目されています。
具体的には、若者の間で健康志向が高まっていることや、飲酒に対する価値観の変化が挙げられます。例えば、健康を意識してアルコールを控える人が増えたり、飲酒以外の娯楽や交流手段を選ぶ傾向が強まっています。また、SNSやデジタルコンテンツの発達により、飲酒を伴わない交流が広がっていることも影響しています。
このような若者のアルコール離れは、居酒屋業界にとって売上減少や来店客数の減少という形で直接的な影響を及ぼしています。若年層は居酒屋の主要な顧客層の一つであり、この層の減少は業界全体の収益に大きな打撃となります。そのため、企業は競争力を維持するための手段として、M&Aを活用し、規模の拡大や市場シェアの確保を目指しています。
居酒屋業界がこれらの課題に対応するためには、以下のような対策が考えられます。
- ノンアルコール飲料や健康志向メニューの充実
- 飲酒以外の楽しみ方を提供するイベントやサービスの導入
- 若者のライフスタイルに合わせた店舗運営やプロモーション戦略の見直し
このように、居酒屋業界は中年層だけでなく、若者の多様なニーズに応え、新たな顧客層の獲得や既存顧客の維持を図ることが求められています。
中食市場の拡大
居酒屋業界におけるM&Aは、経営戦略の一環として注目を集めています。特に、ライフスタイルの変化や中食市場の拡大に伴い、居酒屋の運営は新たな挑戦を迫られています。M&Aを通じて、居酒屋業界では規模の拡大や経営資源の最適化を図り、多様化する消費者ニーズに対応しています。これにより、地域に根ざした居酒屋から大手チェーンまで、さまざまな形態の居酒屋がM&Aを通じて新たな市場機会を模索しています。
- 共働き世帯の増加により、家庭での調理時間が減少していること
- 健康志向や多様な食のニーズに対応した商品開発の進展
- テクノロジーの進化によるデリバリーサービスの普及
- 外食と比べて手軽で経済的な食事選択肢としての認識の高まり
このような中食市場の拡大は、居酒屋業界に対しても大きな影響を与えています。伝統的な居酒屋は店内飲食を中心としていますが、中食の需要増加により、売上構造や顧客のニーズが変化しています。特に、若年層やファミリー層がテイクアウトやデリバリーを利用するケースが増え、居酒屋側もこれらのサービス展開を検討・強化する必要が生じています。
このような市場環境の変化に伴い、居酒屋業界ではM&Aが活発化しています。M&Aを通じて、規模の拡大や新しいビジネスモデルの導入を図ることが、競争力を維持するための重要な戦略となっています。
居酒屋業界のM&Aが選択される理由
居酒屋業界の経営者がM&Aを選択する理由は、以下の通りです。
- 同業他社との競争力・ブランド強化
- 人材不足や経営資源の改善
- 事業承継による後継者不足の解消
- 大手チェーン店の海外進出
それぞれについて見ていきましょう。
同業他社との競争力・ブランド強化
居酒屋業界におけるM&Aは、同業他社との競争力向上とブランド強化を目指す重要な戦略です。その理由は、競争が激化する市場での生き残りを図るために、単に店舗数を増やすだけでなく、業態の多様化やサービスの質の向上が求められるためです。M&Aを通じて成功している他社のビジネスモデルや運営ノウハウを取り入れることで、オペレーションの効率化や顧客満足度の向上が期待されます。
さらに、ブランド力の強化により、既存顧客のロイヤリティを高めると同時に、新規顧客の獲得にもつながります。例えば、地域に根付いた人気店をM&Aで買収することで、その地域における知名度や信頼性を一気に高めることが可能です。加えて、異なるブランドを持つ企業同士のM&Aは、様々なターゲット層にアプローチできるという点でも有利です。
特に、若年層やファミリー層、ビジネスパーソンなど、異なるニーズを持つ顧客に対して、カスタマイズされたサービスを提供できるようになります。これにより、競合他社との差別化が図れ、長期的な成長基盤を構築することが可能となります。
人材不足や経営資源の改善
居酒屋業界は近年、人材不足と経営資源の限界という深刻な課題に直面しています。これらの課題は店舗運営の効率化やサービスの質の維持・向上に大きな影響を及ぼしており、M&Aが解決策として注目される背景の一つです。
まず、人材不足の現状ですが、労働人口の減少や若年層の業界離れ、コロナ禍後の雇用環境の変化などにより、スタッフの確保が困難になっています。特に居酒屋業界は飲食店の中でも勤務時間が長く、労働環境の厳しさから人材の定着率が低くなりがちです。ここで、M&Aは優秀な人材の確保手段として効果を発揮します。M&Aを活用することで、他企業との統合により人材の流動性を高め、必要なスキルを持つスタッフを効率的に確保できます。
次に、経営資源の面では、設備や店舗の老朽化、資金繰りの難しさ、新規事業展開のためのノウハウ不足などが挙げられます。これらは単独経営では対応が難しく、事業の成長や競争力強化の妨げとなっています。M&Aを通じて、買収側は既存の優秀な人材を取り込むことで、即戦力となるスタッフを確保できます。また、M&Aによって、設備投資や資金調達の面でも有利に働くことがあります。
さらに、M&Aにより、売却側は経営資源の不足を補い、事業の持続可能性を確保する手段となります。両社の経営ノウハウやネットワークを統合することで、効率的な運営体制を構築しやすくなります。このように、M&Aは居酒屋業界における多くの課題を解決するための重要な戦略となり得ます。M&Aを積極的に活用することで、業界全体が持続可能な成長を遂げることが期待されます。
事業承継による後継者不足の解消
居酒屋業界では、経営者の高齢化や後継者不足が深刻な課題となっており、多くの店舗が事業の継続に不安を抱えています。特に家族内での後継者がいない場合、経営の引継ぎがスムーズに進まず、結果として閉店や売却を余儀なくされるケースが増えています。
こうした背景から、居酒屋のM&Aは事業承継の有効な手段として注目されています。理由として、M&Aにより後継者不在の問題を解決し、事業の持続性を確保することが可能だからです。具体的には、外部の買収企業や投資家が経営権を引き継ぐことで、店舗の運営が継続され、従業員の雇用も守られます。
また、M&Aを通じて経営資源やノウハウの継承が行われるため、買収側の専門的な経営支援を受けることができ、経営の安定化や成長が期待されます。特に、買収企業が既存の店舗ネットワークやブランド力を活用し、シナジー効果を生み出すケースも多いです。これが、M&Aが単なる売却や買収にとどまらず、事業承継の課題をクリアし、経営の未来を支える重要な戦略となっている理由です。
このように、居酒屋業界におけるM&Aは、後継者不足に悩む経営者にとって、事業の継続と発展を可能にする有力な選択肢と言えるでしょう。M&Aを活用することで、事業の持続性と成長の両立が期待できます。
大手チェーン店の海外進出
居酒屋チェーン店の海外進出戦略としてもM&Aが活用されています。特にアジア市場は経済成長が著しく、飲食業界においても大きな成長ポテンシャルを秘めているため、居酒屋業界のM&Aにおいて重要なテーマとなっています。
アジア市場への進出は、単なる店舗の増加だけでなく、現地の消費者ニーズや文化への適応が不可欠です。その理由は、現地の消費者の嗜好や習慣を理解しなければ、ビジネスが成功しにくいからです。M&Aにより既存の現地企業を買収することで、現地の市場理解や運営ノウハウを迅速に獲得できるメリットがあります。これにより、リスクを抑えつつスムーズな海外展開が可能となります。
さらに、M&Aは新しい市場への参入を迅速に行うための手段としても有効です。その理由は、ゼロから市場に参入するよりも、既存の企業を通じて参入する方が時間とコストを大幅に削減できるからです。居酒屋業界においては、競争が激化する中で、M&Aを通じて競争優位性を高めることが求められています。以下に、チェーン店の海外進出におけるM&Aのポイントを整理します。
- 経済成長と市場規模:中国、東南アジア諸国(タイ、ベトナム、インドネシアなど)は中産階級が増加し、飲食業の需要が急拡大しています。
- 現地パートナーの重要性:文化や消費行動の違いを理解するため、現地企業との連携や買収が成功の鍵となります。
- ブランドの現地適応:メニューやサービスのカスタマイズが求められ、現地の嗜好に合わせた商品開発が必要です。
- 法規制とビジネス環境:各国の規制や商習慣を把握し、適切な対応を行うことが重要です。
- 人材確保と育成:現地スタッフの採用や教育体制の構築に注力し、安定した店舗運営を目指します。
実際の事例として、トリドールホールディングスがシンガポールのMC GROUP PTE.LTD.に出資し、アジア市場での展開を加速させているケースが挙げられます。このようなM&Aは、居酒屋チェーンが海外市場で成功を収めるための有効な手段となっています。 ただし、海外進出には文化の違いや経営統合の課題も伴うため、慎重な市場調査と現地対応が求められます。M&Aを通じた海外展開の成功には、明確な目的設定と専門家の活用が重要なポイントです。
居酒屋の特徴と他の業界のM&Aとの違い
居酒屋業界におけるM&Aは、地域性や人材確保といった独特の課題を抱えています。他の業界との違いとして、地域に根ざした顧客基盤を活かし、地元の文化やニーズに対応する必要があります。また、労働集約型のため、人材の確保と育成が鍵となり、M&Aでの既存人材の活用が求められます。
居酒屋業界の特徴
- 地域密着型である
- 労働集約型である
- 中小規模店舗が多い
- 価格競争が発生しやすい
それぞれについて解説します。
地域密着型である
居酒屋業界のM&Aの特徴の一つが、地域密着型であることです。地域密着型の居酒屋は、地元の顧客層との強固な関係を築いており、地元の文化やニーズに深く根ざしています。この特性はM&Aにおいても重要な要素となり、買収側が地域の消費者に受け入れられるための戦略的な基盤となります。
地域に根ざした居酒屋が持つ顧客基盤は、M&Aを通じて短期的な利益追求だけでなく、長期的な経営の安定性にも寄与します。地元の顧客との信頼関係は、他の大規模チェーン店では得にくい継続的な収益源となり得ます。このような地域密着型の店舗をM&Aによって獲得することにより、買収側は新たな地域市場に迅速に参入し、地元のブランドイメージを強化することが可能です。
さらに、地域密着型の居酒屋は地元の生産者やサプライヤーとの関係も築いており、これがM&Aにおける経営資源の最適化にも寄与します。地元産の素材を利用することで、独自性のあるメニューを提供し、他店との差別化を図ることができるため、買収後も競争力を維持しやすくなります。
M&Aを通じて地域密着型の居酒屋を取り込む際には、地域の文化や顧客ニーズを尊重し、既存のブランド価値を損なわないようにすることが成功の鍵となります。地域密着型であることがもたらす信頼感や親近感は、地域のコミュニティにおいて重要な役割を果たしており、新たな市場開拓の際にはM&Aを最大限に活用することが求められます。
労働集約型である
居酒屋業界は労働集約型産業の代表例であり、店舗運営における人材の役割が非常に大きいことが特徴です。労働集約型とは、製造業のように機械や設備に依存する比率が低く、人の労働力が事業の成果に直結する業態を指します。居酒屋の場合、多くの業務が従業員の手作業や接客、調理に依存しているため、労働集約型の典型的な例となっています。
この業界における人材の重要性は、以下のように整理できます。
- スタッフの接客スキルやコミュニケーション能力が顧客満足度に直結する
- 調理技術やメニュー開発は店舗の特色やブランド力を左右する
- 従業員のシフト管理や労働環境は店舗運営の効率性に影響する
- 人材の定着率や育成が長期的な経営の安定に不可欠である
また、居酒屋業界は従業員の多様性も特徴であり、若年層から中高年層、アルバイトや正社員、パートタイムなど幅広い雇用形態が混在しています。
しかし、労働集約型であるがゆえに、以下のような課題も存在します。
- 人材不足による店舗運営の負担増加
- 労働時間が長くなりやすいことによる従業員の疲労蓄積
- 労働環境の改善が進みにくい構造的な問題
こうした課題は居酒屋のM&Aにおいても重要な検討ポイントとなります。M&Aでは買収側が既存の従業員や経営ノウハウを引き継ぐことが多く、労働集約型の特性を踏まえた人材継承や労働環境の整備が成功の鍵となります。
労働集約型の居酒屋業界におけるM&Aでは、人材の質と量の確保、従業員のモチベーション維持、適切な労働環境の提供が経営の持続性を左右すると言えるでしょう。
中小規模店舗が多い
居酒屋業界は、多くの店舗が中小規模で運営されているという特徴があります。これは、居酒屋が地域密着型のビジネスであることや、初期投資や運営コストの面で中小規模が適しているためです。
中小規模店舗の特徴として、店舗面積が比較的小さく、従業員数も限定されていることが挙げられます。これにより、経営者が現場に密接に関わりやすく、顧客との距離が近い運営が可能となっています。一方で、資金調達や人材確保、設備投資などで制約が多いことも事実です。
このような中小規模店舗が多いことは、M&Aにおいても特有の影響を与えます。特にM&Aの際には、企業価値評価が難しく、買収や売却の際には、店舗の規模や経営体制が交渉の重要なポイントとなります。また、M&Aによって成長を目指す企業にとって、居酒屋業界は魅力的なターゲットとなることもあります。M&Aを通じて、経営基盤を強化し、より広範な市場への展開を図ることが期待されています。
以下に中小規模店舗の特徴とM&Aにおけるポイントをまとめます。
- 経営者が店舗運営に深く関与しやすく、柔軟な経営判断が可能
- 小規模ゆえに資金調達や人材確保が課題となることが多い
- 設備や内装の老朽化が経営リスクとなる場合がある
- M&Aにより経営資源の補完やノウハウの共有が期待できる
- 複数店舗の統合によるスケールメリットの獲得が可能
このように、中小規模店舗が多い居酒屋業界では、M&Aを通じて経営基盤の強化や事業拡大を図ることが重要な戦略となっています。特に、買収側は既存の店舗の強みを活かしつつ、経営の効率化を進めることで競争力を高めることができます。売却側にとっても、経営課題の解決や事業承継の一環としてM&Aは有効な選択肢です。
価格競争が発生しやすい
居酒屋業界は多くの中小規模店舗が存在し、地域ごとに多様な競合がひしめくため、価格競争が非常に激しく発生しやすい特徴があります。
まず、居酒屋の価格競争が起きやすい背景には、以下のような要因があります。
- 中小規模店舗が多く、差別化が難しいため、価格で顧客を引きつける戦略が取りやすい。
- 地域密着型であるため、同じエリア内に多数の競合店舗が存在し、顧客の取り合いが起きる。
- 消費者の価格に対する感度が高く、特に若年層やファミリー層はコストパフォーマンスを重視する傾向にある。
- 飲食業界全体での原材料費や人件費の高騰により、競争がさらに激化している。
この価格競争の激化は、店舗の収益性に直接影響を及ぼし、経営の安定を脅かすリスクとなります。価格を下げ過ぎると利益率が低下し、持続可能な経営が困難になるため、経営者は価格設定に慎重さが求められます。
M&Aの場面では、価格競争の激しさが重要な検討ポイントとなります。買収側は、M&Aのプロセスにおいて、買収対象の店舗が価格競争に巻き込まれていないか、競合状況や価格戦略を詳細に調査する必要があります。また、売却側も価格競争による収益悪化がM&Aでの売却価格に影響する可能性があるため、適切な価格設定や経営改善策を講じることが重要です。
価格競争に対処するためには、単に価格を下げるだけでなく、店舗独自のサービスやメニューの差別化、顧客体験の向上を図ることが効果的です。これにより、価格以外の価値で顧客を引きつけ、安定した収益基盤を築くことが可能となります。
以上のように、居酒屋業界の価格競争の激しさはM&Aにおいても大きな影響を与えるため、慎重な市場分析と戦略的な経営判断が成功のポイントとなります。M&Aを検討する際には、これらの要素を考慮に入れた上で計画を進めることが求められます。
居酒屋業界のM&Aのメリット
居酒屋をM&Aで売却・買収することのメリットについて、売り手と買い手の視点から紹介します。
M&Aによる売却側のメリット
居酒屋業界におけるM&Aは、売却側にとって多くのメリットをもたらします。主なメリットとして以下が挙げられます。
- 経営改善のための新たな経営資源とノウハウの獲得
- 効率的な業務フローの導入
- 従業員のスキルアップとサービス向上
- 財務基盤の安定化
- 将来的な投資や事業展開の柔軟性
- 個人の資産形成と新たなビジネスへの投資
それぞれについて解説します。
経営改善のための新たな経営資源とノウハウの獲得
売却を通じて、買収先から新たな経営資源や専門的なノウハウを得ることができます。これにより、これまでの運営で抱えていた課題を効果的に解決し、業務の効率化やサービスの質の向上を図ることが可能です。
効率的な業務フローの導入
買収企業が持つ効率的な業務フローを導入することで、業務の生産性が向上します。これにより、コスト削減やサービスの迅速化が実現し、顧客満足度の向上に繋がります。
従業員のスキルアップとサービス向上
売却によって得た資金やノウハウは、従業員の教育やトレーニングに活用できます。従業員のスキルアップは、サービスの質を高めるだけでなく、従業員のモチベーション向上にも寄与します。
財務基盤の安定化
売却により得た資金を活用して、債務の返済や運転資金の確保が可能です。これにより、財務状況が改善され、経営の安定性が増します。
将来的な投資や事業展開の柔軟性
財務基盤が安定することで、将来的な投資や新規事業の展開に向けた資金の準備が可能となります。これにより、戦略的な事業拡大や多角化を柔軟に行うことができます。
個人の資産形成と新たなビジネスへの投資
売却によって得られる資金は、個人の資産形成や新たなビジネスへの投資にも活用できます。これにより、経営者自身のキャリアの幅を広げる機会が生まれます。
このように、居酒屋のM&Aは単なる売却に留まらず、新たなスタートを切るための重要なステップとなります。
M&Aによる買収側のメリット
買収側にとっての居酒屋M&Aのメリットとして主に以下が挙げられます。
- ブランド力の活用による市場拡大
- スケールメリットによる運営効率化
- 独自のメニューやサービスの活用
- プロモーション活動の展開
それぞれについて解説します。
ブランド力の活用による市場拡大
居酒屋のM&Aにおいて、既存のブランドを手に入れることは大きなメリットです。確立されたブランドは消費者の信頼を得ており、新規マーケティング費用を抑えることができます。特に地域密着型の居酒屋チェーンを買収することで、地元顧客へのアプローチが自然になると同時に、ブランドの知名度を活用して新たな市場に進出しやすくなります。
スケールメリットによる運営効率化
買収によって店舗数が増加すると、仕入れや物流のコスト削減が可能になります。また、スケールメリットを活用してスタッフのトレーニングや管理体制を最適化することで、効率的な運営が実現します。これにより、コスト削減と同時にサービスの質を向上させることができます。
独自のメニューやサービスの活用
買収したブランドが持つ独自のメニューやサービスを取り入れることで、他の店舗との差別化を図ることができます。これにより、競争の激しい市場においても、ユニークな顧客体験を提供し、独自のポジションを築くことが可能になります。
プロモーション活動の展開
既存のブランドを活用することで、新たなプロモーション活動やコラボレーション企画を展開しやすくなります。デジタルプロモーションを活用することで、特に若者を中心とした新たな顧客層を獲得するチャンスが広がります。顧客のロイヤルティを高め、リピーターを増やすことができます。
これらの要素を組み合わせることで、買収側は居酒屋業界における地位を強化し、持続的な成長を実現することが可能となります。
居酒屋業界のM&Aのデメリットとリスク
M&Aにはメリットがある一方で、デメリットやリスクも存在します。売り手と買い手両者の視点から解説します。
M&Aによる売却側のデメリットとリスク
居酒屋のM&Aにおける売却側のデメリットとリスクについて解説します。
- 経営権の喪失とブランドの変化
- 競業避止義務の発生
- 売却価格の妥当性の見極め
- 情報漏洩のリスク
- 従業員の離職
それぞれについて解説します。
経営権の喪失とブランドの変化
M&Aを通じて経営権を手放すと、これまで築き上げてきた店舗のブランドや経営方針が変わる可能性があります。これにより、従業員や常連客にとっての店舗のアイデンティティが失われ、顧客離れが起きるリスクがあります。
競業避止義務の発生
売却後、同業界で新たなビジネス展開を行う際に制約が生じることがあります。競業避止義務は、特に同じ業界で再起を図る場合に大きな障害となる可能性があるため、契約内容を事前によく確認することが重要です。
売却価格の妥当性の見極め
市場価値を正確に把握していないと、適正価格での売却が難しくなります。専門家の意見を取り入れ、詳細な評価を行うことで、適切な価格での交渉を目指すことが大切です。
情報漏洩のリスク
交渉過程での情報管理が不十分だと、競争相手に不利な情報が流出する可能性があります。情報漏洩は経営に悪影響を及ぼす可能性があるため、情報管理には細心の注意を払う必要があります。
従業員の離職
M&Aによる組織変更は従業員の不安を煽る可能性があり、離職率の増加につながる恐れがあります。従業員への十分な説明と理解の促進を通じて、不安を和らげることが必要です。
これらのデメリットやリスクを最小限に抑えるためには、事前の準備と計画的なアプローチが不可欠です。専門家の支援を積極的に活用し、慎重に進めることが推奨されます。
M&Aによる買収側のデメリットとリスク
居酒屋のM&Aにおける買収側のデメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 企業文化・経営スタイルの違い
- 顧客層・ブランドイメージの違い
- 財務リスク
- 法規制・労務管理の問題
- シナジー効果の不確実性
それぞれの項目を詳しく解説します。
企業文化・経営スタイルの違い
買収後の統合プロセスでは、企業文化や経営スタイルの違いが障害となる可能性があります。特に、居酒屋業界特有のサービス業としての柔軟性や地域性をうまく統合できない場合、従業員のモチベーションが低下したり、サービスの質が低下したりするリスクがあります。
顧客層・ブランドイメージの違い
買収対象の店舗が持つ顧客層やブランドイメージが自社と異なる場合、市場での競争力を失うリスクがあります。ターゲット顧客が異なることで、既存顧客とのギャップが生じ、売上減少につながる可能性があります。
財務リスク
買収に伴う初期投資や運営コストが予想以上にかかる場合があります。特に不採算店舗の再建や合理化が必要な場合、追加の資金投入が求められ、経営資源が分散し、本業への集中が阻害される恐れがあります。
法規制・労務管理の問題
買収後に法規制の遵守や労務管理などの面で潜在的な問題が表面化することがあります。これらの問題に対処するためには、事前のデューデリジェンスやリスクアセスメントが不可欠です。
シナジー効果の不確実性
M&A後のシナジー効果が期待通りに発揮されないケースもあります。特に、収益性の向上やコスト削減が見込めない場合、投資回収が難しくなり、経営戦略の再考を余儀なくされることがあります。
これらのデメリットを十分に理解した上で、戦略的な意思決定を行うことが重要です。
居酒屋のM&Aを成功させるポイントと注意点
居酒屋のM&Aを成功させるためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 市場調査の徹底
- 自社の強みと弱みの評価
- 専門家の活用
- 文化の統合と従業員のケア
- 明確な目的と計画の策定
- 専門家の活用
それぞれについて解説します。
市場調査の徹底
事前の市場調査はM&Aの成功に不可欠です。業界の動向や競合他社の動きを把握し、自社のポジショニングを明確にすることで、最適な買収・売却のタイミングを見極めます。これにより、より有利な条件で交渉を進めることが可能となります。
自社の強みと弱みの評価
自社の強みや弱みを客観的に分析し、M&Aにおける交渉材料を準備することが重要です。財務状況の透明性を高めるためにデューデリジェンスを徹底し、買収先または売却先が望む価値を提供できるよう事前の改善策を講じましょう。
文化の統合と従業員のケア
M&A後の組織統合を円滑に進めるためには、文化の統合や従業員の不安解消が重要です。従業員コミュニケーションを強化し、新たな企業文化の醸成を図り、従業員の士気を維持することが、事業運営の円滑化につながります。
明確な目的と計画の策定
M&Aの目的を明確にし、それに向けた具体的な計画を策定することが成功を左右します。短期的な利益だけでなく、長期的な成長戦略を見据えた決定を行うことが、持続的な成功をもたらします。
専門家の活用
M&Aプロセスは複雑なため、法務、税務、財務の専門家のアドバイスを受けることでリスクを最小限に抑えることができます。特に交渉戦略においては、双方がWin-Winとなる条件設定が求められるため、経験豊富な専門家のサポートが有効です。
居酒屋のM&Aは、単なる取引にとどまらず、新たなビジネスチャンスへの扉を開く機会です。市場調査、強みと弱みの評価、専門家の活用、文化の統合、明確な目的と計画の策定といったポイントを押さえることで、成功に繋げることができます。
居酒屋M&Aの譲渡費用と買取案件の相場
居酒屋の譲渡費用は、地域や立地条件、店舗の規模、収益性など、多くの要因によって大きく変動します。都市部では人の流れが多いため、譲渡価格が高くなる傾向がありますが、地方では競争が少ない反面、集客力の面でリスクがあるため価格が抑えられることが一般的です。
また、居酒屋業界のM&Aは、大手チェーン店が中心となって行われています。これらの企業は、地域に根強い企業やブランド化している店舗を買収することで、事業の拡大やコスト削減によるシナジー効果を目指しています。一方で、個人経営の居酒屋や従業員が5名以下の店舗では、黒字であっても売却価格が1,000万円以下となる案件も珍しくありません。
売却の理由を見ると、後継者不在や経営者の体力の限界が挙げられています。個人事業主にとっては事業を始めやすい業態であるものの、従業員の確保や運用コスト、売上の維持など、経営を続けることが難しいことがうかがえます。
居酒屋の企業価値の算出方法
居酒屋の企業価値を算出するためには、複数の評価方法を組み合わせて使用することが一般的です。代表的な方法には、年買法、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、類似企業比較法、資産アプローチなどがあります。
DCF法は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法で、居酒屋の将来の収益性を精緻に反映することができます。類似企業比較法では、同業他社の市場価値や財務指標と比較して企業価値を評価しますが、業界全体の動向や競争環境も考慮する必要があります。一方、資産アプローチは、所有する不動産や設備、その他の資産の価値を基に計算する方法で、特に資産が多い場合に有効です。
また、居酒屋業界特有の要素として、立地条件やブランド力、顧客層の分析が重要です。立地条件は集客力に直結し、ブランド力は競争優位性をもたらします。これらの要素は定量化が難しいため、専門的な知識を持つ評価者の判断が求められます。さらに、季節性や地域性によって売上が影響を受けやすい業界特性を考慮に入れることも不可欠です。
企業価値の算出は、M&A戦略を成功させるための基盤となるため、精度の高い評価を行うことが求められます。適切な評価方法を選択し、これらの要素をバランスよく考慮することで、居酒屋の企業価値を正確に算出することが可能となります。
居酒屋の売却価格の目安
居酒屋の売却価格の目安は、年間の営業利益の3倍から5倍程度が相場とされていますが、これはあくまで参考値であり、具体的な評価は個別の状況に応じて大きく異なります。売却を検討する際には、専門家のアドバイスを受け、詳細な企業価値評価を行うことが推奨されます。これにより、適正な価格設定ができ、結果的に売却プロセスの成功に寄与するでしょう。
居酒屋のM&A事例5選
居酒屋業界でM&A(合併・買収)を行っている企業の事例を5つ紹介します。
事例➀トリドールホールディングスによる買収
やきとり屋「とりどーる」、うどん専門店「丸亀製麺」、焼きそば専門店「長田本庄軒」など、多様な飲食ブランドを展開する株式会社トリドールホールディングスは、「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、複数の企業を買収し、グローバル展開にも注力している外食企業です。
2013年にはアメリカで日本食カジュアルレストランを運営する「Dream Dining Corporation」を買収し、その後、「Nom Nom Enterprise LLC」、「WOK TO WALK FRANCHISE B.V.」、「株式会社ZUND」、「MC GROUP PTE.LTD.」など、複数の企業の株式を取得し、事業の拡大および収益の向上を目指しています。
事例②クリエイト・レストランツ・ホールディングスに買収
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、1995年にレストラン事業を開始しました。2012年には「株式会社ルモンデグルメ」を買収し、その後も「SFPダイニング株式会社」、「株式会社イートウォーク」、「株式会社YUNARI」、「株式会社KRフードサービス」、「株式会社いっちょう」などを子会社化しています。
クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、今後も既存事業とのシナジーと財務規律を重視しながら、M&Aを積極的に進めていく方針です。
参考:クリエイト・レストランツ・ホールディングス|有価証券報告書
事例③チムニー株式会社による買収
「はなの舞」や「さかなや道場」をはじめとしたブランド展開を行うチムニー株式会社は、1984年に創業(旧:株式会社エフ・ディー)しました。2011年には「漁鮮水産」を営業し、2012年には「升屋」12店舗を譲受して事業を開始しました。同年、都内を中心に串焼き店「新橋やきとん」を運営する株式会社紅フーズコーポレーションを買収し、完全子会社化しています。
2013年には株式会社やまやの子会社となりましたが、その後も株式会社つぼ八の株式(34%)を取得し、持分法適用関連会社にしたり、株式会社シーズライフの株式を100%取得したりと、M&Aを通じて事業を拡大しています。
事例④株式会社ジェイグループホールディングスによる買収
寿司居酒屋やイタリアン酒場を運営する株式会社ジェイグループホールディングスは、1997年に設立されました。2000年には和風炉端居酒屋「てしごと家」1号店、2002年にはご飯ダイニングバー「ほっこり」1号店を名古屋にオープンしました。
ハワイ州で飲食店を運営する「NEWFIELD HONOLULU,INC」や、かわ焼き店「博多かわ屋」を経営する「株式会社かわ屋インターナショナル」、スペインで飲食店「KAKEHASHI S.L.U.」などを買収し、従来のチェーン店展開とは異なる個店主義の店舗展開を進めています。
なお、NEWFIELD HONOLULU,INCおよびKAKEHASHI S.L.U.は2022年以降に株式譲渡されています。
参考:株式会社ジェイグループホールディングス|有価証券報告書
事例⑤株式会社コロワイドによる買収
「甘太郎」や「3・6・5酒場」などを展開する株式会社コロワイドは、1963年に創業しました。「株式会社平成フードサービス」、「株式会社ダブリューピィージャパン」、「明治製菓リテイル株式会社」、「株式会社贔屓屋」、「株式会社アトム」などを子会社化しています。
アトムを存続会社とする吸収合併や、日本ゼネラルフード株式会社や株式会社BeerThirtyの設立などを通じて、事業を拡大しています。
まとめ|今後の居酒屋M&A市場の展望
今後の居酒屋のM&A市場は、国内外の市場動向や消費者の嗜好の変化により、さらなる活性化が期待されます。特に、海外展開を視野に入れたM&Aが増加する可能性があります。アジア市場を中心に、日本の居酒屋文化に対する関心が高まっており、現地のフランチャイズ展開や共同事業による市場拡大のチャンスが広がっています。
また、国内では業界再編が進む中で、中小規模の居酒屋チェーンが大手企業による買収の対象となり、M&Aを通じた経営資源の統合が進むことが予想されます。これにより、効率的な経営体制の構築やコスト削減が実現し、競争力が強化されるでしょう。特に、事業承継を考える経営者にとっては、M&Aが有効な選択肢となります。
さらに、消費者の多様なニーズに応える新たなビジネスモデルの模索が進む中で、健康志向に応じたメニュー開発など、革新的な取り組みがM&Aを通じて加速する可能性があります。特に、テイクアウトやデリバリーサービスの強化、オンラインプラットフォームを活用した予約システムの導入などにより、顧客体験の向上が図られる動きが見られます。
一方で、居酒屋業界特有の課題として、地域密着型の店舗運営や独自のサービススタイルをどのように継承しつつ全国展開を進めるかが鍵となります。各地域の文化や消費者の嗜好に配慮した柔軟な戦略が求められ、これがM&Aの成否を左右する要因となるでしょう。今後の市場では、単なる規模の拡大だけでなく、持続可能な成長を目指す企業の動向にも注目が集まります。
居酒屋のM&Aは、事業の強化や安定を目指す上で有効な手段です。しかし、成功には事前の市場調査や自社の強み・弱みの明確化が不可欠です。また、売却や買収には専門家のアドバイスを活用し、M&A交渉を慎重に進めることが重要です。居酒屋のM&Aを検討中の経営者は、まず専門家に相談し、具体的なステップを明確にすることをお勧めします。これにより、成功の可能性を高め、事業の持続的な成長を実現できるでしょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。