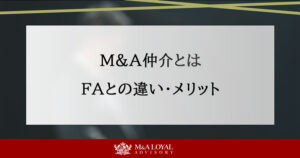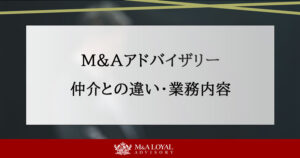投資銀行とは?仕事内容や銀行・証券会社との違いを分かりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
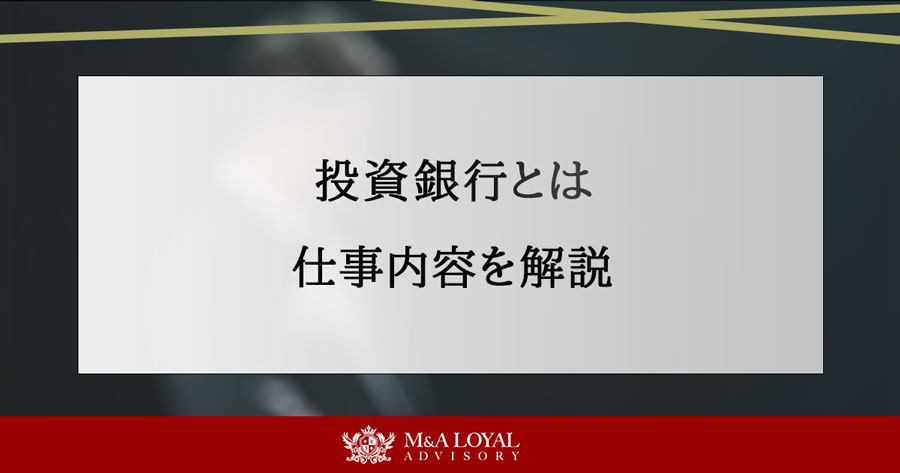
企業のM&Aや資金調達、IPO(新規株式公開)などにおいて重要な役割を果たす投資銀行ですが、聞いたことはあっても、具体的に何をしているのかは曖昧な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、投資銀行の基本的な機能や主要業務について詳しく解説します。
M&Aアドバイザリーをはじめ、ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)やDCM(デット・キャピタル・マーケット)、IPO支援といった部門ごとの役割や、信託銀行やPEファンドとの違いについても分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
投資銀行とは
まず、投資銀行の定義や歴史を解説します。
投資銀行の定義
投資銀行とは、主に企業向けにM&A支援や資金調達(株式・債券の引き受け)、IPO(新規株式公開)支援などを行う金融機関です。
預金や貸し付けを行う一般の銀行とは異なり、企業の成長戦略や資本政策をサポートする「プロフェッショナル・アドバイザー」の役割を担います。
投資銀行の歴史
投資銀行の起源は19世紀のアメリカにあり、商業銀行が預金・融資を担う中で、企業の資金調達や証券引き受けを行う「投資銀行業務」が誕生しました。
J.P.モルガンは鉄道・鉄鋼産業に巨額資本を供給し、近代的投資銀行の原型を築いたとされています。
1933年には世界恐慌を契機にグラス=スティーガル法が制定され、商業銀行と投資銀行の分離が義務化されましたが、1999年に撤廃され、再び多機能な金融機関が誕生しました。
日本では戦後、証券会社が急速に成長しました。特に野村証券や大和証券などが企業の株式や債券を発行などの資金調達を支援し、投資銀行的な役割を担うようになりました。
1950年代〜1970年代にかけて、日本は高度経済成長を遂げました。この時期、企業の資金調達ニーズが急増し、証券会社を中心にした投資銀行業務が拡大しました。
近年ではM&Aや資本市場に加え、スタートアップ支援やESGなどへも業務が広がり、投資銀行は常に時代とともに進化を続けている存在です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



投資銀行と他の銀行との違い
投資銀行と似た金融機関には次のようなものがあります。
- 商業銀行
- 証券会社
- 信託銀行
- PEファンド
- FAS
- M&A仲介会社
それぞれの役割を分かりやすく解説します。
投資銀行と商業銀行の違い
商業銀行とは、個人や企業から預金を受け入れ、その資金を貸し出しなどに回すことで利ざやを得る「預貸業務」を中心に据えた金融機関のことです。
ATMや口座管理、振込、クレジットカードの発行など、日常生活に密着した金融サービスを提供しており、経済のインフラとしての役割を果たしています。
これに対し、投資銀行は預金や貸し付けといった業務は行わず、企業の経営戦略に直接関わる資金調達やM&Aの支援を専門としています。
商業銀行が「お金を預けて借りる」仕組みを回す存在であるのに対し、投資銀行は「企業の資本構造や戦略に踏み込んで助言する」存在といえるでしょう。
投資銀行と証券会社の違い
投資銀行と証券会社は、いずれも金融市場の中で重要な役割を担っているものの、対象とする顧客層に大きな違いがあります。
証券会社は主個人投資家や機関投資家など幅広い相手を対象とし、株式や債券、投資信託などの売買を仲介し、取引手数料が主な収益源です。加えて、市場動向の情報提供や資産運用に関するアドバイスを行うなど、個人の投資活動を幅広く支援しています。
一方、投資銀行は法人を対象とし、企業の資金調達やM&A、IPOといった経営に直結する局面での戦略的なサポートが主な業務です。
投資銀行と信託銀行の違い
信託銀行は、個人や法人の財産を長期的に管理・運用することが主な役割です。例えば、遺言信託や不動産信託、年金信託などを通じて、相続・資産承継や企業年金の運営などを支援し、信託報酬を収益源としています。
また、証券代行業務や不動産関連サービスなど、専門的かつ継続的な資産管理に特化したサービスを幅広く展開している点が特徴です。
両者共に高度な金融機能を担っていますが、信託銀行が「財産の長期管理」、投資銀行が「企業の戦略支援」に特化している点が大きな違いです。
投資銀行とPEファンドの違い
PEファンド(プライベート・エクイティ・ファンド)は、自己資金や投資家から集めた資金を用いて企業の株式を取得し、自らオーナーとして企業経営に深く関与します。
株式を購入した価格よりも高く売却することで得られる利益を目的としており、リターンを得る主体そのものです。
加えて、経営陣の刷新や事業ポートフォリオの見直し、財務戦略の再構築などを通じて企業改革を主導するケースも少なくありません。
両者はM&Aの場面で連携することもありますが、PEファンドが「買い手」、投資銀行が「助言者」として機能している点が最大の違いといえます。
投資銀行とFASの違い
投資銀行とFAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)は、いずれも企業のM&Aや再編を支援する存在ですが、担う役割や関与の範囲には明確な違いがあります。
FASは、監査法人やコンサルティングファームが提供する専門サービスで、企業価値評価や財務デューデリジェンス、バリュエーション、会計処理支援など、M&Aに伴う財務・会計面の実務を担います。
一方、投資銀行は企業のM&A案件全体を主導するアドバイザリーを行います。意思決定支援や相手先との交渉の前面に立つ役割を担い、FASとは対照的に表舞台での進行管理が中心です。両者は補完的な関係にあります。
投資銀行とM&A仲介会社の違い
投資銀行とM&A仲介会社は、どちらも企業のM&Aを支援する存在ですが、関与のスタンスや対応範囲に大きな違いがあります。
M&A仲介会社は、主に売却や買収の成立に向けた交渉・調整を中心に支援を行います。比較的コンパクトな体制で、初期相談から契約締結後の経営統合(PMI)まで、一貫したフォローを提供する点が特徴です。
一方、投資銀行は、M&Aに加えて資金調達や財務戦略の立案など、より包括的なサービスを提供します。
また、取り扱う案件の規模にも違いがあります。投資銀行は大規模な取引を主に担当し、仲介会社は中堅・中小企業を対象とした実務的な支援に強みを持っています。
投資銀行の存在意義
投資銀行の存在意義は、次のとおりです。
- 企業の意思決定を支える
- 投資家に安心を届ける
- 経済の循環を生み出す
それぞれを詳しく解説します。
企業の意思決定を支える
企業がM&Aや資金調達を検討する場面では、財務・法務・戦略の各分野における高度な知識と、第三者としての客観的な視点が求められます。
投資銀行は、企業価値の評価やスキームの設計に加え、関係者間の調整などを通じて、経営判断の実効性を高める役割を担います。
特に大規模な資本移動を伴う案件では、自社のみでの対応には限界が生じやすく、外部の専門機関による支援が不可欠です。
投資家に安心を届ける
投資家が株式や債券に資金を投じる際には、正確かつ公平に整理された情報が不可欠です。
投資銀行は、企業の財務状況や成長可能性を評価し、その内容を市場に適切な形で提示することで、投資判断の信頼性を高めています。
投資家が将来性のある企業に安心して資金を提供できる環境を整備することで、市場の信頼性と透明性を維持し、健全な資本形成を促進することも重要な役割です。
経済の循環を生み出す
企業の成長や産業の進化には、必要な資金が適切な形で供給される仕組みが欠かせません。
投資銀行は、企業の資金ニーズと金融市場を結びつける役割を担っており、株式発行や社債の引き受けといった手段を通じて、資本の流れを円滑にします。
また、M&Aや再編の支援を行うことで、経営資源の再配置を促し、産業の生産性向上にも貢献しています。
投資銀行の主要業務と部門
投資銀行の主要業務と部門は、次のとおりです。
- M&Aアドバイザリー
- IPO支援
- ECM
- DCM
- リサーチ
- その他の業務
それぞれを分かりやすく解説します。
M&Aアドバイザリー
投資銀行の中核業務のひとつが、M&Aアドバイザリーです。
企業の合併・買収や事業売却、統合再編などにおいて、戦略の立案から取引の実行までを一貫して支援する役割を担っています。
具体的には、対象企業の候補選定や企業価値評価(バリュエーション)、意向表明書や基本合意書の策定、買収スキームの設計、交渉支援、デューデリジェンスの調整、契約締結まで、多岐にわたる業務です。
案件の規模が大きい場合や関係者が多数関与するケースでは、透明性の高い情報管理と、意思決定プロセスの明確化が求められます。近年では、クロスボーダーM&Aや業界再編といった複雑化する案件に対する需要が高まっています。
IPO支援
IPO(新規株式公開)支援は、企業が証券取引所に上場するプロセスを包括的に支援する業務です。
投資銀行は、上場に向けた準備段階から関与し、適正な企業価値の算定や目論見書の作成支援、審査対応などを担当します。また、主幹事証券として、投資家への情報提供や株式の販売管理を行うのもIPO支援業務のひとつです。
上場企業として市場から信頼を得るには、透明性と説明責任を確保する体制が不可欠です。
投資銀行は、その整備と実行支援を通じて、企業の市場参入をスムーズに実現させる役割を果たしています。
ECM
ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)は、株式での資金調達を企業の資金調達を支援する仕組みを指します。
資本市場の動向や投資家のニーズを適切に把握し、最適なタイミングと条件で資金調達を実現するための設計が求められます。
投資銀行は、発行体との協議を通じて調達額や発行方式を確定し、引受業務や投資家向けのマーケティング活動を遂行します。
市場の信頼を損なうことなく、企業が成長戦略を推進するための資本を安定的に確保できるよう支援する点において、ECM部門の果たす役割は極めて重要です。
DCM
DCM(デット・キャピタル・マーケット)は、債券を活用した資金調達を専門に担う部門であり、企業や自治体による社債・劣後債・サムライ債などの発行を支援します。
中長期的に安定した資金を確保する手段として、借り入れに代わる柔軟な選択肢を提供できる点が特徴です。
投資銀行は、市場環境や金利動向を踏まえた上で、最適な発行条件の設計や投資家向け資料の作成、さらには発行後の流通管理までを担います。 的確な戦略を立案し、スムーズな実行を実現することがこの部門の使命です。
リサーチ
リサーチ部門は、企業分析や業界動向、市場環境に関する調査・報告を行う専門部門です。
証券アナリストが中心となり、個別企業の財務状況や事業戦略を分析し、投資判断に資する情報を提供します。こうした分析は、投資家へのレポート発行のみならず、ECM・DCM・IBDなど他部門の業務判断にも活用されます。
マクロ経済や政策動向、セクターごとの成長予測などもカバーしており、知見の深さと広がりが求められます。
その他の業務
企業再生や事業再編、企業防衛策の助言、さらにはストラクチャード・ファイナンスやファンド設立支援など、多様な金融ソリューションを提供しています。
近年ではESG(環境・社会・ガバナンス)対応やサステナビリティ関連の資金調達支援も拡大しており、社会的価値と経済的成果の両立が求められる場面が増えています。
顧客の課題に応じて最適なスキームを設計し、実行支援を通じて新たな企業価値の創出に貢献することが、投資銀行の本質的な役割といえるでしょう。
日本の主な投資銀行
日本で事業を展開する主な投資銀行や投資銀行業務を担う証券会社を紹介します。
外資系投資銀行
外資系投資銀行は、グローバルに展開する金融グループの日本法人または支店として、日本国内でもハイエンドな投資銀行業務を展開しています。
外資系投資銀行は、主にグローバル企業や政府系ファンドを顧客とし、国際的な案件に特化しています。英語による対応力やスピードを重視する企業文化も特徴です。
代表的な外資系投資銀行は、次のとおりです。
- ゴールドマン・サックス証券
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- JPモルガン証券
- BofA証券
- シティグループ証券
日系大手証券会社
日本では、海外のように独立型の専業投資銀行は少なく、主に証券会社やメガバンクの一部門として投資銀行業務を担っているケースが一般的です。
日本の証券市場で長年の実績を持ち、高いブランド力を背景に、M&AやIPO、株式・債券の引き受けなど多岐にわたる業務を展開しています。
国内外の大企業を主な顧客とし、グローバル案件にも対応可能な体制を整えています。
特に、クロスボーダーM&Aやグローバルオファリングといった高度な取引では、豊富な実績と専門チームの存在が大きな強みです。
投資銀行部門がある証券会社は次のとおりです。
- 野村證券
- 大和証券
- みずほ証券
- SMBC日興
日系準大手証券会社
日系準大手証券会社は、大手証券会社に比べ規模はやや小さいものの、特定分野や中堅企業向けに強みを持ちます。
証券業務に加え、M&Aや資金調達支援などの投資銀行機能を併せ持つことが特徴です。
主に中堅・中小企業を顧客とし、事業承継や地場産業の資本政策支援に注力しています。地域金融機関や地元企業とのネットワークを生かした提案力が強みです。
代表的な日系準大手証券会社は、次のとおりです。
- 岡三証券
- 東海東京証券
- いちよし証券
- 岩井コスモ証券
- 丸三証券
投資銀行におけるM&Aアドバイザリー業務の流れ
投資銀行におけるM&Aアドバイザリー業務の一般的な流れは、次のとおりです。
- 【売り手】M&A戦略立案
- 【売り手】提案資料の作成
- 【売り手】ネームクリアの確認
- 【買い手】ノンネーム検討
- 【両手】トップ面談の実施
- 【買い手】意向表明書の提示
- 【両手】基本合意契約の締結
- 【買い手】デューデリジェンスと条件交渉
- 【両手】最終契約書の締結(SPA)
- 【両手】クロージング(譲渡実行)
それぞれを詳しく解説します。
【売り手】M&A戦略立案
投資銀行は売り手企業とM&Aアドバイザリー契約を締結します。この段階では、経営課題や成長戦略とM&Aの整合性を確認し、方針に合意できれば正式にプロジェクトが始動します。
契約書には、業務範囲や報酬体系(成功報酬や着手金)、守秘義務、独占交渉の有無などが明記されます。この契約を起点に、投資銀行は戦略立案から交渉・実行に至るまでの全工程で中心的な役割を果たします。
【売り手】提案資料の作成
売り手企業は投資銀行とのアドバイザリー契約締結後、投資銀行はまず、売り手企業の情報を基に匿名概要資料(ティーザー)を作成します。この資料は企業名を伏せた簡易資料で、事業の概要や特徴を買い手候補に伝えるためのものです。
【売り手】ネームクリアの確認
買い手企業への打診し、交渉フェーズに進む際に、売り手企業は「ネームクリア」を行います。これは、アプローチ予定の買い手に対し、社名を公開するプロセスです。
売り手は望ましくない相手に対してネームクリアを拒否することもでき、お互いが同意した場合はNDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)締結後に実施されます。
【買い手】ノンネーム検討
買い手企業は、ノンネーム資料(ティーザー)に基づく初期検討を行います。
この段階では売り手企業名は伏せられており、概要情報のみを基に買収の是非や戦略的整合性を社内で評価します。関心を持った場合は、NDAを締結しIM(Information Memorandum:企業概要書)の提供を受ける準備に進みます。
【両手】トップ面談の実施
両社の関心が高まり、基本的な条件が擦り合わされた段階で、トップ面談が実施されます。
これは、経営方針や事業理解、統合後のシナジーについて、経営者同士が直接意見を交わす重要なプロセスです。
【買い手】LOIの提示
トップ面談で信頼関係が築かれ、双方が相手として適切であると判断した場合、投資銀行が間に立ち、条件面の調整に入ります。
この段階で、買い手企業は「LOI(Letter of Intent:意向表明書)」を提出します。
LOIは、買収スキームや取引スケジュール、独占交渉の希望など、買収に関する基本的な提案条件をまとめたものであり、売り手企業に対して正式な関心を示す重要な文書です。
【両手】基本合意契約の締結
意向表明書の内容に基づき、両社間で基本合意契約が締結されることもあります。
この合意書は法的拘束力を持たない場合もありますが、一定期間の独占交渉権や価格の目安などが盛り込まれることが多く、実務上重要なステップです。
【買い手】デューデリジェンスと条件交渉
意向表明書の提示後、売り手側が基本的な条件に同意すると、買い手はDD(Due Diligence:デューデリジェンス)へと進みます。
このプロセスでは、財務・税務・法務・人事・ITなどの多角的な観点から対象企業の実態とリスクを徹底的に調査します。
投資銀行は、資料準備や情報開示、関係者との調整などを担い、調査結果を基に価格や条件の詳細交渉を進めていきます。
【両手】SPAの締結
DDの結果と交渉内容を踏まえ、条件面の最終合意に至ると、SPA(Share Purchase Agreement:最終契約書)の締結に移ります。
この契約には、譲渡対象・価格・支払い方法・表明保証・クロージング条件など、法的拘束力を持つ条項が含まれます。弁護士や関係者と連携しながら文言を精査し、署名に至ります。
【両手】クロージング(譲渡実行)
最終契約書の締結後、クロージング(譲渡実行)として株式譲渡、資金決済、資産の引渡しなどが行われます。
これには、代表者私物の買い戻しや会社印の引渡しなど実務も含まれ、全ての手続きが完了してはじめてM&Aは成立となります。
投資銀行を活用すべきM&Aの種類
投資銀行を活用すべきM&Aの種類は、次のとおりです。
- 大型M&A
- クロスボーダーM&A
- 業界再編を伴うM&A
- 上場企業の非公開化(ゴーイング・プライベート)
- 敵対的買収
それぞれを分かりやすく解説します。
大型M&A
取引金額が数百億円を超えるような案件では、単なる企業売買にとどまらず、資金調達の設計やバリュエーション(企業価値評価)の精緻化、さらには法務・税務・会計など、多方面にわたる高度な対応が求められます。
買収スキームも複雑になりやすく、LBO(レバレッジド・バイアウト)や合併、持株会社の活用といった構造を採用することも珍しくありません。
こうした案件では、投資銀行がプロジェクトの中核を担い、多様な専門家を束ねながら、全体を統括する役割を果たします。
クロスボーダーM&A
海外企業を対象としたM&Aでは、取引相手国の法制度や税務、開示基準、外資規制といった制度面に加え、商慣習や言語、文化の違いも考慮する必要があります。
さらに、為替変動リスクや現地政府との関係、クロスボーダー特有のディールスキーム設計といった点も、プロジェクトの進行における重要な論点です。
業界再編を伴うM&A
同業他社との統合やグループ再編を目的としたM&Aは、単なる企業単体の利益追求にとどまらず、業界全体の構造に影響を及ぼすケースが少なくありません。
こうした取引では、競争環境や市場シェア構造の把握に加え、統合によるコスト削減や成長余地の定量的な分析が不可欠です。また、独占禁止法(公正取引法)への適合性や、ステークホルダーへの影響も慎重に検討する必要があります。
特に市場が成熟または過渡期にある場合には、業界全体の中長期的な再編の方向性を見据えた戦略提案が求められます。
株式の非公開化(ゴーイング・プライベート)
上場企業が株式を非公開化する取引では、TOB(株式公開買付)やMBO(経営陣による買収)といった手法が一般的です。
対象企業の既存株主に対する説明責任や、買付価格の妥当性確保、インサイダー情報への配慮、開示手続きの厳格な順守など、高度かつ繊細な対応が求められます。
さらに、上場廃止までのスケジュール管理に加え、従業員や取引先との関係調整、市場およびメディアへの説明対応も重要な要素です。
こうした一連のプロセスを円滑に進めるには、法律や会計、金融の専門知識に加え、広範な利害関係者を見渡す視野と全体調整力が不可欠です。
敵対的買収
企業側の同意を得ずに進められる買収は「敵対的買収(hostile takeover)」と呼ばれ、通常のM&Aとは異なり、より高度な対応が求められます。
買い手企業側は、TOB(株式公開買付)を仕掛けるタイミングや買付条件の設計に加え、世論や株主の反応も意識した慎重な進行が必要です。
一方、防衛側は、ポイズンピル(新株予約権の発行)やホワイトナイトの導入、株式持ち合いの強化など、複数の対抗策を検討します。
こうした局面では、法務・IR(広報)・資本政策といった要素が複雑に絡み合い、対応の遅れが経営権の喪失に直結するリスクもあります。
M&Aで投資銀行を利用するときのポイント
M&Aで投資銀行を利用するときのポイントは、次のとおりです。
- 案件の難易度や規模を見極める
- なるべく早い段階で相談する
- 支援内容と報酬体系を事前に確認する
- 得意分野や業界知見の有無をチェックする
それぞれを詳しく解説します。
案件の難易度や規模を見極める
投資銀行は、大規模なM&Aにおいて、多く活用されます。
一方、比較的小規模な事業承継や地域密着型のM&Aでは、仲介会社や独立系アドバイザーの方が、コスト面や柔軟性の観点から適している場合もあります。
まずは、自社の置かれた状況とM&Aの目的を整理し、どのレベルの専門的支援が必要かどうかを見極めることが肝要です。
なるべく早い段階で相談する
M&Aを検討し始めた段階で、できるだけ早期に投資銀行へ相談することが望まれます。
戦略立案や候補先の選定基準の策定、アプローチ資料の準備といった初期フェーズの質は、その後のプロセス全体に大きな影響を及ぼします。
早い段階から支援を受けることで、情報管理や交渉戦略を事前に整理でき、意思決定のスピードと確実性が格段に高まります。
支援内容と報酬体系を事前に確認する
投資銀行と契約を交わす際には、どこまでの業務を依頼できるのか、また報酬体系がどのように構成されているのかを、事前に正確に把握しておくことが重要です。
FA(フィナンシャル・アドバイザリー)契約では、着手金や月額報酬、成功報酬が組み合わされるケースと成功報酬のみのケースがあり、案件の規模や難易度に応じてその金額や割合が変動します。
契約条項を十分に確認し、自社のニーズや意思決定の進め方と整合しているかどうかを慎重に見極める必要があります。
得意分野や業界知見の有無をチェックする
投資銀行には、それぞれ得意とする業種や支援領域があり、強みは一様ではありません。
例えば、製造業の再編に強みを持つ日系投資銀行、クロスボーダーM&Aに精通した外資系投資銀行、IPO支援や資本政策を中心に展開する企業など、その特色は多岐にわたります。
過去の実績や担当者の経歴を確認することで、業界特有の課題を深く理解しているアドバイザーを見つけやすいでしょう。
投資銀行が関与したM&A成功事例
投資銀行や証券会社の投資銀行部門が関与したM&A成功事例を紹介します。
ソフトバンクグループによるARMの買収(2016年)
2016年、ソフトバンクグループは英国の半導体設計大手ARMを約3.3兆円で買収し、日本企業による過去最大級のクロスボーダーM&Aを実現しました。
買収にはゴールドマン・サックスなどのグローバル投資銀行が関与し、資金調達やスキーム設計、各国の規制対応まで多方面で支援しました。
ARMはIoTやスマートデバイス分野に強みを持ち、ソフトバンクの成長戦略における中核的存在でした。
買収は短期間で完了し、戦略的な意思決定と関係機関との連携が成功を支えました。本件は、グローバル展開を目指す日本企業にとって象徴的なM&A成功事例です。
武田薬品工業によるシャイアー買収(2018年)
2018年、武田薬品工業はアイルランドの大手製薬会社シャイアーを約6兆8000億円で買収し、日本企業による過去最大規模のクロスボーダーM&Aを実現しました。
買収には野村證券が財務アドバイザーとして参画し、買収スキームの構築から資金調達のアレンジメントまで包括的に支援しました。
資金面では、複数通貨建ての社債発行やローンを組み合わせ、調達コストの最適化が図られました。
この取引は金額の大きさに加え、法規制、通貨、会計、税務といった多面的な要素が絡む高難度案件であり、投資銀行の高度な専門性と国際的な調整力が発揮された象徴的な事例です。
NTTによるNTTドコモの完全子会社化(2020年)
2020年、NTTはNTTドコモを完全子会社化するため、約4兆円規模のTOB(株式公開買付)を実施し、親子上場の解消を実現しました。
本件は、企業統治や株主平等の観点からも注目を集めた象徴的な取引であり、市場の信頼性確保と株主の公平な取り扱いが重要な論点となりました。
野村證券は財務アドバイザーとして参画し、買収価格の妥当性評価、TOBスキームの設計、株主対応やディスクロージャーなど、戦略面から実務面まで幅広い支援を提供しました。
上場企業を対象とした大規模TOBは迅速かつ慎重な進行が求められる中、投資銀行の専門的な知見と実行力によって、円滑な手続きと確実な取引完了が実現された成功事例といえます。
投資銀行に関するQ&A
最後に、投資銀行に関するよくある質問とその回答を紹介します。
中小企業でも投資銀行に相談できる?
中小企業でもM&Aの相談に対応している投資銀行も増えています。 ただし、メガバンクや外資系の投資銀行の場合、大型案件が中心となり、対応していないケースもあるため確認が必要です。
投資銀行の報酬はどう決まる?
報酬は通常、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)契約に基づいて設定されます。
契約には、着手金や月額報酬、成功報酬といった要素が含まれ、案件の規模や難易度によってその構成比が異なります。
特に成功報酬はM&Aの成立時に発生し、取引金額に対する一定の割合(数%前後)で設定されることが一般的です。
複数の投資銀行に同時に相談しても良い?
契約前の段階であれば、複数の投資銀行に相談し、それぞれの提案内容や支援体制を比較することは可能です。
ただし、FA契約は専属契約が一般的であり、契約後は原則として1社のみに依頼します。
支援実績や業界理解、報酬条件の透明性など、複数の観点から慎重に比較検討し、自社に最も適したアドバイザーを選ぶことが重要です。
投資銀行はPMIまで対応してくれる?
投資銀行のサポートは選定から、リスクと価値評価、公正な価格交渉と契約作成、クロージングまでと一貫して行われますが、PMIをサポートまで行うかどうかは銀行によって異なるため、事前の確認が必要です。
投資銀行についての基本的な理解を深めることで、企業や個人投資家としての次のステップを考える手助けになるでしょう。投資銀行は、企業の成長を支えるパートナーとして、資金調達やM&Aなどで重要な役割を果たしています。
ただし、案件によってはM&A仲介会社が向いているケースもあるため、中小企業の場合は両方を視野に入れることをおすすめします。M&Aや経営課題のお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。