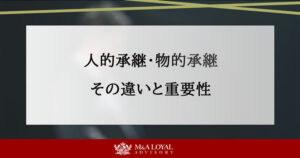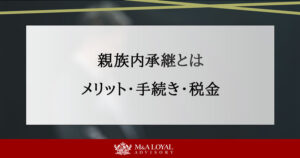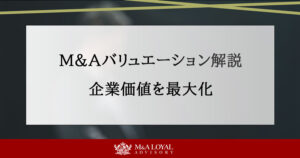承継の読み方とは?事業継承との違いと5つの成功ポイントを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
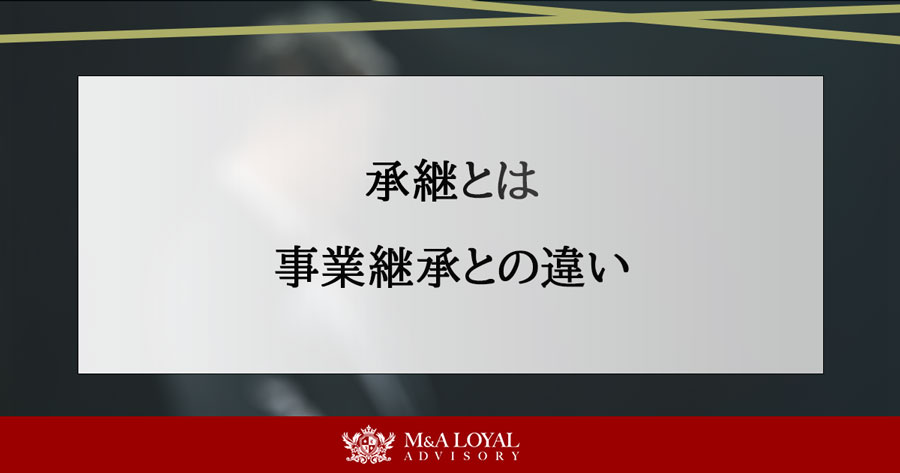
「承継」という言葉を見聞きすることはあっても、正確な読み方や意味を知らない経営者の方も多いのではないでしょうか。「承継」は「しょうけい」と読み、単に事業を引き継ぐだけでなく、経営理念や企業文化など抽象的なものも含めて受け継ぐという重要な意味を持っています。
本記事では、「承継」の読み方から始まり、事業継承との違い、引き継ぐべき3つの資源、承継方法の比較、具体的な進め方まで、事業承継を成功させるために必要な知識を詳しく解説します。皆様の大切な会社を次世代へ円滑に引き継ぐための参考にしてください。
目次
承継の読み方と基本的な意味を理解しよう
「承継」という言葉は、会社経営やM&Aに関わる重要な用語でありながら、正確な意味を理解している人は意外と少ないかもしれません。ここでは、「承継」の正確な読み方から、ビジネスや法律の世界での使われ方まで、基本的な知識を深めていきましょう。
承継の読み方「しょうけい」の由来と覚え方
「承継」は「しょうけい」と読みます。この言葉は「承」と「継」という二つの漢字から成り立っています。
「承」は「うけたまわる」という意味を持ち、何かを受け入れることを表しています。一方、「継」は「つぐ」という意味で、続けることや引き継ぐことを示しています。つまり「承継」とは「受け入れて継続すること」を意味しています。
覚え方としては、「承知する(しょうちする)」の「承」と「継続する(けいぞくする)」の「継」を組み合わせると「しょうけい」になると考えるとよいでしょう。また、似た言葉に「継承(けいしょう)」がありますが、読み方が逆になっているので注意が必要です。
「承継」は日常会話ではあまり使われませんが、ビジネスや法律の世界では重要な概念です。特に事業承継やM&Aを検討する際には、必ず耳にする用語となります。
ビジネスシーンでの承継の一般的な使われ方
ビジネスの現場では、「承継」は主に「事業承継」として使われることが多く、企業オーナーや経営者が自社の事業を次世代に引き継ぐことを指します。中小企業の経営者高齢化に伴い、これは重要な社会課題となっています。
また、「権利承継」「義務承継」といった特定の権利や義務を引き継ぐ場面や、会社における「地位承継」という表現も一般的です。例えば、特許権の承継や代表取締役の地位を息子に承継するといったケースが該当します。
「承継計画」も重要な用語で、事業や資産をどのように引き継ぐかについての具体的な計画を指します。中小企業では、後継者育成や株式移転、税金対策など、多角的な視点からの計画が必要です。
このように、ビジネスシーンでは「承継」は単なる引き継ぎ以上の、計画的かつ戦略的な意味合いを持ちます。
法律用語としての承継の定義と適用範囲
法律の世界では、「承継」は権利や義務が一方から他方へ移転することを指す専門用語です。法律上、承継は「包括承継」と「特定承継」の2種類に分けられます。
包括承継は、権利義務の全部または一定の割合を一括して引き継ぐことで、相続や会社の合併がこれに当たります。例えば、相続人は被相続人の財産に関する権利義務を一括して承継し、会社合併では消滅会社の権利義務のすべてを存続会社が承継します。
一方、特定承継は特定の権利義務のみを個別に引き継ぐもので、売買や贈与、債権譲渡などがこれに該当します。不動産売買では、対象の物件と権利が買主に承継されます。
事業承継においては、これらの概念を理解することが重要です。中小企業の事業承継では、会社法、相続法、税法など様々な法律が関わるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



事業承継と事業継承の違いと使い分け
「承継」と「継承」はどちらも「引き継ぐ」という意味を持つ言葉ですが、微妙に意味合いが異なります。事業を引き継ぐ際には「事業承継」と「事業継承」のどちらが正しい表現なのか、混乱することも多いでしょう。ここでは両者の違いと適切な使い分けについて解説します。
事業継承の基本的な意味
「継承」は「けいしょう」と読み、主に具体的・形のあるものを受け継ぐことを意味します。辞書によれば、「身分・権利・義務・財産などを受け継ぐこと」と定義されています。
「事業継承」は、事業に関連する具体的な権利や資産、財産を引き継ぐという意味合いが強くなります。たとえば、会社の株式や不動産、設備などの財産、取引先との契約関係などの引き継ぎに焦点が当たる場合に「事業継承」という表現が使われることがあります。
一般的には、「継承」は日常生活でもよく耳にする言葉であり、「王位継承」「伝統芸能の継承」など、法律問題が絡まない地位や伝統の引き継ぎに使われるケースが多いとされています。
事業承継と事業継承の使い分け事例
「承継」と「継承」は文脈によって使い分けられることがあります。以下に具体的な使い分けの例を示します。
- 経営者が後継者に「地域に愛される店を目指す」という精神や理念を引き継ぐ場合
→「承継」
- 経営者が後継者に店舗や設備などの資産や権利を引き継ぐ場合
→「継承」
しかし実際のところ、事業を引き渡す際には精神や理念といった抽象的なものと、資産や権利といった具体的なものの両方が引き継がれるため、厳密に使い分けられないことも多いです。
一般的に、事業全体を次世代に引き継ぐプロセスを表す場合には「事業承継」が使われることが多く、歴史や伝統、理念など事業の本質的な価値を引き継ぐことに焦点を当てる場合は「事業継承」という表現が用いられることがあります。
事業承継と事業継承の法的解釈の違い
法的には「承継」が正式な用語として使われることが多いです。たとえば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)や「事業承継税制」など、法令や行政文書では「承継」という表記が採用されています。
法律上、「承継」はより厳密な定義を持ち、権利義務が一方から他方へ移転することを指します。「包括承継」(相続や会社合併など、権利義務を一括して引き継ぐこと)と「特定承継」(特定の権利義務のみを個別に引き継ぐこと)の区別もあります。
契約書や公的文書では「承継」が適切とされることが多く、実務や公式な場面では「事業承継」が一般的です。中小企業庁などの公的機関も「事業承継」という表記を採用しています。
M&A契約書における承継関連用語の正しい理解
M&Aや事業譲渡の契約書においても、「承継」という表現が標準的に使用されています。以下に、M&A契約書でよく使われる承継関連の用語を紹介します。
「権利義務の承継」は、契約上の地位や債権債務を他者に引き継ぐことを指します。例えば事業譲渡契約書では「譲渡会社は譲受会社に対し、本事業に関する一切の権利義務を承継させる」といった表現が用いられます。
「地位の承継」も重要な概念です。取引先との契約関係を承継する場合、契約の相手方の同意が必要となりますが、これを「契約上の地位の承継」と呼びます。事業譲渡における地位の承継には、譲渡会社と譲受会社の合意だけでなく、契約相手方の同意も必要とされます。
「包括的承継」という表現は主に会社合併の際に使われます。会社法では、合併を「消滅会社の権利義務の全部を存続会社に承継させるもの」と定義しており、このような全ての権利義務を一括して引き継ぐことを「包括的承継」と呼びます。
M&A実務では、これらの用語を正確に理解し、適切に契約書に反映させることが重要です。契約書作成の際には、承継の対象となる権利義務を明確に特定し、承継の方法や条件を詳細に規定することが求められます。
事業承継で引き継がれる3つの資源
事業承継は単に社長の交代だけを意味するものではありません。企業が長期的に存続し、発展していくためには、現経営者から後継者へ様々な経営資源を適切に引き継ぐことが必要です。
中小企業庁の事業承継マニュアルでは、事業承継において引き継ぐべき要素として、「経営権(人の承継)」「経営資源」「知的財産」の3つを挙げています。これらの要素をバランスよく承継することで、スムーズな事業の引き継ぎが実現します。
経営権(人の承継)
経営権の承継とは、会社を運営する権利を後継者に引き継ぐことです。多くの中小企業では、経営者と株主(オーナー)が一致しているため、経営権を引き継ぐには株式の承継が不可欠となります。
経営権承継の重要ポイント:
- 株式保有比率は議決権の過半数(1/2以上)を確保することが理想的
- 2/3以上の株式保有で特別決議の可決権限が得られる
- 1/2以下の株式保有だと解任リスクがある
- 段階的な権限委譲が円滑な承継のカギとなる
- 代表権だけでなく実質的な経営能力の獲得も重要
株式の承継は主に、代表取締役の地位と役割を後継者へと引き継ぐために行われます。企業の経営権を適切に得るためには、株式の保有数が少なくとも議決権の過半数(1/2以上)を獲得することが理想的です。この水準の株式保有により、株主総会での普通決議が単独で可決できるようになり、ある程度の経営権が確保できます。
さらに、株式の保有数が2/3以上に達すると、特別決議を可決する権限が得られます。特別決議では、会社の解散や定款の変更など、企業における重要な意思決定が可能となります。一方、株式保有が1/2以下にとどまると、他の株主の意向によって代表取締役を解任されるリスクが生じます。
経営権の承継は、単なる形式上の手続きにとどまらず、後継者による実質的な経営能力の獲得も含みます。そのため、後継者の育成や教育も重要な要素となります。
経営資源
経営資源の承継とは、会社が所有する財産や資産を後継者に引き継ぐことです。事業承継において引き継がれる経営資源には、様々な種類があります。
承継すべき主な経営資源:
- 運転資金などの事業に必要な資金
- 土地や建物などの不動産、機械や設備などの固定資産
- 株式や有価証券などの金融資産
- 特許権、商標権などの知的財産権
- 債務や個人保証などのマイナス面の財産
まず重要なのは、事業に必要な資金です。運転資金は事業活動を維持するために不可欠であり、後継者が十分な資金を確保できるよう計画的に承継することが必要です。
次に事業用資産として、土地や建物などの不動産、機械や設備などの固定資産が挙げられます。これらは事業を安定して運営するための基盤となります。会社が所有する不動産や設備は、株式を承継することで後継者へと自動的に引き継ぐことができます。しかし、オーナー経営者が個人で事業用資産を所有している場合は、これらも合わせて移転することが望ましいでしょう。
また、会社の負債や個人保証などのマイナス面の財産も承継の対象となります。後継者の保証負担を軽減するための「経営者保証解除」の仕組みの活用も検討すべきです。
資産の承継においては、相続税や贈与税の負担が課題となることがあります。事業承継税制などの税制優遇措置を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。資産の規模によっては多額の税金が発生する場合もあるため、専門家に相談しながら計画的に進めることが重要です。
知的財産
知的財産の承継は、目に見えない無形の資産を引き継ぐことです。これらは企業の競争力の源泉となる重要な要素であり、事業承継において慎重に取り扱う必要があります。
承継すべき主な知的財産:
- 取引先との関係:長年かけて構築した信頼関係や取引ネットワーク
- 顧客データ:顧客情報や購買履歴などの蓄積されたデータ
- 経営方針:会社の方向性や意思決定の指針
- 従業員のスキル:従業員が持つ技術や知識、ノウハウ
- 商標や特許:法的に保護された権利 ・企業の信用:市場での評判や信頼性
これらの知的財産は、形がないため数値化や文書化が難しく、承継が容易ではありません。特に従業員が持つ技術やノウハウは、人材の流出とともに失われる可能性があるため、後継者は従業員との良好な関係構築に努める必要があります。
知的財産の中には、段階的に引き継ぐ必要があるものもあります。経営者の思いや会社の未来像も知的財産の一部であり、これらを後継者に適切に伝えることが、事業の継続的な発展につながります。
事業承継を成功させるためには、経営との向き合い方に共感し、人脈を大切にする後継者を選ぶことが重要です。後継者は単に経営権や資産を引き継ぐだけでなく、会社の文化や価値観を理解し、尊重することが求められます。
中小企業における3つの事業承継方法の比較
中小企業の経営者が高齢化する中、事業承継は避けては通れない課題となっています。中小企業庁のデータによれば、2025年までに約245万人の経営者が70歳を超え、そのうち約半数が後継者未定という状況です。
事業承継には大きく分けて「親族内承継」「親族外承継」「M&A」の3つの方法があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自社に最適な方法を選ぶことが重要です。
親族内承継
親族内承継は、経営者の子どもや兄弟姉妹、配偶者などの親族に事業を引き継ぐ方法です。かつては事業承継の主流であり、家業を代々受け継ぐという形で多くの中小企業で行われてきました。
親族内承継の最大のメリットは、従業員や取引先から心情的に受け入れられやすいことです。長年親しんできた経営者の血縁者が後を継ぐことで、社内外の関係者に安心感を与えることができます。また、後継者教育を計画的に行うための準備期間を十分に確保できるのも大きな利点です。
一方、デメリットとしては、適切な後継者候補が親族内にいるとは限らない点が挙げられます。経営者の子どもが必ずしも経営に関心を持っているとは限らず、近年では他業種への就職を希望するケースも増えています。また、親族間で相続トラブルが発生するリスクもあります。株式や事業用資産の相続において、後継者とその他の相続人との間で遺留分をめぐる問題が生じることもあるでしょう。
親族外承継
親族外承継は、会社の役員や従業員など、親族以外の人物に事業を引き継ぐ方法です。近年、親族内に適切な後継者がいないケースが増える中で、重要性が高まっています。
メリットは、経営能力や資質を見極めた上で後継者を選定できることです。会社の事業や文化をよく理解している人材を選べるため、経営の一貫性を保ちやすいという特徴があります。また、経営者として必要な能力を持つ人材を広い範囲から選定できるため、事業の発展につながる可能性も高まります。
デメリットとしては、後継者が株式を取得するための資金をどう調達するかという課題があります。特に、自社株の評価額が高い場合、後継者個人の負担が大きくなります。また、親族内の株主から株式を買い取る際に交渉が難航するケースや、他の従業員から反発を受けるリスクもあるでしょう。さらに、金融機関から個人保証を求められる可能性もあり、後継者にとって大きな負担となることがあります。
M&A
M&Aによる事業承継は、第三者(他の企業や個人)に事業を売却する方法です。親族内や従業員に適切な後継者がいない場合の選択肢として、近年急速に増加しています。
最大のメリットは、広範囲から最適な引き継ぎ先を探せることです。適切な買い手が見つかれば、会社の持つ技術やノウハウ、従業員の雇用を守りながら事業を存続させることができます。また、オーナー経営者にとっては、長年築き上げてきた事業の対価として譲渡益を得られるのも魅力です。さらに、借入金の個人保証からの解放や、経営からの円満な引退が実現できる可能性もあります。
一方で、M&Aのデメリットとしては、企業文化の違いから統合が難しいケースがあることや、従業員が不安を感じる可能性があることが挙げられます。また、機密情報の漏洩リスクや、条件に合う買い手が見つからない可能性もあります。さらに、売り手と買い手の間で価格交渉が折り合わず、成約に至らないケースもあるでしょう。
中小企業の特性に合わせた最適な承継方法の選び方
最適な事業承継方法を選ぶには、以下のポイントを考慮しましょう。
まず、後継者候補の有無と資質を見極めることが重要です。親族や従業員に経営者としての資質を持つ人物がいれば、親族内・外承継が選択肢になります。適切な後継者がいない場合はM&Aを検討しましょう。
次に、会社の財務状況や規模も考慮すべき要素です。業績が良好で将来性が高い企業はM&Aで高評価が期待できますが、地域密着型の小規模事業では地元の理解者への承継が適している場合もあります。
オーナー経営者自身の希望も重要です。経営からの完全な引退を望むならM&Aが、引退後も一定の関与を続けたいなら親族内・外承継がマッチするでしょう。
最後に、従業員の雇用継続や取引先との関係維持などステークホルダーへの配慮も欠かせません。どの方法を選ぶにせよ、早期からの準備と専門家への相談が成功のカギとなります。
事業承継の具体的な進め方
事業承継は経営者にとって重要なライフイベントであり、計画的に進めることが成功の鍵となります。多くの専門家が指摘するように、事業承継の準備には5〜10年程度の期間が必要とされています。ここでは、事業承継を円滑に進めるための具体的なステップを解説します。
事業承継計画を5年前から始める
事業承継を成功させるためには、十分な準備期間を設けることが不可欠です。理想的には、実際の承継を行う5年以上前から計画を立て始めることをおすすめします。
計画の第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。早期に計画を立てる主なメリットには以下のものがあります。
- 後継者育成の時間確保:経営者としての知識やスキルを身につける十分な期間が得られる
- 税制優遇措置の活用:計画的な株式移転により、相続税・贈与税の負担を軽減
- 関係者への周知と理解:従業員や取引先、金融機関に後継者を認知させる時間が持てる
- 経営課題の解決:事業承継前に経営上の課題を洗い出し、解決する時間的余裕が生まれる
特に中小企業の場合、経営者の個人的な信用や人脈に依存している部分が大きいため、これらを後継者に引き継ぐには十分な時間が必要です。
承継前に企業価値を向上させる
事業承継を控えた企業にとって、承継前に企業価値を高めておくことは非常に重要です。特にM&Aによる第三者承継を検討している場合は、企業の魅力を高めることで、より良い条件での譲渡が可能になります。
企業価値向上のための具体的な取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。
- 財務体質の強化:不採算事業の整理、収益性の改善、負債の圧縮
- 業務プロセスの整備:業務の標準化、マニュアル化による属人性の排除
- 経営の見える化:経営指標の明確化、情報共有の仕組み構築
- 知的資産の可視化:技術やノウハウ、顧客関係など目に見えない資産の価値化
これらの取り組みにより、後継者が経営を引き継ぎやすい環境を整えることができ、スムーズな事業承継が実現します。
承継手続きを段階的に進める
事業承継の手続きは、一度に行うのではなく、段階的に進めることが望ましいです。具体的なステップとしては以下のようなものがあります。
- 経営参画フェーズ:後継者に少しずつ責任ある立場を任せ、経営者としての経験を積ませる
- 関係構築フェーズ:従業員や取引先、金融機関に後継者を紹介し、信頼関係を構築する
- 権限委譲フェーズ:実務的な決裁権限を徐々に移譲していく
- 株式移転フェーズ:贈与税の暦年課税制度や事業承継税制を活用し、計画的に株式を移転する
- 完全移行フェーズ:代表権を移譲し、経営の全権を委ねる
株式の承継と経営権の承継は必ずしも同時に行う必要はなく、状況に応じて柔軟に進めることが重要です。例えば、経営権は早期に委譲しつつ、株式は段階的に移転するといった方法も考えられます。
税務・法務の専門家に早めに相談する
事業承継には複雑な税務・法務の問題が伴うため、専門家への早期相談が不可欠です。特に以下のような専門家の支援を受けることで、スムーズな事業承継が実現できます。
- 税理士:相続税・贈与税対策、株式評価、事業承継税制の活用
- 弁護士:株主間契約、事業承継契約の作成、法的リスクの洗い出し
- M&A専門家:企業価値評価、買い手探し、条件交渉(M&Aの場合)
- 金融機関:資金調達、財務戦略の立案
- 公的支援機関:「事業承継・引継ぎ支援センター」での無料相談、マッチング支援
これらの専門家と連携しながら、自社に最適な事業承継の方法を選択し、計画的に進めていくことが重要です。また、国や自治体が提供する支援策(事業承継税制、補助金など)も積極的に活用しましょう。
事業承継を成功させる5つのポイント
事業承継は企業の将来を左右する重要なプロセスですが、うまく進めないと様々なトラブルや課題が発生する可能性があります。ここでは、事業承継を円滑に進め、成功させるための5つの重要なポイントを解説します。
早期からの承継準備
早期からの承継準備に必要なアクションステップ:
- 60歳頃までに事業承継計画書を作成する
- 後継者の選定と育成計画を立てる
- 株式や資産の移転方法を検討する
- 取引先や金融機関への説明計画を策定する
- 家族や関係者との話し合いの場を設ける
事業承継の成功の鍵は、早期からの準備にあります。理想的には、経営者が60歳頃には事業承継の準備を始めることが望ましいとされています。早期から準備を始めることで、後継者の育成や経営ノウハウの伝承、株式や資産の移転計画など、様々な課題に余裕を持って対応できます。
特に重要なのは、後継者の育成期間の確保です。経営者として必要な知識やスキル、人脈などを身につけるためには、5〜10年程度の時間が必要だとされています。この期間を通じて、徐々に権限を委譲し、実務経験を積ませることで、スムーズな事業承継が可能になります。
また、早期から準備を始めることで、万が一経営者に突発的な事態が起きた場合でも、事業を継続できる体制を整えることができます。予期せぬ事態に備えるためにも、早め早めの行動が大切です。
株式と資産の承継における税務最適化の実践
税務最適化のための主な対策:
- 事業承継税制(特例措置)の活用
- 種類株式の発行による議決権の確保
- 株式の分散防止と集中対策
- 生前贈与の計画的な実施
- 自社株評価を下げるための純資産圧縮
- 不要資産の処分による株価の適正化
事業承継において、株式や事業用資産の移転は大きな税務負担を伴うことがあります。特に自社株式の評価額が高い場合、相続税や贈与税の負担が大きくなり、資金繰りに影響を与える可能性があります。
この課題に対応するためには、事業承継税制の活用が効果的です。2027年末までの特例措置として、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が大幅に拡充されており、条件を満たせば実質的な税負担をゼロにできる可能性があります。この特例を活用するためには、「特例承継計画」の作成と都道府県への提出が必要です。
また、自社株式の評価を適正化するための対策も重要です。不要な資産の整理や、会社分割などを活用して企業価値を適正に評価してもらうための準備を早期に行うことが求められます。株式の分散防止のための議決権制限株式の活用や、種類株式の発行なども検討価値があります。
承継プロセスにおける専門家の効果的な活用
活用すべき専門家とその役割:
- 税理士:税務対策、株式評価、事業承継税制の活用
- 弁護士:株主間の調整、契約書作成、法的リスク対策
- 中小企業診断士:経営戦略、事業計画の策定
- 金融機関:資金調達、M&Aの助言
- 事業承継、引継ぎ支援センター:総合的な支援と専門家紹介
事業承継には、税務、法務、財務など多岐にわたる専門知識が必要です。これらすべてを経営者自身が把握し対応することは困難であり、専門家の支援を受けることが不可欠となります。
特に、税理士は税務対策や株式評価の面で、弁護士は株主間の調整や契約書の作成などの法務面で、中小企業診断士は経営戦略や事業計画の策定面で、それぞれ専門的なサポートを提供できます。また、金融機関は資金面での支援や、事業承継に関する情報提供などを行ってくれる重要なパートナーとなります。
近年では、各都道府県に設置された「事業承継・引継ぎ支援センター」などの公的支援機関も充実しており、無料相談や専門家の紹介なども行っています。これらの専門家や支援機関をうまく活用することで、事業承継に関する様々な課題を効率的に解決することができます。
ステークホルダーとの関係維持による承継後の事業安定化
ステークホルダー対応のポイント:
- 従業員への丁寧な説明と不安解消
- 主要取引先への早期の後継者紹介
- 金融機関との良好な関係構築
- 地域社会や業界団体への周知
- 株主(特に親族株主)との調整
- 顧客への継続的サービス保証
事業承継後の事業の安定化のためには、従業員、取引先、金融機関などのステークホルダーとの良好な関係維持が不可欠です。経営者が交代することで、これらの関係者が不安を感じ、離反するリスクがあります。
このリスクを軽減するためには、事業承継の計画段階から主要なステークホルダーに対して適切な説明を行い、理解と協力を得ることが重要です。特に従業員に対しては、経営方針の継続性や雇用の安定性について明確なメッセージを伝えることで、不安を払拭し、モチベーションの低下を防ぐことができます。
また、主要取引先や金融機関に対しては、後継者を早めに紹介し、信頼関係の構築を図ることも大切です。後継者が取引先を訪問する際には現経営者が同行するなど、円滑な関係の引継ぎを意識した行動が求められます。これらの取り組みにより、事業承継後も安定した事業運営を継続することができます。
承継後の統合プロセス(PMI)を成功させるポイント
PMI成功のためのアクションプラン:
- 明確な統合計画と責任者の設定
- 100日間の集中的な取り組み
- 企業文化の融合のための施策実施
- 早期のシナジー効果創出
- 業務プロセスの標準化
- 社内コミュニケーションの強化
- 定期的な進捗確認と計画修正
事業承継、特にM&Aによる第三者への承継の場合、承継後の統合プロセス(PMI: Post Merger Integration)の成否が事業承継全体の成功を左右します。PMIとは、承継後に両社の経営方針や業務、企業文化などを統合するプロセスのことです。
PMIを成功させるためには、まず明確な統合計画を策定することが重要です。どの部分をどのように統合するのか、どのようなシナジー効果を狙うのかなど、具体的なアクションプランを作成しましょう。また、統合作業の責任者や実行チームを明確にし、進捗管理を徹底することも欠かせません。
特に重要なのは、企業文化の融合です。異なる企業文化を持つ組織が統合する際には、価値観や行動規範の違いから様々な摩擦が生じることがあります。相互理解と尊重の姿勢を持ち、コミュニケーションを密にすることで、こうした摩擦を最小限に抑え、新たな企業文化を醸成していくことが求められます。
承継後100日間は特に重要な期間とされており、この期間に信頼関係の構築や緊急課題への対応など、優先度の高い取り組みを集中的に行うことが、PMIの成功に繋がります。
まとめ|事業承継の知識を活かして円滑に進めよう
「承継(しょうけい)」の正しい理解から始め、事業承継の基本を学んできました。事業承継では経営権、経営資源、知的財産の3要素を引き継ぎ、親族内承継、親族外承継、M&Aという選択肢から最適な方法を選ぶことが重要です。
成功のカギは早期からの準備にあります。事業承継計画の策定、企業価値の向上、段階的な承継プロセスを実践し、専門家を効果的に活用しましょう。
事業承継は終わりではなく新たな成長の始まりです。地域の支援機関も活用しながら、今すぐ準備を始めることで、大切な会社を確実に次世代へ引き継ぐことができます。 M&Aや事業承継に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。