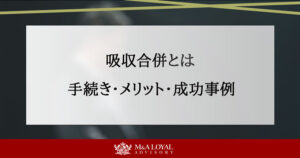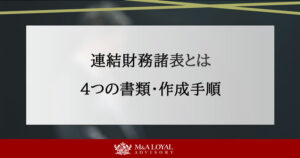抱合せ株式消滅差益とは?生じるケースや会計処理のポイントを紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型

企業の合併や買収などのM&A取引において、「抱合せ株式消滅差益」という会計上の概念が生じることがあります。 この特殊な会計処理は、特に親会社が子会社を吸収合併する際によく発生するものですが、多くの中小企業の経営者にとっては馴染みが薄い概念かもしれません。 本記事では、M&A戦略を成功させるために抱合せ株式消滅差益の基本から実務上のポイントまで、わかりやすく解説していきます。
目次
抱合せ株式消滅差益の基本概念
M&Aの中でも特に合併において重要となる「抱合せ株式消滅差益」について、まずは基本的な概念を押さえておきましょう。この会計上の取り扱いを正確に理解することで、M&A戦略の立案や実行における判断材料となります。
抱合せ株式とは何か、そしてなぜ消滅差益が生じるのか、その仕組みから解説していきます。
抱合せ株式とは
抱合せ株式とは、組織再編(特に合併)において存続会社が保有している消滅会社の株式のことを指します。例えば、親会社が子会社を吸収合併する場合、親会社(存続会社)が保有している子会社(消滅会社)の株式が「抱合せ株式」となります。この株式は、合併によって消滅会社が法的に消滅すると同時に、物理的な価値がなくなるため、会計上も消滅することになります 。
抱合せ株式は合併時に自動的に消滅し、その株式に対する新株等の対価は交付されません。これは、自分自身に対して株式を発行する意味がないためです。
消滅差益が生じる仕組み
抱合せ株式消滅差益は、合併によって引き継いだ純資産の額(親会社持分)と、消滅する抱合せ株式の簿価との差額として計上されます。 具体的には以下の計算式で表されます。
抱合せ株式消滅差益 = 引き継いだ純資産の額(親会社持分) – 抱合せ株式の簿価
この差額がプラスの場合、「抱合せ株式消滅差益」として特別利益に計上され、マイナスの場合は「抱合せ株式消滅差損」として特別損失に計上されます。この会計処理により、実質的には子会社株式の含み益(または含み損)が合併時に顕在化することになります 。
抱合せ株式消滅差益の会計基準における位置づけ
抱合せ株式消滅差益は、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」において規定されています。
この会計処理は、企業結合会計における「パーチェス法」の考え方に基づいており、合併により消滅する会社の資産・負債を時価で評価し直す際に生じる差額を認識するものです。 ただし、共通支配下の取引(同一企業グループ内の組織再編)では、資産・負債は簿価で引き継がれるケースが多いため、その場合の処理とは異なる点に注意が必要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



抱合せ株式消滅差益が生じるケース
抱合せ株式消滅差益は特定の条件下でのみ発生します。 どのようなケースで生じるのか、典型的なパターンを理解しておくことで、M&A戦略の立案時に予測可能となります。
ここでは、実務上よく見られる抱合せ株式消滅差益が生じるケースを具体的に解説していきます。
親会社による子会社の吸収合併
最も典型的なケースは、親会社が子会社を吸収合併する場合です。親会社が保有している子会社株式(抱合せ株式)は合併により消滅し、代わりに子会社の資産・負債を引き継ぎます。 この時、子会社の純資産価値が親会社の保有する子会社株式の簿価を上回っていれば、その差額が抱合せ株式消滅差益として認識されます 。
例えば、親会社Aが子会社Bを100%保有しており、B社株式の簿価が6億円、B社の純資産が10億円である場合、A社がB社を吸収合併すると4億円の抱合せ株式消滅差益が生じます。
兄弟会社間の合併
同一の親会社を持つ兄弟会社間の合併においても、一方の会社が他方の株式を保有している場合に抱合せ株式消滅差益が発生することがあります。例えば、親会社Pの下に子会社A(存続会社)と子会社B(消滅会社)があり、A社がB社の株式を一部保有している場合、その保有株式は合併により消滅します。
この場合、A社がB社から引き継ぐ純資産のうちA社持分と、A社が保有するB社株式の簿価との差額が抱合せ株式消滅差益(または差損)となります。
孫会社の親会社への合併
子会社(中間持株会社)を経由して孫会社を間接的に保有している場合、親会社が孫会社を直接吸収合併するケースも考えられます。この場合、親会社が直接保有している孫会社株式があれば、それが抱合せ株式となります。
ただし、間接保有部分については、抱合せ株式ではなく少数株主持分の買取りとして処理される点に注意が必要です 。
抱合せ株式消滅差益の事業承継・M&Aにおける活用例
抱合せ株式消滅差益は、事業承継やM&A戦略においても重要な役割を果たします。例えば、創業者が複数の会社を保有しており、後継者への承継にあたって企業グループを整理・統合する場合などに活用されます。
また、M&Aで取得した子会社を経営統合する際にも、抱合せ株式消滅差益の発生を踏まえた戦略立案が重要です。 場合によっては、この会計処理を活用することで財務体質の改善や税務メリットを得られることもあります。
| ケース | 特徴 | 抱合せ株式消滅差益発生の条件 |
|---|---|---|
| 親会社→子会社吸収合併 | 最も一般的なケース | 子会社純資産 > 子会社株式簿価 |
| 兄弟会社間の合併 | 一方が他方の株式を保有 | 消滅会社純資産持分 > 保有株式簿価 |
| 孫会社の親会社への合併 | 複雑な株式保有関係 | 直接保有分のみ抱合せ株式に |
| 事業承継目的の統合 | グループ再編の一環 | 事業価値向上で差益発生の可能性大 |
このように、抱合せ株式消滅差益が発生するケースは多岐にわたります。特に中小企業の経営者にとっては、グループ内再編や事業承継の検討時に理解しておくべき重要な概念といえるでしょう。
抱合せ株式消滅差益の会計処理
抱合せ株式消滅差益を適切に会計処理するためには、具体的な仕訳方法や処理手順を理解する必要があります。実務上の混乱を避けるためにも、基本的な会計処理のステップを押さえておきましょう。
ここでは、合併時の基本的な仕訳から具体的な数値例まで、実務に即した形で解説していきます。
抱合せ株式消滅差益が生じる場合の基本的な仕訳パターン
抱合せ株式消滅差益が生じる場合の基本的な仕訳パターンは以下のようになります。合併時には、消滅会社から引き継ぐ資産・負債を計上すると同時に、抱合せ株式を消滅させ、その差額を特別利益として認識します 。
例えば、親会社が子会社を吸収合併する場合、以下のような仕訳になります。
- (借方)資産 XXX / (貸方)負債 XXX
- (借方)抱合せ株式消滅差益 XXX / (貸方)子会社株式 XXX
差額が子会社株式の簿価を下回る場合は、以下のような仕訳になります。
- (借方)資産 XXX / (貸方)負債 XXX
- (借方)子会社株式 XXX / (貸方)抱合せ株式消滅差損 XXX
この仕訳により、消滅会社の資産・負債を引き継ぎつつ、保有していた株式を消滅させることで、純資産の増減を適切に反映させます。
適格合併と非適格合併の違い
合併の会計処理は、税法上の区分である「適格合併」か「非適格合併」かによって大きく異なります。この違いは抱合せ株式消滅差益の処理にも影響します。
適格合併の場合、消滅会社の資産・負債は帳簿価額で引き継がれます。一方、非適格合併では時価評価が必要となり、その評価差額も合わせて認識することになります。
例えば、適格合併の場合は以下の通りです。
- 資産・負債は帳簿価額で引き継ぐ
- 抱合せ株式消滅差益は帳簿価額ベースで計算
- 税務上は資本金等の額の調整として処理
非適格合併の場合は以下の通りです。
- 資産・負債は時価で引き継ぐ
- 抱合せ株式消滅差益は時価ベースで計算
- 税務上も原則として益金に算入
具体的な数値例による解説
抱合せ株式消滅差益の計算と会計処理を具体的な数値例で見てみましょう。
【ケース】親会社P社が100%子会社S社を吸収合併するケース
| 項目 | P社(親会社) | S社(子会社) |
|---|---|---|
| 資産 | 8,000万円 | 3,000万円 |
| 負債 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 純資産 | 5,000万円 | 2,000万円 |
| S社株式簿価 | 1,600万円 | – |
この場合、P社はS社を吸収合併することで、S社の資産および負債を引き継ぎます。具体的には、S社の資産3,000万円と負債1,000万円を合併時に引き継ぎます。
計算の流れ
- S社の純資産の引き継ぎ
- S社の純資産は、資産3,000万円から負債1,000万円を引いた2,000万円です。この純資産がP社に引き継がれます。
- 抱合せ株式消滅差益の計算:
- P社が保有するS社株式の簿価は1,600万円です。この株式が合併により消滅します。
- S社の純資産(2,000万円)からP社が保有する株式の簿価(1,600万円)を引くと、差額400万円が抱合せ株式消滅差益として計上されます。
合併時のP社の仕訳
以下のような仕訳が行われます。
- (借方)資産 3,000万円 / (貸方)負債 1,000万円
- (借方)抱合せ株式消滅差益 400万円 / (貸方)S社株式 1,600万円
合併後のP社の財務状況
合併後のP社の財務状況は以下のようになります。
- 資産: 8,000万円(元の資産) + 3,000万円(S社の資産) = 11,000万円
- 負債: 3,000万円(元の負債) + 1,000万円(S社の負債) = 4,000万円
- 純資産: 11,000万円(資産) – 4,000万円(負債) = 7,000万円
さらに、抱合せ株式消滅差益400万円が特別利益として計上され、P社の当期純利益に影響を与えます。
連結決算における抱合せ株式消滅差益の影響
連結財務諸表を作成している企業グループにおいて、親会社が子会社を吸収合併した場合、抱合せ株式消滅差益は連結上どのように処理されるのでしょうか。
連結決算においては、連結子会社を合併する前から既に連結グループ内の取引として相殺消去されているため、単体決算で計上された抱合せ株式消滅差益は連結決算上で消去されることになります。つまり、連結業績に対する影響はありません。
単体決算で計上される特別利益が連結業績に影響しないという点は、投資家や金融機関への説明時に重要になります。
抱合せ株式消滅差益の税務処理
抱合せ株式消滅差益は会計上の概念ですが、税務上の取り扱いも重要です。適切な税務処理を行わなければ、予期せぬ税負担が生じたり、逆に節税機会を逃したりする可能性があります。
ここでは、抱合せ株式消滅差益の税務上の取り扱いについて、法人税法の観点から解説します。
法人税法上の抱合せ株式消滅差益の取り扱い
抱合せ株式消滅差益の税務上の取り扱いは、合併が「適格合併」に該当するかどうかで大きく異なります。 適格合併の場合、抱合せ株式消滅差益は原則として益金不算入となります。一方、非適格合併の場合は、原則として益金算入の対象となります。
ただし、完全支配関係(100%の株式保有関係)がある法人間の合併については、適格・非適格に関わらず、抱合せ株式消滅差益は資本金等の額の調整として扱われ、益金に算入されません (法人税法施行令9条1項1号)。
つまり、100%子会社の合併においては、会計上は特別利益として計上されても、税務上は課税対象とならないケースが一般的です。
適格合併の要件
税務上の「適格合併」として認められるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 完全支配関係
- 合併法人と被合併法人との間に完全支配関係がある場合(100%グループ内)。
- 支配関係がある場合
- 合併法人が被合併法人の議決権の50%以上を保有している場合で、以下の要件を満たすこと。
- 被合併法人の従業員の概ね80%以上が合併後も業務に従事すること。
- 被合併法人の主要な事業が合併後も引き継がれること。
- 合併法人が被合併法人の議決権の50%以上を保有している場合で、以下の要件を満たすこと。
- 共同事業を営むための合併
- 共同事業を営むための合併で、以下の要件を満たす場合。
- 事業関連性があること。
- 事業規模が概ね5倍を超えないこと。
- 経営参画要件を満たすこと。
- 従業員引継要件・事業継続要件を満たすこと。
- 共同事業を営むための合併で、以下の要件を満たす場合。
これらの要件を満たすことで適格合併として認められ、税務上有利な取り扱いを受けることができます。
税効果会計との関係
抱合せ株式消滅差益が会計上特別利益として計上されるものの、税務上は益金不算入となる場合、両者の間に差異が生じます。この場合、税務上の益金不算入は通常「永久差異」として扱われるため、繰延税金資産は計上されません。
一方、非適格合併の場合には、税務上も益金算入されることがあり、通常の課税所得として法人税等が課されます。
抱合せ株式消滅差益の実務上の留意点
抱合せ株式消滅差益の税務処理における実務上の留意点として、以下のようなポイントが挙げられます。
- 適格合併の要件確認
- 適格合併の要件を満たしているかの事前確認を行うことが重要です。
- 法的書類への明記
- 合併契約書等の法的書類に適格要件を明記し、後のトラブルを回避します。
- 事業継続性の担保
- 合併後の事業継続性を確保できることが、適格合併として認められるためには不可欠です。
- 従業員の処遇文書化
- 従業員の処遇に関する文書化を行い、適切な処遇がなされるようにします。
- 税務申告書の適切な処理
- 税務申告書における適切な処理(別表調整等)を行うことが必要です。
特に、グループ内組織再編においては、計画段階から適格要件を満たすよう注意深く検討し、必要な文書や手続きの準備を整えることが重要です。要件を満たさない場合、予期せぬ税負担が生じる可能性があります。
実務におけるポイントと注意点
抱合せ株式消滅差益に関する理論的な理解に加えて、実務において注意すべきポイントも押さえておく必要があります。特に中小企業の経営者が会社売却や事業承継を検討する際には、細かな実務知識が重要になってきます。
ここでは、抱合せ株式消滅差益に関連する実務上の重要ポイントと注意点を解説します。
合併前の事前準備と検討事項
合併により抱合せ株式消滅差益が生じる可能性がある場合、事前に以下の準備や検討を行うことが重要です。
合併前に子会社の財務状況を精査し、想定される抱合せ株式消滅差益(または差損)の金額を試算しておくことで、合併後の財務インパクトを予測できます。試算には、資産評価や負債引き継ぎの方法など、詳細な要素を考慮する必要があります。特に、大きな消滅差益が見込まれる場合は、決算への影響や株主・金融機関への説明方法を事前に検討しておくべきでしょう。
また、適格合併の要件を満たすための準備として、従業員の処遇や事業継続性についても計画を立てておく必要があります。具体的には、雇用契約や福利厚生の引き継ぎに関する方針を検討することが重要です。合併契約書等の法的書類にも、適格要件を満たすことを明記しておくと良いでしょう。
財務諸表への影響と開示
抱合せ株式消滅差益は特別利益として計上されるため、当期純利益に大きな影響を与える可能性があります。特に、通常の営業活動から生じる利益とは区別して管理・分析する必要があります。
財務諸表の注記においては、抱合せ株式消滅差益の内容や金額について適切に開示することが求められます。特に上場企業の場合、投資家への情報提供という観点からも、合併の概要や抱合せ株式消滅差益の発生理由について明確に説明することが重要です。
非上場の中小企業においても、金融機関や取引先への説明資料として、抱合せ株式消滅差益の性質や一時的な利益であることを明示しておくと良いでしょう。
組織再編戦略への活用方法
抱合せ株式消滅差益の特性を理解することで、組織再編戦略に活かすことができます。例えば、以下のような活用方法が考えられます。
- 赤字子会社の吸収合併による税務上の損失活用
- 複数子会社の段階的統合による経営効率化
- 不採算事業の切り離しと収益事業の統合
- 純資産の改善による財務体質強化
- 事業承継を見据えたグループ構造の単純化
特に中小企業グループにおいては、オーナー経営者の相続対策や事業承継の一環として、複雑な企業構造を単純化する目的で合併を活用するケースも多く見られます。
専門家との連携の重要性
抱合せ株式消滅差益に関連する会計・税務処理は複雑であり、専門的な知識を要します。そのため、以下のような専門家との連携が重要です。
特に、会計と税務の両面から抱合せ株式消滅差益の取り扱いを検討し、最適な組織再編スキームを構築するためには、専門家チームによる総合的なサポートが不可欠です。
また、M&A取引における抱合せ株式消滅差益の取り扱いについては、買収側と売却側で利害が異なる場合もあるため、それぞれの立場に立った専門家のアドバイスを受けることが重要です。
まとめ
抱合せ株式消滅差益は、合併などの組織再編において特有の会計処理であり、特に親会社が子会社を吸収合併する際に発生する重要な概念です。引き継いだ純資産と消滅する株式の簿価の差額として計上され、適切に理解し処理することがM&A戦略成功の鍵となります。
会計上は特別利益として計上される一方、税務上は適格合併の場合に益金不算入となるなど、会計と税務で取り扱いが異なる点に注意が必要です。この差異を理解し活用することで、財務体質の改善や税務メリットを得られる可能性があります。
中小企業の経営者が事業承継やM&Aを検討する際には、抱合せ株式消滅差益の発生可能性を事前に試算し、専門家と連携しながら最適な組織再編スキームを構築することが重要です。適切な準備と実行により、円滑な事業承継や企業価値の向上につなげることができるでしょう。
M&Aや組織再編における抱合せ株式消滅差益の取り扱いについて、さらに詳しい内容や個別のケースに関するご相談は、M&Aの専門家へご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。