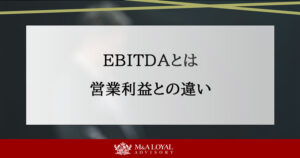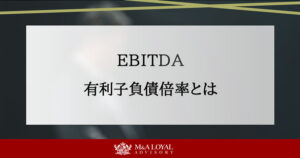EV/EBITDA倍率とは?活用法や適正倍率の見極め方などを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
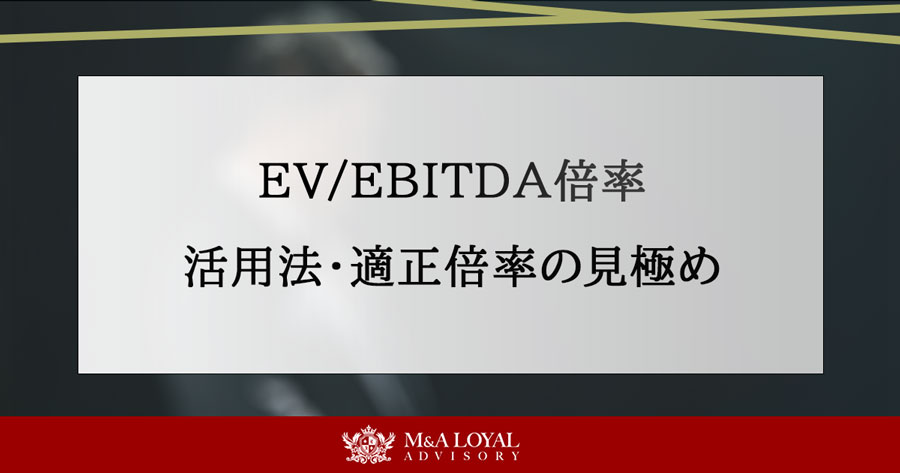
M&Aや企業価値評価において、EV/EBITDA倍率は投資効率を判断するための重要な指標として広く活用されています。EV/EBITDA倍率を理解することで、企業の真の価値を見極め、適切な投資判断を行うことが可能になります。
特に中小企業のM&Aでは、上場企業とは異なる評価基準や業界特性を考慮した分析が求められるため、正確な知識と実践的なスキルが成功の鍵となります。本記事では、EV/EBITDA倍率の基礎知識から業種別の目安、具体的な計算手順、さらにはM&A交渉での活用テクニックまで、実務で即座に役立つ情報を体系的に解説します。
目次
EV/EBITDA倍率とは?基本概念と中小企業での重要性
EV/EBITDA倍率は、M&Aにおいて企業価値を評価し、投資効率を判断するための重要な指標です。特に中小企業のM&Aでは、簡便性と実用性の高さから広く活用されており、売り手・買い手双方にとって投資判断の基準となっています。
この指標を理解することで、M&A取引における適正価格の判断や投資回収期間の見極めが可能になります。本記事では、EV/EBITDA倍率の基本概念から実践的な活用方法まで、中小企業のM&Aに焦点を当てて詳しく解説していきます。
EV/EBITDA倍率が示す投資回収期間の本質
EV/EBITDA倍率とは、企業の事業価値(EV)が、その企業が生み出すキャッシュフローの代理指標であるEBITDAの何倍に当たるかを示す指標です。これは「投資回収期間」を示すものではなく、類似企業と比較して株価が相対的に割安か割高かを判断するために用いられます。
例えば、EV/EBITDA倍率が5倍と算出された場合、これを「5年で投資を回収できる」と解釈するのは重大な誤りです。EBITDAは税金や設備投資などを考慮していないため、投資家が自由に使える現金(フリー・キャッシュフロー)とは異なります。この倍率は、あくまで類似企業の倍率と比較するための「ものさし」として機能します。この数値が低いほど投資効率が良く、短期間での投資回収が期待できる割安な企業として評価されます。
計算式は「EV ÷ EBITDA」で表され、投資家や経営者にとって非常に分かりやすい投資回収期間の目安となるため、M&Aの初期段階における企業選別に頻繁に活用されています。
企業価値(EV)と収益力(EBITDA)の関係性
企業価値(EV)は、株式時価総額に純有利子負債(有利子負債-現預金)を加え、さらにマイノリティ持分(非支配株主持分)を足した値で構成され、M&Aにおける実質的な買収コストを表します。一方、EBITDAは営業利益に減価償却費を加えた値で、企業の本業における収益力を示す指標です。
EBITDAが注目される理由は、税制や会計基準、資本構成の違いによる影響を排除できるためです。これにより、異なる企業間や国際的な比較においても、純粋な事業の収益力を評価することが可能になります。
EV/EBITDA倍率は、この企業価値と収益力の関係を数値化したもので、「高い企業価値に対して十分な収益力があるか」を判断する重要な指標となっています。収益力が高い企業ほど倍率は低くなり、投資効率の良い案件として評価されます。
中小企業M&AでEV/EBITDA倍率が重視される3つの理由
中小企業のM&AでEV/EBITDA倍率が重視される理由は、主に以下の3点にあります。
第一に、計算の簡便性です。中小企業では精緻な企業価値算定に高額なコストをかけることが難しいケースが多く、EV/EBITDA倍率を用いることで比較的簡単に適正価格の目安を把握できます。類似上場企業のデータを活用すれば、専門業者に依頼することなく自社での概算が可能です。
第二に、投資判断の明確性です。「何年で投資回収できるか」という分かりやすい指標により、経営者レベルでの意思決定が容易になります。多くの中小企業買い手は「3年から5年での投資回収」を基準としており、EV/EBITDA倍率3〜5倍以下の案件を投資対象とするケースが一般的です。
第三に、業界標準としての浸透です。M&A仲介会社や金融機関において標準的な評価指標として定着しており、取引の透明性や比較可能性が確保されています。これにより、売り手は自社の市場価値を客観的に把握でき、買い手は複数案件の比較検討が効率的に行えるようになっています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



EV/EBITDA倍率の計算方法|実践的な3ステップ
EV/EBITDA倍率の計算は、正確な企業価値評価の基礎となる重要なプロセスです。計算方法は比較的シンプルですが、各要素の意味を正しく理解し、適切な数値を用いることが成功の鍵となります。
特に中小企業のM&Aでは、上場企業と異なる特殊事情を考慮する必要があります。ここでは、実際のM&A実務で活用できる実践的な3ステップの計算方法を、具体的な計算例とともに詳しく解説していきます。
ステップ1|企業価値(EV)の3要素を算出する
企業価値(EV)の算出は、EV/EBITDA倍率計算の第一歩です。EVは「株式時価総額+純有利子負債」で構成され、M&Aにおける実質的な買収コストを表します。
株式時価総額は「株価×発行済み株式数」で算出されますが、中小企業では株式が非上場のため市場価格が存在しません。この場合、類似上場企業比較法やDCF法などを用いた株式価値算定が必要になります。
純有利子負債は「有利子負債-現預金等」で計算されます。有利子負債には銀行借入、社債、リース債務などが含まれ、現預金等には現金、預金、短期投資などの流動性の高い資産が含まれます。例えば、有利子負債が5,000万円、現預金が2,000万円の場合、純有利子負債は3,000万円となります。
ステップ2|営業利益と減価償却費からEBITDAを計算する
EBITDAは企業の本業における収益力を示す指標で、最も簡便な計算式は「営業利益+減価償却費」です。この計算により、税制や会計基準の違いによる影響を排除し、純粋な事業の収益力を把握できます。
営業利益は損益計算書から直接取得でき、減価償却費は損益計算書の販売費及び一般管理費の内訳、またはキャッシュフロー計算書の営業活動による現金収支から確認できます。のれん償却費がある場合は、これも加算して調整します。
より厳密な計算では「税引前当期純利益+支払利息+減価償却費」という方法もありますが、中小企業のM&Aでは簡便法の「営業利益+減価償却費」が一般的に採用されています。継続性を保つため、同じ計算方法を一貫して使用することが重要です。
特に中小企業の評価では、財務諸表の数値をそのまま使うのではなく、「正常化調整」を行うことが不可欠です。これには、市場水準から乖離した役員報酬の適正化、オーナーの私的な経費の除外、非経常的な損益の調整などが含まれます。この調整によって、事業の持続的な収益力である「正常収益力」を算出し、評価の基礎とします。
ステップ3|非上場企業の株式価値を適正に評価する
中小企業の株式価値算定では、上場企業のような市場価格が存在しないため、専門的な評価手法を用いる必要があります。最も実用的なアプローチは、類似上場企業のEV/EBITDA倍率を活用する方法です。
まず、評価対象企業と同業種・同規模の上場企業を3〜5社選定し、それらの平均EV/EBITDA倍率を算出します。次に、評価対象企業のEBITDAにこの平均倍率を乗じることで企業価値(EV)を求めます。最後に、EVから純有利子負債を差し引くことで株式価値を算定します。
中小企業の評価では、主に2種類の調整が重要です。一つは、企業規模や経営者依存度などのリスクを反映させるための「サイズ・ディスカウント」で、これは類似企業の倍率を調整する際に考慮されます。もう一つは、より重要な「非流動性ディスカウント」です。非上場株式は市場で自由に売買できないため、その換金性の低さを理由に、算出された株式価値から20〜30%程度の割引が適用されるのが一般的です。この調整により、より現実的な株式価値評価が可能になります。
中小企業での計算事例を実践する
具体的な計算例で理解を深めましょう。製造業のB社(資本金1,000万円、従業員50名)のケースを想定します。財務データは以下の通りです。
・営業利益:6,000万円、減価償却費:2,000万円、有利子負債:8,000万円、現預金:3,000万円
まず、EBITDAを計算します。EBITDA = 6,000万円 + 2,000万円 = 8,000万円
次に、純有利子負債を算出します。純有利子負債 = 8,000万円 – 3,000万円 = 5,000万円
類似上場企業のEV/EBITDA倍率が平均6倍の場合、中小企業ディスカウント20%を適用すると、適用倍率は4.8倍になります。
企業価値(EV)= 8,000万円 × 4.8倍 = 3億8,400万円 株式価値 = 3億8,400万円 – 5,000万円 = 3億3,400万円 EV/EBITDA倍率 = 3億8,400万円 ÷ 8,000万円 = 4.8倍
この結果、B社のEV/EBITDA倍率は4.8倍と算出されました。これは、類似上場企業の平均倍率6倍と比較して割安である可能性を示唆しており、価格交渉における一つの基準となります。
EV/EBITDA倍率の業種別目安
EV/EBITDA倍率は業種によって大きく異なるため、同業種内での比較が基本となります。各業種の事業特性や資本構造の違いが倍率に反映されており、適切な投資判断を行うためには業種別の標準的な水準を理解することが重要です。
本章では、中小企業と上場企業の倍率差、主要業種別の標準倍率、さらに成長段階による違いまで、実際のM&A実務で活用できる具体的な目安を詳しく解説していきます。
中小企業はEV/EBITDA倍率が3〜5倍、上場企業は8〜10倍の理由
中小企業と上場企業の間には明確なEV/EBITDA倍率の格差が存在します。上場企業の平均EV/EBITDA倍率が8〜10倍であるのに対し、中小企業では3〜5倍程度が一般的な水準となっています。
この格差が生じる主な理由は、企業規模に伴うリスクの違いです。中小企業は経営者依存度が高く、組織体制や内部統制が脆弱であるケースが多いため、買い手企業はより短期間での投資回収を求める傾向があります。また、財務情報の透明性や将来予測の確実性において上場企業に劣ることも、ディスカウント要因となっています。
一方、上場企業は厳格な開示制度により透明性が高く、経営基盤も安定しているため、投資家はより長期的な視点で投資回収を考えることができます。この結果、同じ収益力を持つ企業であっても、企業規模によって倍率に2〜3倍の開きが生じることになります。
製造業・サービス業・IT業界の標準倍率
業種別のEV/EBITDA倍率は、各業界の事業特性を反映して大きく異なります。2024年の日本上場企業データを基に、主要業種の傾向を見ていきましょう。
製造業系では比較的低い倍率となっており、輸送用機器が5.6倍、鉄鋼が5.7倍、パルプ・紙が6.2倍程度です。これらの業種は大規模な設備投資が必要な資本集約型ビジネスであり、固定資産が多いため倍率が抑制される傾向があります。
サービス業では15.3倍(中央値8.0倍)と高い水準を示しています。これは設備投資が少なく、人的資本中心のビジネスモデルが多いためです。同様にIT業界を含む情報・通信業は17.4倍(中央値8.9倍)と最も高い倍率となっており、無形資産による高収益性が評価されていることがわかります。
中小企業においても同様の傾向があり、製造業では2〜4倍、サービス業では3〜6倍、IT業界では4〜8倍程度が目安となります。ただし、個別企業の競争力や成長性によって大きく変動することに注意が必要です。
成長企業と成熟企業で異なるEV/EBITDA倍率の適正水準
企業の成長段階によってもEV/EBITDA倍率の適正水準は大きく変わります。成長企業と成熟企業では、投資家の期待や評価の観点が根本的に異なるためです。
成長期にある企業では、将来の収益拡大への期待から高い倍率が正当化されます。特にベンチャー企業やスタートアップでは、現在の収益力よりも将来のポテンシャルが重視されるため、10倍を超える倍率で取引されることも珍しくありません。ただし、成長の持続性や収益性の確実性にリスクがあるため、慎重な評価が必要です。
一方、成熟期にある企業では安定した収益力が評価される反面、成長性への期待は限定的になります。このため、8倍を超える倍率は割高と判断されるケースが多く、むしろ配当能力や資産価値が重視される傾向があります。
成長段階別の適正EV/EBITDA倍率の目安は以下の通りです。
・新興・成長企業:高い成長率を背景に10〜15倍程度
・安定・成熟企業:安定収益を評価して6〜8倍程度
・衰退・再生企業:低リスクプレミアムで3〜5倍程度
M&A実務では、対象企業の成長段階を正確に見極め、適切な倍率水準を適用することが成功の鍵となります。
EV/EBITDA倍率を使った企業価値評価の実践方法
EV/EBITDA倍率を活用した企業価値評価は、マルチプル法(類似企業比較法)として知られる実践的な手法です。この方法は計算が比較的簡単で、短期間で企業価値の目安を把握できるため、M&Aの初期段階における価格交渉の基準として広く活用されています。
実際の評価プロセスでは、類似上場企業の選定、倍率の算出、調整要因の考慮という3つのステップを経て、より精度の高い評価結果を導き出すことができます。本章では、実務で即座に活用できる具体的な手法を詳しく解説していきます。
類似上場企業の選定と倍率の適用手順
類似企業の選定は、EV/EBITDA倍率法における最も重要なプロセスです。適切な類似企業を選ぶことで、評価結果の信頼性が大きく向上します。
選定基準として最も重要なのは事業内容の類似性です。同じ業界内でも、BtoBとBtoCでは収益構造が異なるため、できる限り同じビジネスモデルの企業を選定します。次に企業規模を考慮し、売上高が評価対象企業の0.5〜5倍程度の範囲内にある企業を優先的に選択します。
財務特性も重要な判断要素となります。負債比率、収益性、成長率などの財務指標が近い企業を選ぶことで、より適切な倍率を適用できます。最終的に3〜5社程度に絞り込み、各社のEV/EBITDA倍率を算出します。
算出された倍率は単純平均、加重平均、中央値のいずれかで代表値を決定します。市場環境が不安定な場合は中央値を、安定している場合は平均値を採用するのが一般的です。この代表倍率に評価対象企業のEBITDAを乗じることで企業価値(EV)を算出し、純有利子負債を差し引いて株式価値を求めます。
コストアプローチ・インカムアプローチとの併用
EV/EBITDA倍率法は単独で使用するより、他の評価手法と併用することで評価の精度と信頼性を高めることができます。特にコストアプローチとインカムアプローチとの組み合わせは、多角的な視点から企業価値を検証する上で効果的です。
コストアプローチ(修正純資産法)は、企業の保有資産の現在価値に基づく評価手法です。EV/EBITDA倍率法で算出した企業価値と修正純資産額を比較することで、事業価値と資産価値のバランスを確認できます。特に資産集約型の企業では、純資産価値が収益価値を上回るケースがあり、この場合は純資産価値を重視した評価が適切になります。
インカムアプローチ(DCF法)は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り戻して企業価値を算出する手法です。EV/EBITDA倍率法では過去の実績に基づく評価となるため、成長性の高い企業や事業環境の変化が予想される企業では、DCF法による将来価値の検証が重要になります。
実務では、これら3つの手法による評価結果を比較し、最も合理的な価格帯を決定します。評価結果に大きな乖離がある場合は、各手法の前提条件を見直し、より適切な評価モデルを構築することが必要です。
中小企業特有の調整項目と補正方法
中小企業の企業価値評価では、上場企業とは異なる特殊事情を考慮した調整が必要になります。これらの調整を適切に行うことで、より実態に即した評価結果を得ることができます。
流動性ディスカウントは最も重要な調整項目の一つです。非上場株式は市場での売買ができないため、流動性の欠如に対する割引を適用します。一般的に10〜30%程度のディスカウントが適用され、企業規模が小さいほど、また事業の特殊性が高いほどディスカウント率は大きくなります。
マイノリティディスカウント(少数株主割引)も重要な調整要因です。支配権を取得しない少数持分の場合、経営への影響力が限定されるため、10〜20%程度の割引を適用します。逆に、完全支配権を取得する場合はコントロールプレミアムとして10〜20%程度の上乗せを行います。
経営者依存度の調整も中小企業では重要です。創業者や特定の経営者に過度に依存している企業では、その人材リスクを反映した調整を行います。また、関連者取引の正常化、役員報酬の適正化、遊休資産の除外なども、実態に即した評価のために必要な調整項目となります。
EV/EBITDA倍率でM&A価格の妥当性を判断する実践テクニック
M&A交渉において、EV/EBITDA倍率は価格の妥当性を客観的に判断するための重要な指標となります。しかし、単純に倍率を比較するだけでは十分ではなく、買い手と売り手それぞれの立場から戦略的に活用することが成功の鍵となります。
本章では、実際のM&A交渉で活用できる具体的なテクニックを、買い手視点と売り手視点に分けて詳しく解説します。これらの実践的な手法を身につけることで、より有利な条件でのM&A成約を実現することができます。
買い手視点:割安案件を見極める3つのポイント
買い手企業にとって、EV/EBITDA倍率は投資効率を測る重要な指標であり、割安な案件を発見するための有効なツールとなります。効果的な活用には、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
第一のポイントは、業界標準倍率との比較による相対評価です。まず、対象企業と同業種の上場企業平均EV/EBITDA倍率を調査し、基準値を設定します。例えば、製造業であれば5〜7倍、IT業界であれば8〜12倍といった業界相場と比較することで、案件の割安度を客観的に判断できます。特に業界平均より20〜30%低い倍率の案件は、詳細検討に値する有望案件として位置づけられます。
第二のポイントは、自社の投資回収基準との整合性確認です。多くの買い手企業は「EV/EBITDA倍率○倍以下」という独自の投資基準を設定しており、これを超える案件は原則として検討対象外とします。中小企業の買収では3〜5年での投資回収を目指すケースが多いため、EV/EBITDA倍率5倍以下を基準とする企業が一般的です。
第三のポイントは、将来性を加味した動的な評価です。過去の財務数値に基づくEV/EBITDA倍率だけでなく、今後の事業成長性や市場環境の変化を考慮した修正倍率で評価を行います。成長性の高い企業であれば、現在の倍率が高くても将来の収益拡大により実質的な投資回収期間は短縮される可能性があります。
売り手視点:自社の売却可能性と想定価格の把握
売り手企業にとって、EV/EBITDA倍率は自社の市場価値を客観的に把握し、M&A戦略を立案するための重要な指標となります。効果的な活用により、より高い売却価格の実現が可能になります。
自社のEV/EBITDA倍率を算出し、同業他社の倍率と比較することで、市場における自社の位置づけを把握できます。業界平均を上回る倍率であれば売り手市場での交渉が期待でき、下回る場合は企業価値向上施策の実施が必要になります。この分析により、M&A実施時期の判断材料を得ることができます。
売却価格の想定には、複数のシナリオを用意することが重要です。保守的シナリオでは業界平均倍率の80〜90%、標準シナリオでは業界平均倍率、楽観的シナリオでは業界平均倍率の110〜120%を適用し、想定価格レンジを算出します。これにより、交渉時の最低価格と希望価格を明確に設定できます。
企業価値向上のための具体的施策も重要な要素です。EV/EBITDA倍率改善には、収益力の向上(営業利益率の改善)と財務構造の最適化(有利子負債の削減)が効果的です。売却までの期間を活用して、これらの施策を計画的に実行することで、より有利な条件での売却が実現できます。
M&A交渉で活用できる倍率の解釈と説明方法
M&A交渉において、EV/EBITDA倍率を効果的に活用するためには、相手方に対する適切な説明と論理的な根拠の提示が重要になります。数値の客観性を活かした説得力のある交渉が成功の鍵となります。
価格交渉での根拠提示では、複数の類似企業データを用いた比較分析を行い、提示価格の妥当性を論理的に説明します。「同業上場企業3社のEV/EBITDA倍率平均が○倍であり、御社の特性を考慮すると○倍が適正水準」といった具体的な根拠を示すことで、交渉相手の理解と納得を得やすくなります。
調整要因の説明も重要な要素です。中小企業特有のリスク要因(経営者依存度、組織体制、市場地位など)や成長ポテンシャル(新規事業、技術力、顧客基盤など)を定量的に評価し、倍率の上下調整理由を明確に説明します。この際、感情的な議論ではなく、客観的データに基づいた論理的な説明を心がけることが重要です。
交渉の最終段階では、EV/EBITDA倍率以外の評価手法(DCF法、純資産法など)との比較も有効です。複数の評価結果を総合的に検討し、最も合理的な価格水準を相互に確認することで、双方が納得できる合意点を見つけることができます。
主要な調整要因とその目安は以下の通りです。
・リスク要因による調整:経営者依存度が高い場合は10〜20%のディスカウント
・成長要因による調整:独自技術や強固な顧客基盤がある場合は10〜20%のプレミアム
・市場要因による調整:業界の成長性や競争環境を反映した調整
EV/EBITDA倍率の限界と活用時の5つの注意点
EV/EBITDA倍率は非常に有用な指標である一方で、万能ではありません。適切に活用するためには、その限界を正しく理解し、注意すべきポイントを把握しておくことが重要です。
以下の5つの注意点を理解することで、EV/EBITDA倍率の誤用を避け、より精度の高い企業価値評価とM&A判断を行うことができます。
・赤字企業では別の評価手法への切り替えが必要
・将来の成長性は別途DCF法での補完が不可欠
・業界特性に応じた倍率調整の実施
・簡易版EBITDA使用時の保守的評価
・他の評価手法との併用による精度向上
赤字企業では別の評価手法に切り替える
EBITDAがマイナスの企業では、EV/EBITDA倍率による評価は適用できません。営業損失が発生している企業や、減価償却費を加えてもプラスにならない企業では、倍率計算が意味を持たないためです。このような場合は、純資産法やDCF法など他の評価手法を採用する必要があります。
将来の成長性は別途DCF法で補完する
EV/EBITDA倍率は過去の実績に基づく評価のため、将来の成長性を適切に反映できません。特に成長期にある企業や事業転換期の企業では、DCF法による将来価値の検証が不可欠です。両手法を併用することで、より包括的な企業価値評価が可能になります。
業界特性に応じて倍率を調整する
業界によってEV/EBITDA倍率の標準水準は大きく異なります。製造業とIT業界では2倍以上の差があることも珍しくないため、必ず同業種内での比較を行う必要があります。異業種との比較は適切な投資判断を妨げる原因となります。
簡易版EBITDAを使う際は保守的に評価する
中小企業では「営業利益+減価償却費」の簡易計算を用いることが多いですが、厳密なEBITDAとは差異が生じる場合があります。簡易版を使用する際は、やや保守的な評価を心がけ、他の評価手法との比較検証を行うことが重要です。これにより、過大評価のリスクを回避できます。
まとめ|EV/EBITDA倍率を正しく理解してM&A成功へ
EV/EBITDA倍率は、M&Aにおける企業価値評価と投資判断の重要な指標として、中小企業から上場企業まで幅広く活用されています。本記事で解説した内容を踏まえ、適切な理解と活用により、M&A成功の確率を大幅に向上させることができます。
中小企業のM&Aでは、上場企業とは異なる3〜5倍程度の倍率目安を基準とし、業種特性や成長段階を考慮した評価が不可欠です。単純な計算だけでなく、類似企業比較や他の評価手法との併用により、より精度の高い価値算定を実現できます。
買い手・売り手双方にとって、EV/EBITDA倍率の正しい理解と戦略的活用は、交渉を有利に進めるための強力な武器となります。その一方で、限界や注意点を理解し、適切な場面で適切に使用することが、M&A成功への確実な道筋となるでしょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。