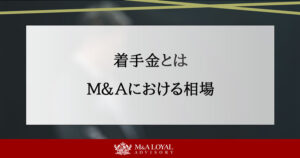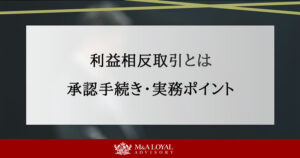M&Aの両手取引とは?仲介手数料は誰が払う?相場とポイント解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
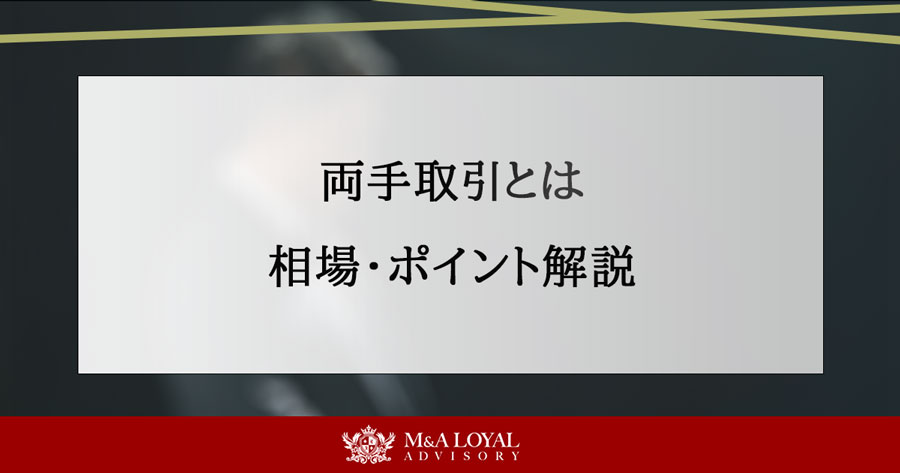
両手取引とは、一つの仲介業者が売り手・買い手の双方をサポートする形態を指します。この取引形態はM&A市場において、一般的な手法ですが、M&A(企業の合併・買収)を検討する中小企業の経営者にとってはあまり馴染みがない言葉かもしれません。
この記事では、両手取引の基本的な仕組み、メリット・デメリット、手数料の相場、片手取引との違いについて、中小企業経営者向けにわかりやすく解説します。
目次
両手取引とは?M&A仲介の基本的な仕組みを理解する
M&Aを検討される多くの中小企業経営者にとって、「両手取引」という言葉は初めて耳にするかもしれません。しかし、この仕組みを理解することは、適切な仲介業者選びと成功するM&A取引の実現に不可欠です。ここでは、両手取引の基本的な概念から、片手取引との違い、そして中小企業で選ばれる理由まで詳しく解説します。
売り手と買い手の間に立つ仲介業者の役割
M&A仲介業者は、売り手企業と買い手企業をマッチングし、取引を円滑に進める専門家です。両手取引では、一つの仲介業者が売り手と買い手の双方と契約を結び、双方の意見や立場を調整しながら取引の成立を目指します。ただし、仲介業者が売り手と買い手双方から報酬を受け取る構造上、利益相反リスクが内在している点も理解しておく必要があります。
仲介業者の主な役割は、企業価値評価の実施、買い手候補の探索と紹介、価格交渉の調整、契約条件の検討支援、そして各種手続きのサポートです。売り手に対しては企業概要書の作成や買い手探しを行い、買い手に対しては売り案件の紹介や相場観のアドバイスを提供します。
両手取引における仲介業者は、双方の利害関係を調整しながら、全体最適を図る調整役として機能します。専門知識と豊富な経験を活かし、複雑なM&Aプロセスを効率的に進めることで、取引の成功確率を高める重要な存在といえるでしょう。
片手取引との違いとそれぞれの特徴
両手取引と片手取引の最も大きな違いは、関与する仲介業者の数と契約形態です。両手取引では一つの仲介業者が売り手と買い手の双方をサポートしますが、片手取引では売り手と買い手がそれぞれ別の業者と契約を結びます。
片手取引では、各仲介業者(ファイナンシャルアドバイザー)が自社のクライアントの利益最大化を目指します。売り手側のアドバイザーはより高い売却価格を追求し、買い手側のアドバイザーは有利な買収条件を求めるため、交渉が複雑化する可能性があります。
ただし、片手取引では双方の立場が明確に分かれているため、利益相反のリスクが低く、クライアントの利益を追求しやすいというメリットもあります。
- 両手取引:一つの業者が双方をサポート
- 片手取引:売り手・買い手がそれぞれ別の業者と契約
- 手数料負担:両手取引は売り手・買い手双方が負担、片手取引は片方が負担
両手取引は情報を一元管理しながら双方を調整するアプローチであり、片手取引は売り手と買い手それぞれの利益を最大化する独立型のアプローチといえます。それぞれの手法には適した場面や企業規模があり、取引内容や条件によって選択することが大切です。
中小企業M&Aで両手取引が選ばれる理由
中小企業のM&Aでは、両手取引が広く採用されています。その理由は、中小企業特有のニーズと両手取引の特性が合致しているからです。
まず、取引の円滑化が期待できる点が挙げられます。片手取引では売り手と買い手がそれぞれ仲介業者に手数料を支払うため、負担が倍増します。両手取引では一つの仲介業者が双方から手数料を得る構造ですが、これが必ずしも総コストの抑制に繋がるとは限りません。
手数料の真のコストは、料率だけでなく、成功報酬の計算基準や最終的な譲渡価格に大きく左右されるため、慎重な検討が必要です。
次に、友好的な取引の実現です。中小企業のM&Aは、売却後も経営陣や従業員が継続して関わることが多く、双方の良好な関係構築が重要です。両手取引では、仲介業者が双方の意見を調整しながら進めるため、対立を避けて円満な取引を実現しやすくなります。
さらに、取引期間の短縮効果もあります。同一の仲介業者が情報を一元管理し、双方との連絡調整を効率的に行うため、片手取引と比較してスピーディーな取引進行が可能です。 ただし、利益相反のリスクや調整の難しさが取引の進行に影響を与える場合もあります。仲介業者のスキルや条件調整の複雑さによっては、片手取引が有利になる場合もある点に留意する必要があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



両手取引の仲介手数料は誰が払うのか
M&A取引において最も気になる点の一つが、仲介手数料の負担者です。特に両手取引では、売り手と買い手の双方が同一の仲介業者と契約を結ぶため、手数料の支払い責任や分担方法について正確な理解が必要です。ここでは、両手取引における手数料負担の仕組みを詳しく解説します。
仲介手数料の支払い責任者は売り手・買い手の両方
両手取引における仲介手数料は、売り手企業と買い手企業の双方が支払い責任を負います。これは、同一の仲介業者が売り手・買い手の両方にサービスを提供し、双方から対価を受け取る仕組みだからです。
売り手側では、企業価値評価や企業概要書の作成、買い手候補の探索といったサービスに対して手数料が発生します。一方、買い手側では、売り案件の紹介や相場感のアドバイス、買収調査のサポートなどに対する対価として手数料を支払います。
この双方負担の仕組みにより、仲介業者は売り手・買い手の両方から報酬を得ることができ、より充実したサービス提供が可能になります。また、双方が手数料を負担することで、取引に対する責任意識が高まり、友好的な関係構築にも寄与します。
手数料の負担割合と交渉の余地
両手取引では、仲介手数料の負担割合について柔軟性がある場合があります。売り手と買い手がそれぞれ仲介業者に対して手数料を支払う仕組みが一般的ですが、契約内容や取引の性質によって手数料の割合や負担方法が異なることもあります。
多くの場合、売り手と買い手は各自が仲介業者と契約を結び、自身が受けるサービスに応じた手数料を負担します。例えば、売り手側は企業価値評価や買い手候補の探索などに対して手数料を支払い、買い手側は売り案件の紹介や買収交渉支援などに対して手数料を支払います。これにより、双方が独立して手数料を負担する形となります。
手数料の料率は一般的に売却額や買収額の5~10%程度が設定されますが、売り手と買い手の負担額が同等である場合もあれば、異なる場合もあります。買い手の負担が高く設定されるケースもありますが、これは契約内容や取引の規模、提供されるサービスの種類に依存します。
また、手数料負担の調整が行われる場合には、企業規模や財務状況、取引の緊急性などの要素が考慮されます。例えば、以下のような調整が行われることがあります。
- 標準的な負担:売り手と買い手がそれぞれ同等の手数料を負担するケース。
- 売り手優遇:売り手が比較的少ない手数料を負担し、買い手側が多くの手数料を負担するケース。
- 買い手優遇:買い手が比較的少ない手数料を負担し、売り手側が多くの手数料を負担するケース。
このような手数料負担の調整が必要な場合、売り手と買い手の双方が合意することが前提となります。また、仲介業者が調整役となり、双方の状況や要望を踏まえて負担割合を設定することもあります。
完全成功報酬型における支払いタイミング
多くの両手取引では、完全成功報酬型の料金体系が採用されています。この場合、M&A取引が正式に成立した時点で仲介手数料の支払い義務が発生します。
支払いタイミングは、最終契約書の締結完了後、通常は30日以内に設定されることが一般的です。仲介会社や契約内容によって即日や15日以内に設定される場合もあります。契約書には支払い期限が明記されるため、事前に確認しておくことが重要です。
着手金や中間報酬が不要な完全成功報酬型では、取引が不成立に終わった場合は手数料負担が発生しないため、売り手・買い手双方にとってリスクを軽減できます。ただし、一部の仲介業者では基本合意締結時に中間報酬として成功報酬の一部(通常10~20%)を請求するケースがあります。これは取引破談リスクへの対応策として設定されるものであり、売り手側に求められる場合もあります。
完全成功報酬型は、売り手・買い手双方にとってリスクを軽減できる魅力的な料金体系ですが、契約内容や手数料体系について事前に仲介業者と十分に確認することが重要です。
両手取引のメリット
M&Aにおける両手取引は、中小企業のM&A市場で広く採用されている取引形態です。その背景には、両手取引特有の複数のメリットがあり、特に初めてM&Aに取り組む企業にとって魅力的な特徴を備えています。ここでは、両手取引の主要なメリットを具体的に解説します。
交渉がスムーズに進みやすい
両手取引では、一つの仲介業者が売り手と買い手の双方をサポートするため、交渉プロセスが非常にスムーズに進行します。仲介業者は双方の意向を熟知しており、両者の落としどころを探りながら建設的な交渉を進めることができます。
従来の片手取引では、売り手側と買い手側がそれぞれ異なるアドバイザーを持つため、両者の交渉が明確に分かれるという特徴があります。各アドバイザーは自社のクライアント(売り手または買い手)の利益最大化を目指すため、条件面での調整が難航し、交渉が長期化したり決裂したりするリスクが生じることがあります。
しかし、片手取引はそれぞれのアドバイザーが独立して動くため、利益相反リスクが低く、クライアントの利益により特化した交渉が可能という利点もあります。
一方、両手取引では、一つの仲介業者が売り手と買い手の双方をサポートするため、情報の共有がスムーズに進みやすく、認識のすり合わせも効率的に行われます。この結果、交渉期間の短縮が期待できることが特徴です。
また、仲介業者は売り手と買い手の意向を熟知し、双方にとって受け入れ可能な条件を模索する調整役を担います。ただし、両手取引では仲介業者が双方から報酬を得る構造上、利益相反リスクが内在しているため、中立性や公平性を保つための仕組みが重要です。
時間と労力を節約できる効率的な取引
両手取引では、売り手・買い手が別々に仲介業者を探す必要がないため、大幅な時間と労力の節約が可能です。特に初めてM&Aに取り組む企業にとって、信頼できる仲介業者の選定は困難で時間のかかる作業です。
同一の仲介業者が取引全体を管理するため、情報の一元化が図られ、重複する作業や無駄な手続きが排除されます。企業概要書の作成、デューデリジェンスの調整、契約書の作成など、各段階での作業効率が向上し、経営者の本業への集中度を高めることができます。
- 情報管理の効率化:一元管理による情報伝達ミスの回避
- 手続きの簡素化:重複作業の排除による時間短縮
- 意思決定の迅速化:中間調整者の存在による合意形成の促進
また、M&A成立後の統合プロセスにおいても、取引経緯を熟知した仲介業者からの継続的なサポートを受けやすく、円滑なPMI(買収後統合)の実現に寄与します。これにより、M&A本来の目的であるシナジー効果の早期実現が期待できます。
両手取引のデメリット
両手取引には多くのメリットがある一方で、構造的な問題に起因するデメリットも存在します。これらのデメリットを理解し、適切な対策を講じることが、両手取引を成功に導く重要な要素となります。特に売り手企業にとっては、これらのリスクを事前に把握しておくことが不可欠です。
利益相反のリスクと対処法
両手取引における最も深刻な問題は利益相反のリスクです。売り手は「できるだけ高く売りたい」と考える一方、買い手は「できるだけ安く買いたい」と考えるため、両者の利益は本質的に対立関係にあります。
仲介業者が双方から手数料を受け取る構造では、どちらか一方に偏った助言を行うインセンティブが生まれる可能性があります。理論上は中立的な立場を保つべきですが、実際には様々な要因によって公平性が損なわれるリスクが存在します。
2020年末に河野太郎行政改革担当大臣(当時)が指摘したように、「仲介者にとってみれば、一回限りのビジネスにしかならない売り手に寄り添うよりも、今後もビジネスができる買い手に寄り添う方が得になる」という構造的問題があります。
対処法として、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」(2024年8月改訂)では、より踏み込んだ対策が求められています。
具体的には、
①手数料の算定基準や相手方から受け取る手数料体系の開示義務
②リピーターである買い手を不当に優遇するなどの利益相反行為の具体的な禁止
③セカンドオピニオン取得を妨げない契約の推奨
などが定められています。
売り手企業は契約前にこれらの点を十分確認することが重要です。
売り手が不利になりやすい構造的問題
両手取引では、売り手企業が構造的に不利な立場に置かれやすい傾向があります。この問題の根本原因は、仲介業者にとってのリピート顧客の可能性にあります。
買い手企業、特に積極的にM&Aを行う企業は、仲介業者にとって継続的な取引相手となり得ます。一方、売り手企業は基本的に一度限りの取引となるため、仲介業者の優先順位が買い手寄りになりがちです。
具体的な問題として、企業価値評価が低めに設定される、買い手に有利な条件での合意を促される、売り手の希望条件が十分検討されないまま交渉が進められるといった事例が報告されています。
- バリュエーション(企業価値算定)の恣意性:売り手に不利な評価手法の採用
- 交渉戦略の偏重:買い手の条件を優先した提案の実施
- 情報格差の悪用:買い手により詳細な情報を提供する傾向
売り手企業はこれらのリスクを回避するため、独自に企業価値評価を実施し、複数の仲介業者から意見を聞くなどの自衛策を講じることが推奨されます。
情報管理における課題と対策
両手取引では、仲介業者が売り手・買い手双方の機密情報を扱うため、情報管理上の課題が生じる可能性があります。特に、一方の企業の戦略や内部情報が、意図せず他方に漏洩するリスクが存在します。
売り手の交渉戦略や価格の最低ラインが買い手に伝わってしまう、買い手の買収予算や条件の上限が売り手に知られる、競合他社への情報漏洩による競争上の不利益などが懸念されます。
仲介業者内部での情報管理体制が不十分な場合、チャイニーズウォール(情報遮断)が機能せず、利益相反がより深刻化する恐れがあります。また、仲介業者が同時に複数の類似案件を扱っている場合、異なる案件間での情報混在リスクも存在します。
対策として、契約時に情報管理に関する詳細な取り決めを行う、機密保持契約(NDA)の内容を厳格に定める、仲介業者の情報管理体制を事前に確認する、重要な戦略情報の開示タイミングを慎重に判断することが重要です。
信頼できる仲介業者を選択し、透明性の高い取引プロセスを維持することで、これらのデメリットを最小限に抑えながら両手取引のメリットを享受することが可能になります。
両手取引で成功するための5つのポイント
両手取引のメリットを最大限に活用し、デメリットを最小限に抑えるためには、事前準備と適切なパートナー選択が不可欠です。特に初めてM&Aに取り組む中小企業経営者にとって、以下の5つのポイントを実践することが成功への鍵となります。
信頼できる仲介業者を見極める
両手取引の成否は、仲介業者の質に大きく左右されます。信頼できる仲介業者を見極めるためには、複数の観点から総合的に判断することが重要です。
まず、実績と専門性を確認しましょう。自社と同規模・同業種でのM&A成約実績があるか、担当アドバイザーの経験年数と成約件数はどの程度かを具体的に質問します。まず必須条件として、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録され、最新の「中小M&Aガイドライン」の遵守を宣言しているかを確認します。これは、公的な補助金(事業承継・引継ぎ補助金)を利用する際の要件にもなっており、信頼性を測る上で不可欠な第一歩です。
次に、中立性の確保体制を確認します。利益相反を防ぐための社内体制、情報管理システム、チャイニーズウォールの運用状況について説明を求めましょう。優良な仲介業者は、これらの質問に対して透明性を持って回答できるはずです。
- 成約実績:同規模・同業種での実績数と詳細事例
- 専門資格:公認会計士、弁護士等の有資格者の在籍状況
- 支援体制:各分野の専門家との連携体制の充実度
また、初回面談での対応姿勢も重要な判断材料です。自社の状況を丁寧にヒアリングし、M&Aの目的や課題を正確に理解しようとする姿勢があるかを確認してください。
手数料体系の透明性を事前に確認する
両手取引では手数料負担の軽減が期待できることもありますが、料金体系が不透明だと予想外のコストが発生するリスクがあります。契約前に、すべての手数料項目を明確にしておくことが必要です。
成功報酬の計算方法、最低報酬額の設定、着手金・中間報酬・リテイナーフィーの有無と金額を詳細に確認します。特にレーマン方式を採用している場合は、成功報酬の計算根拠となる「報酬基準額」の定義を必ず書面で確認することが極めて重要です。基準額の定義は「株式譲渡価格」だけでなく、負債額を加算する「企業価値」や「移動総資産額」など複数あり、どの基準を用いるかによって最終的な支払額が数倍に膨れ上がる可能性があります。
追加費用の発生条件も重要な確認事項です。デューデリジェンス費用、専門家費用、契約書作成費用などが別途発生するのか、それらは成功報酬に含まれるのかを事前に把握しておく必要があります。
手数料の支払いタイミングと条件も確認が必要です。事前に支払いスケジュールを詳細に確認することが強く推奨されます。
複数の仲介業者から見積もりを取得する
適正な手数料水準を把握し、最適なサービスを選択するためには、複数の仲介業者から見積もりを取得することが不可欠です。少なくとも3~5社から提案を受け、比較検討することを推奨します。
見積もり比較では、手数料の総額だけでなく、サービス内容の違いも詳細に検討します。同じ手数料でも、提供されるサービスの範囲や質が異なる場合があるため、費用対効果の観点から判断することが重要です。
各社の強みと特徴を比較し、自社のニーズに最も適した業者を選択します。例えば、迅速な取引を重視するなら実行力のある業者を、慎重な検討を重視するなら分析力の高い業者を選ぶといった具合です。
見積もり取得時には、同一条件での比較が可能になるよう、企業概要や希望条件を統一して提示することが大切です。
契約書の重要条項を必ずチェックする
両手取引では利益相反リスクを回避するため、契約書の内容を特に慎重にチェックする必要があります。標準的な契約書であっても、自社の利益を守るための条項が適切に盛り込まれているかを確認してください。
専任契約と非専任契約の違いを理解し、セカンドオピニオンの取得が可能かどうかを確認します。中小企業庁のガイドラインでは、セカンドオピニオンの取得を妨げない契約とすることが推奨されています。
情報管理に関する条項も重要です。機密情報の取り扱い方法、第三者への情報開示の制限、競合他社への情報漏洩防止策などが明記されているかを確認しましょう。
- 専任条項:他社との並行検討の可否
- 守秘義務:情報管理と漏洩防止の具体的措置
- 解約条項:契約解除時の条件と費用負担
契約解除に関する条項も事前に確認が必要です。どのような場合に契約解除が可能か、解除に伴う費用負担はどうなるかを明確にしておきます。
自社の交渉力を高める準備を行う
両手取引で対等な交渉を行うためには、売り手企業側も十分な準備と知識武装が必要です。仲介業者任せにせず、自社でも主体的に取り組む姿勢が重要です。
企業価値の把握が最も重要な準備です。独自に簡易的な企業価値評価を実施し、市場価値の目安を把握しておきます。複数の評価手法(DCF法、類似企業比較法、純資産法など)を用いて、客観的な企業価値レンジを設定しましょう。
財務・法務・事業面の課題を事前に整理し、対策を講じておくことも大事です。デューデリジェンスで指摘される可能性のある問題点を事前に把握し、改善できるものは改善し、説明が必要なものは適切な資料を準備します。
M&Aの目的と条件を明確にし、譲れない条件と妥協可能な条件を整理しておきます。交渉の場で一貫した姿勢を保つためには、事前の方針策定が不可欠です。
専門知識の習得も重要な準備の一つです。M&Aの基本的な流れ、契約書の重要条項、税務上の取り扱いなど、最低限必要な知識を身につけておくことで、より効果的な交渉が可能になります。
まとめ|両手取引を理解してM&Aを成功に導こう
両手取引は中小企業M&Aにおいて主流の取引形態です。交渉の円滑化や手数料負担の調整がしやすいといったメリットがある一方、利益相反リスクや売り手が不利になりやすい構造的問題も存在します。特に仲介業者がリピート顧客となる買い手企業を優遇する傾向があるため、注意が必要です。
成功のためには、信頼できる仲介業者の選定が最も重要です。実績・専門性・中立性を総合的に判断し、手数料体系の透明性を確認して複数社から見積もりを取得することが欠かせません。また、契約条件の詳細確認とセカンドオピニオンの活用も重要です。
両手取引の特性を正しく理解し、適切な対策を講じることで、満足度の高いM&A取引を実現することが可能です。M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。