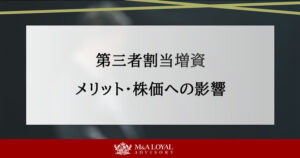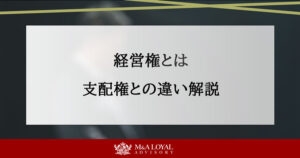株の希薄化(ダイリューション)とは?リスクや計算方法、対策を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
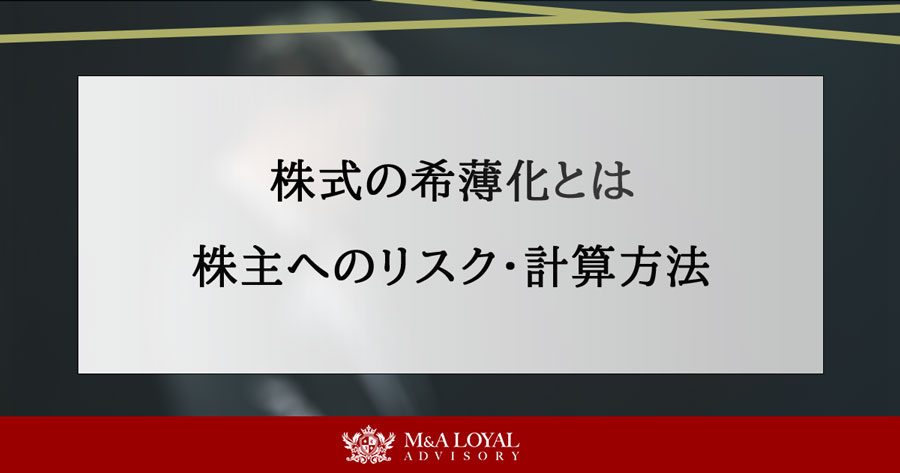
株の希薄化とは、企業が新株を発行することで発行済株式総数が増加し、株主が保有する1株あたりの価値や議決権比率が相対的に低下する現象を指します。これを「ダイリューション」とも言います。中小企業のオーナー経営者にとって、資金調達や事業提携のために第三者割当増資を検討する際、この希薄化がどのような影響をもたらすかを理解することが重要です。
本記事では、株式希薄化の基本的な定義から具体的な計算方法、株主が直面するリスク、そして適切な対策まで、会社売却やM&Aを検討している経営者の視点に立って解説します。
目次
株式の希薄化とは?定義を解説
株式の希薄化を理解するためには、まず発行済株式総数と1株あたりの価値の関係性を把握する必要があります。企業が新株を発行すると、株主が保有する株式の総数に対する相対的な割合が変化します。これが株式の希薄化を起こす基本的なメカニズムです。
株式の希薄化の基本概念
株式の希薄化とは、発行済株式総数が増加し、1株あたりの利益、配当、純資産などの指標が低下する現象を意味します。例えば、総資産1億円の企業で1万株が発行されている場合、1株あたりの純資産価値は1万円となります。しかし、新たに1万株を発行すると、総資産が変わらない限り1株あたりの純資産価値は5千円に低下します。
この現象は株主にとって一見不利益に見えますが、実際には新株発行の目的と調達資金の使途によって評価が変わります。新たに調達した資金を効果的な設備投資やM&Aに活用し、企業価値を向上させることができれば、希薄化が発生しても株主にとってプラスの結果をもたらす可能性があります。
希薄化が発生する主な状況
株式の希薄化が発生する状況はいくつかのパターンに分類できます。最も一般的なのは第三者割当増資ですが、それ以外にも様々な場面で希薄化が起こります。
- 第三者割当増資による新株発行
- 公募増資や株主割当増資の実施
- 新株予約権(ストックオプション)の行使
- 転換社債型新株予約権付社債(CB)の転換
- 合併や株式交換における新株発行
これらの中でも、中小企業のM&Aや事業再編において頻繁に利用されるのが第三者割当増資です。取引先との資本業務提携や、財務基盤強化のための戦略的投資家の受け入れなど、特定の目的を持って実施されるケースが多く見られます。
ポジティブな希薄化とネガティブな希薄化
希薄化には、企業価値向上につながるポジティブな希薄化と、株主の利益を損なうネガティブな希薄化の二つの側面があります。ポジティブな希薄化の典型例は、調達資金を成長投資に充当し、中長期的に企業価値を向上させるケースです。例えば、新工場建設による生産能力拡大や、シナジー効果の高いM&Aの実施などが該当します。
一方、ネガティブな希薄化は、明確な成長戦略がないまま単に資金繰りのために増資を行うケースや、既存株主への説明が不十分なまま不透明な条件で新株を発行するケースです。特に時価を大きく下回る価格での「有利発行」は、株主の利益を損なう可能性があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



第三者割当増資と希薄化の関係
第三者割当増資は、中小企業が資金調達を行う際の有力な選択肢の一つです。しかし、この手法は必然的に株式の希薄化を伴うため、実施にあたっては慎重な検討が必要となります。ここでは第三者割当増資の仕組みと、希薄化が発生するメカニズムを詳しく見ていきます。
基本構造
第三者割当増資とは、株主以外の特定の第三者に対して新株を割り当てる手法です。対象となる第三者には、取引先企業、金融機関、ベンチャーキャピタル、個人投資家など様々なケースがあります。この手法の最大の特徴は、資金調達と同時に戦略的パートナーシップを構築できる点にあります。
公募増資と比較して、第三者割当増資は手続きが比較的簡便で、迅速な資金調達が可能です。また、割当先を選定できるため、単なる資金提供者ではなく、事業面でのシナジーが期待できる相手を選ぶことができます。中小企業のM&Aにおいては、買い手候補企業に対して第三者割当増資を実施し、段階的な資本関係の構築を図るケースも見られます。
発生する具体的なメカニズム
第三者割当増資による希薄化とは、発行済株式総数が増加することで、株主の持株比率と1株あたりの価値が相対的に低下する現象です。例えば、発行済株式数10,000株の企業で、オーナーが7,000株を保有している場合、持株比率は70%です。ここで第三者に3,000株を新規発行すると、発行済株式総数は13,000株となり、オーナーの持株比率は約53.8%に低下します。
この持株比率の変動は、単なる数字の変化以上の意味を持ちます。株主総会における特別決議には3分の2以上の賛成が必要であり、普通決議には過半数の賛成が必要です。持株比率の低下は、これらの意思決定における支配力に直接影響を及ぼします。
有利発行と公正な価格設定
第三者割当増資において特に注意が必要なのが「有利発行」の問題です。有利発行とは、時価を下回る価格で新株を発行することを指します。会社法では、有利発行を行う場合には株主総会の特別決議が必要とされており、株主の利益保護が図られています。
| 発行価格の条件 | 必要な手続き | 株主への影響 |
|---|---|---|
| 時価以上での発行 | 取締役会決議のみ | 希薄化は限定的 |
| 時価より低い発行(有利発行) | 株主総会の特別決議が必要 | 希薄化の影響が大きい |
| 著しく低い価格での発行 | 特別決議+詳細な説明義務 | 株主の利益を損なう可能性 |
非上場の中小企業では客観的な時価の算定が難しいため、株価算定には専門家の評価を活用することが推奨されます。DCF法、純資産法、類似企業比較法など、複数の手法を用いて適正な価格を設定することで、後々のトラブルを回避できます。
株式の希薄化が株主に与えるリスク
株式の希薄化は、株主に対して複数の側面からリスクをもたらします。経済的な損失だけでなく、経営への影響力の低下という重要な問題も含まれます。会社売却やM&Aを検討する際には、これらのリスクを十分に理解しておく必要があります。
1株あたりの利益の減少
株式希薄化の直接的な影響は、EPS(1株あたりの利益)の減少です。EPSは「当期純利益÷発行済株式数」で計算されるため、発行済株式数が増加すると、当期純利益が同じでもEPSは低下します。例えば、当期純利益が5,000万円で発行済株式数が10,000株の企業のEPSは5,000円ですが、新たに2,000株を発行すると、同じ利益でもEPSは約4,167円に減少します。
EPSの低下は株価形成に重要な影響を与えます。株式市場では、PER(株価収益率)という指標がよく用いられますが、これは「株価÷EPS」で計算されます。EPSが低下すると、同じPER水準を維持するためには株価も下落することになります。非上場企業であっても、将来的なIPOやM&Aにおける企業価値評価において、EPSは重要な指標となります。
議決権比率の低下と経営支配力
持株比率の変動は、株主総会における議決権比率に直結します。日本の会社法では、決議の種類によって必要な議決権比率が異なります。普通決議には過半数、特別決議には3分の2以上の賛成が必要とされています。
- 過半数の議決権で可能な事項:取締役の選任・解任、配当の決定など
- 3分の2以上の議決権で可能な事項:定款変更、事業譲渡の承認、合併・分割の承認など
- 3分の1超の議決権で可能な事項:特別決議の否決権
オーナー経営者が第三者割当増資により持株比率を66.7%未満に低下させると、単独で特別決議を成立させることができなくなります。これは経営の自由度に制約をもたらす可能性があります。さらに50%未満になると、他の株主の協力なしには普通決議すら成立させられなくなります。
配当受取額の減少
持株比率の低下は、配当金の受取額にも直接影響します。企業が決定した配当総額は変わらなくても、保有株式数の相対的な減少により、既存株主が受け取る配当金額は減少します。例えば、配当総額1,000万円の企業で70%の株式を保有していた株主は700万円の配当を受け取りますが、希薄化により持株比率が50%に低下すると、受取配当金は500万円に減少します。
特に配当収入を重要な収益源としている投資家や、引退後の生活資金として配当を期待しているオーナー経営者にとって、この影響は無視できません。第三者割当増資を検討する際には、将来の配当計画と合わせて総合的に判断する必要があります。
希薄化率の計算方法とシミュレーション
株式希薄化の影響を正確に把握するためには、希薄化率を計算し、具体的な数値で理解することが重要です。ここでは、希薄化率の算出方法と、実際の企業経営で想定される様々なシナリオでのシミュレーションを示します。
希薄化率の計算式
希薄化率は以下の計算式で求められます。
| 希薄化率=(新規発行株式数÷増資前発行済株式数)×100% |
この計算式により、新株発行が株主の持株比率にどの程度の影響を与えるかを数値化できます。例えば、発行済株式数10,000株の企業が2,000株を新規発行する場合、希薄化率は(2,000÷10,000)×100=20%となります。
計算例とケーススタディ
実際の企業経営では、資金調達額や発行価格によって希薄化の程度が変わるため、複数のシナリオでシミュレーションを行うことが重要です。以下、中小企業のオーナー経営者を想定した具体例を示します。
ケース1:安定成長企業での資本業務提携を想定した増資
| 項目 | 増資前 | 増資後 |
|---|---|---|
| 発行済株式総数 | 10,000株 | 12,000株 |
| オーナー保有株式数 | 7,000株 | 7,000株(変更なし) |
| オーナー持株比率 | 70.0% | 58.3% |
| 新規発行株式数 | – | 2,000株 |
| 希薄化率 | – | 20.0% |
このケースでは、オーナーは依然として過半数の議決権を保持していますが、特別決議を単独で成立させることはできなくなります。資本業務提携先との関係が良好であれば問題ありませんが、将来的な意見対立のリスクも考慮する必要があります。
ケース2:財務再建を目的とした大規模増資
| 項目 | 増資前 | 増資後 |
|---|---|---|
| 発行済株式総数 | 10,000株 | 18,000株 |
| オーナー保有株式数 | 6,000株 | 6,000株(変更なし) |
| オーナー持株比率 | 60.0% | 33.3% |
| 新規発行株式数 | – | 8,000株 |
| 希薄化率 | – | 80.0% |
このケースでは、オーナーの持株比率が3分の1超となり、特別決議の否決権は維持できますが、単独での会社支配は困難になります。財務危機からの脱却という目的があったとしても、経営権の譲渡を伴う重大な決断となります。
持株比率の変化が経営に与える影響
希薄化率の数値だけでなく、その結果として生じる持株比率の変化が、具体的にどのような経営上の意味を持つのかを理解することが重要です。66.7%以上の持株比率を維持できれば、特別決議を単独で成立させることができ、基本的な経営方針を自由に決定できます。50%超であれば、普通決議を単独で成立させることができ、日常的な経営判断において他の株主の同意は不要です。
しかし、33%超の持株比率しかない場合、積極的な経営判断を行うことは難しくなり、他の株主との協調が必須となります。このように、単なる数値の変化ではなく、経営の実質的な自由度がどう変わるかという視点で希薄化を評価する必要があります。
希薄化に関する規制
株式の希薄化、特に上場企業においては、既存株主保護の観点から様々な規制が設けられています。非上場の中小企業であっても、将来的なIPOを視野に入れている場合や、適切なガバナンス体制を構築する上で、これらのルールを理解しておくことは有益です。
25%ルール
東京証券取引所の規則では、希薄化率が25%以上となる第三者割当増資を行う場合、事前に株主総会での承認を得るか、独立した第三者からの意見を取得することが義務付けられています。これは「25%ルール」と呼ばれ、大規模な希薄化が既存株主に与える影響を考慮した規制です。
この規制の趣旨は、経営陣が株主の利益を軽視して安易に大規模増資を実行することを防ぐことにあります。25%という基準は、持株比率への影響が無視できないレベルに達する一つの目安として設定されています。株主総会での承認プロセスを経ることで、増資の必要性や条件について既存株主が判断する機会が確保されます。
第三者意見の取得という選択肢も用意されているのは、迅速な資金調達が必要な場合に株主総会の開催を待つ時間的余裕がないケースを想定したものです。独立した専門家が増資の合理性を評価することで、株主保護と機動的な経営判断のバランスが図られています。
300%ルール
25%ルールよりもさらに厳格なのが「300%ルール」です。希薄化率が300%を超える第三者割当増資は、原則として実施できません。万が一実施した場合、上場廃止となる可能性があります。
- 希薄化率300%超の増資は原則禁止
- 実施する場合は東京証券取引所の承認が必要
- 承認には極めて特殊な事情と合理的な理由が必要
- 無断で実施した場合は上場廃止となる
この規制が設けられた背景には、財務危機に陥った企業が株主の利益を顧みず、極端に安い価格で大量の新株を発行するケースが過去に見られたことがあります。
非上場企業における適用
これらの規制は基本的に上場企業を対象としたものですが、非上場の中小企業であっても、参考とする価値は十分にあります。特に、将来的なIPOを目指している企業や、適切なコーポレートガバナンスを構築したい企業にとっては、これらのルールを自主的に適用することで、株主との信頼関係を構築できます。
非上場企業においても、大規模な第三者割当増資を行う際には、株主への説明と、必要に応じて株主総会での承認を得るプロセスを踏むことが推奨されます。これにより、後々のトラブルを防ぎ、株主との良好な関係を維持することができます。
希薄化リスクを軽減する対策
株式希薄化は避けられない場合でも、適切な対策を講じることでそのリスクを最小限に抑えることが可能です。特に中小企業のオーナー経営者にとっては、経営支配力を維持しながら必要な資金を調達するバランス感覚が求められます。
株主への説明と合意形成
希薄化リスクを軽減する基本的な対策は、株主に対する丁寧で透明性の高い説明です。増資の目的、調達資金の具体的な使途、期待される効果、そして希薄化の程度について、数値を含めた具体的な説明を行うことで、株主の理解と協力を得ることができます。
説明の際には以下の点を明確にすることが重要です。
- なぜこのタイミングで増資が必要なのか
- 調達資金をどのように活用し、どの程度の収益改善が見込めるのか
- 希薄化の程度は具体的にどの程度で、株主への影響はどうか
- 他の資金調達手段と比較して、なぜ第三者割当増資が最適なのか
- 中長期的な企業価値向上のシナリオはどのようなものか
特に重要なのは、増資後の業績見通しを示し、一時的な希薄化が発生しても中長期的には株主価値が向上することを説明することです。例えば、新工場建設による売上増加見込み、M&Aによるシナジー効果の試算、新規事業による収益モデルなど、成長シナリオを提示することで、株主の納得を得ることができます。
資本政策の設計
オーナー経営者が経営支配力を維持するためには、中長期的な視点での資本政策の設計が不可欠です。単発の増資判断ではなく、将来の事業展開や承継計画も視野に入れた包括的な資本戦略を立てることで、不本意な希薄化を避けることができます。
| 持株比率範囲 | 意思決定の内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 66.7%以上 | 特別決議の単独可決が可能 | 経営の自由度が高く、理想的な水準。 |
| 50.0%超~66.7%未満 | 普通決議の単独可決が可能 | 日常経営には問題ないが、大きな変革には他の株主の協力が必要。 |
| 33.4%以上~50.0% | 特別決議の否決権を持つ | 防衛的な立場となるため、積極的な経営は困難。 |
| 33.4%未満 | 実質的な支配力がない | 経営権の確保が困難な状態。 |
増資を計画する際には、増資後の持株比率をシミュレーションし、重要な意思決定に必要な議決権を確保できるかを事前に検証することが重要です。66.7%という特別決議の単独可決ラインを維持することが理想ですが、それが難しい場合でも、少なくとも50%超の持株比率は維持したいところです。
代替的な資金調達手段
第三者割当増資以外の資金調達手段を検討することも、希薄化リスクを軽減する有効な方法です。資金の使途や金額、返済能力などに応じて、最適な調達手段を選択することで、不必要な希薄化を回避できます。
- 金融機関からの借入:希薄化は発生しないが、返済義務と利息負担が生じる
- 社債発行:転換権が付いていない普通社債であれば希薄化は発生しない
- 補助金・助成金の活用:返済不要で希薄化も発生しないが、要件が厳しい
- 資産売却:不要な資産を処分することで希薄化なく資金を確保
- 株主割当増資:株主の持株比率を維持したまま増資が可能
これらの選択肢を総合的に比較検討し、希薄化のリスクと資金調達の迅速性、コストなどを考慮して最適な方法を選択することが重要です。場合によっては、複数の手段を組み合わせることで、希薄化を最小限に抑えながら必要な資金を確保することも可能です。
経営者による追加出資
オーナー経営者自身が増資に参加し、追加で株式を取得することも、持株比率の低下を抑制する有効な方法です。第三者割当増資と並行して、経営者も一定の金額を出資することで、希薄化の影響を部分的に相殺できます。
例えば、第三者に2,000株を割り当てる際、経営者も500株を追加取得すれば、新規発行株式総数は2,500株となりますが、経営者の保有株式も増加するため、持株比率の低下幅を抑えることができます。ただし、この方法は経営者に追加の資金負担を求めるため、個人の資金力との兼ね合いで実行可能性を判断する必要があります。
まとめ
株式の希薄化とは、新株発行により株主の持株比率や1株あたりの価値が相対的に低下する現象です。特に第三者割当増資では、資金調達と同時に持株比率や議決権比率が変動するため、経営支配力への影響を慎重に評価する必要があります。希薄化率の計算方法を理解し、具体的な数値でシミュレーションを行うことで、増資が経営にもたらす影響を正確に把握できます。
希薄化には株主へのリスクが伴いますが、調達資金を効果的に活用して企業価値を向上させることができれば、中長期的には株主利益の増大につながります。重要なのは、増資の目的と資金使途を明確にし、株主に対して透明性の高い説明を行うことです。また、25%ルールや300%ルールといった規制の趣旨を理解し、適切なガバナンス体制を構築することで、株主との信頼関係を維持できます。
会社売却やM&Aを検討する際には、資本政策全体を見据えた戦略的な判断が求められます。希薄化リスクを適切に管理しながら、企業価値を最大化するためには、専門家のアドバイスを活用することも有効です。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継に関するご相談を承っております。経験豊富なアドバイザーが貴社の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーまでお気軽にお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。