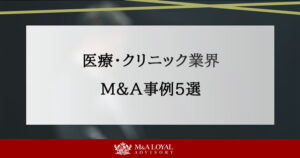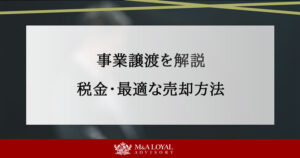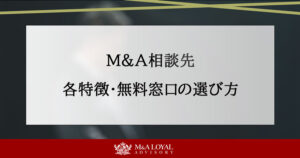クリニック承継・医院継承の方法と手続き、注意点をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
クリニックや医院の事業承継は、新規開業と比べて初期費用の削減や既存の患者や従業員の引き継ぎといった大きなメリットがありますが、一般的な企業の事業承継とは異なる部分もあり、適切な方法を選ばなければ、スタッフや患者離れなどさまざまな問題に直面する可能性もあります。この記事では、クリニック承継・医院継承の方法や手続き、注意点をわかりやすく解説します。
目次
クリニック承継(医院継承)とは
クリニック承継とは、既存のクリニックの運営を新たな医師や経営者に引き継ぐプロセスを指します。クリニックと医院は法律上は違いはなく、どちらも医療法では診療所に位置づけられます。クリニック承継と医院継承には大きな違いはなく、同じ意味で使われることが一般的です。
クリニック承継や医院継承は、その名のとおり、クリニックや医院の事業承継のことであり、クリニックの経営者が引退を考える際や、他者に譲渡したいと考える場合に行われます。クリニック承継は、単なる施設の引き渡しにとどまらず、患者の信頼、スタッフの雇用、地域で築いた評判など、無形の資産を引き継ぐ方法であり、地域医療の継続性や発展に寄与する重要なプロセスです。
承継開業と新規開業の違い
クリニックや医院を始める方法には、「承継開業」と「新規開業」の2つのアプローチがあります。それぞれの特徴について解説します。
承継開業
承継開業とは、既存のクリニックや医院を引き継ぐ形で事業を開始する方法です。承継開業では、既に確立された患者基盤や設備をそのまま活用できるため、開業初期の経営リスクを大幅に軽減することが可能です。また、地域において既に評判があるため、信頼の獲得が容易になることもメリットの一つです。
新規開業
新規開業とは、ゼロからクリニックや医院を立ち上げる方法です。このアプローチでは、自分の理想とするクリニックを一からデザインできる自由度が魅力です。しかし、場所の選定や設備投資、スタッフの採用など、多くの準備が必要であり、開業初期における集客や収益の確保に大きなチャレンジが伴います。また、地域での信頼構築には時間がかかる場合が多く、リスク管理が重要となります。
このように、承継開業が初期投資の削減や安定したスタートを求める場合に向いているのに対し、新規開業は独自性を追求し、柔軟なクリニック運営を目指す場合に適しています。どちらの方法にもそれぞれのメリットと課題があり、開業を考える医師は自身のビジョンやリソースに応じて最適な選択をする必要があります。
個人クリニックと医療法人の違い
クリニックには個人クリニックと医療法人があります。個人クリニックとは、医師個人が経営するクリニックのことを指し、医療法人とは医療法に基づいて設立された法人が運営するクリニックを意味します。
個人クリニック
個人クリニックは、医師個人の裁量で経営方針を決定できる点が特徴です。そのため、迅速な意思決定が可能ですが、資金調達の面では個人の信用力に依存することが多く、限界があります。また、承継に際しては、医師個人が所有しているため、保健所への届出や医療機関コードの変更等の手続きが必要となります。また、親族内承継では贈与税や相続税の発生や親族間のトラブルが懸念されます。
医療法人
医療法人は法人格を有しているため、個人の負担が軽減されるというメリットがあります。資産や負債が法人に帰属するため、経営の安定性が高く、資金調達の選択肢も広がります。しかし、法人としてのガバナンスが求められるため、承継時には法人の規定に基づく手続きが必要となります。特に、役員会や社員総会の決議が必要になることが多く、手続きが煩雑になることがあります。
どちらの形態もそれぞれに特有のメリットとデメリットがありますので、承継を考える際には、クリニックの現状や将来のビジョンを踏まえた選択が求められます。また、法令や税制上の違いも考慮し、適切な手続きと計画を立てることが成功の鍵となります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



クリニック承継(医院継承)のメリット
クリニック承継(医院継承)は、医師や医療従事者にとって多くのメリットをもたらします。代表的なメリットとして次のことが挙げられます。
- 初期費用の削減
- 患者の引き継ぎ
- 従業員の引き継ぎ
それぞれについて解説します。
初期費用の削減
クリニック承継・医院継承の大きなメリットの一つは、初期費用の削減です。新規開業の場合、建物の購入や改装、医療機器の調達、内装の整備など、多額の資金が必要です。既存のクリニックを承継する場合、これらの費用を大幅に削減できます。
既に設備が整っているため、新たに購入する必要がなく、場合によっては設備を更新するだけで十分です。また、医療機器や家具、備品がそのまま利用できるため、開業に必要な時間と手間も軽減されます。
さらに、クリニック承継では、既存の患者基盤や地域での認知度を引き継ぐことができ、早期に安定した運営が見込めます。これにより、資金繰りが楽になり、事業運営に集中できる環境が整います。クリニックの立地や設備条件が既に確立されていることも、初期費用削減に寄与します。新しい場所を探す手間や不動産費用を考慮する必要がなく、承継によりほぼそのままの状態で事業を開始できる点が大きなメリットです。
患者の引き継ぎ
クリニック承継や医院継承では、既存の患者を引き継ぐことができる点も大きなメリットです。新規開業の場合、ゼロから患者を集める必要があり、地域に浸透するまで時間がかかることがあります。しかし、承継により既に地域に根付いた患者基盤をそのまま活用でき、開業後に安定した患者数を確保しやすくなります。
さらに、患者がクリニックに対して信頼を持っている場合、その信頼関係を維持しつつ、新たな診療方針やサービスを提供することで、患者満足度をさらに向上させることも可能です。また、患者のカルテや診療履歴が引き継がれるため、個々の患者の健康状態や過去の治療歴を把握しやすく、より効果的な医療サービスを提供することができます。
患者の引き継ぎは、医療サービスの質を高めるだけでなく、患者とのコミュニケーションを円滑にし、信頼関係を強化する重要な要素となります。さらに、地域における医療ニーズを理解しやすく、地域社会に貢献する形で診療を続けることができるため、地元の患者にとっても安心感を提供できるでしょう。
従業員の引き継ぎ
既存の従業員を引き継げることもクリニックや医院を承継する際のメリットです。従業員の引き継ぎにより、新たにスタッフを採用し、教育する手間と時間を省くことができます。
既存のスタッフは既にクリニックの運営方法、患者のニーズ、地域の特性を理解しているため、日常業務がスムーズに進む可能性が高まります。特に、医療業務では患者との信頼関係が重要です。引き継がれるスタッフがいることで、患者がクリニックの変化に対する不安を感じることなく、安心して通院を続けられるでしょう。
また、従業員が引き継がれることで、突然の人手不足による運営の停滞を防ぎ、安定したサービス提供を維持できます。さらに、既存のチームには長年培ったノウハウや、医療機器の使用、電子カルテの管理方法など、特定の業務に関する知識が豊富であるため、新しいオーナーはその知識を活用しやすくなります。これにより、運営上のトラブルを未然に防ぎ、迅速に経営を軌道に乗せることが可能になります。
クリニック承継(医院継承)の方法
クリニック承継・医院継承の方法として、「親族内承継」「院内承継」「第三者承継(M&A)」の3つがあります。それぞれの特徴について解説します。
親族内承継
親族内承継とは、クリニックを家族内で引き継ぐ方法で、特に同じ医療従事者としての価値観や診療スタイルを共有しやすい点が特徴です。この方法では、クリニックの経営方針や地域に根ざした医療サービスの継続が期待でき、患者や地域社会との関係を維持しやすいというメリットがあります。
しかし、親族内での承継には、後継者の意欲や能力、そして家族間の合意形成が必要です。例えば、後継者が本当に医療職を志望しているか、クリニックの経営に関心があるかを確認することが重要です。また、親族間での財産分与や相続に関する問題も事前にクリアにしておく必要があります。これにより、承継後のトラブルを未然に防ぐことができます。
親族内承継を成功させるためには、早期からの計画と準備が不可欠です。後継者が医療現場での実務経験を積む機会を提供し、経営ノウハウを学ぶ場を設けることで、スムーズな引き継ぎが可能となります。また、税制優遇措置を活用するなど、承継に伴う経済的負担を軽減することも考慮すべきです。
最後に、親族内承継においては、患者やスタッフの信頼を維持するためのコミュニケーションが重要です。患者には、新しい体制でも安心して医療サービスを受けられることを伝え、スタッフには承継に伴う役割の変化について丁寧に説明することで、組織全体の円滑な移行を図ることが求められます。これにより、親族承継の際の潜在的なリスクを低減し、クリニックの長期的な成功を確実にすることができます。
院内承継
院内承継とは、クリニックの運営を現職のスタッフや医師に引き継ぐ方法です。この方法は、既存のスタッフがクリニックの文化や業務プロセスを熟知しているため、比較的スムーズに承継が進むことが期待できます。院内承継の大きなメリットは、患者や地域社会に対して継続性を強くアピールできる点です。既存のスタッフが引き継ぐことで、患者は顔なじみのスタッフがそのまま残る安心感を得ることができます。
しかし、院内承継を成功させるためには、いくつかの課題があります。まず、新たな院長となるスタッフのリーダーシップや経営能力が問われます。医療技術に優れていても、経営の知識やスキルが不足している場合、クリニックの運営がうまくいかない可能性があります。また、スタッフ間での役割や責任の再定義が必要になる場合もあり、これが人間関係の摩擦を生むことも考えられます。
さらに、院内承継の際にはクリニックの将来像を明確にし、新体制での目標やビジョンを共有することが重要です。これにより、スタッフ全員が同じ方向を向いて行動することができ、承継後のクリニックの成長を支える基盤となります。院内承継を検討する場合は、十分な準備期間を設け、計画的に進めることが成功の鍵となるでしょう。
第三者承継(M&A)
M&A(合併・買収)は、クリニックや医院を第三者に承継する方法として近年注目されています。この方法は、親族や院内に適切な後継者がいない場合に特に有効です。M&Aによる承継では、外部の事業者や医療法人がクリニックを買収することで、経営の引き継ぎが行われます。この手法のメリットは、買い手が既に経営資源を持っていることが多く、クリニックの運営をスムーズに引き継ぐことができる点です。
第三者承継では、買い手がクリニックのブランド力や地域での評判を活かしつつ、新たな経営戦略を立てることが可能になることです。これにより、クリニックの成長が期待できるだけでなく、多様な診療科目の導入や最新の医療技術の活用も視野に入れられます。
しかし、第三者承継には注意点も存在します。買い手と売り手の間での交渉が複雑になることがあるため、専門家のサポートが必要です。特に、クリニックの価値評価や法的手続きには慎重さが求められます。加えて、承継後の運営方針の違いから、スタッフや患者の離反が起こるリスクも考慮しなければなりません。
このように、第三者承継(M&A)はクリニックの将来を見据えた選択肢として非常に有効である一方で、その実行には綿密な計画と専門家の助言が不可欠です。適切な準備を行うことで、双方にとって満足のいく承継が実現するでしょう。
個人クリニックと医療法人の譲渡スキーム
クリニックや医院の事業承継のスキームは個人か法人かで異なります。
個人クリニックの場合、通常は事業譲渡が用いられます。事業譲渡とは、クリニックの資産や負債、営業権を新しい経営者に引き継ぐ方法で、法人格ではなく個々の資産や設備、契約を譲渡する形態です。この方法は、個人名義のクリニックをスムーズに承継するために適しています。
一方、医療法人の承継では、出資持分の譲渡と社員の入れ替えが主な方法となります。出資持分譲渡は、法人の出資者(社員)がその持分を新たな出資者に移転することで、法人の支配権を移行します。これにより、法人自体の連続性を保ちながら経営者を交代することが可能です。さらに、社員の入れ替えも重要なステップです。医療法人の運営は、出資者だけでなく、社員の役割や責任が大きいため、新たな経営体制を確立するために必要な措置です。
どちらの方法も、法律や税務上の手続きが複雑であるため、専門家の支援を受けながら進めることが推奨されます。適切な譲渡スキームを選択し、法的手続きをしっかりと行うことで、クリニックの承継を成功させることができるでしょう。
クリニック承継(医院継承)の流れ
クリニック承継や医院継承の手続きの流れを、親族内承継・院内承継・第三者承継(M&A)に分けて説明します。
親族内承継の場合の手続き
親族内承継によるクリニックの承継は、感情的な側面と法的な手続きを丁寧に進めることが重要です。親族内承継の大まかな流れは以下のとおりです。
| 1.診療理念・経営方針の共有 2.経営状況の把握 3.承継後の経営方針を決定 4.承継計画の策定 5.契約の締結 6.クロージング |
まず、承継の意向を確認するための家族会議を開き、後継者の意志やビジョンを共有し合います。その後、具体的な承継計画を立てるために、財務状況やクリニックの運営状況を徹底的に分析します。これには、会計士や税理士といった専門家のサポートが欠かせません。さらに、クリニックの評価を行い、資産や負債の整理を行います。ここでは、後継者が資金面での準備を整えるための計画も必要です。
次に、法的手続きを進めます。個人クリニックの場合は、診療所の名義変更や許認可の更新が必要です。医療法人の場合は、持分の譲渡や役員変更の手続きが含まれることもあるため、より複雑になります。これらの手続きは、法律の専門家と協力しながら進めることが求められます。さらに、承継に伴う税金対策も重要な側面です。贈与税や相続税などの税務上の影響を最小限に抑えるための戦略を練ることが必要です。
最後に、患者やスタッフへの説明と引き継ぎを行います。新しい体制に対する理解と信頼を得るためには、後継者が自らのビジョンをしっかりと伝え、継続性を強調することが重要です。このプロセスを通じて、スムーズな移行を実現し、クリニックの安定的な運営を確保します。親族承継は、家族間の信頼関係を基盤にした承継方法であるため、感情面での配慮も忘れずに行いましょう。
院内承継の場合の手続き
院内承継は、クリニックの院長が自身の医院を内部のスタッフに引き継ぐ方法です。この形態の承継は、クリニックの運営方針や理念を継続しやすく、患者やスタッフにとっても安心感をもたらします。
院内承継の大まかな流れは以下のとおりです。
| 1.経営状況の把握 2.承継計画の策定 3.候補者の選定・教育 4.契約の締結 5.クロージング |
まず、院内承継を成功させるためには、後継者の選定と育成が重要です。現院長が引退を考える数年前から、後継者候補となるスタッフに経営知識や診療技術を伝えることが必要です。
次に、具体的な手続きとして、承継計画の策定が挙げられます。これは、承継のスケジュールや各段階での責任者を明確にする計画です。次に、法的手続きとして、クリニックの名義変更や許可証の取得が必要となることがあります。加えて、医療法人の場合は理事会での承認が必要となることがあります。
また、患者やスタッフに対する情報共有も欠かせません。承継が円滑に進むよう、患者には新体制のビジョンやサービスの継続性を説明し、スタッフには新たな役割や期待される貢献を明示します。このようにして、院内承継のプロセスを透明かつ計画的に進めることで、クリニックの安定した運営を維持することが可能です。
第三者承継の場合の手続き
第三者承継、特にM&Aを通じたクリニック承継は、複雑なプロセスが含まれますが、適切な手続きを踏むことでスムーズに行うことが可能です。M&Aの大まかな流れは以下のとおりです。
| 1.経営状況の把握 2.専門家への相談 3.買い手の選定 4.トップ面談と基本合意契約 5.デューデリジェンスの実施 6.最終契約の締結 7.クロージング |
まず、承継を決定する前にクリニックの現状分析を行い、その価値を評価します。これには財務状況、患者数、地域の競合状況などを詳細に調査し、適正なバリュエーションを行うことが求められます。次に、専門のM&Aアドバイザーを選定し、売却戦略を策定します。この段階で、潜在的な買い手へのマーケティング活動が開始されます。
候補者が見つかると、秘密保持契約(NDA)を締結し、詳細な情報を共有します。その後、買い手候補と具体的な交渉を進め、合意に達した場合には基本合意書を作成します。この基本合意書には、価格や支払い条件、引き継ぎの範囲など重要な事項が含まれます。
次に、買い手によるデューデリジェンスが行われます。これは、クリニックの財務、法律、経営状況を詳細に調査し、リスクや不明点を洗い出すプロセスです。デューデリジェンスが完了すると、最終契約書を作成し、双方の合意の下で調印します。この時点で、必要に応じて法的な手続きや許認可の変更申請を行います。
最後に、承継後の引き継ぎ計画を策定し、クリニックの運営が円滑に進むよう、患者やスタッフへの説明会を実施します。これにより、信頼関係を維持し、新しい体制への移行をスムーズに行うことができます。これらの手続きを経て、第三者承継は完了します。
その他の手続き
クリニック承継において、行政上の手続きは重要なステップです。
行政上の手続き
承継後のクリニックが正式に営業を開始できるよう、保健所での手続きを行う必要があります。これには、施設の変更や新しい管理者の登録が含まれ、現地の保健所への申請が求められます。また、厚生局に対しても必要な書類を提出し、新たな運営体制を報告します。
- 売り手
診療所廃止届:保健所
保険医療機関廃止届:地方厚生局 - 買い手
診療所開設届:保健所
保健所保険医療機関指定申請書:地方厚生局
保険医療機関コードの変更
承継後は、保険医療機関コードの変更も必要です。これは、医療保険制度の下でクリニックが保険診療を継続するために必要な手続きで、迅速に行わなければなりません。承継の際、クリニックのコードを変更することで、患者への保険サービスを継続的に提供することが可能になります。
遡及申請手続き
加えて、遡及申請手続きも考慮すべきです。これは、過去の診療報酬や関連する手続きの見直しを行い、必要に応じて修正を申請する手続きです。遡及申請は、特に引継ぎ時に未解決の事案がある場合に重要で、適切に処理することで、業務の透明性と信頼性を確保できます。
これらの行政上の手続きをスムーズに進めるためには、事前に関係機関に相談し、助言を仰ぐことが推奨されます。これにより、手続きの漏れや不備を防ぎ、スムーズなクリニック承継を実現できます。しっかりと準備を整え、規定に則った手続きを行うことで、新体制の下で安心してクリニック経営を開始することができるでしょう。
クリニック承継(医院継承)の費用と税金
続いて、クリニック承継や医院継承で発生する費用や税金について解説します。
クリニック承継の費用相場
クリニック承継における費用相場は、様々な要因によって大きく変動します。まず、承継するクリニックの規模や立地、設備の状態などが大きく影響します。一般的には、クリニックの評価額はその収益性や地域の医療需要によって異なり、これが費用のベースとなります。
また、承継に際しては不動産の購入や賃貸契約の更新、必要な設備の購入またはメンテナンス、改装費用などが考慮される必要があります。さらに、従業員の引き継ぎに伴う労務管理の費用や、患者情報の引き継ぎに関するシステム更新費用も発生する可能性があります。
費用の目安としては、約2,000万円から6,000万円以上を必要とするケースが多いですが、この範囲よりも安価な場合もあれば高額になる場合もあります。また、医療法人としての承継の場合、法人の資産や負債状況、営業権の評価なども加わり、個人クリニックの承継よりも複雑な評価と費用計算が必要となります。さらに、第三者承継(M&A)の場合には、仲介手数料やデューデリジェンスにかかる費用も考慮しなければなりません。
承継を成功させるためには、事前に詳細な費用見積もりを行い、予算計画を立てることが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な資金調達方法や税制面での最適化を検討することが、スムーズな承継への第一歩となります。費用面の不安を解消し、安心して承継を進めるためにも、包括的な計画と準備が欠かせません。
譲渡益に対する税金
売買によるクリニック承継では、売り手に譲渡益が発生する場合に税金が生じます。譲渡益とは、クリニックの事業資産や設備を譲渡した際に得られる利益のことを指します。特に個人クリニックの場合、譲渡益は総合課税の対象となり、他の所得と合算して課税されます。ただし、土地や建物などの譲渡益は分離課税の対象となる場合があり、適切な計算が必要となります。また、医療法人も持分譲渡の譲渡益は申告分離課税となります。
譲渡益を計算する際には、譲渡価格から取得費用や譲渡にかかる諸経費を差し引いた額が基準となります。このため、譲渡価格だけでなく、クリニックを取得した際の費用や、譲渡に伴う専門家への報酬なども正確に把握しておくことが重要です。特に、医療機器や設備の取得費用は減価償却を考慮する必要があり、専門的な知識を持った税理士の支援を受けることが推奨されます。
また、クリニックの譲渡に際しては、譲渡益のほかにも、事業譲渡に関連する消費税や、固定資産税など、さまざまな税金が関与する可能性があります。これらの税金を事前に考慮し、承継後の資金計画を立てることは、経済的な負担を軽減する上で不可欠です。
相続税・贈与税
親族内でクリニックを引き継ぐ際には、相続税や贈与税が大きな課題となります。
相続税は、被相続人が亡くなった際に遺産を受け継ぐ際に課される税金で、遺産の評価額に基づいて計算されます。クリニックの不動産や設備、顧客リストなどが遺産として評価されるため、その価値が高ければ高いほど、相続税の負担も増加します。
贈与税は、生前に資産を贈与する場合に発生する税金で、相続税と異なり、贈与を受ける側が支払います。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税が非課税となりますが、それ以上の贈与には税金がかかります。これらの税金を最小限に抑えるためには、事前の計画や税務の専門家との相談が不可欠です。
また、贈与税の負担を軽減するための特例制度や控除の活用も考慮する必要があります。例えば、事業承継税制では、一定の条件を満たす場合に相続税や贈与税の支払いを猶予または免除される可能性があります。適切な税務対策を講じることで、クリニック承継の負担を軽減し、後継者が円滑に事業を引き継げる環境を整えることが非常に重要です。
クリニック承継(医院継承)の注意点
クリニック承継や医院継承の注意点についても触れていきます。主なポイントとして以下が挙げられます。
- 後継者選定が難しい
- 旧体制を変更しづらい
- 患者やスタッフ離れの可能性
それぞれについて解説します。
後継者選定が難しい
クリニック承継や医院継承において、適切な後継者を見つけることは容易ではありません。特に、医療機関を承継するためには、医師としての資格が必須であり、これが選定をさらに難しくしています。
後継者を選ぶ際には、医療従事者としての専門的な知識やスキルはもちろん、患者やスタッフとの信頼関係を築ける人物であることが求められます。このため、後継者の候補者が医師免許を有しているかどうかを確認することは必須です。
また、後継者が現在のクリニックの運営方針や医療スタイルを理解し、それを維持または進化させられるかどうかも重要なポイントです。さらに、承継後の経営能力も考慮する必要があります。これには、経営や財務の知識、組織運営の経験が含まれるため、医師としての資格だけでなく、総合的な能力を持つ後継者を選定することが求められます。
後継者が見つからない場合、クリニックの存続が危ぶまれるため、早期に選定プロセスを開始し、候補者の育成や外部からの適任者の探求を進めることが重要です。
旧体制を変更しづらい
クリニック承継や医院継承での注意点として、承継後の旧体制の継続の可能性も挙げられます。事業承継により新しい経営者が就任しても、従来の運営方針や文化が根強く残り、変革が進めにくい状況が生じることがあります。これは、特に長く続くクリニックで、スタッフや患者が現状に慣れ親しんでいる場合に顕著です。
新しい施策や方針を導入しようとする際、旧体制に対する抵抗感や不安が生まれ、円滑な運営を妨げる要因となることがあります。そのため、承継後の初期段階で、旧体制の良い部分を尊重しつつ、新しい体制の必要性をスタッフや患者にしっかりと説明することが重要です。
具体的には、コミュニケーションを密にし、承継に伴う変化に対する理解を深めてもらうための説明会や個別面談を実施することが効果的です。また、旧体制の中で特に評価されていた部分を明確にして、それを維持しつつ新たな施策をどのように組み込んでいくのかを示すことも大切です
患者やスタッフ離れの可能性
クリニックおよび医院の事業承継において、患者やスタッフの離れは避けたい課題の一つです。承継後の新しいクリニックの方針や治療法が以前のものと異なる場合、患者が不安を感じることがあります。このため、承継前から患者に対して方針の変化や新しい院長の紹介を丁寧に行うことが重要です。例えば、事前に説明会を開催し、患者からの質問に答える機会を設けることが効果的です。
一方で、スタッフ離れについては、新しい体制に対する不安や業務内容の変化が原因となることが多いです。これを防ぐためには、従業員に対する十分なコミュニケーションと、可能な限り現状の業務環境を維持する努力が求められます。また、スタッフが新しい体制に適応しやすいよう、研修やサポート体制を整えることも欠かせません。さらに、承継後のビジョンや目標を共有し、スタッフ全員が同じ方向性で働けるようにすることも重要です。
これらの対策を講じることで、患者やスタッフの信頼を獲得し、安定したクリニック運営を続ける基盤を築くことができるでしょう。承継は単なる引き継ぎではなく、新しい体制の構築でもあるため、関係者全員の協力が不可欠です。
クリニック承継(医院継承)を成功させるポイント
クリニック承継を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
計画的な準備
まず、計画的な準備期間を設けることが大切です。承継計画は短期間で完了するものではなく、長期的な視点で準備を進めることで、スムーズな移行が可能となります。そのため、早い段階から後継者の選定や育成に取り組むことが求められます。
透明性のあるコミュニケーション
次に、透明性のあるコミュニケーションが重要です。承継に関わる全てのステークホルダー、特に患者やスタッフに対して、承継の意図やプロセスを明確に伝えることが信頼関係の維持に繋がります。これにより、承継後の運営に対する安心感を醸成し、患者やスタッフの離脱を防ぐことができるでしょう。
経営戦略の見直し
さらに、経営戦略の見直しを行うことも成功の鍵です。承継後のクリニックが持続的に成長するためには、新たな経営者としてのビジョンを明確にし、既存の体制を柔軟に見直す姿勢が求められます。これには、地域の医療ニーズの再評価や、医療技術のアップデートを含むサービスの向上が含まれます。
承継後の体制の整備
また、承継後のサポート体制を整えることも忘れてはなりません。承継後も旧経営者や外部アドバイザーからの支援を受けられる体制を構築しておくことで、問題が発生した際に迅速に対応できる環境を作ることができます。これらのポイントを意識することで、クリニック承継を円滑に成功させることができるでしょう。
専門家のサポート
最後に、法務や税務、M&Aアドバイザーの支援を受けることも重要です。クリニック承継には多くの法的手続きや税務上の配慮が必要となるため、専門家の知見を活用することで、リスクを最小限に抑えた承継が可能となります。
まとめ
クリニックや医院の承継は、単なる経営の引き継ぎにとどまらず、地域医療の継続という重要な役割を担っています。個人クリニックと医療法人の事業承継の違いを理解し、適切な手続きを行うことが求められます。また、承継時には税務や法務、経営面での課題が発生する可能性があるため、専門的な知識を持つアドバイザーのサポートを受けることが成功のポイントです。早期の準備を行い、計画的に進めることで、トラブルを回避しつつ円滑な引き継ぎが可能となるでしょう。
クリニック・医院の事業承継は、地域医療の継続という社会的責任を伴うものです。そのため、早期の準備と計画が欠かせません。クリニック承継を少しでもお考えの方は、M&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。