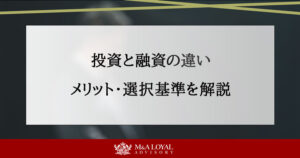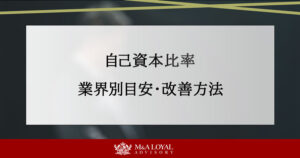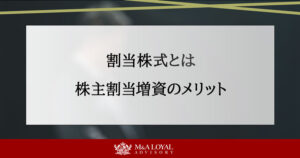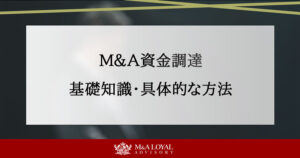増資とは?仕組みやメリット・デメリット、4つの方法を完全解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
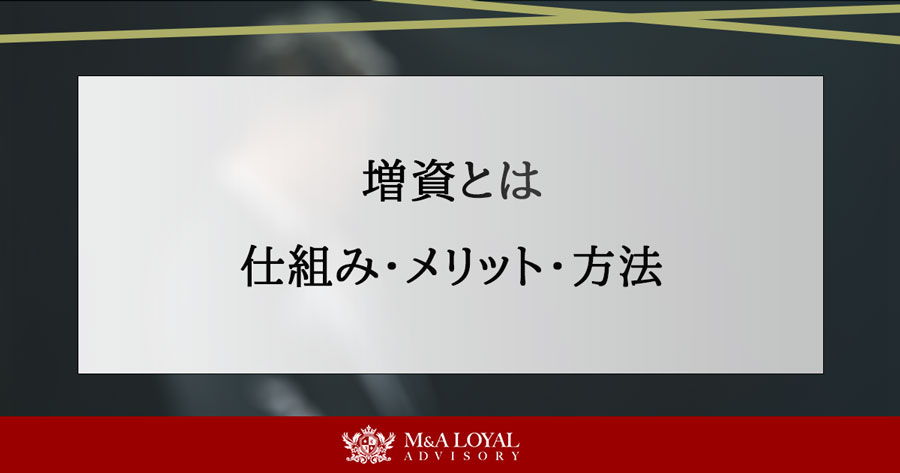
増資とは、企業が新たに株式を発行することによって資金を調達する方法を指します。これは、企業の成長や事業拡大に必要な資金を集めるための一手段であり、返済義務がないため、負債を増やさずに資金を得ることができます。
増資には、第三者割当増資、公募増資、株主割当増資などの方法があります。それぞれの方法には異なる特徴やメリット・デメリットがあり、企業の状況や戦略に応じて最適な手法を選択することが重要です。増資を活用することで、企業は財務基盤を強化し、さらなる成長のための資金を得ることが可能になります。
目次
増資とは何か?
増資とは、会社が資本金の額を増加させる行為のことです。企業経営において重要な資金調達手段の一つであり、事業拡大や財務体質の強化を目指す際に活用されます。中小企業にとっても、成長戦略を実現するための重要な選択肢として位置づけられています。
増資の定義と資本金を増やす基本的な仕組み
増資とは、文字通り「資本を増やす」ことを意味し、会社の資本金額を増加させる手続きを指します。最も一般的な増資の方法は、会社が新たに株式を発行し、その株式と引き換えに株主や投資家から出資を受ける「有償増資」です。新株発行により払い込まれた資金のうち、会社法第445条の規定に基づき、その2分の1を超えない額を資本準備金として計上することが認められており、残額を資本金として計上します。
また、株式を新たに発行せずに増資を行う方法も存在します。これは「利益の資本組み入れ」や「準備金の資本組み入れ」と呼ばれる手法で、会社がこれまでに蓄積した利益剰余金や資本準備金などを資本金に振り替えることで実現します。
この方法は「無償増資」とも呼ばれ、外部からの新たな出資を受けることなく資本金を増やせる特徴があります。
増資が融資と根本的に異なる3つのポイント
増資と融資は、いずれも企業に資金をもたらす手段ですが、根本的に異なる性質を持っています。
- 返済義務の有無:融資は定められた期限内での返済義務があり、利息も支払う必要がある
- 貸借対照表での取扱い:融資は負債として計上され、増資は資本(純資産)として計上される
- 経営への関与:融資では貸し手の経営参加は基本的にないが、増資では新株主が経営に関与する権利を得る
この違いにより、増資は会社の財務基盤を根本的に強化する効果があります。負債として計上される融資とは異なり、増資による資金は自己資本となるため、財務安全性の向上につながります。ただし、新たな株主を迎え入れることで、経営の自由度に影響を与える可能性がある点も理解しておく必要があります。
中小企業における増資の位置づけと重要性
中小企業にとって増資は、事業成長を実現するための重要な資金調達手段です。特に、金融機関からの融資が困難な場合や、借入額の上限に達している企業にとって、増資は貴重な選択肢となります。
中小企業が増資を検討する主な場面として、設備投資による事業拡大、新規事業への参入、M&Aの実行などが挙げられます。これらの投資は将来の成長につながる一方で、相応の資金が必要となるため、返済義務のない増資による資金調達が有効です。
また、増資により資本金が増加することで、取引先や金融機関からの信用度向上も期待できます。中小企業では信用力の不足が事業拡大の障害となることも多く、増資による信用力向上は事業機会の拡大にもつながります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



増資とはどんな時に必要?検討すべき4つのタイミング
増資は単なる資金調達手段ではありません。事業成長や経営基盤強化の重要な戦略として活用すべきものです。中小企業の経営者が増資を検討すべき具体的なタイミングは4つに大別されます。それぞれの場面で増資がもたらす効果を理解し、最適な実行時期を見極めることが成功の鍵となります。
事業拡大による設備投資や運転資金が必要な時
事業が順調に成長し、さらなる拡大を目指す段階では多額の資金投下が必要となります。製造業では新しい生産設備の導入、IT企業ではシステム開発、サービス業では店舗展開など、業種を問わず初期投資が発生します。このような場面で増資による資金調達が有効です。
融資と異なり返済負担がないため、長期的な視点で事業展開を行えます。また、設備投資により生まれる将来のキャッシュフローを返済に充てる必要がないため、さらなる成長投資に資金を回せる利点があります。
M&Aで企業買収を実行する資金が必要な時
M&Aによる事業拡大は、中小企業にとって短期間で市場シェアや技術力を獲得できる有効な成長戦略です。しかし、買収には多額の資金が必要であり、全額を融資で賄うことは現実的ではありません。
増資による資金調達であれば、買収後の統合プロセスにおいても財務負担を軽減できます。さらに、戦略的投資家からの出資を受ける場合は、資金だけでなく事業シナジーも期待でき、買収効果を最大化できます。M&A実行時の増資は、単なる資金調達を超えた戦略的意義を持っているのです。
金融機関からの信用力を高めたい時
中小企業にとって金融機関との良好な関係構築は経営の生命線です。増資により資本金が増加すると、貸借対照表上で自己資本比率が向上し、財務安全性の高い企業として評価されます。この結果、融資の際の条件改善や与信限度額の拡大が期待できます。
また、新規取引先との商談においても、資本金の規模は信用判断の重要な指標となります。特に大手企業との取引を目指す場合、一定水準以上の資本金が取引開始の条件となることも少なくありません。
財務体質を強化して経営を安定させたい時
事業環境の変化や競争激化により、企業には強固な財務基盤が求められています。増資による自己資本の充実は、不測の事態に対する抵抗力を高めます。特に、景気変動の影響を受けやすい業種や、研究開発に長期間を要する企業では、十分な自己資本が経営安定の基盤となります。
また、利益剰余金の資本組み入れによる増資であれば、外部からの資金調達を行わずに財務体質を改善できるため、経営権への影響を最小限に抑えながら財務基盤を強化できます。
増資とはどう実行する?4つの方法と特徴
増資を実行する方法は大きく4つに分類されます。それぞれ適用場面や効果が異なるため、企業の状況や目的に応じて最適な手法を選択することが重要です。中小企業では特に、第三者割当増資と株主割当増資が主流となっており、利益の資本組み入れも財務戦略として活用されています。各方法の仕組みと特徴を詳しく解説します。
第三者割当増資で特定の投資家から資金調達する方法
第三者割当増資とは、会社が特定の第三者に対して新株を引き受ける権利を与え、その対価として出資を受ける方法です。中小企業で広く活用される増資手法の一つです。出資者として、ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家、事業パートナー、取引先企業などが挙げられます。
- 迅速な手続きが可能: 総数引受契約を結ぶ場合、株式の申込みや割当てといった法的手続きを省略でき、プロセスの迅速化が可能。ただし、これは投資家との交渉が全て完了した後の最終的な法手続きにかかる時間であり、実際には投資家の探索から契約締結まで数週間から数ヶ月を要するのが一般的。
- 事業シナジーの創出: 戦略的投資家からの経営ノウハウや人脈活用。
- 柔軟な条件設定: 出資者との直接交渉により条件を決定。
この方法の最大の利点は、単なる資金調達を超えた戦略的パートナーシップの構築が可能な点です。ただし、新たな株主を迎え入れることで既存株主の持株比率が希薄化する点には注意が必要です。
株主割当増資で既存株主の持分を維持する方法
株主割当増資とは、既存株主全員に対して、その持株比率に応じて新株を引き受ける権利を付与する方法です。株主構成を変えることなく資金調達ができる特徴があります。家族経営の中小企業や、既存株主間の関係を維持したい場合に適しています。
この方法では、各株主の持株比率が変わらないため、経営権への影響を回避できます。また、既存株主は会社の事業内容を熟知しているため、出資に対する理解を得やすい利点があります。ただし、特定の株主のみからの資金調達はできないため、大口出資者を求める場合には不向きです。株主全員が新株を引き受ける資金的余裕があることが前提条件となります。
利益の資本組み入れで無償増資を行う方法
利益の資本組み入れとは、会社が蓄積した利益剰余金を資本金に振り替える無償増資の手法です。外部からの資金調達を伴わないため、既存の株主構成に影響を与えることなく資本金を増加できます。財務体質の強化や対外的な信用力向上を目的とする場合に有効です。
- 株主構成への影響なし: 新株発行を伴わないため希薄化が発生しない。
- 手続きの簡便性: 原則として株主総会の普通決議のみで実行可能。ただし、資本組み入れの対象とできるのは、定時株主総会で承認された確定済の貸借対照表に計上されている剰余金に限られる。
- 資金流出なし: 会社の現金を減らすことなく資本金を増加。
ただし、この方法を活用するには十分な利益剰余金の蓄積が必要です。また、将来的な配当原資が減少する点も考慮する必要があります。
公募増資の仕組みと中小企業での活用可能性
公募増資とは、不特定多数の投資家に対して広く新株の引き受けを募る方法です。主に上場企業で活用される手法であり、証券取引所を通じて株式を公開している企業のみが実行できます。大規模な資金調達が可能で、株式の流動性向上にも寄与します。
中小企業が公募増資を活用するには、まず株式を上場する必要があります。IPO(新規株式公開)を経て上場企業となった後に、公募増資による資金調達が可能となります。上場準備には数年間を要し、相当な費用と労力が必要ですが、成功すれば大規模な資金調達と知名度向上が期待できます。現状では中小企業にとって現実的な選択肢とは言えませんが、将来的な成長戦略として検討する価値があります。
増資のメリット
増資は中小企業の成長戦略において多様なメリットをもたらします。単なる資金調達を超えて、企業の競争力向上や事業機会の拡大につながる重要な経営手段です。ここでは、中小企業が増資により得られる5つの主要なメリットを詳しく解説します。これらの効果を理解することで、増資の戦略的価値を最大限に活用できます。
返済不要の資金調達で資金繰りが改善する
増資による資金調達の最大の特徴は、返済義務がないことです。融資では定期的な元本返済と利息支払いが必要ですが、増資で調達した資金に返済期限はありません。これにより、企業は長期的な視点で事業戦略を立てることができ、月々の返済負担に縛られることなく積極的な投資を行えます。
特に設備投資や研究開発など、投資回収に時間を要する事業では、この特性が大きな利点となります。資金繰りの安定により、経営者は事業運営に専念でき、持続的な成長基盤を構築できます。
自己資本比率が向上し財務体質が強化される
増資により資本金が増加すると、貸借対照表上で自己資本が増加し、自己資本比率が向上します。自己資本比率は企業の財務安全性を示す重要な指標であり、一般的に30%以上が健全とされています。比率の向上により、景気変動や業績悪化時の耐性が高まり、事業継続性が強化されます。
- 融資審査での優遇:金融機関からの評価向上により有利な条件での借入れが可能
- 信用格付けの改善:取引先からの信頼度向上により事業機会が拡大
- 財務リスクの軽減:負債依存度の低下により金利変動リスクを軽減
この財務体質の改善は、企業の信用力向上に直結し、様々な事業機会の創出につながります。
取引先や金融機関からの信用力が高まる
資本金の増加は、企業の資金力と安定性を示す重要なシグナルとなります。多くの企業が新規取引先の選定時に資本金規模を判断材料の一つとしており、一定水準以上の資本金が取引条件となることも珍しくありません。特に大手企業との取引において、この効果は顕著に現れます。
金融機関においても、資本金の規模は融資審査の重要な評価項目です。増資により信用力が向上することで、融資限度額の拡大や金利優遇、保証条件の改善などが期待できます。これにより、必要な時により良い条件で資金調達を行えるようになり、事業展開の選択肢が大幅に広がります。
事業パートナーとの強固なネットワークが構築できる
第三者割当増資により新たな株主を迎え入れることで、貴重な事業ネットワークを構築できます。株主は企業の成功に直接的な利害関係を持つため、積極的に事業支援を行う傾向があります。ベンチャーキャピタルからは経営ノウハウの提供、事業会社からは販路開拓支援、エンジェル投資家からは人脈紹介など、資金以外の価値も期待できます。
これらの支援により、自社だけでは実現困難な事業展開が可能となります。新規顧客の開拓、技術提携の実現、優秀な人材の確保など、多方面での成長加速が期待できるのです。
M&A実施時の資金調達手段として活用できる
M&Aによる企業買収は、事業拡大の有効な手段ですが、多額の資金が必要です。増資による資金調達は、買収資金の確保に適しています。融資と異なり返済負担がないため、買収後の統合作業に集中できます。また、戦略的投資家からの出資を受ければ、買収に関するノウハウや人脈も活用でき、M&Aの成功確率を高められます。特に同業他社からの出資では、統合によるシナジー効果も期待でき、買収価値を最大化できる可能性があります。
増資のデメリット
増資には多くのメリットがある一方で、経営者が十分に理解しておくべきデメリットも存在します。これらのリスクを軽視すると、期待した効果を得られないばかりか、企業運営に深刻な影響を与える可能性があります。中小企業の経営者が増資を検討する際に注意すべき4つの主要なデメリットを詳しく解説します。
創業者の持株比率が希薄化し経営権に影響する
増資における最大のリスクは、創業者の持株比率希薄化による経営権への影響です。新株発行により発行済株式総数が増加するため、創業者の持株比率は必然的に低下します。例えば、発行済株式1,000株のうち600株を保有していた創業者(持株比率60%)が、200株の第三者割当増資を実施すると、持株比率は50%に低下し、過半数を割り込んでしまいます。
持株比率が特定の閾値を下回るごとに、経営権は段階的に制限されます。特に重要なのは以下の3つのラインです。
- 3分の2(約66.7%)超:定款変更や合併、事業の重要な譲渡といった会社の根幹に関わる事項を単独で決定できる特別決議の単独可決権を維持できます。
- 2分の1(50%)超:取締役の選任・解任や役員報酬の決定など、基本的な経営判断を行う普通決議の単独可決権を維持できます。
- 3分の1(約33.4%)超:他の株主が全て賛成しても、会社の合併や定款変更といった重要な特別決議を単独で阻止できる拒否権を維持できます。経営権を維持するには、これらの議決権割合が持つ具体的な意味を理解し、資本政策を慎重に計画することが極めて重要です。
この希薄化を「希薄化率」として数値化すると、新規発行株式数÷増資前発行済株式数×100で算出できます。経営権を維持するには、事前に希薄化率を慎重に計算し、適切な増資規模を設定することが重要です。
資本金1000万円超で税負担が増加する
増資により資本金が1,000万円を超えると、税制上の優遇措置を失い、税負担が大幅に増加します。
最も影響が大きいのは消費税の取扱いです。資本金1,000万円未満の企業は、設立1期目は原則として消費税の納税が免除されます。しかし、設立2期目も免除されるためには、1期目の開始日から6ヶ月間(特定期間)の課税売上高、または給与等支払額の合計が1,000万円を超えていないことが条件となります。
資本金が1,000万円以上の場合は、設立1期目から課税事業者となります。 また、法人住民税の均等割額も資本金額に応じて段階的に増加します。東京23区の場合、資本金1,000万円以下では年額7万円ですが、1,000万円超では18万円となり、約2.6倍の負担となります。
さらに、資本金が1億円を超えると外形標準課税の対象となり、赤字でも法人事業税が課されます。注意すべきは、令和6年度(2024年度)税制改正により、このルールが大幅に見直された点です。この改正により、資本金が1億円以下であっても、以下のいずれかに該当する法人は新たに外形標準課税の対象となります。
1.前年度に資本金1億円超であった法人が減資した場合で、かつ「資本金と資本剰余金の合計額」が10億円を超える場合(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)。
2.「資本金と資本剰余金の合計額」が50億円を超える大企業の100%子会社等で、かつ、その子会社自身の「資本金と資本剰余金の合計額」が2億円を超える場合(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)。
この改正は、形式的な減資による租税回避を防ぐためのものであり、増資やM&Aを検討する上で必ず把握しておくべき重要な変更点です。
これらの税負担増加は、特に利益率の低い中小企業にとって経営を圧迫する要因となる可能性があります。
登記変更など手続きに費用と時間がかかる
増資実施には法務手続きが必須であり、相応の費用と時間を要します。最も大きな費用は登録免許税で、増資額の0.7%または3万円のいずれか高い方を支払う必要があります。例えば、1,000万円の増資では7万円、5,000万円では35万円の登録免許税が発生します。
手続きを司法書士に依頼する場合は、追加で報酬を支払う必要があります。一般的な司法書士報酬は5万円以上で、増資額や手続きの複雑さに応じて変動します。また、登記変更手続きは払込完了から2週間以内に実施しなければならず、期限を過ぎると過料の制裁を受ける可能性があります。
増資後は税務署、都道府県税事務所、市区町村への異動届出も必要で、これらの手続きに要する時間と労力も考慮する必要があります。
株主が増えることで意思決定が複雑化する
第三者割当増資により新たな株主を迎え入れることで、意思決定プロセスが複雑化する可能性があります。株主には会社法により様々な権利が保障されており、株主総会での議決権行使、帳簿閲覧権、利益配当請求権などを有します。株主数の増加により、これらの権利行使に対応するための管理負担が増大します。
特に問題となるのは、企業方針に対する意見対立です。成長重視の創業者と安定重視の投資家株主では、事業展開方針や配当政策について異なる意見を持つことがあります。また、株主間での利害対立が生じた場合、意思決定に時間を要し、機動的な経営が困難になる可能性があります。さらに、一度株主となった投資家を排除することは極めて困難であり、長期的な関係性を前提とした慎重な株主選定が必要です。
増資の手続きと費用|実務担当者が知るべき重要事項
増資の実施には法定手続きの遵守が必要であり、適切な準備と正確な理解が成功の鍵となります。手続きミスや期限遅れは法的ペナルティを招く可能性があるため、実務担当者は詳細な知識を身につける必要があります。ここでは、増資にかかる費用、法的期限、必要な届出について、実務で直面する重要事項を解説します。
増資にかかる具体的な費用と計算方法
増資の実施には主に登録免許税と専門家報酬の2つの費用が発生します。登録免許税は法定費用で、「増資額の0.7%」または「3万円」のいずれか高い方が適用されます。具体的な計算例として、増資額500万円の場合は3.5万円(500万円×0.7%)となり、3万円の最低額を上回るため3.5万円の納税が必要です。
- 1,000万円増資:7万円(1,000万円×0.7%)
- 3,000万円増資:21万円(3,000万円×0.7%)
- 5,000万円増資:35万円(5,000万円×0.7%)
司法書士への報酬は事務所により異なりますが、一般的に5万円から15万円程度です。増資額が大きくなるほど手続きが複雑になるため、報酬額も増加する傾向があります。その他、登記事項証明書の取得費用、事前閲覧費用なども必要となり、総額では増資額に応じて10万円から50万円程度の費用を見込んでおく必要があります。
登記変更の期限と守らなかった場合のペナルティ
会社法第915条第1項により、資本金の変更が生じた場合は2週間以内に登記変更手続きを完了しなければなりません。この期限は「出資金の払込完了日」を起算日として計算され、土日祝日も含めて厳格に適用されます。例えば、4月15日に払込が完了した場合、4月29日までに登記申請を法務局に提出する必要があります。
期限を遵守しなかった場合、会社法第976条に基づき、会社ではなく代表者個人に対して100万円以下の過料が科される可能性があります。この過料は代表者個人の責任であり、会社の経費として損金算入することは認められません。
また、登記の遅延は対外的な信用失墜にもつながるため、スケジュール管理は極めて重要です。実務では、払込完了前に必要書類を準備し、払込完了と同時に登記申請を行える体制を整えることが推奨されます。
税務署など各機関への届出と必要書類
増資により資本金額が変更された場合、登記変更と併せて税務署、都道府県税事務所、市区町村役場への異動届出が必要です。これらの届出には、変更後の登記事項証明書の添付が求められるため、登記完了後速やかに取得し、各機関に提出する必要があります。
税務署への届出は「異動届出書」を使用し、資本金額の変更内容を記載します。都道府県税事務所と市区町村には、それぞれの自治体が定める様式での届出が必要です。これらの届出期限は変更後速やかに提出することとされています。
届出を怠ると、正確な税額計算に支障をきたす可能性があり、後日の税務調査で問題となるリスクがあります。実務担当者は、登記完了と同時に各機関への届出スケジュールを作成し、確実に実行することが求められます。
まとめ|増資を成功させて中小企業の成長を実現しよう
増資は単なる資金調達手段ではなく、中小企業の成長戦略を実現するための重要な経営ツールです。事業拡大、M&A実行、財務体質強化など、様々な場面で戦略的に活用することで、企業競争力の向上と持続的成長を実現できます。
適切な増資手法の選択が成功の鍵となります。第三者割当増資では事業シナジーを重視し、株主割当増資では既存株主との関係維持を優先するなど、目的に応じた手法選択が重要です。また、持株比率の希薄化や税負担増加などのデメリットも十分に検討し、総合的な判断を行う必要があります。
増資の実施には法定期限の遵守と適切な手続きが不可欠です。登記変更は2週間以内という厳格な期限があるため、事前準備を怠らず、確実な実行体制を構築しましょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。