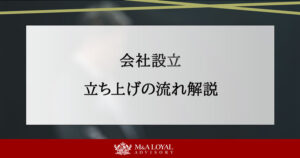現物出資とは?会社設立で失敗しないためのポイントを徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
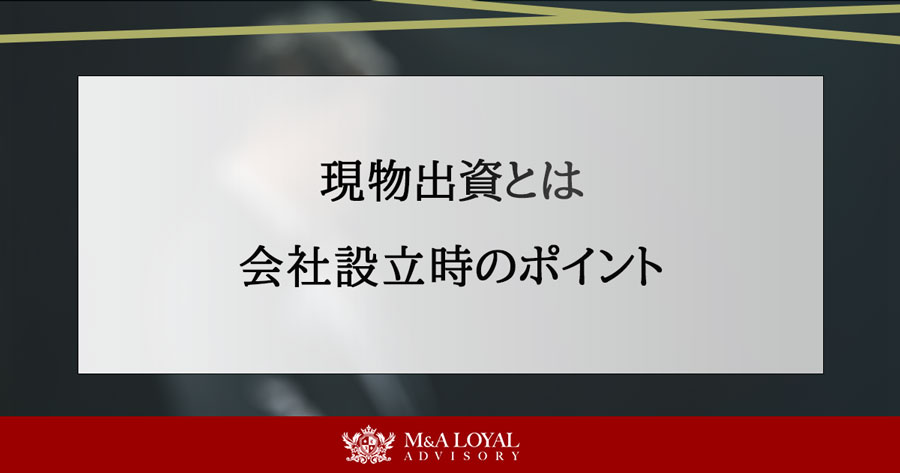
現物出資は、現金の代わりに資産を活用して出資する手段であり、会社設立を考えている経営者が直面する資金調達の課題を解決する方法の一つです。一般的に、会社設立や増資の際には現金による出資が行われますが、現金以外の資産を利用した「現物出資」を適切に活用すれば、手元資金が限られていても会社を設立することが可能です。
ただし、現物出資には複雑な手続きが伴い、正しい評価や税務上の注意点を理解せずに進めると、後々トラブルが発生するリスクがあります。この記事では、現物出資の基本的な仕組みやメリット・デメリット、具体的な手続きの流れについて触れ、現物出資による会社設立や増資を成功させるために必要な知識をわかりやすく解説します。
目次
現物出資とは
現物出資とは、会社設立や増資の際に現金以外の資産を出資する方法のことです。一般的な現金出資とは異なり、土地や建物、機械設備、有価証券、知的財産権などの様々な資産を会社の資本として提供することができます。
この制度は、特に手元資金が限られている起業家や、既存の事業資産を活用して新会社を設立したい経営者にとって有効な選択肢となります。現物出資の対象資産は幅広く、譲渡可能な資産であれば対象となる可能性があります。
現物出資の法的位置づけ
現物出資は会社法において明確に規定されており、適法な出資方法として認められています。会社設立時に発起人が現金以外の財産を出資することで、その財産の価額に相当する株式の割当てを受けることができます。
ただし、現金出資と比較して手続きが複雑であり、適切な評価や法的要件を満たす必要があるため、専門家のサポートを受けることが重要です。会社法では、出資者保護と債権者保護の観点から、厳格な手続きを定めています。
現物出資と現金出資の違い
現物出資と現金出資の最も大きな違いは、出資する財産の性質にあります。現金出資は金銭による出資であるため価値が明確ですが、現物出資では、出資する資産の市場価値を適正に評価することが必要となります。
また、現金出資の場合は資本金がそのまま運転資金として活用できますが、現物出資では固定資産などの形で資本が構成されるため、現物出資による資本金の場合は、事業運営に必要な現金が不足する可能性があることを十分に検討する必要があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



現物出資の要件と手続き
現物出資を行うためには、会社法で定められた厳格な要件を満たす必要があります。これらの要件を理解し、適切に手続きを進めることが、現物出資を成功させる鍵となります。
まず、定款に必要事項を記載することが必須となります。また、原則として裁判所選任の検査役による調査が必要ですが、一定の条件を満たす場合は検査役の調査を省略することも可能です。
定款への記載事項
現物出資を行う場合、定款に以下の事項を必ず記載する必要があります。出資者の氏名または名称、出資財産の内容および価額、そして割り当てる株式数です。
これらの記載事項は現物出資登記の際にも重要な書類となるため、正確かつ詳細に記載することが求められます。特に出資財産の価額については、後述する評価方法に基づいて適正に算定する必要があります。
検査役の調査が不要となるケース
原則として必要な検査役の調査ですが、以下の条件を満たす場合は省略することができます。これにより、現物出資手続きの簡素化と期間短縮が可能となります。
- 割当株式数が発行済株式総数の10分の1以下の場合
- 出資財産の総額が500万円以下の場合
- 市場価格のある有価証券で、払込価額が市場価格以下の場合
- 弁護士、税理士、公認会計士等の証明を受けた場合
- 出資財産が会社に対する金銭債権で、帳簿価額以下の場合
不足額填補責任(価値不足の補償義務)について
現物出資において特に注意すべきは、不足額填補責任です。これは、出資財産の実際の価値が定款に記載の評価額を下回った場合、その差額を発起人が会社に対して補填する責任を負うという制度です。
この責任リスクもあるため、現物出資評価は慎重かつ保守的に行うことが重要です。過大評価によるリスクを避けるためにも、専門家による適正な評価を受けることが推奨されます。
現物出資可能な資産の種類
現物出資の対象資産は多岐にわたり、事業に有用な様々な財産を出資することができます。ただし、すべての資産が対象となるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、金銭評価が可能で、貸借対照表に計上できる財産であることが求められます。以下では、主要な現物出資の対象資産について詳しく解説します。
金銭債権
売掛金、貸付金、受取手形などの金銭債権は、現物出資の対象となります。特に既存事業を新会社に移転する際には、売掛金などの債権を現物出資することで、事業の継続性を保つことができます。
ただし、金銭債権については回収可能性を十分に検討し、貸倒れリスクを考慮した適正な評価を行うことが重要です。また、債務者への通知や承諾などの債権譲渡手続きも必要となる場合があります。
不動産・有形固定資産
土地、建物、機械設備、車両などの有形固定資産も現物出資の対象となります。不動産や自動車、パソコンなど、事業に必要な資産を出資することで、初期投資を抑えながら会社設立を行うことができます。
| 資産区分 | 具体例 | 評価のポイント |
|---|---|---|
| 不動産 | 土地、建物、地上権 | 不動産鑑定評価、固定資産税評価額 |
| 車両 | 営業車、運搬車 | 中古車査定価格、減価償却後の帳簿価額 |
| 機械設備 | 製造設備、PC、備品 | 購入価格からの減価償却、市場価格 |
無形固定資産・知的財産権
特許権、商標権、著作権、営業権(のれん)などの無形固定資産も現物出資の対象となります。特に技術系のベンチャー企業では、特許権や技術ノウハウを現物出資することで、創業者の技術的貢献を適切に評価することができます。
無形固定資産の評価は困難であるため、知的財産権の評価に精通した専門家のサポートを受けることが不可欠です。将来の収益性や市場での競争優位性を考慮した評価が必要となります。
現物出資のメリットとデメリット
現物出資には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。これらを十分に理解した上で、現物出資を活用するかどうかを判断することが重要です。
特に中小企業の経営者にとっては、限られた資金を効率的に活用する手段として現物出資は魅力的ですが、同時にリスクも伴うことを認識しておく必要があります。
現物出資のメリット
現物出資の最大のメリットは、手元資金がなくても会社設立を実現できることです。保有している資産を活用することで、現金を用意することなく発起人として会社設立に参加することができます。
また、減価償却を活用した節税効果も期待できます。現物出資した固定資産については、会社として減価償却費を計上できるため、税務上の費用として処理することで法人税の軽減効果があります。さらに、資本金の増加により会社の信用力向上にもつながります。
備品購入コストの削減も重要なメリットです。パソコン、車両、機械設備などを現物出資することで、会社設立後の初期投資を大幅に削減することができ、キャッシュフローの改善に寄与します。
現物出資のデメリット
一方で、現物出資のデメリットとして最も大きいのは手続きの煩雑さです。現物出資に必要な書類の準備から評価書の作成、登記手続きまで、現金出資と比較して多くの時間と労力が必要となります。
また、資本金の現金比率が低下することにより、運転資金不足に陥るリスクがあります。固定資産中心の資本構成となるため、日常的な事業運営に必要な現金が不足し、資金繰りに苦労する可能性があります。
不足額填補責任も重要なデメリットです。出資財産の評価額が定款に記載の価額を下回っていた場合、その差額を発起人が補填する義務が生じ、予期せぬ負担となる可能性があります。
リスク管理の重要性
これらのメリット・デメリットを踏まえ、現物出資を行う際は適切なリスク管理が必要です。特に評価額の妥当性については、複数の専門家の意見を求めることが重要です。
また、現物出資後の資金繰りについても事前にシミュレーションを行い、必要に応じて現金出資との組み合わせを検討することで、バランスの取れた資本構成を実現することができます。
現物出資の税務上の注意点
現物出資を行う際は、税務上の取り扱いについて十分な理解が必要です。現物出資における税務の知識が不足していると、予期せぬ税負担が発生したり、税務調査で問題となる可能性があります。
特に個人が現物出資を行う場合と法人が行う場合では、税務上の取り扱いが大きく異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
個人による現物出資の税務処理
個人が現物出資を行った場合、税務上は資産の譲渡とみなされます。つまり、出資財産を時価で売却したものとして、譲渡所得税の課税対象となる可能性があります。
特に不動産や有価証券などの値上がり益がある資産を現物出資する場合は、その含み益に対して所得税が課税されることになります。したがって、現物出資を検討する際は、税負担と現物出資のメリットを比較検討することが重要です。
消費税の取り扱い
現物出資において見落としがちなのが消費税の問題です。事業用資産を現物出資する場合、消費税法上は資産の譲渡とみなされ、消費税の課税対象となる場合があります。
特に課税事業者が建物や機械設備などの事業用資産を現物出資する場合は、消費税の納税義務が発生する可能性があるため、事前に税理士等の専門家に相談することが重要です。
適正な評価額の重要性
現物出資評価において最も重要なのは、適正な時価での評価です。過大評価は不足額填補責任のリスクを高めるだけでなく、税務上も問題となる可能性があります。
一方で過小評価も、個人の場合は低額譲渡として税務上の問題となる可能性があるため、客観的で合理的な評価方法を選択することが重要です。不動産であれば不動産鑑定士、有価証券であれば公認会計士など、それぞれの分野の専門家による評価を受けることを推奨します。
現物出資の具体的な手続きの流れ
現物出資の流れを理解することは、スムーズな会社設立を実現するために不可欠です。手続きは複数の段階に分かれており、それぞれの段階で適切な対応が求められます。
全体的な流れとしては、出資財産の選定・評価から始まり、定款の作成、必要に応じて検査役の調査、そして登記申請まで進んでいきます。各段階での注意点を理解し、計画的に進めることが重要です。
事前準備段階
まず、現物出資する財産の選定と評価を行います。この段階では、譲渡可能であり、貸借対照表に資産計上できるもの、適正な評価が可能であること、法的な問題がないことを確認する必要があります。
特に不動産の場合は、登記簿謄本や固定資産税評価証明書などの書類を取得し、担保権の設定状況や税金滞納の有無を確認することが重要です。また、この段階で税理士や弁護士などの現物出資専門家に相談し、全体的な手続きの方針を決定します。
定款作成・認証段階
現物出資に関する事項を定款に記載し、公証人による認証を受けます。定款には、出資者の氏名、出資財産の内容と価額、割り当てる株式数を正確に記載する必要があります。
この段階で記載ミスがあると後の手続きに支障をきたすため、専門家によるチェックを受けることが重要です。また、検査役の調査が必要かどうかの判断もこの段階で行います。
検査役調査・登記申請段階
検査役の調査が必要な場合は、裁判所に検査役選任の申立てを行います。検査役による調査には数か月の期間を要するため、スケジュールに余裕を持って進める必要があります。
検査役の調査が完了した後、または調査が不要な場合は、速やかに法務局に対して会社設立登記の申請を行います。現物出資登記では、通常の設立登記書類に加えて、財産引継書や調査報告書などの追加書類が必要となります。
現物出資を成功させるためのポイント
現物出資を成功させるためには、事前の準備と専門家の活用が不可欠です。特に評価の妥当性と手続きの適正性を確保することが、後々のトラブルを避けるために重要です。
また、現物出資は単なる資金調達手段ではなく、会社の資本構成や事業運営に長期的な影響を与える重要な意思決定であることを理解し、慎重に検討を進める必要があります。
適切な専門家の選定
現物出資の成功には、適切な専門家のサポートが不可欠です。税理士、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士など、出資財産の種類に応じて適切な専門家を選定することが重要です。
特に複数の種類の財産を現物出資する場合は、各分野の専門家が連携してサポートする体制を構築することで、手続きの効率化とリスクの軽減を図ることができます。
現物出資増資への展開
会社設立時の現物出資が成功した場合、将来的に現物出資増資を活用することも可能です。事業拡大に伴って新たな設備投資が必要となった際に、現物出資による増資を行うことで、効率的な資本政策を実現できます。
ただし、増資時の現物出資についてもいくつかの手続きと注意点が必要となるため、継続的な専門家のサポートを受けることが重要です。
事業承継・M&Aへの応用
現物出資の知識は、将来的な事業承継やM&A場面でも活用できます。事業資産の適正な評価方法や税務上の取り扱いに関する知識は、会社売却や事業譲渡を検討する際にも重要な要素となります。
特に中小企業の経営者にとっては、創業時から将来の出口戦略まで一貫した資本政策を検討することが、企業価値の最大化につながる可能性があります。
まとめ
現物出資は、現金以外の資産を活用して会社設立を実現する有効な手段です。手元資金が限られている起業家や、既存の事業資産を新会社に移転したい経営者にとって、大きなメリットをもたらす可能性があります。
一方で、現物出資には複雑な手続きと様々なリスクが伴います。適正な評価、税務上の注意点、不足額填補責任など、専門的な知識が必要な分野が多く、独力で進めることは困難です。成功のためには、早い段階から税理士、弁護士などの専門家のサポートを受けることが不可欠でしょう。
現物出資を検討される経営者の皆様には、メリットとデメリットを十分に理解した上で、慎重な判断をしていただくことをお勧めします。適切に活用すれば、現物出資は会社設立の強力な武器となることでしょう。
事業の成長や将来的な事業承継・M&Aをご検討の方はM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。