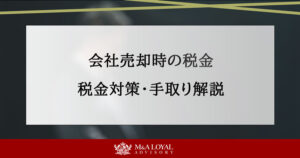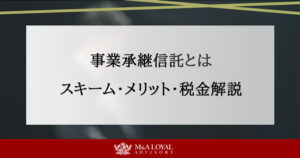事業承継時に消費税の納税義務はある?課税対象や節税対策を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
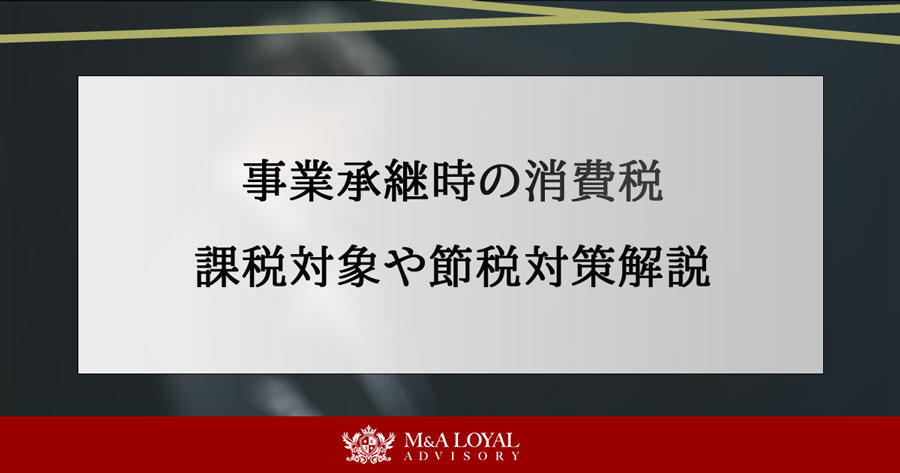
事業承継では、資産の引き継ぎ方によっては消費税が課税される場合があります。承継後に突然納税義務が発生することもあるため、事前にその仕組みを正しく理解しておくことが不可欠です。
さらに、法人と個人事業主では税務の取り扱いに違いがあり、届出の有無や制度の選択によっても納税額に差が出ることがあります。
この記事では、事業承継に関わる消費税の基本的なポイントから、課税対象となる資産の例、必要な手続き、節税対策まで分かりやすく紹介します。
目次
事業承継時は消費税の納税義務があるか
まず、事業承継と消費税に関する基本的な知識について解説します。
課税対象の資産に消費税が発生する
事業承継では、経営権の移転とともに事業用資産が後継者に引き継がれます。この際、譲渡の方法や資産の種類によっては、その取引に対して消費税が課税されることがあります。
課税対象となる資産には、建物や設備などの有形固定資産、営業権・ソフトウェアなどの無形固定資産が含まれます。一方、土地や有価証券、債権などは非課税資産です。
なお、承継方法によっても消費税の課税対象になるか否かが異なります。例えば、売買による承継では消費税が発生し、相続や贈与の場合は消費税は発生しません。ただし、相続であっても課税売上高が1000万円を超える場合は消費税が発生します。どの資産が課税対象になるかを正確に把握し、あらかじめ税理士など専門家に相談しておくことが重要です。
消費税とは
消費税は、商品を買ったりサービスを受けたりといった「消費」に対してかかる税金です。
消費税は、商品やサービスの取引に対して課される間接税で、最終的な負担者は消費者ですが、納税義務は事業者にあります。日本国内では標準税率10%が基本で、食品や新聞など一部の品目には軽減税率8%が適用されています。
事業者は、消費者から受け取った消費税と、仕入や経費に含まれる消費税を相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署へ納付します。課税の対象となるのは、日本国内で事業として継続的に行われる資産の譲渡やサービスの提供など、対価を得る取引に限られます。
なお、事業者であっても、基準期間(原則として前々年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば通常は免税事業者となり、納税義務は免除されます。ただし、適格請求書発行事業者として登録している場合は、売上規模にかかわらず課税事業者となる点に注意が必要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



個人事業主と法人における事業承継時の消費税対応の違い
事業承継においては、個人事業主と法人とで消費税の課税関係が異なります。
個人事業主の場合
個人事業主が事業を承継する場合、消費税の納税義務は事業を営む「個人」に帰属します。
そのため、たとえ同一の事業を引き継いだとしても、旧経営者と後継者はそれぞれ別個の納税義務者となります。承継前に発生した消費税は旧事業主が、承継後の取引については後継者がそれぞれ申告・納付を行う必要があります。
個人事業主の消費税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までと定められ、申告・納付期限は翌年3月31日までです。所得税の申告とは期限が異なりますが、実務上は同時に手続きされることが多く見られます。
また、事業承継では、旧経営者の「廃業届」と、後継者の「開業届」など税務署への届出も必要となる点に注意が必要です。
法人の場合
法人における事業承継では、代表者や株主が交代しても法人そのものが独立した法的主体であるため、消費税の納税義務は法人に継続して発生します。
代表者の交代によって納税義務がリセットされることはなく、法人としての義務が継続される点が、個人事業主との大きな違いです。
消費税の納付期限は、事業年度の終了日の翌日から2カ月以内となっており、法人税と同様のスケジュールで管理されます。
消費税の課税対象となる資産
消費税の課税対象となる資産と、非課税対象となる資産について解説します。
課税対象
土地を除く有形固定資産
土地を除く有形固定資産のうち、建物・機械・車両・設備・船舶などは消費税の課税対象です。
これらは企業や個人事業主が事業活動において長期的に使用する目的で保有する資産です。事業承継時にこれらの資産が有償で引き継がれる場合、対価の授受に対して消費税が課税されます。
無形固定資産
無形固定資産には、特許権・商標権・意匠権・著作権・ソフトウェア・漁業権など、実体はないものの、金銭的な価値を有する資産が該当します。事業承継時にこれらの権利を対価付きで譲渡した場合、消費税の課税対象となります。
また、営業権(のれん)も無形固定資産の一種として扱われ、譲渡金額に含まれる際は課税の対象です。
棚卸資産
棚卸資産は、事業で販売または製造に使用するために保有する資産で、原材料・商品在庫・仕掛品・製品などが該当します。これらは通常の売買同様に事業承継の際に譲渡されると、課税取引として消費税の対象になります。
棚卸資産は在庫量や品目により価額が変動するため、譲渡時の適切な評価と記録が重要です。
非課税対象
土地
土地は有形固定資産の一種ですが、譲渡や貸付に対して消費税は課されません(1ヶ月未満の貸付や特定の利用目的を除く)。これは土地が「消費」されるものではないという税制上の考え方に基づいており、住宅用・事業用いずれの土地でも非課税です。
事業承継時に土地が他の課税資産と一緒に引き渡される場合でも、土地分の対価には消費税がかからないため、明確に区分して記載・評価する必要があります。
有価証券
有価証券には、株式・社債・国債・地方債・手形・小切手などが含まれます。これらは金融商品として位置付けられており、消費税法上、譲渡の場合には非課税とされています。
事業承継において有価証券が引き継がれる場合でも、消費税の申告対象にはなりません。課税資産と混同しないよう、事業譲渡契約において非課税資産として明記することが適正な会計処理につながります。
債権
債権とは、法律上他人に一定の行為(主に金銭の支払い)を請求できる権利を指します。売掛金・貸付金・未収入金などが該当し、消費税法上は非課税資産として扱われます。
事業承継時に債権を引き継ぐ場合でも、譲渡自体に消費税は課されません。帳簿や契約書においては、課税対象となる資産と区別して記載し、非課税取引として処理することが必要です。
事業承継の手法ごとの消費税の扱い
事業承継の手法には、次の方法があります。
- 売買
- 贈与
- 相続
それぞれの場合における消費税の扱いについて解説します。
売買
売買による事業承継では、譲渡資産の内容に応じて消費税が課されます。買い手側は課税対象額に応じて消費税を上乗せして支払い、売り手側が納税を行います。
この手法は、主にM&Aにおいて用いられることが多く、特に事業の一部を切り離して譲渡する「事業譲渡」の形態では、譲渡する資産ごとに課税の有無を判断する必要があります。一方で、株式譲渡や合併、会社分割は、消費税法上「資産の譲渡」に該当せず、不課税とされます。
なお、譲渡金額が高額となり、営業権(のれん)など無形資産の価値が大きい場合は、想定以上の消費税負担が生じることもあるため、譲渡対象資産の明細や消費税額の確認が重要です。
贈与
生前贈与による事業承継は原則として無償譲渡となるため、消費税は課されません。
個人間の承継では「譲渡者の廃業」と「後継者の開業」がセットで行われ、後継者が新規に開業した場合、開業から2年間は原則として消費税の納税義務が免除されます。これは、開業直後の基準期間が存在しないためです。
ただし、後継者が適格請求書発行事業者として登録している場合は、売り上げに関係なく課税事業者として消費税を納める必要があります。
また、個人から法人へ事業資産を無償譲渡するケースでは、税務上「みなし譲渡所得」が発生し、消費税や所得税の課税対象となることがあります。
相続
相続によって事業が承継された場合、被相続人の資産は無償で取得されるため、消費税は課税されません。
しかし、相続が発生した年においては、被相続人の課税売上高が1,000万円を超えていた場合、後継者は相続日の翌日から課税事業者とされます。これは、後継者が過去に事業を行っていなかったとしても例外ではなく、旧経営者の基準期間の売り上げが適用されるためです。
また、相続人が複数いて事業を分割して承継する場合には、それぞれの事業承継割合に応じて課税売上高を案分し、個別に納税義務の有無が判断されます。遺産分割協議が遅れた場合には、相続開始前・協議中・協議後の売り上げを按分して計算しなければならず、煩雑な処理が求められます。
事業承継時の消費税の関連書類
事業承継においては、承継の方法や課税関係に応じて、税務署へ提出すべき届出書類が発生します。具体的には、次のような書類が必要となる場合があります。
- 廃業届出書(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 事業廃止届出書
- 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
それぞれについて解説します。
廃業届出書(個人事業の開業・廃業等届出書)
譲渡側(旧経営者)が個人事業主である場合、事業承継に伴い「個人事業の廃業届出書(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」を税務署に提出する必要があります。
この届出は、事業を廃止した日から1カ月以内に所轄の税務署長宛てに行うことが義務付けられています。
なお、届出を行わないと、税務上の整理がなされず、廃業後も申告案内が送付されるなどの支障が生じる可能性があります。
事業廃止届出書
旧経営者が消費税の課税事業者であった場合には、廃業後速やかに「事業廃止届出書」を提出する必要があります。
これは、消費税の納税義務の終了を明確にするための手続きであり、インボイス発行事業者の登録取消手続きもこれに含まれます。
税務署は廃業日以降の消費税の課税関係を把握するため、この届出を基に課税事業者の区分を変更します。提出が遅れると、不要な消費税の申告案内が継続して届くなどのトラブルに発展する恐れがあります。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書
簡易課税制度を既に選択している事業者が、原則課税制度へ変更したい場合には、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要です。これは、事業の実態や粗利益率などを踏まえた上で、より節税効果の高い方法を選ぶための手続きです。
簡易課税制度とは、年間売上高が5,000万円以下の中小事業者が対象で、実際の仕入税額控除を行わず、業種ごとのみなし仕入率を用いて納付税額を計算できる制度です。ただし、実際の仕入額が大きい業態では、原則課税制度の方が有利となることがあります。
この届出書は、変更を希望する課税期間の開始前に税務署へ提出する必要があります。提出が間に合わない場合は、変更が翌課税期間からしか適用されません。
なお、事業廃止と同時にこの届出を行う場合には、別途の廃止届出書が不要となるケースもあります。
消費税課税事業者選択不適用届出書
「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、既に課税事業者として届出を行っている事業者が、将来的に免税事業者へ戻ることを希望する場合に必要となるものです。
例えば、事業承継後に売上高が年間1,000万円以下となる見込みがある場合、消費税の納税義務を免除される「免税事業者」に戻ることが可能です。ただし、免税事業者に戻る課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があるため、承継時期や売り上げの見通しを踏まえた事前準備が求められます。
なお、一度課税事業者となった場合、届出を提出しない限りその効力は継続するため、自動的に免税事業者には戻れません。
消費税課税事業者選択届出書
「消費税課税事業者選択届出書」は、免税事業者があえて課税事業者を選ぶ場合に必要な書類です。特に、輸入取引や設備投資が多く、仕入れ等にかかる消費税の控除を受けたい場合に有効とされます。
例えば、免税事業者のままだと仕入税額控除が受けられず納税額はゼロであっても損をする可能性があるため、課税事業者として申告・納税した方が結果的に節税になる場合があります。
この届出も免税を適用する課税期間の初日の前日までに提出しなければならず、タイミングを逃すと適用が先送りされます。また、一定の高額資産を取得した場合は3年間課税事業者である必要があるため、今後の投資計画と併せて提出判断を行うことが重要です。
消費税を抑えるための対策とポイント
消費税を抑えるための対策とポイントとして、次の点が挙げられます。
- 課税資産と非課税資産を正確に区分する
- 簡易課税制度を利用する
- 生前贈与を検討する
- 課税事業者かどうかの判定を確認する
それぞれを分かりやすく解説します。
課税資産と非課税資産を正確に区分する
事業承継時に発生する消費税の負担を軽減するためには、資産を課税対象と非課税対象に正しく切り分けることが重要です。建物や設備、営業権などは課税対象となりますが、土地や有価証券、債権といった資産は非課税です。
事業譲渡において譲渡価格がまとめて設定されている場合でも、非課税資産の割合を明確に区分しないと、全てに対して消費税が課されるリスクがあります。
適正な評価額を元に帳簿や契約書で内訳を明示しておくことで、税務上のトラブルを回避できます。資産の区分が曖昧なままだと、後から修正が困難になる可能性もあるため、税理士などの専門家の助言を受けながら事前に整理しておくと安心です。
簡易課税制度を利用する
事業承継の際には、消費税の納税負担を軽減する方法として、簡易課税制度の活用が検討されます。簡易課税制度は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」に基づいて仕入控除額を計算できる制度であり、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象です。
制度を適用すれば、譲渡資産にかかる消費税の納税額を抑えられる可能性があります。ただし、実際の仕入税額がみなし仕入率より多い場合は逆に負担が増すため、業種や事業内容に応じた選択が求められます。
既に簡易課税制度を選択している場合でも、原則課税制度の方が有利な場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出により変更が可能です。粗利率が低い事業者や高額資産の譲渡がある場合は、制度の切り替えを検討すると効果的です。
生前贈与を検討する
事業承継における消費税の負担を抑えたい場合は、相続よりも生前贈与による承継の方が有利になることがあります。
特に個人間で行う承継では、廃業・開業の形となるため、後継者の課税売上高の基準期間がリセットされます。その結果、原則として開業後2年間は消費税の納税義務がありません(後継者が既に適格請求書発行事業者として登録している場合を除く)。
また、法人においても、生前に売り上げや資産内容を把握しながら承継のタイミングを調整できるため、納税額の予測と管理がしやすくなります。
一方で、無償または著しく低額で事業資産を引き継ぐと「みなし譲渡所得」が発生し、別途課税の対象となることがあります。
課税事業者かどうかの判定を確認する
事業承継を行う際には、後継者が課税事業者に該当するかどうかをあらかじめ確認することが大切です。
消費税の課税事業者は、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合に該当しますが、承継によって新たに事業を開始した後継者には基準期間がないため、開業から2年間は原則として免税事業者となります。
ただし、後継者が適格請求書発行事業者として登録している場合には、売り上げに関係なく課税事業者として扱われるため、納税義務が発生します。また、既に課税事業者を選択している場合でも、条件を満たせば「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで免税事業者へ戻ることが可能です。
事業承継に伴って発生し得るその他の税金
事業承継時に発生する消費税以外の税金には、次のものがあります。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税・法人税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
それぞれについて解説します。
相続税
相続税は、経営者が亡くなった際に、その財産を相続した配偶者や子どもなどに課される税金です。対象となる財産には、不動産や預貯金、株式、債券、現金などが含まれます。
相続税の計算では、まず相続財産の総額から債務や非課税財産、基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は3,000万円に600万円を法定相続人の数で掛けた金額です。例えば、配偶者と子ども2人の場合は4,800万円が控除されます。残った課税対象額を各相続人の法定相続分に応じて分け、それぞれに税率を適用して相続税額を算出します。なお、税率は累進制で、1,000万円以下の場合は10%、6億円を超える場合には最大55%が適用されます。
また、配偶者には1億6,000万円または法定相続分まで非課税となる特例があり、負担を大きく軽減できます。申告・納税は相続開始から10カ月以内で、延納や物納も選択できます。
贈与税
贈与税は、個人から個人へ無償で財産が移転した場合に課される税金です。事業承継において後継者が経営資産を譲り受けると、贈与税の対象になります。
贈与税の課税方式には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の二つがあります。
暦年課税では年間110万円までは非課税で、それを超えた部分に対して税率10〜55%の累進課税が適用されます。課税対象が直系尊属(親・祖父母など)からの贈与で、かつ成人である場合は、税率が緩やかな特例税率が適用されます。
一方、相続時精算課税制度では、2,500万円までが非課税となり、超過分は一律20%が課されます。この制度は、贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上であることなどの要件があります。
なお、相続時には精算対象として相続財産に加算されるため、慎重な選択が必要です。申告・納税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。
所得税・法人税
通常の事業承継では、所得税や法人税が直接発生することはありません。しかし、事業譲渡によって対価(譲渡益)を得た場合は、その譲渡益に対して所得税や法人税が課されることになります。
個人が事業用資産を譲渡した場合、譲渡益に対しては原則として譲渡所得税がかかり、法人が譲渡した場合には法人税が課税されます。
所得税率は所得の区分によって異なり、累進課税が適用されます。法人税については、譲渡価額と簿価との差額が益金として計上され、これに対して税率が適用されます。M&Aにおいて株式譲渡を行った場合は、売却益に対して原則20.315%の分離課税が適用されます。
一方、合併や会社分割による事業承継では、資産の譲渡に該当しないとされ、不課税になることがあります。所得税や法人税の取り扱いは、承継方法によって大きく異なるため、事前のシミュレーションと専門家の助言が不可欠です。
不動産取得税
事業承継に伴い、不動産を引き継ぐ場合には「不動産取得税」が課される可能性があります。不動産取得税とは、土地や建物を有償・無償を問わず取得した際に一度だけ課される地方税です。事業譲渡や贈与、相続を通じて不動産の名義変更が行われた場合には、原則としてこの税金の対象になります。
ただし、相続によって取得した場合は、不動産取得税は非課税とされます。これに対して、贈与や売買による取得の場合は課税され、課税標準は固定資産税評価額が用いられます。税率は原則として4%ですが、住宅用土地や建物など一定の要件を満たす場合には軽減措置が適用されることもあります。
登録免許税
登録免許税は、不動産などの資産について所有権移転登記などを行う際に課される税金です。事業承継において、譲渡対象資産に不動産が含まれる場合、所有権の登記手続きに伴って登録免許税が発生します。
税額は、固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されます。事業譲渡における不動産の移転登記では、原則として評価額の2%が課されます。また、相続によって不動産が承継される場合でも、所有権移転登記を行う際には登録免許税が必要ですが、その税率は0.4%と軽減されています。
一方、生前贈与で不動産を承継する場合は、相続とは異なり、評価額の2%が課されるため注意が必要です。
印紙税
印紙税は、事業承継に関連する契約書や金銭の授受に関する文書などを作成する際に課される税金です。具体的には、事業譲渡契約書や売買契約書、金銭の借用証書、不動産譲渡契約書などに印紙を貼付する必要があります。
課税文書の種類や記載された契約金額に応じて税額が異なり、例えば、不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものであれば、契約金額が1,000万円超〜5,000万円以下であれば1万円、5,000万円超〜1億円以下であれば3万円の印紙税がかかります。
相続による承継には契約書の作成が不要な場合も多く、印紙税が発生しないケースもありますが、贈与契約や事業譲渡契約が交わされる場合には印紙税が必要となります。
印紙の貼付がない、または金額が不足していると過怠税が科されることもあるため、契約書を作成する際には金額区分ごとの税額を確認し、適切に対応することが求められます。
参考:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
事業承継のパターンごとに発生する税金の整理
事業承継には、承継元と承継先の組み合わせによりさまざまなパターンがあります。例えば、次のようなパターンが想定されます。
- 個人から個人へ売却する場合
- 個人から法人へ売却する場合
- 個人から個人へ譲渡する場合
- 個人から法人へ譲渡する場合
- 個人から個人へ相続する場合
- 個人から法人へ相続する場合
それぞれのパターンごとに発生する税金について解説します。
個人から個人へ売却する場合
個人間で事業を売買によって承継する場合、売り手側は売却益が所得として課税対象となり、事業資産のうち課税対象となるもの(設備やのれんなど)には消費税も発生します。
一方、買い手側には通常、消費税や相続税・贈与税の納税義務は生じませんが、売買価格が著しく時価を下回る場合には、その差額部分が「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。また、不動産を取得する場合には登録免許税や不動産取得税が発生する場合もあります。
個人から法人へ売却する場合
個人から法人に事業を売却する際も、売り手側には所得税と消費税が課されます。所得税は売却益に対して課税され、消費税は課税資産(建物や営業権など)の譲渡に対して発生します。ただし、株式譲渡や合併、会社分割といった手法による事業承継は、消費税法上「資産の譲渡」には該当せず、原則非課税です。
一方で、買い手が法人の場合、株式譲渡では通常税金は発生しませんが、事業譲渡の場合には消費税が発生します。この消費税は、譲渡される課税資産の売却価格に加算されます。さらに、事業譲渡に関連して不動産取得税や登録免許税が課される場合もあります。
個人から個人へ譲渡(贈与)する場合
個人から個人へ事業を譲渡する場合、対価の支払いがないため、譲渡側に原則として税金は発生しません。
一方で、後継者である譲受側には贈与税の課税対象となる可能性があります。また、引き継ぐ事業に不動産が含まれる場合は、不動産取得税や登録免許税も課税されます。
個人から法人へ譲渡(贈与)する場合
個人が法人に無償または著しく低額で事業を譲渡する場合、所得税法上「みなし譲渡所得」が発生する可能性があります。
これは、対価がないにもかかわらず、時価で譲渡したとみなして課税される制度で、所得税の対象となります(所得税法第59条、施行令第169条)。一方で、消費税は発生しません。
譲受側となる法人には、引き継いだ事業の利益に対して法人税が課され、さらに必要に応じて登録免許税や不動産取得税がかかる場合があります。
個人から個人へ相続する場合
個人から個人へ事業を相続する場合、相続手続により事業資産が後継者に引き継がれます。課税対象となる財産額に応じて相続税が決まり、企業の資産価値が高い場合は高額な税負担が発生する可能性があります。
なお、相続による事業承継では消費税はかかりませんが、不動産を含む場合は登録免許税や不動産取得税が課されることがあります。
個人から法人へ相続する場合
個人から法人に相続する場合、相続人がその事業資産を法人に承継するための手続きを行う必要があります。この場合、被相続人には消費税が発生しませんが、法人側には法人税が生じる可能性があり、加えて登録免許税や不動産取得税も課されることがあります
事業承継における節税方法
事業承継における節税方法として、主に次の方法があります。
- 事業承継税制を利用する
- 相続時精算課税制度を活する用
- 生命保険を活用する
- 役員への退職金の支払いを活用する
- 不動産を購入する
それぞれを詳しく解説します。
事業承継税制を利用する
事業承継税制は、中小企業の経営者が後継者に自社株式を贈与・相続する際に発生する贈与税・相続税の納税を猶予・免除できる制度です。
要件を満たせば、最大で100%の納税猶予が認められ、将来的には免除される場合もあります。後継者が5年以上継続して代表を務めるなどの一定の要件を満たすことが必要ですが、財産の流出を防ぎつつ円滑に承継を進められます。
ただし、制度の適用には事前認定や継続報告などの手続きが求められ、取り消しリスクもあるため、税理士など専門家の関与が欠かせません。
相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度は、生前贈与を促進させるために創設された制度で、早期にまとまった資金が必要な子や孫に贈与できます。
60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して行う贈与に適用され、2,500万円までの贈与に贈与税がかからない制度です。超過分には一律20%の贈与税が課されますが、相続発生時に贈与財産を相続財産に加算して相続税が計算される仕組みです。
2024年からは年間110万円の基礎控除も導入され、これに該当する金額は相続税の対象に含まれません。ただし、一度この制度を選択すると撤回できず、暦年贈与の非課税枠(110万円)は使えなくなります。また、同制度を利用して取得した宅地等には小規模宅地等の特例が使えなくなるなどの制限もあるため、適用には慎重な判断が必要です。
生命保険を活用する
事業承継では、生命保険を戦略的に活用することで、納税資金の確保や相続財産の分割、課税対象の調整といった節税効果が得られます。
経営者が生命保険に加入し、死亡保険金を後継者や法人が受け取る形にすれば、相続時に現金が不足して自社株などを売却せざるを得ない事態を防げます。
また、法人契約の保険であれば、支払保険料を損金算入することで法人税の軽減も図れます。受取人や契約形態によっては相続税や贈与税の課税対象になる場合があるため、設計次第で大きく効果が変わります。
役員への退職金の支払いを活用する
経営者が引退する際に役員退職金を支給することは、法人・個人双方で節税効果がある手段です。法人にとっては、退職金が損金に算入されるため法人税の負担軽減につながります。
一方、個人側でも退職金には「退職所得控除」が適用され、長期勤務に応じて大幅な非課税枠が設けられているため、通常の給与や賞与よりも税負担が抑えられます。特に20年以上勤務していた場合は控除額が大きく、分離課税で課税される点でも有利です。
ただし、過大な退職金は税務上否認されるリスクがあるため、同業他社水準や定款の定めに即した金額設定が求められます。
不動産を購入する
事業承継のタイミングで不動産を活用することは、資産分散と節税の両面で有効な手段です。例えば、法人が不動産を購入し、減価償却費を計上することで法人税の圧縮につながります。
さらに、不動産を後継者に生前贈与する際には、相続税評価額(固定資産税評価額や路線価)が時価より低く設定されるため、株式よりも低い税負担での資産移転が可能です。また、不動産を事業用資産として活用することで、事業承継税制の適用対象となる場合もあります。
ただし、不動産取得税や固定資産税の負担、流動性の低さには注意が必要です。
事業承継時の消費税に関するQ&A
最後に、事業承継時の消費税に関するよくある質問とその回答を紹介します。
みなし譲渡とは何か
みなし譲渡とは、無償または著しく低額で資産を譲渡した場合に、実際には対価がないにもかかわらず、時価で譲渡があったとみなして消費税が課される制度です。
事業承継においては、法人が事業用資産を役員に贈与・低額譲渡した場合や、個人事業主が廃業時に資産を後継者へ引き継いだ場合に、みなし譲渡課税が発生する可能性があります。
通常販売価格の50%未満での譲渡や贈与が課税対象となりやすく、想定外の納税が生じることもあるため注意が必要です。
事業承継信託とは何か
事業承継信託とは、経営者が保有する自社株式などの事業用資産を信託財産として信託し、信頼できる後継者に段階的に経営権を引き継がせる仕組みです。商事信託や民事信託の枠組みを用い、委託者(現経営者)が受託者(信託銀行や親族など)に株式の管理・運用を委ねます。
特に、後継者争いや経営の空白を避けたい場合に有効であり、信託契約の内容によっては、受益権を後継者に段階的に移転させられます。
法人と個人事業主はどちらが事業承継しやすいか
事業承継のしやすさという観点では、一般的に法人の方が制度的にも実務的にも承継しやすいとされています。法人は「法人格」を持つため、代表者が交代しても契約や取引関係が継続されやすく、金融機関との関係や許認可の引き継ぎもスムーズです。
一方、個人事業主は廃業と開業の手続きが必要で、取引先との契約や消費税の課税区分も一から見直される場合があります。特に、消費税の課税事業者としての選択や不適用の届出などが必要となるため、税務面の負担も大きくなりがちです。
まとめ
事業承継における消費税の取り扱いは、多くの経営者にとって複雑であり、理解しておくべき重要なポイントです。この記事では、事業承継時に消費税の納税義務がどのように発生するかを明確にし、個人事業主と法人の違いや、消費税の課税対象となる資産について詳しく解説しました。さらに、事業承継の手法ごとの消費税の扱いや関連書類を整理し、消費税を抑えるための具体的な対策とポイントを紹介しました。
これらの情報を理解することで、事業承継の税務面におけるリスクを最小限に抑えることが可能です。事業承継やM&Aに関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。