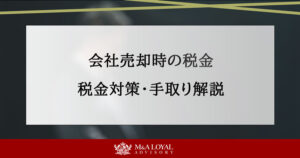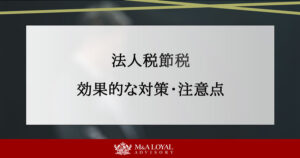租税とは?種類や租税公課で経費計上できるもの・できないものを紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
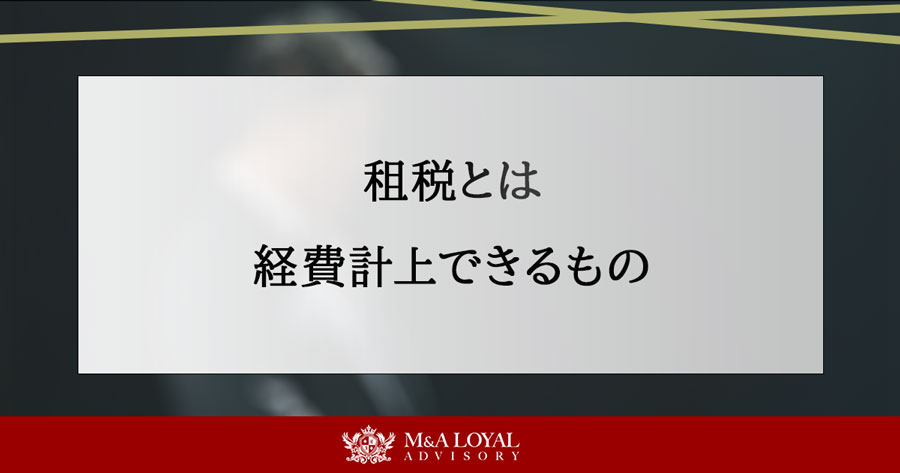
租税とは、国や地方公共団体が公的サービスの財源として徴収する金銭を指します。租税とは、具体的には所得税・法人税・消費税・固定資産税など、さまざまな種類が存在します。特に会社売却においては、租税とは何か、どんな種類があるのかを理解することが重要です。これにより、経費として計上できるかどうか、どのような税負担が発生するかを事前に把握することができ、最終的な手取り額を正確に算出し、最適な売却戦略を立てることが可能になります。
本記事では、租税とは何かといった基本的な仕組みから、会社売却時に関わる税金、租税公課として経費計上できるものとできないものまで詳しく解説し、あなたの会社売却を成功に導くための税務知識をわかりやすくお伝えします。
目次
租税の基本的な仕組みと定義をわかりやすく
租税とは、いわゆる税金のことであり、私たちの経済活動において避けて通れない重要な要素です。租税の基本的な仕組みを理解することは、経営者にとって会社経営や売却戦略を考える上で欠かせません。ここでは租税とは何か基本的な仕組みと定義について解説します。
租税とは何か
租税とは、国や地方公共団体が行政サービスを提供するために法律に基づいて徴収する金銭のことです。租税は国民や企業が社会の維持・発展に貢献するための義務であり、公的サービスを支える財源として機能しています。
租税の特徴として、まず強制性があります。租税は法律に基づいて徴収されるため、納税者の意思に関係なく支払い義務が生じることを意味します。憲法では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うことが明記されています。
次に無償性があり、税金を支払ったからといって直接的な見返りを求めることはできません。租税には収入確保の目的があり、国や地方公共団体が必要な財源を確保するために設けられています。
会社売却を検討する際には、これらの租税の性質を理解した上で、売却に伴って発生する税負担を正確に計算することが重要です。税金の計算を間違えると、想定していた手取り額と大きく乖離する可能性があるため、事前の準備が欠かせません。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



租税の種類と分類
租税とは様々な基準によって分類されており、それぞれの特徴を理解することで適切な税務対策を講じることができます。最も基本的な分類は、徴収する主体による国税と地方税の区分です。
国税と地方税
国税は国が徴収する税金で、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税などがあります。これらは全国統一の税率で課税され、税務署が徴収を担当します。一方、地方税は都道府県や市町村が徴収する税金で、住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税などがあります。
| 税区分 | 税の種類 |
|---|---|
| 国税 | 所得税 法人税 消費税 相続税 贈与税 酒税 たばこ税 自動車重量税など |
| 地方税 | 住民税 事業税 固定資産税 不動産取得税 地方消費税 自動車税など |
直接税と間接税
租税は課税方式によって直接税と間接税でも分けられ、直接税は納税者と負担者が同一の税金(所得税、法人税など)、間接税は納税者と負担者が異なる税金(消費税、酒税など)を指します。この分類は会社売却時の税負担計算において重要な要素となります。
| 種類 | 税金の例 |
|---|---|
| 直接税 | 所得税、法人税、相続税など |
| 間接税 | 消費税、酒税、関税など |
従量税と従価税
従量税と従価税は、租税の中でも特にその計算方法に特徴があります。従量税は、課税対象の数量に基づいて税額が決定される方式です。例えば、アルコール飲料の製品量やたばこの本数に基づいて課税されるため、商品の価格変動に影響されず、安定した税収を確保できます。
これに対して、従価税は課税対象の価値に基づいて税額が決まります。一般的には商品やサービスの価格に一定の税率を乗じて計算されるため、商品の価格が上がると税額も増加します。消費税や関税が従価税の代表例です。
このように、従量税は価格変動によるリスクを抑え、従価税は経済状況に応じた税収変動に対応できるメリットがあります。それぞれの税制は、政府の財政政策や経済状況に応じて使い分けられ、税収の安定性や公平性の確保に寄与しています。
| 税の種類 | 説明 |
|---|---|
| 従量税 | 商品の重量や数量に基づいて課税される税金 |
| 従価税 | 商品の価格に基づいて課税される税金 |
このように、租税の理解には、それぞれの分類や区分の違いを知ることが大切です。
租税科目の課税対象と税率
租税の課税対象は税目によって異なり、所得、財産、消費、流通などが主な対象となります。所得を対象とする税金には所得税や法人税があり、これらは所得の金額に応じて税率が適用されます。
財産を対象とする税金には相続税、贈与税、固定資産税があり、保有している財産の価値や移転する財産の価値に基づいて課税されます。消費を対象とする税金の代表例は消費税で、商品やサービスの購入時に課税されます。流通を対象とする税金には印紙税や登録免許税があり、契約書の作成や不動産の登記などの際に課税されます。
税率についても税目によって大きく異なります。租税の計算には比例税率、累進税率の方式があり、納税者の状況や取引の内容に応じて適用される税率が決まります。会社売却においては、これらの税率を正確に把握し、売却価格に対してどの程度の税負担が発生するかを事前に計算することが重要です。
租税の課税方式の違い
また、課税ベースで見ると、租税は「所得課税」「消費課税」「資産課税等」に分類できます。
| 課税区分 | 種類 |
| 所得課税 | 所得税 法人税 個人住民税 個人事業税 法人住民税 法人事業税 道府県民税利子割など |
| 消費課税 | 消費税 酒税 たばこ税・たばこ特別税 揮発油税 地方道路税 石油ガス税 自動車重量税 航空機燃料税 電気開発促進税 地方消費税 地方たばこ税 軽油取引税 ゴルフ場利用税 入湯税 自動車税・軽自動車税 狩猟者登録税 関税 とん税など |
| 資産課税等 | 相続税 贈与税 地価税 登録免許税 印紙税 不動産取得税 固定資産税 都市計画税 事業所税など |
会社売却時に発生する主な租税
租税とは税金のことであり、会社売却時にも法人税など様々な租税が発生します。これらの税金を理解し、適切に計算することで、売却後の手取り額を正確に把握できるようになります。
株式譲渡による課税の仕組み
株式譲渡による会社売却では、個人が株式を売却した場合と法人が売却した場合で課税の仕組みが大きく異なります。個人の場合、株式譲渡所得として分離課税の対象となり、譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。
個人の株式譲渡所得税は、原則として譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡益に対して、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%の合計20.315%が課税されます。ただし、中小企業の株式については、一定の要件を満たす場合に軽減税率や特例措置が適用される場合があります。
法人が株式を譲渡する場合は、譲渡益が法人の所得として他の所得と合算され、法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます。法人税率は資本金や所得金額によって異なりますが、中小法人の場合、年800万円以下の所得については軽減税率が適用されます。
株式譲渡における取得費の算定も重要なポイントです。設立時からの資本金、資本準備金の増加、過去の増資などを正確に把握し、適切な取得費を計算することで、課税対象となる譲渡益を適正に算出できます。
事業譲渡による課税の仕組み
事業譲渡による会社売却では、株式譲渡とは異なる課税の仕組みが適用されます。事業譲渡は資産・負債を個別に移転する取引であるため、移転される各資産について個別に課税関係が発生します。
譲渡会社側では、事業用資産の譲渡により譲渡損益が発生し、これが法人税等の課税対象となります。土地や建物などの固定資産については、帳簿価額と譲渡価額の差額が譲渡損益として計上されます。営業権(のれん)についても、その価値に応じて譲渡益が発生する可能性があります。
事業譲渡では消費税の課税関係も重要で、土地の譲渡を除く事業用資産の譲渡については消費税が課税され、譲渡価格に消費税を上乗せして請求することになります。これは株式譲渡にはない事業譲渡特有の課税関係です。
譲受会社側では、取得した事業用資産を適正な価額で資産計上し、支払った消費税については仕入税額控除の対象となります。また、営業権については無形固定資産として計上し、一定期間で償却処理を行うことになります。
その他の関連税金
会社売却に際しては、上記の主要な税金以外にも様々な関連税金が発生する可能性があります。これらの税金も事前に把握し、総合的な税負担を計算することが重要です。
印紙税
まず、印紙税があります。株式譲渡契約書や事業譲渡契約書には、契約金額に応じた印紙税が課税されます。例えば、事業譲渡契約書の場合、第1号文章に該当します。印紙税は契約金額が1億円を超える場合は10万円、5億円を超える場合は20万円といったように金額に応じて異なります。ただし、電子契約を利用する場合は印紙税は非課税となります。また、株式譲渡契約では原則印紙は不要ですが、特定のケースに該当する場合、印紙税が必要となります。
参考:国税庁|印紙税額の一覧表
登録免許税
登録免許税も発生する場合があります。事業譲渡において不動産の移転登記を行う場合や、株式譲渡において役員変更登記を行う場合に課税されます。不動産の所有権移転登記では、固定資産税評価額の2%(軽減税率の場合土地は1.5%)の登録免許税が必要です。
さらに、不動産取得税も考慮する必要があります。事業譲渡において不動産を取得した場合、取得者に対して都道府県が課税する地方税です。税率は原則4%ですが、土地と住宅については軽減措置が適用される場合があります。これらの関連税金も含めて総合的な税負担を計算し、売却戦略に反映させることが重要です。
租税公課として経費計上できるものとできないもの
租税公課の経費計上可否を正しく理解することは、会社の税務処理において極めて重要です。間違った処理を行うと税務調査で指摘を受ける可能性があるため、明確な基準を把握しておく必要があります。
経費計上可能な租税公課
法人税法上、損金算入が認められる租税公課には明確な基準があります。原則として、事業に直接関連する税金であることです。
経費計上が可能な代表的な租税公課として、固定資産税、都市計画税、事業税、事業所税、自動車税、印紙税、登録免許税、不動産取得税などがあります。これらは事業運営に必要な経費として認識され、発生した事業年度において損金算入することができます。
固定資産税は事業用資産に対して課税される税金で、土地、建物、機械装置、車両運搬具などが対象となります。毎年1月1日現在の所有者に課税され、年4回に分けて納付します。事業所税は一定規模以上の事業所に対して課税される地方税で、事業所床面積と従業員給与総額を基準として計算されます。
印紙税は契約書や領収書などの文書に課税される税金で、事業上必要な契約締結時に発生します。登録免許税は不動産登記や商業登記の際に課税され、事業に関連する登記であれば経費計上が可能です。これらは事業活動に直接関連するため、適切な経費処理により税負担を軽減できます。
損金計上のタイミング
| 方式 | 説明 | 計上時期 | 租税公課の例 |
|---|---|---|---|
| 申告納税方式 | 納税者の申告に基づき納税額を計算する方式 | 納税申告書を提出した事業年度 | 法人税 所得税 消費税 相続税など |
| 賦課課税方式 | 税務当局が納税額を決定し通知する方式 | 賦課決定通知がされた事業年度 | 固定資産税 不動産取得税 住民税など |
| 特別徴収方式 | 事業者が個人から徴収し納税する方式 | 納入申告書を提出した事業年度 | ゴルフ場利用税 軽油引取税など |
参考:国税庁|租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期
経費計上できない租税公課
一方で、法人税法では明確に損金算入が認められない租税公課も定められています。これらは主に法人の所得計算の結果として課税される税金や、罰則的性格を持つ税金です。
経費計上できない租税公課の代表例は、法人税、法人住民税、法人事業税の一部、所得税、住民税の個人分、相続税、贈与税、各種加算税、延滞税、過怠税などです。これらの税金は法人の所得に対して課税されるものや、税法違反に対する制裁金的性格を持つものであるため、損金算入が認められていません。
法人税は法人の所得に対して課税される基幹税であり、その計算過程で損金算入を認めると循環計算となってしまうため、経費処理できません。法人住民税も同様の理由で損金不算入とされています。
加算税や延滞税などの附帯税は、適正な申告・納税を怠った場合のペナルティとしての性格があるため、経費計上は認められません。これらの税金が発生しないよう、適正な税務処理と期限内申告・納税を心がけることが重要です。
判断が難しい租税公課の取り扱い
実務上、経費計上の可否について判断が困難なケースも存在します。これらについては税法の規定や税務当局の見解を慎重に検討し、適切な処理を行う必要があります。
例えば、消費税については一般的には経費計上せず、仮払消費税として処理しますが、簡易課税制度を選択している場合や免税事業者の場合は取り扱いが異なります。また、源泉所得税についても、自社が源泉徴収義務者として徴収・納付する場合は経費にならず、預り金の処理となります。
自動車関連の税金では、自動車税や軽自動車税は経費計上できますが、自動車取得税や自動車重量税の取り扱いは取得時期や処理方法によって異なります。新車購入時の自動車取得税や重量税は車両の取得価額に含めて減価償却を行うのが一般的ですが、車検時の重量税は経費計上が可能です。
国外で発生した税金については、外国税額控除を選択するか損益算入するかを選択します。どちらを選択するかは専門家のアドバイスを求めることが重要です。これらの複雑なケースについては、税理士などの専門家に相談し、適切な処理方法を確認することをお勧めします。
会社売却における租税公課の実務的な取り扱い
会社売却の実務では、租税公課の取り扱いが売却価格や手取り額に大きく影響します。適切な税務処理と戦略的な対応により、税負担を最適化することが可能になります。
売却準備段階での税務対策
会社売却を成功させるためには、売却準備段階から税務対策を講じることが重要です。まず、過去の税務処理を見直し、適切でない処理があれば修正申告を検討する必要があります。
売却準備では、租税公課の計上状況を詳細に確認し、経費計上できるものが適切に処理されているか、逆に損金不算入となるものが誤って経費計上されていないかをチェックすることが重要です。これにより、買収監査(デューデリジェンス)での指摘事項を最小限に抑えることができます。
また、売却時期の選択も税務上重要な要素です。個人株主の場合、他の所得との関係を考慮して最適な株式の売却時期を検討します。法人株主の場合は、決算期との関係や他の取引との損益通算を考慮した時期選択が有効です。
売却前の組織再編についても検討が必要です。適格組織再編を活用することで、課税を繰り延べながら売却しやすい構造に変更できる場合があります。ただし、これらの手法は複雑で税務リスクも伴うため、必ず税理士などの専門家と相談して進めることが重要です。
売却時の具体的な税務処理
実際の売却時には、契約書の作成から資金決済、税務申告まで、各段階で適切な税務処理が求められます。契約書作成時には印紙税の処理が必要で、契約金額に応じた印紙を貼付するか、電子契約により印紙税を回避するかを選択します。
株式譲渡の場合、譲渡価格の確定とともに、取得費の算定が重要になります。設立時の出資金額、過去の増資履歴、株式分割・株式併合の履歴などを正確に把握し、1株当たりの取得価額を計算します。譲渡費用についても、仲介手数料、弁護士費用、税理士費用など売却に直接要した費用を適切に計上することで、課税対象となる譲渡益を圧縮できます。
事業譲渡の場合は、個別資産ごとの譲渡損益計算と消費税の処理が重要で、土地以外の事業用資産については消費税を加算した金額で請求し、適切な消費税処理を行う必要があります。
代金決済時には源泉徴収の有無も確認が必要です。一般的な株式譲渡では源泉徴収は行われませんが、みなし配当が発生する場合や特殊な取引構造の場合は源泉徴収が必要になることもあります。
売却後の税務申告と納税
会社売却後の税務申告は、売却による所得の種類と税務上の取り扱いに応じて適切に行う必要があります。個人の株式譲渡の場合、翌年の確定申告で株式譲渡所得として申告し、納税を行います。
確定申告書の作成では、譲渡所得の計算明細書を添付し、譲渡価格、取得費、譲渡費用を詳細に記載します。取得費については、実額計算が困難な場合の概算取得費(譲渡価格の5%)の選択も可能ですが、通常は実額の方が有利になります。特定口座を利用していない場合は、自分で計算・申告する必要があります。
法人の場合は、売却による損益を当該事業年度の法人税等の申告書に含めて申告します。株式譲渡益は法人の益金として他の所得と合算され、法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます。
納税資金の準備も重要です。株式譲渡による税金は譲渡代金から捻出できますが、予想以上に税負担が重くなる場合もあるため、事前の税額シミュレーションが欠かせません。分納や延納制度の活用も検討に値しますが、これらには一定の要件があるため、事前に税務署や税理士に相談することをお勧めします。
租税公課の種類と特徴の詳細解説
租税公課を正しく理解するためには、主要な税目の種類と特徴を詳細に把握することが重要です。会社売却に関わる税金を中心に、その仕組みと実務上の注意点を解説します。
国税の種類と会社売却への影響
国税は国が課税・徴収する税金で、会社売却において最も影響の大きい税目が含まれています。主要な国税とその特徴を詳しく見ていきましょう。
所得税
所得税は個人の所得に対して課税される税金で、会社売却においては株式譲渡所得として重要な役割を果たします。株式譲渡所得は分離課税の対象となり、他の所得とは別に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で課税されるため、売却益が大きくなるほど税額も増加します。
法人税
法人税は法人の所得に対して課税される基幹税で、中小法人の場合、年800万円以下の所得には軽減税率(15%)が適用されます。800万円を超える所得には23.2%の税率が適用されるため、売却益の金額によって適用税率が変わることを理解しておく必要があります。
消費税
消費税は事業譲渡において重要な税目です。土地の譲渡以外の事業用資産の譲渡には10%の消費税が課税され、譲渡価格に上乗せして請求することになります。ただし、株式譲渡には消費税は課税されません。この違いは売却スキーム選択において重要な判断要素となります。
相続税・贈与税
相続税・贈与税は、事業承継を絡めた売却スキームにおいて考慮すべき税目です。後継者への株式移転と第三者への売却を組み合わせる場合、これらの税金の影響を慎重に検討する必要があります。
| 税目 | 課税対象 | 税率 | 会社売却への影響 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 個人の株式譲渡所得 | 15.315% | 個人株主の売却益に直接影響 |
| 法人税 | 法人の所得 | 15%~23.2% | 法人株主の売却益に影響 |
| 消費税 | 事業用資産の譲渡 | 10% | 事業譲渡時の譲渡価格に影響 |
| 住民税 | 株式譲渡所得 | 5% | 個人株主の税負担に追加 |
地方税の種類と実務上の注意点
地方税は都道府県や市町村が課税・徴収する税金で、会社売却においても様々な場面で関わってきます。特に事業用資産を多く保有する会社の売却では、地方税の負担も無視できません。
住民税
住民税は個人住民税と法人住民税に分かれており、個人住民税は株式譲渡所得に対して5%の税率で課税されます。法人住民税は法人税額を基準として計算される税額割と、資本金等の金額と従業員数を基準とする均等割から構成されます。
事業税
事業税は法人の事業所得に対して課税される地方税で、業種によって税率が異なります。一般的な法人の場合、所得や資本金に応じて3.5%~7.48%の税率が適用されます。法人事業税の特徴は、その年に支払った税額を翌年に損金算入できることです。これにより実質的な税負担が軽減される仕組みとなっています。
固定資産税
固定資産税は土地、建物などの固定資産を保有する法人や個人に課税される税金で、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。会社売却において事業用不動産を多く保有する会社では、固定資産税の年間負担額も企業価値算定の要素として考慮されます。
不動産取得税
不動産取得税は不動産を取得した際に都道府県が課税する税金で、事業譲渡により不動産を取得する場合に発生します。税率は原則4%ですが、土地と住宅については軽減措置として税率3%が適用されます。この税金は取得者負担となるため、事業譲渡契約においてどちらが負担するかを明確にしておく必要があります。
直接税と間接税の区分と影響
租税は課税方式の違いによって直接税と間接税に分類され、この区分を理解することで税負担の性質や転嫁の可能性を把握できます。
直接税は納税者と負担者が同一の税金で、所得税、法人税、住民税、事業税、固定資産税、相続税、贈与税などが該当します。これらの税金は納税者が直接負担し、他者に転嫁することは基本的にできません。会社売却においては、売却益に対する所得税・住民税や法人税等が直接税として売主の負担となります。
間接税は納税者と負担者が異なる税金で、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税などが該当します。これらは最終的に消費者が負担し、事業者が代理で納税する仕組みとなっています。
この直接税と間接税の区分は、売却スキームの選択や価格交渉において重要な要素となり、特に消費税の課税関係は事業譲渡と株式譲渡の選択に大きく影響します。
例えば、同じ1億円の価値がある事業について、株式譲渡は非課税のため、1億円が売却価格となりますが、事業譲渡は課税対象となるため、消費税1,000万円を加えた1億1,000万円が買主の支払額となります。ただし、買主が消費税の仕入税額控除を受けられる場合は、実質的な負担に大きな差は生じません。また、株式譲渡であっても譲渡手数料は課税対象になる点にも注意が必要です。これらの税制の仕組みを理解し、最適な売却スキームを選択することが重要です。
まとめ
租税とは国や地方公共団体が公的サービスの財源として法律に基づいて徴収する金銭であり、所得税、法人税、消費税、固定資産税など様々な種類があります。会社売却においては、株式譲渡の場合は譲渡益に対して20.315%の税率で所得税と住民税が課税され、事業譲渡の場合は個別資産の譲渡損益計算と消費税の処理が必要となります。
租税公課として経費計上できるものには固定資産税、事業税、印紙税、登録免許税などがあり、事業に直接関連する税金は損金算入が認められています。一方で、法人税、法人住民税、所得税、加算税、延滞税などは損金不算入とされており、適切な区分処理が重要です。会社売却を成功させるためには、これらの租税の仕組みを正しく理解し、事前の税額シミュレーションと適切な税務対策を講じることが不可欠です。
会社売却における租税の取り扱いは複雑で、専門的な知識と経験が求められる分野です。専門家と連携することで、税務リスクを最小限に抑えながら最適な売却戦略を実現できます。
M&Aや経営課題に関するお悩みはぜひ一度、M&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。