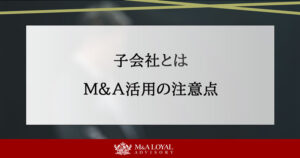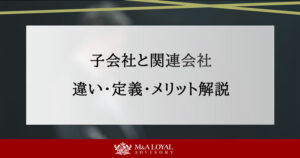グループ会社とは?子会社との違いやメリット・デメリットを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
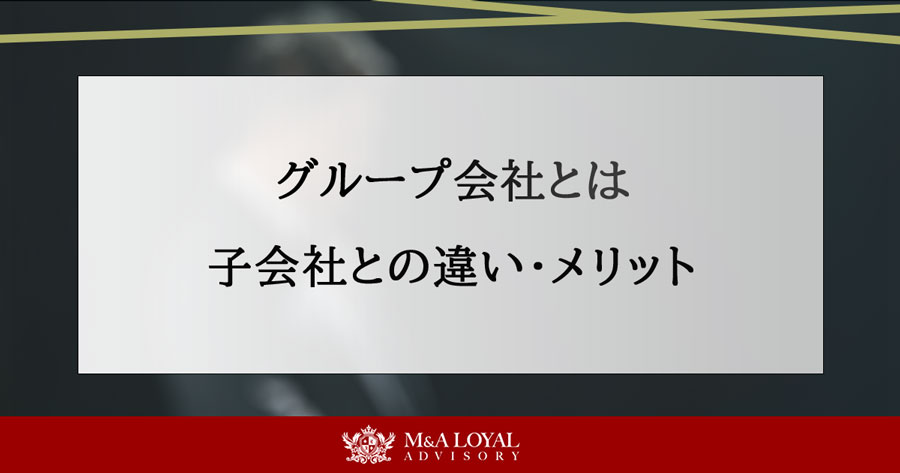
グループ会社とは何でしょうか?企業経営やM&Aを検討する際に、グループ会社や子会社といった用語を耳にする機会は多いものの、それぞれの違いや法的な定義を正確に理解している人は多くないようです。
グループ会社とは親会社を中心に子会社や関連会社が集まった企業集団のことを指し、子会社とは親会社に経営を支配されている会社を意味します。グループ会社とはどういうものかを理解することは、企業の成長戦略や事業承継、M&Aによる事業拡大を考える上で重要です。本記事ではグループ会社とは何か、子会社やグループ会社の法的定義から、M&Aによる子会社化の具体的な手法、そして子会社化することで得られるメリットやデメリットまで、中小企業のオーナー経営者が実務で活用できる知識を解説します。
目次
グループ会社とは何か
グループ会社とは、親会社を中心として子会社や関連会社が集まった企業集団の総称です。単独の会社ではなく、複数の法人が資本関係や契約関係で結ばれた組織体を指します。企業グループ全体で経営戦略やシナジー効果を追求し、グループ全体の企業価値向上を目指すことが一般的です。
グループ会社という用語は、会社法や会計基準では「関係会社」として定義されており、親会社と子会社、さらに関連会社を含めた広い概念として理解されています。親会社が事業持株会社として機能する場合もあれば、ホールディングス形式で純粋持株会社がグループ全体を統括する場合もあります。いずれの形態でも、グループ会社は資本関係を基礎として、経営の意思決定や事業展開において一体性を持つ点が特徴です。
グループ会社の定義と範囲
グループ会社は法律上「関係会社」と呼ばれ、親会社・子会社・関連会社のすべてを含む広義の企業集団を意味します。会社法や金融商品取引法では明確な定義があり、連結財務諸表を作成する際にはこれらの定義に基づいて範囲が決定されます。グループ会社に含まれる企業は、資本関係や人的関係、取引関係などによって実質的な支配や影響を受けている点が共通しています。
グループ会社の範囲を決定する際には、議決権の保有割合だけでなく、役員の派遣状況や事業上の依存関係なども考慮されます。たとえば議決権が過半数に満たない場合でも、取締役の過半数を派遣していたり、重要な財務や営業方針の決定に関与していたりすれば、実質的な支配関係があると判断され、グループ会社に含まれることがあります。このように、形式的な株式保有割合だけでなく、実質的な影響力がグループ会社の範囲を決める基準となっています。
グループ会社と子会社の違い
グループ会社と子会社はしばしば混同されますが、両者には明確な違いがあります。子会社は親会社によって経営を支配されている会社であり、グループ会社はその子会社を含む企業集団全体を指す概念です。つまり子会社はグループ会社の一部であり、グループ会社には子会社以外に親会社や関連会社も含まれるという関係になります。
子会社は親会社が議決権の過半数を保有しているか、または実質的に支配している会社を指します。一方、グループ会社という場合には、親会社が20%から50%の議決権を保有する関連会社や、親会社自身も含めた企業集団全体を指すのが一般的です。したがって、グループ会社という表現は子会社よりも広い範囲をカバーする概念であり、企業グループの全体像を示す際に用いられます。
関連会社との関係
グループ会社の中には、子会社以外に関連会社と呼ばれる企業も含まれます。関連会社とは、親会社が議決権の20%以上50%以下を保有し、経営に重要な影響を与えることができる会社のことです。子会社のように完全な支配下にはありませんが、経営方針や事業展開に一定の影響力を持つ点が特徴です。
関連会社は連結財務諸表において持分法が適用され、親会社の財務諸表に持分比率に応じた損益が反映されます。子会社のように財務諸表を完全に合算するわけではありませんが、グループ全体の業績を把握する上で重要な存在です。関連会社への出資は、完全な子会社化に至る前段階としての戦略的投資や、業務提携を強化する目的で行われることが多く、グループ経営の柔軟性を高める役割を果たしています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



子会社の定義と種類
子会社とは、親会社によって財務や営業の方針決定を支配されている会社のことを指します。会社法や会計基準において明確な定義があり、議決権の保有割合や実質的な支配関係によって判断されます。子会社にはいくつかの分類があり、それぞれ会計処理や法的な取扱いが異なるため、正確な理解が重要です。
子会社は企業グループの中核を成す存在であり、親会社の経営戦略を実行する役割を担います。事業の多角化やリスク分散、税務メリットの享受など、さまざまな目的で子会社が設立または取得されます。以下では、子会社の法的定義から具体的な種類まで詳しく解説します。
子会社の法的定義
子会社は会社法第2条3号において「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省で定めるものをいう」と定義されています。この定義によれば、議決権の過半数を保有していることが基本的な要件となりますが、それ以外の方法で経営を支配している場合も子会社に該当します。
会計基準である連結財務諸表基準では、親会社によって意思決定機関を支配されている会社を子会社と定義しています。具体的には、議決権の過半数を直接または間接的に保有している場合や、議決権が40%以上で役員の派遣などにより実質的に支配している場合が該当します。このように、法的定義と会計上の定義は基本的に一致していますが、実質的な支配関係を重視する点が現代の企業グループ経営において重要なポイントです。
支配関係の判断基準
子会社かどうかを判断する際には、形式的な株式保有割合だけでなく、実質的な支配関係の有無が重要な基準となります。会社法や会計基準では、以下のような要件を総合的に判断して支配関係を認定します。
| 判断基準 | 内容 | 子会社該当性 |
|---|---|---|
| 議決権50%超保有 | 親会社が単独で議決権の過半数を直接保有 | 該当 |
| 議決権40%以上+実質支配 | 議決権40%以上かつ役員派遣や重要な財務方針決定への関与 | 該当 |
| 議決権20%以上50%未満 | 重要な影響はあるが支配には至らない | 関連会社 |
| 議決権20%未満 | 単純な投資先 | 非該当 |
実質的な支配関係を判断する際には、取締役会の構成員の過半数を親会社が実質的に決定できるか、重要な財務および営業の方針決定を親会社が支配しているか、といった点が考慮されます。また、親会社と子会社の間に緊密な取引関係があり、子会社が親会社に経済的に依存している場合なども、支配関係を認定する要素となります。これらの判断基準は、企業の実態に即した適切なグループ経営を実現するために設けられています。
子会社の分類と特徴
子会社にはいくつかの分類があり、それぞれ会計処理や経営管理の方法が異なります。主な分類として、完全子会社、連結子会社、非連結子会社の3つがあります。これらの違いを理解することは、適切なグループ経営戦略を立案する上で不可欠です。
完全子会社とは、親会社が議決権の100%を保有している子会社のことです。親会社が完全に経営権を掌握しているため、意思決定の迅速性や経営方針の一貫性が確保しやすく、グループ経営の効率化を図りやすいという特徴があります。連結財務諸表においては、完全子会社の財務諸表は100%親会社の財務諸表に合算されます。
連結子会社とは、親会社が議決権の過半数を保有するか、または実質的に支配している子会社で、連結財務諸表に合算される会社のことです。完全子会社も連結子会社の一種ですが、連結子会社には少数株主が存在する場合もあります。少数株主持分は連結貸借対照表において純資産の部に別途表示され、連結損益計算書では非支配株主に帰属する当期純利益として区分されます。
非連結子会社とは、法的には子会社に該当するものの、重要性の原則により連結財務諸表の対象から除外される子会社のことです。具体的には、一時的に支配している場合や、事業規模が極めて小さく連結の範囲に含めても連結財務諸表に重要な影響を与えない場合などが該当します。非連結子会社は持分法の対象となるか、または単純な投資として処理されます。
M&Aによる子会社化の手法
M&Aによって子会社化を実現する方法には、複数の枠組みが存在します。それぞれの手法には特徴があり、目的や状況に応じて最適な枠組みを選択することが重要です。子会社化の主な手法としては、株式取得、事業譲渡、会社分割、株式交換などがあり、税務や法務の観点からも慎重な検討が必要です。
M&Aは本来、合併と買収を指す言葉ですが、広義には企業の買収や統合に関わるあらゆる取引を含みます。子会社化は買収の一形態であり、売り手企業を存続させながら経営権を取得する点が特徴です。以下では、実務で用いられる主要な子会社化手法について詳しく解説します。
株式取得による子会社化
株式取得は最も一般的な子会社化の手法であり、売り手企業の既存株主から株式を譲り受けることで経営権を取得します。株式譲渡契約を締結し、議決権の過半数以上を取得することで、対象会社は買い手企業の子会社となります。株式取得のメリットは、対象会社の法人格や契約関係をそのまま維持できる点です。
株式取得の手続きは比較的シンプルで、売り手と買い手の合意があれば実行可能です。中小企業の場合、株主が少数であることが多く、全株主との交渉がスムーズに進めば短期間での子会社化が実現します。ただし、対象会社に簿外債務や偶発債務が存在する場合、それらも含めて引き継ぐことになるため、事前調査が重要となります。
株式取得価格の算定には、時価純資産法、DCF法、類似会社比較法などが用いられ、対象会社の事業価値や将来性を総合的に評価します。取得価格が純資産を上回る部分はのれんとして資産計上され、一定期間にわたり償却されます。税務上も株式取得は資本取引として扱われ、売り手株主には譲渡所得税が課税される点に留意が必要です。
事業譲渡による子会社化
事業譲渡は、売り手企業の事業に関する資産や負債、契約関係などを個別に譲り受ける手法です。株式取得とは異なり、会社そのものではなく事業の一部または全部を取得する点が特徴です。事業譲渡によって取得した事業を新設した子会社に移転することで、子会社化を実現することができます。
事業譲渡のメリットは、譲り受ける資産や負債を選別できる点にあります。簿外債務や不要な資産を引き継がずに済むため、リスクを最小限に抑えることが可能です。一方で、個別の資産移転や契約の巻き直しが必要となるため、手続きが煩雑になりやすく、取引先や従業員の同意取得に時間がかかる場合があります。
事業譲渡は消費税の課税対象となるため、譲渡対価に消費税が加算されます。また、不動産が含まれる場合には不動産取得税や登録免許税などの諸費用も発生します。税務面でのコストを考慮しながら、他の枠組みとの比較検討が重要です。事業譲渡後に新設子会社を設立し、譲り受けた事業を移転することで、グループ内での効率的な事業運営が実現できます。
会社分割による子会社化
会社分割は、会社の事業部門を切り出して別会社に承継させる方法です。吸収分割と新設分割の2つの形態があり、さらに対価の受取先によって分社型分割と分割型分割に区分されます。会社分割を利用することで、特定の事業部門を独立した子会社とすることができます。
吸収分割は既存の会社に事業を承継させる方法であり、新設分割は新しく会社を設立して事業を承継させる方法です。分社型分割では対価が分割元の会社に交付され、分割型分割では分割元の株主に直接交付されます。子会社化を目的とする場合には、新設分割で子会社を設立し、親会社が100%の株式を取得する分社型分割が一般的に用いられます。
会社分割のメリットは、包括承継により事業に関する権利義務を一括して移転できる点です。個別の契約巻き直しが不要なため、事業譲渡に比べて手続きが簡便です。また、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置を受けることができ、譲渡損益の計上を繰り延べることが可能です。ただし、会社分割には債権者保護の手続きや株主総会の特別決議が必要となるため、実行までに一定の期間を要します。
株式交換による完全子会社化
株式交換は、既存の会社を完全子会社化するための方法です。対象会社の株主が保有する株式を、買い手企業の株式と交換することで、対象会社は買い手企業の完全子会社となります。現金を用いずに完全子会社化できる点が大きな特徴です。
株式交換のメリットは、買い手企業が多額の現金を用意する必要がない点です。自社株式を対価として交付するため、資金負担を抑えながら完全子会社化が実現できます。また、適格株式交換の要件を満たせば、対象会社の株主に対する課税が繰り延べられるため、税務上のメリットもあります。
株式交換を実行するには、両社の株主総会において特別決議による承認を得る必要があります。また、株式の交換比率の算定には専門的な企業価値評価が必要となり、公正な比率を設定することが重要です。株式交換後は、対象会社の既存株主が買い手企業の株主となるため、買い手企業の株主構成が変化する点にも留意が必要です。上場企業同士のM&Aでは株式交換が多く用いられ、グループ経営の強化や経営統合の手段として活用されています。
子会社化のメリットとデメリット
子会社化には多くのメリットがある一方で、デメリットやリスクも存在します。親会社側と子会社側それぞれの視点から、メリットとデメリットを正確に理解することが、適切な経営判断を行う上で不可欠です。特に税務面でのメリットは大きく、グループ経営の効率化にも寄与しますが、同時に管理コストや連帯責任のリスクも考慮する必要があります。
以下では、子会社化によって親会社が得られるメリットとデメリット、そして子会社となる側が受ける影響について、実務的な観点から詳しく解説します。
親会社側のメリット
親会社が子会社を持つことで得られるメリットは多岐にわたります。まず、責任の明確化と業績管理の効率化が挙げられます。事業部門を別法人化することで、部門ごとの損益が明確になり、経営の透明性が向上します。これにより、業績評価や経営責任の所在が明確になり、各事業のパフォーマンスを正確に把握できるため、迅速な経営判断が可能となります。
また、税務上のメリットがあります。連結納税制度やグループ法人税制を活用することで、グループ内の利益と損失を通算し、税負担を最適化できます。特に中小企業の場合、資本金1億円以下の子会社は所得800万円以下の部分について軽減税率15%が適用され、税負担の軽減が図れます。この税制は、企業グループ全体の資金効率を向上させる重要な要素です。
さらに、資本金1000万円未満の新設子会社は、設立後の一定期間消費税の免税事業者となる特典を享受できます。この特典は通常2年間適用されますが、条件や期間については適切に確認する必要があります。これらの税務上のメリットを活用することで、親会社はグループ全体の税務戦略を最適化し、財務の安定性を向上させることが可能です。
親会社側のデメリット
子会社化には多くのメリットがある一方で、親会社が直面するデメリットも存在します。主なリスクは、子会社の不祥事や経営上の問題が親会社に波及する可能性です。子会社が重大な不祥事を起こした場合、親会社は社会的な責任を問われ、グループ全体の信用が損なわれる恐れがあります。
また、子会社の管理には相応のコストと労力が必要です。連結決算の作成や内部統制の構築、コンプライアンス体制の整備など、事務作業や会計処理の負担が増加します。特に子会社が複数ある場合、それぞれの管理に相当なリソースを割く必要があり、管理コストが膨らむ傾向があります。
さらに、子会社が赤字に陥った場合、親会社がその損失を補填しなければならない状況に直面することもあります。子会社の財務状況が悪化すれば、親会社からの資金支援や債務保証が必要となり、親会社の財務健全性にも影響を及ぼす可能性があります。子会社化を検討する際には、これらのリスクを十分に評価し、適切なリスク管理体制を構築することが不可欠です。
子会社側のメリットとデメリット
子会社となる側にもメリットとデメリットが存在します。子会社化される企業にとって最大のメリットは、親会社からの経営支援や資金支援を受けられる点です。大企業グループの傘下に入ることで、経営ノウハウやブランド力を活用でき、事業成長の機会が広がります。また、親会社のネットワークを通じて新規取引先の開拓や事業領域の拡大が期待できます。
資金面でも、親会社からの資金調達が容易になり、金融機関からの融資条件も改善される可能性があります。親会社の信用力を背景に、より有利な条件での資金調達が可能となり、事業投資や設備投資を積極的に進めることができます。さらに、親会社が持つ技術力や人材を活用することで、競争力の強化や業務効率の改善も実現できます。
一方で、子会社化によるデメリットも無視できません。最も大きな影響は、経営の独立性が失われる点です。子会社は親会社との支配関係において、事業方針や経営判断が親会社の意向に従う必要があります。そのため、独自の事業戦略を展開しにくくなる場合があります。
さらに、親会社の不祥事が子会社の事業に悪影響を及ぼすリスクもあります。親会社がコンプライアンス上の問題を起こした場合、子会社も風評被害を受け、取引先との関係に支障が出る可能性があります。社名変更やブランドの統一を求められることもあり、長年築いてきた独自のブランドイメージが失われる懸念もあります。子会社化を受け入れる際には、これらのデメリットを十分に検討し、親会社との間で明確な経営方針の合意を形成することが重要です。
グループ会社経営の実務ポイント
グループ会社経営を成功させるためには、法務・税務・会計の各面で適切な実務対応が求められます。単に子会社を設立したり買収したりするだけでなく、グループ全体を統括する仕組みやガバナンス体制の構築が不可欠です。特に中小企業がグループ経営に移行する際には、専門家の助言を得ながら段階的に体制を整備していくことが重要です。
以下では、グループ会社経営において留意すべき実務上のポイントについて、具体的に解説します。
連結決算と会計処理
グループ会社を持つ企業は、個別決算だけでなく連結決算の作成が必要となります。連結決算では、親会社と子会社の財務諸表を合算し、グループ全体の財政状態と経営成績を示します。連結財務諸表の作成には、個別財務諸表の単純合算だけでなく、グループ内取引の相殺消去や未実現利益の調整など、専門的な会計処理が求められます。
連結決算において特に重要なのは、のれんの会計処理です。子会社を取得した際に支払った対価が、取得時の純資産の時価を上回る場合、その差額はのれんとして無形固定資産に計上されます。日本基準では、のれんは最長20年以内の期間で規則的に償却されます。のれんの償却費は連結損益計算書に費用として計上され、グループ全体の利益を減少させる要因となります。
連結決算の作成には、各子会社からタイムリーに正確な財務情報を収集する体制が必要です。会計方針の統一や決算日の調整、連結パッケージの作成など、グループ全体で協調した決算業務の遂行が求められます。上場企業や大企業では連結決算が義務付けられていますが、中小企業でも金融機関からの要請や事業承継対策の一環として連結決算を作成するケースが増えています。
税務戦略とグループ税制
グループ会社経営における税務戦略の立案は、グループ全体の税負担を最適化し、キャッシュフローを改善する上で重要です。連結納税制度を適用すれば、親会社と完全子会社の損益を通算し、グループ全体での課税所得を計算できます。黒字の会社と赤字の会社が混在する場合、損益通算によって全体の税負担を軽減できます。
連結納税制度を適用するには、親会社が完全支配関係にある子会社を原則すべて連結納税グループに含める必要があります。適用には事前の承認申請が必要で、いったん適用を開始すると一定期間は継続適用が求められます。連結納税制度は制度が複雑であるため、税理士などの専門家のサポートが重要です。
グループ法人税制も重要な税務メリットをもたらします。完全支配関係にある法人間で資産を譲渡した場合、譲渡損益の計上を繰り延べることができ、グループ内での資産移転を税務上有利に行えます。また、受取配当金の益金不算入制度により、子会社からの配当金を親会社が受け取る際の税負担も軽減されます。これらの税制を適切に活用することで、グループ経営の効率性と収益性を高めることが可能です。
ガバナンスとリスク管理
グループ会社経営においては、適切なガバナンス体制の構築が重要です。親会社は子会社の経営を監督し、グループ全体の企業価値向上を図る責任を負います。そのためには、子会社への役員派遣や内部統制システムの整備、定期的な経営報告の仕組みなどを構築する必要があります。
リスク管理の観点からは、子会社の事業リスクやコンプライアンスリスクを適切に把握し、問題が発生する前に予防的な措置を講じることが重要です。子会社が独立して事業を行う中で、親会社の方針から逸脱した行動を取らないよう、定期的なモニタリングと経営指導が求められます。特に不正や法令違反のリスクについては、内部監査や外部監査を活用して厳格なチェック体制を敷く必要があります。
また、グループ内取引においては、独立企業間価格の原則に基づいた適正な取引条件を設定することが重要です。税務当局から移転価格税制の適用を受けないよう、取引価格の妥当性を文書化し、説明責任を果たせる体制を整えておくことが求められます。グループ会社経営は単なる資本関係の構築にとどまらず、適切な管理体制と戦略的な運営によって初めて真の価値を生み出します。
まとめ
グループ会社と子会社の違いを正確に理解することは、企業の成長戦略やM&Aを検討する上で重要です。グループ会社は親会社・子会社・関連会社を含む企業集団全体を指し、子会社は親会社に経営を支配されている会社を意味します。子会社化の手法には株式取得、事業譲渡、会社分割、株式交換などがあり、それぞれの特徴を理解して最適なスキームを選択することが求められます。
子会社化には責任の明確化や税務上のメリット、経営資源の共有といった多くのメリットがある一方で、管理コストの増大や連帯責任のリスクも存在します。グループ会社経営を成功させるためには、連結決算や税務戦略、ガバナンス体制の構築など、実務面での適切な対応が重要です。専門家の助言を得ながら、グループ全体の企業価値向上を目指した経営を実践していくことが重要です。
グループ会社や子会社化に関するご相談、M&Aによる事業承継や成長戦略の実現に向けたサポートについては、豊富な実績を持つM&Aロイヤルアドバイザリーが最適なソリューションをご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。