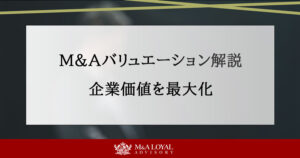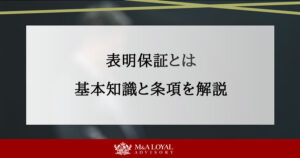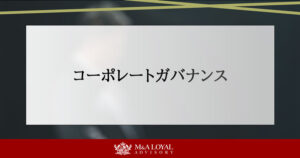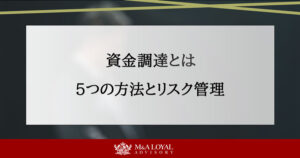総数引受契約とは?M&Aや資金調達の現場で選ばれる理由と注意点
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
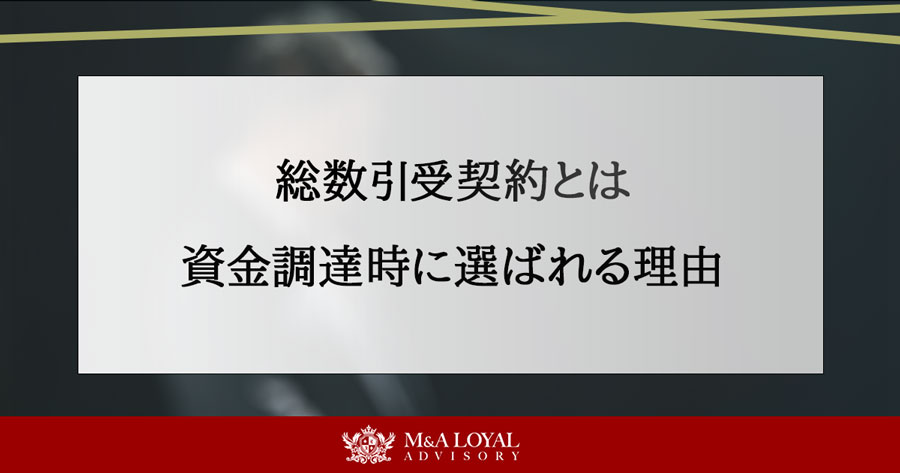
総数引受契約は、株式や社債の発行時において“発行企業が資金を調達するための仕組み”として注目されています。とくにM&AやIPO、資金調達の実務に携わる経営者・CFO・財務法務担当者にとっては、その仕組みを正しく理解し、戦略的に活用することが極めて重要です。
本記事では、「総数引受契約とは何か」という基礎から始まり、実務経験に基づいた交渉ノウハウ・契約設計・成功事例を通じて、どのようにこの契約を活かせるかを【5つの実践ステップ】で解説します。
「どう使えるか?」「メリットは?」「導入の手順は?」という疑問に的確に応える構成で、貴社の課題解決に直結する読み応えある情報を提供します。
目次
総数引受契約とは?M&A・資金調達における基礎理解
総数引受契約の定義と基本特徴
「総数引受契約(そうすうひきうけけいやく)」は、企業が新規株式を発行する際に、証券会社など特定の引受人がすべての株式を買い取る契約方式を指します。この方式は、発行体にとっては販売成否に関わらず、一定の価格で確実に資金を得られるという大きな利点があります。
発行体が公募などを通じて広く資金を集めようとする場合、市場の反応が読めない中で「資金が調達できなかった」というリスクは常に付きまといます。総数引受契約を活用することで、このリスクを証券会社側に移転することが可能となり、資金調達の安定性を高めることができます。
一方で、証券会社は引受けた証券が市場で売れ残るリスクを抱えることになるため、発行体の財務状態や事業計画、市場動向などを慎重に評価したうえで契約条件を設定します。そのため、発行体にとっても信用力の証明や綿密な開示準備が求められます。これは単なる販売契約ではなく、企業と金融市場を結ぶ信頼契約とも言えるのです。
主要方式の詳細比較
資金調達時に用いられる引受方式は主に以下の3つに分類され、それぞれ特徴と適用場面が異なります。
- 総数引受契約:証券会社が全量を事前に引き受け、発行体は確実に資金を確保できる。リスクは証券会社に集中し、その分、手数料などの条件は高めに設定される傾向がある。
- ベストエフォート方式:証券会社が最大限努力して販売を行うが、売れ残った場合の責任は負わない。発行体にとっては調達不確実性が残るものの、コストは抑えられる。
- スタンバイ引受契約:販売未達分を証券会社が引き受ける契約。一定の資金調達の保証を担保しつつ、市場の状況を柔軟に取り込める設計が可能。
これらの方式は、調達金額、発行体の信用力、市場環境、発行スケジュールなどを踏まえ、適切に選択する必要があります。特に大規模な増資やM&A資金調達では、総数引受契約の選択が検討されるケースが多く見られます。
総数引受契約が選ばれる社会・市場的背景
この契約形態が特に選ばれる背景には、近年の企業財務戦略や資本市場の構造的変化が挙げられます。以下の点が代表的です。
- 資金調達の確実性:M&A資金、再建資金など、特定のタイミングで必ず確保すべき資金調達には極めて適しており、プロジェクト推進の信頼性を高めます。
- 発行体の信用力アピール:証券会社がリスクを取って引き受ける体制は、発行体の信用力を対外的に証明する手段となり、IR・投資家対応にも好影響を与えます。
- 市場へのポジティブシグナル:販売失敗リスクが排除されることで、投資家に対して安定性と透明性の高い案件であると認識されやすくなります。
- 経営戦略と資本政策の整合:確実な資金確保によって、事業戦略や投資実行計画に柔軟性を持たせることができ、スピード感ある意思決定を実現できます。
このような背景から、総数引受契約は単なる契約手法を超えた、経営戦略の一環としての意味合いも強まっているのです。
国内外での導入事例と制度比較
日本では、IPOや増資、転換社債の発行、再上場案件などで総数引受契約が広く利用されています。近年では、非上場企業のプレIPO調達やスタートアップのシリーズC以降の資金調達でも、一定の需要が高まっています。
一方、海外とくに米国ではSEC(証券取引委員会)の登録制度や「Shelf Registration(棚卸登録制度)」の下で、柔軟な総数引受スキームが発展しています。引受団に対する情報開示義務や、投資家保護の規定も整備されており、契約の自由度と安全性のバランスが重視されています。
このように、制度的背景や文化的前提が異なる中で、日本企業がグローバルな資金調達を行う際には、現地制度に即した契約設計と事前準備が不可欠です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



契約交渉で焦点となる実務論点とは?
引受価格の決定プロセス
引受価格は発行体と証券会社双方の利益に大きく関わるため、慎重な交渉と設計が必要です。価格決定の際に考慮される要素には、以下があります。
- 同業他社の類似事例と市場価格動向(過去の引受価格や公募価格の分布)
- 発行体の財務健全性、信用格付け、成長可能性(財務3表+中期経営計画)
- ボラティリティや需給バランスといったマーケットリスク(業種特性、時価総額水準、PER比較など)
- 投資家層に応じた需要予測(ブックビルディング結果やIR活動をもとに)
これらを基に価格レンジやプレミアムを調整し、発行体にとって適切な資金調達を実現します。
また、価格の確定にあたっては、マーケティング過程での投資家需要の状況や、価格形成の透明性を確保するためのディスカッションが重要になります。証券会社側も自社のリスクを抑えつつ適正な利幅を確保する必要があり、価格調整メカニズム(価格レンジ提示、見直し条項など)の組み込みが実務的に行われます。
事前のバリュエーションにはDCF法・類似企業比較・市場取引倍率などが用いられ、投資家との齟齬を避けるための適切な開示資料作成とアナリストとの対話も並行して行われる必要があります。
シンジケート組成の実務と注意点
シンジケートとは、複数の証券会社が共同で引受を行う体制です。大型調達や分散販売が求められる案件で採用されます。
- 各社の役割分担(リード・共同主幹事・幹事)
- 販売ネットワークや顧客基盤の組み合わせ(国内外の機関投資家・個人富裕層など)
- リスク負担の比率と契約責任の分配(プロラタ方式・実績配分型など)
- 契約書における情報共有義務や販売報告要件(定時報告・販売残リスト等)
特に注意すべきは、リード証券会社とサブアレンジャー間の責任関係と、意思決定の迅速性です。複数社が関与するため、調整と管理体制を整備しないと、情報の齟齬や責任の分散によるトラブルにつながる恐れがあります。
シンジケート協定書には、重大な意思決定の手順(価格変更、クロージング延期など)を明確に定め、緊急時の対応フローまで含めておく必要があります。さらに、案件の規模やタイミングに応じて、海外証券会社の参加や、法的・税務的観点からの国際的対応力も考慮すべき要素となります。
販売手数料・費用構造の設計
手数料は証券会社のインセンティブ設計にも関わるため、単なる経費ではなく、調達成功へのモチベーションを左右する重要項目です。
- 固定報酬型 vs 成果報酬型(フラット手数料 or 販売達成時ボーナス)
- 一定販売量超過時のインセンティブ設計(スライディングスケール方式)
- 最低保証報酬の有無(引受努力義務の明文化)
- スケジュール遅延時のペナルティ条項(開示延期、販売未達による違約金など)
発行体にとってはコスト最適化、証券会社にとっては販売努力の誘因になるような設計が望まれます。また、販売期間中の市場状況変化にも対応できる柔軟な手数料構造(段階制・条件付き加算等)を導入することで、引受側の行動変容を促す効果も期待されます。
近年では、SDGs関連ファイナンスなどで成果指標連動型報酬(KPI-linked fee)などの導入もあり、契約交渉の自由度と多様性が増しています。
契約条項とリスク共有のポイント
契約交渉では、マーケットリスクや発行中止リスクなどに対応する条項の整備が重要です。
- クロージング条件(法的・財務的前提:例)債務超過の解消、監査意見の取得)
- マーケットアウト条項(相場急変による解除:例)日経平均○%下落等)
- 表明保証と解除条項の整合性(表明違反時の即時解除・損害賠償)
- 販売未達時のスタンバイ条項の適用有無(販売残数分の買取義務条件)
パンデミック、戦争、自然災害などの外的環境の変化により、プロジェクト全体が遅延または中断するリスクがあることを踏まえ、フォース・マジュール条項の整備は不可欠です。リスク最小化の観点からも、こうした不可抗力事由に対応可能な柔軟かつ網羅的な契約解除・履行猶予の条件をあらかじめ定めておくことが重要です。
あわせて、実行期間の延長に関する規定や、クロージングまでに必要な条件整備(例:法務意見書の取得や関係当局の許認可確認)といった契約書の技術的設計項目も、プロジェクト推進における重要な成功要因となります。
契約書のドラフティング過程では、社内の法務・財務・IR部門との連携を密に行い、全ステークホルダーが合意できる条文とスケジュール感を明記することが求められます。
このように、契約交渉は価格や販売枠の調整にとどまらず、広範なリスクマネジメントと企業戦略の整合性を重視した合意形成のプロセスであるべきなのです。
【5つのステップ】総数引受契約を成功に導く実務プロセス
ステップ1:資金調達の目的と規模を確定する
総数引受契約の準備は、資金調達の目的と必要金額の明確化から始まります。この段階では、以下のような点を徹底的に洗い出す必要があります:
- 調達資金の具体的用途(M&A、運転資金、設備投資、借入金返済など)
- 想定調達額とそれに対する財務インパクト(希薄化率、ROE改善、自己資本比率)
- 過去の資金調達履歴と市場からの評価
- 調達タイミングと企業イベント(決算発表、IR説明会)との整合
これらの要素を事前に整理することで、後続の交渉や契約設計における前提が明確になり、関係者全員が共通認識を持ったうえでプロジェクトを進行できます。特に総数引受契約においては、調達の確実性が前提となるため、この段階での精緻な資金計画が不可欠です。総数引受契約を活用することで、発行体は早期かつ安定的に資金を得られる体制を整えることができるのです。
ステップ2:証券会社の選定と初期交渉
次に、総数引受契約を締結する証券会社を選定します。このフェーズでは、以下の観点から比較・評価を行います:
- 過去の引受実績と成功案件の数
- 業界特性への理解とカバレッジ体制
- 投資家ネットワーク(国内・海外の機関投資家、リテール向け)
- 提示された契約条件(手数料、保証条件、販売計画)
- 規制対応やコンプライアンス体制の信頼性
総数引受契約の交渉においては、証券会社のリスク受容度と経験値が契約の成否を大きく左右します。候補となる複数の証券会社に対してRFP(提案依頼)を実施し、面談・条件交渉を経て、パートナー選定に至ります。ここで早期に社内承認ルートと稟議スケジュールも整理しておくと、契約手続きが円滑に進みます。総数引受契約では、証券会社が全量を引き受けるという特性上、初期段階での信頼関係構築と条件整備が成功の鍵を握ります。
ステップ3:契約内容と販売体制の設計
証券会社が決まったら、次に総数引受契約の具体的な契約書の詳細設計と販売体制の構築に移ります。ポイントは以下の通りです:
- 契約条項(クロージング条件、解除条件、マーケットアウト条項等)の文言精査
- 引受条件の明文化(Hard vs Soft Commitment)
- スケジュール、販売フェーズ、報告義務の明示
- IR戦略と連動した販売支援体制の構築
- 取締役会・株主総会等での承認取得とガバナンス対応
総数引受契約に基づくこのプロセスでは、企業と証券会社の信頼関係を築きつつ、スムーズな実行体制を整えることが求められます。このフェーズでは、社内法務、財務、IR、経営企画が密に連携し、開示文書や契約書の整合性チェックを並行して進める必要があります。また、証券会社との定期ミーティングによって進捗管理とリスク共有を徹底します。総数引受契約が含む責任の重さを踏まえると、契約の透明性と実行力は、両者にとっての安心材料となります。
ステップ4:価格・数量・シンジケートの確定
実務における核心は、総数引受契約に基づく発行価格・発行数量の確定とシンジケート体制の組成です。
- 想定価格レンジの提示と機関投資家からのフィードバック収集
- ブックビルディング(BB)方式を用いた実需の把握
- 市場環境を反映した価格調整と最終条件案の策定
- 主幹事証券+複数幹事による販売責任の分散と引受比率調整
- 最終契約書(Definitive Agreement)への署名準備
ここでは、販売スケジュールとIRイベントの整合性も再確認し、投資家との信頼関係を損なわないタイミングで価格を提示することが肝要です。特に、総数引受契約では証券会社が全量を引き受けるため、価格設定の合理性と市場受容性の両立が成功の鍵を握ります。総数引受契約の特徴を活かすことで、調達のスピードと確実性を両立させることができます。
ステップ5:クロージングとフォローアップ
価格・数量が確定した後、総数引受契約に基づくクロージング(払込)までの実務対応が始まります。
- 払込資金の受領、登記・法定書類の提出
- 契約条項に基づく販売報告と開示(有価証券報告書、適時開示など)
- 証券会社からの精算報告と手数料支払い
- 投資家向けのフィードバック対応(Q&A、アフターフォロー)
- 社内プロジェクトレビューとナレッジの蓄積(Post-Mortem)
ここで得られた教訓は、次回以降の調達活動の改善資源となります。プロジェクト終了後は関係部門と振り返りを行い、総数引受契約の契約実務の定型化とプロセス改善を図ることが、企業全体のファイナンス能力向上に直結します。総数引受契約を継続的な企業成長戦略の一環として定着させることで、資本市場との信頼関係を強固にすることができます。
総数引受契約を支える実務オペレーションと体制
総数引受契約の成立には、単なる契約書の取り交わしだけではなく、企業内部の管理体制と実務遂行能力が極めて重要な要素として機能します。本章では、契約成立からクロージング、さらにその後の投資家対応までを支えるオペレーション体制と必要な社内整備について、実務的観点から解説します。
プロジェクトマネジメント体制の構築
上場準備企業の場合、J-SOX(内部統制報告制度)対応と併せて文書の監査トレイルが問われるため、初期段階からの構造的整備が求められます。
- 担当部門:財務部、法務部、IR、経営企画、社外顧問(弁護士、FA)
- プロジェクトマネージャー(PM)設置による進捗管理
- ステークホルダー間の意思疎通フロー(週次会議、Slack/Teams連携)
- 社内向けガントチャートと対外スケジュールの統一
- タスクごとの責任者明確化とレビュー体制(レビューシート導入)
文書管理・開示体制の整備
引受契約では、大量の資料提出と継続開示義務への対応が求められます。これを支えるための文書管理体制は次のような点がカギとなります。
- Dataroomの設定とアクセス管理(社内/外部向け階層分け)
- 提出資料の標準テンプレート化(IRスライド、資本政策シート等)
- 開示資料の事前レビュー体制(法務部+証券会社との整合性確認)
- 取締役会資料・契約案などの電子署名フロー導入
- バックアップ・ログ保存のポリシー整備
また、特に上場準備企業の場合、J-SOX(内部統制報告制度)対応と併せて文書の監査トレイルが問われるため、初期段階からの構造的整備が求められます。
内部統制とガバナンス体制の連動
引受契約における情報漏洩やインサイダー取引を防止するためには、強固な内部統制が必要です。
- 非公開情報の管理規程(情報管理ポリシー、情報遮断ウォール)
- スタッフ教育と署名済NDA(部門横断での教育スケジュール)
- 重要情報のアクセスログ管理(閲覧履歴の自動記録)
- CRO(Chief Risk Officer)による情報監督体制
- モニタリングと定期的リスクアセスメント
近年では、サステナビリティやESGリスクも開示義務の対象となってきており、これら非財務情報の整理・報告もプロジェクトに統合する必要があります。
販売支援とマーケティング部門との連携
総数引受契約の成否は、投資家への適切なアプローチにも大きく依存します。販売フェーズでは、マーケティング部門とIR部門の連携が不可欠です。
- 投資家向け説明資料の作成(エクイティストーリー、成長戦略、競合比較)
- ロードショーの日程調整・運営(海外機関投資家を含む)
- 投資家からのQ&A対応フロー(標準化された回答フォーム)
- 証券会社との連携によるディールPR(メディア・業界誌の活用)
- コーポレートサイト・SNSでの情報一元化と整備
ここで得たフィードバックは、将来的な資本政策の見直し材料として蓄積されるべきです。オープンな姿勢での情報発信が、企業ブランド強化にもつながります。
社内教育とナレッジマネジメント
複雑な契約スキームを正確に理解し遂行できる人材育成も、引受契約の円滑な運営に不可欠です。
- 研修資料の整備(法務・財務・マーケティング各部門向け)
- eラーニング導入や外部講師の活用(引受契約・資本市場制度等)
- 過去案件の振り返り資料(Post-Mortem会議の実施)
- FAQや業務ハンドブックの整備・社内共有
- プロジェクト終了後のフィードバックセッションによる改善文化の醸成
社内での知識の蓄積と再利用が、次回以降の案件スピードと精度に直結します。ナレッジを属人化させない仕組み作りが、組織としての資本政策能力の向上に資するのです。
このように、総数引受契約を裏で支える体制は、法令遵守と業務効率、対外的信頼性のバランスを高度に維持する必要があります。実務の細部にまで配慮された体制こそが、契約全体の信頼性と成功確率を決定づけるのです。
トラブルを防ぐための契約リスク管理とチェックポイント
総数引受契約には高い信頼性と迅速性が求められる一方、細部の設計ミスや情報管理の不備が重大なトラブルを招く恐れもあります。本章では、契約過程で想定されるリスクと、それを防ぐためのチェックポイントについて、実務的に解説します。
市場リスクと価格変動への対応
契約締結から払込までの間に、市場環境が急変する可能性があります。
- マーケットアウト条項の明確化(急変時の契約解除条件)
- ブックビルディング期間の短縮と予備スケジュール設計
- 価格調整条項の組込み(ロックレンジ、下限設定)
- 市況変化を想定した内部レポートと早期アラート制度
これにより、価格変動リスクの軽減と市場との適正な価格整合を保つことができます。
情報漏洩とインサイダー対応
発行準備中の情報は、外部への漏洩や社内関係者の不正利用に注意が必要です。
- 社内外NDAの徹底(個別業務委託先まで適用)
- プロジェクトコードの使用と情報管理階層の明確化
- 開示情報の整合性確認(社外発表資料と内部文書の一致)
- 証券取引等監視委員会ガイドラインに沿った事前自己点検
定期的な研修や模擬ケース演習も効果的です。
契約条件の曖昧さによる解釈トラブル
実務では、文言の不備や条項の解釈により、後日トラブルに発展する事例もあります。
- リスク分担条項の文言チェック(主語・責任主体の明確化)
- 表明保証の対象と範囲(現状開示 vs 将来予測の扱い)
- 責任追及の条件と手続(重大違反時の即時解除条項など)
- 紛争解決方法の明記(裁判管轄・仲裁条項)
契約書のドラフトは法務部と複数回レビューを重ね、実務者間でのドラフト照合を行うべきです。
関係当事者間の連携不備
発行体・証券会社・外部専門家との連携不足は、進行遅延や誤解につながります。
- 連絡窓口の一本化と役割分担表の整備
- 週次または日次の進捗確認と報告フォーマット統一
- 認識齟齬時のエスカレーションルール設定
- 契約締結直前の全関係者ミーティング実施
クロージング前後の段取りを明確にするチェックリストを事前に共有しておくことも効果的です。
不測事態への備えとBCP(事業継続計画)
災害・システム障害・パンデミック等、外部環境による計画変更にも備えが必要です。
- 契約・払込期日変更のフレキシブル設計
- バックアップ証券会社とのサブ契約
- 主要文書のクラウド保存と遠隔対応体制(電子印鑑の整備)
- クロージング時点の最低限対応項目リストの作成
想定外に備えたBCPを設計しておくことで、トラブル時にも最小限の影響で対応可能になります。
このように、契約実務におけるリスクマネジメントは、万一に備えた体制と準備の積み重ねが鍵となります。リスクはゼロにはできなくても、発生時の影響を最小限にすることが実務家としての責任と言えるでしょう。
最新事例から学ぶ!成功・失敗ケーススタディ
理論や制度の理解だけでは、実務での成功は難しいのが総数引受契約の現実です。そこで本章では、近年の実例をもとに、成功事例と失敗事例を比較しながら、学ぶべき実務上の教訓を整理します。
成功事例:成長資金を確実に確保した上場企業のケース
ある成長著しい上場企業(製造業)は、新工場建設資金として80億円規模の資金調達を計画。経済情勢が不安定な中、総数引受契約を選択し、以下の対応を実行しました。
- 価格決定前に詳細なバリュエーションと市場分析を実施
- 投資家向け説明資料にKPIと将来PLモデルを明記
- 海外機関投資家も含めたロードショーを実施し、早期に需要を獲得
- 契約書にクロージングまでの進捗管理とKPI達成状況の逐次報告を明記
結果、希望額を超える需要が集まり、価格・スケジュールともに想定内で着地。IR効果も高く、株価も安定した推移を見せました。
成功要因:
- 契約前の実行可能性調査と投資家との早期対話
- リスク要素を契約条項に明記し、トラブルを回避
- 組織横断的な対応体制と担当者教育の充実
失敗事例:契約後の開示トラブルで価格修正に追い込まれた事例
一方で、IT企業X社では、約40億円の調達を予定していた総数引受契約において、クロージング直前に財務関連の開示遅延が判明し、大きな問題に発展しました。
- 内部監査未了のまま仮条件を発表し、投資家に不信感が拡大
- 証券会社との情報連携不足により、誤った開示が発生
- 再スケジューリング後も信用回復に至らず、調達額を30%削減
失敗要因:
- 開示プロセスに対する社内の理解不足
- コンプライアンス体制の未整備(情報管理規定が形式のみ)
- 社内稟議やクロスチェックの不備による情報の見落とし
この事例では、事前準備の不足と部門間連携の甘さが致命的な結果をもたらしました。
成功と失敗から学ぶ実務教訓
成功事例・失敗事例を比較することで、以下のような実務教訓が浮かび上がります。
- 契約前に全社体制を整備することが必須(プロジェクトマネジメントの導入)
- 投資家視点を常に意識した開示・IR戦略の設計
- 関係者全員への目的共有とリスク認識の徹底(Kick-offミーティングの開催)
- 文書・進捗の定期確認と社外レビューによる精度向上
- 不測事態を想定した柔軟な対応力とバックアッププランの準備
契約実務は「準備の質」がそのまま「成果の質」に直結します。成功企業のノウハウを体系化し、自社の資本戦略に落とし込むことが、今後の安定的な資金調達と企業価値向上への近道なのです。
総括:総数引受契約の本質と実務への提言
本記事を通じて、総数引受契約の基本構造から、実務プロセス、体制構築、リスク管理、そして実例分析までを詳細に解説してきました。最終章では、総数引受契約を正しく活用するための本質的なポイントと、実務家・経営者への具体的提言をまとめます。
総数引受契約の本質とは何か?
総数引受契約の最大の特徴は、発行体にとって「資金調達の確実性」を担保できる点にあります。特に以下のような状況下において、その有効性が顕著になります:
- タイムリーな資金確保が重要なM&Aや再編案件
- 市場環境が不安定でブックビルディング型が困難な局面
- 中小企業やIPO前企業など、信用構築段階の発行体
また、証券会社が全量を引き受けることで、投資家への販売リスクを一元管理でき、発行体は資金繰りに専念することが可能になります。
調達スキームの多様化と戦略的選択
近年、資金調達の手段はますます多様化しており、以下のような選択肢が存在します。
- 公募増資、第三者割当、ワラント債等
- 海外での144A/RegS発行
- ESGファイナンスやサステナブルボンド
- IPOと同時のプレIPOファイナンス
この中で、総数引受契約は「調達スピード」と「計画通りの実行性」という観点で非常に強力なツールです。戦略的なファイナンス設計の中で、他のスキームとの組み合わせや、短中期の資本政策に組み込むべき選択肢として検討すべきでしょう。
今後の実務に向けた提言
本稿の内容を踏まえ、発行体や実務担当者に対して以下の提言を行います:
- 社内の資本政策ガバナンスを強化すること(財務・IR・法務の三位一体)
- 情報管理と法令遵守を基盤とした信頼構築(インサイダー防止と誤開示対策)
- 中長期での資本戦略に沿ったスキーム設計(安易な短期志向を避ける)
- 証券会社との対等な関係構築と事前協議の徹底(受動的でなく、能動的な交渉)
- 成功事例のナレッジ化と社内教育の制度化(属人化防止と継承体制)
これらを実践することで、単なる資金調達にとどまらない「企業価値向上型」のファイナンスが可能となります。
最後に:専門家の伴走による安心設計
総数引受契約は高度な実務と調整が必要な分野です。そのため、外部専門家のサポートを得ることも有効な手段です。特に、資本政策やM&Aを専門とする支援会社と連携することで、契約設計から交渉、実行管理、開示対応に至るまで、ワンストップでの支援が可能になります。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。