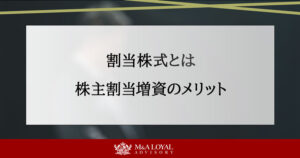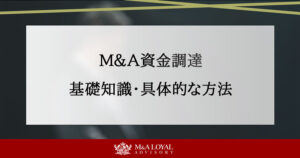第三者割当増資とは?メリットから株価への影響まで手続き完全ガイド
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
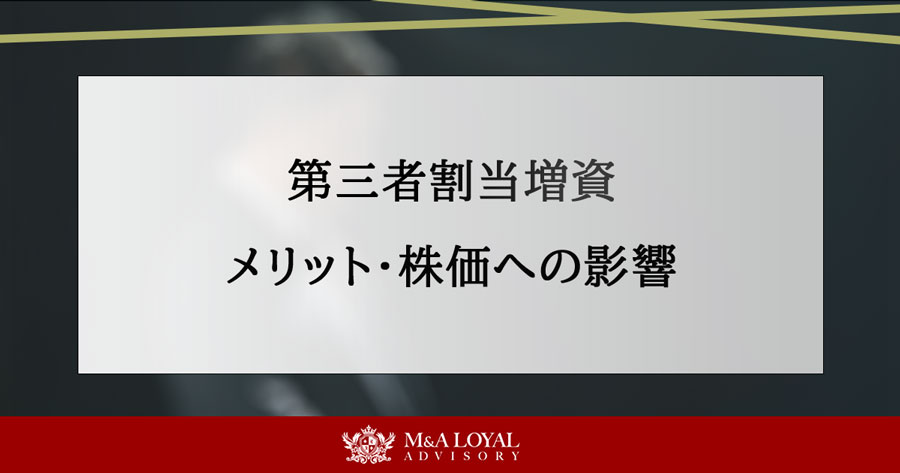
第三者割当増資とは、企業が特定の個人や法人など第三者に対して新株を発行し、資金を調達する方法です。公募増資や株主割当増資と異なり、出資者を選定できるため、戦略的なパートナーシップ構築や事業拡大の資金確保に適しています。近年、多くの企業が第三者割当増資を活用し、数十億円から数百億円規模の資金調達を実現しています。
本記事では、第三者割当増資の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、株価への影響、具体的な手続きの流れまで、会社売却やM&Aを検討する中小企業のオーナーが理解すべき内容を解説します。
目次
第三者割当増資の定義
第三者割当増資は、企業が成長資金やM&A資金を調達する際に選択される重要な手法の一つです。まずは、この増資方式の基本的な定義と増資全般の分類について理解しましょう。
第三者割当増資とは何か
第三者割当増資とは、既存株主以外の特定の第三者に対して有償で新株を割り当て、資金を調達する手法を指します。有償増資の一種であり、新株発行により企業は返済義務のない資本を調達できる点が特徴です。割当先は取引先企業、金融機関、ベンチャーキャピタル、個人投資家など多岐にわたります。
この方式では、発行企業が割当先を選定できるため、単なる資金調達にとどまらず、戦略的な資本業務提携や技術提携を組み合わせることができます。たとえば、製造業の企業が販売網を持つ大手商社に第三者割当増資を実施すれば、資金調達と販路拡大を同時に実現できます。
増資の分類と種類
増資には大きく分けて有償増資と無償増資があります。有償増資は対価として金銭や現物資産を受け取り新株を発行する方式で、無償増資は対価を受け取らずに株式を割り当てる方式です。無償増資は既存株主への株式配当や準備金の資本組み入れなどで用いられます。
有償増資はさらに、公募増資、株主割当増資、第三者割当増資の3つに分類されます。公募増資は不特定多数の投資家から広く資金を集める方式で、主に上場企業が大規模な資金調達を行う際に利用します。株主割当増資は既存株主の持株比率に応じて新株を割り当てる方式で、持分比率の維持が可能です。そして第三者割当増資は、特定の第三者に的を絞って新株を発行する方式となります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



第三者割当増資と他の増資方式の比較
第三者割当増資の特性を理解するには、他の増資方式との違いを明確に把握することが重要です。それぞれの増資方式には固有のメリットとデメリットがあり、企業の状況や目的に応じて最適な手法を選択する必要があります。
公募増資との違い
公募増資は、証券会社を通じて不特定多数の投資家に新株を割り当てる方式です。主に上場企業が活用し、数百億円規模の大規模な資金調達が可能となります。知名度向上や株式の流動性向上にも寄与しますが、証券会社への手数料や開示書類の作成コストが高額になる点がデメリットです。
公募増資では割当先を選べないため、戦略的なパートナーシップ構築は困難ですが、第三者割当増資では出資意欲の高い特定企業を選定でき、資本業務提携を組み合わせた成長戦略が実現できます。また、公募増資は準備期間が長く、市場環境に左右されやすい特徴がありますが、第三者割当増資は比較的短期間で実施できます。
株主割当増資との違い
株主割当増資は、既存株主の持株比率に応じて新株引受権を付与する方式です。既存株主の持分比率が維持されるため、支配権の希薄化を防ぐことができます。中小企業やオーナー企業が経営支配権を維持しながら資金調達したい場合に適しています。
ただし、株主割当増資では既存株主に出資余力がない場合、調達額が限定的になる課題があります。一方、第三者割当増資では資金力のある特定の投資家や企業から大規模な資金を調達でき、成長資金やM&A資金の確保に適しています。既存株主の持分は希薄化しますが、企業価値向上により株主全体の利益につながる可能性があります。
各増資方式の特徴比較表
以下の表は、第三者割当増資、公募増資、株主割当増資の主要な特徴を比較したものです。それぞれの方式の違いを視覚的に理解できます。
| 項目 | 第三者割当増資 | 公募増資 | 株主割当増資 |
|---|---|---|---|
| 割当先 | 特定の第三者 | 不特定多数の投資家 | 既存株主 |
| 調達規模 | 中規模から大規模 | 大規模 | 小規模から中規模 |
| コスト | 比較的低い | 高い | 低い |
| 実施期間 | 短期 | 長期 | 短期 |
| 既存株主の希薄化 | あり | あり | なし |
| 戦略的提携 | 可能 | 困難 | 不可 |
| 主な利用企業 | 未上場・上場企業 | 上場企業 | 未上場・中小企業 |
この表からわかるように、第三者割当増資は調達規模とコストのバランスに優れ、戦略的提携を組み合わせられる点で多くの企業にとって有力な選択肢となります。
第三者割当増資の目的
企業が第三者割当増資を実施する目的は多岐にわたります。単なる資金調達だけでなく、事業戦略や企業成長の観点から様々な活用シーンがあります。
資金調達手段としての活用
第三者割当増資の最も基本的な目的は、企業の成長に必要な資金を調達することです。新規事業への投資、設備増強、研究開発費用、運転資金の補充など、様々な用途に活用できます。特に、銀行融資では調達が難しい長期的な成長投資資金や、財務体質が弱い企業の資本増強に適しています。
返済義務のない資本を調達できるため、財務基盤が強化され、その後の銀行借入の際にも有利に働きます。また、M&Aを実施する際の買収資金としても活用されます。自社の成長戦略に共感する投資家から資金を得ることで、企業価値の向上を目指せます。
資本業務提携による関係強化
第三者割当増資は、単なる資金調達を超えて、戦略的パートナーとの関係構築に活用されます。たとえば、製造業の企業が大手商社に第三者割当増資を実施すれば、資金調達とともに販路拡大や海外進出のサポートを受けられます。技術系スタートアップがIT大手企業に新株を割り当てれば、資金に加えて技術支援や人材交流が期待できます。
このような資本業務提携では、出資者が一定の議決権を取得することで、経営への関与度が高まります。取締役の派遣や定期的な経営会議への参加などを通じて、出資者のノウハウや経営資源を活用できる点が大きなメリットです。金融機関からの出資を受ける場合は、信用力向上により取引条件の改善も期待できます。
事業承継やM&A戦略での活用
中小企業のオーナーにとって、第三者割当増資は事業承継やM&Aの準備段階としても有効です。後継者不在の企業が、将来の買収候補となる企業に対して第三者割当増資を実施し、段階的に経営権を移転していくケースがあります。この方法では、一度に全株式を譲渡するよりもリスクを分散でき、従業員や取引先への影響を最小限に抑えられます。
また、複数の企業から出資を受けることで、将来の買収候補を複数確保し、より有利な条件で最終的な事業承継を実現する戦略もあります。第三者割当増資により資本関係を構築した後、一定期間の協業を経て、相互理解が深まった段階で完全買収に移行するステップアップ方式が、近年注目されています。
第三者割当増資のメリット
第三者割当増資は、自社が選定した特定の第三者に新株を引き受けてもらうことで資金を調達する方法です。銀行借入のように返済義務がなく、出資者との関係構築を通じて事業シナジーを得られる点が大きな魅力です。ここでは、出資を受ける企業にとっての主なメリットを解説します。
出資を受ける企業のメリット
出資を受ける企業にとって、第三者割当増資の最大のメリットは資金繰りの安定です。銀行借入と異なり返済義務がないため、調達した資金を長期的な成長投資に活用できます。自己資本比率が向上することで財務体質が強化され、信用力が高まります。
また、出資者を選択できる点も大きな利点です。自社の事業戦略に合致する企業や、必要なノウハウを持つパートナーを選定することで、単なる資金調達以上の価値を得られます。取引先に出資してもらえば取引関係が強化され、安定的な販路確保につながります。
手続き面でも、公募増資に比べて簡便です。公開会社であれば取締役会決議で実施でき、証券会社への高額な手数料も不要です。
出資をする企業のメリット
出資する企業側から見た場合、第三者割当増資の主なメリットは、出資先企業との強固な関係性を構築できる点です。一定の議決権を取得することで、経営への関与が可能となり、戦略的な協業を進めやすくなります。連結決算の対象となれば、出資先の利益を自社の業績に取り込むこともできます。
また、完全買収と比べてリスクを分散できます。まずは少数株主として関係を構築し、将来的に持分を増やす段階的な投資戦略も可能です。出資先企業の成長により株式価値が上昇すれば、投資リターンも期待できます。
第三者割当増資のデメリット
第三者割当増資によって資金調達を行う際には、メリットだけでなくデメリットも十分に理解しておく必要があります。特に、既存株主の持分比率が希薄化することで経営支配権が低下するリスクや、出資者との関係悪化による経営介入など、経営の自由度に影響を与える可能性があります。また、資本金増加による税負担の増加や、既存株主個人への直接的な利益が得られない点にも注意が必要です。
出資を受ける企業のデメリット
第三者割当増資の最大のデメリットは、既存株主の持分比率が希薄化することです。オーナー企業の場合、経営支配権が低下し、意思決定の自由度が制約される可能性があります。議決権比率が出席株主の議決権の3分の2を下回ると特別決議ができなくなり、また、出席株主の議決権の2分の1を下回ると普通決議すらできなくなります。
また、株式譲渡と異なり、既存株主には直接的な対価が支払われません。新株発行により企業に資金が入るだけで、既存株主個人には現金が入らないため、オーナーの資産流動化には適していません。さらに、資本金が増加すると、法人住民税の均等割や登録免許税などの税負担が増える可能性があります。
出資者との関係悪化リスクも考慮すべきです。経営方針の相違や業績悪化時に、出資者から経営への介入が強まる可能性があります。特に、議決権比率が高い出資者がいる場合、経営の自由度が大きく制約される事態も想定しておく必要があります。
出資をする企業のデメリット
第三者割当増資は株式譲渡による買収と比較して、資金効率が悪い点が挙げられます。新株発行のため、既存株主の持分も残り、100%の議決権を取得できません。また、出資先企業の業績が悪化した場合、投資資金の回収が困難になるリスクもあります。
第三者割当増資が株価に与える影響
第三者割当増資の実施は、特に上場企業の場合、株価に大きな影響を及ぼします。株価が上昇するケースと下落するケースがあり、その要因を理解することが重要です。
株価下落の要因
第三者割当増資により株価が下落する主な要因は、株式の希薄化です。新株が発行されることで発行済株式数が増加し、1株あたりの利益(EPS)が低下します。株価は一般的にPER(株価収益率)×EPSで算出されるため、EPSの低下は株価の下落圧力となります。
特に、財務悪化の改善や資金繰りの悪化を理由とした増資は、市場から「ネガティブな増資」と受け止められ、株価が下落する傾向があります。投資家は企業の将来性に不安を感じ、売却に動くためです。また、有利発行(市場価格より大幅に安い価格での発行)が行われる場合も、既存株主の利益が損なわれるとして株価下落要因となります。
株価上昇の要因
一方、第三者割当増資が株価上昇につながるケースもあります。調達資金が新規事業の立ち上げや研究開発など、将来の成長に向けた前向きな投資に使われる場合、市場は企業価値の向上を期待して株価が上昇します。特に、技術開発型企業やスタートアップが大手企業から出資を受ける場合、信用力向上や事業シナジーへの期待から株価が上昇するケースが多く見られます。
また、出資先との資本業務提携による相乗効果が明確に示される場合も、株価にプラスの影響を与えます。たとえば、製造業の企業が大手商社から出資を受け、海外販路の拡大が具体的に見込まれる場合、将来の収益増加期待から株価が上昇する可能性があります。低位株(株価水準の低い銘柄)に対する注目度の高い企業からの出資は、市場の注目を集め、株価が急上昇することもあります。
株価への影響を左右する要素
株価への影響は、増資の目的、発行価格、希薄化の程度、出資者の属性、市場環境など、複数の要素によって決まります。発行価格が市場価格に近ければ希薄化の影響は限定的ですが、大幅なディスカウント価格での発行は株価下落圧力となります。
また、希薄化率(増資後の発行済株式数の増加率)も重要です。10%程度の希薄化であれば影響は軽微ですが、30%を超えるような大規模な希薄化は株価に大きな影響を及ぼします。出資者が信頼性の高い大手企業や著名な投資家である場合、市場の評価は高まりやすい傾向があります。
市場環境も無視できません。株式市場全体が上昇トレンドにある時期は、多少の希薄化があっても株価への影響は限定的ですが、市場が低迷している時期は、増資のネガティブな側面が強調されやすくなります。
第三者割当増資の手続き
第三者割当増資を実施するには、法律で定められた手続きを適切に進める必要があります。手続きの流れを理解し、期限を守って進めることが重要です。
募集事項の決定と通知
第三者割当増資の最初のステップは、募集事項の決定です。公開会社(株式譲渡制限のない会社)の場合は取締役会決議で決定できますが、非公開会社(株式譲渡制限がある会社)の場合は株主総会の特別決議が必要となります。特別決議とは、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議です。
決定すべき募集事項には以下が含まれます。
- 募集株式の数または上限数
- 募集株式の払込金額またはその算定方法
- 現物出資がある場合はその内容と価額
- 払込期日または払込期間
- 増加する資本金および資本準備金の額
募集事項が決定したら、既存株主および引受希望者に対して通知を行います。株主には株主総会招集通知や取締役会決議の内容を通知し、引受希望者には募集要項を提示します。
申し込みと割当の決定
引受希望者は、所定の申込書を提出して新株の引き受けを申し込みます。申込書には、氏名または名称、住所、引受希望株式数などを記載します。申し込みを受けた後、会社は取締役会(または株主総会)で割当先と割当株式数を決定します。
ただし、総数引受契約を結ぶ場合は、この申し込みと割当決定の手続きを省略できます。総数引受契約とは、募集株式の全部を特定の引受人が引き受ける契約で、手続きの簡素化と迅速化が可能となります。多くの第三者割当増資では、この総数引受契約方式が採用されています。
払い込みと登記手続き
割当が決定したら、引受人は指定された払込期日までに出資金を会社の指定口座に払い込みます。金銭出資の場合は銀行振込、現物出資の場合は現物資産の引き渡しにより出資が実行されます。払い込みが完了した時点で、引受人は株主としての権利を取得します。
払い込み完了後、会社は変更登記を行う必要があります。登記申請は払込期日の翌日から2週間以内に行わなければなりません。登記申請書には、株主総会議事録や取締役会議事録、払込証明書などの書類を添付します。登記を怠ると、過料の制裁を受けたり、休眠会社として解散扱いされるリスクがあるため、期限厳守が重要です。
第三者割当増資の手続きフロー表
以下の表は、第三者割当増資の手続きフローを段階的に整理したものです。各ステップの概要と必要な対応を確認できます。
| ステップ | 内容 | 決定機関 | 期限・注意点 |
|---|---|---|---|
| 1. 募集事項の決定 | 発行株数、払込金額、払込期日等を決定 | 公開会社:取締役会、非公開会社:株主総会 | 株主総会では特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上)が必要 |
| 2. 通知 | 株主・引受希望者への募集事項通知 | 会社 | 払込期日の2週間前までに通知または公告 |
| 3. 申し込み | 引受希望者が申込書を提出 | 引受希望者 | 総数引受契約の場合は省略可 |
| 4. 割当決定 | 割当先と株式数の決定 | 取締役会または株主総会 | 総数引受契約の場合は省略可 |
| 5. 払い込み | 出資金の払い込み実行 | 引受人 | 指定期日までに完了 |
| 6. 登記申請 | 資本金増加等の変更登記 | 会社 | 払込期日翌日から2週間以内 |
この表のように、第三者割当増資は複数のステップを経て実施されますが、総数引受契約を活用することで手続きを簡略化できる点がポイントです。
有利発行に関する規制
第三者割当増資を実施する際、特に注意が必要なのが有利発行の規制です。有利発行とは、時価と比較して著しく有利な価格で新株を発行することを指します。一般的に、時価より10%以上安い価格での発行は有利発行とみなされる可能性があります。
有利発行に該当する場合、既存株主の利益を保護するため、株主総会の特別決議が必要となります。公開会社であっても取締役会決議だけでは不十分で、株主総会での承認を得なければなりません。有利発行の手続きを怠ると、新株発行が無効となるリスクがあるため、発行価格の設定には慎重な検討が必要です。
第三者割当増資における株価算定の方法
第三者割当増資を実施する際、最も重要な決定事項の一つが発行価格です。適切な価格設定には、企業価値の算定が不可欠となります。上場企業と未上場企業では算定方法が異なります。
上場企業の株価算定
上場企業の場合、市場で形成されている株価が客観的な価値を示しているため、これを基準に発行価格を決定します。一般的には、直近1ヶ月間の平均株価や、公表日前営業日の終値などを基準とします。市場株価は日々変動するため、一定期間の平均値を用いることで価格の公平性を担保します。
ただし、市場株価がある場合でも、大規模な第三者割当増資や資本業務提携を伴う場合は、より詳細なデューデリジェンス(企業調査)を実施し、財務内容や事業計画を精査した上で発行価格を決定することもあります。特に、将来の成長性や出資者とのシナジー効果を考慮し、市場株価にプレミアムを上乗せするケースもあります。
未上場企業の株価算定手法
未上場企業の場合、市場株価が存在しないため、専門的なバリュエーション(企業価値評価)手法を用いて株式価値を算定する必要があります。主な算定手法には、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチの3つがあり、それぞれ異なる視点から企業価値を評価します。
コストアプローチは、企業の純資産に着目した評価方法です。簿価純資産法では、貸借対照表に記載された純資産額をもとに株式価値を算定します。時価純資産法では、資産や負債を時価に修正した上で純資産額を算定します。この手法は計算が比較的簡単で、安定した資産を持つ企業に適していますが、将来の収益性や成長性が反映されない点が課題です。
マーケットアプローチは、類似企業との比較により株式価値を算定する方法です。類似業種の上場企業の財務指標(PERやPBRなど)を用いて、評価対象企業の価値を推定します。市場の評価を反映できる点がメリットですが、適切な類似企業を見つけることが難しい場合や、未上場企業と上場企業の規模差が大きい場合は、精度が低下する可能性があります。
DCF法による株価算定
インカムアプローチの代表的な手法がDCF法(割引キャッシュフロー法)です。DCF法は、企業が将来生み出すキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法で、M&Aや第三者割当増資で最も広く用いられています。
DCF法では、まず事業計画に基づいて将来のフリーキャッシュフロー(営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを差し引いたもの)を予測します。次に、資本コスト(加重平均資本コスト:WACC)を用いて、将来キャッシュフローを現在価値に割り引きます。最後に、計算期間終了後の継続価値(ターミナルバリュー)を加算して、企業価値を算出します。
DCF法は将来の収益性や成長性を反映できる点で優れていますが、事業計画の精度や割引率の設定に主観が入りやすく、算定者によって結果が異なる可能性があります。そのため、複数の手法を併用し、結果を総合的に判断することが推奨されます。
株価算定における注意点
株価算定を行う際は、評価手法の選択以外にもいくつかの注意点があります。まず、算定の客観性を担保するため、外部の専門家(公認会計士やM&Aアドバイザー)に依頼することが望ましいです。特に、有利発行に該当する可能性がある場合や、大規模な増資の場合は、第三者による評価が不可欠となります。
また、評価時点も重要です。第三者割当増資の決議日、払込期日、基準日など、どの時点での価値を評価するかによって結果が変わる可能性があります。一般的には、取締役会決議または株主総会決議の直前時点での評価が用いられます。
さらに、少数株主の株式と支配株主の株式では、同じ企業の株式でも価値が異なります。議決権や経営参加の可能性を考慮し、少数株主の株式にはディスカウント(流動性ディスカウントや少数株主ディスカウント)を適用する場合があります。逆に、支配権を取得できる株式にはプレミアムが上乗せされることもあります。
まとめ
第三者割当増資は、特定の第三者に新株を割り当てる有償増資の手法で、資金調達と戦略的提携を同時に実現できる点に特徴があります。公募増資や株主割当増資と比較して、出資者を選定できることや手続きが簡便であることがメリットですが、既存株主の持分希薄化というデメリットも伴います。
株価への影響は増資の目的や発行価格、市場環境によって異なり、成長投資目的であれば株価上昇、財務改善目的であれば株価下落の傾向があります。手続きは募集事項の決定から登記まで複数のステップがあり、特に有利発行の規制や登記期限には注意が必要です。株価算定では、上場企業は市場株価を基準とし、未上場企業はDCF法などのバリュエーション手法を用いて適切な価格を決定します。
M&Aや事業承継を検討する中小企業のオーナーにとって、第三者割当増資は段階的な株式譲渡や資本業務提携の構築に有効な手法です。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、企業の状況に応じた最適な提案と実行支援を提供しています。M&Aや経営課題に関するご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。