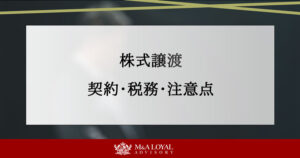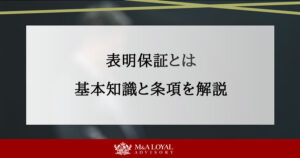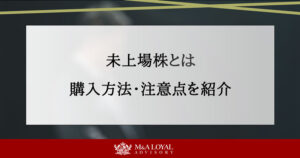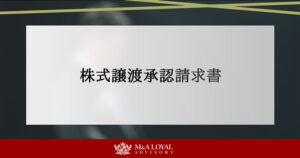株式譲渡契約書とは?印紙やひな形から書き方の注意点まで作成ガイド
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
株式譲渡契約書とは、M&Aにおいて最終契約書の一つであり、売り手と買い手の双方が株式譲渡に関して合意した内容を文書化した書類です。株式譲渡契約書は法的効力を持つため、正確に記載することが求められます。正しく記載することで、取引後のトラブルを避け、安全にM&Aを実行することができます。
本記事では、M&A取引をスムーズに進めるために、株式譲渡契約書の具体的な書き方や印紙の要否、作成時の注意点について詳しく解説します。また、書き方の例やひな形を活用する際に留意するポイントについてもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
株式譲渡契約書とは|SPAの目的と役割
株式譲渡契約書とは、企業や個人が保有する株式を他者に移転する際に、その条件や手続きを明文化した文書です。この契約書は法的拘束力を持ち、後のトラブルを未然に防ぐことができます。また、契約不履行や記載内容と相違があった場合の証拠としても機能します。そのため、M&Aにおいて株式譲渡契約書は欠かすことのできない重要な書類となります。
株式譲渡契約書は「SPA(Stock Purchase Agreement)」とも呼ばれ、譲渡する株式に関する内容や取引に関する項目が盛り込まれます。この契約書を作成することで、M&Aの透明性を確保し、買い手と売り手が安全に取引を進めることが可能になります。
株式譲渡契約書に印紙は不要?必要なケースも
M&Aスキームによっては契約書に印紙税が必要となる場合がありますが、株式譲渡契約書への収入印紙の貼り付けは原則として不要です。これは株式譲渡契約書が課税文書に該当しないためです。課税文書とは、印紙税法によって定められた印紙税が必要となる文書のことを指します。
課税文書は1号から20号まで分類されており、事業譲渡や合併、会社分割に関する契約書はこれに含まれますが、株式譲渡契約書は含まれていません。ただし、譲渡代金が既に支払われており、契約書に譲渡代金を受領した旨が記載されている場合は、第17号文書に該当し、収入印紙が必要となります。
印紙が必要な場合の印紙税は、契約書に記載されている代金によって異なります。1億円以下の印紙税は以下の通りです。
| 契約書に記載の譲渡代金 | 収入印紙税 |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超え2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超え3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超え1億円以下 | 2万円 |
参考:国税庁|印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式譲渡契約書に必要な記載事項
株式譲渡契約書に記載する内容として、以下の項目があります。
| ・譲渡合意 ・譲渡対価の金額 ・譲渡対価の支払い方法 ・譲渡実行の前提条件 ・譲渡実行の手続き ・表明保証 ・契約解除 ・損害賠償 ・秘密保持 ・競業避止義務 ・合意管轄 |
これらの記載事項は株式譲渡契約書の基本であり、内容が不明瞭な場合、後にトラブルが発生する可能性があります。そのため、契約書を作成する際には、M&A仲介会社や弁護士などの専門家の助言を受けることを強く推奨します。専門家のサポートを得ることで、契約内容の記載漏れを防ぐことができ、適切なリスク管理が可能となります。
譲渡合意
株式譲渡契約書の譲渡合意条項には以下の内容が記載されます。
| ・譲渡日 ・会社名 ・会社の所在地 ・譲渡する株式の数 ・譲渡する株式の種類 |
譲渡合意では次のポイントに留意します。
- 譲渡する株式の種類と数を正確に記載すること。普通株式や優先株式など、対象となる株式の種類も明記。
- 譲渡日や譲渡時期を明確に記載し、契約の効力発生日をはっきりさせること。
- 譲渡の対象となる株主や譲渡先を特定し、双方の権利義務を明確にすること。
実際の契約書には次のように書かれることが多いです。ただし、契約書のフォーマットやテンプレートにより、表現が異なることもあります。
書き方の例
| 甲は乙に対し、〇年〇月〇日、甲が保有する株式会社X(本店所在地:〇〇〇)の普通株式〇株を譲り渡し、乙はこれを譲り受ける。 |
譲渡対価の金額・支払い方法
株式譲渡契約の譲渡対価に関する項目では以下の内容が記載されます。
| ・譲渡代金 ・支払い方法 ・支払い期日 ・振込口座 |
なお、株券発行会社の場合は株券を交付する旨も契約書に記載します。書式によっては合計金額のみ記載する場合もありますし、1株あたりの金額を記載する場合もあります。また、支払い方法に関しては実行手続きの条項に含めることもあります。
書き方の例
| 譲渡代金は金〇〇円(1株あたり〇〇円)とする。乙は譲渡代金を〇年〇月〇日までに甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。 |
譲渡実行の前提条件
株式譲渡契約書の前提条件とは、譲渡日(効力発生日)までに売り手および買い手が完了すべき内容が明記されます。株式譲渡制限がある会社の場合、会社での譲渡承認手続きが必要となるため、その旨が記載されます。
| ・株主総会または取締役会での承認 ・法定手続きの完了 ・必要書類の準備 ・その他必要な手続き |
また、契約に必要な手続き等も必要に応じて記載されます。これら前提条件に不備がある場合、手続きが進まず取引が無効となることもあるため注意しましょう。
書き方の例
| 甲は、譲渡日までに、本件株式譲渡に必要な承認を得るものとする。 |
株式譲渡の手続きに関しては以下の記事をご覧ください。
譲渡実行の手続き(クロージング)
譲渡代金の支払いと同時に株式譲渡の実行が行われる旨を契約書に記載します。具体的には株主名簿の名義の変更手続きに関する内容などが明記されます。株主名簿の名義書換請求は買い手と売り手が共同で行うものと会社法で定められています。ただし、株券発行会社の場合は、株券の交付を受けていれば単独での書換請求ができるため、共同で行う条項は不要です。
なお、支払い方法がクロージング条項に記載されていることもあります。どの条項に何を書くかよりも売り手と買い手の双方が誤解のないように明確に記載することが大切です。
書き方の例
| 甲および乙は、譲渡の実行後、直ちに対象会社に対し、共同して株主名簿の書き換えを請求するものとする。 |
表明保証
株式譲渡契約書の表明保証条項は、買い手と売り手が契約締結時点での重要な事実や状況について相手方に対して保証する条項です。特にM&A取引においては、リスクの明確化と契約の安全性を高めるために欠かせない記載事項となっています。
表明保証の主な目的は、株式譲渡に関わる事実の真実性を確保し、将来的な紛争や損害発生を防止することにあります。表明保証条項によって、売り手は契約内容の透明性を保証し、買い手は対象会社の財務状況や法的問題を把握することができます。
表明保証に含まれる主な項目は以下の通りです。
| 項目 | 内容の説明 |
|---|---|
| 会社の設立・存続 | 譲渡対象会社が適法に設立され、現在も存続していることを保証します。 |
| 権利の帰属 | 譲渡される株式が売り手に正当に帰属していること、第三者の権利が設定されていないことを確認します。 |
| 財務状況 | 譲渡対象会社の財務諸表が正確であり、重大な債務や負債が隠されていないことを保証します。 |
| 法令遵守 | 会社が関連法令を遵守していること、重大な法的問題がないことを明示します。 |
| 訴訟・紛争 | 現在進行中または予見される訴訟や紛争がないことを保証します。 |
| 許認可・契約 | 必要な許認可が有効であり、重要な契約が適正に履行されていることを示します。 |
表明保証を記載する際の注意点としては、以下のポイントが挙げられます。
- 内容が事実に即しているかどうかを慎重に確認すること。虚偽の表明は後のトラブルや損害賠償請求の原因となります。
- 保証の範囲や期間を明確に定めること。いつまでの事実について保証するのかをはっきりさせることが重要です。
- 曖昧な表現を避け、可能な限り具体的かつ詳細に記載すること。
表明保証条項は買い手よりも売り手が保証する内容が多くなります。デューデリジェンスでは把握できなかった内容も表明保証条項に加えることで、買い手はより安心して取引を進めることができます。売り手が保証できない事項に関しては「売主が知る限り」などのように限定的に定めることもあります。
書き方の例
| 甲は、乙に対し、本契約締結日および譲渡日において下記の事項が全て真実かつ正確であることを表明し、保証する。 乙は、甲に対し、本契約締結日および譲渡日において下記の事項が全て真実かつ正確であることを表明し、保証する。 |
表明保証に関しては、以下の記事をご覧ください。
契約解除
株式譲渡契約書の契約解除条項は、契約の履行が困難または不可能となった場合に契約を解除できる旨を定めた規定です。解除条項を明確にすることで、双方のリスクを管理し、トラブル発生時の対応をスムーズにする役割を果たします。
契約解除の意義は、契約当事者が合意した条件に基づき、一定の事情が生じた場合に契約関係を解消できることにあります。これにより、不履行や重大な違反があった場合など、無理に契約を継続することによる損害を防止します。
| 解除条件の例 | 具体的内容 |
|---|---|
| 表明保証違反 | 契約時に売り手が保証した事項に虚偽があった場合 |
| 重要な契約違反 | 支払い遅延や契約義務不履行など、契約の根幹を揺るがす行為 |
| 承認手続き未完了 | 譲渡承認が得られず、譲渡が無効となる場合 |
| 重大な法的問題の発覚 | 訴訟や規制違反など、取引に重大な影響を及ぼす事象 |
契約解除の方法としては、通知による解除が一般的であり、解除通知の方法や期間を契約書に明示しておくことが重要です。また、解除後の対応についても、譲渡対価の返還や損害賠償の請求など、双方の権利義務を整理しておく必要があります。
書き方の例
| 甲または乙は本契約に違反した場合、相手方は本契約を解除することができる。 |
契約解除条項の作成にあたっては、曖昧な表現を避け、具体的かつ明確に解除の条件等を記載することが大切です。不明瞭な条項は解釈の違いを生み、紛争の原因となるため、弁護士など専門家の助言を受けながら作成することが推奨されます。
損害賠償
株式譲渡契約書における損害賠償条項は、契約違反や表明保証に関する虚偽記載があった場合に発生する損害を補填するための重要な規定です。この条項により、譲渡当事者間のリスク分配が明確になります。
以下の表は、株式譲渡契約書における損害賠償の主なポイントと内容の概要を示しています。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 損害賠償の意義 | 契約違反や表明保証の虚偽によって生じた損害を補償するための規定。 | 損害の範囲や因果関係を明確にしておくことが重要。 |
| 適用範囲 | 表明保証に違反した場合や契約内容の不履行など、具体的に賠償が発生する状況を明記。 | 範囲を曖昧にするとトラブルの原因になるため、具体的に記載すること。 |
| 請求条件 | 損害賠償請求の手続きや期間、通知義務などを定める。 | 請求期限や通知方法を契約書に明記し、適切な対応を促す。 |
| 免責事項 | 特定の損害について賠償責任を免除する条件や制限を記載。 | 免責範囲が広すぎると買い手の保護が不十分になるため、バランスが必要。 |
| 注意点 | 弁護士に相談し、法務リスクを確認しながら作成することが望ましい。 | 契約条項の曖昧さを避け、実務的な視点での記載を心がける。 |
損害賠償条項は、予期せぬトラブルが発生した際に会社を守る上で欠かせない項目です。特に表明保証と連動させて記載することで、リスク管理がより効果的になります。契約書作成時には弁護士などの専門家の助言を受けることを強くおすすめします。
書き方の例
| 甲および乙は、本契約に違反があった場合、それによって相手方が被った損害、損失、費用などを賠償しなければならない。 |
秘密保持
秘密保持条項とは、契約当事者間で共有される情報が第三者に漏洩しないようにするための取り決めです。株式譲渡契約に関する交渉や契約の履行過程では、会社の財務情報、事業戦略、顧客リストなど、機密性の高い情報がやり取りされることが一般的です。秘密保持条項は、こうした情報が不正に使用されることを防ぎ、当事者双方の利益を保護します。
秘密保持条項には、守秘義務の範囲や適用期間、例外事項などが具体的に記載されます。例えば、法律で要求される場合や、すでに公知の情報については秘密保持の対象外とすることが多いです。また、どのような状況下で情報を開示してもよいか、開示する場合の手続きについても明確に規定します。これにより、情報漏洩リスクを最小限に抑え、契約を安全かつ円滑に進めることが可能となります。
さらに、秘密保持義務に違反した場合のペナルティについても、契約書に明記されることがあります。これには、損害賠償請求の可能性や、契約の解除権などが含まれ、情報漏洩を未然に防ぐための抑止力となります。
書き方の例
| 甲および乙は、本契約において相手方から開示を受けた情報を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に対して開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。 |
競業避止義務
競業避止義務は、売り手が譲渡後に一定期間、譲渡対象会社と同業または類似の事業を行わないことを約束する条項です。この義務は買い手の事業保護を目的として設定され、譲渡後の競合による事業価値の毀損を防止します。
競業避止義務の主な内容として、以下のポイントがあります。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 譲渡対象会社の事業と競合する業種や地域を特定します。具体的には業種の限定や地理的範囲の設定が含まれます。 | 範囲が広すぎると売り手の自由を不当に制限するため、合理的な範囲にとどめる必要があります。 |
| 期間 | 競業避止義務の有効期間を定めます。一般的には譲渡後数年程度が多いです。 | 期間が長すぎると法的に無効となるリスクがあるため、適切な期間設定が重要です。 |
| 義務の内容 | 同業他社への就職や新規事業の開始を禁止するなど具体的な行動制限を明記します。 | 曖昧な表現は避け、明確に定義することが求められます。 |
| 違反時の対応 | 違反が発覚した場合の損害賠償請求や差止請求などの措置を規定します。 | 具体的な違反時の対応を明確にしておくことで、抑止力を高められます。 |
競業避止義務を株式譲渡契約書に記載する際の注意点としては、義務の範囲や期間が過度に広範囲・長期間にならないよう、売り手の職業選択の自由と買い手の事業保護のバランスを考慮することが重要です。また、内容の曖昧さはトラブルの原因になるため、具体的かつ明確な記載を心掛けるべきです。
合意管轄
株式譲渡契約書における合意管轄条項は、契約当事者間で将来的に紛争が発生した場合にどの裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするかを事前に定める規定です。これは、紛争解決の迅速化と裁判管轄の不確定性を排除するために設けられます。
書き方の例
| 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 |
株式譲渡契約書の作成時の注意点
株式譲渡契約書の作成や締結時の注意点について解説します。
- 株券発行の有無
- 株式譲渡制限の有無
- 株式譲渡の目的の明確化
- みなし承認規定の確認
- 契約書の保管期間
- ひな形・テンプレートの活用時の留意点
それぞれについて解説します。
株券発行の有無
株式譲渡契約書の作成および締結前に確認するポイントの一つが、対象企業が株券発行会社かどうかです。株券発行会社とは、株主に対して紙の株券を発行している会社を指します。発行会社か不発行会社かにより手続きが異なるため、契約書に記載する内容に変更が生じる場合があります。
株券とは、株主の権利を証明する有価証券を指します。現在は上場企業の株券の発行は原則廃止され、電子管理されています。ただし、非上場企業の場合は株券が発行されている場合もあります。株券発行会社の場合、株式の譲渡には株券の引き渡しが必要です。したがって、契約書には株券の引渡し方法や時期、引き渡しに関する確認事項を明確に記載する必要があります。 一方、株券不発行会社では、株券の発行自体がないため、株券の引渡しは発生しません。
契約締結時には、株券発行会社であれば株券の引渡しに関する具体的な取り決めを契約書に盛り込み、押印や書類の管理方法についても十分に配慮することが重要です。また、株券不発行会社の場合は、株主名簿の管理体制や承認手続きの確認を怠らないようにしましょう。
株式譲渡制限の有無
譲渡制限の有無も株式譲渡契約書の作成時に確認する項目です。譲渡制限とは、会社法上、特定の株式について譲渡の際に会社や株主の承認を必要とする法的な制約を指します。特に売り手が非上場企業の場合、譲渡制限株式であるケースが多く、譲渡の自由度が制限されるため、契約書への記載が欠かせません。
譲渡制限株式は、会社の支配権を安定させる目的で設定されることが多く、譲渡の際には会社の取締役会や株主総会の承認が必要となります。そのため、前提条件に承認を必要とする旨が含まれます。 契約締結前には、対象会社が譲渡制限株式に該当するかどうかを必ず確認し、必要に応じて契約書の記載内容に含めましょう。
株式譲渡の目的の明確化
株式譲渡契約書の作成において、譲渡の目的を明確にすることも大切です。M&Aによる第三者への譲渡か、会社の社員への譲渡かなど目的によって契約書に盛り込む内容が異なるためです。例えば、M&A目的の場合は表明保証や競業避止義務を充実させることが多く、個人間売買では譲渡対価や税務上の注意点を重点的に記載します。
譲渡の目的が曖昧なままだと、契約内容が不十分となり、双方の認識に齟齬が生じる恐れがあります。特に譲渡制限株式の場合、会社の承認を得るための手続きや条件設定に影響を与えるため、目的の明確化が推奨されます。譲渡の目的を具体的に理解し、契約書に反映させることで、取引の透明性が高まり、後のトラブルを防止することができます。
| 目的 | 契約書作成時のポイント |
|---|---|
| 会社の資本構成を最適化するための株式譲渡 | 譲渡後の株主構成や議決権の配分を明確にし、関連条項を調整。 |
| 事業の継続や拡大を目的とした譲渡(M&A) | 事業の引き継ぎに関する条項や表明保証の充実が必要。 |
| 個人間での株式売買による所有権の移転 | 譲渡対価の明確化や税務上の注意点を盛り込む。 |
| 対価を伴わない無償譲渡 | 無償譲渡に伴う税務・法的リスクを契約書に反映。 |
みなし承認規定の確認
譲渡制限株式を譲渡する場合、株主は会社に対して株式譲渡承認請求を行います。会社は請求から2週間以内に承認の可否を通知する必要があります。期間内に通知がない場合は承認されたものとみなされ、これを「みなし承認」と言います。
このみなし承認期間は定款によって変更されている場合もあるため、確認するようにしましょう。
契約書の保管期間
株式譲渡契約書の保管期間は、法人と個人で異なります。会社法には具体的な保管期間の規定はないものの、税法上の観点から、法人の場合は最低でも7年間、個人の場合は5年間の保管が必要です。また、ビジネスの観点からも、トラブルや紛争が発生した際に契約内容を証明するため、契約書を長期間保管しておくことが望ましいです。
契約書を保管する際には、紙媒体だけでなく電子データとしても保存することを検討すると良いでしょう。電子データの保存は、物理的な劣化を防ぐだけでなく、必要なときに迅速にアクセスできるという利点があります。ただし、電子データの保存においては、データの改ざん防止や適切なバックアップの実施が大切です。
ひな形・テンプレート活用時の留意点
株式譲渡契約書は、株式の売買に関する基本的な合意事項を明文化する重要な書類であり、法的にも非常に重要な役割を担います。とはいえ、ゼロから契約書を作成するのは時間と労力がかかります。ひな形やテンプレートを活用することで、契約書の作成が効率的かつ効果的に進められます。
ひな形・テンプレートには、一般的な条項があらかじめ組み込まれており、譲渡の目的や条件に応じて必要な部分を修正・追加することで、実際の契約に適した内容に仕上げることができます。
ただし、ひな形やテンプレートを活用する際には、いくつかの注意点もあります。まず、ひな形やテンプレートは一般的な状況を想定して作られているため、個別の契約や状況に完全にフィットするわけではありません。そのため、自社の実情や取引の詳細に合わせてカスタマイズが必要です。特に、譲渡の条件や保証条項に関する部分は、標準化された文章では対応しきれないケースが多々存在します。
また、法律や規制は時折変更されるため、使用するテンプレートが最新の法規制に適合しているか確認することも大切です。テンプレートに依存し過ぎると、曖昧な表現が残ったり、誤解を招く恐れがあるため、専門家のレビューを受けるようにしましょう。
ひな形やテンプレートに頼ることで効率化は図れるものの、契約の重要性を軽視せず、しっかりと内容を精査することが適切な契約書を作成する鍵となります。
まとめ
株式譲渡契約書は、株式を売買する際に必要不可欠な書類であり、これを適切に作成することは、取引の安全性とスムーズな進行を保証するために重要です。本記事を通じて、株式譲渡契約書の基本的な構成や記載事項、契約締結時の注意点についてご理解いただけたでしょうか。
印紙の要否やひな形の活用方法も含め、これらをしっかり押さえておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。もし具体的な契約書の作成に悩んでいる場合は、専門家に相談することをお勧めします。法律のプロにアドバイスを仰ぐことで、安心して契約を進めることができるでしょう。今後の株式譲渡が円滑に進むよう、必要な知識をしっかりと身につけていきましょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはぜひ一度、M&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。経験豊富なアドバイザーが貴社の状況に応じた最適なプランをご提案させていただきます。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。