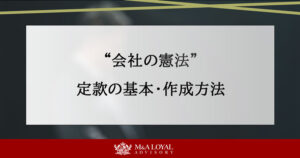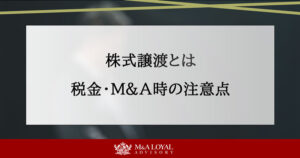売渡請求とは?条件や流れ、注意点をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
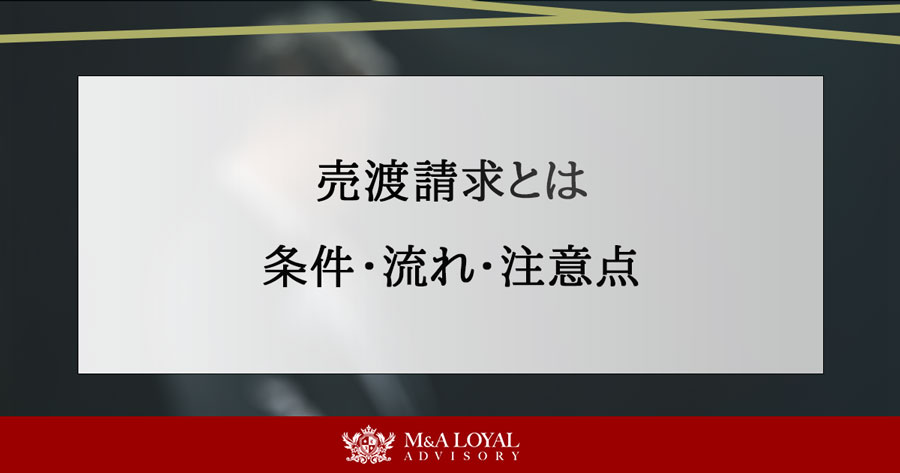
売渡請求とは、会社が少数株主に対して、その保有する株式を会社に売り渡すよう請求できる制度です。この制度を活用することで会社は、少数株主の同意を得ずに株式を強制的に取得できます。売渡請求によって、主に相続により社外に流出した株式を取り戻したり、将来的な経営権の分散を防いだりすることが可能になります。ただし、適用には厳格な条件や手続きが定められており、それらを正確に理解しておかなければなりません。本記事では、売渡請求の基本的な仕組みから具体的な手続きの流れ、さらには実務上の注意点まで、わかりやすく解説します。
目次
売渡請求とは何か 基本的な仕組みと意義
売渡請求は会社法に基づく制度で、一定の条件を満たした場合に会社が株主に対して株式の売却を強制できる仕組みです。主に相続が発生した際に活用されることが多く、会社経営の安定性を確保するための重要な手段となっています。
売渡請求は拒否できない
売渡請求とは、会社法第174条から第177条に規定されている制度で、正式には「相続人等に対する売渡しの請求」と呼ばれています。この制度により、会社は特定の株主(主に相続人)に対して、その保有する株式を会社に売り渡すよう強制的に請求することが可能となります。一例として、株主が死亡し相続が発生した場合、会社は定款の定めに基づいて相続人から株式を強制的に買い取ることができます。これにより、会社は望まない第三者が株主になることを防ぎ、会社の支配権を守ることができるのです。
中小企業オーナーにとっての重要性
中小企業にとって、株式の分散は経営の安定性を損なう大きなリスクとなります。特に創業者や主要株主が亡くなった場合、その株式が複数の相続人に分散すると、意思決定の遅延や経営方針の対立を招く恐れがあります。
売渡請求制度を活用することで、こうしたリスクを回避し、会社の意思決定や経営の一貫性を維持することができます。
売渡請求と株式買取請求権と株式等売渡請求の違い
株式に関する権利や制度には、売渡請求、株式買取請求権、株式等売渡請求(スクイーズアウト)などがあります。これらはそれぞれ異なる目的と特徴を持っています。
- 売渡請求 売渡請求は主に、閉鎖的な会社の株主間で株式の流動性や所有権の調整を目的として利用されます(ただし、具体的な適用は契約や定款に依存します)。日本の会社法に明確な規定があるわけではなく、実務上の取り決めや合意に基づくケースが多いです。
- 株式買取請求権 株式買取請求権は、会社の重要な決定(合併、会社分割、株式交換など)に反対する少数株主が、自身の株式を会社に買い取るよう請求できる権利です。この制度は、少数株主の利益を保護し、会社の意思決定に協力しない株主の退出を円滑にする目的があります。
- 株式等売渡請求 株式等売渡請求は、特別支配株主(発行済み株式の90%以上を保有する株主)が少数株主に対してその株式を売却するよう請求できる制度です。この制度は、特別支配株主が企業の所有権を統一し、経営を効率化するために利用されます。
| 制度名 | 請求主体 | 対象 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 売渡請求 | 会社 | 相続人等 | 相続時の株式分散防止 |
| 株式買取請求権 | 株主 | 会社 | 反対株主の保護 |
| 株式等売渡請求(スクイーズアウト) | 特別支配株主 | 少数株主 | 完全子会社化 |
上記の表からわかるように、売渡請求は会社が主体となって行う点が特徴的です。この制度を正しく理解し活用することで、中小企業オーナーは自社の株式構成を適切に管理できるようになります 。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



売渡請求を行うための3つの重要条件
売渡請求を実施するためには、いくつかの重要な条件を満たしている必要があります。これらの条件が整っていなければ、適法に売渡請求を行うことができません。ここでは、売渡請求の前提となる3つの条件について詳しく解説します。
譲渡制限株式であること
売渡請求の第一の条件は、対象となる株式が「譲渡制限株式」であることです。譲渡制限株式とは、株式を譲渡する際に会社の承認が必要とされる株式のことを指します。会社法では、株式会社の定款で株式の譲渡制限を設けることができると規定されています。非上場会社の多くは譲渡制限株式を発行していますが、 上場会社の株式や譲渡制限のない株式に対しては売渡請求を行うことができません。そのため、自社の株式が譲渡制限株式であるかどうかを、まず確認する必要があります。
定款に売渡請求条項が必要
売渡請求を行うための二つ目の条件は、会社の定款に売渡請求に関する条項が明記されていることです。このような条項は、譲渡制限株式を採用する会社や非公開会社において、株式の流動性を制御するために設けられることがあります。
具体的には、定款に「相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、その取得した株式を当会社に売り渡すことを請求できる」といった趣旨の規定を設ける必要があります。定款に該当条項がない場合、株主総会の特別決議(会社法第309条第2項)によって定款変更を行う必要があります。
分配可能額の範囲内であること
売渡請求の三つ目の条件は、株式を買い取るための資金(対価)が会社の分配可能額の範囲内であることです。会社法第461条により、自己株式の取得は分配可能額の範囲内でしか行えません。
分配可能額とは、会社が株主への配当や自己株式の取得などに使用できる金額の上限のことです。これは貸借対照表上の剰余金から一定の金額を控除して計算されます。 分配可能額を超える取得は違法となり、取締役は連帯して会社に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
- 分配可能額の基本的な計算式:
- 分配可能額 = 剰余金の額 – 自己株式の帳簿価額 – 法定準備金 – その他法令で定める額
- 分配可能額を超える取得の場合の影響:
- 取締役の会社に対する損害賠償責任
- 株主からの責任追及の可能性
- 取引の無効リスク
これら3つの条件を全て満たしていることを確認した上で、売渡請求の手続きに進むことが重要です。条件の一つでも欠けている場合は、適法に売渡請求を行うことができないため、事前の確認が不可欠です。
売渡請求の具体的な手続きの流れ
売渡請求を実行するためには、法令に従った適切な手続きを踏む必要があります。ここでは、売渡請求の具体的な流れを時系列で解説し、各ステップで注意すべき点を明らかにします。
相続発生の把握と初期対応
売渡請求のプロセスは、株主の死亡と相続の発生を会社が把握することから始まります。株主が死亡した場合、通常は相続人から会社に対して連絡がありますが、積極的に情報収集する体制を整えておくことも重要です。相続発生を把握したら、速やかに相続人の特定と連絡先の確認を行い、 売渡請求を行うかどうかの検討を始める必要があります。この段階で顧問弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
株主総会の特別決議
相続が発生した場合、会社が相続人から株式を買い取るための売渡請求を行うには、会社の定款に基づき株主総会の特別決議による承認が必要です。特別決議は会社法第175条に基づき、以下の要件を満たす必要があります。
- 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席していること(定足数)。
- 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が得られること(賛成要件)。
特別決議では、以下の事項を議題とすることが一般的です。
- 売渡請求を受ける株主(例:相続人)
- 対象となる株式の数
- 売買価格またはその決定方法
なお、この特別決議は、会社の定款に基づき、株主が死亡してから1年以内に行うことが求められる場合があります。この期限を過ぎると売渡請求権が消滅する可能性があるため、迅速な対応が必要です。具体的な期限や手続きについては、会社の定款を確認することが重要です。
相続人への売渡請求通知
株主総会で特別決議が承認された場合、相続人に対して売渡請求の通知を行います。この通知は書面で行い、特別決議の内容(特に売買価格や価格決定方法)を明示する必要があります。
通知には法的トラブルを防ぐため、以下の内容を含めることが望ましいです:
- 売渡請求を行う根拠(定款の条項および株主総会決議の内容)。
- 対象となる株式の種類と数。
- 売買価格または価格決定方法(例:第三者評価額、帳簿価額など)。
- 支払方法と期日(例:現金払い、振込、支払い期日)。
- 回答期限(例:通知受領後20日以内)。
回答期限や具体的な手続きについては、会社の定款に基づいて設定する必要があります。通知内容は明確かつ公平であることが重要であり、トラブルを防ぐためには専門家の助言を受けることも推奨されます。
価格協議と価格決定申立て
相続人は、売渡請求を受けた後、通知に記載された期限内に価格について異議を述べることができます(通常20日以内と定められることが多い)。異議が出された場合、会社と相続人との間で価格協議が行われます。
協議が整わない場合、会社または相続人は、会社法に基づき裁判所に対して価格決定の申立てを行うことができます。申立ての具体的な期限は、会社の定款や売渡請求通知の内容に基づいて設定されるため、通知内容を確認する必要があります。裁判所は、株式の客観的価値を考慮し、公正な価格を決定します。
手続きの段階と期限
| 手続きの段階 | 法定期限または目安 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 株主総会特別決議 | 相続発生から1年以内(定款による) | 期限を過ぎると請求権が消滅する可能性がある |
| 相続人の異議申立 | 請求通知から20日以内(通知内容による) | 異議がない場合、提示された価格で確定する |
| 価格決定の裁判所申立 | 通常20日以内(通知内容や状況による) | 申立てがなければ協議不調で終了する可能性がある |
株式譲渡と対価の支払い
価格が確定したら、会社は相続人に対して対価を支払い、株式譲渡の手続きを行います。譲渡手続きには以下のステップが含まれます。
- 株式譲渡証書の作成と取得
- 対価の支払い(会社の分配可能額の範囲内であることを再確認)
- 株主名簿の書換え
- 必要に応じて株券の回収(株券発行会社の場合)
これらの手続きが完了したら、会社は自己株式として取得した株式の処分または消却を検討します。自己自己株式の長期保有は、議決権比率の変化や資本効率の低下などの問題を引き起こす可能性があります。そのため、消却や再発行など適切な対応を検討すべきです。
売渡請求における株式価格の決定方法
売渡請求において最も重要かつ難しい問題の一つが、株式価格の決定です。適正な価格を設定することは、相続人との紛争を避け、円滑に手続きを進めるために不可欠です。ここでは、株式価格の決定方法とその留意点について詳しく解説します。
基本的な株式評価の方法
非上場会社の株式価値の評価には、一般的に以下の3つの方法が用いられます。実務上は、これらの方法を組み合わせたり、会社の業種や規模に応じて適切な方法を選択したりすることが重要です。各方法には長所と短所があり、状況に応じた使い分けが必要です。
- 純資産価額方式:会社の純資産(資産から負債を引いた額)を基に株式価値を算出する方法
- 収益還元方式:将来の予想収益を現在価値に割り引いて株式価値を算出する方法
- 類似会社比準方式:同業種の類似会社の株価を参考に株式価値を推定する方法
税務上の株式評価との関係
売渡請求における株式価格は、必ずしも税務上の評価額と一致する必要はありませんが、税務上の評価方法を参考にすることは有用です。国税庁の財産評価基本通達に基づく評価方法は、一定の客観性があると認められています。
税務上の評価方法としては、原則として以下の方法が用いられます。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- これらの折衷方式
ただし、税務上の評価額はあくまで相続税や贈与税の課税基準を定めるためのものであり、実際の取引価格としては低く評価される傾向があります。そのため、会社と相続人の間で公正な価格について協議することが重要です。
裁判所による価格決定の基準
会社と相続人の間で価格協議が整わず、裁判所に価格決定の申立てが行われた場合、裁判所は「公正な価格」を決定します。裁判所が考慮する要素には以下のようなものがあります。
- 会社の財務状況(純資産、収益性、成長性など)
- 業界の動向や経済環境
- 株式の流動性
- 会社の将来性
裁判所の決定は、一般的に客観的な株式価値に基づいて行われますが、相続という特殊な状況も考慮されることがあります。裁判所の決定には相応の時間とコストがかかるため、可能な限り当事者間での合意が望ましいでしょう。
価格決定における実務上の注意点
株式価格の決定に際しては、以下の点に注意することが重要です。
- 複数の評価方法を用いて総合的に判断する
- 最新の財務データを用いる
- 隠れた資産(含み益)や負債を適切に評価に反映させる
- 業績の変動や将来の見通しを考慮する
- 専門家(公認会計士、税理士、弁護士など)の意見を求める
また、株式価格は客観的な要素だけでなく、会社と相続人との関係性や相続人の状況なども考慮して決定することが実務上は重要です。例えば、相続税の納税資金が必要な相続人に対しては、その点を考慮した価格設定が当事者間の合意を促進することがあります。
売渡請求を行う際の実務上の注意点と対策
売渡請求は強力な制度ですが、実務上はさまざまな課題や注意点があります。ここでは、売渡請求を円滑に進めるための実務上の注意点と、トラブルを回避するための対策について解説します。
売渡請求の事前準備の重要性
売渡請求を行う際には、事前の準備が成功の鍵を握ります。特に重要なのは、株主の死亡に備えた体制整備です。株主が高齢化している会社では、相続が発生した際に速やかに対応できるよう、あらかじめ売渡請求の手順や必要書類をまとめておくことが重要です。また、定款に売渡請求条項が含まれているかどうかを確認し、必要に応じて定款変更を検討すべきです。
さらに、分配可能額の確保も重要な準備の一つです。主要株主の持株数が多い場合、その株式を買い取るための資金が十分にあるかを事前に確認し、必要に応じて資金計画を立てておくことが望ましいでしょう。< /p>
相続人との関係構築
売渡請求は会社が相続人に対して強制的に株式の売却を求める制度ですが、可能な限り相続人との良好な関係を維持することが望ましいです。特に、相続人が会社の従業員や取引先である場合は、感情的な対立を避けるため、丁寧な説明と誠実な対応が求められます。
価格協議においても、相続人の立場や事情を考慮し、一方的な価格設定を避けることが重要です。相続人が納得できる価格や支払条件を提示することで、紛争を未然に防ぎ、円滑な手続きが可能になります。
法定期限の厳格な管理
売渡請求に関する手続きには、定款や通知に基づく期限が設定されることが一般的です。特に重要な期限は以下の通りです(例:定款や通知内容に基づく):
- 株主総会特別決議:相続発生から1年以内(定款による)
- 相続人の異議申立て:請求通知から20日以内(通知内容による)
- 価格決定申立て:通知に記載された期間内
これらの期限を管理するため、相続発生後すぐにスケジュールを立て、期限管理を徹底することが重要です。特に、1年の期限は比較的長く見えますが、忘れるリスクがあるため注意が必要です。リマインダーの設定や定期的な確認を行い、確実に期限内に手続きを進めましょう。
専門家の活用と書類管理
売渡請求の手続きは法的に複雑であり、専門知識が必要です。そのため、弁護士、税理士、公認会計士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。特に以下の局面では専門家の助言が有効です。
- 定款変更の検討段階
- 株主総会特別決議の準備
- 株式評価・価格決定
- 相続人との交渉
- 裁判所への申立て
また、手続きの各段階で作成・取得した書類は、適切に保管しておくことが重要です。特に株主総会議事録、売渡請求通知、相続人とのやり取りの記録、株式評価資料などは、後々のトラブル防止のために慎重に管理すべきです。
他の選択肢との比較検討
売渡請求は有効な手段ですが、状況によっては他の方法がより適切な場合もあります 。例えば、以下のような選択肢も検討する価値があります。
| 対応策 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 相続人との任意交渉による買取り | 手続きの柔軟性、関係維持 | 合意が必要、高額になる可能性 |
| 株主間契約の締結 | 事前の取り決めによる紛争防止 | 全株主の合意が必要 |
| 種類株式の活用 | 議決権と経済的権利の分離 | 設計の複雑さ、導入コスト |
会社の規模、株主構成、財務状況などを総合的に考慮し、自社に最適な方法を選択することが重要です。場合によっては、これらの方法を組み合わせることも効果的かもしれません。
まとめ
売渡請求は、中小企業のオーナーが会社の支配権を守るための重要な手段となる場合があります。この手続きを活用することで、相続により社外に流出した株式を取り戻し、会社の経営安定性を維持することができます。売渡請求を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 譲渡制限株式であること。
- 定款に売渡請求に関する条項が定められていること。
- 分配可能額の範囲内であること。
また、相続発生後の手続きについては、会社の定款に基づき期限が設定されている場合があるため、速やかな対応が求められます。一般的には、特別決議を行い、相続人に通知を送り、必要に応じて価格協議や裁判所への申立てを進めるプロセスが含まれます。
売渡請求の成功には、事前準備の徹底、相続人との良好な関係構築、期限の管理、専門家の活用などが重要です。会社の支配権を守り、安定した経営を継続するためには、この制度を正しく理解し、適切に活用することが欠かせません。M&Aや事業承継を検討する際にも、株式の集約化の手段として有効です。会社の将来を見据えた戦略的な対応を心がけましょう。
会社売却や事業承継に関するご質問やご相談は、M&Aの専門家にご相談ください。売渡請求に関する詳細な分析や最適な戦略をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。