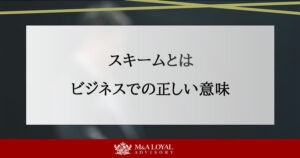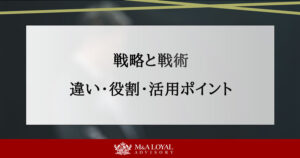スキーム図の作り方完全ガイド!基本ステップやテンプレートを紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
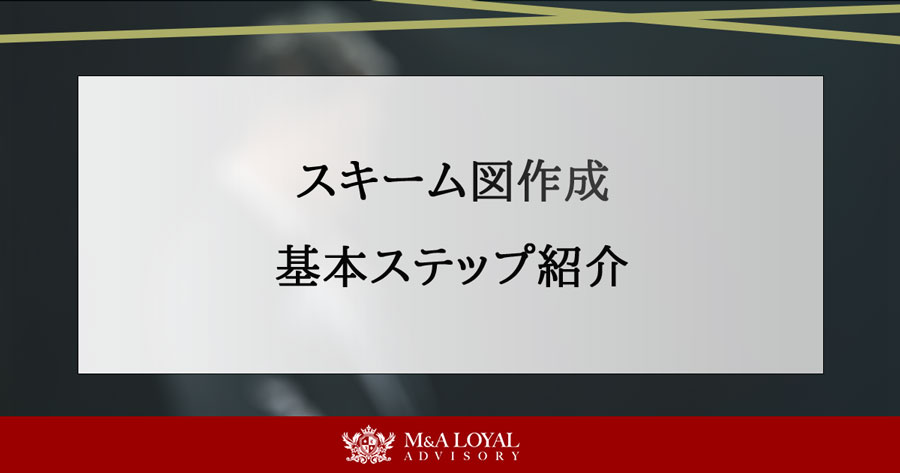
ビジネスの複雑な仕組みや関係性を第三者に分かりやすく説明するのは、多くの経営者が直面する課題です。文章だけでは伝わりにくい事業構造や組織体制を、一目で理解できるように表現する方法として注目されているのが「スキーム図」です。
投資家への事業説明、銀行融資の相談、新規事業の企画提案など、重要な場面で相手の理解と共感を得るためには、視覚的で説得力のある資料が不可欠です。特に中小企業では、限られた時間とリソースの中で最大限の効果を発揮する必要があるため、スキーム図を用いることで自社の状況を伝えやすくなります。
本記事では、スキーム図の基本的な作り方から実践的な活用テンプレートまで、初心者でも今日から使える具体的な手法を詳しく解説します。効果的なスキーム図を作成して、あなたのビジネスを成功に導きましょう。
目次
スキーム図とは|ビジネスの仕組みを可視化する最強ツール
「スキーム」とは、特定の目的を達成するための計画や仕組みそのものを指す無形の概念です。一方、「スキーム図」とは、この無形のスキームを、図や記号を用いて視覚的に表現した有形の成果物を指します。その目的は、複雑なビジネスモデルや関係性を第三者にも直感的に理解できるよう可視化することにあります。リスクや新たな機会を特定でき、さらに、視覚的に整理された情報は、経営層や関係者の迅速な意思決定を支援するという、より能動的な戦略的価値を持ちます。
スキーム図の価値は単なる「分かりやすさ」に留まりません。作成プロセスを通じて、事業モデルの非効率な点やボトルネックを特定することが可能です。現代のビジネス環境では、事業の多様化や関係者の増加により、従来の文書だけでは十分に情報を伝達することが困難になっています。そこで重要な役割を果たすのがスキーム図です。ヒト・モノ・カネ・情報という4つの経営資源の流れや関係性を図解することで、事業の全体像を一目で理解できるようになります。
スキーム図が解決するビジネス課題と活用メリット
スキーム図は現代のビジネスシーンで発生する様々な課題を効果的に解決します。最も大きなメリットは、複雑な情報の可視化による理解促進です。
文章だけでは伝わりにくい事業構造や取引関係を、図と記号を用いて直感的に表現できます。これにより、投資家への事業説明、新規プロジェクトの企画提案、組織再編の説明などで、相手の理解を深めることが可能になります。
また、スキーム図の作成プロセス自体が事業の整理に役立ちます。各要素間の関係性を明確化する過程で、非効率な部分や改善点が浮き彫りになり、業務プロセスの最適化につながります。さらに、関係者間での情報共有が円滑になり、プロジェクトの進行や意思決定のスピードが向上します。
中小企業でスキーム図が特に効果的な3つの理由
中小企業においてスキーム図は特に高い効果を発揮します。第一に、限られた時間とリソースの中で効率的にビジネスモデルを説明できることです。大企業のような詳細な資料作成に時間をかけられない中小企業にとって、一枚の図で事業の全体像を伝えられるスキーム図は貴重なツールとなります。
第二に、ステークホルダーとの信頼関係構築に寄与することです。銀行からの融資相談や投資家への説明において、明確で分かりやすいスキーム図があることで、事業への理解と信頼を得やすくなります。これは資金調達の成功率向上に直結します。
第三に、事業承継やM&Aの検討において重要な役割を果たすことです。後継者への事業説明や買収候補企業への提案で、現在の事業構造と将来のビジョンを明確に示すことができます。特に、複数の事業を展開している場合や、関係会社が存在する場合には、スキーム図による整理が不可欠となります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



スキーム図の基本的な3つの種類と使い分け方
スキーム図には、表現したい内容に応じて「樹形型」「相関型」「フロー型」の3つの基本タイプがあります。実際のビジネスシーンでは、これらを組み合わせた「ハイブリッド型」で表現することも少なくありません。
また、スキーム図をより広い図解手法の中に位置づけることも重要です。例えば、システム開発や厳密な業務プロセス定義には、国際標準の記法であるBPMN(Business Process Model and Notation)などが用いられます。一方で、本記事で扱うスキーム図は、BPMNほど厳格なルールに縛られず、より柔軟にビジネスの全体像を捉えるのに適しており、特に戦略立案の初期段階や、非技術系の関係者との合意形成において絶大な効果を発揮します。
効果的なスキーム図を作成するためには、まず何を表現したいかを明確にし、その内容に最も適した図の種類を選ぶことから始まります。各タイプの特徴を理解することで、より説得力のあるビジネス資料を作成できるようになります。
樹形型スキーム図|組織構造や業務体系を表現
樹形型スキーム図は、中心となる組織や概念から枝分かれするように下位要素を整理して表現する図です。一般的に四角形と線で構成され、階層構造や上下関係を明確に示すことができます。
この形式は組織図や業務体系図として頻繁に使用されます。例えば、本社から各支店への指揮系統、親会社から子会社への資本関係、事業部門から各チームへの業務分担などを表現する際に効果的です。中小企業では、社内の権限関係や情報伝達ルートを明確化する際によく活用されています。
樹形型の最大の特徴は、トップダウン式の関係性を視覚的に分かりやすく表現できることです。新入社員への組織説明や、事業再編時の新体制説明などで威力を発揮します。
相関型スキーム図|複数の関係者間の取引を可視化
相関型スキーム図は、複数の関係者が対等な立場で相互に関係し合う状況を表現するのに適しています。円や四角形を配置し、矢印で各要素間のやり取りを示すことで、複雑な取引関係や協力体制を一目で理解できるようにします。
特に、異なる企業間の業務提携、販売代理店ネットワーク、サプライチェーン構造などの表現に威力を発揮します。中小企業では、協力会社との関係性や、顧客・仕入先との取引フローを説明する際によく使用されます。
相関型スキーム図の利点は、各関係者の役割と相互依存関係を明確に示せることです。これにより、関係者全員が自分の位置づけと責任を理解しやすくなり、円滑な協力関係の構築に貢献します。
フロー型スキーム図|時系列での変化やプロセスを図解
フロー型スキーム図は、時間の経過に伴う変化やプロセスの流れを表現するのに最適です。左から右へ、または上から下へと時系列に沿って要素を配置し、各段階での状況変化を視覚的に示します。
製品開発プロセス、プロジェクトのマイルストーン、事業計画の実行ステップなどの説明で頻繁に使用されます。中小企業では、新商品の企画から販売までの流れや、業務改善の実施手順を説明する際に効果的です。
フロー型の特徴は、複雑なプロセスを段階的に整理し、各段階での目標や成果物を明確にできることです。これにより、プロジェクトメンバーが全体の流れを把握しやすくなり、効率的な業務遂行が可能になります。
スキーム図を作成する6つの基本ステップ
効果的なスキーム図は、規律あるプロセスから生まれます。以下の6つのステップに従うことで、思考が整理され、説得力のある図を作成できます。
ステップ1|目的と範囲の定義
作成を始める前に、最も重要な問いに答える必要があります。それは「この図は、誰に、何を伝え、どのような行動を促すためのものか?」です。例えば、銀行の融資担当者に見せる図と、社内の新入社員に見せる図では、盛り込むべき情報の粒度や強調すべき点が全く異なります。この最初のステップが、図全体の方向性を決定づける羅針盤となります。
ステップ2|ヒト・モノ・カネ・情報の要素を洗い出す
スキーム図作成の第一歩は、関係するすべての経営資源を明確にすることです。ヒト(人材・組織)、モノ(製品・設備・不動産)、カネ(資金・収益)、情報(データ・ノウハウ)の4つの視点から、スキームに関わるすべての要素を洗い出します。
この段階では完璧を求める必要はありません。思いつく限りの要素を書き出し、後で整理することが大切です。例えば、新規事業のスキーム図を作る場合、関係者(経営陣・従業員・顧客・協力会社)、必要な資源(資金・設備・技術)、流通する情報(市場データ・顧客情報)などを幅広く列挙します。
ステップ3|各要素間の関係性と流れを整理する
次に、洗い出した要素同士がどのような関係にあるかを整理します。誰が誰に何を提供し、何を得ているかを明確にすることで、スキーム全体の構造が見えてきます。
この作業では、要素間の関係を「提供する側」と「受け取る側」に分けて考えると整理しやすくなります。また、一方向の関係だけでなく、相互に影響し合う関係も見落とさないよう注意が必要です。関係性の強弱や重要度も併せて整理しておくと、後の図解作業がスムーズに進みます。
ステップ4|最適な図の種類(樹形・相関・フロー)を選択する
整理した要素と関係性を基に、最も適切な図の種類を選択します。階層的な関係が中心なら樹形型、複数の関係者が対等に関わるなら相関型、時系列の変化を表現するならフロー型を選びます。
図の種類の選択は、スキーム図の効果を大きく左右する重要な決定です。迷った場合は、最も重要な関係性に焦点を当てて判断します。複数のタイプの要素が混在している場合は、メインとなる構造に合わせて選択し、必要に応じて部分的に他のタイプの表現を取り入れることも可能です。
ステップ5|統一された記号と矢印で関係性を表現する
選択した図の種類に基づいて、実際に図を描いていきます。この際、矢印や記号の使い方を統一することで、見る人にとって理解しやすい図になります。例えば、資金の流れには¥マーク付きの矢印、情報の流れには点線の矢印を使うなど、一貫したルールを設けます。
色や形も効果的に活用しましょう。重要な要素は目立つ色にする、同じ種類の要素は同じ形にするなど、視覚的な工夫により情報の整理ができます。ただし、あまり多くの色や形を使いすぎると逆に分かりにくくなるため、必要最小限に留めることが大切です。
ステップ6|各関係者の視点で分かりやすさを検証する
完成した図を、実際に見せる相手の立場に立って検証します。専門知識のない人でも理解できるか、必要な情報が漏れていないか、逆に不要な情報が入りすぎていないかをチェックします。
可能であれば、実際に関係者に見てもらい、フィードバックを得ることが理想的です。特に中小企業では、経営陣、従業員、外部パートナーなど、異なる立場の人々に理解してもらう必要があるため、それぞれの視点での検証が重要です。必要に応じて修正を加え、最終的に全員が納得できる図を完成させます。
スキーム図作成で押さえるべき実践的なポイント
理論的な知識だけでなく、実際の作成現場で役立つ実践的なポイントを押さえることで、より効果的なスキーム図を作成できます。多くの中小企業で見られる失敗例を避け、確実に成果を上げるための具体的な手法を身につけることが重要です。
特に限られた時間とリソースの中で最大限の効果を得る必要がある中小企業では、これらの実践的なポイントを押さえることで作業効率と成果品質の両方を向上させることができます。
必要最小限の要素でシンプルな図を作成する
スキーム図の最大の価値は、複雑な情報を分かりやすく伝えることです。そのため、必要最小限の要素に絞り込み、シンプルな図を心がけることが成功の鍵となります。
- 重要度の高い要素に焦点を絞る
- 詳細な説明は別資料に分ける
- 一つの図で表現する内容を限定する
情報を詰め込みすぎると、かえって理解が困難になります。例えば、事業スキーム図を作成する際は、主要な収益源と重要なパートナーシップに焦点を当て、細かい業務フローは除外します。必要に応じて、複数の図に分けて段階的に説明することも効果的です。重要なのは、一目見て全体像が把握できることです。
色・形・線を使い分けて情報の種類を区別する
視覚的な工夫により、情報の種類や重要度を直感的に理解できるようにします。統一されたルールに基づいて色・形・線を使い分けることで、専門知識のない人でも図の内容を理解しやすくなります。
- 資金の流れ:赤色の実線矢印
- 情報の流れ:青色の点線矢印
- 重要な関係者:太枠の四角形
ただし、使用する色や形の種類は3〜4種類程度に限定することが重要です。あまり多くの色を使うと、かえって混乱を招きます。また、色だけに依存せず、形や線の種類でも区別することで、印刷時やモノクロ表示でも理解できるよう配慮します。カラーユニバーサルデザインの観点からも、色覚に配慮した色選択を心がけることが大切です。
各関係者の役割・メリット・提供価値を明記する
スキーム図を見る人が自分の立場や利益を理解できるよう、各関係者の役割とメリットを明確に示します。これにより、関係者の協力を得やすくなり、プロジェクトの成功確率が向上します。
- 顧客:○○サービスを受ける
- パートナー企業:△△の対価を得る
- 自社:□□の価値を提供する
特に中小企業では、限られたリソースで多くの関係者と連携する必要があるため、Win-Winの関係を明確に示すことが重要です。単に取引関係を示すだけでなく、各関係者がどのような価値を得られるかを具体的に記載することで、説得力のある提案資料として活用できます。また、将来的な発展可能性や追加メリットも併せて示すことで、長期的なパートナーシップの構築につながります。
スキーム図の作成ツール比較と効率的な使い方
スキーム図作成の成功は、適切なツール選択から始まります。身近なOfficeソフトから専門的な作図ツールまで、それぞれに特徴とメリットがあります。中小企業では予算とリソースの制約がある中で、最適なツールを選択することが重要です。
ツール選択の際は、作成頻度、図の複雑さ、チーム内での共有方法、既存システムとの連携などを総合的に考慮する必要があります。適切なツールを選ぶことで、作業効率が大幅に向上し、より説得力のあるスキーム図を作成できるようになります。
PowerPoint・Excelで作る手軽なスキーム図の作成法
PowerPointとExcelは、多くの中小企業で既に導入されているため、追加コストなしでスキーム図作成を始められる最も身近なツールです。PowerPointでは図形機能とSmartArtを活用することで、基本的なスキーム図を効率的に作成できます。
PowerPointでの作成手順は、まず紙に下書きを作成し、要素ごとに図形を配置、矢印でつなげるという流れになります。色分けやレベル感の統一により、分かりやすい図に仕上げることができます。特に、図形の「塗り」または「枠線」のどちらか一方のみに色を付けることで、すっきりとした印象の図を作成できます。
Excelでも表計算機能を活用したデータ連動型のスキーム図作成が可能です。ただし、これらのツールは汎用ソフトのため、複雑な図形描画や専門的な記号には制約があります。シンプルな図や急ぎの資料作成には最適ですが、本格的なビジネス提案書には物足りない場合があります。
クラウド作図ツール(Miro, Lucidchart等)で作る共同作業スキーム図
現代のビジネスシーンでは、MiroやLucidchartといったクラウドベースの作図ツールが主流になりつつあります。これらのツールは、豊富なテンプレートに加え、「リアルタイム共同編集機能」を備えており、チームメンバーが同時に一つの図を編集できます。また、付箋やコメント機能で議論を活性化させたり、「AIによる作図支援機能」で作業を効率化したりすることも可能です。
これらのツールの最大の利点は、作図に特化した支援機能です。自動レイアウト機能、配置ガイド、コネクタの自動調整など、Officeソフトでは困難な図形配置を自動化できます。ドラッグ&ドロップによる直感的な操作により、複雑な相関図やフロー図も短時間で作成可能です。
また、業界別のテンプレートやアイコンが充実しているため、素材を探す時間を大幅に短縮できます。M&A関連のスキーム図テンプレートや、中小企業向けの事業計画図なども用意されており、専門性の高い図を効率的に作成できます。
用途別おすすめツールの選定基準と活用のコツ
ツール選択は、作成目的と使用頻度を基準に決定することが重要です。月1回程度の簡単な社内資料であれば、PowerPointで十分対応できます。一方、投資家向けの重要な提案書や、複雑な事業構造の説明が必要な場合は、専門ツールの導入を検討すべきです。
・月1〜2回の簡単な図:PowerPoint・Excel
・週1回以上の作成:専門ツール導入を検討
・複雑な相関関係の表現:専門ツール推奨
・外部向け重要資料:専門ツール推奨
予算面では、PowerPointやExcelは既存ライセンスで対応可能ですが、専門ツールは月額または年額の費用が発生します。しかし、作業時間の短縮効果を考慮すると、頻繁に作成する場合は専門ツールの方がコストパフォーマンスに優れることが多いです。また、チーム内での共有・編集機能や、クラウド連携機能も考慮要素として重要です。
スキーム図の実践活用事例|中小企業の5つのテンプレート
中小企業におけるスキーム図の活用場面は多岐にわたります。実際のビジネスシーンで頻繁に使用される5つの代表的なテンプレートを理解することで、様々な場面で効果的なスキーム図を作成できるようになります。
これらのテンプレートは、単なる図の型ではなく、中小企業の実際の課題解決に直結する実践的なフレームワークです。各テンプレートの特徴と活用方法を習得することで、経営戦略の立案から日常業務の改善まで、幅広い場面でスキーム図を戦略的に活用できるようになります。
事業計画・新規事業のスキーム図テンプレート
事業計画のスキーム図は、新規事業の全体像を投資家や関係者に分かりやすく伝えるための重要なツールです。相関型のスキーム図を基本とし、顧客、自社、パートナー企業、投資家などの関係者を配置し、それぞれの価値提供と対価の流れを明確に示します。
このテンプレートでは、収益モデルの核心となる部分を中央に配置し、周囲に関係者を配置します。矢印の色分けにより、資金の流れ(赤)、商品・サービスの流れ(青)、情報の流れ(緑)を区別することで、複雑なビジネスモデルも一目で理解できるようになります。特に中小企業では、限られたリソースで最大の効果を得る必要があるため、各関係者のメリットを明確に示すことが重要です。
新規事業の企画段階では、このスキーム図を作成することで事業の実現可能性を検証し、必要な提携先や投資額を明確にできます。また、事業計画書の要約として活用することで、短時間で事業の本質を伝えることが可能になります。
販売・マーケティングのスキーム図テンプレート
販売・マーケティングのスキーム図は、顧客との接点から成約まで全体の流れを可視化し、営業効率の向上と顧客体験の改善に役立ちます。フロー型のスキーム図を基本とし、認知から購入、アフターサービスまでの顧客ジャーニーを時系列で表現します。
このテンプレートでは、各段階での顧客の状態、企業の活動、使用するツールやチャネルを明確に整理します。例えば、認知段階ではWebサイトとSNS、検討段階では営業担当者との面談、購入段階では契約書類とシステム、アフターサービス段階ではサポート体制といった具合に、具体的な接点を示します。
中小企業では営業リソースが限られているため、このスキーム図により非効率な部分を特定し、自動化やデジタル化による改善ポイントを見つけることができます。また、顧客視点での価値提供を可視化することで、競合他社との差別化要因を明確にできます。
組織再編・業務改善のスキーム図テンプレート
組織再編や業務改善のスキーム図は、現状の課題と改善後の理想像を比較して示すことで、変革の必要性と効果を明確に伝えます。樹形型またはフロー型を組み合わせ、改善前後の組織構造や業務フローを対比させて表現します。
このテンプレートでは、現状の問題点(赤色でマーク)、改善案(青色でマーク)、期待される効果(緑色でマーク)を色分けして示します。組織図では報告ラインの簡素化や権限委譲の明確化、業務フローでは無駄な工程の削除や自動化部分を視覚的に表現します。
中小企業の組織再編では、従業員の理解と協力が不可欠です。このスキーム図により、なぜ変革が必要なのか、変革後にどのような効果が期待できるのかを分かりやすく説明できます。また、変革の段階的な実施計画を示すことで、現実的で実行可能な改善策として提示できます。
資金調達・投資計画のスキーム図テンプレート
資金調達・投資計画のスキーム図は、資金の調達源、使途、期待される収益を明確に示し、投資家や金融機関からの理解と支援を得るためのツールです。相関型のスキーム図を基本とし、資金提供者、自社、投資対象、収益構造を関連付けて表現します。
このテンプレートでは、調達資金の種類(融資、出資、補助金など)ごとに色分けし、それぞれの条件と返済計画を明記します。投資対象については、設備投資、人材投資、マーケティング投資などに分類し、各投資が収益にどう貢献するかを矢印で示します。
中小企業の資金調達では、事業の将来性と返済能力を具体的に示すことが重要です。このスキーム図により、投資の合理性と収益予測の根拠を視覚的に説明できます。また、複数の調達手段を組み合わせた最適な資金調達戦略を検討する際にも有効です。
M&A・事業承継のスキーム図テンプレート
M&A・事業承継のスキーム図は、複雑な企業間取引や所有権移転を分かりやすく整理し、関係者全員の理解を促進する重要なツールです。樹形型と相関型を組み合わせ、買収前後の企業構造、資金の流れ、シナジー効果を包括的に表現します。
このテンプレートでは、買収対象企業の事業構造、買収スキーム(株式譲渡、事業譲渡、合併など)、買収後の統合計画を段階的に示します。特に重要なのは、買収価格の算定根拠、資金調達方法、統合によるコスト削減効果、売上シナジーなどを具体的な数値とともに表現することです。
中小企業のM&Aでは、事業承継や規模拡大の手段として活用されることが多く、関係者の利害関係が複雑になりがちです。このスキーム図により、取引の全体像と各関係者のメリットを明確に示すことで、円滑な交渉と合意形成を促進できます。また、買収後の統合プロセスを事前に可視化することで、実行段階でのトラブルを防止できます。
まとめ|スキーム図で事業の見える化を実現しよう
スキーム図は、中小企業の成長と発展を支える強力なツールです。複雑なビジネスモデルや組織構造を視覚的に表現することで、ステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを実現し、事業の理解促進と信頼関係の構築に大きく貢献します。
本記事で紹介した3つの基本タイプ(樹形型・相関型・フロー型)と6つの作成ステップを活用することで、初心者でも効果的なスキーム図を作成できるようになります。特に、ヒト・モノ・カネ・情報の4つの要素を整理し、関係性を明確にする手法は、どのような業種の中小企業でも応用可能です。
実践的な活用においては、PowerPointやExcelから始めて段階的にスキルを向上させ、必要に応じて専門ツールの導入を検討することをお勧めします。事業計画から組織改革、M&A・事業承継まで、様々な場面でスキーム図を活用することで、より説得力のある提案と効率的な意思決定が可能になります。今日からでも身近な業務でスキーム図の作成を始めて、事業の見える化による競争力向上を実現していきましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。