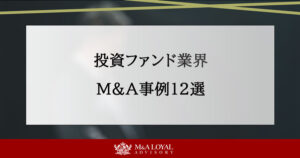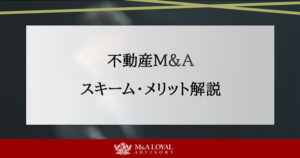不動産ファンドとは?種類や利回り、リスク、REITとの違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
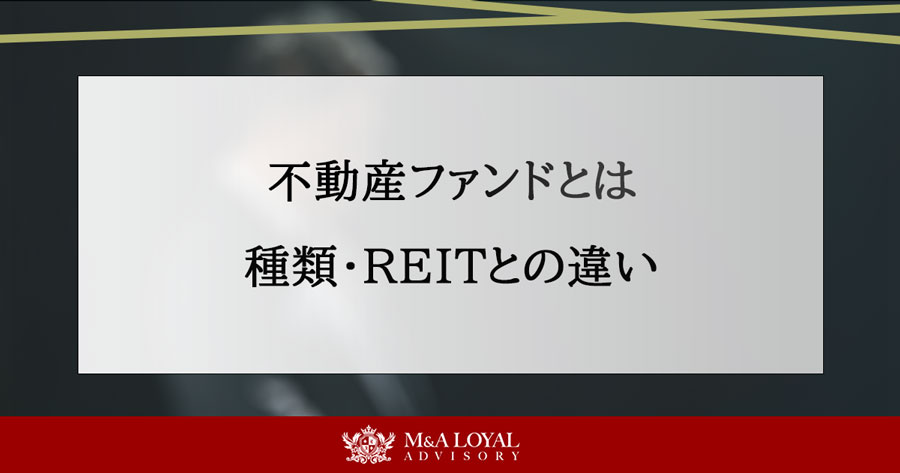
不動産投資を検討する際に耳にする不動産ファンドとは、どんなものかご存知でしょうか。少額から始められる投資手法として注目を集めていますが、その仕組みや種類、利回り、リスクについて正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。
本記事では、不動産ファンドとは何か、その基本から代表的な種類、投資リターンの目安や注意すべきリスクまでを分かりやすく解説します。
さらに、REIT(不動産投資信託)との違いも整理し、どのような投資家に適しているのかを明らかにします。不動産投資を始める前に、不動産ファンドとはどういうものかを知るため、ぜひご参照ください。
目次
不動産ファンドとは
まず、不動産ファンドの基本知識について分かりやすく解説します。
不動産ファンドの概要
そもそも「ファンド」とは、多くの投資家から集めた資金をまとめて運用し、その運用成果を出資者に分配する仕組みを指します。
資金の運用は、専門の運用会社やファンドマネージャーが行い、株式や債券、不動産、未公開株、インフラなど、さまざまな資産に投資します。不動産に投資するファンドが「不動産ファンド」です。
ファンドの目的は、投資家が単独では難しい規模や分散投資を実現し、リスクを抑えつつリターンを狙うことにあります。
ファンドと投資信託の違い
「ファンド」のことを「投資信託」と和訳する場合も多いです。
しかし、日本における「投資信託」は、投資信託および投資法人に関する法律(投信法)に基づき主務官庁の監督を受けている金融商品のことを指します。
そのため、日本では「ファンド」は意味が広く、「投資信託」はより限定的な使われ方をします。
不動産ファンドと現物不動産投資の違い
不動産投資は大きく分けて、直接投資と間接投資があります。
直接投資は現物不動産投資と一般的にいわれ、投資家が自ら現物の不動産を購入し、賃貸経営や売却益によって収益を得る方法です。
これに対し、間接投資は、不動産ファンドなどを通じて資金を出資し、運用益や分配金を受け取る方法を指します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



不動産ファンドの収益
不動産ファンドの収益は次の二つに大別されます。
- 賃料収入
- 売却益
それぞれを解説します。
賃料収入
賃料収入は、ファンドが保有するオフィスビルや商業施設、マンション、物流倉庫などをテナントに貸し出すことで得られる家賃収入です。
安定した賃料収入はファンドの基礎的な収益となり、定期的に投資家へ分配されます。
物件の立地や契約条件、稼働率によって収益性が変わるため、長期的な安定運用にはテナント管理や物件価値の維持が重要です。
売却益
売却益は、保有している不動産を購入時より高い価格で売却した際に得られる利益です。
市況の好転や開発・改修による物件価値向上が高利益の要因となります。売却益は一度きりの収入ですが、金額が大きくなることもあり、ファンド全体の収益を大きく押し上げる可能性があります。
ただし、市場環境やタイミング、購入時の価格設定次第で売却益が得られない場合もあります。また、譲渡所得税などの税負担を考慮する必要があるため、慎重な運用判断が求められます。
不動産ファンドの種類
不動産ファンドの分類方法には複数ありますが、最も分かりやすいものは次のとおりです。
- 公募REIT(J-REIT)
- 私募REIT
- 私募ファンド
それぞれの特徴と違いを分かりやすく解説します。
公募REIT(J-REIT)
REIT(リート)とは、多くの投資家から集めた資金で不動産を購入・運用し、その賃料収入や売却益を投資家に分配する仕組みです。「Real Estate Investment Trust」の頭字語です。一般的に「不動産投資信託」と呼ばれています。
個人では難しい大規模かつ複数の不動産への分散投資を可能にし、少額からでも不動産投資に参加できる点が特徴です。
この仕組みはアメリカで1960年代に誕生し、日本では2001年に制度化された「日本版REIT(J-REIT)」として導入されました。J-REITは日本国内の不動産市場に適した形で設計され、運用資産にはオフィスビルや商業施設、物流施設、ホテル、住宅などが含まれます。
J-REITは証券取引所に上場しており、株式と同じように証券会社を通じて売買が可能です。市場価格は需給や不動産市況によって変動しますが、現物不動産を直接購入する場合と比べて流動性が高く、売買のしやすさが大きな魅力です。
J-REITは約10年遅れて始まった私募REITと区分するため、「公募REIT」や「上場REIT」などと呼ばれます。
私募REIT
私募REITとは、J-REITの制度を活用しつつ、非上場で運用される不動産投資信託です。
集めた資金で不動産を取得・運用し、賃料収入や売却益から費用を差し引いた利益を投資家に分配する仕組みはJ-REITと同じです。運用期間が定められていない場合が多く、長期的な資産運用にも適している点もJ-REITと共通しています。
一方で、募集対象は特定の機関投資家や限られた投資家に限定され、市場での売買は行われません。そのため流動性は低いものの、不動産鑑定評価額を基に算定される基準価格は比較的安定している点が、J-REITとの違いです。
私募REITは、J-REITと後述する私募ファンドの中間に位置付けられる不動産ファンドといえます。
私募ファンド
私募ファンドには法律上の明確な定義はありませんが、REIT(特にJ-REIT)が「投資信託及び投資法人に関する法律」(投信法)を根拠法とするのに対し、私募ファンドは商法、会社法、不動産特定共同事業法などを根拠法とします。投信法の厳格な規制が適用されないため、柔軟な運用や組織設計が可能です。
「私募ファンド」という用語は、J-REIT以外の不動産ファンドを広義に指す場合もあれば、特定の非公開型ファンドを指す場合もあり、文脈によって異なることがあります。
ファンド種類別の市場規模
一般社団法人不動産証券化協会(ARES)によると、2024年12月時点での不動産ファンド別の市場規模は次のとおりです。
- J-REIT:23.4兆円
- 私募REIT:6.8兆円
- 私募ファンド(国内特化型+グローバル型):34兆円
私募ファンドの市場規模が最も大きいことが分かります。
不動産ファンドのメリット
不動産ファンドの中から、個人を含む幅広い投資家が参加できる公募REIT(J-REIT)と、現物不動産投資との違いに注目してメリットを解説します。
不動産ファンドの主なメリットは次のとおりです。
- 少額から投資を始められる
- 複数物件への分散投資ができる
- 運営・管理の手間がかからない
- 流動性が高く換金しやすい(条件による)
- 専門知識がなくても始められる
それぞれを分かりやすく解説します。
少額から投資を始められる
現物不動産の購入には多額の資金が必要で、一棟マンションであれば都内では数億円以上、区分マンションでも1,000万円以上が相場です。ローンを組まない限り、個人が簡単に手を出せる金額ではありません。
一方、不動産ファンドであれば数万円から、なかには1万円程度から投資できるファンドもあり、資金面のハードルが大幅に下がります。これにより、まとまった資金がない投資初心者や個人投資家でも、不動産市場に参加できます。
なお、最低投資額はファンドによって異なるため、余裕資金の範囲内で投資できるか事前に確認することが重要です。
複数物件への分散投資ができる
現物不動産投資では、購入資金や管理負担の関係から、保有物件数は限られる傾向にあります。
これに対して、不動産ファンドでは一つのファンドが多数の不動産を保有しており、オフィスビルや商業施設、物流施設、住宅など多様な物件への投資が可能です。ただし、ファンドによって投資対象の用途や地域が偏る場合もあるため、分散効果はファンド選びによって異なります。
これにより、特定地域の景気低迷や一部物件の空室率上昇といったリスクを抑え、安定した収益が期待できますが、全体的な市場環境の変化には影響を受ける可能性があります。
運営・管理の手間がかからない
現物不動産を所有すると、テナント募集や契約更新、家賃回収、建物の清掃・修繕、法令順守など多岐にわたる管理業務が発生します。管理会社に委託ができますが、さまざまな判断が求められます。
不動産ファンドの場合、インターネット上だけで手続きが完了するものもあり、投資家は管理の負担を負うことなく収益を受け取れます。
特に本業が忙しい人や不動産管理の経験がない人にとって、大きなメリットです。
流動性が高く換金しやすい
現物不動産は売却に数カ月単位の時間がかかることが普通です。
一方、J-REITなどの上場型不動産ファンドは、株式と同じように証券取引所で取引されるため、必要に応じてすぐに売却し現金化できます。
資産運用の柔軟性が高く、突発的な資金需要にも対応しやすい点は大きな魅力です。
専門知識がなくても始められる
不動産投資には、物件選定や市場分析、契約交渉、管理業務など高度な知識と経験が求められます。
しかし不動産ファンドでは、経験豊富な運用会社がこれらの業務を一括して担うため、投資家は不動産の専門知識がなくても投資が可能です。
運用会社は市場動向や資産評価のプロであり、適切な売買タイミングや物件改善を通じて資産価値を高める取り組みを行うため、個人で行うよりも効率的な運用が可能です。
不動産ファンドのデメリット・注意点
不動産ファンドの注意点は次のとおりです。
- 元本割れ・価格変動のリスクがある
- 金融機関の融資が受けられない
- 運用方針を定められない
それぞれを詳しく解説します。
元本割れ・価格変動のリスクがある
不動産ファンドは、不動産市場や経済環境の変化によって価値が変動します。
例えば、景気の後退や地域経済の低迷、不動産需要の減少などが起こると、保有物件の価格が下落し、売却益が減少する可能性があります。また、賃料水準の下落や空室率の上昇によって賃料収入が減れば、分配金が減額されることもあります。さらに、金利の上昇は不動産価格の下落要因となるほか、ファンドの借り入れコスト増加を招き、運用成績を圧迫する場合があります。
特にJ-REITのような上場型の場合、株式市場と同様に投資口価格が日々変動し、不動産市況だけでなく株式市場全体の動向や投資家心理など多様な外部要因が影響します。
金融機関の融資が受けられない
現物不動産投資では、購入物件を担保に金融機関から融資を受けることで、自己資金以上の規模で投資を行うことが可能です。
一方、不動産ファンドの場合、投資口や持分を個人が担保としてローンを組むことは基本的にできません。そのため、個人投資家としては、自己資金の範囲内での投資に限られます。
ただし、不動産ファンド自体はレバレッジを活用して資金を調達し、不動産を購入することが多いため、投資家は間接的にレバレッジの恩恵を受ける場合があります。
運用方針を定められない
不動産ファンドでは、物件の取得・売却や改修、テナント戦略などの運用判断は全て運用会社が行います。
投資家はファンドの運用方針や個別物件の選定に直接関与できず、自分の意向に沿わない運用が行われる可能性もあります。
そのため、投資前に運用会社の実績や方針を十分に確認しておくことが重要です。
不動産ファンドへ投資する前の準備事項
不動産ファンドへの投資を開始する前に、次の項目を把握しておきましょう。
- 投資目的
- 投資期間
- リスク許容度
- 投資可能額
それぞれを分かりやすく解説します。
投資目的
不動産ファンドに投資する前に、まずは自分が何を目的として投資を行うのかをはっきりさせることが重要です。
例えば、分配金による安定的なインカムゲインを重視するのか、将来的な価格上昇によるキャピタルゲインを狙うのかによって、選ぶべきファンドの種類や運用方針が変わります。
目的が曖昧なまま投資を始めると、途中で方針がぶれてしまい、思わぬ損失を招く可能性があります。
投資期間
不動産ファンドは、短期売買で利益を狙うケースもあれば、数年から10年以上保有して安定収益を得る長期運用型のものもあります。
自分の資金を必要とする時期やライフプランに合わせて投資期間を設定することで、出口戦略を立てやすくなります。
なお、REITと比較して私募ファンドは運用期間が設定されている場合が多く、数年から10年程度の期間で終了する傾向があります。一方、J-REITは無期限に事業を継続することを前提としており、これは企業の継続性を表す「ゴーイング・コンサーン(going concern)」の概念と類似しています。
リスク許容度
リスク許容度とは、投資家が耐えられる価格変動や損失の大きさを指します。資産運用において自分のリスク許容度を正しく理解することは、金融商品選びや運用方針を決める上で非常に重要です。
リスク許容度は年齢や収入、保有資産額、投資経験、扶養家族の有無などを総合的に考慮して判断します。
例えば、年齢が若く高収入で独身の人は、将来の収入や時間的余裕から比較的高いリスクを取れると考えられます。一方で、すでに定年を迎え、投資経験が乏しく、扶養家族がいる人は、生活への影響を避けるため低リスクの商品を選ぶべきといえます。
リスク許容度を無視して投資を行うと、市場の変動に過剰反応してしまい、冷静な判断を欠いた売買に陥る恐れがあります。
投資可能額
生活費や緊急時に備える資金は別に確保した上で、余剰資金の中から投資に回せる金額を算出します。
不動産ファンドは基本的に元本保証がなく、投資額全てを失う可能性もゼロではないため、生活に支障が出ない範囲で投資することが鉄則です。
また、最低投資額はファンドによって異なるため、自分の資金計画と照らし合わせて選びましょう。
不動産ファンドの選び方
不動産ファンドを選定する際、確認すべき事項は次のとおりです。
- 運用主体の実績と信頼性
- 投資対象エリア・物件タイプ
- 収益性と成長性
- 契約条件と換金性
それぞれを詳しく解説します。
運用主体の実績と信頼性
ファンドを運営する運用会社の実績や信頼性は、投資成果に直結します。
過去の運用実績や分配金履歴、物件の取得・売却戦略、テナント管理の手腕を確認し、長期間安定した運用成績を残しているか、複数の経済局面でどのように対応してきたかを評価することが重要です。
また、ガバナンス体制や情報開示の透明性が高い運用会社ほど、投資家にとって安心度が高まります。さらに、第三者機関の評価やリスク管理体制についても確認することで、より信頼性の高い運用会社を選定することができます。
投資対象エリア・物件タイプ
不動産ファンドは、物件の立地や用途によって収益性やリスクの特性が大きく異なります。
例えば、都心のオフィスビルは高い賃料収入が期待できる一方、景気後退時には空室率が上昇しやすい傾向があります。住宅や商業施設、物流施設、ホテルなども、それぞれ異なる需要要因を持っています。
複数のエリアや物件タイプに分散することで、特定の地域や用途に依存するリスクを軽減できます。
収益性と成長性
利回りの高さだけでなく、その水準が今後も維持・向上できるかを見極めることが大切です。
分配金の方針や配当性向、賃料の安定性、物件の稼働率、将来的な賃料改定の余地などを総合的に判断します。
また、保有物件の改修やリニューアルによる価値向上、成長市場への新規投資といった戦略も、長期的な収益拡大の可能性を示す重要な要素です。
契約条件と換金性
不動産ファンドは、上場型と非上場型で換金性や契約条件が大きく異なります。
上場型(J-REIT)は市場で売買できるため比較的流動性が高い一方、価格変動リスクがあります。非上場型(私募REITや私募ファンド)は市場取引がなく、解約や償還まで資金が拘束されることが多いため、運用期間や解約条件を事前に確認することが重要です。
資金の必要時期に応じて、換金性の高い商品と低い商品を適切に組み合わせることが望まれます。
不動産の種類別の特徴
不動産ファンドの投資先の不動産の種類は主に次のとおりです。
- オフィスビル
- 賃貸住宅
- 商業施設
- 物流施設
- ホテル
- ヘルスケア施設
それぞれの特徴を解説します。
オフィスビル
都市の中心部や主要ビジネス街に立地し、企業や団体がオフィスとして使用します。
安定したテナント契約が結ばれれば長期間にわたり一定の賃料収入を見込める点が強みです。
一方で、景気後退や企業の経営悪化により入居企業が縮小・撤退すると空室率が上昇し、賃料水準が下落する可能性があります。
特に近年はテレワーク普及に伴いオフィス需要の構造変化が進んでおり、立地条件の良さや耐震性能、設備の充実度、最新のオフィスニーズへの対応力が資産価値と稼働率を左右します。
賃貸住宅
主に個人が居住するマンションやアパートなどの住宅物件も投資対象です。
住宅は生活の基盤であるため、景気変動の影響を受けにくく、安定的な稼働率を維持しやすいのが特徴です。また、一室当たりの賃料が比較的小さいことから、大幅な人口減少や地域の需要低下がない限り、安定した賃料収入を得やすいのが特徴です。
一方で、景気回復局面では賃料の上昇幅が限定的となり、収益面で大きな恩恵を受けにくいという側面もあります。
立地や周辺環境、建物の管理状態が入居者の確保に直結します。
商業施設
ショッピングモールや百貨店、路面店、複合商業施設などは、オフィスや住居に比べて賃貸借契約期間が長く、安定した賃料収入を得やすい傾向があります。ただし、歩合賃料制を採用する場合、集客力が収益に直結します。
集客力は立地、交通アクセス、テナント構成に左右され、景気が好調な時期には収益が増加しやすい一方、不況やEC利用の拡大で影響を受けやすい分野でもあります。そのため、リニューアルやイベント開催、話題性のあるテナント誘致など継続的な集客施策が重要です。
物流施設
倉庫や配送センター、フルフィルメント施設などが該当します。
EC市場の拡大やサプライチェーンの高度化に伴い需要が増加しています。大口テナントと長期契約を結ぶケースが多く、契約期間中の入れ替わりが少ないため、稼働率や賃料収入が安定しやすいのが大きなメリットです。
一方で、流動性が低く、市場での売買や用途転換が難しいことがデメリットとされます。また、テナントが少数に集中している場合は、契約更新や退去の影響が大きく、収益性が一時的に低下するリスクもあります。
都市近郊や高速道路IC付近など、交通アクセスの良い立地が重視されます。
ホテル
ビジネスホテルやリゾートホテル、シティホテルなど多様な形態があります。
宿泊客は国内外の観光客や出張客であり、観光需要やビジネス需要、イベント開催などによって収益が変動します。繁忙期は高い稼働率と宿泊単価の上昇が見込まれる一方、閑散期や景気後退期、災害、感染症流行など外部要因の影響で稼働率が急落することがあります。
インバウンド需要や地域イベント、観光資源の魅力度が運営成績を左右するため、立地やブランド力、運営会社の販売戦略が極めて重要です。
ヘルスケア施設
医療施設や高齢者向け施設などが含まれます。
少子高齢化の進展により長期的な需要が見込まれる分野で、景気変動の影響は比較的小さい傾向があるのが特徴です。入居期間が長く安定した賃料収入を得られますが、運営事業者の経営状態やサービス品質が安定収益の継続性に直結します。
また、介護・医療分野の制度改正や人材確保の難しさなど、外部環境の変化にも注意が必要です。
不動産投資のリスクの種類
不動産投資には主に次のようなリスクがあります。
- 市場・景気変動リスク
- 物件運営リスク
- 流動性リスク
- 法制度・税制変更リスク
- 自然災害・事故リスク
- 運用会社の信用リスク
それぞれを解説します。
市場・価格変動リスク
不動産市場は、景気動向や金利の変化、人口動態、企業活動の活発さなど、さまざまな要因によって価格や賃料が変動します。
景気後退期には不動産の需要が減少し、物件価格が下落するとともに、賃料の引き下げや空室の増加が発生しやすいです。また、金利が上昇すると借り入れコストが増加し、不動産投資の利回りが低下するだけでなく、評価額自体も下がる傾向があります。
さらに、外国為替や海外投資マネーの流入・流出も、市場の需給バランスを変化させる要因です。こうした外部環境の変化は避けられないため、価格変動リスクは常に念頭に置く必要があります。
物件運営リスク
保有物件の収益は、入居率やテナントの安定性、管理状況によって大きく左右されます。
例えば、空室率が上昇すると賃料収入が減少し、収益性が直ちに低下します。テナントが賃料を滞納したり、経営破綻によって退去した場合も同様です。
加えて、契約更新時に賃料を引き下げざるを得ないケースや、入れ替わった新規テナントの契約条件が不利になる場合もあります。
さらに、建物や設備の老朽化が進めば修繕や更新工事が必要となり、それに伴うコスト増加が利益を圧迫します。これらの運営・収益リスクは、物件のタイプや立地条件、管理会社の能力にも大きく依存します。
流動性リスク
不動産は本来、現金化までに時間がかかる資産であり、株式や債券と比べると流動性が低いのが特徴です。
現物不動産を売却する場合、条件交渉や契約手続き、登記などにより数カ月から場合によっては年単位の時間がかかることがあります。さらに、不動産市場が低迷していると買い手が少なくなり、希望する価格で売却できない可能性もあります。
私募REITや私募ファンドでは、中途解約や持分売却が制限されている場合があり、運用期間中は資金が拘束されやすく、急な資金需要に対応しにくい点もデメリットです。こうした流動性の制約を事前に理解しておくことが重要です。
法制度・税制変更リスク
不動産投資は法律や税制の影響を大きく受けます。例えば、固定資産税や不動産取得税の増加は運用コストを押し上げ、利回りを低下させます。また、建築基準法や都市計画法の改正で建て替えや用途変更が制限されることや、賃貸契約関連の法律改正で賃料改定や契約条件が厳しくなる可能性もあります。
こうした制度改正は突然行われることも多いため、税理士や弁護士の助言を得たり、専門メディアで情報収集を行うことが重要です。
自然災害・事故リスク
地震や台風、洪水、豪雨などの自然災害は、不動産の物理的な損害を引き起こし、長期間の稼働停止や修復費用の発生につながります。
火災や事故も同様に、賃料収入の減少やテナントの退去を招く恐れがあります。さらに、土壌汚染やアスベストといった環境問題が発覚すると、利用制限や大規模な修復作業が必要となり、莫大(ばくだい)なコストが発生します。
特に自然災害は発生確率を完全に予測できないため、ハザードマップや建物の耐震・防災性能を確認し、保険加入などの対策を講じることが重要です。
運用会社の信用リスク
不動産ファンドや物件管理を担う運用会社の経営状態や運営能力は、投資成果を左右する重要な要素です。
運用会社が経営不安に陥ったり倒産すれば、物件の適切な管理や分配金の支払いが滞る恐れがあります。また、情報開示が不十分な場合や、投資家の利益よりも運用会社の利益を優先した運営が行われると、長期的な資産価値や収益性が損なわれます。
過去の運用実績や財務基盤、ガバナンス体制、コンプライアンス順守の姿勢などを事前に確認することで、このリスクをある程度軽減できます。
不動産投資を始める際の相談先
不動産投資を開始する際におすすめの相談先は主に次のとおりです。
- 不動産投資会社
- ファイナンシャルプランナー
- 信託銀行
- 税理士
それぞれのメリットと注意点を解説します。
不動産投資会社
不動産投資会社は、物件の選定から購入、運用サポートまで一貫して行う事業者です。自社で保有・管理する物件を紹介するケースや、投資家の希望条件に合わせて市場から物件を探すケースがあります。
不動産市場やエリア特性に精通しており、収益性や将来性を踏まえた提案を受けられるのが強みです。
ただし、自社利益を優先した提案が行われる可能性もあるため、複数社の情報を比較検討することが重要です。
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー(FP)は、資産形成やライフプラン全体を踏まえて、不動産投資の位置付けや資金計画を提案します。
物件や金融商品の販売を行わない独立系FPであれば、中立的な立場から助言を得られるのが特徴です。住宅ローンや保険、税制など幅広い知識を持っており、不動産投資を含む総合的な資産戦略を立てたい人に向いています。
ただし、個別物件の選定や契約条件の交渉などは対応範囲外の場合があります。
金融機関
銀行や信用金庫などの金融機関は、不動産投資に必要な融資やローン商品の提供を通じて資金面をサポートします。銀行融資は、不動産投資家が物件を購入・運用する際の主要な資金調達手段です。
金融機関は融資審査を通じて、物件の収益性や担保価値、借入希望者の返済能力を評価し、適切な融資条件を提示します。また、一部の金融機関では不動産投資に関するセミナーや市場情報の提供を行っており、投資判断の参考になる場合もあります。
ただし、融資条件や金利、返済期間は金融機関ごとに異なるため、複数行を比較して最適な条件を選ぶことが重要です。
税理士
税理士は、不動産投資に伴う税務処理や節税対策を専門的にサポートします。
不動産所得に関する確定申告や減価償却の計算、相続税・贈与税対策など、税金に関する重要な領域をカバーします。特に複数物件を保有する場合や法人化を検討する場合、税務の最適化によって手取り収益を大きく左右することがあります。
ただし、投資物件の選定やマーケット分析は専門外となる場合が多いため、他の相談先と併用するのが効果的です。
不動産ファンドに関するQ&A
最後に、不動産ファンドに関するよくある質問とその回答を紹介します。
Q.不動産ファンドの利回りはどれくらいか
A.不動産ファンドの利回りは、ファンドの種類や投資対象物件、運用方針によって異なります。
J-REITでは、一般的に年3〜5%程度の分配金利回りが目安とされますが、市場環境や物件稼働率、金利動向によって変動します。一方、非上場型の私募REITでは、4%程度が目安ですが、ファンドによってばらつきがあります。
高利回りの商品はリスクも高くなる傾向があるため、利回りの数字だけで判断せず、安定性や資産内容、流動性などを総合的に確認することが重要です。
Q.不動産ファンドにおけるAUMとは何か
A.AUMは「Assets Under Management」の略で、日本語では「運用資産残高」と呼ばれます。不動産ファンドの場合、ファンドが保有・運用している不動産の総額を指し、運用規模を示す重要な指標です。
AUMが大きいほど運用資産が多く、規模の経済や分散効果が働きやすい一方、必ずしも運用成績の良し悪しを保証するものではありません。
投資判断の際は、AUMの大きさだけでなく、その内訳やポートフォリオの質も確認する必要があります。
Q.不動産ファンドにおけるAMとは何か
A.AMは「Asset Management(アセットマネジメント)」の略で、不動産ファンドにおいては、ファンドの資産運用全般を担う業務や担当会社を指します。
AM会社は投資戦略の策定、物件取得や売却の判断、運用計画の立案、投資家への報告などを行い、ファンドの価値最大化を目指します。
現場での物件管理(PM:プロパティマネジメント)は別の役割であり、AMはファンド全体の資産ポートフォリオを戦略的に管理する立場です。
Q.不動産ファンドにおけるウォーターフォールとは何か
A.ウォーターフォール(Waterfall)とは、不動産ファンドにおける利益分配の仕組みを段階的に定めたルールのことです。
通常は、まず元本返還や優先分配を投資家に行い、その後、一定の利益率(ハードルレート)を超えた部分を運用者と投資家であらかじめ決められた割合で分配します。この仕組みにより、投資家は優先的に利益を確保できる一方、運用者は高い成果を上げることでインセンティブ報酬(キャリードインタレスト)を得られるようになっています。
ただし、この分配の条件や利益率はファンドごとに異なり、特にハードルレートや分配割合などは契約内容に明記されます。そのため、投資前に必ず契約内容を確認し、リスクとリターンを慎重に評価することが重要です。
Q.不動産特定共同事業とは何か
A.不動産特定共同事業とは、複数の投資家から資金を集め、その資金で不動産を取得・運用し、そこで得られた収益を出資者に分配する仕組みを指します。不動産特定共同事業法に基づく制度で、前述の分類では私募ファンドに該当します。
投資家と事業者の間で締結される契約の種類によって、次の3つに分けられます。
- 匿名組合型:投資家が事業者に資金を出資し、事業者が不動産を運用して収益を分配する形式です。投資家は不動産の所有権を持たず、損益の分配を受ける立場となります。この形態はクラウドファンディング型の不動産投資で広く採用されています。
ただし、事業者の倒産リスクや管理能力が投資家の利益に影響する可能性があるため、契約内容を十分に確認することが重要です。
- 任意組合型:投資家全員が共同事業主として組合を構成し、不動産の所有権を共有する形態です。実際の運用は事業者が代表して行いますが、投資家は所有者としての権利を持ち、運営への関与度合いが比較的高い点が特徴です。
- 賃貸借型:投資家が所有する不動産を事業者に賃貸し、事業者がその不動産を活用して収益を上げ、賃料や収益を分配する形態です。投資家は不動産の所有権を持ちつつ、運用は事業者に委ねる仕組みです。
Q.不動産クラウドファンディングとは何か
A.不動産クラウドファンディングとは、インターネットを通じて多数の投資家から少額ずつ資金を集め、その資金を用いて不動産を取得・運用し、得られた収益を分配する仕組みです。
不動産投資を小口化することで、従来は数百万〜数千万円の資金が必要だった不動産投資に、個人が数万円単位から参加できるようになった点が大きな特徴です。
不動産クラウドファンディングは不動産特定共同事業法に基づいて行われるため、前述の分類では私募ファンドに該当します。
Q.不動産STとは何か
A.不動産ST(セキュリティ・トークン)は、不動産ファンドの投資持分をブロックチェーン上で発行・管理し、権利移転できる金融商品です。
少額投資が可能でありながら、少数物件に投資できるため現物不動産に近い手触り感がある点が特徴です。J-REITに比べて分散効果や流動性は劣りますが、J-REITより市場変動の影響を受けにくい点も特徴です。
また、特性が近い不動産クラウドファンディングと比較して、投資運用期間が長期です。
J-REITと不動産クラウドファンディングの双方の利点を兼ね備えた不動産投資の新しいカタチといえます。
Q.J-REITはどのように始められるか
A.J-REITは証券取引所に上場しているため、株式と同じ手順で投資できます。
まず証券会社に口座を開設し、取り扱っているJ-REIT銘柄の中から投資先を選びます。投資判断の際は、利回りや運用資産の内容、投資対象エリア、運用会社の実績などを確認すると良いでしょう。
購入は株式同様に注文を出すだけで可能で、少額から投資できる銘柄もあります。購入後は分配金や価格動向、運用状況を定期的にチェックし、必要に応じて保有比率や銘柄を見直します。
まとめ
不動産ファンドは、不動産への投資をより手軽に、そして分散して行うための手段として、多くの投資家に注目されています。この記事を通じて、不動産ファンドの基本や種類、リスク、利回りについて理解が深まったのではないでしょうか。
不動産ファンドは少額から参加できるため、初心者でも始めやすい一方、リスクも存在するため、注意が必要です。次に、不動産ファンドへの投資を具体的に検討する際には、投資目的や期間、リスク許容度を明確にし、信頼できる運用会社を選ぶことが大切です。さらに、実際に投資を始める前には専門家に相談することもおすすめです。ぜひ、この知識を活かして、不動産ファンドへの投資をスムーズに始めてみてください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。