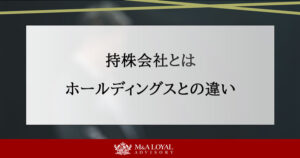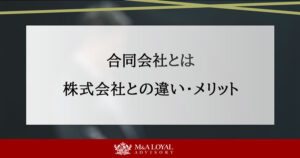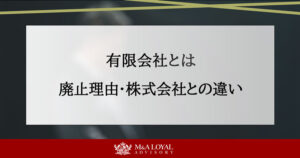純粋持株会社とは?メリット・デメリットを解説!有名企業の例も紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
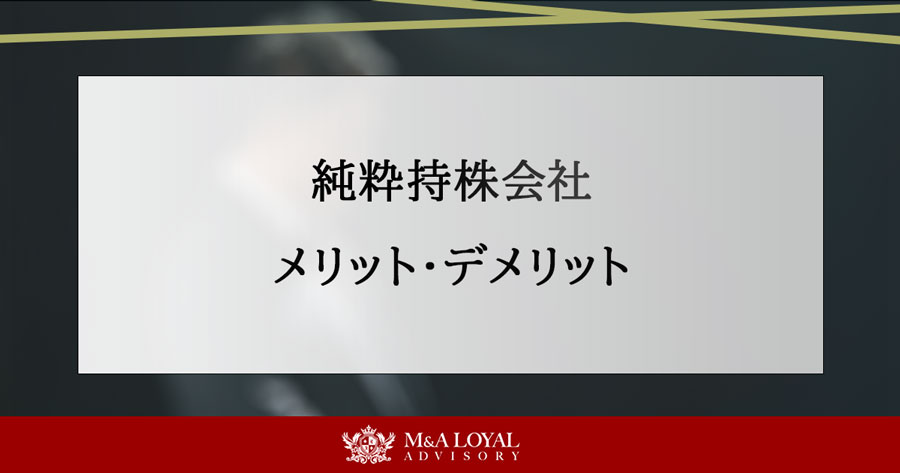
企業経営の多様化やグローバル化が進む中で、近年注目を集めているものが「純粋持株会社」という形態です。純粋持株会社は事業そのものは行わず、グループ会社の株式を保有・管理することに特化した仕組みであり、効率的な経営戦略の実行やリスク分散に大きな役割を果たします。一方で、経営コストの増加や社会的批判の対象となる場合もあり、導入には注意が必要です。
本記事では、純粋持株会社の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、事業承継やM&Aで活用される理由、さらには有名企業の具体例まで幅広く解説します。併せて、純粋持株会社の設立スキームや設立時に押さえておくべきポイントもご紹介しますので、経営者や起業家の方だけでなく、ビジネス全般に関心を持つ方にも役立つ内容となっています。
目次
純粋持株会社とは
まず、純粋持株会社の概要について紹介します。
純粋持株会社の概要
純粋持株会社とは、自社で製造や販売などの事業を直接行わず、他の会社の株式を保有することでグループ全体を支配・管理することを目的とした会社です。
経営陣や管理部門はグループの戦略立案や子会社の経営監督といった本社機能に専念します。
現在では上場企業グループだけでなく、中小企業の事業承継や資産管理のスキームとしても活用されています。
純粋持株会社の解禁
日本における純粋持株会社は、戦前の財閥解体を背景に長らく禁止されてきました。かつての財閥は持株会社を通じて銀行・製造業・商社などを系列化し、経済を支配していたため、戦後の独占禁止法では「株式を保有するだけの会社」の設立が原則禁止されていました。
しかし、バブル崩壊後の企業再編の必要性が高まる中で、1997年の独占禁止法改正により純粋持株会社が解禁されました。この改正は、日本企業がグローバル競争の中でグループ再編や事業ポートフォリオの見直しを柔軟に進められるようにすることを目的としていました。
純粋持株会社と事業持株会社の違い
純粋持株会社と事業持株会社の違いは、事業活動を行うかどうかという点にあります。
純粋持株会社は、自ら製造や販売といった事業を営むことは一切なく、子会社の株式を保有し、その経営方針を決定・監督することだけを目的としています。いわばグループ全体の「統括本部」として位置付けられ、子会社の経営管理や戦略調整を中心的な役割とします。
一方で事業持株会社は、子会社の株式を保有して経営に関与するだけでなく、自社としても一つの事業主体として活動します。
持株会社と株式会社の違い
持株会社と株式会社は、性質の異なる概念ですが、関連性があります。株式会社とは、会社法に基づく法人形態の一つであり、株主が出資して設立される組織を指します。株式会社は、一般的に営利を目的として事業を行い、得られた利益を株主に配当する仕組みを持つ「会社の形態」のことです。
一方、持株会社とは「会社の機能や役割」を表す言葉であり、通常は株式会社の形態をとります。持株会社は、その活動目的を「子会社の株式を保有・管理し、グループ全体を統括すること」に特化した会社を指します。ただし、持株会社は特定の法人形態に限定されるわけではなく、他の形態を取ることも可能です。
このように、持株会社は株式会社の一種として機能することが多いですが、その目的や役割において特異な存在です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



純粋持株会社以外の組織形態
純粋持株会社制以外に、次のような組織形態があります。
- 事業部制
- カンパニー制
- 分社制
それぞれを分かりやすく解説します。
事業部制
事業部制は、一つの会社の中に複数の「事業部」を設け、それぞれが独立した利益責任を持って運営される仕組みです。
例えば、家電メーカーであれば「テレビ事業部」「冷蔵庫事業部」「洗濯機事業部」と分けられ、各事業部が企画から販売までを担当します。
会社全体としては一つの法人ですが、事業部ごとに小さな会社のような役割を持つ点が特徴です。経営資源を効率的に配分でき、業績管理もしやすいですが、最終的な意思決定権は本社にあります。
カンパニー制
カンパニー制は、事業部制をさらに発展させた形で、各カンパニー(社内カンパニー)がより高い独立性を持つ仕組みです。
カンパニーごとに経営トップが置かれ、人事や財務などの機能もある程度持たせるため、社内に複数の「会社」が存在しているかのような形態になります。
トヨタやソニーなどの大企業で導入され、スピード感のある経営や多角化への対応が可能です。ただしあくまで一つの法人の中で運営されるため、法的には分社化とは異なります。
分社制
分社制は、既存の会社の一部門を切り離して新しい会社として独立させる方法です。
分社化によって設立された会社は、独立した法人格を持つため、資産・負債・従業員も新会社に移転します。これにより、責任の範囲を明確にできるほか、経営判断を迅速化したり、M&Aや事業売却をしやすくしたりする効果があります。
例えば、親会社が特定の事業をスピンオフさせて子会社として運営するケースは分社制にあたります。分社化された会社は純粋持株会社または事業持株会社によって管理されます。
純粋持株会社のメリット
事業持株会社と比較した際の純粋持株会社の主なメリットは次のとおりです。
- 事業戦略へリソースを集中できる
- 親会社の事業リスクを回避できる
- 経営判断が中立的にできる
- 財務構造がシンプルで分かりやすい
- 子会社が「兄弟会社」になり公平になる
それぞれを詳しく解説します。
純粋持株会社は事業戦略へリソースを集中できる
純粋持株会社は自ら事業を運営しないため、日々の販売活動や製造管理といったオペレーション業務に経営陣が時間や人材を割く必要がありません。その結果、トップマネジメントはグループ全体の長期的な方向性を考えることに専念できます。財務や法務といった各事業に共通して重要な部署を統合することで、経営を効率化できる側面もあります。
例えば、どの事業に追加投資を行うか、どの事業を縮小または売却するかといった大きな意思決定に集中できます。
これは、個別事業の売り上げ目標や現場課題に縛られやすい事業持株会社にはない大きな特徴であり、グループ全体の成長戦略を加速させる基盤となります。
純粋持株会社は親会社の事業リスクを回避できる
事業持株会社では、親会社が営む事業で発生した赤字や訴訟リスクがグループ全体に波及してしまう危険があります。これに対し、純粋持株会社は基本的に事業を持たないため、製品不良や取引先とのトラブル、景気変動による業績悪化といった直接的な事業リスクを抱えることはありません。ただし、純粋持株会社も子会社の業績やリスクの影響を受ける可能性があるため、完全にリスクから解放されているわけではありません。
そのため、グループの経営中枢である持株会社は、特に純粋持株会社の場合、安定した立場から長期的な管理・監督を行いやすいと言えます。
純粋持株会社は経営判断が中立的にできる
純粋持株会社は自社事業を持たないため、特定事業の利益や社内政治にとらわれることなく、グループ全体を公平な立場から見渡せます。
例えば、親会社自身が事業を抱えていると、その事業に有利な投資判断が優先され、子会社への投資判断がゆがむケースも起こりえます。
しかし純粋持株会社であれば、どの子会社も平等に評価され、グループ全体の最適化を第一にした意思決定が可能です。結果として、子会社間の資源配分や成長支援がバランスよく行われ、グループ全体の競争力を底上げできます。
純粋持株会社は財務構造がシンプルで分かりやすい
事業持株会社では、自社事業の売り上げや費用と子会社からの配当収入が混在するため、財務諸表が複雑になりやすく、外部への説明も難しくなります。これに対して、純粋持株会社は主な収益源が子会社からの配当であるため、財務構造は比較的シンプルです。ただし、そのシンプルさは各子会社の業績や配当政策に依存することもあります。財務諸表を見れば、どの子会社がどれだけグループに貢献しているかを比較的明確に把握できます。
その結果、投資家や金融機関に対して透明性の高い説明がしやすく、グループ全体の信頼性向上にもつながります。シンプルで分かりやすい財務構造は、資本政策を柔軟に進める上でも一般的に有利に働くと考えられますが、具体的な戦略や状況によっては異なる場合もあるため、注意が必要です。
純粋持株会社は子会社が「兄弟会社」になり公平になる
事業持株会社では、親会社が自ら事業を持つため、子会社から見ると「親会社の事業部」と「自分たちの会社」が親子(上下)の関係になります。この場合、親会社の事業が優遇されるのではないかといった不信感や摩擦が生じやすいのです。
純粋持株会社の場合、子会社同士はいずれも横並びの「兄弟会社」として位置付けられるため、親会社と子会社の間に競合構造が生まれません。
これにより、グループ内で公平性が保たれ、各子会社は対等な立場で協力やシナジーの創出に取り組みやすくなります。グループの一体感を高め、相互補完的な成長を促す上で大きな効果を持ちます。
純粋持株会社のデメリット
純粋持株会社の主なデメリットは次のとおりです。
- 経営管理コストの負担が大きくなる
- 経営関与が間接的になる
- モチベーションの低下リスク
- 社会的批判の対象になる場合がある
それぞれを詳しく解説します。
純粋持株会社は経営管理コストの負担が大きくなる
純粋持株会社は、事業を持たないにもかかわらず、グループ全体を監督するための本社機能を維持する必要があります。
例えば、経営企画や財務管理、人事制度設計、リスク管理、コンプライアンス体制の構築など、グループ全体に横串を通す管理部門が必要です。ところが、これらの本社部門は売り上げを直接生み出すわけではなく、純粋に「コストセンター」として機能します。
そのため、外部の投資家や株主から見ると、場合によっては経営効率を疑問視されることがあります。
純粋持株会社は経営関与が間接的になる
純粋持株会社は、自ら現場を抱えないため、事業環境や市場の変化を直接感じ取る機会が少なくなります。経営陣は子会社からの報告資料や経営会議を通じて情報を得ることになりますが、そこには必ずフィルターがかかるため、現場感覚を失いやすいのです。例えば、競合他社の新しい商品やサービスが市場で受け入れられるスピード、顧客の細やかなニーズの変化などは、実際に事業を動かしている当事者でないとつかみにくい部分です。
このため、純粋持株会社の経営判断が机上の分析や理論に偏り、現実との乖離(かいり)を招くリスクがあります。このリスクを軽減するためには、子会社との密なコミュニケーションや現場の情報を適切に収集するプロセスが重要です。
モチベーションの低下リスクがある
純粋持株会社は、基本的にグループ全体の経営管理や統制を行うことが主な役割であり、直接的に製品やサービスを市場に提供することはありません。そのため、持株会社に勤務する従業員にとって「自分たちが何を生み出しているのか」が分かりにくくなり、仕事のやりがいを感じにくくなる恐れがあります。
特に若手社員にとっては、商品をつくったり顧客にサービスを提供したりする経験が得られないため、モチベーションの低下やキャリア形成への不安につながることがあります。また、純粋持株会社は経営管理に特化するため、業務内容が形式的・官僚的になりやすく、「現場を支えている」という実感を持ちにくい傾向も見られます。
このような課題に対処するためには、持株会社も自らの役割を意識し、子会社との連携やコミュニケーションを強化することが重要です。
社会的批判の対象になる場合がある
日本では、かつて独占禁止法により持株会社の設立が禁止されていた歴史があり、「持株会社=支配や統制の仕組み」といったネガティブなイメージが一部に残っています。そのため、純粋持株会社は、租税回避や不透明な資本関係の温床として批判を受けやすい立場にあります。
実際、海外子会社を経由した税負担の軽減策が問題視されることもあります。このような状況を受けて、持株会社は法的規制や開示義務の強化の対象になりやすく、ガバナンスに関する社会的な監視の目が厳しくなるのです。
純粋持株会社が事業承継に活用される理由
前述した以外にも純粋持株会社は事業承継においてもメリットがあります。純粋持株会社が事業承継に活用される理由は主に次のとおりです。
- 株式の分散を防げる
- 節税できる可能性がある
- 資金調達がしやすい
- 先代経営者が現金を取得できる
それぞれを分かりやすく解説します。
株式の分散を防げる
事業承継において大きな課題となることが、相続によって株式が複数の相続人に分散してしまうことです。株式が分散すると、後継者が経営権を十分に握れず、意思決定に時間がかかる、経営方針が一致しない、親族間での対立が生じるといった問題が発生しやすいです。
純粋持株会社を設立して、株式をそこに集約しておけば、経営権を純粋持株会社に一元化できます
結果として、後継者は純粋持株会社を通じて安定した経営権を確保でき、グループ全体の運営を一貫して進められます。特に同族会社においては、株式分散の防止は承継成功の鍵となるため、この仕組みは大きな効果を発揮します。
節税できる可能性がある
贈与や相続で株式を承継すると、評価額が高く算定されやすく、後継者に大きな税負担がかかる可能性があります。これに対し、純粋持株会社を利用して株式を売却する形にすれば、課税は先代経営者に譲渡所得として一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が課されます。
株価などの条件によっては、この方法が贈与税や相続税よりも負担が軽くなり、結果的に節税につながる可能性があります。ただし、税制は非常に複雑であり、具体的な状況によって税負担が異なるため、専門家に相談することが重要です。
資金調達がしやすい
事業承継では、後継者が親会社の株式を取得するために多額の資金を必要とすることが少なくありません。個人で資金を調達することは難しく、銀行融資を受けるにも限界があります。
そこで、純粋持株会社を設立しておけば、純粋持株会社が子会社の株式や不動産といった資産を保有します。これらの資産を担保にして金融機関から資金を調達することで、後継者は大きな個人負担を背負わずに承継を進めることができます。
つまり、純粋持株会社はグループ全体の信用力を生かした資金調達のハブとして機能し、承継の資金計画を柔軟に設計できるようになります。ただし、成功するためには適切な経営戦略と財務管理が重要です。
先代経営者が現金を取得できる
純粋持株会社を活用すれば、先代経営者は自社株式を持株会社に売却し、その対価としてまとまった現金を受け取れます。
これにより、引退後の生活資金を確保できるだけでなく、資産運用や退職後のライフプランに充てられます。しかし、前述したとおり、先代経営者に譲渡所得が課される点には注意が必要です。
純粋持株会社がM&Aの推進に有効な理由
純粋持株会社はM&Aを推進するために組織されることがあります。純粋持株会社がM&Aに有効な理由は次のとおりです。
- 多角化に適している
- PMI(統合プロセス)を円滑にできる
- M&Aの相談が増加する
それぞれを詳しく解説します。
多角化に適している
純粋持株会社は、自ら事業を営まず、グループ全体の統括・管理を担うことに専念しています。そのため、既存事業と直接的な関連性のない企業をM&Aによって傘下に収める際にも、組織上の違和感が生まれにくい点が特徴です。
通常の事業会社が本業と関係のない分野の企業を買収すると、親会社と子会社との間で指揮命令系統がスムーズに機能せず、経営上の摩擦を生むことがあります。しかし、持株会社体制では、子会社が並列的に管理される仕組みが整っているため、事業ポートフォリオを柔軟に拡張でき、多角化戦略を円滑に進めることが可能です。
PMI(統合プロセス)を円滑にできる
M&Aにおける大きな課題の一つが、買収後の統合プロセス(PMI)です。特に、買収対象が競合関係にある場合、被買収企業の従業員は「敵対的に支配される」という感覚を抱きやすく、モチベーションの低下や人材流出につながるリスクがあります。事業会社が直接子会社化した場合、この懸念は一層強まります。
これに対し、持株会社体制であれば、買収後の会社は他の事業子会社と「兄弟会社」という立ち位置で並列化されるため、従業員の心理的な抵抗感が軽減されます。結果として、組織文化の融合や業務プロセスの調整がスムーズに進み、統合後の成果を早期に発揮しやすくなるのです。
M&Aの相談が増加する傾向がある
持株会社化している企業にはM&Aの案件が集まりやすい傾向があります。金融機関やM&A仲介会社は「持株会社はM&Aを推進しやすい体制を備えている」と認識しているため、自然と新規案件を提案しやすくなります。
案件の情報が豊富に集まることで、選択肢の幅が広がり、より自社に適した買収対象を見極めやすくなります。結果として、M&Aの成約率が高まり、グループ全体の成長スピードを加速させる好循環を生み出すのです。
純粋持株会社の有名企業
純粋持株会社制を取り入れている有名企業を紹介します。
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、銀行、信託、証券、アセットマネジメント、コンシューマーファイナンスなどを傘下に持つ日本最大の金融持株会社です。グループ各社の専門性と「グループ総合力」を生かし、多様な顧客ニーズに応えるソリューションを提供しています。
強固なバランスシートと最大級の顧客基盤を背景に国内での競争力を強化する一方、APAC地域では世界最大級のエクスポージャーを有し、モルガン・スタンレーとの連携を通じて米国経済の成長も取り込み、グローバルに安定した成長を実現しています。
野村ホールディングス
野村ホールディングスは、グローバルに展開する日本有数の金融持株会社であり、野村グループ各社を統括しています。グループは「ウェルス・マネジメント」「インベストメント・マネジメント」「ホールセール」「バンキング」という四つの部門を柱とし、横断的な連携によって国内外の顧客に多様なソリューションを提供しています。
個人・法人向けの資産管理サービスから、機関投資家向けのリサーチやトレーディング、M&Aアドバイザリー、さらに信託・銀行機能を生かした資産承継や資金調達まで、幅広い領域をカバーしています。強固な専門性とグローバルネットワークを背景に、持株会社としての統括力と事業会社の実行力を組み合わせ、顧客価値の最大化と持続的な成長を追求しています。
ソニーグループ
ソニーグループ株式会社は、2021年4月1日にソニー株式会社から商号を変更して発足した純粋持株会社です。従来のソニー株式会社が担っていたグループ本社機能とエレクトロニクス事業の本社間接機能を分離・再定義し、グループ本社機能に特化した会社として位置付けられています。
ソニーグループ株式会社の主なミッションは、事業ポートフォリオ管理とそれに基づく資本配分、グループシナジーと事業インキュベーションによる価値創出、人材と技術への長期的投資を通じたグループ全体の価値向上です。こうした役割を担うことで、ソニーグループ全体の持続的成長と競争力強化を推進しています。
パナソニックホールディングス
パナソニック株式会社は、2022年4月に持株会社制へ移行し、商号を「パナソニックホールディングス株式会社」に変更しました。持株会社制への移行は、2019年に策定した中期戦略に基づく基幹事業の強化、不採算事業の再編、さらには新型コロナウイルスや地政学リスクなど急速に変化する経営環境に対応するための決断です。
持株会社化により、事業会社ごとに明確な責任と権限を付与し、自主責任経営を徹底することで、迅速な意思決定や柔軟な制度設計を可能にしました。グループ本体であるパナソニックホールディングスは、事業会社の成長を支援するとともに、グループ全体最適の視点から成長領域の確立に注力し、企業価値の向上を目指しています。
博報堂DYホールディングス
博報堂DYホールディングスは、2003年10月1日に株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社読売広告社の3社による株式移転方式を通じて設立された共同持株会社です。この方式により3社はホールディングスの100%子会社となり、それぞれの個性や強みを生かしつつ、従来どおりの競争関係を維持しながら多様なソリューションを提供できる体制を整えました。
発足同年の12月1日には、3社のメディア機能を統合し、総合メディア事業会社「博報堂DYメディアパートナーズ」を設立しました。これにより、広告事業のみならずメディア領域における課題解決力を強化しました。日本に前例のない新しい枠組みの広告会社グループとして、クライアントや媒体社、さらには生活者や社会全体に対して創造的かつ多様な価値を提供し続けることを使命としています。
純粋持株会社を設立するスキーム
純粋持株会社を設立する主なスキームは次のとおりです。
- 株式移転
- 株式交換
- 会社分割(抜け殻方式)
それぞれを分かりやすく解説します。
株式移転
組織再編における株式移転とは、既存の会社が新たに親会社を設立し、その親会社に既存会社の発行済株式を取得させることで、既存会社を子会社化する方法です。このスキームでは、新たに設立される会社が純粋持株会社となり、既存会社はその傘下に入ります。
ポイントは、既存会社自体は存続法人として残るため、もしその会社が許認可事業を行っている場合でも、改めて許認可の移転手続きを行う必要がなく、従来どおり事業を継続できるという点です。
さらに、株式移転は金銭出資を伴わずに実行できるため、多額の資金を準備せずとも純粋持株会社を設立できる柔軟性があります。複数の会社を一つの持株会社のもとに統合したい場合や、新たにグループの中核となる親会社を作りたい場合によく利用される方法です。
株式交換
株式交換とは、既存会社の株主が保有している株式を、既に存在している持株会社の株式と交換することで、持株会社が既存会社の全株式を取得し、完全子会社化する方法です。
株式移転が「新しく持株会社を設立する」手法であるのに対し、株式交換は「既に存在する会社を親会社として利用する」という点で異なります。
株式交換も株式移転同様に資金を準備する必要はありません。
会社分割(抜け殻方式)
「抜け殻方式」と呼ばれる手法では、既存会社が営んでいた事業を新たに設立した子会社へ移し、元の会社は事業を持たずに子会社の株式だけを保有する純粋持株会社に変わります。
抜け殻方式も現金の調達は不要です。
株主構成を維持したまま持株会社化できます。さらに事業を段階的に移管できるため、株主関係がシンプルな場合や事業ごとに適切なタイミングで分社化したい場合に適した方法です。
純粋持株会社を設立する際のポイント
純粋持株会社を有効に活用するためのポイントは次のとおりです。
- 目的を明確化する
- 税務を正しく処理する
- 労務・法務を正しく対処する
それぞれを解説します。
目的を明確化する
純粋持株会社を設立する際には、まず「なぜ持株会社体制に移行するのか」という目的を明確にすることが重要です。
グループ全体の経営を効率化するためなのか、事業承継のためなのか、あるいはM&Aを見据えた再編なのかによって、最適な設計は変わってきます。
目的をはっきりさせておかないと、持株会社体制に移行したものの管理コストだけが増え、期待した効果が得られないケースもあります。設立前に目的を整理し、その目的を達成するためにどのような組織設計が必要かを検討することが欠かせません。
税務を正しく処理する
持株会社化には「受取配当益金不算入制度」など税務上のメリットがありますが、その一方で税務処理は複雑化します。
また、持株会社設立時の株式移転や会社分割の際にも、税務上の取り扱いが複雑になる場合があります。そのため、税務の専門家と連携し、適切な仕組みと申告体制を構築することが不可欠です。
労務・法務を正しく対処する
純粋持株会社の設立にあたっては、労務面や法務面での対応も重要です。例えば、従業員が新設会社へ転籍する場合には、労働契約の承継や就業規則の整備といった労務対応が必要です。
また、許認可事業を行っている会社を子会社化する場合には、許認可の取り扱いや関連法令の確認が欠かせません。
さらに、公正取引委員会や金融庁などの規制当局から監督を受ける可能性があるため、法務リスクを事前に洗い出しておく必要があります。こうした労務・法務の課題に対応することによって、持株会社体制への移行をスムーズに進められます。
純粋持株会社に関するQ&A
最後に、純粋持株会社に関するよくある質問とその回答を紹介します。
日本初の純粋持株会社はどの会社か
1997年の独占禁止法改正により、純粋持株会社の設立が解禁されました。日本で最初に純粋持株会社体制へ移行したのは大和証券グループであり、1999年4月に持株会社制へ移行し、証券業界の中核企業を束ねる形でグループ経営を開始しました。その後、他の金融機関や大企業も次々と純粋持株会社化を進め、現在では多くの業界で一般的な形態となっています。
ホールディングスとは何か
「ホールディングス(Holdings)」とは、英語の hold(持つ・保有する)に由来し、子会社の株式を保有してグループ全体を管理・支配する会社を指します。日本では社名に「〜ホールディングス」と付けるケースが多く、略して「HD」と表記される場合もあります。また、持株会社の社名には「〜グループ」が用いられることも一般的です。
なお、「持株会社」の正しい英語表現は「ホールディングカンパニー(Holding Company)」です。
受取配当益金不算入制度とは何か
受取配当益金不算入制度とは、法人が他の会社から受け取った配当金の一定割合を課税所得に含めずに済む制度です。これは同じ利益に二重に課税することを避けるために設けられた仕組みであり、持株会社を含む法人にとって重要な税務上のメリットです。
適用される割合は株式の保有割合によって異なり、支配関係の強い子会社からの配当であれば100%益金不算入とされるケースもあります。これにより、持株会社は子会社から受け取った配当を効率的にグループ全体の資金循環に回すことが可能となり、内部留保の活用や再投資の原資確保につながります。
特に純粋持株会社は収益源を子会社からの配当に依存しているため、この制度の恩恵を大きく受ける存在です。
中間持株会社とは何か
中間持株会社とは、純粋持株会社の下に設けられ、特定の事業領域や地域に属する子会社群を統括するための持株会社です。例えば、グローバルに展開する企業グループが「アジア地域を統括する持株会社」や「IT関連事業を統括する持株会社」を設置する場合がこれに当たります。
中間持株会社を設置することで、最上位の持株会社が全ての子会社を直接管理する必要がなくなり、組織の階層を整理しやすくなります。これにより、現場に近いレベルでの迅速な経営判断が可能となり、地域特性や事業特性に応じた柔軟なマネジメントが実現します。大規模なグループ企業では、純粋持株会社→中間持株会社→事業子会社という三層構造が一般的に採用されています。
資産管理会社とは何か
資産管理会社とは、事業活動を行わず、株式・不動産・金融資産などの保有や管理を目的とする会社です。純粋持株会社と似た点がありますが、資産管理会社は必ずしも企業グループ全体を経営統括するために設立されるわけではありません。
特にオーナー企業や富裕層においては、相続税や贈与税の負担を軽減する目的で資産管理会社が利用されます。例えば不動産を資産管理会社に移し替えることで相続評価額を下げられるケースや、株式を資産管理会社にまとめることで次世代への承継を容易にするケースがあります。
つまり、資産管理会社は「グループ経営を統制する会社」ではなく、「資産の保有・承継を効率的に行うための会社」という点で、純粋持株会社とは目的が異なります。
純粋持株会社が解消される理由は何か
純粋持株会社は企業グループの経営を効率化する仕組みとして増えている一方で、逆に解消されるケースも見られます。その背景にはいくつかの典型的な理由があります。
まず挙げられることは、さらなる統合を目指す場合です。持株会社体制を導入した後に、グループ内外での再編が進み、よりシンプルな形で事業を一本化した方が経営効率が高まると判断されるケースがあります。
次に、事業の整理や統合に伴う組織体制の変更です。不要な子会社を整理したり、事業を再編したりする過程で、持株会社の存在意義が薄れ、解消に至ることがあります。
また、本業の不振による合理化対策も理由の一つです。事業環境の悪化や収益力の低下に直面した際、グループ全体の管理コストを削減するために、持株会社を廃止して組織をスリム化する動きが生じます。
最後に、当初想定していたより成果が出ないことがあります。グループシナジーや経営効率化を狙って設立したものの、思ったほどメリットが得られず、かえって本社機能の重複やコスト増が目立つようになり、結果として持株会社体制を見直すことになるのです。
中小企業が持株会社を組織するメリットは何か
中小企業にとって持株会社を組織するメリットは、事業ごとに分社化してグループ傘下に収めることでリスクを切り分けられるため赤字事業や新規事業の影響が本体に直接波及しにくくなる、事業承継の際に節税できる場合がある、などです。
また、持株会社を通じてグループ全体の資金調達や投資判断を一元化できるため、M&Aを活用した成長戦略にも適しています。
持株会社と持株会の違いは何か
持株会社と持株会は名前が似ていますが、その役割や性格は全く異なります。
持株会社は、子会社の株式を保有してグループを統括・管理する法人であり、経営戦略やM&Aをリードする「司令塔」の役割を果たします。
これに対して持株会は、従業員や取引先などが自社株式を共同で保有するための組織であり、福利厚生制度や従業員の資産形成、安定株主の確保を目的としています。
持株会社とコングロマリットの違いは何か
コングロマリットは、多角的な事業を展開する企業グループ全体を指す言葉であり、異なる業種や市場において複数の事業を持つ企業の形態を表す概念です。例えば、電機メーカーが金融、保険、不動産といった異業種に進出し、複数の分野で収益を上げている状態はコングロマリットと呼ばれます。
これに対して持株会社制は「グループ会社の経営の仕組み」を表す概念で、株式保有を通じて複数の子会社を支配し、グループを統括する役割を担います。
コングロマリットの多くの企業は持株会社制を取り入れています。
持株会社とコンツェルンの違いは何か
コンツェルンはドイツ語由来の概念で、資本関係や人的関係などを通じて複数の企業が一体となって活動する「企業集団」を意味します。日本では「企業グループ」や歴史的には「財閥」とほぼ同義で用いられることもあります。
持株会社が株式の保有によって子会社を統括するのに対し、コンツェルンはより広い概念で、持株会社制を中心とした企業結合の形態を指します。
まとめ
純粋持株会社は、企業が効率的な経営を追求するための組織形態の一つです。特に、事業戦略の集中やリスク管理、グループ全体の調和を図りたい企業にとって、大きなメリットを提供します。しかし、その一方で管理コストの増加や、経営の複雑化といったデメリットも考慮する必要があります。
これらを踏まえて、純粋持株会社の設立を検討している方は、まず自社の経営目的や戦略を明確にし、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断することが重要です。また、実際に持株会社を利用している企業の事例を参考にし、具体的な成功例や課題を学ぶこともおすすめです。今後の経営方針をしっかりと固めるためにも、まずは専門家への相談をし、必要な情報を集めることから始めてみてください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。