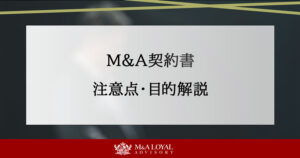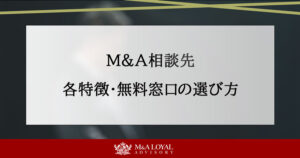NDAとは?秘密保持契約書の基本知識と作成のポイントを徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
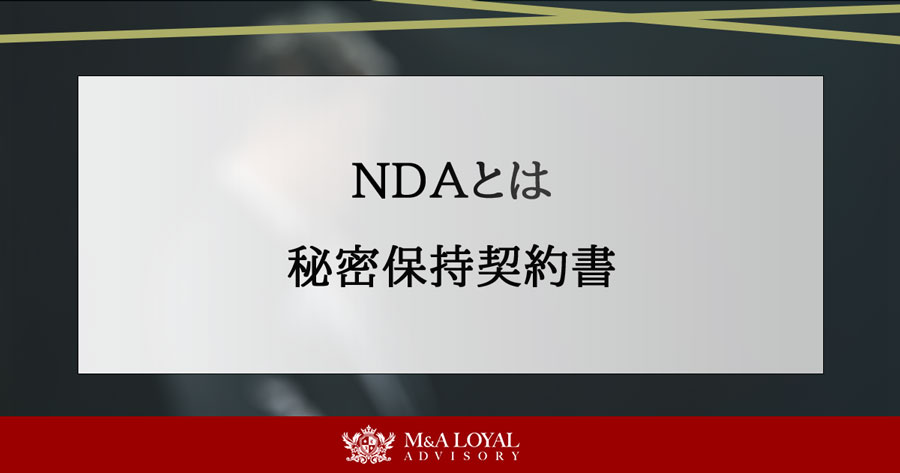
NDAとは、「Non Disclosure Agreement」の略で、日本語では秘密保持契約と呼ばれます。会社の売却や業務提携、新規取引の開始において、財務情報や顧客情報、技術ノウハウなどの機密情報を開示する機会は少なくありません。
こうした情報が第三者に漏洩すれば、企業の信用失墜や競争力の低下につながり、場合によっては企業存続の危機を招く可能性もあります。そこで重要なのが、秘密保持契約であるNDAです。NDAを適切に締結することで、開示した情報の不正利用や漏洩を防ぎ、万が一の際には法的な対応を取ることができます。
本記事では、M&Aや取引の現場で必要となるNDAの基本知識から、締結のタイミング、契約書に盛り込むべき重要な条項、さらにはM&Aにおける具体的な活用方法まで、中小企業のオーナー様にも分かりやすく解説します。
目次
NDA(秘密保持契約)とは
企業が保有する情報には、公開情報と非公開情報があります。非公開情報の中でも特に重要なものが秘密情報であり、これらが外部に流出すれば事業の継続が困難になる場合もあります。NDAを締結することで、どの情報が秘密情報に該当するのか、その情報をどのように取り扱うべきか、違反した場合にどのような責任を負うのかを明確にできます。
NDAの法的役割
NDAは単なる形式的な書類ではなく、法的拘束力を持つ正式な契約です。契約を締結した当事者は、契約書に記載された義務を履行する法的責任を負います。秘密保持義務に違反した場合、債務不履行として損害賠償請求の対象となることもあります。
また、NDA締結前に口頭で「この情報は他言しない」と約束していても、契約書がなければ法的な証明が困難です。後から「聞いていない」「そんな約束はしていない」と言われてしまえば、法的な対応が取れません。こうしたリスクを回避するためにも、NDAという書面による契約が重要です。
不正競争防止法との違い
日本には不正競争防止法という法律があり、営業秘密の不正取得や使用、開示を禁止しています。しかし、この法律で保護される営業秘密には厳格な要件があり、全ての企業情報が保護されるわけではありません。具体的には、秘密として管理されている情報であること、有用な情報であること、公然と知られていない情報であることの3要件を満たす必要があります。
これに対してNDAでは、契約当事者間で合意した範囲の情報を全て秘密情報として定義できます。不正競争防止法の要件を満たさない情報であっても、NDAを締結しておけば契約上の保護を受けられるため、より広範囲な情報保護が可能になります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



NDA締結のタイミング
NDAの効力は、契約締結の時点から発生します。つまり、契約を結ぶ前に開示してしまった情報は、原則として保護の対象外となります。そのため、秘密情報を開示する前、つまり具体的な情報交換を始める前にNDAを締結することが重要な原則です。
では、実際のビジネスシーンにおいて、どのようなタイミングでNDAを締結すべきなのでしょうか。以下に代表的な場面を紹介します。
商談や提案の初期段階
新規顧客への営業活動や新しいサービスの提案を行う際には、自社の製品やサービスの詳細を説明する必要があります。この段階で、製造方法や技術的なノウハウ、価格戦略、顧客リストなどを開示することがあります。相手が信頼できる企業であっても、口約束だけでは情報の保護は保証されません。
特に初めて取引を行う相手や、業界内で競合関係にある可能性がある企業との商談では、詳細な情報提供を始める前にNDAを締結することが重要です。万が一、商談が不成立に終わった場合でも、開示した情報が他社に流れたり、競合製品の開発に利用されたりするリスクを防げます。
取引開始時と継続的な取引
取引が正式に開始される段階では、より高度な情報共有が必要になります。発注情報、在庫状況、生産計画、物流ルートなど、日常業務に関わる多くの情報が行き交います。こうした情報の中には、自社のビジネスモデルや取引先との関係性が明らかになるものも含まれます。
取引開始時にNDAを締結しておくことで、取引の中で開示する企業情報を保護できます。また、取引契約書の中に秘密保持条項を盛り込む方法もありますが、より詳細な保護を求める場合には、別途NDAを締結することが推奨されます。
提携や協業の検討段階
資本提携や業務提携、共同開発などを検討する際には、お互いの財務状況や経営戦略、技術情報などを開示し合う必要があります。特に上場企業や上場を目指す企業の場合、未公表の財務情報や経営方針が外部に漏れると、株価への影響や信頼失墜につながる可能性があります。
提携の検討段階は、まだ正式な契約に至っていないため、情報開示に慎重になる必要があります。この段階でNDAを締結することで、検討が不成立に終わった場合でも、開示した情報の不正利用を防ぐことができます。
従業員の入社時と退職時
従業員は日々の業務を通じて、顧客情報、技術情報、経営戦略など多くの秘密情報に触れる立場にあります。特に中小企業では、少数の従業員が重要情報にアクセスする場合が多く、情報管理の重要性が高まります。
入社時には雇用契約書や就業規則に秘密保持条項を盛り込むことが一般的ですが、特に重要なポジションや機密性の高い部署に配属される従業員とは、別途NDAを締結することが推奨されます。また、退職時にも改めてNDAを締結し、退職後も一定期間は秘密保持義務が継続することを明確にすることで、情報漏洩のリスクを低減できます。
NDA締結の目的
NDAを締結する主な目的は、自社の秘密情報を保護し、ビジネス上のリスクを最小限に抑えることです。しかし、その効果は単なる情報漏洩の防止にとどまりません。ここでは、NDA締結によって得られる具体的なメリットを解説します。
秘密情報の流出防止と管理の明確化
NDAの大きなメリットは、秘密情報の流出を未然に防ぐ効果です。契約によって情報の利用目的や取り扱い方法を明確に定めることで、受領者は契約の範囲内でのみ情報を使用することが義務づけられます。また契約終了後には情報の返還や破棄を求めることができるため、情報が不要に拡散するリスクを抑えられます。
さらに、NDAには情報管理の明確化という効果もあります。どの情報が秘密情報であり、どのように管理すべきかが契約書に明記されるため、社内での情報管理体制の構築にも役立ちます。従業員や取引先に対しても、情報の重要性を認識させる教育的な効果があります。
保護対象となる情報範囲の拡大
前述のとおり、不正競争防止法で保護される営業秘密には厳格な要件があります。しかし、NDAを締結することで、法律の要件を満たさない情報であっても、契約上の秘密情報として保護できます。例えば、一般的なビジネス情報や将来の事業計画、検討中のアイデアなども、NDAで定義すれば保護の対象となります。
また、NDAでは秘密情報の定義を柔軟に設定できます。書面で開示される情報だけでなく、口頭で伝えられた情報や、会議の場で共有された情報なども、契約書の定義次第で秘密情報に含めることが可能です。これにより、より幅広い情報を保護できるメリットがあります。
損害賠償請求と差止請求の権利確保
NDAに違反して秘密情報が漏洩した場合、契約違反として損害賠償を請求できます。契約書に損害賠償の範囲や計算方法を明記しておくことで、実際に損害が発生した際の立証や請求がスムーズになります。また、違約金条項を設けることで、損害額の立証が困難な場合でも一定の金銭的補償を受けられます。
さらに、NDAには差止請求権を明記することも可能です。これにより、情報の不正使用を発見した際に、裁判所に対して使用の差止を求めることができ、被害の拡大を防止できます。損害賠償と差止請求の両方を契約に盛り込むことで、違反への抑止力が大きく高まります。
NDA締結時の重要な注意点
NDAを締結する際には、契約内容を十分に確認し、自社にとって不利な条項がないか、必要な保護が得られるかをチェックすることが重要です。特に相手方から提示されたNDA案をそのまま署名してしまうと、後で問題が生じる可能性があります。
秘密情報の定義と範囲の適切性
NDAで重要な条項の一つが、秘密情報の定義です。定義が曖昧だと、どの情報が保護されるのか不明確になり、紛争の原因となります。秘密情報の定義は、できる限り具体的かつ明確に記載することが望ましいです。例えば「本契約に基づいて開示される全ての技術情報、財務情報、顧客情報」といった包括的な表現と、具体的な情報の例示を組み合わ せることで、定義の明確性を高められます。
一方で、秘密情報から除外される情報についても確認が必要です。一般的に、以下のような情報は秘密情報から除外されます。
- 開示時点で既に公知となっていた情報
- 開示後に受領者の責めによらず公知となった情報
- 開示前に受領者が既に保有していた情報
- 第三者から適法に取得した情報
これらの除外事項が適切に規定されているかを確認し、自社が開示する情報が除外事項に該当しないかをチェックすることが重要です。
使用目的の明確化と制限
秘密情報の使用目的を明確に定めることも重要です。NDAでは通常、「本契約の目的のためにのみ使用する」といった目的外使用の禁止条項が設けられます。ここでいう「本契約の目的」が何を指すのかを具体的に記載することで、情報の不正利用を防げます。
例えば、M&Aの検討のために情報を開示する場合、「本契約の目的は、両社間の株式譲渡の検討および交渉に限定される」といった具合に、使用目的を明確にします。これにより、受領者が他の事業目的で情報を使用することを防止できます。
秘密保持期間と契約終了後の対応
NDAには秘密保持義務の有効期間を定めることが一般的です。期間が短すぎると十分な保護が得られず、長すぎると相手方の負担が大きくなり、契約締結が困難になる可能性があります。一般的には、契約締結から1年から5年程度の期間が設定されることが多いですが、情報の性質や取引の内容に応じて適切な期間を設定します。
また、契約終了時または契約期間満了時の対応についても明確に規定します。具体的には、開示した秘密情報の返還または破棄を求める条項を設けることが一般的です。返還だけでなく、複製物やバックアップデータの破棄についても明記し、情報が受領者の手元に残らないようにすることが重要です。
損害賠償と違反時の対応策
NDA違反が発生した場合の対応策を契約書に明記することで、実際に違反が起きた際の対応がスムーズになります。損害賠償の範囲や計算方法、違約金の有無、差止請求の可否などを明確にしておくことが推奨されます。
NDA締結の具体的な流れ
実際にNDAを締結する際の流れと、実務上のポイントについて解説します。NDAは契約の一種であるため、両者の合意が必要であり、一方的な内容では締結できません。
NDA締結までのステップ
NDA締結の一般的な流れは以下のとおりです。
- NDAのドラフト(草案)を作成する
- ドラフトを相手方に提示し、内容の確認と修正を依頼する
- 双方で内容を協議し、必要に応じて修正を加える
- 最終的な内容に双方が合意したら、契約書に署名・捺印を行う
- 契約書の原本を双方で保管する
開示側がドラフトを作成するのが一般的ですが、受領側から提示される場合もあります。いずれの場合も、内容をよく確認し、自社にとって不利な条項がないかをチェックすることが重要です。
電子契約の活用
近年では、電子署名を用いた電子契約によるNDA締結が増えています。電子契約には以下のようなメリットがあります。
- 契約締結のスピードが速い(郵送の時間が不要)
- 印紙税が不要(紙の契約書には印紙が必要な場合がある)
- 契約書の保管や検索が容易
電子契約サービスを利用する場合には、電子署名法に準拠したサービスを選ぶことが重要です。適切な電子署名が付与されていれば、紙の契約書と同等の法的効力が認められます。
NDAで定めるべき主な条項
NDAには以下のような条項を盛り込むことが一般的です。各条項の内容を理解し、自社の状況に合わせて適切に設定することが重要です。
| 条項名 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 秘密情報の定義 | 保護対象となる情報の範囲を定義 | 具体的かつ包括的に記載し、除外事項も明記 |
| 使用目的の制限 | 秘密情報の使用目的を限定 | 目的外使用を禁止し、目的を明確に規定 |
| 秘密保持義務 | 第三者への開示禁止と厳重管理義務 | 開示先の制限と管理方法を具体的に記載 |
| 有効期間 | 契約の有効期間と義務の継続期間 | 情報の性質に応じて適切な期間を設定 |
| 返還・破棄義務 | 契約終了時の情報の返還または破棄 | 複製物やデータの破棄についても明記 |
| 損害賠償 | 違反時の損害賠償責任 | 範囲と計算方法を明確にし、違約金も検討 |
| 準拠法・管轄 | 契約に適用される法律と管轄裁判所 | 自社に有利な裁判所を指定 |
これらの条項を適切に設定することで、実効性の高いNDAを作成できます。
M&AにおけるNDAの重要性
M&A(企業の合併・買収)のプロセスにおいて、NDAは極めて重要な役割を果たします。M&Aでは、機密性の高い情報が開示されるため、情報漏洩のリスクも大きくなります。ここでは、その重要性について解説します。
マッチング段階でのNDA
M&Aでは、企業の財務状況、取引先情報、従業員情報、知的財産など、機密性の高い情報が開示されるため、情報漏洩のリスクも高まります。
マッチング段階でのNDAは、企業名や具体的な財務情報、事業内容などを保護するために締結されます。特に中小企業の場合、M&Aを検討していること自体が外部に漏れると、取引先や従業員の不安を招き、事業運営に支障をきたす可能性があります。そのため、初期段階からのNDA締結が不可欠です。
基本合意書(LOI/MOU)における秘密保持
M&Aの交渉が進展すると、基本合意書(Letter of Intent: LOI、またはMemorandum of Understanding: MOU)が締結されます。基本合意書は、M&Aの基本的な条件(譲渡価格の概算、譲渡時期、デューデリジェンスの実施など)について合意する書面です。
基本合意書には、秘密保持義務と独占交渉権に関する条項が含まれることが一般的です。これらの条項には法的拘束力が認められるため、基本合意の段階であっても秘密保持義務違反は損害賠償の対象となります。特にデューデリジェンスでは、さらに詳細な情報が開示されるため、基本合意書における秘密保持条項の重要性は非常に高いといえます。
最終契約(DA)と包括的な秘密保持
デューデリジェンスを経て、最終的な条件に合意すると、最終契約書(Definitive Agreement: DA)が締結されます。最終契約書には、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書などがあり、M&Aの全条件が詳細に記載されます。
最終契約書の一般条項には、秘密保持義務に関する規定が含まれることが一般的です。この段階での秘密保持義務は、M&A取引に関連して開示されたすべての情報を包括的に保護するものであり、取引実行後も一定期間継続します。また、クロージング後の情報共有や統合プロセスにおける秘密保持についても規定されます。
M&AにおけるNDAの特殊性
M&AにおけるNDAには、通常の取引におけるNDAとは異なる特殊な条項が含まれることがあります。例えば以下のようなものです。
- スタンドスティル条項(買い手による敵対的買収の禁止)
- デューデリジェンスで取得した情報の特別な取扱い
これらの条項は、M&A取引の円滑な進行と、売り手企業の事業価値の保全のために重要な役割を果たします。
NDA作成における専門家の必要性
インターネット上には、NDAのテンプレートや雛形が多数公開されています。これらを利用することで、基本的なNDAを作成することは可能です。しかし、実際のビジネスシーンでは、取引の内容や業種、開示する情報の性質によって、必要となる条項や表現が異なります。
雛形利用のリスク
雛形をそのまま使用した場合、自社の状況に合わない条項が含まれていたり、必要な保護が得られなかったりする可能性があります。また、法律の改正や判例の変化により、雛形の内容が最新の法的要件を満たしていない場合もあります。
特に重要な取引やM&Aにおいては、雛形だけに頼るのではなく、専門家のアドバイスを受けることが強く推奨されます。弁護士や公認会計士、税理士などの専門家は、取引の内容を理解した上で、適切なNDAの作成や修正をサポートしてくれます。
M&Aにおける専門家の役割
M&Aのような高度な取引では、NDAだけでなく、基本合意書や最終契約書など、複数の契約書が必要になります。これらの契約書は相互に関連しており、整合性を保つことが重要です。また、税務や会計の観点からも、契約内容を適切に設計する必要があります。
M&A専門のアドバイザーや弁護士は、これらの複雑な契約書の作成や交渉をサポートし、依頼者の利益を最大化するために尽力します。NDAの段階から専門家に相談することで、その後のプロセス全体をスムーズに進めることができます。
まとめ
NDAは、ビジネスにおける秘密情報を保護するための基本的かつ重要な契約です。商談、取引開始、提携検討、M&Aなど、さまざまな場面で秘密情報を開示する際には、必ず情報開示前にNDAを締結することが原則です。NDAを適切に締結することで、情報漏洩のリスクを低減し、万が一の際には法的な対応を取ることができます。
NDAで定めるべき重要な事項には、秘密情報の定義、使用目的の制限、秘密保持義務、有効期間、返還・破棄義務、損害賠償などがあります。これらの条項を自社の状況に合わせて適切に設定することで、実効性の高い契約を作成できます。特にM&Aにおいては、情報の機密性が極めて高いため、各段階で適切なNDAを締結し、専門家のサポートを受けることが成功の鍵となります。
会社の売却やM&Aを検討されている中小企業のオーナー様にとって、NDAは最初の重要なステップです。信頼できる専門家のアドバイスを受けながら、適切な情報保護体制を構築することで、安心して次のステージへと進むことができるでしょう。
M&Aや事業承継に関するご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。専門知識と豊富な実績を持つアドバイザーが、貴社の大切な情報をしっかりと保護しながら、最適なM&A戦略をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。