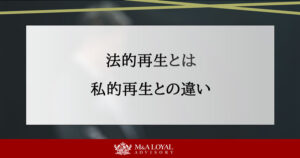メイン寄せとは?企業再生における背景とリスク
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
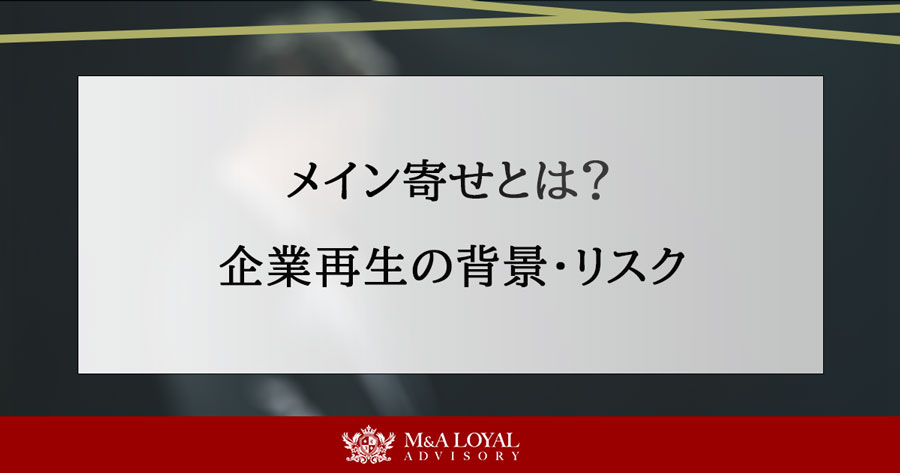
メイン寄せとは、融資を受けている複数の金融機関のうちメインバンク以外が融資に消極的になることでメインバンクの融資比率が上昇することをいいます。
本記事は初心者でもわかるメイン寄せの概念から背景、私的再生への影響やリスクと注意点について解説していきます。
目次
メイン寄せとは?定義と背景を解説
メイン寄せの定義とは
企業が複数の金融機関から融資を受けている場合、最も融資額が多い金融機関を「メインバンク」といいます。メインバンクは企業に対して単なる資金支援だけでなく、経営を監視する役割も担います。
メイン寄せとは、企業の経営難などの事由によって、その他の金融機関が融資を引き揚げ、メインバンクの融資比率が高くなることをいいます。
また、企業が経営難に陥り、債権回収が難しくなった場合、対象企業に融資していた金融機関はその責任をメインバンクに求める傾向があります。
メインバンクとは、金融支援を受ける銀行の中でも企業と最も深い関係を築いている主要な銀行のことです。メインバンクは企業が経営難に直面した際には資金供給や融資条件の見直しなどを行い、企業が存続できるように支援することが期待されています。
企業が経営が困難な状況に陥り、事業再建のために私的再生の手続きを適用する際には「私的整理に関するガイドライン」に基づいて進められます。
私的整理に関するガイドラインでは、債権者の権利は平等であること、債権者が負担する割合は個別に検討し、全員が合意することとされています。
私的再生は法的再生と異なり法的拘束力がありません。そのため、金融機関を含む債権者全員が合意しなければ進まず、法的再生に移行することもあります。
メインバンクは私的再生を進めるためにも、他の金融機関よりも多額の債権放棄を行う傾向があります。
メイン寄せの背景
メイン寄せの背景は戦後の金融システムにあります。1990年代末以前、日本の金融機関システムはメインバンクシステムでした。メインバンクが融資先の企業を破たん処理を行わない限り、他の金融機関も融資を続けるのが一般的でした。
しかし、1990年代末以降になり不良債権問題が深刻化、メインバンクが企業への融資を続けていても他の金融機関は融資を引き揚げるケースも見られるようになりました。
他の金融機関が融資を引き揚げた場合、メインバンクは企業の事業を継続させるために引き揚げられた融資額も穴埋めする必要があり、結果として企業に対する融資比率が上がっていくことになります。
メインバンクの役割
企業が経営危機に陥ると、メインバンクは債権者の中で最も大きな影響力を持つ存在として、他の金融機関や関係者と協力しながら再生計画を進めていく役割を担います。特に、企業が私的再生を目指す場合、メインバンクの関与が不可欠となるため、メイン寄せが発生するのです。
- メインバンクが企業の財務状況を最も深く理解している
- メインバンクが企業の再生に成功することで自身の債権も守れる
- 他の金融機関がメインバンクに主導権を委ねる傾向がある
メインバンクは、企業にとって単なる融資元ではなく、経営の「パートナー」として機能することがあります。企業の経営状態が良好な場合、メインバンクは資金提供や経営アドバイスを通じて企業の成長を支援します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



私的再生とガイドライン
私的再生の手続きに関するガイドラインは「私的整理に関するガイドライン」として2001年に策定され、尊重・遵守することが求められています。しかし、ガイドラインには法的拘束力はないため、債務整理に応じるかどうかは債権者に委ねられます。
金融機関の合意を得て私的再生を円滑に進めるためには、法的再生を行うよりも私的再生のほうが債権回収額が大きくなるなど金融機関にメリットがあることを示す必要があります。
その後、新型コロナウイルスの感染拡大により経営に大きな影響を受けた企業が急増。事業再生に向けたガイドラインとして、2022年に「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が発表されました。
このガイドラインでは、中小企業と金融機関のそれぞれの役割と私的整理に関するルールが明確化されています。
中小企業の役割
ガイドラインでは、企業と金融機関は「平時」「有事」「事業再生計画成立後のフォローアップ」の段階別の考え方が示されています。ガイドラインを活用することで、企業と金融機関は普段から良好な信頼関係を構築し、企業のライフステージにおける取組意欲の増進を図ることを目的としています。
【中小企業の役割】
- 収益力の向上と財務基盤の強化
- 適時適切な情報開示による経営の透明性の確保
- 法人と経営者の資産等の分別管理
- 予防的対応
- 実務専門家の活用
このようにガイドラインでは中小企業の役割が定められています。
私的再生における企業リスク
私的再生は、裁判所を介さずに債権者との交渉を通じて企業再生を目指す方法です。債権者に対して債権放棄を求めるためメイン寄せが発生しやすい手法であり、以下のようなリスクが伴います。
- 債権者間の調整が困難
- 透明性の欠如
- 時間とコストの増加
債権者間の調整が困難
金融機関はメインバンクに融資額よりも多い割合の債権放棄を求める場合があります。複数の債権者がいる場合は調整が難航する可能性があります。
透明性の欠如
私的再生は裁判所を介さないため、法的拘束力がありません。そのため、再生プロセスにおける透明性が低く、ステークホルダーの不信感を招く恐れがあります。
時間とコストの増加
交渉が長引くことで、再生のための時間とコストが増加する場合があります。
私的再生のメリット・デメリット
私的再生は私的整理ガイドラインの規定に基づいて行われます。法的再生と異なり、法的拘束力はないため、一部の債権者が反対した場合には進めることができません。
【私的再生のメリット・デメリット】
| メリット | ・信用低下を防げる ・迅速かつ柔軟に行える ・法的再生よりもコストを抑えられる |
| デメリット | ・手続きが不透明になりやすい ・担保権を止められない |
私的再生を成功させるためのポイント
メイン寄せのリスクを回避し、私的再生を成功させるために以下のポイントに注意する必要があります。
- 透明性の確保:再生計画や交渉プロセスにおける情報を全てのステークホルダーに共有し、信頼を築くことが重要です。
- プロフェッショナルの活用:弁護士やコンサルタントなどの専門家を活用することで、交渉の効率性が向上します。
- 現実的な再生計画の策定:企業の財務状況や市場環境を正確に分析し、実現可能な計画を立てることが必要です。
どの金融機関も、自らの債権がカットされてしまう内容の再建計画を好んで受け入れてくれるわけではありません。金融機関は企業からいかに回収の最大化を図るかを考えています。
私的再生を成功させるためには、金融機関の協力を得ることが非常に重要です。普段から良好な取引を行い信頼関係を構築することと、具体的かつ客観的に実現可能な再建計画を作成することが大切です。
メイン寄せによる企業の影響
企業にとってメイン寄せは私的再生時だけの問題ではありません。メインバンクに融資比率が偏ることは、メインバンクへの依存度が高くなるということです。メインバンクの影響力が強くなるため、融資条件が不利になったり、交渉力が低下し、経営の自由度が下がる可能性があります。
そのため、企業は複数の金融機関との関係性を適切に管理し、円滑な取引を行うことが大切です。
また、金融機関に依存するだけでなく資本金比率を増加させ、経営基盤を強化することも大切です。健全な経営は企業価値を高めることにつながり、将来的にM&Aなど事業承継を選択する際にも有利に働きます。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継の初期的な関心でもご相談いただけます。事業承継には時間がかかるものなので、早い段階で情報収集を行い、M&Aを含めた最適な解決策を検討することが重要です。
今後のプランを考えるためにも、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。