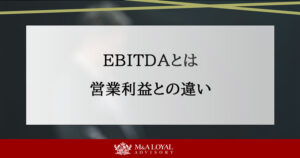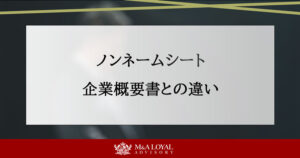M&Aのティーザーとは?記載内容や作成方法をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
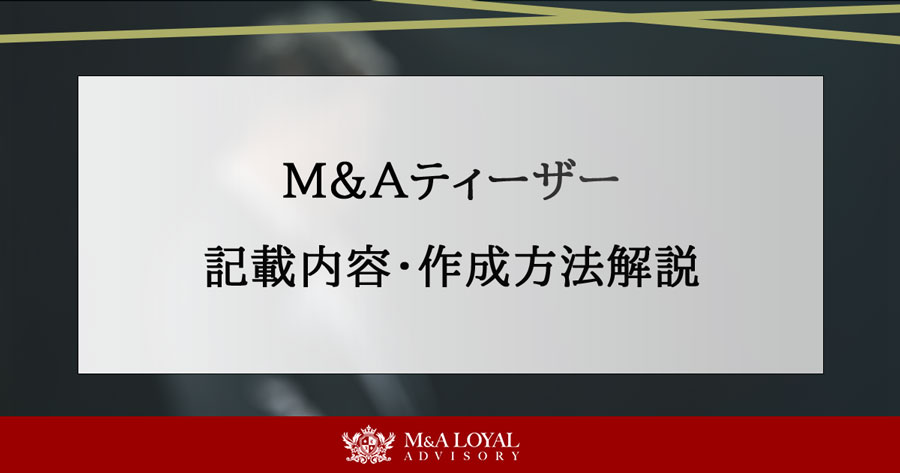
ティーザーとは、M&Aを検討する際、最初に作成する重要な資料のことです。ティーザーは、譲渡企業の情報を匿名で開示し、買い手候補の関心を引くための初期資料として活用されます。適切に作成されたティーザーは、情報漏洩のリスクを抑えながら譲受企業の興味を惹き、M&Aプロセスを円滑に進める鍵となります。
しかし、記載内容のバランスを誤ると企業が特定されるリスクや、逆に魅力が伝わらず商談機会を逃す可能性もあります。本記事では、M&Aにおけるティーザーの役割から具体的な記載内容、作成時の注意点まで解説します。
目次
M&Aのティーザーとは
M&Aにおけるティーザーとは、譲渡企業の情報を匿名で記載した企業概要書のことです。英語の「tease(じらす)」に由来し、企業名を明かさずに買い手候補の興味を惹くという特徴があります。
ティーザーは、M&Aプロセスの最初期段階で使用される資料であり、秘密保持契約(NDA)を締結する前に譲受企業へ提示されます。この段階では譲渡企業の名称や所在地などの特定情報を開示せず、事業内容や規模感といった概要のみを伝えることで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら買い手候補を探索できます。
定義と基本的な役割
ティーザーは通常A4用紙1枚から数枚程度にまとめられた簡潔な資料です。譲渡企業側から見れば、自社の魅力を適切に伝えつつ企業秘密を守るための重要なツールとなります。一方、譲受企業側にとっては、数多くのM&A案件の中から自社の戦略に合致する候補を効率的に選別するための判断材料となります。
ティーザーの特徴は、企業を特定できない範囲で必要最低限の情報を開示し、買い手候補の関心度合いを測る点にあります。この初期段階で関心を示した企業とのみ次のステップへ進むことで、無用な情報拡散を防ぎつつ効率的にM&Aを進められます。
ティーザーの作成にあたり、M&Aアドバイザーや仲介会社が支援することが一般的であり、専門家の視点から適切な情報開示のレベルと魅力的な表現方法をアドバイスしてもらえます。譲渡企業が単独で作成するよりも、情報特定リスクの回避と訴求力の両立が実現しやすくなります。
ティーザーとノンネームシートの違い
M&A業界では「ティーザー」と「ノンネームシート」という2つの用語が使われます。厳密には情報量や用途に若干の違いがありますが、両者を区別せず同一の資料を指す言葉として使われることもあります。
以下の表で、両者の理論的な違いと実務上の扱いを整理します。
| 項目 | ティーザー | ノンネームシート |
|---|---|---|
| 情報量 | やや多め(3〜10枚程度) | 少なめ(A4 1枚程度) |
| 想定用途 | 同業以外の買い手候補向け | 同業者など業界知識のある買い手向け |
| 詳細度 | 事業の特徴や強みを比較的詳しく記載 | 基本情報のみ簡潔に記載 |
| 実務上の扱い | ノンネームシートと同義で使用されることが多い | ティーザーと同義で使用されることが多い |
実際のM&A実務では、多くの仲介会社やアドバイザーがA4用紙1〜2枚程度の簡潔な資料を「ティーザー」または「ノンネームシート」として作成しています。買い手候補の業界知識や求める情報レベルに応じて、記載する情報量を調整することが一般的です。
いずれの名称を使用する場合でも、企業を特定できない範囲で事業概要を伝え、買い手候補の興味を惹くという基本的な目的は共通しています。本記事では以降、「ティーザー」という用語で統一して解説を進めます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



M&Aのティーザーの構成要素
M&Aで使用するティーザーは定量情報と定性情報の2つの要素で構成されます。定量情報では企業の規模や事業概要を数値や事実ベースで示し、定性情報では譲渡理由や企業の強みといった背景を伝えます。この2つをバランス良く組み合わせることで、買い手候補の関心を引きつつ企業特定を避ける資料が完成します。
適切なティーザーを作成するには、どの情報をどこまで開示するかの判断が重要です。情報不足では買い手候補の興味を惹けず、情報過多では企業が特定されるリスクが高まります。以下、それぞれの要素について具体的に解説します。
定量的情報の記載方法
定量的情報とは、数値や客観的事実に基づく情報のことです。ティーザーでは、企業規模や事業内容を大まかに把握できる程度の情報を記載します。
ティーザーに記載する事業内容については、日本標準産業分類における大分類・中分類レベルで記載することが基本です。例えば「情報サービス業のシステム開発事業」「小売業の食品販売事業」といった表現にとどめ、具体的な商品名やサービス名は記載しません。特定の商材名や独自の技術名称を記載すると、業界関係者であれば企業を特定できてしまう可能性があるためです。
所在地については、都道府県名すら記載せず「関東地方」「近畿地方」といった地域レベルにとどめます。特に地方の専門業種では、都道府県と業種の組み合わせだけで企業が特定されるリスクがあるため注意が必要です。複数拠点がある場合は「関東・関西に展開」といった表現を使います。
従業員数や売上高は概算値で記載します。「従業員約50名」「売上高約5億円」のように、おおよその規模感が伝わる程度の表現とします。正確な数値は秘密保持契約(NDA)締結後の詳細資料で開示するため、この段階では買い手候補が検討対象とするかどうかを判断できる情報があれば十分です。
想定譲渡スキームについては、株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの候補を記載します。この段階では確定していなくても構いませんが、買い手候補が検討しやすいよう現時点での想定を示します。オーナーの意向や事業の特性によって適したスキームが異なるため、専門家と相談して記載内容を決めることをおすすめします。
定性的情報の書き方
定性的情報では、譲渡を希望する理由や企業の特徴・強みを記載します。この部分が買い手候補の関心を引く重要な要素となるため、単に事実を列挙するのではなく、魅力が伝わる表現を工夫します。
譲渡理由については、簡潔かつ明確に記載します。「後継者不在のため」「事業の更なる発展のため」「選択と集中による経営資源の再配分」など、買い手候補が納得できる理由を端的に示します。ネガティブな理由であっても隠さず正直に記載することが、後のトラブルを避けるために重要です。
企業の特徴や強みでは、競合他社との差別化ポイントを具体的に表現します。ただし、企業特定につながらない範囲での記載が前提です。例えば「主要駅から徒歩圏内の好立地に店舗展開」「官公庁との長期継続取引実績」「特定業界向けの専門ノウハウ保有」といった表現であれば、魅力を伝えつつ特定を避けられます。
「顧客から高評価を得ている」といった抽象的な表現は避け、具体性と匿名性のバランスを取った記載を心がけます。「業界団体から表彰実績あり」「リピート率80%以上」など、数値や客観的事実を交えることで説得力が増します。
また、買い手候補にとってのメリットを意識した記載も効果的です。「既存事業とのシナジーが期待できる顧客基盤」「即戦力となる技術者が在籍」など、M&A実行後の価値を想像させる表現を盛り込むことで、買い手候補の検討意欲を高められます。
記載すべき財務情報の範囲
財務情報については、ティーザーの段階では詳細な開示は不要ですが、買い手候補が投資判断の検討を始められる程度の情報は必要です。売上高と営業利益または経常利益の概算値を直近3~5年分程度記載するのが一般的です。
利払い前・税引き前・減価償却前の利益を示す「EBITDA」を記載するケースも増えています。EBITDAは、企業の本業での収益力を示す指標として買い手候補が重視します。特に製造業など設備投資が大きい業種では、減価償却費の影響を除いた収益力を示すことで、正確な評価につながります。
総資産や純資産についても、大まかな金額を記載することがあります。ただし、詳細な貸借対照表の開示はNDA締結後となるため、ティーザーでは「総資産約3億円」「自己資本比率約40%」といった概要レベルにとどめます。
希望譲渡価格については、記載するかどうかが分かれます。記載する場合でも「○億円程度を想定」といった幅を持たせた表現とし、確定金額ではないことを明示します。価格を記載しないことで柔軟な交渉の余地を残す戦略もあり、M&Aアドバイザーと相談して決定します。
M&Aのティーザーの作成手順
ティーザーを作成する際は、情報の整理から始まり、記載内容の選定、表現の工夫、リスクチェックという段階を踏むことが重要です。このプロセスを丁寧に進めることで、情報漏洩リスクを抑えつつ買い手候補の興味を惹くティーザーが完成します。
多くのM&A仲介会社やアドバイザーは独自のティーザーフォーマットを持っていますが、基本的な作成の流れは共通しています。専門家の支援を受ける場合でも、オーナー自身が作成プロセスを理解しておくことで、より効果的な資料作成が可能になります。
情報収集と整理のステップ
まずは自社の情報を客観的に整理することから始めます。事業内容、事業規模、財務状況、組織体制、取引先構成、競合環境、強みと弱みなど、M&Aに関連する情報を網羅的にリストアップします。
この段階では、情報の取捨選択は考えず、まず全体像を把握することが重要です。過去3〜5年分の決算書、組織図、主要取引先リスト、商品・サービス一覧、設備・不動産リストなどの資料を準備します。情報を整理する過程で、自社の事業価値や強みを改めて認識できることも多く、この作業自体がM&A戦略を考える機会となります。
次に、整理した情報の中からティーザーに記載すべき要素を選定します。買い手候補が最も関心を持つであろう情報は何か、どの情報が企業特定につながるリスクが高いか、という2つの観点でバランスを取りながら選定します。
業界特性によって重視すべき情報は異なります。製造業であれば生産能力や設備状況、サービス業であれば顧客基盤や人材、小売業であれば立地や在庫回転率など、業種ごとの特性を踏まえた情報選定が必要です。同業他社への売却を想定する場合と異業種への売却を想定する場合でも、訴求すべきポイントが変わります。
記載内容の具体的な書き方
情報の選定が終わったら、具体的な記載内容を作成します。この際、専門用語や業界用語は可能な限り平易な表現に置き換え、異業種の買い手候補でも理解できる文章を心がけます。
事業内容の記載では、ビジネスモデルが理解できる程度の説明を加えます。単に「製造業」ではなく「自動車部品の製造・販売。大手自動車メーカー向けに特殊部品を供給」といった具体性を持たせつつ、企業が特定されない範囲での表現とします。
定性情報では、ストーリー性を持たせることも効果的です。「創業以来30年以上にわたり地域密着で事業展開」「近年はEC販売にも注力し新規顧客層を開拓」など、事業の歴史や方向性が伝わる記載は買い手候補の共感を得やすくなります。
アドバイザーとの連携方法
ティーザー作成においてM&Aアドバイザーの支援を受けることは、成功確率を高める重要なポイントです。アドバイザーは多数のM&A案件を扱った経験から、どのような表現が買い手候補の関心を引き、どのような情報が特定リスクを高めるかを熟知しています。
アドバイザーとの連携では、まずオーナーの希望や譲渡の背景を率直に伝えることが重要です。どのような買い手候補を想定するか、譲渡後の従業員処遇についての希望、譲渡時期の制約など、オーナーの意向を共有することで、それに適したティーザーの方向性を提案してもらえます。
アドバイザーが作成した原案に対しては、事実関係の正確性を確認するとともに、自社の魅力が適切に表現されているかを検証します。数値の誤りや事業内容の誤解がないか、強みとして記載されている内容が実態と合っているかなど、オーナーにしか分からない視点でのチェックが不可欠です。
また、アドバイザーから想定買い手候補の傾向や市場動向についての情報提供を受けることも重要です。同業他社の動向、近隣地域での同種案件の成約状況、類似業種の評価トレンドなど、市場環境を理解することで、より効果的なティーザー作成につながります。
M&Aのティーザー作成時の注意点
ティーザーは企業の重要情報を扱う資料であるため、作成と取り扱いには細心の注意が必要です。情報漏洩は取引先や金融機関からの信頼失墜、従業員の動揺、競合他社への情報流出など、深刻な事態を招く可能性があります。
適切なリスク管理を行いながらティーザーを活用することで、M&Aプロセスを安全かつ効率的に進められます。以下、特に注意すべきポイントについて解説します。
企業特定のリスクを避ける工夫
企業特定のリスクは、業種・地域・規模・特徴などの組み合わせで高まります。それぞれの情報は単独では特定につながらなくても、複数の情報を組み合わせることで企業が絞り込まれてしまう可能性があるため注意が必要です。
特に地方の専門業種や、特定地域で知名度の高い企業の場合は慎重な記載が求められます。「四国地方の医療機器販売」「東北地方の建設コンサルタント」など、地域と業種の組み合わせだけで候補企業が数社に絞られる場合は、地域を「西日本」「東日本」といったより広い範囲に変更するなど、特定リスクを避ける工夫が必要です。
特徴的な事業内容や独自技術についても注意が必要で、「特許取得済みの○○技術」「業界唯一の○○サービス」といった表現は、特定リスクを高めます。このような強みを訴求したい場合は、「独自技術による差別化」「業界内での希少なサービス提供」といった抽象度を上げた表現に変更します。
取引先情報も特定につながりやすい要素です。「大手○○メーカーと継続取引」といった記載は避け、「上場企業を含む大手企業との安定取引」程度の表現にとどめます。NDA締結後に具体的な取引先名を開示すれば、買い手候補の評価には十分対応できます。
従業員数についても、正確な数字は避けます。「従業員45名」ではなく「従業員約50名」とすることで、特定リスクを下げられます。特に従業員数が少ない企業や、逆に地域で最大規模の従業員数を持つ企業は、この情報だけで特定される可能性があるため注意が必要です。
情報漏洩を防ぐための対策
ティーザーの配布先管理は重要なリスク管理です。M&Aアドバイザーを通じて配布する場合は、どの企業にいつ配布したかの記録を残し、無制限に拡散しないよう管理します。また、閲覧制限機能を活用し、競合他社や取引先など、情報を知られたくない企業には配布しないよう設定します。
ティーザーには「秘密情報」である旨の記載と、無断複製や第三者への開示禁止の文言を明記します。法的拘束力は限定的ですが、受領者に対する注意喚起として機能します。また、ページ番号や作成日付を記載し、資料管理をしやすくします。
電子ファイルで配布する場合は、パスワード設定や閲覧期限の設定など、技術的な対策も重要です。印刷や転送を制限できるPDF形式での配布や、専用の情報開示システムの利用も検討に値します。
社内での情報管理も徹底します。M&A検討の事実は、必要最小限の関係者のみで共有し、一般従業員には開示しません。経理担当者など、ティーザー作成に協力を求める場合でも、目的を明確に説明し守秘義務を徹底します。
魅力を伝えるポイント
企業特定リスクを避けることに注力しすぎると、情報が抽象的になりすぎて買い手候補の興味を惹けないという問題が生じます。匿名性と訴求力のバランスを取ることが、効果的なティーザー作成の鍵となります。
定量情報と定性情報を組み合わせることで、企業特定を避けながら魅力を伝えられます。例えば売上高の推移を示すだけでなく、「堅調な成長の背景には、顧客ニーズに応じた商品開発力がある」といった定性的な説明を加えることで、数字以上の価値が伝わります。
買い手候補の視点に立った記載も重要です。「この企業を買収することでどのようなメリットがあるか」を意識した表現を盛り込みます。「既存顧客基盤とのクロスセル機会」「優秀な人材の獲得」「新規エリアへの進出足がかり」など、M&A後のシナジーを想像させる記載が効果的です。
業界動向や市場環境に関する情報を加えることも、訴求力を高めます。「高齢化による市場拡大が見込まれる分野」「DX推進により需要増加中のサービス」など、成長性や将来性を示す背景情報があると、買い手候補の関心が高まります。
ネガティブ情報についても、適切に開示することが後のトラブル回避につながります。「設備の老朽化」「特定取引先への依存度が高い」といった課題は、NDA締結前の段階では詳細に記載する必要はありませんが、重大なリスク要因については「一部設備の更新が必要」程度の示唆をしておくことで、後の交渉段階でのギャップを減らせます。
まとめ
M&Aにおけるティーザーは、譲渡企業の情報を匿名で開示し買い手候補の興味を惹くための重要な初期資料です。企業名や所在地を特定できない範囲で事業内容や規模を示し、NDA締結前の段階で効率的に買い手候補を探索できます。定量情報と定性情報をバランス良く記載し、企業特定リスクを避けながら自社の魅力を適切に伝えることが成功の鍵となります。
ティーザー作成では、事業内容は大分類レベル、所在地は地域レベル、数値は概算値での記載が基本です。譲渡理由や企業の強みといった定性情報では、具体性と匿名性のバランスを取りながら買い手候補の関心を引く表現を工夫します。情報漏洩リスクを最小限に抑えつつ、M&Aプロセスを円滑に進めるためには、M&Aアドバイザーの支援を受けながら慎重に作成することをおすすめします。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、豊富な経験を活かし、経営者様のニーズに応じたサポートを提供しております。M&Aや経営課題に関するお悩みがございましたら、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。