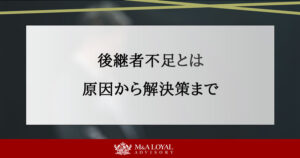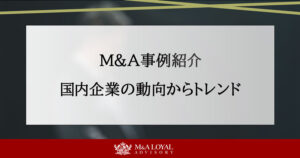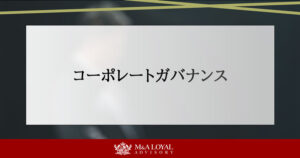M&A件数と推移|最新の統計データから現状と増加理由を徹底解析
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
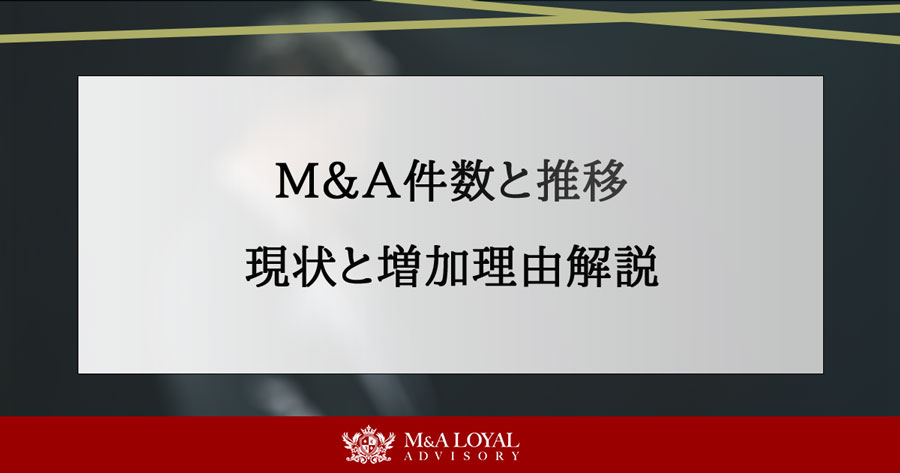
M&A件数は年々増加しており、企業の成長戦略や存続維持の手段としてM&Aが国内や海外で注目を集めていることがわかります。後継者の有無に限らず、中小企業の経営者にとってM&A件数の推移やその背景と市場動向を知ることは、企業の未来の選択肢を増やすことにつながります。
本記事では、最新のM&A件数の推移や市場、日本と海外の取引や歴史的背景を今後の見通しも含めて詳しく解説していきます。
目次
M&A件数の現状と動向|日本と世界の比較
M&Aの件数は、国内外で増加の傾向を見せています。世界的な経済成長や企業のグローバル化が進む中で、M&Aは企業の成長戦略の一環としてますます重要視されています。特に国内市場においては、少子高齢化に伴う後継者不足や事業承継のニーズが高まっており、中小企業を中心にM&A件数は増加しています。
一方で、コロナ禍以降、経済環境の不透明さが増す中で、リスク分散や資源の最適化を目的としたM&Aも積極的に行われています。また、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や、業界再編の一環としてのM&Aも進んでいます。さらに、金融緩和政策や法改正、事業承継支援の制度など環境も整いつつあり、M&Aをより実行しやすい状況が整っていることも件数増加の一因と考えられます。
国内企業同士のM&A件数は堅調に推移していますが、特に注目されているのは、国境を超えたクロスボーダーM&Aの増加です。日本企業が海外市場へ進出するための手段として、また海外企業が日本市場に参入するための方法として、クロスボーダーM&Aは戦略的に活用されています。今後も国内外においてM&A市場は成長していくことが予測されます。
国内のM&A件数の推移|統計データから見る現状と動向
国内のM&A件数は、ここ数年で着実に増加しています。特に2024年にはM&Aの取引件数が4700件に達し、過去最多を記録しています。取引の内訳を見てみると、国内・国外ともに増加していますが、特に国内取引は前年と比較して大きく伸びていることがわかります。
日本企業のM&A件数の推移
| 年 | M&A件数 | IN-IN | IN-OUT | OUT-IN |
| 2020年 | 3730件 | 2944件 | 557件 | 229件 |
| 2021年 | 4280件 | 3337件 | 625件 | 318件 |
| 2022年 | 4304件 | 3345件 | 625件 | 334件 |
| 2023年 | 4015件 | 3071件 | 661件 | 283件 |
| 2024年 | 4700件 | 3702件 | 665件 | 333件 |
参考:MARROnline|2024年のM&A回顧(2024年1-12月の日本企業のM&A動向)
また、中小企業庁のデータによれば、過去10年間で子会社や関連会社を増やした中小企業は緩やかに増加しています。一方、大企業については、2018年以降、やや減少傾向にあることが示されています。
| 年度 | 大企業 | 中小企業 |
| 2015年 | 1.0% | 0.7% |
| 2016年 | 1.1% | 0.7% |
| 2017年 | 1.2% | 0.7% |
| 2018年 | 1.3% | 0.7% |
| 2019年 | 1.2% | 0.8% |
| 2020年 | 1.0% | 0.7% |
| 2021年 | 1.0% | 0.9% |
参考:中小企業庁|事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について
2014年度と2022年度のM&A実施件数を比較すると、以下のとおりです。
- 2014年度:事業承継・引継ぎ支援センター102件、民間M&A支援機関260件
- 2022年度:事業承継・引継ぎ支援センター1681件、民間M&A支援機関4036件
8年間で、M&A件数はそれぞれ10倍以上増加していることがわかります。
M&A件数からわかる事業承継の変化
M&Aが増加している背景には、事業承継スタイルの変化も影響しています。以前は、中小企業の後継者として経営者の子どもや親族への承継が一般的でした。しかし、同族承継は年々減少しており、社内の役員や従業員に承継する内部昇格や第三者へのM&Aが拡大しています。
| 年 | 同族承継 | M&Aほか | 内部昇格 | 外部招聘 |
| 2020年 | 39.3% | 17.2% | 31.9% | 7.6% |
| 2021年 | 38.7% | 18.6% | 31.4% | 7.3% |
| 2022年 | 37.6% | 18.6% | 33.3% | 7.1% |
| 2023年 | 36.0% | 19.4% | 34.4% | 6.9% |
| 2024年 | 32.2% | 20.5% | 36.4% | 7.5% |
参考:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024 年)
同族承継が減少している理由の一つとして、経営者に後継者となる子どもがいないことが挙げられます。中小企業庁のデータによれば、日本では毎年多くの企業が後継者不足の問題に直面しています。
事業承継が円滑に行われない場合、その企業の存続が危ぶまれることになります。これは企業だけでなく、日本経済にも大きな影響を及ぼします。特に、長年受け継がれてきた日本の伝統や技術が途絶えることは、日本文化の衰退につながる可能性があります。そのため、後継者が不在の経営者や政府にとって第三者への事業承継であるM&Aが事業存続の選択肢として期待されています。
政府によるM&Aの促進
M&Aの件数が増加している要因の一つとして、政府の支援が挙げられます。後継者不足による黒字経営企業の廃業問題は、国内経済にも影響を与えています。このため、経済産業省は「第三者承継支援総合パッケージ」を通じて、70歳以上の経営者で後継者が未定の中小企業の中から、黒字廃業の可能性がある約60万社に対して第三者承継を促進する取り組みを発表しました。
政府や自治体は、中小企業の事業承継を支援するために、制度や助成金を提供し、事業承継計画を支援する専門家ネットワークの構築を進めています。こうした政府の後押しもあり、M&Aは近年活発に行われるようになっています。
また、M&A支援事業者も2018年には1176事業者でしたが、2023年には3057事業者と約2.6倍に増加しています。このような背景が、M&A件数の増加に寄与しています。
M&A取引額の推移
M&Aの件数だけでなく、取引額を比較することで、M&Aの規模の変動も分析できます。2004年から2024年の国内間のM&A件数(IN-IN)を見ると、2007年から2011年にかけて件数が減少していますが、その後は大きく増加しています。2011年と2024年を比較すると、M&Aの取引件数は3倍以上に拡大しています。
しかし、取引額の推移にはばらつきがあり、M&A件数が前年を上回っていても、取引額が前年よりも低くなる年も少なくありません。これは1件あたりの取引額に起因しています。2004年と2023年の平均取引額を比較すると、半分以下になっており、案件が比較的小規模である取引が多いことが推察されます。
| 年 | 1件あたりの取引額 |
| 2004年 | 57.1億円 |
| 2011年 | 32.4億円 |
| 2018年 | 10.6億円 |
| 2023年 | 26.0億円 |
参考:大和総研|日本企業による M&A の動向(2023年版)
取引額の減少の理由としては、2000年代には金融機関の合併・統合などの大型案件が続いたのに対し、2010年代や2020年代には中小企業の取引が増えたことが挙げられます。
2020年から2024年の日本企業(国内・国外)のM&A件数と取引額の推移は、次のとおりです。
| 年 | M&A件数 | 取引額 |
| 2020年 | 3730件 | 14.7兆円 |
| 2021年 | 4280件 | 16.4兆円 |
| 2022年 | 4304件 | 11.4兆円 |
| 2023年 | 4015件 | 17.9兆円 |
| 2024年 | 4700件 | 19.6兆円 |
国内間取引(IN-IN)を見ると以下の推移となっています。
| 年 | M&A件数 | 取引額 |
| 2020年 | 2944件 | 3.3兆円 |
| 2021年 | 3337件 | 3.0兆円 |
| 2022年 | 3345件 | 4.0兆円 |
| 2023年 | 3071件 | 7.7兆円 |
| 2024年 | 3702件 | 6.5兆円 |
参考:MARROnline|2024年のM&A回顧(2024年1-12月の日本企業のM&A動向)
さらに、2023年のM&A件数(IN-IN)が多い業種は次のとおりです。
| 業種 | シェア率 |
| サービス業 | 28.8% |
| その他金融業 | 25.1% |
| 情報・通信業 | 7.5% |
| 卸売業 | 7.3% |
| 小売業 | 4.2% |
上位5業種は、直近20年のデータにおいてシェア率に変動はあるものの、順位は変わらず、M&Aを行う業種はある程度固定されていることがわかります。特に、サービス業とその他金融業(投資ファンドなど)のM&A件数は全体の半数以上を占めています。
また、2023年のシェア率を取引額ベース(IN-IN)で見ると以下のようになります。
| 業種 | シェア率 |
| その他金融業 | 50.4% |
| 医薬品 | 8.9% |
| 卸売業 | 7.1% |
| 証券業 | 6.4% |
| サービス業 | 4.4% |
国内のM&Aを取引ベースで分析すると、半分以上がその他金融業によるものであることが分かります。直近20年間の合計値では、その他金融業のシェア率は約15%のため、2023年の取引額は3.3倍以上に伸びていることが確認できます。ただし、取引額についてはその年のM&Aの取引規模に大きく影響されるため、毎年一貫して伸びているわけではありません。
海外企業とのM&A件数と取引金額の推移
世界のM&A件数の推移は近年減少傾向にあり、2024年は50,223件と3年連続で前年度を下回っています。これには世界情勢が大きく影響しています。特にアメリカやヨーロッパの先進国では、経済の安定性と企業規模の拡大を目的としたM&Aが行われています。一方で、アジア諸国では急速な経済成長と共に、国内市場の競争力を高める目的でM&Aが進行しています。
日本の企業と海外の企業の取引は、クロスボーダーM&Aと呼ばれます。国内企業による海外企業の買収をIN-OUTといい、海外企業による国内企業の買収をOUT-INといいます。
クロスボーダーM&A(IN-OUT)の件数と取引額の推移
| 年 | M&A件数 | 取引額 |
| 2020年 | 557件 | 4.4兆円 |
| 2021年 | 625件 | 7.0兆円 |
| 2022年 | 625件 | 3.4兆円 |
| 2023年 | 661件 | 8.1兆円 |
| 2024年 | 665件 | 9.5兆円 |
2024年に日本とクロスボーダーM&Aを行った国別の取引件数は以下のとおりです。
| 国名 | M&A件数 |
| アメリカ | 213件 |
| シンガポール | 51件 |
| イギリス | 36件 |
| インド | 33件 |
| ドイツ | 30件 |
| オーストラリア | 30件 |
| フランス | 24件 |
| ベトナム | 21件 |
| 中国 | 20件 |
| 韓国 | 19件 |
国別で見てみると、In-Outでは、アメリカやアジア諸国とのM&Aが拡大傾向にある一方で、ヨーロッパや中国との取引件数は横ばいか縮小しています。
クロスボーダーM&A(OUT-IN)の件数と取引額の推移
| 年 | M&A件数 | 取引額 |
| 2020年 | 229件 | 6.9兆円 |
| 2021年 | 318件 | 6.3兆円 |
| 2022年 | 334件 | 3.9兆円 |
| 2023年 | 283件 | 2.0兆円 |
| 2024年 | 333件 | 3.6兆円 |
OUT-INでは、アメリカ、ヨーロッパ、中国、アジア諸国が主要な取引先となっています。IN-OUTでは取引件数が比較的少ない中国ですが、OUT-INでは大きく増加しており、中国による日本企業の買収が積極的に行われていることが推測されます。しかし、取引額ベースで見ると、ASEANとの取引額と同等またはそれ以下の年もあり、案件としては中小規模のものが多いことが考えられます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



M&A件数の増加理由と背景
M&A件数の増加には、複数の要因が絡み合っています。まず、日本経済の成熟化に伴い、企業は新たな成長機会を求めてM&Aを戦略的な選択肢として積極的に活用するようになりました。特に、少子高齢化による労働力不足や地方企業の後継者問題が深刻化している中で、企業の存続や成長を目的としたM&Aの利用が増加しています。
ここでは、M&Aが増加している理由について解説していきます。
リーマンショックによる影響
リーマンショックは、2008年に世界的な金融危機を引き起こし、企業の財政状態に大きな打撃を与えました。この影響により、M&A市場も大きな変化を余儀なくされました。資金調達の困難さから企業の買収意欲が低下し、M&A件数は一時的に減少しました。特に中小企業は資金力の弱さから、買収を受ける側としての立場を余儀なくされるケースが増加しました。
一方で、リーマンショックは企業の再編成を促進する契機ともなりました。景気後退による収益悪化を背景に、非効率な事業の売却やコスト削減を目的とした組織再編が進められました。こうした動きは、企業が生き残りをかけた戦略的なM&Aを促進し、特定の業界ではM&A活動が活発化するという現象も見られました。
さらに、市場の不安定さにより企業価値が下落したため、買収を検討する企業にとっては魅力的な買い時ともなりました。国内の企業同士の売買だけでなく、日本の企業と海外の企業のM&Aも積極的に行われるようになりました。こうしたグローバル化により、M&Aの国際化が進行し、日本の市場の活性化を促す一因となりました。
総じて、リーマンショックはM&A市場に短期的な抑制をもたらすと同時に、長期的には市場の再編成を促す転機となりました。企業が新たな成長機会を模索する中で、M&Aは戦略的な選択肢としての重要性を増したのです。
経済のグローバル化
経済のグローバル化は、国境を越えた市場統合を促進し、企業活動をより広範囲にわたって活性化させています。通信技術の進化と貿易障壁の低下がその進展を後押しし、企業はかつてないほど多様な市場にアクセスしやすくなりました。この環境下で、M&Aの件数は世界的に増加傾向にあります。
新市場に迅速に参入し、技術や資源を獲得する手段として、M&Aを積極的に活用する企業も増えています。特に、グローバル化が進む中で、新興市場への進出はますます重要となり、多国籍企業はアジアやアフリカといった新興国を重要な投資先と見なしています。
しかし、M&Aには異なる文化や規制の中で統合を進めるという課題も伴います。成功するためには、企業文化の融合や経営資源の効率的な再配置が必要です。これらの課題を克服し、持続可能なビジネスモデルを構築することで、企業は地域社会への貢献を強化し、経済に大きな恩恵をもたらすことができます。
コロナ禍の影響
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、世界経済に多大な影響を及ぼし、M&A市場もその例外ではありません。パンデミックの初期段階では、多くの企業が不確実性の高まりや市場の不安定さのためにM&A活動を一時的に停止しました。この影響は特に2020年の第一四半期に顕著で、取引件数は急激に減少しました。しかしながら、パンデミックが進行するにつれて、経済の回復を目指す中でM&Aは再び注目を集め始めました。
コロナ禍がもたらした最大の変化の一つは、デジタル分野における取引の増加です。リモートワークの普及やオンラインサービスの需要拡大に伴い、テクノロジー関連企業のM&Aが活発になりました。また、ヘルスケア業界でも同様に取引が増加し、特に医療技術やバイオテクノロジー分野でのM&Aが加速しました。
さらに、コロナ禍により企業は財務体質の強化や事業ポートフォリオの再構築を目的として、資産の売却や不採算事業の切り離しを進める傾向が見られました。これにより、特に中小企業においては買収の好機が生まれ、新たな成長戦略を模索する動きが加速しました。また、低金利政策や政府の経済支援策もM&A活動を後押しする要因となりました。
経営者の高齢化と少子化
日本の経済環境において、経営者の高齢化と少子化は大きな課題となっています。経営者の平均年齢が上昇する中、後継者不足が深刻化し、特に中小企業においては事業承継の問題が顕在化しています。日本の経営者の約60%以上が60歳以上であり、多くが引退を考える年齢に達していますが、若い世代の経営者候補が少なく、事業を引き継ぐことが難しい状況にあります。
また、少子化による労働人口の減少は、企業の持続的成長を阻む要因となっており、国内市場の縮小と相まって、企業は新たな成長戦略を模索する必要に迫られています。このような背景から、M&Aは事業承継の有効な手段として注目されています。経営者が自らの引退を見据え、会社を売却することで、事業の存続と従業員の雇用を確保を守ることができます。
また、少子化は新しいビジネスチャンスの創出を促す一方で、労働力不足が生産性の向上を求める圧力として作用しています。M&Aは資源の最適化や技術革新の促進に寄与し、企業が競争力を維持するための手段として位置づけられています。したがって、経営者の高齢化と少子化が進む中で、M&Aは企業の生き残りと成長のための重要な戦略となりつつあります。このような動向は、今後さらに加速することが予想され、政策面での支援も一層求められています。
デジタル化の進展
デジタル化の進展は、現代のビジネス環境において重要なテーマとなっており、M&Aの分野においてもその影響は顕著です。企業がデジタル技術を活用することで、効率的な業務運営や市場での競争力向上が可能となり、M&A戦略の一環としてデジタル技術を積極的に取り入れるケースが増えています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、新たなビジネスモデルの創出や、既存のビジネスプロセスの革新が進められています。
デジタル化はまた、M&Aのプロセス自体にも変革をもたらしています。例えば、人工知能(AI)やビッグデータ解析の活用により、企業価値の評価やリスク分析がより迅速かつ正確に行えるようになりました。これにより、買収の意思決定がスピーディーかつ効果的に行えるようになり、競争が激化する市場での優位性が高まっています。
さらに、デジタル化は企業間のシナジーを生む可能性も高めています。デジタル技術を共有することで、新たな価値の創出やコスト削減が実現されることが期待されています。これにより、企業は従来の事業領域を超えた成長機会を追求し、グローバル市場での地位を強化することが可能となります。
最後に、デジタル化は企業の透明性を高め、ガバナンスの強化にも寄与しています。デジタルプラットフォームを通じた情報の一元管理により、企業はコンプライアンスの強化やリスクマネジメントの向上を図ることができ、企業価値の向上と投資家やステークホルダーに対する信頼性を高めることができます。
中小企業のM&A事例
中小企業のM&Aは、近年特に注目を集めています。中小企業がM&Aを選択する主な理由として、後継者問題の解決、事業の最適化、そして新市場への進出が挙げられます。例えば、ある製造業の中小企業では、経営者が高齢化し、後継者が不在のため、企業の存続を考慮して同業他社への売却を決断しました。これにより、企業は新たな経営陣のもとでの成長が期待され、従業員の雇用も安定しました。
また、別のIT関連企業では、自社の技術を強化するために、特定の技術を持つスタートアップ企業を買収しました。これにより、短期間で技術力を向上させ、新たな顧客層を獲得することに成功しました。さらに、地域の中小企業が統合することで、規模の経済を実現し、競争力の向上を図った事例も見られます。これにより、資源の効率的な利用とコスト削減が可能となり、地域経済にも貢献しています。
中小企業におけるM&Aは、単なる企業の売買に留まらず、経営課題の解決や新たな成長の機会を提供する重要な手段として位置付けられています。特に小規模な企業においては、資金力や知名度の限界を超えるための戦略的な手段となり得ます。
M&Aの件数増加と法改正
日本でのM&Aの件数が増加した背景には、法改正も大きな役割を果たしています。特に、近年の法制度の見直しが、企業間の取引を促進する一因となっています。例えば、2017年に施行された「事業承継税制の特例措置」は、中小企業の後継者不足問題に対応するために導入され、これにより事業承継時の税負担が軽減されました。これが中小企業のM&Aを一層活性化させる原動力となっています。
さらに、2019年には会社法が改正され、株主総会の手続きの簡素化や、少数株主の権利が強化されました。これにより、M&Aのプロセスが効率化され、取引の透明性が向上しています。また、近年のコーポレートガバナンス・コードの改訂により、企業に対して透明性と説明責任を求める動きが強まっており、これもM&Aの信頼性を高める要因となっています。
これらの法改正は、企業がM&Aを通じて成長戦略を描く際に、これまで以上に柔軟な選択肢を提供しています。特に、海外企業とのM&Aにおいては、法的なハードルが低くなり、より活発な取引が期待されています。今後も法制度の整備が進むことで、M&A市場はさらに活発化することが予想されます。
税制措置や最新の事業承継制度
政府はM&Aを促進するために、税制面での優遇措置や関連制度を整備しています。これにより、企業が合併や買収を行う際の資金負担を軽減し、より円滑な取引の実現をサポートしています。具体的には、企業が持つ株式の譲渡や資産の売却に対して、一定の条件を満たすことで税負担を軽減する特例措置が設けられています。例えば、事業承継税制の特例があり、これにより中小企業の後継者が事業を引き継ぐ際の相続税や贈与税の負担を大幅に減らすことが可能です。
さらに、政府は中小企業のM&Aを支援するための相談窓口や、情報提供を行うプラットフォームを設置しています。企業は専門的な知識を持つアドバイザーのサポートを受けながら、適切な判断を下すことができようになります。これらの制度は、第三者への事業承継を難しく考えている中小企業の経営者にとってM&Aの難易度を下げることに貢献しています。
コーポレートガバナンスの重要性
コーポレートガバナンスは、企業が持続可能な成長を遂げるための重要な枠組みとして、特にM&Aが活発化する現代においてその役割が再評価されています。M&Aの増加に伴い、企業の統合後における経営の透明性や効率性を確保する必要性が高まり、適切なガバナンス体制の構築が求められています。コーポレートガバナンスは、取締役会の機能強化や内部統制システムの整備、情報開示の透明性を高めることで、株主や関係者の信頼を得ることを目的としています。
また、近年の法的整備により、企業はより高いガバナンス基準を遵守することが求められています。これには、独立した外部取締役の導入や、監査委員会の機能強化といった具体的な施策が含まれます。特にM&A後の企業統合においては、異なる文化や業務プロセスの調和を図ることが大切です。ガバナンスの強化を行うことにより、企業は統合効果を最大化し、持続可能な成長を実現することが可能となります。
企業は短期的な利益追求にとどまらず、長期的な視点での経営を意識することが求められます。ガバナンスの強化は、単なる法令遵守に留まらず、企業価値の向上と社会的信頼の獲得に寄与する重要な要素となっています。M&Aにおける成功を左右する要因として、コーポレートガバナンスは今後ますます注目されることでしょう。
M&A件数の今後の見通し
今後の国内のM&A市場は、いくつかの要因によりさらなる成長が予測されています。
少子高齢化による影響
少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少や後継者不足が深刻な問題となっています。このような背景から、多くの中小企業が事業承継の手段としてM&Aを選ぶケースが増加しています。特に地方に根付く企業では、若者の都市部への流出が加速しており、後継者が不在となることが少なくありません。その結果、企業の存続を図るために他社との合併や買収が活発化しています。
また、企業の高齢化も一因です。経営者の平均年齢が上昇する中、早期に事業承継を行い、企業の持続可能性を確保するためにM&Aが利用されています。これにより、企業は新たな資本や技術の導入を図り、競争力の強化を目指します。
経済産業省や中小企業庁では、こうしたM&Aを支援するための施策を強化しており、マッチングイベントや専門家の相談窓口を設けるなど、企業が円滑にM&Aを進められる環境を整えています。このように、少子高齢化はM&Aを加速させる要因となり、経済全体に新たなダイナミズムをもたらしています。今後もこの動向が続くと予想されます。
グローバル化による影響
グローバル化が進展する中で、企業は市場の成長機会を求めて国境を越えた事業展開を積極的に行っています。特に、先進国と新興国の経済成長の差を活用し、先進国の企業が新興市場への進出を図るケースが多く見られます。この流れは、技術やノウハウの取得、新規市場への参入、リスク分散といった企業の戦略的目的を達成する手段として位置づけられています。
また、国際的な競争力を強化するためには、優れたサプライチェーンの構築やコストの最適化が求められています。こうした理由から、日本と海外のクロスボーダーM&Aは今後も増加することが見込まれます。日本企業が海外市場でのプレゼンスを高めるためには、現地企業との連携や、現地事情に精通した経営資源の活用が不可欠です。
市場競争の激化による影響
市場競争の激化は、企業が競争優位性を確保するためにM&Aを積極的に活用する要因となっています。急速な技術革新や消費者ニーズの変化に対応する必要がある業界では、企業は成長戦略の一環としてM&Aを選択するケースが増えています。特に、競合他社の買収や新市場への参入を目指したM&Aが活発化しています。
また、競争が厳しい市場環境では、規模の経済を追求し、コスト効率を向上させるためにM&Aが重要な戦略となっています。このような背景から、企業は必要な技術やリソースを迅速に獲得するためのM&Aを模索し、その結果として件数が増加しています。
このように、競争が激しい市場での企業の生き残りと成長において、M&Aは今後も増大していくと考えられます。
政府による支援や法改正による影響
政府は、中小企業の事業承継や経済成長を支援するために、さまざまなM&A施策を実施しています。中小企業庁が提供するM&A支援や、事業承継税制の特例措置により、次世代への事業引き継ぎ時の税負担が軽減され、後継者不足に悩む企業がM&Aを積極的に検討する流れが加速しています。
さらに、2020年には「中小M&Aガイドライン」が策定され、経験の浅い中小企業が安心してM&Aを進められる環境が整っています。これらの取り組みは地域経済の活性化や雇用維持にも寄与しており、今後もM&Aが積極的に行われることが期待されます。
まとめ
M&A件数の増加は、企業の成長戦略としてますます鍵を握る要素です。この記事では国内外のM&A件数の動向とその背景、そして成功事例を解説しました。M&Aは単なる取引にとどまらず、企業の未来を形作る重要な手段であり、M&A件数が増加するのはそれだけ経営者不足や事業存続の期待がされているためです。
M&Aは実際に進める場合、複雑な専門知識も必要となります。M&Aや経営課題に関するお悩みはぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。