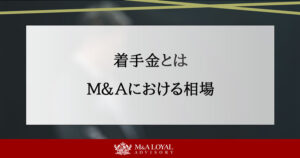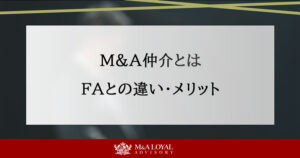M&A仲介手数料の相場と種類を解説!費用を抑える5つのポイント
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
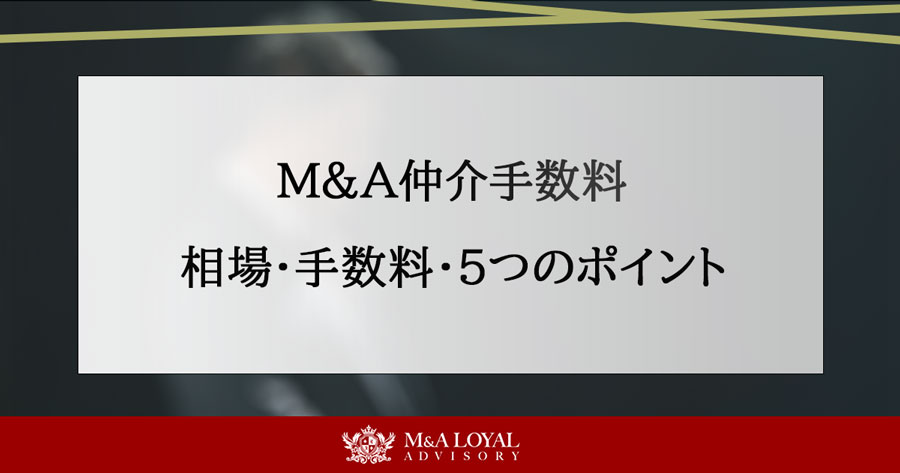
M&Aを検討する際、避けて通れないのが仲介手数料の問題です。M&A仲介会社に支払う手数料は取引全体の大きなコストとなり、場合によっては数千万円に達することもあります。しかし、多くの経営者はM&A仲介手数料の種類や相場、計算方法について詳しく知らないまま取引に臨んでいるのが現状です。
本記事では、M&A仲介手数料の基本知識から始まり、種類別の相場、レーマン方式による計算方法、両手取引と片手取引の違い、そして中小企業のM&Aにおける手数料の選び方まで徹底解説します。
さらに、実際にM&A仲介手数料を抑えるための実践的なポイントも紹介しています。適切な知識を身につけることで、余計なコストを抑え、最適なM&Aを実現しましょう。
目次
M&A仲介手数料とは?費用が発生するタイミングと基本知識
M&Aを進める際には、仲介会社や専門家に依頼して進めることが一般的です。特に中小企業のM&Aでは、適切な相手企業の発掘や交渉を自社だけで行うことは困難なため、M&A仲介会社のサポートが重要な役割を果たします。そのため、株式譲渡金額に加えて仲介会社に支払う手数料も事前に把握しておく必要があります。
仲介手数料の役割と重要性
M&A仲介手数料は、仲介会社が提供する専門的なサービスに対して支払う対価です。一見すると費用負担が大きいように感じるかもしれませんが、以下のような重要な役割があります。
- 買い手と売り手のマッチング支援
- 情報の非対称性の解消
- 適正な企業価値評価と価格交渉のサポート
- 秘密保持を徹底した案件進行
- 専門的知識の提供
M&A取引は高度な秘密保持が求められるため、情報漏洩による企業価値の毀損を防ぐ体制も重要です。M&A仲介手数料は単なる費用ではなく、M&A成功のための投資と考えるべきでしょう。
仲介会社が提供するサービス内容
M&A仲介会社が提供するサービスには以下のようなものがあります。
- 企業価値評価:財務分析や業界分析を通じた適正価値算出
- マッチング支援:最適な相手企業の選定と紹介
- 交渉サポート:条件交渉と調整
- デューデリジェンス調整:外部専門家との連携と調査調整
- 契約書作成支援:適切な契約書作成のサポート ・クロージングまでの一連のプロセス管理
中小企業のM&Aでは、初めてM&Aに取り組むオーナー経営者も多いため、基本的な知識や流れの説明、意思決定のサポートも重要な役割です。
手数料が発生するタイミングとM&A全体の流れ
M&A仲介手数料はM&Aの進行プロセスに応じて、以下のタイミングで発生します。
- 相談段階(相談料) 初回相談は多くの仲介会社で無料ですが、一部では数万円程度の相談料がかかる場合もあります。
- 契約締結時(着手金) 業務委託契約締結時に支払う手数料で、相場は50万円〜200万円程度。M&Aが成約しなくても返金されないことが一般的です。
- 基本合意時(中間報酬) 基本合意書締結時に支払う手数料で、成功報酬の10〜20%程度が相場。最終的なM&A成約時には成功報酬から差し引かれますが、不成立の場合は返金されないことが多いです。
- デューデリジェンス実施時(調査費用) 財務・法務・税務などの調査費用で、200万円〜300万円程度が相場です。
- 最終契約締結時(成功報酬) M&A成約時に支払う最大の手数料で、一般的にレーマン方式で算出されます。
- 進行中(リテイナーフィー) 月額固定報酬で、すべての仲介会社で必要というわけではありません。
M&A全体は「相談→業務委託契約締結→企業評価・マッチング→条件交渉・基本合意→デューデリジェンス→最終契約締結→クロージング」という流れで進みます。各段階で必要となる手数料を事前に把握し、全体の費用感を理解しておくことが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



M&A仲介手数料の種類と相場を徹底解説
M&A仲介会社に支払う手数料はM&Aプロセスの各段階で発生し、種類や金額は仲介会社ごとに異なります。事前にしっかりと確認しておくことが重要です。主な手数料としては、相談料、着手金、中間報酬、デューデリジェンス費用、成功報酬、リテイナーフィーなどがあります。ただし、すべての仲介会社がこれらの手数料を設定しているわけではありません。
相談料とその特徴
相談料は、M&A仲介会社に最初に相談する際に発生する費用です。現在では多くの仲介会社が初回相談を無料で行っていますが、中には数千円から数万円程度の相談料を設定しているケースもあります。また、初回は無料でも2回目以降は有料になる場合や、時間制の課金体系をとる場合もあるため、事前に確認が必要です。
専門性の高い分野に特化した仲介会社では相談料を設定していることもあります。トラブルを避けるためにも、相談前に料金体系を確認しておきましょう。
着手金とその相場
着手金は、M&A仲介会社と正式に業務委託契約を締結する際に支払う手数料です。仲介会社が本格的に案件に着手するための初期費用として位置づけられています。
相場は50万円~200万円程度ですが、競争激化により着手金無料を打ち出す仲介会社も増えています。ただし、着手金が無料の場合は成功報酬が高く設定されていることもあるため、全体のコストバランスを見ることが重要です。
着手金はM&A案件の規模や複雑さによっても異なり、成立しなかった場合でも返金されないことが一般的です。仲介会社の選定は慎重に行いましょう。
中間報酬の役割と金額
中間報酬は、買い手と売り手が基本合意書を締結した時点で支払う手数料です。M&Aプロセスが一定の段階まで進んだことへの対価として設定されています。
相場は成功報酬全体の10~20%程度です。M&Aが最終的に成立した場合は成功報酬から差し引かれますが、不成立の場合は返金されません。
中間報酬には買い手・売り手双方に対して一定の拘束力を持たせる意味合いもあります。基本合意書自体には法的拘束力がない場合が多いですが、中間報酬を支払うことで両者の真摯な取り組みを促します。
デューデリジェンス費用の内訳と相場
デューデリジェンス費用は、対象企業を財務・税務・法務・労務など多角的に調査する際に発生する費用です。この調査は買い手企業にとって対象企業の価値やリスクを正確に把握するために不可欠です。
専門的な知識が必要なため、通常は弁護士、公認会計士、税理士などの専門家に依頼します。費用の相場は案件の規模や複雑さによって異なりますが、中規模企業の場合、200万円~300万円程度が目安です。
内訳としては以下のような項目があります。
- 財務デューデリジェンス:80万円~120万円程度
- 税務デューデリジェンス:50万円~80万円程度
- 法務デューデリジェンス:50万円~100万円程度
- 労務デューデリジェンス:30万円~50万円程度
通常は買い手企業が負担しますが、仲介会社によっては着手金や成功報酬に含まれる場合もあります。
成功報酬の算定方法と相場
成功報酬は、M&Aの最終契約締結後に支払う最大の手数料です。M&A仲介会社の主な収益源であり、不成立の場合は支払いません。
最も一般的な算定方法は「レーマン方式」で、取引金額に応じて段階的に手数料率が変動し、金額が大きいほど料率が低くなります。
一般的な手数料率は下記の通りです。
- 5千万円までの部分:10%
- 5千万円超、1億円まで:5%
- 1億円超、5億円まで:4%
- 5億円超、10億円まで:3%
- 10億円超の部分:2%
重要なポイントとして、「取引金額」の定義が仲介会社によって異なります。株式価額のみを対象とする「株価レーマン方式」と、企業価値や移動総資産を対象とする「企業価値レーマン方式」があり、算出される成功報酬額に大きな差が生じることがあります。
また、「最低報酬額」(500万円~2,500万円程度)が設定されていることも多く、この額を下回る場合は最低報酬額が適用されます。
リテイナーフィーの性質と支払い方法
リテイナーフィー(月額固定料)は、M&A仲介会社と契約期間中毎月支払う手数料です。顧問料的な性格を持ち、継続的なサポートの対価として設定されています。
相場は契約内容やM&Aの難易度によって20万円~200万円/月程度です。支払い方法は主に以下の3パターンがあります。
- 着手金のみ(リテイナーフィー無料を含む)
- リテイナーフィーのみ
- 着手金とリテイナーフィーの両方
成功報酬からリテイナーフィーの累計額が控除されるケースや、一定期間を超えると免除される場合もあります。M&Aが長期化すると総額が高額になる可能性があるため、契約前に支払い条件を詳細に確認することが重要です。
両手取引と片手取引から見るM&A仲介手数料の違い
M&A仲介において、「両手取引」と「片手取引」という2つの取引形態があります。これらの違いはM&A仲介手数料の構造に大きく影響し、M&Aを成功させるためには取引形態を理解した上で選択することが重要です。ここでは、両形態の基本的な仕組みと、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。
両手取引とは何か
両手取引とは、1社の仲介会社が売り手企業と買い手企業の両方を担当する取引形態です。買い手と売り手の間に立って交渉を進め、取引の成立をサポートします。この場合、1社の仲介会社が取引全体をコントロールするため、情報共有がスムーズに行われやすく、取引が効率的に進むことが期待できます。
両手取引では、仲介会社は売り手・買い手の双方から成功報酬を受け取ります。同じ取引で2倍の手数料を得られるため、仲介会社にとっては収益性の高い取引形態となります。中小企業のM&Aでは、この両手取引が一般的に行われています。
両手取引の主な特徴として、以下の点が挙げられます。
- 1社の仲介会社が取引全体を担当
- 売り手・買い手双方から仲介手数料を受領
- 情報共有がスムーズで取引の進行が効率的
- 交渉プロセスの調整がしやすい
片手取引の基本的な仕組み
一方、片手取引は売り手企業と買い手企業がそれぞれ別の仲介会社に依頼する取引形態です。売り手側にはFA(ファイナンシャルアドバイザー)、買い手側にもFAが付き、それぞれの依頼者の利益を最大化するために活動します。この場合、少なくとも2社の仲介会社が関わることになります。
片手取引では、各仲介会社はそれぞれの依頼者からのみ手数料を受け取ります。欧米ではこの片手取引が主流であり、依頼者の利益を最優先に考えるという点で透明性の高い取引形態と言えます。
片手取引の主な特徴として、以下の点が挙げられます。
- 売り手/買い手がそれぞれ別の仲介会社に依頼
- 各仲介会社は依頼者のみから手数料を受領
- 依頼者の利益を最優先に活動できる
- 専任のアドバイザーによる手厚いサポートが受けられる
両手取引と片手取引のメリット・デメリット比較
両手取引と片手取引には、それぞれにメリットとデメリットがあります。M&Aを検討する際は、これらを理解した上で最適な取引形態を選択することが重要です。
【両手取引のメリット】
- 取引の進行がスムーズで効率的
- 1社が全体を把握するため情報の一元管理が可能
- 仲介手数料の総額が理論上は抑えられる可能性がある(実際にはケースバイケース)
- 中小企業のM&Aに適している
- 売り手・買い手間の調整がしやすい
【両手取引のデメリット】
- 利益相反のリスクがある
- 売り手と買い手どちらかの利益が損なわれる可能性
- 仲介会社の中立性に疑問が生じることがある
- 買い手側に有利になりやすいという指摘もある
【片手取引のメリット】
- 依頼者の利益を最優先に活動できる
- 専任のアドバイザーによる手厚いサポート
- 利益相反の心配が少ない
- 交渉において強い立場を確保できる
- より高い専門性を持つ仲介会社を選べる
【片手取引のデメリット】
- 仲介手数料の総額が高くなる
- 情報共有や調整に時間がかかる場合がある
- 交渉が対立的になりやすい
- 2社の仲介会社の調整が難しいことがある
利益相反のリスクと対処法
両手取引において最も懸念されるのが利益相反のリスクです。1社の仲介会社が売り手と買い手の両方を代理することで、双方の利益を同時に最大化することは原理的に困難です。例えば、売り手は高く売りたい、買い手は安く買いたいという相反する希望があります。
利益相反のリスクに対処するための方法として、以下のような点が重要です。
- 中立性の高い仲介会社の選定
優良な仲介会社は、両手取引においても公平な立場で取引をサポートします。実績や評判を確認し、中立性の高い仲介会社を選びましょう。
- 情報開示の徹底
取引の透明性を高めるため、価格算定の根拠や交渉経過などの情報開示を徹底してもらいましょう。
- 補完的なアドバイザーの活用
必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に意見を求め、仲介会社の提案を客観的に評価することも有効です。
- 契約内容の明確化
仲介会社との契約において、利益相反が発生した場合の対応や責任の所在を明確にしておきましょう。
中小企業のM&Aでは、両手取引が一般的に行われていますが、取引規模が大きくなるほど片手取引が選ばれる傾向があります。どちらの取引形態を選ぶかは、取引の規模や複雑さ、依頼者の希望などを総合的に判断する必要があります。利益相反のリスクを理解した上で、適切な対策を講じることが、M&Aを成功させるための鍵となるでしょう。
M&A仲介手数料の計算方法とレーマン方式
M&A仲介手数料のうち、最も金額が大きい成功報酬は、「レーマン方式」と呼ばれる計算方法で算出されるのが一般的です。ここでは、レーマン方式の基本的な考え方や計算方法、種類の違いについて解説します。
レーマン方式の基本的な考え方
レーマン方式とは、M&A取引の成功報酬を算出するための計算方式で、取引金額が大きくなるほど手数料率が低くなる「累進逓減方式」を採用しています。アメリカの投資銀行リーマン・ブラザーズが考案したとされています。
レーマン方式の基本的な考え方は以下の通りです。
- 取引金額を複数の区分に分ける
- 各区分に対して異なる手数料率を適用する
- 取引金額が大きくなるほど手数料率は低くなる
- 最終的な成功報酬は、各区分ごとの計算結果の合計となる
この方式は、小規模な取引では比較的高い料率が適用され、大規模な取引では低い料率が適用されます。これは、M&A仲介の業務量が必ずしも取引規模に比例して増えるわけではなく、取引金額が大きい場合は料率を下げることで公平性を保つという考え方です。
一般的なレーマン方式の手数料率テーブルは以下の通りです。
- 取引金額が5億円までの部分:5%
- 取引金額が5億円超~10億円までの部分:4%
- 取引金額が10億円超~50億円までの部分:3%
- 取引金額が50億円超~100億円までの部分:2%
- 取引金額が100億円超の部分:1%
株価レーマン方式と企業価値レーマン方式の違い
レーマン方式には、「報酬基準額」(取引金額)の考え方によって複数の種類があります。主な種類としては「株価レーマン方式」と「企業価値レーマン方式」があり、その違いを理解することが重要です。
株価レーマン方式
株価レーマン方式は、株式譲渡対価(株式価値)のみを報酬基準額とする方式です。M&Aで一般的な株式譲渡では、買い手が売り手に支払う株式の対価額をそのまま報酬基準額とします。シンプルでわかりやすく、他の方式と比較して手数料総額が最も少なくなる傾向があります。
企業価値レーマン方式
企業価値レーマン方式は、株式価値に有利子負債を加えた「企業価値(Enterprise Value)」を報酬基準額とする方式です。企業の売却によって株式価値だけでなく、借入金などの負債からも解放されるため、その分も価値として認識すべきという考え方です。株価レーマン方式よりも報酬基準額が大きくなるため、成功報酬も高くなります。
その他のレーマン方式
- オーナー受取額レーマン方式:株式譲渡対価に役員借入金を加えた金額を基準とする
- 移動総資産レーマン方式:株式価値に負債総額を加えた金額を基準とする(最も報酬基準額が大きくなる)
同じ会社のM&Aでも、採用するレーマン方式によって成功報酬に大きな差が生じることがあります。
例えば、株式価値が5億円、有利子負債が3億円、その他負債が2億円の会社の場合:
- 株価レーマン方式:報酬基準額=5億円
- 企業価値レーマン方式:報酬基準額=8億円
- 移動総資産レーマン方式:報酬基準額=10億円
このように、移動総資産レーマン方式では株価レーマン方式の2倍の報酬基準額となり、成功報酬もその分高くなります。特に負債が多い企業では、この差が非常に大きくなるため注意が必要です。
最低報酬額の設定と相場
M&A仲介会社の多くは、レーマン方式による計算とは別に「最低報酬額」(最低保証料)を設定しています。これは、小規模なM&A案件でもレーマン方式で計算すると非常に少額になってしまうケースがあるため、仲介会社の業務量との兼ね合いから設けられている最低限の報酬額です。
例えば、取引金額が3,000万円のM&A案件では、レーマン方式で計算すると成功報酬は150万円(3,000万円×5%)となりますが、これではM&A仲介会社の採算が取れない場合があります。そのため、多くの仲介会社では最低報酬額を設定しています。
最低報酬額の相場は、M&A仲介会社によって異なりますが、一般的には500万円~2,500万円程度となっています。
最低報酬額は特に小規模なM&Aで重要となります。例えば、取引金額が5,000万円のM&Aでレーマン方式により計算すると成功報酬は250万円ですが、最低報酬額が1,000万円に設定されていると、実際に支払う成功報酬は1,000万円となり、取引金額の20%にもなってしまいます。
具体的な計算例と総額シミュレーション
レーマン方式による成功報酬の計算例を具体的に見てみましょう。
ケース1:取引金額7億円の場合
株価レーマン方式を適用し、一般的な料率テーブルを使用すると:
- 5億円までの部分:5億円×5%=2,500万円
- 5億円超~7億円までの部分:2億円×4%=800万円
- 合計:2,500万円+800万円=3,300万円
ケース2:企業価値レーマン方式との比較 株式価値が5億円、有利子負債が3億円の企業の場合:
株価レーマン方式:
- 5億円×5%=2,500万円
企業価値レーマン方式:
- 5億円までの部分:5億円×5%=2,500万円
- 5億円超~8億円までの部分:3億円×4%=1,200万円
- 合計:2,500万円+1,200万円=3,700万円
同じ企業でも計算方式の違いにより、1,200万円もの差が生じます。
M&A仲介手数料の総額を計算する際は、成功報酬以外の費用も考慮する必要があります。
例えば:
- 着手金:100万円
- 中間報酬:成功報酬の20%(一時的に支払い、後に成功報酬から控除)
- デューデリジェンス費用:200万円
- 成功報酬:3,300万円(上記ケース1の場合)
このケースの総費用は3,600万円となります。複数の仲介会社の手数料体系でシミュレーションを行い、比較検討することで、自社に最適な仲介会社を選ぶ判断材料とすることができます。
中小企業向けM&A仲介手数料の選び方と注意点
中小企業がM&Aを検討する際、仲介会社の選定は成功の鍵を握ります。特に仲介手数料は大きな費用負担となるため、自社に最適な仲介会社を選ぶことが重要です。
中小企業のM&A規模に合った仲介会社を選ぶ
中小企業のM&A規模に合った仲介会社を選ぶためには、いくつかの重要ポイントがあります。
まず、仲介会社の得意とする案件規模を確認しましょう。大手M&A仲介会社は大企業間のM&Aを主に扱うケースが多く、中小企業向けには対応しきれないことがあります。中小企業専門のM&A仲介会社は小規模案件にもきめ細かいサービスを提供していることが多いため、自社の規模に合った仲介会社を選びましょう。
また、最低報酬額の設定にも注意が必要です。多くのM&A仲介会社は500万円~2,500万円程度の最低報酬額を設けています。小規模なM&Aでは、この最低報酬額が手数料全体に占める割合が高くなるため、慎重に比較検討しましょう。
業種や業界の専門性も重要な選定基準です。自社と同じ業界での実績が豊富な仲介会社を選ぶことで、適切な買い手候補の発掘や業界特有の課題への対応が期待できます。地域密着型の仲介会社が適している場合もあるため、対応エリアも考慮しましょう。
手数料体系を徹底比較して最適な仲介会社を見つける
M&A仲介会社の手数料体系は千差万別です。同じM&A案件でも、仲介会社によって支払う手数料が大きく異なる場合があります。
手数料の種類としては、相談料、着手金、月額報酬、中間報酬、成功報酬などがあります。近年は着手金や月額報酬を無料にする「完全成功報酬制」の仲介会社も増えており、初期コストを抑えたい中小企業には有利な選択肢となっています。
特に重要なのが成功報酬の計算方法であるレーマン方式の種類です。株価レーマン方式、企業価値レーマン方式、移動総資産レーマン方式などがありますが、中小企業のM&Aでは株価レーマン方式を採用している仲介会社を選ぶことで手数料を抑えられる可能性が高くなります。
複数のM&A仲介会社から見積もりを取り、手数料だけでなくサービス内容や実績なども含めて総合的に比較検討することをおすすめします。
総支払額を事前にシミュレーションする方法
M&A仲介手数料の総支払額を事前にシミュレーションしておくことで、予算計画を立てやすくなります。
まず、自社の財務諸表から株式価値、有利子負債、負債総額などの数値を整理します。これらの数値をもとに、仲介会社のレーマン方式に当てはめて計算します。例えば、株式価値が5億円、有利子負債が3億円、その他負債が2億円の場合、報酬基準額は方式によって大きく異なります。
- 株価レーマン方式:5億円
- 企業価値レーマン方式:8億円(5億円+3億円)
- 移動総資産レーマン方式:10億円(5億円+3億円+2億円)
算出した金額が最低報酬額を下回る場合は、最低報酬額が適用されることに注意し、成功報酬以外の費用も含めて総額を計算しましょう。
仲介手数料を適切に会計処理する
M&A仲介手数料の会計処理も重要なポイントです。適切な処理を行うことで、税務上のメリットを最大化できます。
売り手の場合、M&A仲介手数料は「支払手数料」などの勘定科目で費用計上されるか、株式譲渡の場合は譲渡原価に算入することもあります。買い手の場合は、費用計上するか、取得資産の原価に含めるかの選択肢があります。
成功報酬は原則として一括処理されますが、長期契約の場合は期間按分するケースもあります。税務上は原則として損金算入可能ですが、取引の内容によって取り扱いが異なるため、事前に税理士や会計士に相談することをおすすめします。
M&A仲介手数料を抑えるための5つの実践ポイント
M&A仲介手数料は数百万円から数千万円と高額になることが少なくありません。しかし、適切な方法を知れば、手数料を大幅に抑えることも可能です。ここでは、M&A仲介手数料を抑えるための5つの実践ポイントを解説します。
複数の仲介会社から相見積もりを取り比較する
M&A仲介手数料を抑える最も基本的な方法は、複数の仲介会社から相見積もりを取ることです。M&A仲介会社の手数料体系は千差万別で、同じM&A案件でも仲介会社によって手数料が倍以上違うケースも少なくありません。
最低でも3社程度から見積もりを取り、大手だけでなく中小企業専門の仲介会社も含めて検討しましょう。見積もりの際は、成功報酬だけでなく着手金や月額報酬なども含めた総額で比較し、手数料の算定方法や最低報酬額も確認することが重要です。
ただし、手数料の安さだけで選ぶのではなく、サービス内容や実績、専門性なども総合的に評価することが大切です。M&Aが成立しなければ意味がないので、成約率や評判も確認しましょう。
株式価値基準で算定する仲介会社を選択する
M&A仲介手数料の中で最も金額が大きい成功報酬は、通常「レーマン方式」という計算方法で算出されます。このレーマン方式にも複数の種類があり、どの方式を採用しているかによって手数料額が大きく変わります。
主なレーマン方式の種類としては、以下の3つがあります。
- 株価レーマン方式:株式譲渡価格のみを基準とする
- 企業価値レーマン方式:株式価値+有利子負債を基準とする
- 移動総資産レーマン方式:株式価値+負債総額を基準とする
これらのうち、最も手数料を抑えられるのが「株価レーマン方式」です。株式譲渡価格のみを報酬基準額とするため、他の方式と比較して基準額が小さくなり、手数料も少なくなります。
たとえば、株式価値が5億円、有利子負債が3億円、その他負債が2億円の企業の場合:
- 株価レーマン方式:5億円
- 企業価値レーマン方式:8億円
- 移動総資産レーマン方式:10億円
同じ料率でも、移動総資産方式では株価方式の2倍の手数料になります。契約前に必ず報酬基準額の定義を確認し、株式価値基準で算定する仲介会社を選ぶと良いでしょう。
事業承継・引継ぎ補助金を活用して費用を抑える
国や地方自治体が提供する補助金制度を活用することで、M&A仲介手数料の負担を軽減できます。特に注目すべきなのが、2025年から「事業承継・M&A補助金」に名称変更された補助金制度です。
事業承継・M&A補助金の「専門家活用枠」では、M&A仲介会社に支払う手数料を補助対象経費としています。補助率は2/3または1/2、補助上限額は800万円以内と、相当な額の補助を受けられます。
申請には「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者の費用であることが条件となるため、仲介会社選定時にこの登録状況も確認しましょう。
申請は電子申請システム「Jグランツ」のみで、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウント取得には2~3週間かかるため、余裕をもって準備を進めましょう。
参照:事業承継・M&A補助金事務局「事業承継・引継ぎ補助金」
不必要なオプションサービスを見極めて断る
M&A仲介会社によっては、基本的な仲介サービスに加えて様々なオプションサービスを提供しています。自社のM&Aに必ずしも必要ではないものも含まれている可能性があるため、不要なサービスを見極めて断ることで手数料を抑えられます。
契約前に含まれるサービスの内容を明確にし、自社のM&Aに本当に必要かどうかを精査しましょう。特に以下の項目は慎重に検討すべきです。
- 中間報酬:基本合意書締結時に発生し、M&Aが不成立でも返金されないことが多い
- 月額固定報酬:M&Aプロセスが長期化すると総額が膨らむ可能性がある
- デューデリジェンス費用:必要な調査範囲を明確にし、過剰な調査を避ける
また、着手金と成功報酬のバランスも重要です。自社の状況に合わせて最適なバランスを検討し、各サービスの具体的な内容や効果、費用対効果を確認した上で、本当に必要なサービスだけを選びましょう。
効果的な交渉で手数料を引き下げる
M&A仲介手数料は交渉によって引き下げられる可能性があります。特に複数の仲介会社から相見積もりを取得している場合は、それを材料に交渉することでより有利な条件を引き出せることがあります。
交渉を行う際の具体的なポイントとしては、以下のようなものがあります。
- 業界の相場と比較して高い場合は、根拠を示しながら交渉する
- 最低報酬額についても交渉の余地がある
- オプションサービスの取捨選択を交渉材料にする
交渉は一方的な値下げ要求ではなく、双方にとってメリットのある提案をすることが重要です。「長期的な取引を前提にしている」「将来的に他の案件も依頼する可能性がある」といった条件を示すと、仲介会社側も柔軟に対応してくれる可能性が高まります。
交渉は早い段階から始め、相手を尊重し誠実かつ前向きな姿勢で臨むことが、良好な関係構築と交渉成功の鍵となります。
まとめ|M&A仲介手数料の知識を活かして最適なM&Aを実現しよう
M&A仲介手数料は成功へのコストであると同時に、適切な知識があれば大幅に抑えることができます。手数料の種類や発生タイミングを理解し、仲介会社の料金体系を比較することがまず重要です。特に株価レーマン方式を採用している仲介会社を選ぶことで、手数料を抑えられる可能性があります。
また、複数の仲介会社から相見積もりを取り、事業承継・M&A補助金を活用し、不要なオプションサービスを見極めることで、さらに費用を抑えられます。ただし、手数料の安さだけで判断せず、仲介会社の実績や専門性、サービス内容も総合的に考慮しましょう。M&Aの失敗は手数料以上の損失をもたらす可能性があることを忘れないでください。
適切な準備と知識を持って臨めば、M&Aは企業の持続的成長と発展への強力な選択肢となります。M&A仲介手数料の知識を武器に、最適な仲介会社を選び、コストを適正に抑えながら成功確率の高いM&Aを実現しましょう。
M&Aロイヤルアドバイザリーは着手金無料の完全成功報酬型です。事業承継やM&Aに関するご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。