土地の相続税はいくら?計算方法と節税に使える特例・控除を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
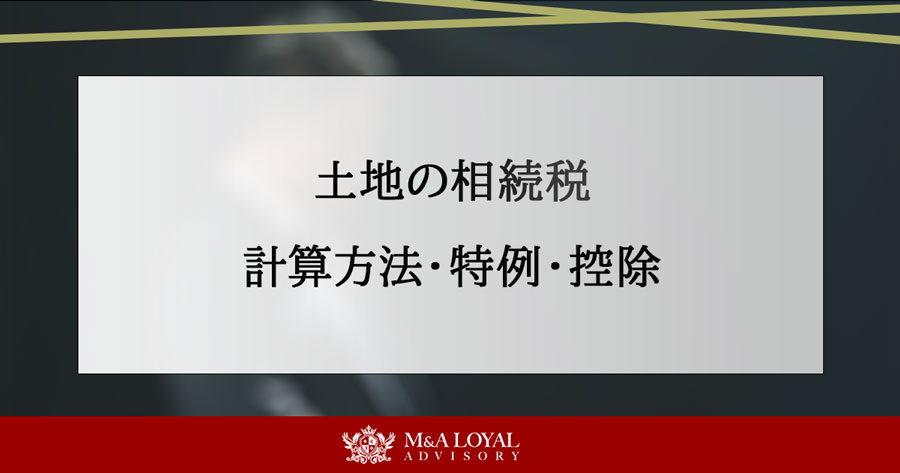
土地を相続することになった際、「相続税はいくらかかるのか」「どのような手続きが必要なのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。土地の相続税は複雑な計算が必要で、評価方法や適用できる特例によって税額が大きく変わります。
しかし、正しい知識を身につけることで、合法的に税負担を軽減し、円滑な相続を実現することが可能です。本記事では、土地の相続税計算の基本から具体的なシミュレーション、活用できる特例や控除、さらには現代的な事業承継の選択肢まで、実践的な情報を分かりやすく解説します。
目次
土地の相続税の基本知識と課税の仕組み
土地を相続することになった際、多くの方が「相続税はいくらかかるのか」「手続きはどうすればよいのか」といった不安を抱えています。土地は財産価値が高い場合が多いため、相続税の負担が重くなるのではないかと心配される方も少なくありません。しかし、相続税は必ずしもすべての土地相続にかかるわけではなく、基礎控除額という仕組みにより、一定額までは非課税となっています。
土地を相続したら必ず相続税がかかるのか
土地を相続したからといって、必ずしも相続税が課税されるわけではありません。相続税は、被相続人(亡くなった方)から財産を受け継いだ際に、その財産の総額が一定の基準額を超えた場合のみ課税される仕組みです。
土地も当然ながら相続財産に含まれますが、現金や預貯金、株式などの他の財産と合算して評価されます。相続税が課税されるかどうかは、土地単体の価値ではなく、遺産全体の価値によって決まることを理解しておくことが重要です。
基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人数まで無税になる
相続税には「基礎控除額」という非課税枠が設けられており、遺産総額がこの金額以下であれば相続税は一切かかりません。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。なお、この「法定相続人の数」には、相続を放棄した人がいてもその人を含めて計算します。また、被相続人に実子がいる場合、法定相続人に含めることができる養子の数は1人まで、実子がいない場合は2人までという制限があります。
例えば、配偶者と子供2人が法定相続人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。つまり、土地を含む遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税の申告も納税も不要です。
ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった特例を適用した結果、遺産総額が基礎控除額以下になる場合は、特例の適用を受けるために納税額が0円でも申告が必要となるため注意が必要です。この基礎控除額は2015年の税制改正により約4割引き下げられましたが、それでも多くの相続において税負担を軽減する重要な制度となっています。
中小企業の事業用地における相続税の特徴
中小企業のオーナーが事業用地を相続する場合、一般的な住宅用地とは異なる特別な考慮点があります。事業用地特有の課題と対策を整理すると次のようになります。
- 評価額が高額:基礎控除額を大きく上回るケースが多い
- 特例による減額:特定事業用宅地等で最大80%の評価減
- 所有形態の違い:個人所有と法人所有で取り扱いが異なる
- 事業継続要件:特例適用には事業の継続が必要
中小企業の事業継続と雇用維持を考慮し、適切な事業承継対策を検討することが、相続税負担の軽減だけでなく企業の存続にとっても重要な課題となっています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



土地の相続税評価額の計算方法
相続税を正確に計算するためには、土地の適切な評価額算出が必要不可欠です。土地の相続税評価額は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて算出されますが、土地の所在地域や利用形態によって評価方法が異なります。現金や預貯金とは違い、土地の価値は複数の要素によって決まるため、評価方法を正しく理解することが重要です。
路線価方式による評価額の算出手順
都市部や住宅地の大部分では、路線価方式を用いて土地の相続税評価額を算出します。路線価とは、道路に面した標準的な土地の1㎡あたりの価額のことで、千円単位で表示されています。基本的な計算式は「路線価×補正率×面積(㎡)」となります。
例えば、路線価が20万円、土地面積が100㎡の場合、基本的な評価額は2,000万円です。ただし、実際の計算では土地の形状や条件に応じて補正が必要になります。主な補正の種類は以下の通りです。
- 奥行価格補正:奥行きが長すぎる、短すぎる場合
- 間口狭小補正:間口が狭く使いにくい場合
- 不整形地補正:形がいびつで利用価値が下がる場合
- 側方路線影響加算:角地など複数の道路に面していることで利便性が高まる場合に、評価額を増額するための補正
路線価は国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。評価には、相続が開始した年(被相続人が亡くなった年)の路線価を使用する必要があります。路線価は毎年7月頃にその年分が公表されるため、例えば1月に相続が発生した場合でも、その年の7月に公表される路線価を用いて評価額を算出します。
倍率方式が適用される地域での計算方法
路線価が設定されていない地域では「倍率方式」で土地の相続税評価額を算出します。主に郊外や農村地域で適用されるこの方式は、固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を乗じて計算します。計算式は「固定資産税評価額×倍率」となります。
固定資産税評価額は、毎年市町村から送付される固定資産税の納税通知書に記載されており、3年に一度見直しが行われます。評価倍率は宅地、田、畑、山林など地目ごとに設定され、路線価と同様に国税庁のホームページで確認できます。
倍率方式では、路線価方式のような形状補正は原則として行いません。これは、土地の形状や立地条件がすでに固定資産税評価額に反映されているためです。そのため、倍率方式の方が計算は比較的シンプルになります。
貸宅地・貸家建付地の評価額の求め方
同じ土地でも利用形態によって評価方法が異なります。自分で自由に使える土地(自用地)以外に、貸宅地と貸家建付地という特殊な評価方法があります。
貸宅地とは、土地そのものを他人に貸している場合の評価方法です。計算式は「自用地評価額×(1-借地権割合)」となります。借地権割合は地域ごとに30~90%に設定されており、都市部ほど高く設定される傾向があります。
貸家建付地は、土地所有者が建物を建てて他人に貸している場合の評価方法です。アパートやマンション経営をしている土地がこれに該当します。計算式は「自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」となります。
- 借地権割合:路線価図で確認できる地域別の割合
- 借家権割合:全国一律30%
- 賃貸割合:実際に賃貸されている部分の床面積割合
例えば、自用地評価額1億円、借地権割合60%、賃貸割合100%の貸家建付地の場合、評価額は8,200万円(1億円-1億円×0.6×0.3×1.0)となり、1,800万円の評価減となります。
土地の相続税を軽減できる特例・控除
土地を相続した際の相続税負担を軽減するため、税制上様々な特例や控除が設けられています。これらの制度を適切に活用することで、相続税を大幅に削減できる場合があります。特に土地の評価額が高い場合、これらの特例の適用可否が相続税負担に大きく影響するため、要件や手続きを正しく理解しておくことが重要です。
小規模宅地等の特例で最大80%減額する条件
小規模宅地等の特例は、相続税対策において最も効果の高い制度の一つです。一定の要件を満たす土地について、評価額を最大80%減額できます。適用対象となる土地の種類と減額条件は以下の通りです。
- 特定居住用宅地等:330㎡まで80%減額
- 特定事業用宅地等:400㎡まで80%減額
- 特定同族会社事業用宅地等:400㎡まで80%減額
- 貸付事業用宅地等:200㎡まで50%減額
特定居住用宅地等では、配偶者が相続する場合、被相続人との同居の有無にかかわらず無条件で適用されます。同居親族が相続する場合は相続税の申告期限まで居住と保有を継続する必要があります。
なお、居住用と事業用など複数の土地に特例を適用することも可能ですが、その場合は適用できる面積の上限について複雑な調整計算が必要になります。 事業用の土地については、相続人が事業を継続し、申告期限まで土地を保有することが要件です。
また、同居していない親族でも「家なき子特例」により、持ち家がないなどの要件を満たせば特定居住用宅地等の適用を受けられる場合があります。ただし、平成30年改正により要件が厳格化されています。
※参照:国税庁「小規模宅地等の特例」
配偶者の税額軽減で1億6,000万円まで非課税にする方法
配偶者の税額軽減は、被相続人の法律上の配偶者(戸籍上の婚姻関係にある者)が財産を相続した場合に適用される制度です。内縁関係や事実婚のパートナーは対象外となります。「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで相続税が非課税となります。
この制度により、配偶者が取得した財産の価額が1億6,000万円以下であれば相続税はかかりません。また、遺産総額が1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分以下であれば非課税となります。
配偶者の税額軽減を適用する際の注意点は、二次相続への影響です。一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続時に子供の相続税負担が重くなる可能性があります。二次相続では配偶者控除が使えず、法定相続人も減るため基礎控除額も少なくなるためです。
また、この特例を適用するためには、相続税の申告が必要です。特例適用により相続税額が0円になる場合でも、申告期限内に申告書を提出しなければなりません。
事業承継に活用できる特定事業用宅地等の要件
中小企業の事業承継において、特定事業用宅地等の特例は重要な役割を果たします。被相続人が生前に事業を営んでいた土地について、400㎡まで80%の評価減が適用されます。
適用要件は、事業承継要件と保有継続要件の2つです。事業承継要件は、相続人が被相続人の事業を相続税の申告期限まで継続して営むことです。保有継続要件は、その土地を申告期限まで継続して保有することです。
特定同族会社事業用宅地等として、被相続人が役員として関与していた同族会社の事業用地についても、同様の特例が適用されます。この場合、相続人が会社の役員に就任し、土地を会社に貸し続けることが要件となります。
これらの特例は、事業用土地の相続税負担を大幅に軽減し、事業継続を支援する制度として機能しています。ただし、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供した土地は、原則として特例の対象外となるため、事前の対策が重要です。M&Aによる事業承継を検討する場合も、土地の取り扱いを含めた総合的な判断が必要となります。
土地の相続税の具体的な計算手順とシミュレーション
土地を相続した場合の相続税計算は、複数のステップを経て行われます。単純に土地の評価額に税率を乗じるのではなく、遺産全体を評価し、基礎控除や各種特例を適用した上で税額を算出する必要があります。ここでは、実際の計算手順を段階的に解説し、具体的な数値例を用いて相続税額のシミュレーションを行います。
遺産総額から課税遺産総額を算出する流れ
相続税計算の第一歩は、遺産総額(課税価格の合計額)の算出です。まず各相続人が取得した財産の課税価格を計算します。課税価格は「相続財産の価額-非課税財産-債務・葬式費用+生前贈与加算」で求められます。
相続財産には、土地や建物などの不動産、現金・預貯金、株式などの有価証券が含まれます。また、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も対象となります。
非課税財産として、墓地・墓石・仏壇などの祭祀用財産、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。債務は借入金や未払金、葬式費用は通夜・告別式費用や火葬料などが控除対象です。
生前贈与加算は、相続開始前7年以内(2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長)に被相続人から受けた贈与財産を相続税計算に含める制度です。なお、延長された4年間(相続開始前4年~7年)の贈与については、その合計額から100万円を控除した金額が加算の対象となります。各相続人の課税価格を算出後、それらを合計して課税価格の合計額とします。
次に、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。課税遺産総額がマイナスになる場合、相続税は課税されません。
実際の相続割合に応じた税額の按分計算
課税遺産総額が確定したら、以下の2段階のプロセスで税額を計算します。
第一段階:相続税の総額を計算する
まず、課税遺産総額を、実際の遺産分割とは関係なく、法律で定められた「法定相続分」で仮に按分します。次に、その仮に按分された各人の取得金額に相続税の速算表を適用して税額を計算し、それらをすべて合計して「相続税の総額」を算出します。
第二段階:各人の納税額を計算する
第一段階で算出した「相続税の総額」を、「実際に取得した財産の割合」に応じて按分し、各相続人の納税額を算出します。
最後に、配偶者の税額軽減や未成年者控除などの税額控除を適用して、各人の最終的な納税額が決定されます。
5,000万円の土地を相続した場合の税額例
具体例として、以下の条件で相続税を計算してみます。相続人は配偶者と子供2人の計3人、相続財産は土地5,000万円(小規模宅地等の特例適用後1,000万円)、建物2,000万円、預貯金2,000万円、債務・葬式費用200万円とします。
まず各財産の相続税評価額を個別に算出します。土地5,000万円は小規模宅地等の特例(80%減)を適用し、評価額は1,000万円(5,000万円 × (1 – 0.8))となります。
次に、すべての財産を合計して遺産総額を求めます。遺産総額は、土地1,000万円+建物2,000万円+預貯金2,000万円=5,000万円です。
遺産総額から債務・葬式費用を差し引き、課税価格の合計額を算出します。課税価格の合計額は、5,000万円-200万円=4,800万円となります。
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
したがって、課税遺産総額は、4,800万円-4,800万円=0円となります。
この場合、課税遺産総額が0円のため相続税は課税されません。ただし、小規模宅地等の特例を適用しているため、特例適用により相続税が0円になる場合でも相続税申告が必要です。
仮に小規模宅地等の特例を適用しなかった場合、課税価格の合計額は8,800万円、課税遺産総額は4,000万円となります。この4,000万円を法定相続分で仮に按分すると、配偶者2,000万円、子供各1,000万円となります。これを速算表に当てはめて計算すると、相続税の総額は450万円(配偶者分250万円+子供分100万円×2人)となります。
実際の分割割合に応じて按分し、配偶者控除を適用すると、子供の相続税負担は大幅に軽減されることがわかります。
土地の相続税の申告期限と必要な手続き
土地を相続した場合、相続税の申告だけでなく所有権移転の手続きも必要になります。これらの手続きには法定の期限が設けられており、遅れた場合には重いペナルティが課される可能性があります。相続が発生してから慌てることのないよう、必要な手続きと期限を事前に把握しておくことが重要です。
相続開始から10か月以内に完了すべき申告手続き
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は死亡日の翌日から起算されます。この期限内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、同時に相続税を納付しなければなりません。
10か月という期間は長いようで実際は短く、多くの作業を並行して進める必要があります。主要な作業項目は以下の通りです。
- 相続人確定:戸籍収集と法定相続人の特定
- 財産評価:土地評価と遺産総額の算出
- 遺産分割:協議書作成と分割方法の決定
- 特例検討:小規模宅地等の特例適用可否の判断
- 申告書作成:複数の申告書類の作成と提出
申告が必要なケースは、課税遺産総額がプラスとなる場合です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減により相続税額が0円になる場合でも、これらの特例を適用するためには申告が必要です。
期限に遅れた場合のペナルティと延滞税
相続税申告が期限に遅れた場合、複数のペナルティが課される可能性があります。無申告加算税は、納付すべき税額に対して15%(50万円超の部分は20%)の割合で課税されます。ただし、期限後1か月以内に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。
相続税の納付が遅れた場合、延滞税が課税されます。延滞税の割合は年によって異なりますが、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%程度、それ以降は年8.7%程度の高い割合となります。
さらに重要なのは、申告期限に遅れると小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例が適用できなくなることです。これにより相続税額が大幅に増加する可能性があります。ただし、やむを得ない理由がある場合は救済措置が設けられています。
期限内申告が困難な場合、税務署に相談することで期限の延長が認められることもありますが、特別な事情が必要です。海外に相続人がいる場合や、遺産分割調停が長期化している場合などが該当します。
相続登記の義務化と登録免許税の計算
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続により取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を行う際には登録免許税が必要です。税額は「固定資産税評価額×0.4%」で計算されます。例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地の場合、登録免許税は8万円となります。この登録免許税は相続税評価額ではなく固定資産税評価額を基準とする点に注意が必要です。
相続登記の申請には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類が必要です。これらの書類収集にも時間を要するため、早めの準備が重要です。
相続登記は相続人自身で行うことも可能ですが、複雑な案件では司法書士に依頼するのが一般的です。登記の専門家に依頼することで、確実かつ迅速な手続きが可能になります。相続税申告と並行して進める必要があるため、税理士と司法書士が連携してサポートを受けることが効率的です。
土地の相続税対策とM&Aによる事業承継の選択肢
土地を含む資産の相続税対策は、単に税負担を軽減するだけでなく、事業の継続性や家族の生活基盤を守るという重要な意味を持ちます。特に中小企業の経営者にとって、土地などの事業用資産の承継方法は慎重に検討すべき課題です。近年では、従来の親族内承継に加えて、M&Aによる事業承継という選択肢も注目されており、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で最適な手法を選択することが重要です。
生前贈与で計画的に節税対策を進める
生前贈与は、相続税対策の基本的な手法の一つです。被相続人が生前に財産を後継者に移転することで、相続時の遺産総額を減らし、相続税負担を軽減できます。毎年の贈与税基礎控除額110万円を活用した暦年贈与は、長期間継続することで大きな節税効果を生みます。
土地を生前贈与する場合、相続時精算課税制度の活用も検討できます。この制度では、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ2,500万円まで贈与税を納税せずに財産を移転できます。さらに、2024年1月1日からは、この2,500万円の特別控除枠とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が創設されました。この年間110万円までの贈与は、相続財産への加算対象外となり、贈与税の申告も不要です。
特に将来的に価値上昇が見込まれる土地については、早期に移転することで相続税負担を軽減できる場合があります。
ただし、生前贈与には注意点もあります。贈与から相続開始まで7年以内の財産は相続財産に持ち戻し計算されるため、計画的な実行が必要です。また、不動産の贈与では登録免許税や不動産取得税などの費用も発生します。
事業用地については、事業承継税制を活用することで、株式と一体として税負担を大幅に軽減できる場合があります。特例措置では、株式にかかる贈与税・相続税の納税猶予割合が100%に拡充されており、事業継続要件を満たせば実質的な免除が可能です。
二次相続を見据えて遺産分割を最適化する
一次相続での遺産分割を検討する際は、必ず二次相続への影響を考慮する必要があります。配偶者の税額軽減により一次相続で配偶者が多額の財産を取得した場合、二次相続時の子供世代の税負担が過重になる可能性があります。
二次相続では配偶者控除が使えず、法定相続人数も減少するため基礎控除額が少なくなります。一次相続と二次相続の税負担を通算して最小化する分割案を検討することが重要です。
土地については、一次相続で配偶者が取得し二次相続まで保有し続けるよりも、一次相続で子供が直接取得して小規模宅地等の特例を適用する方が有利な場合があります。特に、配偶者が高齢である場合や、二次相続までの期間が短いと予想される場合は、この点を慎重に検討する必要があります。
また、土地の利用形態を変更することで評価額を下げる対策も考えられます。更地にアパートを建築して貸家建付地とすることで、評価額を20%程度減額できます。さらに小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を適用できれば、200㎡まで50%の減額も可能です。
M&Aで会社と土地を一体で承継する
中小企業の事業承継において、M&Aという選択肢が注目されています。親族内に後継者がいない場合や、相続税負担が過重で事業継続が困難な場合、第三者への売却により事業を存続させることができます。
M&Aによる事業承継の最大のメリットは、経営者が株式売却により現金を得られることです。これにより相続税の納税資金を確保でき、残された家族の生活基盤を安定させることができます。また、売却対価は譲渡所得として課税されますが、株式等に係る譲渡所得の税率は20.315%と相続税の最高税率55%と比較して低く抑えられています。
事業用地についても、会社資産として一体で承継されるため、個人での土地承継時のような複雑な相続手続きは不要です。買い手企業が事業継続に必要な土地として活用するため、地域経済や雇用の維持にも貢献できます。
M&Aを検討する際は、企業価値の最大化が重要です。土地の含み益がある場合、これも企業価値の一部として評価されます。ただし、個人所有の土地と法人所有の土地では税務上の取り扱いが異なるため、事前に専門家と相談して最適な所有形態を検討することが必要です。
※参照:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
共有名義を避けて相続トラブルを防ぐ
土地の相続において、相続人間での公平性を重視するあまり共有名義とすることは、将来的なトラブルの原因となる可能性があります。共有不動産は売却や活用の際に全員の合意が必要で、意見調整が困難になりがちです。
共有状態を回避する方法として、代償分割や換価分割があります。代償分割では、一人の相続人が土地を取得し、他の相続人に現金で代償金を支払います。換価分割では、土地を売却して現金化し、相続人間で分割します。
中小企業の事業用地については、後継者が単独で承継することが事業継続の観点から重要です。他の相続人には、生命保険や他の資産で代償するか、退職金や役員報酬の調整により実質的な公平性を図ることが考えられます。
M&Aによる事業承継を選択する場合、売却代金を相続人間で分割することで、土地を含む事業資産の共有状態を解消できます。これにより、相続人間の利害対立を避け、円満な相続を実現できる可能性が高まります。
まとめ|土地の相続税を適切に計算して賢く節税しよう
土地の相続税は、適切な知識と対策により大幅に軽減できる可能性があります。本記事では、基礎控除の仕組みから具体的な計算方法、活用できる特例・控除、さらにはM&Aという新たな事業承継の選択肢まで幅広く解説してきました。
土地の相続税対策は、単なる節税テクニックではありません。家族の生活基盤を守り、事業を次世代に確実に引き継ぐための重要な経営課題です。特に中小企業の経営者にとって、土地を含む事業資産の承継方法は会社の存続に直結する問題となります。
相続税対策は早期からの計画的な取り組みが効果的です。相続が発生してからでは選択できる対策が限られてしまいます。専門家と相談しながら、個々の状況に応じた最適な対策を検討することをお勧めします。
M&Aによる事業承継を含む総合的な事業承継対策については、M&Aの専門家に相談することで、より幅広い選択肢から最適な解決策を見つけることが可能です。土地を含む事業資産の承継でお悩みの経営者の方は、ぜひ専門家のサポートを受けながら、将来を見据えた戦略的な対策を進めていただければと思います。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。













