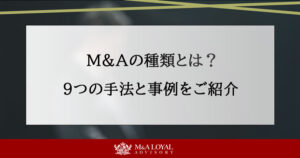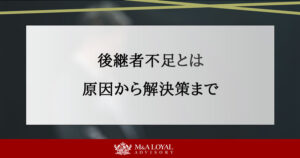人手不足の原因は?日本の状況や深刻な業界、解消する方法を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
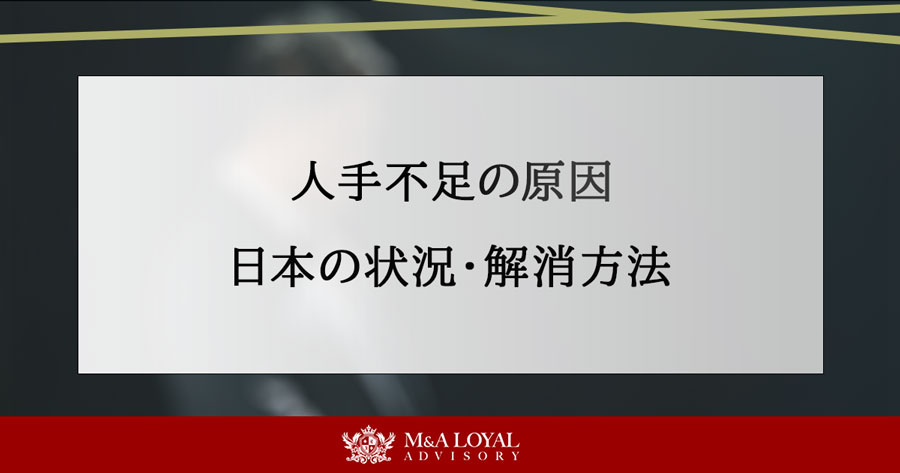
人手不足は日本経済に深刻な影響を及ぼしており、多くの企業が対応を迫られています。本記事では、人手不足の意味や人材不足との違い、日本における現状と特に影響が大きい産業を解説します。
さらに、社会的要因や企業側の課題など人手不足の原因を整理し、その結果として生じる業務負荷や倒産リスクなどの影響についても詳しく説明します。
また、採用戦略の見直しやAI導入、M&Aの活用など、企業が取り得る解決策や成功事例を紹介し、将来に備えるための視点を提供します。
目次
人手不足とは
まず、人手不足に関する基本的な知識について解説します。
人手不足の意味
「人手不足」とは、必要な業務を遂行するために十分な労働力が確保できない状態を指します。企業が求める人材の数や能力に対し、供給が追いつかない状況です。
この不足は単に人数が少ないことだけでなく、専門知識や技術を持つ人材が不足する場合にも生じます。特にITや介護などでは深刻で、採用難が続いています。
結果として既存従業員の負担増加や生産性低下、サービス品質の低下を招く恐れがあります。企業は採用戦略や人材育成、働き方改革を通じて解決を図る必要があります。
人材不足との違い
人手不足は、単純に働き手の数が足りない状態を指し、現場の業務を回すための労働力そのものが不足している状況です。特に接客業や製造業など、多くの人数を必要とする分野で使われます。
人材不足は、人数よりもスキルや専門知識を備えた人が足りない状態を意味します。ITや医療、研究分野など高度な能力を求められる領域で深刻化しています。
ほぼ同じ意味で使われることもありますが、前者は量的な不足、後者は質的な不足を強調する違いがあります。文脈に応じて区別されることが一般的です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



日本における人手不足の現状
帝国データバンクの調査を参考に、日本における人手不足の現状を解説します。
正社員の人手不足
正社員の人手不足を感じる企業は2025年1月時点で53.4%に達し、コロナ禍以降で最高水準となりました。前年1月を上回り、4年連続の上昇です。
業種別では「情報サービス」が72.5%で最も高く、システムエンジニア不足が顕著です。次いで「建設」が70.4%と深刻で、2024年問題や高齢化、若手不足が影響しています。
また、「メンテナンス・警備・検査」(66.5%)や「運輸・倉庫」(66.4%)など8業種で6割を超え、人手不足は幅広い分野で慢性化している状況です。
非正社員の人手不足
非正社員不足も30.6%と2年ぶりに3割を超え、過去4番目の高さを記録しました。正社員不足が深刻化する一方、非正社員も高止まりが続いています。
業種別では「人材派遣・紹介」が65.3%で最も高く、派遣需要の増加に供給が追いつかない状況です。「飲食店」や「旅館・ホテル」では不足割合が低下し、非正社員数の回復やDX化の進展が影響しています。
さらに「各種商品小売」(56.8%)や「飲食料品小売」(54.5%)など小売・サービス業で不足感が強く、労働集約型の分野を中心に慢性的な課題が浮き彫りとなっています。
人手不足企業の半数以上が賃上げ予定
2025年度に正社員の賃上げを予定する企業は全体で61.9%でした。特に人手不足を感じる企業では68.1%に達し、全体平均を大きく上回っています。
雇用過不足別では「適正」の企業では58.3%、「過剰」の企業では51.9%と、人手不足企業との差が鮮明です。人材確保のための賃上げ圧力が強まっている状況です。
過去の推移では、コロナ禍で一時5割台に低下したものの、2023年度には79.8%まで急上昇しました。2025年度見込みも68.1%と、コロナ禍以前を上回る賃上げ機運が続いています。
日本で人手不足が特に深刻な産業・業界
日本で人手不足が特に深刻な産業・業界として次が挙げられます。
- 情報通信業
- 建設業
- 医療・福祉
- 運輸・倉庫業
- 宿泊・飲食サービス業
それぞれを説明します。
情報通信業
情報通信業は、全産業の中でも特に人手不足が深刻な分野です。背景には、社会全体のデジタル化やDX推進の加速があり、システム開発やネットワーク構築など高度なサービス需要が急増しています。
一方で、専門スキルを持つ人材の育成には時間がかかり、供給が需要に追いついていません。そのため、経験豊富なエンジニアやプログラマーを巡る採用競争は非常に激しくなっています。
さらに、技術革新のスピードが速く、現場では常に新しい知識やスキル習得が求められるため、人材に過大な負担がかかっています。
建設業
建設業は人手不足が慢性化している代表的な産業です。住宅やインフラ整備など需要は堅調に推移していますが、現場を担う労働力の確保が難しく、受注があっても対応できない状況が生じています。
背景には、職人の高齢化と若手人材の不足があります。専門技能を持つ人材の育成が進まず、世代交代が遅れているため、技能の継承にも課題が残っています。
加えて、働き方改革による労働時間規制や人件費の上昇が経営に重くのしかかっています。
医療・福祉
医療・福祉は人手不足が最も深刻な産業の一つです。高齢化の進展により需要は増加の一途をたどっていますが、看護師や介護職員など現場を支える人材が十分に確保できていません。
背景には、業務の身体的・精神的な負担の大きさや長時間労働、賃金水準の低さがあります。こうした環境が離職を招き、慢性的な人材不足を加速させています。
さらに、専門性を持つ人材の育成には時間がかかる上、急増する需要に追いつけない状況です。
運輸・倉庫業
運輸・倉庫業は、人手不足が慢性化している産業の代表例です。EC拡大や物流需要の増加により業務量は増え続けていますが、ドライバーや倉庫作業員の確保が難しく、現場の負担が大きくなっています。
不足の背景には、長時間労働や夜間・休日勤務といった厳しい労働環境があります。若年層の応募が少なく、高齢化による退職も重なり、人材の入れ替えが進まない状況です。
その結果、配送の遅延やコスト上昇が生じ、社会インフラとしての物流機能に影響を及ぼしています。
飲食サービス業
飲食業は人手不足が深刻な産業であり、ホールスタッフや調理スタッフなど幅広い職種で人材確保が難しくなっています。外食需要が回復する一方で、労働供給が追いつかない状況です。
背景には、長時間労働や不規則勤務、低賃金といった労働環境の厳しさがあります。非正社員への依存度が高く、離職率も高いため、人材の定着が課題となっています。
その結果、営業時間の短縮や店舗数の縮小を余儀なくされる事例も見られます。
日本社会でなぜ人手不足が生じる?原因を解説
人手不足が生じる社会的な原因には次の点が挙げられます。
- 少子高齢化による労働力人口減少や地方の若年層流出による人手不足
- 求人において若者の価値観の変化による人手不足
- 専門人材の養成不足による人手不足
- インフレにコスト増による人手不足
- 優秀な人材の海外流失による人手不足
- 転職市場の硬直性による人手不足
- 限定的な移民政策による人手不足
それぞれについて詳細に説明します。
少子高齢化による労働力人口減少や地方の若年層流出による人手不足
少子高齢化により労働力人口は年々減少しており、日本社会全体で人手不足の大きな要因です。若年層の人口自体が減っているため、新たな労働力の供給が限られています。
さらに、都市部への人口集中が進み、地方では若年層が流出しています。その結果、地域産業や中小企業は人材を確保できず、労働力不足が深刻化しています。
一方で都市部でも需要増に供給が追いつかず、人材獲得競争が激化しています。
求人において若者の価値観の変化による人手不足
若者の価値観の変化も、人手不足の大きな社会的要因です。従来のように長時間労働や休日返上で働くことを前提とせず、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっています。
また、リモートワークや柔軟な働き方を望む人が増えており、現場勤務が必須の業種やサービス業では採用が難しくなっています。こうした働き方志向の変化は、特に都市部の若年層で顕著です。
さらに、肉体労働や単純作業を敬遠する傾向があり、建設業や運輸、介護・飲食業など労働集約型産業では深刻な人材不足を招いています。
専門人材の養成不足による人手不足
専門人材の養成不足も、人手不足を生じさせる大きな要因です。ITや医療、建設などでは高度なスキルを持つ人材への需要が急増していますが、教育や訓練の供給が追いついていません。
背景には、大学や専門教育機関の定員やカリキュラムが需要変化に対応しきれていないことがあります。また、現場でのOJTに依存する部分が大きく、計画的な人材育成が難しい状況です。
その結果、専門性が必要な分野では経験者の採用競争が激化し、未経験者を育てる余力も不足しています。
インフレにコスト増による人手不足
インフレによるコスト増も、人手不足を深刻化させる社会的要因です。原材料やエネルギー価格の上昇により企業の経営環境は厳しさを増し、人件費に十分な資金を回せない状況が生まれています。
特に中小企業では価格転嫁が難しく、賃金水準を引き上げられないため、人材確保で大企業に後れを取ります。その結果、採用難や離職増加が進み、人手不足が加速します。
さらに物価上昇で生活コストが増え、労働者はより高賃金の職場を求めて流動化します。賃上げが追いつかない企業には人が集まらず、インフレが構造的な人手不足を固定化する一因となっています。
優秀な人材の海外流失による人手不足
優秀な人材の海外流出も、人手不足を引き起こす社会的要因の一つです。グローバル化が進む中で、日本の人材がより高待遇や成長機会を求めて海外で働くケースが増えています。
背景には、国内の賃金水準や昇進機会の限界があります。特にITや研究分野など国際競争力が高い領域では、海外企業の方が報酬やキャリアの魅力が大きく、人材流出が顕著です。
その結果、国内では専門性を持つ人材の確保が難しくなり、育成の遅れとも相まって人手不足が深刻化します。
転職市場の硬直性による人手不足
日本の転職市場の硬直性も、人手不足を引き起こす社会的要因の一つです。終身雇用や年功序列の文化が根強く、人材が産業間を柔軟に移動しにくい状況があります。
その結果、人手が余っている産業から不足している産業への労働移動が進まず、特定の業界では慢性的な人材不足が固定化されます。即戦力を求める企業も多く、未経験者の採用が限定的です。
さらに、転職への社会的ハードルや情報の非対称性も人材流動を妨げています。
限定的な移民政策による人手不足
移民政策の制約も、人手不足を深刻化させる社会的要因です。日本では少子高齢化が進む中で労働力不足が拡大していますが、外国人労働者の受け入れ枠は諸外国に比べて限定的です。
制度上も高度人材には門戸が開かれている一方、介護や建設など人手不足産業で必要とされる中間・単純労働分野では制約が多く、十分に補えません。言語や生活支援の環境整備も不十分です。
その結果、潜在的に活用できる労働力が国内に流入せず、人手不足が構造的に固定化されています。
日本企業で人手不足が生じる原因
人手不足が生じる企業側の原因には次の点が挙げられます。
- 採用力不足
- 労働環境・条件が悪い
- 離職率が高い
- IT化・DXの未対応
- 需要変動への対応不足
- 人材育成の不足
- 企業文化、風土が古典的
- 成果主義や評価制度の不透明さ
それぞれについて詳細に説明します。
採用力不足
企業の採用力不足は、人材不足を招く要因の一つです。知名度が低い企業は求職者に情報が届きにくく、応募者数が限られるため人材確保で不利になります。
また、ブランド力の弱さも課題です。大手企業や人気業界に比べて魅力が伝わりにくく、待遇や成長機会が同等でも応募が集まりにくい状況があります。
その結果、必要な人材を採用できず、既存社員の負担増や事業機会の損失につながります。
労働環境・条件が悪い
労働環境や条件の悪さも、人材不足を引き起こす大きな要因です。長時間労働や休日が取りにくい職場は、応募者から敬遠され、定着率の低下にも直結します。
さらに、賃金水準が低かったり昇給の機会が限られていたりすると、労働者はより待遇の良い企業へ流出しやすくなり、人材確保が難しくなります。
加えて、福利厚生の不足やテレワーク・時短勤務など柔軟な働き方制度が整っていない企業は、多様な働き手のニーズに応えられず、結果的に人材不足を深刻化させています。
離職率が高い
離職率の高さも、人材不足を招く要因です。キャリアパスが不透明で将来像が描けない職場では、従業員のモチベーションが低下し、転職を選ぶ人が増えます。
また、ハラスメントや上司との関係悪化といったマネジメント不全は、職場環境を悪化させ、精神的負担から離職を加速させる要因です。
さらに、教育や研修の機会が乏しいと成長を実感できず、自己投資の場を求めて他社に流出します。
IT化・DXの未対応
IT化・DXへの未対応は、人材不足を深刻化させる要因です。業務効率化が進まない企業では人海戦術に依存せざるを得ず、必要以上の人員を必要とする構造が続いています。
また、デジタル化が遅れていると若手人材から魅力的な職場と見なされず、応募が集まりにくくなります。結果として新規採用が難しく、既存社員の負担が増加します。
さらに、IT環境が整備されていない企業ではリモートワークなど柔軟な働き方が導入できず、多様な人材の活用が進みません。
需要変動への対応不足
需要変動への対応不足も、人手不足を招く企業側の要因です。繁忙期と閑散期の差が大きい産業では、柔軟な人員配置ができないと一時的に大量の人材不足が発生します。
特に小売・宿泊・飲食などでは、短期間に人材を確保する体制が整っていない企業が多く、ピーク時にサービス提供が追いつかず顧客満足度の低下を招いています。
さらに、データ活用や予測システムが未整備だと需要変動を事前に把握できず、計画的な採用やシフト管理が困難になります。
人材育成の不足
人材育成の不足も、人材不足を引き起こす要因です。研修や教育制度が整っていないと従業員がスキルを高められず、即戦力人材に過度に依存する体質になります。
また、成長機会が乏しい職場では従業員のモチベーションが下がり、キャリア形成を求めて離職するケースが増えます。これが採用難と重なり、さらなる人材不足を招きます。
さらに、計画的な人材育成が行われないと次世代のリーダーや専門人材が育たず、長期的な組織運営にも支障が生じます。
企業文化、風土が古典的
企業文化や風土の問題も、人材不足を招く大きな要因です。年功序列や上下関係が強い旧来的な風土が残る企業では、若手や多様な人材が働きにくく、応募者が集まりにくい傾向があります。
また、変化を受け入れにくい閉鎖的な文化は、新しい働き方や柔軟な制度導入を阻害します。その結果、求職者が求めるワークライフバランスやキャリア志向と合わず、採用力の低下につながります。
さらに、社員が意見を言いにくい環境や挑戦を評価しない風土は、離職を招きます。
成果主義や評価制度の不透明さ
成果主義や評価制度の不透明さは、人手不足を生じさせる企業側の要因です。評価基準が曖昧だと、社員は努力が正しく認められていないと感じ、不満や不信感を募らせます。
その結果、やりがいを失った人材が離職し、優秀な社員ほど成長機会を求めて他社へ流出する傾向が強まります。特に若手や専門職は公正な評価を重視するため、採用や定着の難しさが増します。
さらに、不透明な制度は求職者からも魅力を感じられにくく、応募段階で敬遠される原因となります。
人手不足(または人材不足)が企業に与える影響
人手不足(または人材不足)が企業に与える影響には次のものが挙げられます。
- 顧客離れやシェア低下
- 少数の従業員に業務負荷が集中
- 採用コストの増加
- ブランド価値の低下
- 倒産リスクの上昇
それぞれを詳しく解説します。
顧客離れやシェア低下
人手不足は企業の受注対応力や営業体制を直撃します。必要な人員が確保できず、営業時間の短縮や受注制限を余儀なくされると、売り上げ機会を逃し顧客離れやシェア低下につながります。
また、人員不足により作業効率が落ち、生産性が低下します。結果として生産量やサービス提供数が減少し、顧客に対する価値提供が限定的になります。
さらに、業務の停滞や遅延が常態化し、プロジェクトや納期に支障が生じます。
少数の従業員に業務負荷が集中
人手不足は、少数の従業員に業務負荷を集中させます。限られた人員で通常以上の仕事をこなす必要があり、長時間労働や休日出勤が常態化しやすくなります。
過重な負担は心身の疲弊を招き、退職や休職につながります。特に中堅社員や現場の即戦力が離脱すると、さらに残された人への負担が増す悪循環が生じます。
結果として職場全体の士気が低下し、生産性も下がります。
採用コストの増加
人手不足が進むと、限られた労働力を巡って企業間で競争が激化します。その結果、求人広告や人材紹介サービスへの依存度が高まり、採用にかかるコストが増加します。
また、優秀な人材を確保するために初任給や待遇を引き上げざるを得ず、人件費全体が上昇します。採用活動に割く時間や労力も膨らみ、経営資源の圧迫につながります。
さらに、採用しても定着せずに早期離職が続くと、再度募集や教育に追加コストが発生します。
ブランド価値の低下
人手不足は顧客対応の遅延やサービス品質の低下を招き、クレームの増加につながります。顧客満足度が下がることで、企業への信頼が揺らぎやすくなります。
こうした状況が続くと、人手不足は「不安定な企業」という印象を与え、ブランド価値の毀損(きそん)につながります。採用活動にも悪影響を及ぼし、優秀な人材を確保しにくくなります。
さらに、余剰人員を新規事業や改善活動に充てられず、イノベーションが停滞します。
倒産リスクの上昇
人手不足が深刻化すると、受注対応力や生産能力が低下し、売り上げ機会を逃す状況が続きます。収益の減少は経営基盤を直撃し、資金繰りの悪化を招きます。
また、人件費の上昇や採用・教育コストの増大が重なれば、利益率はさらに圧迫されます。人手不足を補えない企業は、競合との差が拡大し事業継続が難しくなります。
このような悪循環が続いた場合、最悪の場合には企業は倒産に追い込まれます。
人手不足(または人材不足)を企業が解消する方法
企業が人手不足(または人材不足)を解消する方法として、次の方法があります。
- 採用チャネルの多様化
- ターゲット人材層の拡大
- 採用ブランディング強化
- 採用プロセスの改善
- 報酬・待遇の競争力向上
- パートナーシップの活用
- AIやロボティクスの導入
それぞれについて詳細に説明します。
採用チャネルの多様化
採用チャネルの多様化は、人手不足解消に有効な手段です。オンライン求人媒体を最適に活用し、Indeedやリクナビ、マイナビ、LinkedInなど複数の媒体に出稿することで、幅広い層にアプローチできます。
加えて、SNSやリファラル採用を取り入れることも有効です。社員紹介制度やLinkedIn、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokを活用すれば、企業文化や魅力を直接伝えられ、若年層を中心に応募を増やせます。
さらに、地域密着型のチャネルも重要です。ハローワークの利用や地方大学・専門学校との連携、地域紙への広告掲載を通じて、地元の人材確保につなげられます。
ターゲット人材層の拡大
ターゲット人材層の拡大は、人手不足を解消する有効な戦略です。シニア人材が60歳を超えても働ける制度を整備すれば、経験豊富な人材を長く活用できます。
また、主婦・主夫層には短時間勤務や柔軟なシフト制度を導入し、家庭との両立を支援することが重要です。さらに、障がい者雇用ではバリアフリーや職務再設計を行い、多様な人材の活躍機会を広げられます。
加えて、副業・兼業人材をプロジェクト単位で活用したり、外国人材を技能実習や特定技能制度、留学生からの正社員登用につなげることで、新たな労働力を確保できます。
採用プロセスの改善
採用プロセスの改善は、人材不足を解消する有効な手段です。応募から内定までのスピードを短縮するため、一次面接を省略したりオンライン面接を導入することで、求職者の離脱を防げます。
また、応募ハードルを下げるために経験よりポテンシャル採用を重視することも重要です。さらに、面接官のトレーニングや選考時のフィードバック提供によって、選考体験を向上させられます。
内定後は辞退防止策としてフォローイベントを実施したり、早期にオンボーディングを進めることで入社意欲を維持できます。
企業ブランディングの強化
企業ブランディングの強化は、人材獲得競争で企業が選ばれるために不可欠です。企業理念や働き方、社員インタビューをSNSや自社HPで発信することで、会社の魅力を求職者に直接伝えられます。
また、給与やキャリアパス、福利厚生を明確に公開し、透明性を高めることで応募者の安心感を醸成できます。さらに、学生や若手向けにはインターンシップや会社見学を強化し、早期からの関心を引きつけることが重要です。
加えて、SDGsや地域貢献活動などCSRの取り組みを打ち出すことで、社会的意義に共感する人材をひきつけられます。
報酬・待遇の競争力向上
報酬や待遇の競争力を高めることは、人手不足解消に直結します。まず市場水準を調査し、業界平均に見合った給与設計を行うことで、応募者から選ばれやすい環境を整えられます。
さらに、成果報酬やインセンティブ制度を導入し、頑張りが適切に評価される仕組みを整えることも重要です。これにより従業員のモチベーションが向上し、定着率の改善にもつながります。
加えて、フレックスタイムやリモートワーク、副業許可など柔軟な勤務制度を導入し、住宅手当・子育て支援・学習補助・ウェルビーイング施策といった福利厚生を充実させることが、人材確保の強い武器となります。
パートナーシップの活用
パートナーシップの活用は、人手不足解消の有効な手段です。人材紹介会社と連携すれば、成功報酬型で即戦力人材を効率的に確保でき、採用活動の負担を軽減できます。
また、大学や専門学校と協力し、カリキュラムへの参画や共同研究を行うことで、学生との接点を早期に築き、将来の採用につなげる「囲い込み」が可能です。
さらに、自治体や商工会議所と連携し、地域の雇用施策や補助金制度を活用することで、人材確保の幅を広げられます。
AIやロボティクスの導入
AIやロボティクスの導入は、人材不足を根本から補う手段です。自動化によって業務効率を高め、人材そのものを必要としない体制を整えることで、慢性的な不足を緩和できます。
具体的には、AIを活用したデータ分析やチャットボットによる顧客対応、ロボットによる製造や物流作業の自動化が挙げられます。これにより人間が担う業務量を大幅に削減できます。
また、人材を単純作業から解放し、付加価値の高い仕事に集中させることで、生産性向上と働きがいの向上を両立できます。
人手不足の解消に成功した企業の例
人手不足の解消に成功した、中小企業の例を紹介します。
株式会社吉原精工
金属加工業を営む株式会社吉原精工では、それまで月90時間超の残業が常態化していましたが、生産計画の徹底と日報活用による進捗(しんちょく)管理の改善で、2009年には残業ゼロが定着しました。
この取り組みにより、社員の生産性が向上し、売り上げは7年間で倍増しました。さらに利益を社員に還元する仕組みを整え、年間ボーナスを100万円以上支給するなど待遇改善も進めました 。
結果として、社員の平均年収は600万円に達し、採用面でも「残業がない働きやすい企業」として注目されるようになりました。また、新人社員を育てようとする風潮が生まれ若手社員の定着率が改善しました。
株式会社ダッドウェイ
株式会社ダッドウェイでは、多様な働き方を認め、健康的な企業活動を促す仕組みづくりが行われています。
2008年には、業務のマニュアル化、ノー残業デー、朝夕のメールによる業務内容の把握を開始しました。また、2013年には、育児や介護などの制約が生じる場合において、多様な働き方を認め、社員の育児や介護と両立できる環境を整えました。
その結果、2011年から2018年までの新卒入社社員の離職率は5%未満となりました。多様な人材を受け入れ活躍できる体制を整えたことが、人手不足の克服と企業成長につながった好例です。
エイベックス株式会社
エイベックス株式会社では、早期離職が課題となっていました。従業員数と売り上げは大幅に拡大した一方、入社10年未満が9割を占め、新入社員への教育不足や上司の目が届かない環境から離職率は2012年度に13.2%まで上昇しました。
そこで入社時の「導入教育」や年3回の「共育デー」を設け、基礎知識や理念を徹底しました。さらに、文理・男女・国籍を問わない採用方針を掲げ、現場女性社員との面談や認定制度の活用で女性採用を強化しました。
加えて、定時退社日や多能工化、短時間勤務制度を導入し、労働環境を改善。その結果、離職率は2015年度に8.8%、2016年には5.4%まで低下し、女性応募者も増加しました。
株式会社OZ Company
企業内保育所を運営する株式会社OZ Companyは、2012年度に離職率44%と業界平均を大きく上回り、求人費増大やサービス低下、クレーム多発といった悪循環に直面していました。スタッフ間の待遇差や負担偏りが問題を深刻化させていたのです。
そこで「ワークライフバランスとダイバーシティによる成果向上」というビジョンを掲げ、残業ゼロ・有給完全消化を推進。さらに地域で初めて同一労働同一賃金制度を導入し、パート社員を含む全員が主体的に働ける環境を整備しました。
加えてITツールを活用し業務効率化を実現。在宅勤務も取り入れ柔軟な働き方を支援した結果、2015年度には離職率がゼロに。サービス向上により口コミで園児数も増加し、求人広告なしでも人材が集まる好循環を生みました。
コーナン建設株式会社
コーナン建設株式会社は、新卒男性志望者の減少により採用・育成に苦慮し、女性採用を進めたものの早期離職が続くという課題を抱えていました。建設業界特有の女性比率の低さが背景にありました。
そこで女性社員の採用を継続し、技術職や営業職、現場など幅広い部署で男性と同様に活躍できる場を提供しました。さらに育児短時間勤務制度や再雇用制度を導入し、結婚・育児後も働ける環境を整えました。
その結果、営業職でトップ成績を収めた女性が管理職に昇進。多くの女性社員が資格を取得し専門性を発揮するなど、定着率も向上しました。育休後復帰が当然となる風土も根付き、人材活用の幅が広がりました。
人手不足な職場にM&Aがおすすめな理由
売り手目線で人手不足な企業にM&Aがおすすめな理由として、次の点が挙げられます。
- 迅速に経営資源の補完できる
- 事業継続を確保できる
- 株主の利益を最大化できる
それぞれについて詳細に説明します。
迅速に経営資源の補完できる
M&Aは、人手不足に悩む企業が迅速に経営資源を補完できる手段です。新たに人材を採用・育成するよりも短期間で必要な人員やノウハウを確保できます。
特に後継者不足や人材流出に直面する中小企業にとっては、M&Aにより経験豊富な社員や専門スキルを持つ人材を一括で引き継げます。これにより事業の継続性が高まります。
さらに、自社だけでは難しい新規分野への進出や業務効率化も、人材や仕組みを持つ企業を取り込むことで実現できます。
事業継続を確保できる
M&Aは、人手不足によって経営が不安定になっている企業にとって、事業継続を確保する有効な手段です。自力での採用や育成が難しい場合でも、必要な人材や体制を引き継ぐことで安定を取り戻せます。
特に中小企業では、人材不足が原因で受注減少やサービス低下に陥り、最悪の場合は倒産リスクに直面します。M&Aを活用すれば、経営資源を補完しつつ倒産を回避可能です。
さらに、買収先企業のネットワークやノウハウを活用することで、新たな成長の道も開けます。
株主の利益を最大化できる
M&Aは、人手不足に直面する企業の株主にとって利益を最大化できる手段です。企業売却によって株式譲渡益を得られ、まとまった資金を確保できるため、資産価値を最大限に引き出せます。
さらに、M&Aにより経営者が背負っていた個人保証や債務リスクから解放されます。借入金や保証責任の負担が軽減されることで、精神的な安心感も得られます。
また、得られた資金を活用すれば、早期リタイアや新たな事業への挑戦といった新しい人生設計も可能です。
人手不足に関するQ&A
最後に、人手不足に関するよくある質問とその回答を紹介します。
人手不足倒産とは何か
人手不足倒産とは、十分な人材を確保できないことが直接的な原因となって企業が経営破綻することを指します。採用難や離職増加により、必要な労働力が不足することで発生します。
人員不足により受注を断らざるを得なかったり、納期遅延やサービス低下が続くと顧客が離れ、売り上げが減少します。その結果、資金繰りが悪化し、経営の継続が困難になります。
特に中小企業では代替人材を確保する余力が乏しいためリスクが高く、最悪の場合は倒産に至ります。
人手不足はうそといわれる理由は何か
「人手不足はうそ」といわれる理由の一つは、求人の多くが低賃金や過酷な労働環境の職種に集中しているためです。待遇を改善すれば人材は集まるはずだ、という見方が背景にあります。
また、企業が即戦力や特定スキルに過度にこだわることで採用条件が厳しくなり、実際には働ける人がいても「人がいない」と扱われる場合があります。これが「不足は企業側の都合」と受け止められる原因です。
さらに、自動化や業務改善で解消可能な仕事も含めて人手不足とされている点も批判の対象です。
2030年問題とは何か
2030年問題とは、少子高齢化の進行により労働力人口が大幅に減少し、深刻な人手不足が社会全体に広がることを指します。特に団塊世代が後期高齢者となることで影響が顕在化します。
企業にとっては働き手が減少する一方で、介護・医療などの需要は急増するため、供給と需要のバランスが崩れ、労働市場に大きなひずみが生じます。
結果として、生産性低下やサービス提供の停滞、経済成長の鈍化につながる可能性があります。
人手不足は世界でも問題か
人手不足は日本だけの問題ではなく、世界共通の課題です。マンパワーグループ株式会社が42カ国・地域を対象に実施した調査によれば、「人手不足感」の世界平均は74%で、日本は77%とこれを上回っています。
人手不足感が特に高い国はドイツ(86%)、イスラエル(85%)、ポルトガル(84%)で、日本も世界的に見て高水準に位置しています。採用難は先進国を中心に広がっています。
本調査では、人事関連スキルの採用が最も困難とされ、対策として「賃金引き上げ」や「社員のスキルアップ・リスキリング」が挙げられました。
どこに相談すればよいか
人材不足に悩む企業がまず活用できる相談窓口は、ハローワークです。採用支援や求人票作成のアドバイスだけでなく、人材確保に向けた各種助成金制度についても相談できます。
また、商工会議所や中小企業団体中央会も有効な窓口です。地域の中小企業向けに専門家を派遣したり、人材確保や働き方改革に関するセミナーを実施しています。
さらに、中小企業庁や厚生労働省の相談窓口では、IT導入補助や人材育成支援など幅広い施策を案内しています。
まとめ
人手不足は、少子高齢化や労働条件の悪化、専門人材の不足など、さまざまな要因が絡み合って生じている複雑な問題です。このままでは、企業の成長が阻害されるだけでなく、倒産リスクが高まる可能性もあります。そのため、企業は積極的に採用プロセスの改善やIT化、AIの導入を進めることが求められます。また、企業文化や労働環境の見直しを通じて、働きたいと思える職場づくりも重要です。
この問題に直面している方は、まず自社の現状を把握し、具体的な改善策を講じることが必要です。例えば、採用チャネルを多様化したり、報酬や待遇を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。また、専門家に相談することで、より効果的な解決策を見つけることができるかもしれません。まずは小さな一歩から行動を始め、持続可能な解決策を模索していきましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。