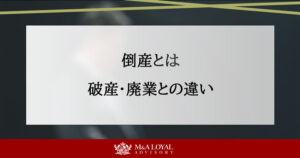労働基準監督署に通報されると会社は潰れる?5つの対策を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
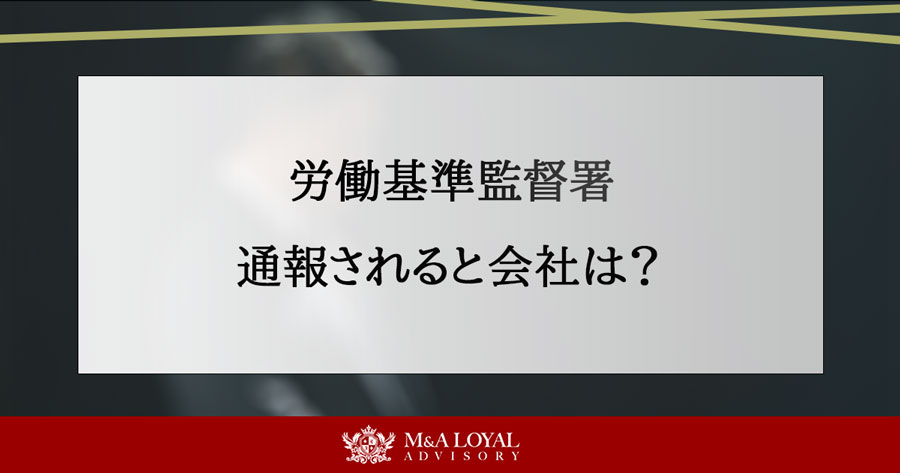
「労働基準監督署に通報されたら会社が潰れてしまうのではないか」という不安を抱える中小企業の経営者は少なくありません。実際に従業員からの申告(通報)により立ち入り調査を受け、経営が困難になった企業も存在します。しかし、適切な知識と対策があれば、こうしたリスクは大幅に軽減できるのが現実です。
本記事では、労働基準監督署への通報が企業経営に与える具体的な影響と、通報を未然に防ぐための実践的な対策を詳しく解説します。また、万が一通報を受けた場合の適切な対応方法から、経営継続が困難になった際のM&Aという選択肢まで、企業を守るための総合的な戦略をご紹介します。労務リスクを正しく理解し、持続可能な経営基盤を構築するための参考にしてください。
目次
労働基準監督署への通報で会社は潰れるのか?
「労働基準監督署に通報されると会社が潰れるのではないか」という不安を抱える経営者は少なくありません。確かに労基法違反による行政処分や社会的信用の失墜は、企業経営に深刻な影響を与える可能性があります。しかし現実的には、通報そのものが直接的に倒産を引き起こすケースは限定的です。重要なのは、通報後の対応と日頃からの労務管理体制です。
労基法違反による倒産企業の実例と統計データ
厚生労働省の「令和4年 労働基準監督年報」によると、同年に労働基準関係法令違反で検察庁に送検された事案は783件でした。この数値は、日本の全企業数から見れば限定的であり、送検が日常的に発生する事象ではないことを示しています。
東京商工リサーチの調査では、労働基準関係法令違反で公表された企業520社のうち、売上高5億円未満の中小企業が212社(55.7%)と半数を占めています。特に建設業182社(35.0%)、製造業117社(22.5%)で違反が多く発生しており、これらの業種では労働安全衛生法違反が8割に達しています。ただし、これらの統計は「違反が発覚した企業」の数であり、「倒産した企業」の数ではありません。
「労基法を守ったら倒産する」という経営者の本音
多くの中小企業経営者が「労基法を完全に守ると経営が成り立たない」と感じているのが実情です。特に人手不足が深刻な業界では、残業代の完全支給や法定休日の確保が収益を圧迫するという懸念があります。しかし、この考え方は根本的な問題を見過ごしています。労基法違反を前提とした経営モデルは、いずれ限界を迎えるリスクが高く、長期的な企業成長を阻害します。実際には、適切な労務管理により生産性向上と法令遵守を両立している企業も多数存在しています。
通報から倒産に至るまでの実際のプロセス
労基署への通報から企業倒産に至るプロセスは複雑で、単純な因果関係ではありません。通報により立ち入り調査が実施され、法令違反が確認されると是正勧告が出されます。この段階で適切に対応すれば、指導終了となります。
しかし、是正に応じない場合や悪質と判断された場合には、企業名の公表や送検に至る可能性があります。企業名公表による社会的信用の失墜、取引先との関係悪化、人材の流出などが連鎖的に発生し、最終的に経営困難に陥るケースが実際の倒産パターンです。重要なのは、通報を受けた時点での迅速かつ適切な対応です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



なぜ従業員は労働基準監督署に通報するのか?
従業員が労働基準監督署への通報に踏み切るのは、単なる思いつきではありません。そこには深刻な労働環境の問題と、会社に対する信頼の失墜があります。
通報に至る従業員の心理と不満の蓄積プロセス
従業員が労働基準監督署への通報を決意するまでには、段階的な心理変化があります。最初は残業代の未払いや長時間労働に対して社内での改善を期待しますが、直属の上司や人事部門に相談しても「会社の方針だから」「みんな我慢している」といった理由で取り合ってもらえないことが多くあります。この段階で従業員は会社への不信感を抱き始めます。
さらに問題が継続し、健康被害や生活への影響が深刻化すると、従業員は「このまま泣き寝入りするしかないのか」という絶望感を抱きます。最終的に「外部の力を借りなければ状況は変わらない」と判断した時点で、労基署への通報という行動に移るのです。
内部通報者への圧力がもたらす法的リスク
従業員が労働基準監督署に通報したことが企業側に発覚した場合、通報者に対して不利益な取り扱いを行うことは労働基準法第104条により明確に禁止されています。
また、労働基準法第119条では、労働基準法違反に対する罰則が定められています。第104条により禁止されている通報者への不利益な取り扱いに関しても、違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。この規定により、従業員が報復を恐れずに通報できる環境が整えられています。
しかし現実には、「通報者を特定して圧力をかける」「職場での孤立化を図る」といった陰湿な報復が行われるケースも存在します。こうした対応は企業にとって二重のリスクとなります。まず追加的な法的責任を負うことになり、さらに他の従業員からの信頼も失うため、新たな通報を誘発する悪循環に陥る危険性があります。
労使関係悪化を防ぐコミュニケーションの重要性
通報を未然に防ぐために最も重要なのは、日常的な労使間のコミュニケーション体制です。従業員が気軽に労務上の相談や改善提案を行える窓口の設置、定期的な従業員満足度調査の実施、経営陣と現場従業員との直接対話の機会創出などが効果的です。
また、労務問題が発生した際の迅速な対応体制を整備し、問題解決に向けた具体的なタイムスケジュールを従業員に示すことで、信頼関係を維持できます。重要なのは、従業員の声を「面倒な要求」ではなく「会社改善のための貴重な情報」として捉える経営姿勢です。
労働基準監督署に通報されたら会社はどうなる?具体的な影響と対応
労働基準監督署への通報を受けた企業は、申告監督という立ち入り調査の対象となります。この段階での対応が企業の将来を大きく左右するため、正確な知識と適切な準備が不可欠です。調査に非協力的な態度を取ると、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があり、問題がさらに深刻化するリスクがあります。
申告監督(立ち入り調査)の詳細な流れ
申告監督は通常、事前通知なしの抜き打ち調査として実施されます。労働基準監督官が事業所に直接訪問し、以下の書類確認を行います。
- 組織図:会社の体制把握
- 労働者名簿:従業員情報の確認
- 賃金台帳:給与計算の適正性
- 就業規則:労働条件の明文化
- タイムカード:労働時間の記録状況
- 36協定届:時間外労働の合法性
特に重点的にチェックされるのは、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化といった近年の法改正項目です。調査では、タイムカードの打刻記録と実際の入退室記録やPC使用記録との整合性が細かく検証されます。
労働基準監督官は関係者への事情聴取も行い、通報内容の事実確認を進めます。この調査は通常1日で完了しますが、問題の複雑さや規模によっては数日間にわたることもあります。調査拒否や虚偽の申告を行うと、追加的な法的責任を負うことになるため、誠実な対応が求められます。
是正勧告書・指導票が交付される基準と対処法
立ち入り調査の結果、法令違反が確認されると、その重大性に応じて是正勧告書または指導票が交付されます。是正勧告書は労働基準法等に明確に違反している場合に交付され、法的強制力は持たないものの、無視すると送検の対象となる可能性があります。一方、指導票は法令違反までは至らないが改善が望ましい事項について交付されます。いずれの場合も、企業は指定された期日までに改善報告書を提出する必要があります。
対処法としては、まず指摘事項を正確に理解し、根本原因を分析することが重要です。その上で、具体的な改善計画を策定し、実施状況を定期的に確認する体制を構築します。改善報告書には、問題の認識、改善措置の内容、再発防止策を詳細に記載し、期日厳守で提出することが求められます。
送検・企業名公表に至る条件とリスク回避策
是正勧告に従わない場合や悪質な法令違反が認められた場合、企業は送検される可能性があります。是正勧告に従わない、あるいは違反が悪質と判断された場合、企業は送検される可能性があります。厚生労働省「労働基準監督年報」によると、令和4年には783件の企業が労働基準関係法令違反で送検されており、これは刑事処分を意味します。
さらに重大な違反については、厚生労働省が「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として企業名と違反内容を実名で公表します。この企業名公表は社会的信用の失墜を招き、取引先からの契約解除、優秀な人材の流出、新規採用の困難化といった深刻な経営影響をもたらします。リスク回避策としては、第一に是正勧告を受けた時点で速やかに改善に着手することです。
専門家のアドバイスを受けながら、確実に法令遵守体制を構築し、労働基準監督署との継続的な協力関係を築くことが重要です。また、改善の進捗状況を定期的に報告し、誠実な姿勢を示すことで、送検リスクを大幅に軽減できます。
労基への通報を防ぐ!会社を潰さないための予防的労務管理
労働基準監督署への通報を未然に防ぐためには、日常的な労務管理の徹底が不可欠です。労働基準監督署への通報を未然に防ぐためには、日常的な労務管理の徹底が不可欠です。
令和4年の労働基準監督年報によると、従業員からの申告に基づき法令違反が認められた11,218件のうち、最も多いのは賃金不払いで8,262件(約73.6%)を占めています。これらの問題は適切な予防策により回避可能であり、企業の持続的成長につながる投資として捉えることが重要です。
賃金未払いを防ぐ勤怠管理システムを導入する
賃金未払い問題の根本原因は、不正確な労働時間の把握にあります。従来の手書きタイムカードや自己申告制では、実際の労働時間との乖離が生じやすく、サービス残業の温床となります。客観的な勤怠管理システムの導入により、正確な出退勤記録が可能になります。これらのシステムには以下の機能が備わっており、人的ミスを大幅に減らせます。
- ICカードやスマートフォンでの正確な打刻
- 顔認証システムによる本人確認
- 位置情報を活用した不正打刻防止
- 打刻漏れの自動通知機能
- PC使用記録との照合機能
導入コストを懸念する中小企業も多いですが、月額数千円から利用できるクラウド型サービスも充実しており、賃金未払いによる労務トラブルのコストと比較すれば十分に投資対効果が見込めます。
36協定を適切に締結し労基署に提出する
時間外労働を命じる場合、36協定の締結と届出は法的義務です。36協定なしに残業を命じると、たとえ1分でも労働基準法違反となります。
協定締結時は「月45時間・年360時間」の上限を遵守し、特別条項を設ける場合でも「年720時間以内」「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」「時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均が全て1月あたり80時間以内」という条件を厳守する必要があります。
また、36協定は毎年更新が必要で、有効期間が切れると新たに時間外労働ができなくなります。労働基準監督署への届出は電子申請も可能で、手続きの効率化が図れます。重要なのは協定の内容を全従業員に周知し、上限時間の管理を徹底することです。
労働条件通知書・雇用契約書を必ず交付する
労働基準法第15条により、雇用主は労働者に対して労働条件を書面で明示することが義務付けられています。労働条件通知書には、雇用期間、就業場所、業務内容、労働時間、賃金、休日などの必須記載事項があります。雇用契約書の作成も併せて行うことで、労働条件に関する合意を明確化し、後のトラブルを防げます。
パートタイム労働者や有期雇用労働者についても同様の義務があり、正社員と区別して管理する必要があります。また、労働条件に変更があった場合は、その都度書面による通知が必要です。これらの書類は労働者とのトラブル時の重要な証拠となるため、適切な保管も重要です。
法定帳簿を正確に作成し3年間保存する
企業は労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿の4つの法定帳簿を整備・保存する義務があります。これらの帳簿では以下の項目が頻繁に指摘されるため、事前に確認が必要です。
- 労働者名簿:退職者の退職年月日記載漏れ
- 賃金台帳:労働時間数や残業時間数の未記載
- 出勤簿:始業・終業時間の未記録
- 年次有給休暇管理簿:付与日と付与日数の未記載
これらの帳簿は相互に整合性を保つ必要があり、矛盾があると労務管理の杜撰さを指摘される原因となります。デジタル化により帳簿作成の効率化と精度向上が可能で、クラウド型の労務管理システムを活用すれば自動的に法定帳簿を生成できます。
2020年の労働基準法改正により、これらの帳簿の保存期間は原則として5年間に延長されました。ただし、当面の間は企業の負担を考慮した経過措置として3年間の保存が認められています。期間内に破棄すると保存義務違反となるため注意が必要です。
健康診断を毎年実施し報告書を提出する
従業員の健康診断実施は労働安全衛生法第66条により企業の義務です。対象は正社員全員と、週の所定労働時間が通常労働者の4分の3以上で1年以上継続雇用予定のパート・アルバイトです。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務もあります。
健康診断の未実施は50万円以下の罰金の対象となり、労働基準監督署の重点調査項目でもあります。健康診断の結果、異常が認められた労働者については医師の意見を聴き、必要に応じて就業制限や作業環境の改善を行う必要があります。また、健康診断の結果は5年間保存義務があり、適切な記録管理が求められます。
労基法を守りながら会社経営を維持する現実的な方法
「労基法を守ると経営が成り立たない」という経営者の声をよく耳にしますが、これは短期的な視点に基づく誤解です。適切な労務管理は初期投資こそ必要ですが、中長期的には生産性向上、離職率低下、優秀な人材確保といった経営メリットをもたらします。法令遵守を前提とした持続可能な経営モデルの構築が、真の競争優位性を生み出すのです。
業務プロセスを見直して残業時間を削減する
残業時間削減の鍵は、業務プロセスの抜本的な見直しにあります。まず現在の業務フローを詳細に分析し、以下の改善策を実施します。
- 会議の時間短縮や回数削減
- 承認プロセスの簡略化
- 定型業務の自動化
- 業務の優先順位明確化
- 重要度の低い業務の廃止または外部委託
ITツールの活用により、手作業で行っていた集計作業やデータ入力を自動化できれば、大幅な時間短縮が可能です。これらの改善により、従来と同じ成果を短時間で達成でき、残業代コストの削減と従業員の働きやすさを両立できます。業務効率化は一度実施すれば継続的な効果が期待できるため、投資対効果の高い施策といえます。 ただし、定期的な見直しやモニタリングが推奨されます。
成果主義評価制度を導入して生産性を向上させる
時間ベースの評価から成果ベースの評価への転換は、労働時間短縮と生産性向上の両方を実現する有効な手段です。従来の「長時間働く=頑張っている」という評価基準を改め、「限られた時間で高い成果を出す」従業員を適正に評価する制度を構築します。
具体的には、各職種・職位に応じた定量的な成果指標を設定し、達成度に基づく評価システムを導入します。この制度により、従業員は効率的な働き方を追求するようになり、自然と生産性が向上します。また、高い成果を出した従業員には昇進や昇給の機会を提供することで、モチベーション向上も図れます。
ただし、成果主義の導入時は評価基準の透明性と公平性を確保し、従業員の理解と納得を得ることが重要です。制度の運用開始後も定期的な見直しを行い、継続的な改善を図る必要があります。
従業員との対話を増やして労使関係を改善する
良好な労使関係は、労務トラブルの最大の予防策です。以下の取り組みにより双方向のコミュニケーションを活性化します。
- 定期的な個人面談の実施
- 従業員満足度調査の定期実施
- 経営方針説明会の開催
- 改善提案制度の運用
特に重要なのは、従業員からの意見や要望に対して真摯に検討し、可能な範囲で改善に取り組む姿勢を示すことです。全ての要求に応える必要はありませんが、検討プロセスと判断理由を透明化することで、従業員の納得感を高められます。また、労働環境の改善や福利厚生の充実により、従業員のエンゲージメント向上を図ることも効果的です。
会社が潰れる前に検討すべきM&Aという選択肢
労務問題により経営が困難な状況に陥った場合、廃業を選択する前にM&Aという選択肢を検討することが重要です。適切なタイミングでのM&Aは、従業員の雇用を守りながら事業の継続を可能にし、経営者にとっても廃業よりもメリットの大きい出口戦略となる可能性があります。
労務リスクが高まった時のM&A検討タイミング
労務リスクが顕在化し、自社での解決が困難と判断した時点で、M&Aの検討も一つの選択肢として挙げられます。具体的には、労働基準監督署からの是正勧告が出された段階、複数の従業員から労務問題の申し立てがあった段階、労務コンプライアンス体制の整備に多額の投資が必要と判明した段階などが該当します。
この段階でのM&Aには、買い手企業の労務管理ノウハウと財務基盤を活用して問題を解決できるというメリットがあります。労務問題を抱えた企業であっても、事業の収益性が高い場合や優秀な従業員を擁している場合は、買い手企業にとって魅力的な投資対象となり得ます。
重要なのは、問題が深刻化して企業価値が大幅に毀損する前に、早期に専門家に相談することです。M&A検討の際は、労務問題の詳細な開示と解決計画の提示により、買い手企業の理解と協力を得ることが成功の鍵となります。
事業承継で従業員の雇用を守る方法
中小企業における事業承継問題は深刻化しており、後継者不在により廃業を余儀なくされる企業が増加しています。M&Aによる事業承継は、従業員の雇用を維持しながら事業を継続する有効な手段です。買い手企業は既存従業員のスキルと経験を活用でき、売り手企業は従業員の生活基盤を守ることができます。
事業承継型M&Aでは、労働条件の引き継ぎが重要な論点となります。M&Aのスキームによって従業員の契約の扱いは異なり、株式譲渡の場合は会社の法人格が維持されるため、労働契約は労働条件を含めてそのまま買い手企業に包括的に承継されます。
一方、事業譲渡の場合は労働契約が自動的に承継されるわけではなく、従業員から個別に同意を得て、買い手企業と新たに雇用契約を結び直すのが一般的です。いずれの場合も、従業員の同意なく一方的に労働条件を不利益に変更することはできません。
また、M&A実行前に労務デューデリジェンスを実施し、潜在的な労務リスクを明確化することで、買い手企業の理解を得やすくなります。従業員に対しては、M&Aの目的と効果を丁寧に説明し、雇用継続への不安を解消することが重要です。適切なコミュニケーションにより、従業員のM&Aに対する協力と理解を得ることができれば、スムーズな事業承継が実現できます。
廃業よりもM&Aを選ぶべき経営判断
廃業とM&Aを比較した場合、多くの観点でM&Aの方が優位性があります。経済面では、廃業時の清算コストや従業員への退職金支払い負担を考慮すると、M&Aによる事業売却の方が経営者にとって有利な条件となるケースが多くあります。
また、廃業の場合は全ての雇用が失われますが、M&Aでは従業員の雇用継続が可能で、社会的責任も果たせます。事業面では、廃業により蓄積された技術やノウハウ、顧客関係が全て失われますが、M&Aでは買い手企業によりこれらの価値が活用され、さらなる発展の可能性があります。労務問題を抱えた企業であっても、コア事業に競争力がある場合や市場での地位が確立されている場合は、買い手企業にとって魅力的な投資対象となります。
M&A検討時は、労務問題の解決コストと事業価値を総合的に評価し、買い手企業との建設的な協議により最適な解決策を見出すことが重要です。早期の専門家への相談により、最適なタイミングでのM&A実行が可能となります。
まとめ|労働基準監督署への対応で会社を潰さないための総合戦略
労働基準監督署への通報そのものが企業を倒産に追い込むわけではありませんが、不適切な対応や継続的な法令違反は企業経営に深刻な影響を与える可能性があります。重要なのは、通報を「企業改善の機会」として捉え、根本的な労務管理体制の見直しを行うことです。
日常的な予防策として、勤怠管理システムの導入、36協定の適切な締結、法定帳簿の正確な作成、健康診断の確実な実施といった基本的な労務管理を徹底することが大切です。これらの取り組みは初期投資こそ必要ですが、長期的には生産性向上と労務リスクの軽減により、企業価値の向上につながります。
万が一通報を受けた場合は、労働基準監督署の調査に誠実に対応し、是正勧告があれば迅速に改善措置を講じることで、送検や企業名公表といった深刻な事態を回避できます。また、従業員との良好なコミュニケーションを維持し、労使関係の改善に継続的に取り組むことで、根本的な問題解決を図ることが可能です。
労務問題により経営継続が困難になった場合は、廃業よりもM&Aによる事業承継を検討することをお勧めします。適切なタイミングでのM&Aは、従業員の雇用を守りながら事業の継続を可能にし、全ての関係者にとってより良い結果をもたらす可能性があります。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。