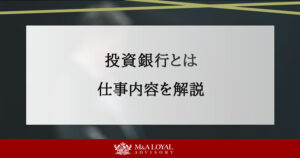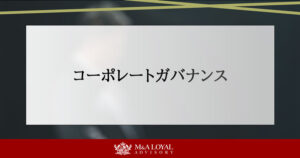株式上場の種類とは?プライム・スタンダード・グロースの違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
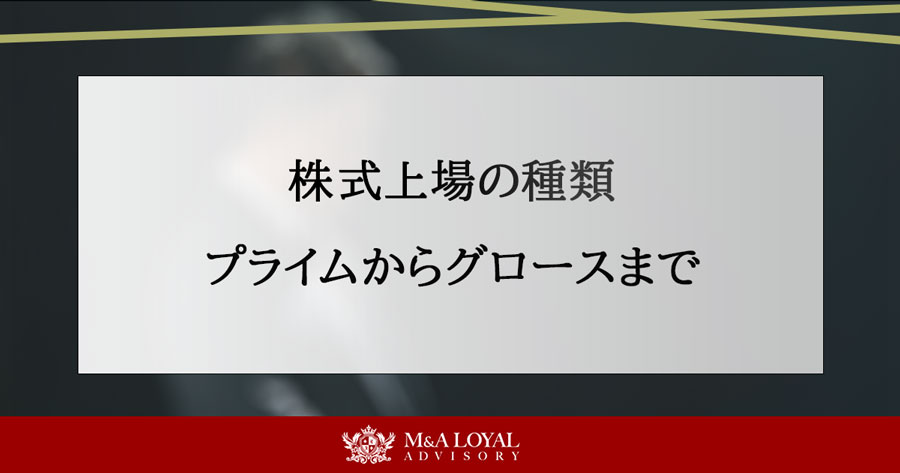
「上場って種類があるの?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
市場区分という言葉を耳にしたことはあっても、その仕組みや選び方までは把握できていないという方も少なくありません。市場区分を正しく理解することで、上場企業の経営戦略や資本政策を学ぶことができます。
本記事では、証券取引所の市場区分の種類について特徴を整理し、分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
上場とは
まず、上場の意味や非上場との違いを解説します。
上場の定義
上場とは、証券取引所が企業の株式が取引所の示す一定の基準を満たしたとして、場内でその売買を認めることです。
上場した株式を「上場株」といい、企業の所有が広く一般に開かれます。
上場は単なる資金調達手段にとどまらず、企業の透明性や社会的信頼性を高めるための重要な手段であり、経営の大きな転換点です。
証券取引所とは
証券取引所は、株式などの有価証券を売買する市場です。
企業が株式を上場するには、証券取引所が定める基準を満たし、上場申請を行う必要があります。審査に通過して上場が認められると、その企業の株式は証券会社を通じて投資家の間で売買されるようになります。
証券取引所は、上場審査だけでなく、上場後も企業によるルールの遵守や適切な情報開示が行われているかを継続的に監視する役割を担っています。
上場企業と非上場企業の違い
自社株式が証券取引所に登録されていない状態を「非上場」といいます。
上場企業は誰でもその株を市場で売買できますが、非上場企業は限られた関係者の間でのみ株式が売買されます。
上場企業には株主や投資家に向けた定期的な決算報告や適時開示など、厳格な情報公開義務が課されています。一方で、非上場企業は情報開示の義務が限定的であるため、経営の柔軟性や意思決定のスピードを保ちやすいという特徴があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



上場と似た言葉との違い
上場とよく混同される言葉は次のとおりです。
- IPO
- 店頭公開
これらの言葉の意味について解説します。
上場とIPOとの違い
IPOは「Initial Public Offering」の略で、「新規株式公開」と和訳され、上場とほぼ同義で使われます。
IPO(新規株式公開)は、企業が初めて株式を一般公開するプロセス全体を指し、そのプロセスの最終段階として、証券取引所における「上場」が行われます。上場により、公開された株式が市場で取引可能となります。
IPOには創業者が保有する株式を放出する「売り出し」と、株券を新規発行する「公募」の二つの形態があります。株券の新規発行のことをIPOと勘違いしている場合があるため注意しましょう。
上場と店頭公開の違い
店頭公開とは、証券取引所を介さずに証券会社や金融機関の店頭で取引できる状態にすることを指します。 店頭公開はかつては上場前の成長株を早期に取得して、上場後の値上がり益を狙う手段として広く利用されていました。
以前はジャスダック市場が「店頭市場」としてこれらの株式を扱っていましたが、現在はプライム市場、スタンダード市場、グロース市場に再編されました。
証券取引所の市場区分
企業が上場する際には、証券取引所ごとに用意されている「市場区分」の中から、自社の規模や事業フェーズに適した市場を選ぶ必要があります。
市場ごとに上場基準や求められるガバナンス体制、投資家層の特徴が異なるため、あらかじめその違いを理解しておくことが重要です。
ここでは、日本に存在する四つの証券取引所の区分を解説します。
東京証券取引所(東証)の市場区分
2022年4月に東証は市場区分を再編し、次の四つの市場を設けました。
プライム市場
プライム市場は、東京証券取引所が定める最上位の市場です。グローバルな機関投資家を主な対象としています。
上場には厳格な基準が設けられており、企業には高いガバナンス体制や情報開示の透明性が求められます。株主との対話や持続的な成長を重視した中長期の経営戦略が不可欠です。
上場基準には、株主数800人以上、流通株式数2万単位以上、流通時価総額100億円以上、流通株式比率35%以上といった数値的な要件に加え、コーポレート・ガバナンス・コードの厳格な順守も含まれます。
プライム市場には日本を代表する有力企業が数多く上場しており、信頼性と国際競争力を兼ね備えた企業が選ばれる市場としての位置付けです。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | グローバルに展開する大企業 |
| 株主数 | 800人以上 |
| 流通株式数 | 2万単位以上 |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 |
| 流通株式比率 | 35%以上 |
| 情報開示・ガバナンス | コーポレートガバナンス・コード完全対応 |
| 投資家層 | 国内外の機関投資家 |
参考:日本取引所グループ
スタンダード市場
スタンダード市場は、一定の事業規模や実績を持ち、安定した経営を行っている中堅企業を主な対象とする市場です。
プライム市場ほどの厳格な基準は課されていないものの、適切なガバナンス体制や継続的な情報開示、安定的な収益基盤などが求められます。
上場基準としては、株主数400人以上、流通株式数2000単位以上、流通時価総額10億円以上、流通株式比率25%以上といった要件に加え、コーポレート・ガバナンス・コードへの対応も必要です。
成長性よりも安定性や持続可能性を重視する企業が多く上場しており、地域に根差した企業や老舗企業も多く見られます。主に国内の個人投資家や中小型株を志向する投資家層にとって、親しみやすい市場といえるでしょう。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | 中堅企業・地域企業 |
| 株主数 | 400人以上 |
| 流通株式数 | 2000単位以上 |
| 流通株式時価総額 | 10億円以上 |
| 流通株式比率 | 25%以上 |
| 情報開示・ガバナンス | 一定基準の情報開示と社内体制が必要 |
| 投資家層 | 個人投資家・中小型株志向の投資家 |
グロース市場
グロース市場は、革新的な技術や新しいビジネスモデルを武器に成長を目指すベンチャー企業のために設けられた市場です。
上場時点での業績よりも、将来性や成長性が重視される点が最大の特徴です。
上場基準として、株主数150人以上、流通株式数1000単位以上、流通時価総額5億円以上、流通比率25%以上といった要件に加え、「事業計画および成長可能性に関する開示」が求められます。
未成熟な企業も多いため投資リスクが高いものの、ハイリターンを狙う投資家からの注目度も高い市場です。
成長段階にある企業にとって、グロース市場は資本市場への登竜門であり、飛躍のきっかけとなる重要なステージです。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | ベンチャー企業 |
| 株主数 | 150人以上 |
| 流通株式数 | 1000単位以上 |
| 流通株式時価総額 | 5億円以上 |
| 流通株式比率 | 25%以上 |
| 情報開示・ガバナンス | 成長計画に関する説明責任が求められる |
| 投資家層 | リスク許容度の高い投資家 |
TOKYO PRO Market
TOKYO PRO Marketは、東京証券取引所が運営する特定投資家向け市場で、主にプロの投資家を対象としています。
一般投資家は原則として参加できず、プロ投資家のみが参加できます。
この市場には、株主数や流通株式数、時価総額、利益といった形式的な上場基準が設けられておらず、企業は経営の支配権を保ったまま上場が可能です。この柔軟性が、TOKYO PRO Marketの大きな特徴といえます。
一方で、上場後は継続的な情報開示や監査法人による監査が義務付けられており、一定の透明性は維持する必要があります。
地方の中小企業や事業規模は小さくても公開企業としての信頼性を得たい企業にとって、段階的な成長の第一歩として選びやすいといえるでしょう。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | 中小企業・地方企業・成長初期企業 |
| 株主数 | 指定なし(制限なし) |
| 流通株式数 | 指定なし |
| 流通株式時価総額 | 指定なし |
| 流通株式比率 | 指定なし |
| 情報開示・ガバナンス | 簡素化されたルール下での継続開示が必要 |
| 投資家層 | プロ投資家のみ(一般投資家は原則参加不可) |
名古屋証券取引所(名証)の市場区分
ここでは、2022年4月の再編によって新たに設けられた、名古屋証券取引所(名証)の市場区分について解説します。
プレミア市場
プレミア市場は、名古屋証券取引所における最上位の市場区分で、東証プライム市場に相当する位置付けです。中部圏を中心に、全国的な知名度と実績を持つ大企業が主な対象です。
ガバナンス体制や財務基盤、情報開示の透明性など、あらゆる面で高度な要件が課されています。
上場には、株主数800人以上、流通株式数2万単位以上、流通株式比率35%以上、時価総額250億円以上といった厳格な数値基準が設けられており、さらにコーポレートガバナンス・コードへの対応も求められます。
東海地方を拠点に全国、さらには海外市場への展開を目指す企業にとって、プレミア市場は信頼性や成長性を対外的に示す大きなステップです。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | 全国的な規模を持つ大企業 |
| 株主数 | 800人以上 |
| 流通株式数 | 2万単位以上 |
| 流通株式比率 | 35%以上 |
| 時価総額 | 250億円以上 |
| 情報開示・ガバナンス | ガバナンス体制の整備が必要 |
| 投資家層 | 国内外の機関投資家 |
参考:名古屋証券取引所
メイン市場
メイン市場は、一定の事業規模と安定した業績を持つ企業を対象とした市場であり、旧・名証第一部と第二部の機能を統合して設けられました。
プレミア市場よりも上場要件が緩やかで、収益基盤や情報開示体制が一定水準に達していれば上場が可能です。
具体的には、株主数300人以上、流通株式数2000単位以上、時価総額10億円以上といった数値基準が求められます。加えて、ガバナンス体制や情報開示体制についても、基本的な整備が必要です。
メイン市場には、地域に根ざした企業や、成長よりも堅実な経営を続ける中堅企業が上場しており、企業の信頼性や安定性を外部に示す手段としても活用されています。
また、メイン市場に上場する企業の中には、将来的なプレミア市場への移行を視野に入れ、段階的な成長戦略の一環として位置付けているケースも見られます。
中部圏の投資家との接点を築きたい企業や、長期的な事業継続性の評価を得たい企業にとって、有効な市場といえるでしょう。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | 安定した実績を持つ中堅企業 |
| 株主数 | 300人以上 |
| 流通株式数 | 2000単位以上 |
| 時価総額 | 10億円以上 |
| 情報開示・ガバナンス | 一定水準の情報開示が必要 |
| 投資家層 | 個人投資家・地元の金融機関など |
ネクスト市場
ネクスト市場は、将来の成長が期待される企業や上場を通じて信用力の向上を図りたい企業に向けた市場です。
名証独自の成長支援型市場として位置付けられており、設立からの年数が浅い企業や地方の中小企業が上場のチャンスを得られます。
上場基準は、株主数が150人以上、時価総額が3億円以上です。
ただし、事業計画や成長戦略に関する開示、最低限のガバナンス体制の構築は必要であり、株主に対して将来的な成長の道筋を示すことが求められます。
上場によって事業拡大に必要な資金を調達し、ステップアップを目指す企業にとって、ネクスト市場は現実的かつ柔軟な選択肢となります。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | ベンチャー企業 |
| 株主数 | 150人以上 |
| 時価総額 | 3億円以上 |
| 情報開示・ガバナンス | 成長計画に関する説明責任が求められる |
| 投資家層 | リスク許容度の高い投資家 |
参考:名古屋証券取引所
福岡証券取引所(福証)の市場区分
ここでは、福岡証券取引所(福証)の市場区分について解説します。
本則市場
本則市場は、福岡証券取引所における主要な市場区分であり、一定の業績や経営基盤を有し、安定した運営を行っている企業を対象としています。
特に、福岡を中心とした九州地方の中堅企業が多く上場しており、地域経済との結び付きが強い点が特徴です。
上場基準は、株主数300人以上、流通株式数2000単位以上、流通株式比率25%以上、時価総額10億円以上が求められます。また、情報開示体制や社内管理体制の整備に加え、継続的なIR活動やコンプライアンス体制の構築も重要な要件とされています。
東証のプライム市場やスタンダード市場ほどの規模は求められないものの、透明性の高い経営が前提となる市場であり、地域金融機関や個人投資家から高い関心を集めています。
地方に本拠を置く企業であっても、信頼性や資金調達力の向上を目指す上で、本則市場は有効な上場先の選択肢と言えるでしょう。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | 安定経営を行う中堅・地域企業 |
| 株主数 | 300人以上 |
| 流通株式数 | 2000単位以上 |
| 流通株式比率 | 25%以上 |
| 流通時価総額 | 10億円以上 |
| 情報開示・ガバナンス | 継続開示と社内管理体制の整備が必要 |
| 投資家層 | 九州の個人投資家・地域金融機関 |
参考:福岡証券取引所
Q‐Board
Q-Boardは、成長意欲の高いベンチャー企業を対象に、福岡証券取引所が独自に設けた成長支援型の市場です。
本則市場と比べて上場基準が柔軟に設計されており、株主数200人以上、時価総額3億円以上が求められます。
実績が優れていない企業でも、将来的なビジョンや技術力が評価されれば上場が可能であり、特に九州発のベンチャー企業にとって、資本市場への登竜門といえるでしょう。
一方で、上場後には適切な情報開示体制と健全な企業運営が求められ、一定水準のガバナンス体制を整備する必要があります。
Q-Boardは、九州地域において地域発のイノベーション企業を育成・支援するための重要なプラットフォームとして期待されています。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | ベンチャー企業 |
| 株主数 | 200人以上 |
| 時価総額 | 3億円以上 |
| 情報開示・ガバナンス | 成長計画やビジョンの開示が求められる |
| 投資家層 | 地元投資家・ベンチャー投資志向の個人 |
Fukuoka PRO Market
Fukuoka PRO Marketは、プロ投資家を対象とした市場で、東京証券取引所の「TOKYO PRO Market」に準じた制度設計がなされています。
上場基準は簡素化されており、株主数や時価総額などの定量的な条件は設けられていません。ただし、一定の情報開示義務や監査体制の整備は必要とされます。
コストや手続き面での負担が少なく、上場による信頼性向上を目的とする地方企業や中小企業にとって、非常に現実的な選択肢です。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | 地方の中小企業・上場による信頼性向上を目指す企業 |
| 株主数 | 制限なし(上限・下限共に設定なし) |
| 流通株式数 | 定量的基準なし(自由な株式構成が可能) |
| 流通時価総額 | 基準なし(小規模資本でも上場可能) |
| 情報開示・ガバナンス | 適時開示体制の整備・監査法人による会計監査(無限定適正意見が必要) |
| 投資家層 | プロ投資家(特定投資家)限定 |
札幌証券取引所(札証)の市場区分
ここでは、札幌証券取引所(札証)の市場区分について解説します。
本則市場
本則市場は札幌証券取引所における標準的な市場で、北海道を中心に事業を展開する企業が上場しています。
情報開示やガバナンス体制の整備が求められる市場であり、上場企業には一定の信頼性が期待されます。こうした企業は、金融機関や個人投資家にとって、地域経済を支える有望な投資先として注目されています。
上場基準は、株主数300人以上、流通株式数2000単位以上、流通株式時価総額10億円以上です。
また、上場後も継続的な開示や監査が義務付けられているため、企業の信頼性や透明性の確保につながります。
札証本則市場での上場は、地域金融機関や個人投資家とのつながりを強化したい企業にとって、有効な資金調達手段です。東京や名古屋での上場に比べて、より地域密着型の成長戦略を描ける場として支持を集めます。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | 安定した業績を持つ中堅・地域企業 |
| 株主数 | 300人以上 |
| 流通株式数 | 2000単位以上 |
| 流通株式比率 | 25%以上 |
| 時価総額 | 10億円以上 |
| 情報開示・ガバナンス | 継続開示義務と体制整備が必要 |
| 投資家層 | 北海道の個人投資家・地銀など |
参考:札幌証券取引所
アンビシャス
アンビシャスは、札幌証券取引所が独自に設けた成長企業向けの市場です。将来的な本則市場や他取引所へのステップアップを目指す企業に適しています。
上場基準は本則市場よりも緩やかに設計されており、株主数100人以上が求められます。
特に北海道発のベンチャー企業や中小企業にとって、資金調達や社会的信用を得るための第一歩となる市場であり、地域経済の活性化にも貢献します。
ただし、上場後は一定の情報開示や内部管理体制の整備が求められるため、透明性のある経営姿勢が必要です。
| 項目 | 内容 |
| 主な対象企業 | 地方の成長企業 |
| 株主数 | 100人以上 |
| 情報開示・ガバナンス | 成長計画や内部体制に関する開示が必要 |
| 投資家層 | 地域投資家・成長企業志向の個人投資家 |
証券取引所の旧市場区分
東京証券取引所と名古屋証券取引所では、2022年4月に市場区分の再編が行われました。ここでは、再編前に設けられていた東証および名証の旧市場区分について紹介します。
東京証券取引所(東証)の旧市場区分
ここでは、東京証券取引所(東証)の旧市場区分を解説します。
東証一部
東証一部は、かつて東京証券取引所の最上位市場であり、国内外の機関投資家にとって重要な投資対象とされていました。
日本の中核的企業が上場しており、株主数や流通株式数、時価総額など非常に厳格な基準が課されていました。
上場後も継続的な情報開示やコーポレート・ガバナンス体制の整備が求められるなど、高い透明性が期待される市場でもありました。企業にとっては信頼性やステータスの証とされ、実績や安定性を重視する長期投資家にとっては、主要な投資先と位置付けられていました。
再編前の東証一部上場企業の約85%が、プライム市場に移行しました。
東証二部
東証二部は一部市場に比べて上場基準がやや緩やかで、中堅企業や地方の事業者などが上場しやすい市場でした。
流通株式数や時価総額に関する基準はあるものの、一部市場ほどの厳しさはなく安定した業績と一定のガバナンス体制があれば上場可能だった点が特徴です。
企業によっては東証二部を成長段階の通過点とし、後に一部市場への昇格を目指す動きも見られました。
また、地域との結び付きが深い企業が多く、地域金融機関との接点を持つ場としても機能してきました。
再編後は多くの企業がスタンダード市場へ移行しています。
JASDAQ スタンダード
JASDAQ スタンダードは、安定した事業基盤と一定の収益性を持つ中小企業や中堅企業が上場するための市場区分です。
歴史ある地方企業や堅実な経営を重ねてきた老舗企業が数多く上場しており、「安定成長型」の企業群として投資家から一定の評価を受けていました。
JASDAQ市場は元々日本証券業協会によって設立されましたが、後に東証に統合された後もスタンダードとグロースに分かれて運用されていた経緯があります。
業績が安定した地域密着型の企業にとって、上場の現実的な選択肢として活用されてきました。
2022年の再編で、スタンダード市場へ統合されました。
JASDAQ グロース
JASDAQ グロースは、将来性を重視したベンチャー企業向けに設けられていた市場です。
実績が優れていなくても革新的な技術や独自のビジネスモデルを持つ企業が上場できるよう設計されており、成長の可能性を軸に評価される環境が整っていました。
株主側はリターンの大きさを見込んで積極的に参加する傾向が強く、新産業分野への関心が高い層から注目を集めていた市場です。
一方で、業績の振れ幅が大きい企業も多く、一定のリスクを内包していた点も否めません。現在ではグロース市場が役割を引き継いでいます。
マザーズ
マザーズは、「Market of the high-growth and emerging stocks(高成長・新興企業市場)」の名のとおり、東証がベンチャー企業向けに創設した市場でした。ITやバイオ、ヘルスケアなどの成長分野に特化した企業が数多く上場していた点が特徴です。
業績の裏付けよりも、事業の将来性や革新性を重視する市場設計となっており、IPO市場の中心的な存在として注目を集めていました。多くの企業がマザーズをきっかけに飛躍を遂げています。
2022年の再編で、同様のコンセプトを持つグロース市場へと統合されました。
名古屋証券取引所(名証)の旧市場区分
次に、名古屋証券取引所(名証)の旧市場区分を解説します。
市場第一部
名証の市場第一部は、一定の企業規模や安定した業績、情報開示体制などが整っている中堅企業または大企業向けの市場として運用されていました。中部圏を代表する企業が上場していた点が特徴です。
上場には流通株式数や株主数、時価総額などの明確な基準があり、ガバナンス体制の整備も求められていました。
2022年の市場再編により、プレミア市場、メイン市場、ネクスト市場へと移行しています。
市場第二部
名証の市場第二部は、第一部ほどの基準は求められないものの、一定の事業実績のある企業を対象とした市場です。
地場の中堅企業やこれから事業拡大を進めたい企業にとって、資本市場との接点を持つ入り口として機能していました。
2022年の再編に伴い、プレミア市場、メイン市場、ネクスト市場へと移行しています。
セントレックス
セントレックスは、名証が独自に設けていたベンチャー企業向けの市場でした。将来性のある企業にとっての登竜門として位置付けられ、多くのベンチャー企業が上場を果たしていました。
革新的な事業内容や明確な成長計画が審査の中心とされていたため、設立から間もない企業でも上場が可能でした。この柔軟な基準がセントレックスの大きな特徴といえます。
セントレックスは、資金調達や知名度向上を目指す企業にとって、大きなチャンスとなる市場でしたが、2022年の市場再編以降、プレミア市場、メイン市場、ネクスト市場へと移行し、セントレックスの役割はネクスト市場が引き継いでいます。
上場するメリット
企業が上場する主なメリットは次のとおりです。
- 資金調達の拡大
- 信用力と企業ブランドの向上
- 人材の採用・定着
それぞれを分かりやすく解説します。
資金調達の拡大
上場する最大のメリットは、株式を通じて一般の投資家から広く資金を集められる点です。
新株を発行することで、銀行融資に頼らない、多額な資金調達ができます。
調達した資金は、設備投資や人材確保、新規事業の立ち上げなど、成長を加速させる施策に充てられます。これらの取り組みにより、株式市場から継続的に資金を得られる体制を築けます。
資金調達の柔軟性が高まることは、企業にとって経営の選択肢を広げる大きな後押しとなり、中長期的な経営計画の実現も可能です。
信用力と企業ブランドの向上
前述したように、上場するためには、証券取引所による厳格な審査を通過しなければなりません。
上場企業は透明性やガバナンス体制などの基準を満たしているため、外部からの信頼性が高くなります。
結果として上場することで取引先や金融機関からの信用を得やすくなります。その結果、より有利な取引条件や融資が受けやすくなる可能性があります。このような信用力の向上は、上場の大きな魅力の一つといえるでしょう。
さらに、上場企業は報道機関や証券アナリストなどからも注目されることが多くなり、自然と企業名の認知度が高まります。知名度の上昇にともなってブランドイメージが強化され、新たな顧客との接点を広げられます。
人材の採用・定着
上場によって企業の知名度や社会的評価が高まることで、優秀な人材を採用しやすくなります。特に新卒の採用に有利です。
また、株式報酬制度の導入や福利厚生の充実により、社員のモチベーションや帰属意識の向上につながります。
上場するデメリット
企業が上場することには次のようなデメリットもあります。
- コストと事務負担の増加
- 経営の自由度が制限される
- 情報公開による競争リスク
それぞれを解説します。
コストと事務負担の増加
上場を目指す際には、監査法人や証券会社との契約や目論見書の作成、内部統制の整備など多くの準備作業が発生します。
こうした対応には相応の専門知識と時間が必要であり、外部の専門家への支払いも含めて高額なコストがかかる点がデメリットです。
また、上場後は決算短信や有価証券報告書などの法定開示に加え、株主総会やIR活動にも対応する必要があります。
上場は、企業に透明性や社会的責任を求める一方で、人員や体制の整備に継続的な労力を要します。また、非上場時には必要なかった業務が増えるため、非上場時よりも負担を感じる企業は少なくありません。
経営の自由度が制限される
上場企業は、株主や投資家に対して常に説明責任を負っており、短期的な業績や株価の動向を強く意識する必要があります。
その結果、将来を見据えた中長期的な成長戦略よりも、目先の成果を優先せざるを得ない局面が増える傾向にあります。
さらに、上場により株式が広く分散される場合、創業者や経営陣が持っていた経営権が希薄化し、外部株主の意向が経営判断に影響を及ぼす可能性が高いです。
情報公開による競争リスク
上場企業には、財務状況や経営戦略、組織体制など、多くの情報を定期的に外部へ開示する義務があります。
こうした情報は株主にとっては透明性の確保につながる反面、競合他社にとっては事業方針や経営資源の把握に役立つ材料となりかねません。
上場により情報開示が求められるため、成長戦略や新規事業の方向性が競合他社に知られる可能性があります。その結果、競合が模倣や対策を講じ、市場での優位性が損なわれるリスクが生じることがあります。
上場は、企業が透明性を高めることで投資家から信頼を得る一方で、情報開示の範囲が広がるため、情報管理の複雑さや難しさが伴う選択であると言えるでしょう。特に、適時開示やインサイダー取引の防止、競合他社への情報漏洩リスクへの対応が課題となります。
上場するまでの流れ
上場には数年単位の準備期間を要し、段階的に進めるプロセスがあります。
- 上場準備の検討と課題の洗い出し
- 組織体制と会計制度の整備
- 上場申請と証券取引所による審査
それぞれの工程を紹介します。
上場準備の検討と課題の洗い出し
上場を意識し始めたら、まず経営体制や資本構成の見直しから着手します。
専門家によるショートレビュー(簡易調査)を受けて、改善すべき点を明確にします。 同時に社内では準備チームを編成し、主幹事証券会社や監査法人の選定にも取りかかります。
上場に向けた本格的な基盤作りが、上場準備初期の目的です。
組織体制と会計制度の整備
上場準備の検討と課題の洗い出しを行ったら、業務フローや社内規程の整備を進め、内部統制や法令順守体制の強化に取り組みます。
上場企業は、金融商品取引法に基づき、適切な会計基準に従って財務諸表を作成する必要があります。また、これらの財務諸表は監査法人による監査を受けることが義務付けられています。
加えて、グループ会社の整理や特別利害関係者との取引の透明化も求められます。
上場申請と証券取引所による審査
直前期の決算が確定した後、証券取引所への上場申請を行います。 審査では、財務内容の正確性に加えてガバナンスやコンプライアンス体制、内部統制の実効性などが総合的に評価されます。
これらの審査項目を全て満たすと上場の承認が下り、株式の公開が市場で正式に開始されます。
上場に関するQ&A
最後に、上場に関するよくある質問とその回答を紹介します。
上場するにはどれくらいの期間が必要か
一般的に、上場を実現するまでには2年半から3年程度の準備期間が必要とされています。
上場申請の約3年前から会計制度の見直しや内部統制の整備、監査法人・主幹事証券会社の選定などに着手します。
審査自体は数カ月で終わりますが、経営体制や財務基盤を整えるには相応の時間がかかるため、早期の計画立案が欠かせません。
上場のために必要な売り上げや利益の目安はあるか
上場に必要な具体的な数値は、どの市場を目指すかによって異なります。
例えば、東京証券取引所のスタンダード市場では、直前期における経常利益がおおむね1億円以上あることがひとつの基準です。
ただし、審査では利益だけでなく収益の安定性や継続的な成長が見込めるかどうかも重視されるため、単年度の数字だけでは判断されません。
なぜ非上場のまま事業を続ける企業もあるのか
上場には多額のコストや煩雑な情報開示義務が伴い、経営判断の自由度が制限される場面も増えます。
そのため、長期的なビジョンや独自の経営方針を重視する企業では、あえて非上場を選ぶケースも珍しくありません。
資金調達が内部で賄える場合や外部株主を迎え入れたくない事情がある場合にも、非上場という選択がなされることが多いです。
最後に
株式上場にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や目的が異なります。プライム、スタンダード、グロースといった市場区分の違いを理解し、適切な市場を選択することが大切です。
M&Aや経営課題に関するお悩みがある場合は、M&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。