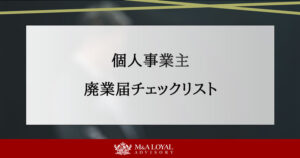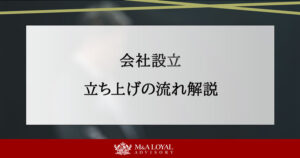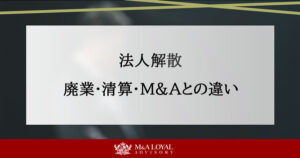廃業届とは?出し方を徹底解説!書き方・提出期限・必要書類など
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
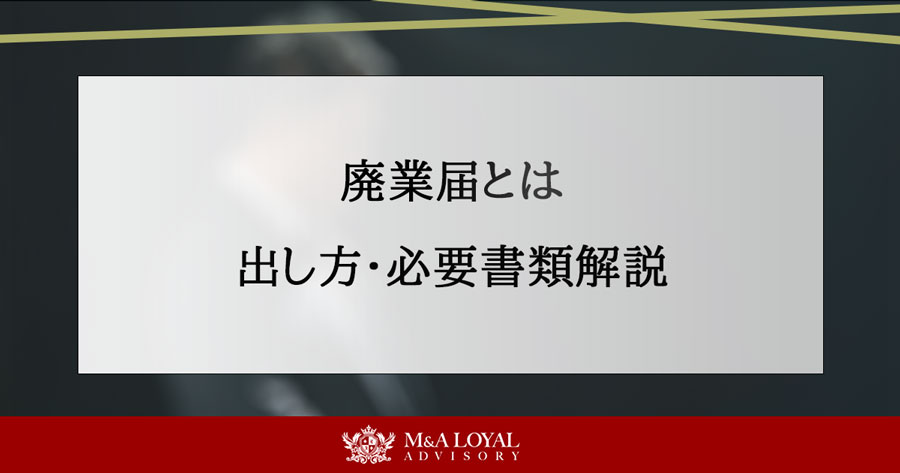
廃業届の出し方をご存じでしょうか。廃業届とは、個人事業主が事業を終了する際に提出が必要な書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。廃業届を出すことで、事業の終了を税務署に正式に通知することができ、これを怠ると予期せぬ税務上の問題が発生する可能性があります。
本記事では、廃業届の基本的な知識から具体的な出し方、記入方法、e-Taxでの申請手順まで、個人事業主が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。また、廃業以外の選択肢についても触れているので、最適な判断材料としてお役立てください。
目次
廃業届とは?個人事業主が知っておくべき基本知識
個人事業主が事業を終了する際に必要となる廃業届について、基本的な知識から重要なポイントまでを詳しく解説します。事業を終えることを検討している方や、将来的な備えとして情報収集をしている方は、正確な理解を深めておくことが大切です。
廃業届の正式名称と役割
廃業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業届と同じ書式を使用します。この書類は、個人事業主が事業を廃止したことを税務署に正式に通知するための重要な手続きです。
国や都道府県は、個人がどのような事業を営んでいるかを常時把握しているわけではありません。そのため、開業時に「開業届」を提出し、廃業時に「廃業届」を提出することで、いつからいつまで事業を行っていたかを明確にする仕組みになっています。
廃業届は所得税法第229条で提出が義務付けられており、現行法では事業を廃止した日から1ヶ月以内に納税地を所轄する税務署長宛に提出する必要があります。提出方法は税務署への直接持参、郵送、またはe-Tax(電子申告)から選択できます。
※税務行政DXの一環として所得税法第229条の改正が予定されており、2026年(令和8年)1月1日以降に事業を廃止する場合、届出の提出期限は事業を廃止した年の確定申告期限までが適用される見込みです。
参考:財務省|所得税法等の改正
廃業届を提出しないとどうなる?
廃業届を提出しなくても、法律上の罰則や延滞税などのペナルティが直接課されることはありません。しかし、提出を怠ると様々な実務上の問題が生じる可能性があります。
最も大きな問題は、税務署が事業継続中と判断し続けることです。その結果、確定申告義務があるとみなされ、申告を行わない場合は無申告加算税や延滞税が発生する恐れがあります。また、税務署から確定申告の催促状が継続的に送付されたり、事業実態の聞き取り調査が行われる可能性もあります。
さらに、事業用の銀行口座やクレジットカードを解約する際に、金融機関から廃業届の控えの提示を求められることがあります。適切な書類がないと口座やカードの解約手続きが進まず、不要な維持費用が発生し続ける場合もあります。
廃業と休業の違い
事業を一時的に停止する場合は「休業」、完全に終了する場合は「廃業」と区別されますが、税務上の取り扱いには重要な違いがあります。
休業の場合、所得税には「休業届」という制度は存在しません。将来的に事業を再開する予定があるなら、廃業届を提出せずに休業状態を維持することが推奨されます。廃業届を提出してしまうと、再開時に改めて開業届や青色申告の承認申請書などを提出する必要があり、手続きが煩雑になります。
ただし、休業中でも青色申告の繰越控除を継続したい場合は、収入がなくても確定申告を毎年行う必要があります。また、個人事業税については、自治体によって「事業休止届」の提出を求められる場合があるため、事前に確認が必要です。
将来的にM&Aによる事業承継を検討している場合も、休業状態の維持が有利です。廃業してしまうと許認可や取引先との関係、事業の継続性などが失われ、事業価値が大幅に低下する可能性があるためです。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



廃業届の出し方|5つのステップで完全理解
個人事業主が事業を廃業する際は、適切な順序で手続きを進めることが重要です。ここでは、廃業手続きを5つのステップに分けて詳しく解説します。これらのステップを正しく実行することで、法的トラブルを避け、スムーズに事業を終了できます。
ステップ1:事業資産の処分と債権債務の整理
廃業手続きの最初のステップは、事業に関連する資産の処分と債権債務の完全な整理です。この作業は廃業届を提出する前に完了させる必要があります。
事業用資産については、固定資産(店舗、設備、車両など)の売却や譲渡を行い、在庫品や商品も適切に処分します。これらの資産を売却した場合、譲渡所得として確定申告が必要になる場合があるため、事前に税理士に相談することをお勧めします。
債権債務の整理では、取引先への未払金や借入金などの債務を完済するか、返済計画を明確にします。同時に、売掛金などの債権についても回収漏れがないよう注意深く整理を行います。リース契約や賃貸借契約がある場合は、解約手続きも併せて実施しましょう。
この段階での整理が不十分だと、廃業後にトラブルが発生する可能性があるため、時間をかけて丁寧に行うことが大切です。
ステップ2:廃業日を決定する
廃業日の決定は、税務上の観点から重要な意味を持ちます。廃業後に発生した支出は、原則として事業の必要経費として認められません。ただし、事務所の原状回復費用など、その廃業した事業に直接関連して発生した費用については、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」により、廃業した年の必要経費として計上することが認められています。
廃業日は、事業に関する全ての支出を完了し、決済も済ませた後の日付に設定することが推奨されます。また、年をまたぐと確定申告を2回(2年分)行う必要があるため、年末間際に廃業を考えている場合は年内で廃業することを検討しましょう。
廃業日を年末に設定することで、所得税の計算上でメリットが出る場合もあります。具体的な廃業日については、税理士などの専門家に相談して最適なタイミングを決定することをお勧めします。
ステップ3:必要書類を準備する
廃業手続きには複数の書類の準備が必要です。基本となる「個人事業の開業・廃業等届出書」のほか、事業の状況に応じて追加書類が必要になります。
青色申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、従業員がいた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、消費税の課税事業者の場合は「事業廃止届出書」の準備が必要です。
本人確認書類として、マイナンバーカード(ない場合は個人番号通知書と運転免許証または健康保険証)の写しも必要です。書類に不備があると受理が遅れたり、再提出を求められる場合があるため、提出前に一つずつ確認することが大切です。
ステップ4:廃業届を正しく記入する
廃業届の記入は、正確性が重要です。「個人事業の開業・廃業等届出書」の各項目を順番に記入していきます。
まず、提出先の税務署名と提出年月日を記入し、納税地(通常は自宅住所)、氏名、生年月日、マイナンバーを正確に記載します。職業欄には現在の事業内容を、屋号欄には登録している屋号があれば記入します。
届出の区分では「廃業」にチェックを入れ、廃業の事由を具体的に記載します(例:「経営不振による事業継続困難のため」「法人化による個人事業廃業のため」など)。所得の種類では、廃業する事業に該当する所得すべてにチェックを入れ、全てを廃業する場合は「全部」にもチェックを入れます。
ステップ5:提出方法を選択して期限内に提出する
廃業届の提出方法は、税務署への直接持参、郵送、e-Tax(電子申告)の3つから選択できます。それぞれにメリットがあるため、自身の状況に応じて最適な方法を選びましょう。
直接持参する場合は、担当者にその場で確認してもらえるため安心感があります。郵送の場合は時間を節約でき、控えが必要であれば返信用封筒を同封することで返送してもらえます。e-Taxの場合は24時間いつでも提出でき、自宅から手続きが完了しますが、事前にマイナンバーカードとカードリーダーの準備が必要です。
提出期限は事業を廃止した日から1ヶ月以内と法律で定められています。この期限を過ぎても特別な罰則はありませんが、税務署は事業が継続していると判断し、不要な申告義務が発生する可能性があります。適切なタイミングで確実に提出することが、トラブル回避の鍵となります。
廃業届の書き方|記入例と注意点
廃業届の正確な記入は、スムーズな手続き完了のために不可欠です。「個人事業の開業・廃業等届出書」は開業届と同じ様式を使用するため、各項目の記入方法を正しく理解することが重要です。ここでは、具体的な記入例と注意すべきポイントを詳しく解説します。
届出の区分欄の記入方法
届出の区分欄では、まず「廃業」にチェックを入れます。事由欄には廃業の理由を具体的かつ簡潔に記載します。一般的な記入例は以下の通りです。
- 経営不振により事業継続が困難になったため:「経営不振による事業継続困難のため」
- 個人事業主の健康上の理由:「健康上の理由により事業継続が困難となったため」
- 個人事業主の高齢化:「高齢のため事業継続が困難となったため」
- 会社員への転職:「会社員転職のため個人事業を廃業」
- 家族の事情:「家庭の事情により事業継続が困難となったため」
事由は税務署の記録として残るため、事実に基づいた内容を記載することが大切です。詳細すぎる説明は不要ですが、廃業の主な理由が分かる程度の記載で十分です。
廃業事由の具体的な書き方
廃業事由の書き方で特に注意が必要なのは、事業譲渡を行う場合です。この場合は譲渡先の住所と氏名を併せて記載する必要があります。
また、所得の種類欄では、廃業する事業に関連するすべての所得にチェックを入れます。事業所得、不動産所得、山林所得のうち該当するものをすべて選択し、全ての事業を廃業する場合は右欄の「全部」にもチェックを入れましょう。一部の事業のみを廃業する場合は「一部」を選択します。
開業・廃業等日の欄には、実際に事業を廃止した日を記入します。この日付は非常に重要で、廃業後の支出は経費として認められない可能性があるため、慎重に決定する必要があります。年月日はすべて算用数字で記入し、年は元号(令和○年)または西暦(20○○年)のいずれでも構いません。
法人成りの場合の特別な記載事項
個人事業を法人化する「法人成り」の場合は、特別な記載が必要になります。この場合の事由欄には「法人成りのため個人事業を廃業」と記載するのが一般的です。
「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄には、設立する法人の詳細情報を記入します。具体的には、設立法人名(株式会社○○など)、法人代表者名、法人の納税地(本店所在地)、設立登記日を正確に記載します。
法人成りの場合、開業・廃業に伴う届出書の提出の有無欄では、通常「所得税の青色申告の取りやめ届出書」や「事業廃止届出書」の提出が必要になるため、該当する項目の「有」にチェックを入れます。これらの書類は廃業届と同時に提出することで、手続きの漏れを防ぐことができます。
給与等の支払の状況欄では、従業員や専従者に給与を支払っていた場合の詳細を記入します。従業員数、専従者数、給与の支払開始年月日などを正確に記載し、法人移行後も継続雇用する予定がある場合はその旨も記録として残しておくことが重要です。
法人成りは個人事業の完全な終了を意味するため、すべての項目を正確に記入し、移行先の法人情報も含めて完全な記録を残すことで、将来的なトラブルを回避できます。
廃業届と同時に提出する書類一覧
個人事業主が廃業する際は、廃業届だけでなく、事業の状況に応じて複数の関連書類を同時に提出する必要があります。これらの書類を適切に提出することで、税務上のトラブルを避け、スムーズに事業を終了できます。
青色申告の取りやめ届出書
青色申告による確定申告を行っていた個人事業主は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です。この書類は青色申告の承認を取り消すための手続きで、廃業届とは別に提出しなければなりません。
- 提出期限:青色申告を取りやめる年の翌年3月15日まで
- 記入内容:取りやめ理由欄に「個人事業を廃業するため」と記載
- 提出方法:廃業届と同時提出で手続き漏れを防止
重要な注意点として、青色申告の取りやめ届出書を提出しない場合、青色申告の承認は継続されます。重要な注意点として、この届出書を提出せずに廃業した場合でも、個人事業主の場合は青色申告の承認が自動的に取り消されることはありません。しかし、手続きの不備が将来の税務判断に影響しないとも限らないため、廃業の事実と連動させて青色申告の承認を取り消しておくことが、最も確実な手続きと言えます。
また、事業所得と不動産所得の両方がある場合で事業所得のみを廃業する際は、取りやめ届出書を提出すると不動産所得も白色申告になってしまうため、慎重に判断する必要があります。
消費税の事業廃止届出書
消費税の課税事業者であった個人事業主は、「消費税の事業廃止届出書」を廃業後速やかに所轄税務署に提出する必要があります。この書類により、消費税の課税事業者から外れる手続きを行います。
- 対象者:基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者など
- 提出期限:廃業後すみやかに(明確な期限なし)
- 提出先:所轄税務署
- 代替手続き:他の消費税関連届出書への事業廃止記載でも可
消費税の課税事業者とは、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える事業者や、特定期間(前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与等支払額の合計額が1,000万円を超える事業者などが該当します。
提出期限は明確に定められていませんが、「廃業後すみやかに」とされているため、廃業届と同時に提出することが推奨されます。なお、他の消費税関連の不適用届出書(課税事業者選択不適用届出書、簡易課税制度選択不適用届出書など)に事業廃止の旨を記載して提出した場合は、事業廃止届出書を提出したものとみなされます。
給与支払事務所の廃止届出書
従業員や青色事業専従者に給与を支払っていた個人事業主は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。この手続きは所得税法第230条に基づくもので、源泉徴収義務者としての届出を行います。
- 提出期限:廃業日から1ヶ月以内
- 提出先:源泉所得税を納付していた所轄税務署
- 対象者:従業員や専従者に給与を支払っていた事業主
- 納税期限:最後の給与分の源泉所得税は廃業日の翌月10日まで
給与支払事務所を廃止する際は、最後の給与支給分の源泉所得税を廃業日の翌月10日までに納付する必要があります。納期の特例を受けていた場合でも、この期限は変わらないため注意が必要です。
また、従業員の住民税を特別徴収していた場合は、市区町村に対して普通徴収への切り替え手続きも必要になります。これらの手続きを怠ると、廃業後も税務上の義務が継続してしまう可能性があるため、確実に実施することが重要です。
e-Taxで廃業届を提出する方法
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、廃業届を24時間いつでもオンラインで提出できます。自宅にいながら手続きが完了し、本人確認書類の提示や写しの添付も不要になるため、効率的な方法です。ここでは、e-Taxによる廃業届提出の具体的な手順について解説します。
e-Tax利用のための事前準備
e-Taxで廃業届を提出するには、事前にいくつかの準備が必要です。以下の項目を事前に準備しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
- マイナンバーカードまたはその他の電子証明書
- インターネット環境に接続されたパソコン
- ICカードリーダライタまたは対応スマートフォン
- e-Taxソフト(ダウンロード版)
初めてe-Taxを利用する場合は、利用者識別番号(16桁の番号)の取得が必要です。取得方法には「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。マイナンバーカード方式の場合、マイナンバーカードを使用してオンラインで利用者識別番号を取得できます。
次に、電子証明書の取得が必要です。これは、送信データが改ざんされていないことを証明する電子署名を行うために必要な手続きです。
最後に、e-Taxソフト(ダウンロード版)のインストールが必要です。廃業届の作成・提出には、e-TaxソフトのWEB版ではなく、必ずダウンロード版を使用する必要がある点に注意してください。
オンライン申請の具体的な手順
e-Taxソフトのインストールが完了したら、以下の手順で廃業届を作成・提出します。各ステップを順番に実行することで、確実な手続きが可能です。
- e-Taxソフト起動→税目プログラム「所得税」をインストール
- マイナンバーカードで利用者ファイル作成(4桁パスワード入力)
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択して新規作成
- 基本情報入力(マイナンバーカードで自動取得可能)
- 廃業詳細情報入力(廃業事由、廃業日、所得の種類など)
廃業届の作成は、e-Taxソフトのメニューから「作成」→「申告・申請等」→「新規作成」の順に進み、手続きの種類で「申請・届出」を、税目で「所得税」を選択します。次に「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択し、申告の名称を入力します。
基本情報の入力では、マイナンバーカードを利用することで自動取得が可能です。その後、廃業に関する詳細情報(廃業事由、廃業日、所得の種類など)を入力し、必要に応じて青色申告の取りやめ届出書や消費税の事業廃止届出書も同時に作成します。
すべての書類の作成が完了したら、電子署名を行います。署名には6~16桁の署名用電子証明書暗証番号(利用者証明用の4桁パスワードとは異なります)が必要です。電子署名が完了すると、各帳票の「署名数」欄に「1」が表示されます。
最後に、署名された書類をe-Taxで送信します。送信が完了すると受信通知が発行され、手続きは完了です。e-Taxによる提出では、メンテナンス時間を除いて24時間いつでも利用できるため、営業時間を気にする必要がありません。
廃業前に検討すべき3つの選択肢
個人事業主が事業の終了を考える際、廃業以外にも複数の選択肢があります。中小企業庁の調査によると、廃業企業の約6割が黒字廃業であり、後継者不在を理由に事業を終了するケースが多く見られます。しかし、適切な選択肢を検討することで、事業価値を保持したまま次のステップに進むことが可能です。
M&Aによる事業売却の可能性
M&A(合併・買収)による事業売却は、個人事業主にとって新たな事業承継の手段として注目されています。個人事業主の場合、株式譲渡ができないため、事業譲渡という形で事業に関する資産・負債、従業員、取引先との契約などを買い手に包括的に譲渡します。
M&Aによる事業売却の最大のメリットは、事業を継続させながら売却対価を得られることです。譲渡価格は、事業用財産の時価に営業権(のれん)の価値を加算して算定されます。営業権は通常、年間利益の3~5年分で評価されるため、収益性の高い事業ほど高額での売却が期待できます。
近年、小規模M&Aの市場は拡大しており、数十万円から1,000万円程度の取引も活発に行われています。事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的機関や、M&A仲介会社を通じて買い手を見つけることが可能です。ただし、買い手探しには時間がかかる場合があるため、早めの相談が重要です。
M&Aによる事業売却では、従業員の雇用継続、取引先との関係維持、事業ノウハウの承継など、廃業では失われる価値を保持できます。また、売り手は事業から完全に離れることも、一定期間サポートを継続することも選択できるため、柔軟な引き継ぎが可能です。
事業承継で価値を引き継ぐ方法
事業承継は、長年築いてきた事業価値を次世代に引き継ぐ重要な手段です。個人事業主の事業承継には、親族承継、従業員承継、第三者承継(M&A)の3つの方法があります。
親族承継では、贈与または相続により事業を家族に引き継ぎます。贈与の場合は生前に事業移転を行い、後継者の教育期間を確保できます。相続の場合は事業主の死亡後に承継が行われますが、準確定申告などの特別な手続きが必要です。個人版事業承継税制を活用することで、贈与税や相続税の納税猶予を受けることも可能です。
従業員承継は、長年事業に携わってきた従業員に事業を引き継ぐ方法です。事業内容を熟知した人材が承継者となるため、事業の継続性が高く、既存の取引先や顧客との関係も維持しやすいメリットがあります。ただし、個人事業の場合、従業員が個人保証を引き継ぐ必要があるため、金融機関との調整が重要になります。
どの承継方法を選択する場合でも、事業の引き継ぎには5~10年程度の準備期間が必要とされています。後継者の教育、取引先への紹介、許認可の名義変更など、段階的な準備を進めることで、スムーズな事業承継が実現できます。
一時的な休業という選択
事業の永続的な終了ではなく、一時的な事業停止を選択する休業という方法もあります。休業は廃業とは異なり、将来的な事業再開の可能性を残した状態で事業活動を停止することです。
個人事業主の場合、税務上「休業届」という制度は存在しません。しかし、事業を一時的に停止しても、廃業届を提出しなければ事業は継続している状態とみなされます。これにより、屋号や許認可、取引先との契約関係などを維持できます。
休業を選択するメリットは、市場環境の変化や個人的な事情により一時的に事業継続が困難になった場合でも、状況改善後に事業を再開できることです。また、将来的にM&Aによる事業承継を検討している場合、事業の継続性を保つことで譲渡価値を維持できます。
ただし、休業中も青色申告の繰越控除を継続したい場合は、収入がなくても毎年確定申告を行う必要があります。また、個人事業税については自治体によって「事業休止届」の提出を求められる場合があるため、事前に確認が必要です。
休業は、経営者の健康問題、家族の事情、市場の一時的な悪化など、将来的に解決可能な理由で事業継続が困難になった場合に適した選択肢です。廃業と異なり、事業価値を保持したまま再起を図ることができるため、慎重に検討する価値があります。
廃業届に関するよくある質問
個人事業主が廃業手続きを進める際に、よく寄せられる質問について詳しく解説します。これらの疑問を事前に解決しておくことで、スムーズで確実な廃業手続きを行うことができます。
個人事業主と法人の廃業手続きの違い
個人事業主と法人では、廃業手続きの複雑さと必要な手続きの範囲が大きく異なります。個人事業主の廃業は法人の解散・清算手続に比べるとシンプルですが、税務署への届出だけで完了するわけではありません。実際には、税務署(国税)への届出に加え、都道府県税事務所(地方税)への届出が全ての事業主に必要です。さらに従業員がいた場合は、年金事務所やハローワークへの手続も発生し、それぞれ提出先と期限が異なります。許認可が必要な業種では、その返納手続も別途必要となります。
一方、法人の廃業は複数の段階を経る必要があります。まず株主総会で解散決議を行い、解散登記を実施します。その後、清算人を選任して清算手続きを進め、法人税や消費税の清算申告を行います。さらに、厚生年金保険や雇用保険の廃止手続き、清算結了登記など、多くの機関での手続きが必要です。
個人事業主の場合、法人のような「解散」「清算」という概念がありません。「事業を廃業した」時点で事業はなくなるため、手続きが簡素化されています。法人の廃業には数ヶ月から1年以上の期間と相応の費用がかかりますが、個人事業の廃業は適切に準備すれば数週間で完了できます。
ただし、個人事業主でも従業員を雇用していた場合や、特定の許認可を持っていた場合は、追加の手続きが必要になる点は共通しています。
廃業後の確定申告はどうすればよい?
廃業した年も確定申告が必要です。廃業したからといって、その年の所得に対する申告義務がなくなるわけではありません。廃業年の確定申告では、1月1日から廃業日までの所得を申告します。
廃業前の事業所得に加えて、資産の売却による譲渡所得や、廃業後に会社員として働いた場合の給与所得なども合算して申告する必要があります。廃業した年の所得金額が48万円を超える場合は、必ず確定申告を行わなければなりません。
青色申告をしていた場合で事業に赤字(純損失)が生じていれば、その赤字を他の所得(例えば、廃業後に会社員として得た給与所得など)と相殺(損益通算)することができます。損益通算してもなお赤字が残る場合には、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すこと(純損失の繰越控除)が可能です。
法人成りによる廃業の場合は特に注意が必要です。個人事業の期間と法人の期間を明確に区別して申告する必要があります。例えば、5月31日に個人事業を廃業し6月1日に法人成りした場合、個人事業分は1月1日~5月31日の期間で確定申告を行い、法人は6月1日~翌年3月31日の期間で法人税申告を行います。
また、消費税の課税事業者であった場合は、消費税の申告も忘れずに行う必要があります。廃業時に保有していた棚卸資産には消費税がかかる場合があるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
業種別の許認可返上手続き
業種によっては、廃業時に許認可や免許の返上手続きが必要です。これらの手続きを怠ると、将来的にトラブルの原因となる可能性があるため、必ず確認しておきましょう。
飲食店を経営していた場合は、保健所への「食品営業許可の廃止届」の提出が必要です。酒類販売業の場合は税務署への「酒類販売業免許の取消申請書」、建設業の場合は国土交通省または都道府県への「建設業許可の廃止届」を提出します。
- 飲食店:食品営業許可の廃止届(保健所)
- 酒類販売業:酒類販売業免許の取消申請書(税務署)
- 建設業:建設業許可の廃止届(国土交通省または都道府県)
- 宅地建物取引業:宅地建物取引業者の廃業等の届出(都道府県)
- 運送業:一般貨物自動車運送事業の廃止届出(運輸局)
専門的な資格に基づく事業(行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士など)を行っていた場合は、それぞれの監督官庁や士業団体に事業停止の届出が必要な場合があります。これらの手続きは業種ごとに提出先や期限が異なるため、所轄官庁に事前に確認することが重要です。
許認可の返上手続きを怠った場合、更新手続きの案内が継続的に送付されたり、更新を行わないことによるペナルティが課される可能性があります。また、将来同じ業種で事業を再開する際に、過去の許認可状況が影響することもあるため、適切な手続きを行うことが大切です。
許認可によっては返上手続きに費用がかかる場合もあるため、廃業の費用計画にも含めて検討しておくことをお勧めします。
まとめ|廃業届の出し方を理解してスムーズな手続きを
廃業届は事業廃止日から1ヶ月以内に税務署への提出が必要です。提出を怠ると税務トラブルが発生する可能性があるため、関連書類と合わせて確実に手続きを行いましょう。
ただし、廃業前にM&Aによる事業売却や事業承継も検討することをお勧めします。収益性のある事業なら、廃業ではなく事業価値を活かした選択により売却対価を得ることも可能です。適切な準備と正確な知識で、最適な選択肢を見つけてください。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。