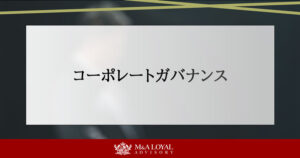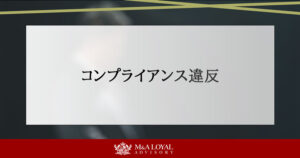ガバナンスとは?日本語の意味と使い方、コンプライアンスとの違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
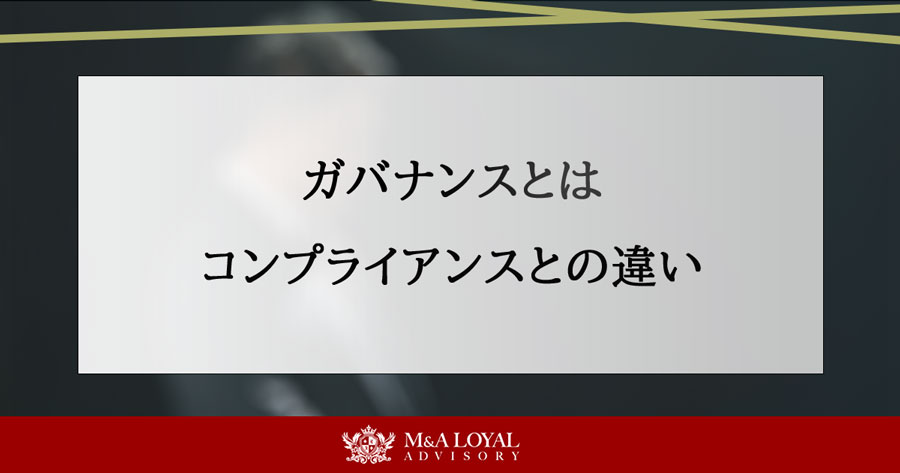
企業経営を取り巻く環境が急速に変化するなかで、「ガバナンス(Governance)」の重要性はこれまで以上に高まっています。
ガバナンスとは、企業や組織が健全かつ持続的に運営されるための「統治の仕組み」を指し、法令順守や不正防止だけでなく、迅速で透明性のある意思決定を実現するための枠組みでもあります。
本記事では、ガバナンスの基本的な意味から、コンプライアンスやマネジメントとの違い、ガバナンスを強化する方法などを詳しく解説します。
目次
ガバナンスとは
まず、ガバナンスの概要を紹介します。
意味
ガバナンスとは、組織や社会の秩序を保ち、適切に運営するための仕組みを指します。特に企業においては「コーポレートガバナンス(企業統治)」として使われ、経営者の暴走や不正を防ぎ、ステークホルダー(株主・社員・顧客など)の利益を守る役割を持ちます。
ガバナンスは、経営の透明性や信頼性を高め、持続的な成長を実現する土台です。つまり、ガバナンスとは「正しく導く力」といえるでしょう。
言葉の使い方
ビジネスシーンでは、「ガバナンスを強化する」「ガバナンス体制を整える」「ガバナンスを効かせる」といった表現で使われます。
「ガバナンス強化」は、不祥事の防止や内部統制の充実など、組織の健全性を高めるための取り組みを指します。「ガバナンス体制」は、経営陣・監査役・社外取締役などが適切に役割を果たすための仕組み全体を意味します。そして「ガバナンスを効かせる」とは、ルールを形だけでなく実際に機能させ、組織を正しい方向へ導くことを表します。いずれも、企業の信頼性や持続可能性を守る上で欠かせない考え方です。
語源
「ガバナンス」の語源は英語「governance」です。「governance」は、「組織をまとめ、方針やルールを定めて、それを実行・浸透させること」を意味します。日本語では「統治」「支配」「管理」と訳されます。
現代では企業経営や行政、ITなど、幅広い分野で「健全に運営する仕組み」を示す重要な概念として定着しています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



ガバナンスと似た言葉との違い
ガバナンスと似た言葉との違いを分かりやすく解説します。
コンプライアンス
コンプライアンスは「規則や方針に従うこと」「秩序に沿って行動すること」を意味します。英語の「comply(従う)」を語源とし、企業活動においては、法令だけでなく、社会的倫理や社内ルール、取引先との信頼関係を守る姿勢そのものを指します。
ガバナンスが「組織を正しい方向へ導く仕組み」であるのに対し、コンプライアンスは「その仕組みの下で守るべき行動規範」を示す概念です。ガバナンスがかじ取りだとすれば、コンプライアンスは航路を外れないための規律と考えると分かりやすいでしょう。
マネジメント
マネジメントとは、組織の目標を達成するために、人材・資金・設備・情報などの経営資源を計画的に活用し、効果的に業務を遂行することを指します。経営の成果を最大化するには、計画・実行・評価・改善を繰り返す「PDCAサイクル」が基本です。マネジメントの中には、リスクマネジメント(危機を予測し、損失を最小限に抑える管理手法)も含まれます。
一方で、ガバナンスはマネジメント全体を正しい方向へ導くための「統治の仕組み」です。マネジメントが組織を動かす実行の力だとすれば、ガバナンスは進路を定め、誤った判断を防ぐ羅針盤といえるでしょう。
セキュリティ
セキュリティ(security)とは、外部からの脅威や不正行為から組織・情報・資産を守り、安全な状態を維持するための取り組みを指します。
企業活動では、情報漏えいやサイバー攻撃、内部不正、災害によるシステム停止など、さまざまなリスクに対して防御策が求められます。情報セキュリティや物理的セキュリティ、人的セキュリティなどが含まれ、技術面と運用面の両立が重要です。
ガバナンスとの違いは、セキュリティが「安全を守るための具体的な手段」であるのに対し、ガバナンスは「その安全をどう確保・運用するかを定める枠組み」である点です。
内部統制
内部統制(internal control)とは、企業が健全な経営を行うために、業務の流れや責任範囲、意思決定の手続きを体系的に整備し、組織全体で適正に運用する仕組みを指します。経営資源を有効に活用しながら、業務の誤りや不正を防ぎ、財務情報の正確性を保つことを目的としています。
内部統制は、ガバナンスを支える実践的な仕組みであり、同時にコンプライアンスを実現するための重要な手段でもあります。言い換えれば、ガバナンスが「組織の方向性を示す羅針盤」だとすれば、内部統制は「現場でその方針を具現化するための操作システム」です。
ガバメント
ガバメント(govenment)とは、法律や制度に基づいて国民や地域社会を統治・運営する国家や地方自治体などの公的機関を指します。語源はラテン語の「gubernare(かじを取る)」で、「ガバナンス」と共通のルーツを持ちますが、意味合いには明確な違いがあります。
ガバメントが「統治を行う主体」すなわち政府や行政組織そのものを指すのに対し、ガバナンスは「どのように統治が行われるか」という仕組みやプロセスを意味します。例えば、ガバメントが政策を実行する力そのものなら、ガバナンスはその政策を決定・監視・評価するための枠組みといえるでしょう。
関連用語
ガバナンスの関連用語の一例として、以下のものがあります。
- コーポレートガバナンス(コーポレートガバナンス・コード)
- ガバナンスモデル
- データガバナンス
- プロダクトガバナンス
- グローバルガバナンス
それぞれを分かりやすく解説します。
コーポレートガバナンス(コーポレートガバナンス・コード)
コーポレートガバナンスとは、上場企業が不祥事や不正を防ぎ、公正で透明性の高い経営を実現するための統治体制を指します。経営陣を監督する社外取締役や社外監査役が、株主や従業員、債権者などの立場を代表し、経営の健全性を確保します。目的は、ステークホルダーの権利を尊重し、企業価値を中長期的に高めることにあります。
コーポレートガバナンスの基本的な原則の体系化が「コーポレートガバナンス・コード(Corporate Governance Code)」、通称CGコードです。2015年に金融庁と東京証券取引所が共同で策定し、2018年と2021年に改訂されました。改訂では、経営トップの選任・解任手続きの明確化、多様な人材の登用、政策保有株式の見直し、そして人的資本やサステナビリティに関する情報開示などが強化されています。
ガバナンスモデル
ガバナンスモデルとは、企業や組織がどのような仕組みで経営を監督・統治するかを示す基本的な枠組みのことです。取締役会や監査役会の構成、社外取締役の関与、権限や責任の分担、意思決定の流れなどを含みます。目的は、経営の監視機能と執行機能のバランスを保ち、企業統治の有効性を高めることです。
日本企業では、主に「監査等委員会設置会社」や「指名委員会等設置会社」といったモデルが代表的です。各企業は事業規模や業種、経営課題に応じて適切なガバナンスモデルを選択し、運営の透明性と健全性を確保します。
また、ガバナンスモデルは企業ごとに異なり、経営の目的や体制に合わせて柔軟に設計されます。明確なモデルを構築することが、責任ある意思決定と持続的な成長の基盤です。
データガバナンス
データガバナンスとは、企業が保有するデータを安全かつ効率的に活用するための全社的な管理体制を指します。データの収集・保管・活用・運用といったデータマネジメントの活動に対し、経営の視点から統一された方針やルール、プロセス、体制を整え、監督・評価することで、データの価値を最大化しつつリスクを最小限に抑えます。
近年はDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、部門ごとにデータを扱う機会が増え、誤った運用や不正利用のリスクが高まっています。こうした背景から、データの扱いを全社的に統制し、信頼性と一貫性を確保するデータガバナンスの重要性が高まっています。
プロダクトガバナンス
プロダクトガバナンスとは、商品設計から販売以降の運用・検証に至る全段階で品質管理・モニタリングを行う統治体制のことです。金融機関が顧客に適した金融商品・サービスを提供する責任を果たすことを目的としています。金融機関はプロダクトガバナンス体制を整備し、取締役会が実施状況を監督する役割を担います。
プロダクトガバナンスは、金融庁が推進する「顧客本位の業務運営(日本型フィデューシャリー・デューティー)」の枠組みの一部として扱われており、2023年末に策定された「資産運用立国実現プラン」にも反映されました。その後、市場制度の議論を経て、2024年9月には、補充原則としてプロダクトガバナンスに関する規定が「顧客本位原則」に追加されています。
各社は顧客利益を中心とした商品設計・販売・アフターケアの仕組みを一層明確に構築することが求められています。
グローバル・ガバナンス
グローバル・ガバナンスとは、国境を越えて生じる地球規模の課題に対し、国際社会が連携して解決策を導き出すための意思決定や調整の仕組みを指します。明確な定義は存在しませんが、一般的には「国際的な協力体制を通じて、共通の問題にルールと秩序をもたらす枠組み」と理解されています。
取り組む対象は、貧困や飢餓、感染症、気候変動、人権問題、テロ対策など、単一の国家では解決が難しいグローバルな課題です。こうした問題に対し、国連をはじめとする国際機関や多国間会議(G7・G20など)が協力して方針を定めています。
国際社会全体が「私たち=We」として地球規模の課題に向き合う姿勢こそ、グローバル・ガバナンスの本質といえます。
ガバナンスに関する日本の状況
ガバナンスに関する日本の状況について、分かりやすく解説します。
戦後から続く日本型ガバナンスの特徴
日本企業のガバナンス体制は、英米型の株主中心のモデルとは異なり、戦後長く続いたメインバンク制度や株式の持ち合いといった独自の企業環境の中で形成されてきました。
これらの仕組みは、安定的な経営や長期的な取引関係を支える一方で、外部との対話不足や経営の透明性欠如を招く要因の一つです。そのため、経営に対する説明責任や規律意識は欧米企業と比較して十分とはいえず、ガバナンスの水準が国際的な投資家から厳しく評価されています。
ガバナンス改革の進展と制度的化
日本では、従来の閉鎖的な企業構造を改め、国際基準に沿ったガバナンス体制の確立を目指す動きが本格化しました。会社法の改正や「コーポレートガバナンス・コード」「スチュワードシップ・コード」の策定・改訂により、取締役会の独立性や多様性の向上、社外取締役の積極的な登用、情報開示の充実が進んでいます。
さらに、株式持ち合いの縮小や親子上場の見直しなど、長年続いた経営慣行にも変化が生まれました。これらの改革を通じて、日本企業は投資家との建設的な対話を深め、国際市場で信頼を得ながら競争力を高める基盤を整えつつあります。
ガバナンス評価で注目される企業の動向
近年、企業のガバナンス体制は社会的信頼の指標として注目を集めています。なかでも「日経ESGブランド調査2023」では、トヨタ自動車がコーポレートガバナンス分野で最高評価を獲得しました。法令順守の徹底や経営層の高い倫理観、役員・従業員の社会規範に基づく行動が評価の中心です。また、日本マイクロソフトが2位に躍進し、個人情報保護や情報セキュリティへの取り組みなど、ITガバナンスを重視する姿勢が企業価値向上に直結していることを示しました。
こうした動きは、ガバナンスが「経営の質」を測る重要な指標として位置付けられている現状を象徴しています。
ガバナンスが必要とされる背景
ガバナンスが必要とされる背景には、以下のようなものがあります。
- 不祥事防止と内部統制の必要性
- 経営環境の複雑化とリスクの多様化
- 投資家・社会からの評価基準の変化
それぞれを詳しく解説します。
不祥事防止と内部統制の必要性
2000年代に入ると、日本企業では大規模な粉飾決算が相次ぎ、社会的信頼を大きく損なう事態が続きました。カネボウやライブドア、西武鉄道などの不正会計事件は、経営監督の形骸化や内部けん制の欠如、閉鎖的な企業文化が招いた典型的な例とされています。これらの事件は、「企業内部で適切にリスクを管理・抑制する仕組みが機能していなかった」という共通の問題を浮き彫りにしました。
こうした背景から、政府と金融庁は企業のガバナンス体制を強化するための制度改革を進め、2006年には証券取引法を改正して「金融商品取引法(いわゆる日本版SOX法)」を導入しました。これにより、上場企業は経営者自らが内部統制の有効性を評価し、その結果を報告する義務を負うようになりました。これが現在の内部統制報告制度の基盤といわれています。この改革を契機に、取締役会や監査機能の独立性を確保し、経営判断や財務報告の透明性を高める動きが広がりました。
経営環境の複雑化とリスクの多様化
グローバル化とデジタル化の急速な進展により、企業を取り巻く経営環境はかつてないほど複雑化していることもガバナンスが必要とされる背景の一つです。地政学的緊張によるサプライチェーンの寸断、頻発するサイバー攻撃、AI・データ利活用に伴う法的リスク、気候変動や自然災害への対応など、企業は多面的かつ相互に連動するリスクに直面しています。
こうした不確実性の高い状況では、単なる危機対応にとどまらず、リスクを経営資源として把握し、組織全体で統制・判断する体制が欠かせません。ガバナンスは、経営層が情報を的確に共有し、迅速かつ説明責任を伴う意思決定を行うための基盤であり、企業が持続的に成長するための羅針盤として機能します。
投資家・社会からの評価基準の変化
現在、企業は株主だけでなく、従業員・顧客・取引先・地域社会など、多様なステークホルダーに対して説明責任を負う立場にあります。特にESG投資やサステナビリティ経営が広まりを見せる中では、環境・社会・統治(ガバナンス)のうち「G」が企業価値を支える支柱として近年注目されています。
信頼を獲得するためには、単に情報を開示するだけでなく、開示内容が正確で整合性があり、かつ容易に理解できるものであることが不可欠です。加えて、取締役会の独立性や社外取締役の監督力が担保されている企業は、経営判断の偏りを抑え、外部からの目線を取り入れやすいです。
ガバナンス体制を整えた企業は、投資家からの評価で信用を得やすくなり、結果として資金調達コストが下がったり、支持株主層の拡大を得たりする可能性も高まります。
ガバナンスを整備する目的・メリット
ガバナンスを整備する目的やメリットには、以下のようなものがあります。
- 信頼性と企業価値の向上
- 経営判断の質とスピードの向上
- 組織文化と従業員エンゲージメントの向上
それぞれを詳しく解説します。
信頼性と企業価値の向上
整ったガバナンス体制は、経営の透明性と説明責任を高め、企業と社会との間に強固な信頼関係を築くための基盤です。
株主や取引先、顧客、従業員など多様なステークホルダーが安心して関われる環境を整えることで、企業のブランド価値は着実に向上します。さらに、透明性の高い統治体制は、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価やサステナビリティ格付けの向上にも直結し、国内外の投資家から「信頼できる企業」として認識される契機になります。
ガバナンスを強化することは、不祥事を防ぐ「守り」の仕組みであると同時に、信頼そのものを経営資本として生かす「攻めの戦略」であるといえます。信頼資本が長期的な企業価値の持続と市場での競争力向上を支え、結果的に経営の安定性と社会的評価の双方を高めることにつながります。
経営判断の質とスピードの向上
ガバナンス体制を整えることは、単にルールを定めるだけでなく、経営判断の「質」と「スピード」の両立を実現する仕組みづくりでもあります。経営執行と監督の役割が明確になることで、意思決定の責任範囲が可視化され、取締役会による監督の実効性が高まります。これにより、経営陣は感覚的な判断ではなく、データやリスク分析に基づいた合理的な意思決定が可能です。
また、社外取締役の参加や独立した委員会の設置によって、外部の視点から経営方針をチェックできる体制が強化されます。多様な知見が加わることで、経営判断に偏りが生じにくくなり、意思決定のスピードも上がります。さらに、組織全体で情報共有とリスク報告の仕組みを整えることにより、変化の激しい経営環境でも迅速に対応できる「戦略的ガバナンス」が実現します。
明確な統治体制は、企業が変化に適応し続けるための柔軟性と実行力を支える中枢的な仕組みといえるでしょう。
組織文化と従業員エンゲージメントの向上
健全なガバナンスは、企業文化の健全化や従業員のエンゲージメント向上に大きく寄与する点もメリットです。透明性と公正性を備えた評価制度、権限と責任の明確な分担は、従業員の心理的安全性を高め、安心して意見を発信できる職場風土を醸成します。そのため、従業員が自らの役割を理解し、組織の目的に主体的に関わる姿勢が育ちます。
さらに、経営層が誠実かつ説明責任を果たす姿勢を示すことで、従業員の信頼が高まり、現場の声が経営判断に反映されやすくなります。これにより、組織全体に双方向のコミュニケーションと学習の循環が生まれ、企業の創造性や持続的成長を支える基盤が形成されます。
ガバナンスは単なる統制の枠組みではなく、「人と組織を強くする経営基盤」として、組織文化の質を高める重要な役割を担っています。
ガバナンスを強化する方法
ガバナンスを強化する方法は、次のものがあります。
- 社内ルールを整備する
- 倫理意識とコンプライアンスを浸透させる
- リスクマネジメントを徹底する
- 内部統制と外部監督の仕組みを強化する
それぞれを詳しく解説します。
社内ルールを整備する
ガバナンス強化の出発点は、法令順守と不正防止を目的とした社内ルールの体系化です。まず、自社の業務プロセスを可視化し、部門横断的に課題や潜在的リスクを洗い出すことから始めましょう。その上で、行動規範・倫理方針・取引先とのコンプライアンス基準などを明文化し、就業規則や社内規程として整理します。これにより、社員一人ひとりが取るべき行動の基準を明確に理解できます。
さらに、ルールは策定して終わりではなく、実際の運用状況をモニタリングし、問題があれば速やかに見直す仕組みを設けることが大切です。経営層が率先して順守姿勢を示すことで、全社的なコンプライアンス意識が定着し、組織としての信頼性が高まります。
倫理意識を浸透させる
健全なガバナンスは、法令順守だけでなく、社員一人ひとりの倫理観と誠実な行動に支えられています。そのためには、企業理念を土台とした「行動規範」や「倫理憲章」を策定し、全社員が共有できる価値観として定着させることが欠かせません。これらの理念は文書化するだけでなく、研修・eラーニング・社内報などを通じて継続的な教育が効果的です。
また、株主や取引先、地域社会などのステークホルダーにも、企業としての倫理的姿勢やルールの背景を丁寧に説明することが重要です。透明性を高めることで、外部からの信頼が強化されるだけでなく、社員自身の責任意識も向上します。
リスクマネジメントを徹底する
リスクマネジメントは、ガバナンスの中核をなす仕組みです。企業経営には、法令違反・不正会計・自然災害・サイバー攻撃・サプライチェーン断絶など、さまざまなリスクが存在します。これらを放置すれば、財務的損失だけでなく企業の信頼そのものを失いかねません。
まず、経営に影響を及ぼすリスクを特定し、その性質に応じて「回避」「低減」「移転」「保有」の四つの方法で対応策を設けます。加えて、リスクの重要度に応じた優先順位を定め、社内の担当部署や責任者を明確にすることで、発生時の迅速な対応が可能です。
さらに、リスク対策は一度作って終わりではなく、定期的な内部監査や外部評価を通じて継続的な改善が不可欠です。全社的リスクマネジメント(ERM)の視点を取り入れ、経営層から現場まで情報を共有する体制を築くことで、不正や不祥事の未然防止だけでなく、危機発生時にも機動的な判断ができる強い組織を実現します。
内部統制と外部監督の仕組みを強化する
企業のガバナンスを実効性のあるものにするためには、内部統制の確立と外部による監督体制の強化が欠かせません。まず、社外取締役や社外監査役を登用し、経営の監督機能と執行機能を明確に分離することで、意思決定の独立性と客観性を確保します。経営陣の判断が特定の利害に偏らないようにするためには、外部の視点を持つ人材の存在が不可欠です。
また、「指名委員会等設置会社」や「監査等委員会設置会社」といった組織形態へ移行し、役員指名・報酬・監査の各プロセスに第三者が関与する仕組みを導入することで、経営責任や権限の所在がより明確になります。さらに、外部監査法人や独立した監査委員会による定期的な評価を受けることで、経営の健全性を客観的に検証できます。
こうした仕組みを継続的に機能させることで、社内外の信頼を高め、ガバナンスの持続的な改善につなげられます。
ガバナンスを強化する際の注意点・デメリット
ガバナンスを強化する際の注意点・デメリットは、次のとおりです。
- コストと運用負担の増大
- 人材・組織文化への影響
- グローバル展開時の統一性確保
それぞれを詳しく解説します。
コストと運用負担の増大
ガバナンス体制を構築・維持するには、制度設計や内部統制、リスクマネジメント、情報開示、社員教育など多面的な取り組みが求められます。
そのため、初期段階では人件費・外部専門家への委託費・システム導入費などのコストが発生し、特に中堅・中小企業では経営負担となる場合があります。さらに、社外取締役の選任や監査委員会の設置、定期的な内部監査の実施など継続的な運用コストも無視できません。
ガバナンスは「整備すること」自体が目的ではなく、組織の特性・規模・事業リスクに即した最適なバランス設計が重要です。短期的にはコスト増につながるとしても、長期的に見れば信頼性・資金調達力・企業価値向上といったリターンをもたらす「投資」として位置付ける視点が求められます。
人材・組織文化への影響
ガバナンス強化は、企業の透明性や公正性を高める一方で、組織文化に副作用を及ぼす可能性がある点がデメリットです。ルールや監視体制が強調されすぎると、社員が「ミスを恐れる」ようになり、挑戦や創意工夫を避ける傾向が生まれることがあります。特に、形式的な監査やチェックリスト中心の運用が続くと、現場の意見が軽視され、モチベーションの低下や離職につながる恐れもあります。
また、社外取締役や外部監査の関与が増えることで、経営層と現場の距離が広がり、意思疎通が難しくなるケースも見られます。こうした弊害を防ぐためには、「監視のためのガバナンス」ではなく「信頼を育てるガバナンス」を目指すことが大切です。経営層が率先して倫理的判断を示し、社員が安心して意見を発信できる環境を整えましょう。
グローバル展開時の統一性確保
海外に複数拠点を持つ企業では、各国で異なる法制度・商習慣・文化に対応しながら、一貫したガバナンスを維持することが大きな課題です。日本本社のルールをそのまま適用すると、現地法令との不整合や文化的摩擦が生じる可能性があります。逆に、現地任せにしすぎると統制が緩み、企業グループ全体の方針が不明確になる恐れもあります。
そのため、グローバル企業では「共通の原則」と「地域の自律性」を両立させる仕組みづくりが不可欠です。例えば、グループ全体で共有する行動規範・倫理基準・内部統制方針を設けた上で、各国拠点に権限を委譲し、現地特性に合わせた運用が理想的です。さらに、全拠点のデータを統合的に管理するデジタル基盤(ERPなど)の導入も有効でしょう。
国内企業の実例
日本の有名企業でのガバナンスの例をご紹介します。
ユニ・チャーム
ユニ・チャームは、「社会から信頼される経営」を企業理念の中心に据え、ガバナンス体制の強化を通じて持続的な成長を目指しています。
取締役会は、中長期的な経営戦略の方向性を示すとともに、社内外の多様な視点を取り入れた助言や監督を行い、透明で公正な意思決定を支えています。社外取締役には戦略・国際経営などの分野に精通した人材を登用し、専門性と客観性を両立している点も特徴です。さらに、監査等委員会設置会社として、取締役会における監査・助言機能を強化しています。
加えて、任意の指名委員会・報酬委員会を設け、社外取締役が委員長を務める体制を採用しています。これにより、経営陣の選任や報酬決定の透明性・公正性を担保し、ステークホルダーとの信頼関係を深めています。
パナソニックホールディングス株式会社
パナソニックホールディングス株式会社は、「企業は社会の公器である」という理念の下、説明責任と透明性を重視した経営を実践しています。
同社は、取締役会がグループ全体の重要戦略や業務執行を決定し、監査役・監査役会が取締役の職務執行を監督する「監査役制度」を採用しています。これにより、経営監督の独立性と実効性を確保しています。また、カンパニー制を導入し、各事業部が迅速に意思決定できる体制を整備している点も特徴です。株主の権利尊重、情報開示の徹底、リスクテイクを支える仕組みなどを通じて、健全なコーポレート・ガバナンスを推進しています。
さらに、グループ全体のオペレーション効率化と高度化を目的として「パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社」を設立しました。全社共通の制度・基盤整備を進めるとともに、内部監査・内部統制・コンプライアンス機能を強化し、ステークホルダーへの責任ある対応を推進しています。
キリンホールディングス
キリンホールディングスは、「食と健康を通じて豊かな社会をつくる」という理念の下、持続的な成長を実現するためのガバナンス体制を整えています。グループ全体で共有する価値観「One KIRIN Values(情熱・誠実・多様性)」を軸に、目指しているのは、長期ビジョン「キリングループ・ビジョン2027(KV2027)」で掲げる「食から医まで幅広い分野で価値を生み出すCSV先進企業」です。
同社は、顧客や株主・投資家、従業員、地域社会、取引先、地球環境といったステークホルダーを重要なパートナーと位置付け、対話と協働を通じて新しい価値の共創に取り組んでいます。情報開示においても透明性と公平性を重視し、投資家との建設的なコミュニケーションを積極的に推進しています。
さらに、資本政策の健全性を保つために、政策保有株式は原則として持たない方針を採用している点も特徴です。保有銘柄については取締役会で定期的に見直しを行い、企業価値向上につながらない場合は売却を進めています。このように、説明責任と透明性を重視した経営姿勢が、キリンの信頼性とガバナンスの強さを支えています。
ガバナンスに関するQ&A
最後に、ガバナンスに関するよくある質問とその回答を紹介します。
スタートアップや中小企業にガバナンスは必要か
スタートアップや中小企業においても、ガバナンスは必要です。ガバナンスは大企業だけのものではなく、「経営を安定化させるための基本構造」といえます。
スタートアップでは意思決定のスピードが重視されますが、創業者中心の判断が続くと不正や資金使途の不透明さが生じるリスクがあります。簡易的な取締役会や外部アドバイザーによるレビュー制度を導入するだけでも、客観性と透明性を確保できるでしょう。
中小企業でも、承認フローの明確化や会計のダブルチェック体制を整えることで、経営リスクを抑え、取引先や投資家からの信頼を得やすくなります。
経営者自身がガバナンスを軽視するとどうなるか
経営者がガバナンスを軽視すると、経営の透明性や説明責任が失われ、結果として企業価値を大きく損なうリスクが生じます。
ガバナンス不在の企業では、意思決定が属人的になり、不正会計や情報隠蔽(いんぺい)、ハラスメント、利益相反などが発生しやすい点が大きなデメリットです。これらは一度発覚すれば、従業員や取引先、顧客、投資家などステークホルダー全体の信頼を一気に失います。
さらに、SNSやニュースメディアを通じた情報拡散スピードが速い現代では、企業の評判がわずか数時間で失墜することもあります。健全なガバナンスは「外からの監視」ではなく、「経営を守る仕組み」です。
社外取締役はどのように選ぶべきか
社外取締役を選任する際は、独立性・専門性・多様性の3点を軸に検討しましょう。
まず、経営陣や主要株主、主要取引先と利害関係のない「独立した立場」であることが前提です。独立性が確保されていないと、経営監督機能が形骸化し、実効性のあるガバナンスが成立しません。次に、財務や法務、人事、IT、サステナビリティなど、自社が弱い分野を補える専門的知見を持つ人物を選ぶことで、取締役会の議論の深度が高まります。
さらに、異業種出身者や女性、海外経験者など、多様なバックグラウンドを持つ人材を登用すれば、経営課題に対する視点が広がり、リスクへの洞察も向上します。
重要な点は「名誉職として置く」のではなく、「企業の未来を共に考えるパートナー」としての姿勢で迎えることです。
家族経営企業におけるガバナンスの課題は何か
家族経営企業では、経営と所有の一体化による意思決定の属人化が最も大きな課題です。
親族中心で経営が行われる場合、感情的な判断や縁故的な人事が優先され、組織運営の客観性・透明性が損なわれる恐れがあります。これにより、従業員の士気低下や外部からの信頼失墜につながるケースも少なくありません。
対策としては、社外取締役や外部監査人、顧問税理士など第三者の視点を経営判断に取り入れる仕組みを整備することです。また、後継者の選定基準や承継手続きを文書化し、ガバナンスの「見える化」を図ることで、世代交代時の混乱を防げます。
さらに、経営方針の共有や家族会議のルール化などを通じて、親族間の情報の非対称性を減らすことも重要です。家族経営の強みである結束力を生かしつつ、透明性と客観性を両立させることが、持続的な発展の鍵といえます。
まとめ
ガバナンスは、企業や組織が健全に運営されるために欠かせない仕組みです。法令順守や不正防止といった基本的な役割から、迅速で透明性のある意思決定を支える枠組みとして、現代の経営においてますます重要視されています。ガバナンスの強化には、社内ルールの整備や倫理意識の浸透、リスクマネジメントの徹底が求められますが、コストや運用負担が増えるという側面もあります。これからガバナンスを見直したいと考えている方は、まず自社の現状を把握し、必要な改善策を具体的に検討することが大切です。始めは小さなステップからでも、しっかりとしたガバナンス体制を構築することが、長期的な企業価値の向上につながります。ぜひ、この機会にガバナンスの見直しを始めてみてください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。