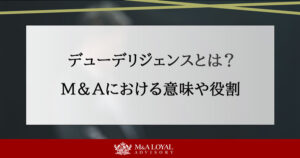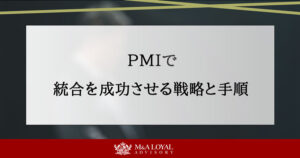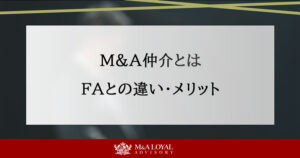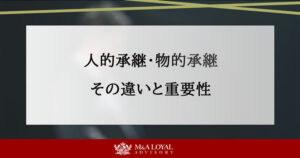「実査」の意味とは?目的や流れ、注意点、監査・往査との違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
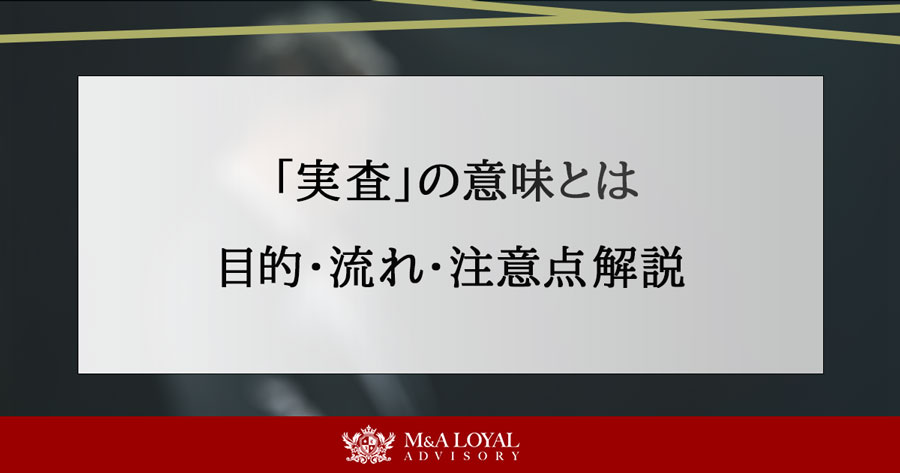
近年、監査対応や内部統制の重要性が高まる中で、「実査って具体的に何をするの?」「どう準備すればいいの?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
現場での対応を間違えると、信頼を損ねたり、指摘事項が残ってしまうリスクもあります。
本記事では、実査の基本的な意味や目的、監査や往査との違い、さらに現場で注意すべきポイントやトラブル時の対処法まで、実査に関する疑問や不安を解消できるよう丁寧に解説します。
目次
実査とは
まず、実査の意味や語源について解説します。
実査の意味
「実査(じっさ)」とは、実物を調べる、実際に検査する、という意味です。「実物調査」または「実地調査」の略で、会計・監査用語として主に使用され、監査法人や公認会計士が、財務諸表が適正であるか実際に確かめることを指します。
帳簿の記載とおりに現金があるかなど、実際に現場や対象物を「目で見て、手で触れて」確かめる調査方法を指します。
実査の語源・初出
「実査」という用語の語源や初出は、明確な情報がなく不明です。 しかし、日本における会計用語の多くは、明治時代以降に欧米の会計制度が導入される過程で翻訳・創出されたものであり、「実査」もその一環として生まれたと考えられます。
明治初期に翻訳された『帳合之法』や『銀行簿記精法』などの文献では、西洋の簿記・会計用語が日本語に翻訳され、広く普及していきました。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



実査と似た言葉の違い
実査と似た言葉は次のとおりです。
- 監査
- 往査
- デューデリジェンス
- 立会
- テストカウント
それぞれの意味と使い方を分かりやすく解説します。
実査と監査の違い
「監査」は、組織の業務や財務情報の適正性を総合的に検証する制度であり、実査はその中の一手法にあたります。監査とは、企業や組織の会計処理や業務運営が適正に行われているかを、第三者の立場から確認する仕組みです。
公認会計士による「外部監査(法定監査)」のほか、企業が自ら実施する「内部監査」も含まれます。
監査では、書類の内容を精査するだけでなく、必要に応じて現場に赴き、実物や状況を直接確認する「実査」が実施されることもあります。 つまり、実査は監査における重要な検証手段のひとつであり、帳簿の数字と実際の在庫や設備などの実態が一致しているかどうかを確認する役割を担っています。
実査と往査の違い
実査と「往査(おうさ)」は、いずれも監査において現場で行われる手続きに関係しますが、その意味や役割は異なります。
「往査」とは、監査人が企業や組織の現地に赴いて、直接監査を実施すること自体を指す用語です。これは、帳簿や書類だけを基に行う「机上監査」とは異なり、現場でのヒアリングや環境確認などを通じて、より実態に即した情報を得る監査スタイルです。
つまり、往査は「現地に行って監査すること」全体を表す言葉であり、実査はその中で行われる「現物確認の手続き」です。往査の一部として実査が組み込まれることはあります。
実査とデューデリジェンスの違い
「デューデリジェンス」とは、企業買収や出資などの意思決定を行う際に、対象企業の財務・法務・人事などの実態を多角的に調査・分析するプロセスを指します。専門家が書類の精査や経営陣へのヒアリングを通じて、潜在的なリスクや課題を洗い出すことが主な目的です。
さらに、設備の老朽化や在庫の水増しなど、書類では把握しにくい実態が疑われる場合には、現地を訪問して実物の状況を確認する「実査」も行われることもあります。つまり、デューデリジェンスは意思決定のための包括的な調査プロセスであり、実査はその一部として実地で情報を補完する具体的手続きという位置付けです。
実査と立会の違い
「立会」とは、棚卸や資産確認などの場面で、調査者(監査人や内部監査担当者など)が現地に同席し、企業側の担当者が行う作業の手順や結果を観察・検証する行為を指します。
この場合、あくまで実務の執行者は企業側であり、調査者は手続きが適切に実施されているかどうかを外部の立場から検証します。
一方、実査とは、調査者自身が棚卸資産や現金などを自ら数えたり、目視・接触によって資産の実在を確認する手続きです。
つまり、立会は企業の実務を見ることに重点を置くのに対し、実査は自ら確かめる行為であり、関与の深さや主体性に違いがあります。
実査とテストカウントの違い
「テストカウント」とは、実地棚卸の際に会計士や経理部門の担当者が倉庫などを巡回し、在庫品をカウントして、棚卸作業の正確性を検証する監査手続きです。
調査者自身が在庫を数える場合もあれば、現場担当者に特定の品目を再カウントさせ、その結果を帳簿や棚卸記録と照合するケースもあります。
企業によっては、テストカウントを実査と扱う場合もありますが、厳密には役割が異なります。実査は資産の実在性を確認するための手続きであるのに対し、テストカウントは棚卸作業の信頼性を評価するための監査手続きです。
なお、テストカウントという用語は主に在庫棚卸に対して用いられ、現金や有価証券など在庫以外の資産に対しては使用されません。
実査の実行者と行われる主な場面
実査が行われる代表的な場面は、次のとおりです。
- 外部監査(法定監査)
- 内部監査
- M&Aにおけるデューデリジェンス(買収監査)
- 補助金・助成金の実績確認
- 税務調査
それぞれを分かりやすく解説します。
外部監査(法定監査)
外部監査では、公認会計士や監査法人が、企業の財務諸表の適正性を検証する目的で実査を行います。
特に棚卸資産や現金、有価証券などの資産について、現物を確認し、帳簿と一致しているかを調べることで、企業が公表する財務情報の信頼性を第三者の立場から評価します。
外部監査の対象となるのは、上場企業および「大会社」に該当する非上場企業(資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の株式会社)です。
これらの企業には監査法人による会計監査の実施が義務づけられています。その中で行われる実査は、法定監査の重要な一環として位置づけられています。
内部監査
内部監査では、企業内の監査部門や経理・管理部門が、自社の資産管理や内部統制の運用状況を定期的に検証します。その一環として実査を実施し、棚卸資産や固定資産などの実在性を確認するだけでなく、保管状況や管理ルールが適切に守られているかを現場で確認します。
内部監査は企業自身の意思と管理体制に基づいて実施されるもので、主に不正や誤りの早期発見、業務の改善、リスク管理の強化を目的としている点が外部監査との違いです。
特に上場企業では、内部統制報告制度(J-SOX)への対応の一環として、実査の重要性が年々高まっています。
M&Aにおけるデューデリジェンス(買収監査)
M&Aにおけるデューデリジェンスでは、買収を検討する企業やその財務・法務アドバイザー(公認会計士や税理士、M&Aコンサルタントなど)が、対象会社の資産や業務の実態を確認するために実査を実施します。
監査対象は、棚卸資産や設備、帳簿などです。 開示された財務情報の信頼性を見極め、買収価格の妥当性や契約条件の交渉材料とするために実査を行う必要があります。
また、実査を通じて、潜在的な不正や経営リスク、管理上の不備を発見し、買収後のトラブル回避や統合計画(PMI)にも役立てます。
補助金・助成金の実績確認
補助金や助成金の交付後には、行政機関や第三者調査機関が、交付先の企業・団体に対して補助対象の設備や事業が適切に実施されたかを確認する目的で実査を行います。
例えば、雇用調整助成金などの制度では、労働局が実査を行い、実際に雇用が維持されているか、支給申請内容と労務管理の実態が一致しているかなどを確認します。
他にも、設備導入を伴う補助金では、購入した機器が報告通りに設置・稼働しているかなどの現場確認が行われます。こうした実査は、不正受給や目的外使用を防ぐための重要な手段です。
税務調査
税務調査の一環として実査が行われることも珍しいことではありません。
税務調査では、国税局や税務署の調査官が企業を訪れ、帳簿や申告内容の正当性を精査します。その際、書類上では確認できない資産の実在や状態について、現地で直接確認するケースが多いです。
実査の結果、申告内容に食い違いがあると判断されれば、追徴課税や修正申告を求められる可能性があります。
実査の意義・目的
実査の目的は、次のとおりです。
- 帳簿と現物の整合性を確認する
- 不正や誤りを早期に発見する
- 現場の実態を把握し、改善につなげる
- 内部統制の有効性を検証する
- 経営判断の根拠を得る
それぞれを詳しく解説します。
帳簿と現物の整合性を確認する
実査の最も基本的な目的は、帳簿に記載された内容と現物の状況が一致しているかを確認することです。例えば、在庫や設備、現金などが帳簿どおりの数量・状態と合致しているかを、現地で目視や実地検証によって確かめます。
帳簿に記録があっても、実際に現物が紛失・劣化・使用不能の状態にある場合、その資産価値は適正でない可能性があります。こうしたギャップを把握することで、財務データの信頼性を担保し、資産管理の正確性や内部統制の健全性を高められます。
不正や誤りを早期に発見する
実査は、帳簿と実態の不一致を通じて、不正や誤記などの異常を早期に発見するための有効な手段でもあります。例えば、在庫の過大計上や帳簿にない資産の存在、現金の使途不明などは、書類の確認だけでは見抜けず、実地での検証によって初めて明らかになるケースも少なくありません。
こうした異常は、会計不正や内部統制の不備につながる可能性があるため、実査によってその兆候を察知し、原因の究明と早期対応を行うことが重要です。
実査は、単なる確認作業にとどまらず、企業のガバナンス強化やリスク管理の一環としても機能する重要な手続きといえるでしょう。
現場の実態を把握し、改善につなげる
実査は単なる確認作業にとどまらず、現場の運用実態を観察し、課題や改善点を発見する貴重な機会でもあります。例えば、在庫管理の非効率や設備配置の無駄、従業員の対応状況などは、現地を訪れることで正確に把握できる情報です。
こうした現場視点での気づきを積み重ねることで、業務プロセスの見直しや効率化のヒントが得られ、組織全体の運営レベルの向上にもつながります。
内部統制の有効性を検証する
実査は、企業が定めた管理ルールや業務プロセスが実際の現場で適切に運用されているかを確認する手段でもあります。
例えば、在庫管理マニュアルが形式的に存在していても、現場では棚卸が形骸化していたり、現金管理が担当者任せになっているような場合、内部統制は実質的に機能していないと判断されます。
実査では、マニュアルの実際の運用状況や、従業員の対応・説明内容を通じて、内部統制が現場でどの程度有効に機能しているかを実地で評価できます。
経営判断の根拠を得る
実査によって得られる確認結果は、経営層が意思決定を行う際の重要な判断材料です。帳簿上の数字だけでは判断できない現場の実態を把握することで、資産評価やリスク評価、契約条件の見直しなどにおいて、客観的な根拠を補強できます。
特に、M&Aや投資、企業再編といった重要な局面では、書面情報に依存するだけでなく、現物や現場の実態に基づいた判断を行うことが、取引の信頼性や成功率の向上に直結します。
実査の対象となるもの
実査の対象となるものは、次のとおりです。
- 棚卸資産
- 現金・預金
- 有形固定資産
- 不動産
- 人的資源
- 工場・現場・店舗などの物理的環境
- 船荷証券、倉荷証券
- 予備株券
- 絵画・貴金属等
- ゴルフ会員権等の預託会員券
それぞれを分かりやすく解説します。
棚卸資産
棚卸資産は、実査において最も基本かつ重要な確認対象のひとつです。商品や製品、原材料などの資産が実際に存在しているかを確認することで、帳簿と現場の情報が一致しているかどうかを検証します。
監査人や調査担当者が倉庫や保管場所を訪問し、在庫の数量・品目・品質・保管状況を目視で確認し、帳簿の記録と照合します。この手続きにより、在庫の過大計上や滞留、不良在庫の有無が明らかとなり、資産の過少・過大評価といったリスクの低減につながります。
また、実査を通じて在庫管理体制の運用実態が把握できるため、財務情報の信頼性を確保する上でも欠かせないプロセスといえるでしょう。
現金・預金
現金や預金は不正リスクが高いため、実査の中でも特に慎重に確認される対象です。現金については、監査人が帳簿や出納帳の記録と照合します。
預金については通帳や銀行の取引明細と突き合わせ、資金の出入りが正確に記録されているかを確認します。現金の不一致や使途不明金が判明した場合、内部統制上の重大な問題となるため、こうした実地での確認は企業の健全性を評価する上で極めて重要です。
実査によって資金管理の実態が明らかとなり、財務報告の信頼性向上にも大きく貢献します。
有形固定資産
有形固定資産とは、建物や機械設備、車両、備品などの物理的な形を持つ長期保有資産のことを指します。実査では、これらの資産が帳簿に記載されたとおりに実在し、適切に使用・保管されているかを確認します。
例えば、資産の稼働状況や老朽化の程度、修繕履歴などを現地で把握し、資産としての価値が維持されているかどうかを検証します。併せて、未使用や遊休状態にある資産が帳簿に計上されたままになっていないかも確認対象です。
こうした実査により、資産評価の正確性や減価償却の妥当性を確認し、財務情報との整合性を確保可能です。
不動産
不動産は、企業資産の中でも高額なため、実査による確認が重要です。実査では、登記情報や契約書に記載された内容と、実際の物件の所在地や使用状況、管理状態が一致しているかを現地で確認します。
敷地の境界や建物の老朽化、未登記の増改築など、帳簿には反映されにくいリスク要因の有無も確認対象です。 特にM&Aの場面では、不動産の利用実態や、将来的な収益性・保守コストなどを含めた総合的な判断材料となるため、実査は不可欠なステップといえます。
人的資源
実査では、物的資産だけでなく「人」に関する実態の確認も重要視されます。経営者や従業員と接することで、組織の雰囲気や業務の習熟度、説明の信頼性などを直接確認できます。
特にM&Aや統合を控えた企業においては、従業員の定着率や社内文化、マネジメント体制の実態が今後の組織運営に大きく影響します。ヒアリングや現場での観察を通じて、社内の連携状況や問題意識の有無といった、帳簿には現れない定性的な情報も把握できます。
人的資源の状態は、企業の強みや潜在的リスクを浮き彫りにする重要な情報源であり、実査において見過ごせない観点といえるでしょう。
工場・現場・店舗などの物理的環境
実査では、作業現場や店舗などの物理的な環境も確認対象です。 例えば、生産設備の配置や作業動線、衛生・安全管理の実施状況などが主なチェックポイントにあたります。
マニュアルどおりに運用されているか、従業員が安全に作業できる環境が整っているかを実地で確認することで、内部統制や業務効率の水準を把握可能です。
また、現場の清潔感や整理整頓の状況からは、企業の管理意識や統制の文化も垣間見えます。こうした現地での観察は、業務の健全性や改善の余地を見極める上で有効な手段といえるでしょう。
船荷証券、倉荷証券
船荷証券(B/L)および倉荷証券は、貨物に準ずる権利を表す有価証券であり、実査においては特に慎重な確認が求められます。
主な確認事項は、現物の有無や券面記載情報(管理番号・発行日・名義人など)と帳簿との整合性、さらに保管状態などが挙げられます。
これらの証券は、改ざんや二重譲渡といったリスクを伴うため、実査では貸金庫や耐火金庫など、適切な保管場所に保管されているかどうかかも併せて確認します。
予備株券
予備株券や未発行株券は、発行会社が保有する重要な証券資産です。実査では、まず現物の有無を確認した上で、券面の通し番号や発行予定記録との整合性、名義や数量が帳簿記録と一致しているかを確認します。
また、不正発行や流出リスクを防ぐために、貸金庫や封印付き保管箱など、厳重な保管体制が確保されているかどうかも確認項目です。さらに、入出庫記録や保管担当者の管理状況を検証することで、内部統制が適切に機能しているかどうかを総合的に評価します。
絵画・貴金属等
絵画や貴金属なども実査においては現物確認が求められる対象です。実査では、資産台帳に記載された作家名やサイズ、材質、取得日や取得価格などの情報と、現物とを丁寧に照合します。
併せて、鑑定書や証明書といった付属書類の有無や、保管状態(温度・湿度・防犯措置等)も確認ポイントです。また、役員室や私的なスペースに保管されている場合は、企業所有であることが明確かどうか、個人資産と混同されていないかも確認が必要です。
資産の実在性に加え、管理状況および所有権の帰属が明確であることが重要な観点です。
ゴルフ会員権等の預託会員券
ゴルフ会員権やスポーツクラブなどの預託会員券も実査の対象に含まれます。実査では、現物の有無や保管状況に加え、名義・会員番号・有効期限が帳簿記録と一致しているかどうかを確認します。
また、会員権が譲渡可能か、現在利用中か否かといった利用状況も重要な確認ポイントです。
さらに、市場での流通性がある場合は、帳簿上の評価額が時価と乖離(かいり)していないかを検討し、必要に応じて再評価を行うこともあります。
実査の実施時期
実査の実施時期は、調査の目的や対象資産の性質によって異なります。
会計監査においては、期末日またはその直後に行われることが一般的であり、棚卸資産や現金など、時点の正確性が求められる資産が主な対象です。なお、不正リスクが高い場合や急な確認が必要なケースでは、抜き打ち的に実査が行われることもあります。
いずれにせよ、実査の目的は「実態を正しく把握する」ことにあるため、資産の変動状況や管理体制を踏まえ、最も適切なタイミングで実施することが重要です。
実査の具体的な方法とプロセス
実査の具体的な方法とプロセスは、次のとおりです。
- 目的と対象の明確化
- 現地訪問と現物確認
- 結果の整理と報告書の作成
それぞれを詳しく解説します。
目的と対象の明確化
実査の実施に先立ち、調査の目的と対象範囲を明確に設定することが重要です。具体的には、「何を」「どこで」「なぜ」確認するのかを整理し、棚卸資産・現金・固定資産など、重点的に確認すべき項目を洗い出します。
また、帳簿や過去の監査資料を事前に確認し、現地で注目すべきポイントを把握しておくことが求められます。
現地訪問と現物確認
実査とは、現地に直接赴き、資産や設備といった対象物を実際に確認する作業です。例えば、倉庫を訪れて在庫の数量や種類を目視で確認したり、備品の型番や状態を実物と照合します。
設備の場合は、設置状況や稼働の有無、老朽化や破損の有無までを確認対象とします。現金は、レジや金庫の残高をその場で数え、帳簿や出納帳と照らし合わせて不一致がないかを確認します。
これらの作業は、事前に作成したチェックリストに基づいて進め、項目ごとに記録を残すことが重要です。
結果の整理と報告書の作成
実査の終了後には、収集した情報を整理し、報告書として文書化する工程が必要です。 報告書には、確認項目とその結果、不一致や問題点、今後対応が必要な事項などを体系的に記載します。
文書作成にあたっては、主観的な評価や曖昧な表現を避け、事実に基づいた内容を正確に反映させることが重要です。 また、チェックリストなどの添付資料を活用することで、報告書の説得力と客観性が一層高まります。
この報告書は、社内での意思決定資料としてはもちろん、外部監査やM&A交渉時の重要な参考資料としても利用されます。
実査を受ける際の注意点
実査を受ける際の注意点は、次のとおりです。
- 現物台帳をあらかじめ準備する
- 帳簿と現物の整合性を事前に点検しておく
- 現場の整理整頓と対応者を明確にする
- 記録・資料の準備と説明を一貫する
- 誠実かつ冷静な対応を心がける
それぞれを分かりやすく解説します。
現物台帳をあらかじめ準備する
実査の際、固定資産については、「固定資産台帳」ではなく、現場に存在する資産の一覧である「現物台帳」が確認資料として用いられることが一般的です。
固定資産台帳は会計上の管理資料であるのに対し、現物台帳は実査時に資産の所在や状態を確認するための実務的な記録です。 資産ごとの設置場所や管理番号、状態などを明確に整理しておくことで、実査がスムーズに進みます。
あらかじめこの現物台帳を整備・更新しておくことは、当日の確認作業の効率化と整合性の確保に大きく寄与します。
帳簿と現物の整合性を事前に点検しておく
実査では、帳簿に記載された情報と現場の実物が一致しているかどうかが厳しく確認されます。事前に棚卸資産や設備の有無、数量、状態を確認し、不一致がないかを点検しておきましょう。
例えば、帳簿上では在庫が100個と記録されていても、実際に一致していない場合、その理由を説明する必要があります。 こうしたギャップをあらかじめ把握しておくことで、当日の対応がスムーズになり、調査側との信頼関係を損なうリスクも軽減されます。
現場の整理整頓と対応者を明確にする
実査当日は、調査員が倉庫や事業所を訪れるため、現場の整理整頓が基本です。整っていない状態では、在庫の確認や設備の点検に時間がかかり、非効率な対応を招く恐れがあります。
また、各項目の確認に対応する担当者をあらかじめ明確にしておくことも重要です。調査対象ごとに案内や説明を行う担当者が決まっていれば、調査が円滑に進みます。
記録・資料の準備と説明を一貫する
実査で求められる帳簿や記録類は、当日にすぐ提示できるように整理・準備しておくことが重要です。 対象資産に関する台帳や管理表、手順書などは、整った状態で提示できるようにしておきましょう。
また、複数人が対応する場合には、説明内容に一貫性があることも大切です。 発言に食い違いがあると、調査員に不信感を与え、追加確認を求められる可能性があります。
誠実かつ冷静な対応を心がける
実査の場では、思わぬ指摘や記録との不一致が見つかることもありますが、その際には冷静に事実確認に努める姿勢が重要です。
隠そうとしたり、ごまかしたりする対応は、かえって信頼を損なう結果につながります。問題があった場合は、状況を正直に伝えた上で、その理由や今後の対応方針を明確に説明しましょう。
実査におけるトラブルとその対処法
実査におけるトラブルとその対処法は、次のとおりです。
- 実査対象が不明確で、準備漏れが発生する
- 実査中に資産が移動・使用され、確認できない
- 対応者の引き継ぎが不十分で説明できない
- 実査後の指摘事項が放置され、再指摘を受ける
それぞれを詳しく解説します。
実査対象が不明確で、準備漏れが発生する
実査当日に「何を確認されるのか」が曖昧なままだと、資料の準備が間に合わず、現場が混乱してしまいます。特に複数の資産区分がある場合、対象が明確でないと対応に支障をきたす可能性が高くなります。
こうした事態を防ぐには、実査通知を受けた段階で、対象範囲(棚卸資産、固定資産、現金など)の明細を確認し、不明点があれば早めに調査担当者へ問い合わせることが重要です。
また、文書やメールなど形に残る方法で対象範囲を明確化しておくことで、部内での準備の方向性が統一され、準備漏れの防止にもつながります。
実査中に資産が移動・使用され、確認できない
実査のタイミングで、対象資産が他部署で使用中、外部に貸出中、あるいは修理・点検などで移動しており、現場で確認できないというケースは少なくありません。こうしたトラブルを防ぐには、事前に該当資産の使用スケジュールや移動履歴を確認し、必要に応じて一時使用停止や返却を関係部署に依頼しておくことが有効です。
どうしても現物確認が難しい場合は、写真や保管伝票、移動記録、担当者の証明メモなどを代替資料として準備し、調査員に提示することで、柔軟かつ信頼性のある対応が可能です。
対応者の引き継ぎが不十分で説明できない
実査当日に、担当者が不在だったり、異動・退職により引き継ぎが不十分な場合、資産の管理状況や背景を正しく説明できないという問題が発生します。このような状況では、現場の信頼性が損なわれるだけでなく、再確認や調査のやり直しが必要になるリスクも高まります。
実査前に担当変更があった場合は、過去の記録やメール履歴を確認し、説明可能な代替対応者を事前に設定しておく必要があります。
不明点がある場合は、無理に回答せず「確認の上、後日回答する」といった誠実な姿勢を示すことで、誤解や信頼低下を防ぐことができます。
実査後の指摘事項が放置され、再指摘を受ける
実査で指摘された事項への対応を後回しにした結果、次回の実査や別部門の監査で同じ指摘を再度受けるケースがあります。これは、対応の優先順位が明確でないことや、記録が残っていないことにより、誰が何をするのかが不明確になっている場合に多く見られます。
このような事態を防ぐには、実査後に「対応履歴シート」や「改善計画書」を作成し、対応内容と期限、担当者を明確にした上で関係者間で共有することが必要です。
たとえ小さな指摘であっても、対応状況を記録・可視化しておくことで、再指摘のリスクを減らし、組織としての信頼性も高められます。
実査に関するQ&A
最後に、実査に関するよくある質問とその回答を紹介します。
実査は拒否できるか
原則として、実査は正当な業務行為であるため、拒否することはできません。実査を拒否したり協力を渋ったりすると、監査人や調査担当者からの信頼を損なうだけでなく、内部統制や管理体制に対する疑念を招く可能性もあります。
やむを得ない事情がある場合には、事前に理由を説明し、日程の調整や代替手段の提案を行うことが望ましいです。誠実な対応が、結果として組織全体の信頼性向上につながります。
実査の頻度に決まりはあるか
実査の頻度について、法的に一律の決まりがあるわけではありません。ただし、会計監査(外部監査)の一環として行われる実査(特に棚卸資産や現金の確認)は、通常、年1回の決算期前後に実施されます。
頻度は法律によるルールではなく管理上の方針として定められており、リスクの高い資産や部門ほど実施頻度が高くなる傾向があります。また、不正対応や突発的な確認として、随時実査が行われるケースもあり、柔軟な運用が求められます。
まとめ
実査は、企業や組織の信頼性を確保するための重要なプロセスです。適切な準備と対応が求められ、これにより内部統制の強化や問題の早期発見が可能となります。実査という言葉を聞くと不安に感じるかもしれませんが、この記事で紹介した注意点やトラブル対策を参考に、事前にしっかりと準備を進めましょう。
なお、M&Aや経営課題に関してお悩みの際は、専門的なサポートが必要です。M&Aロイヤルアドバイザリーは、これらの課題に対してプロフェッショナルなアドバイスを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。