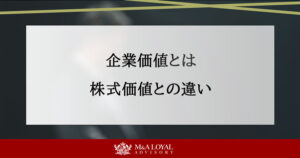割引率の計算方法!M&Aにおけるメリットと効果的な活用テクニック
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
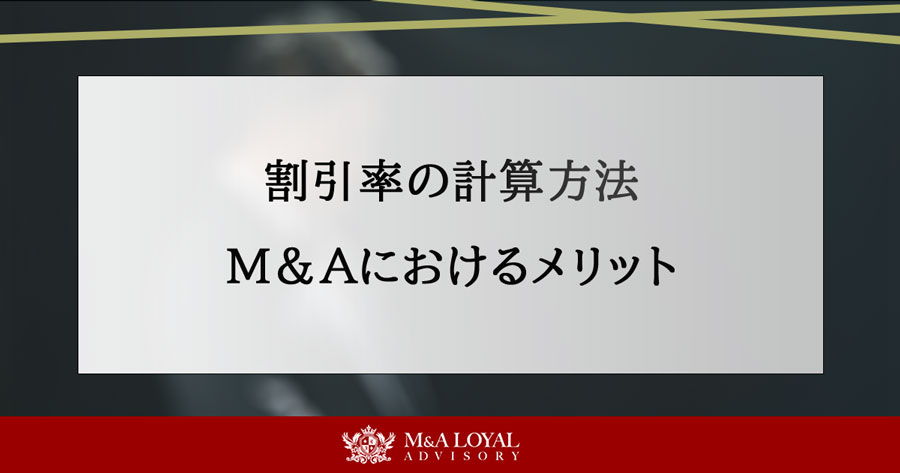
M&Aにおける企業価値評価では、将来のキャッシュフローを現在の価値に換算する「割引現在価値法」が広く活用されています。この計算の核心となるのが「割引率」であり、その設定次第で企業価値は大きく変動します。 割引率は将来の不確実性やリスクを数値化した指標であり、適切に計算することで合理的な買収価格の算定や投資判断が可能になります。 本記事では、M&Aを検討する中小企業経営者に向けて、割引率の計算方法から実務での活用法まで解説します。
目次
割引率とは何か
割引率は将来得られるキャッシュフローを現在の価値に換算する際に用いる利率のことです。M&Aや投資判断において、将来のお金の価値を現在の価値に直すために不可欠な要素となります。
割引率の基本的な概念
割引率とは、将来受け取る金銭の価値を現在の価値に割り引くための指標であり、時間の経過によって生じるお金の価値の変化を数値化したものです。例えば、今日の100万円と1年後の100万円では、インフレや投資機会の喪失などの理由により価値が異なります。割引率が高いほど、将来のお金の現在価値は低くなります。
M&Aにおいては、買収対象企業が将来生み出すキャッシュフローを現在価値に換算し、適正な買収価格を算定する際に割引率が使用されます。この割引率の設定が不適切だと、企業価値を過大評価または過小評価してしまい、M&A後に想定外の損失を被る可能性があります。
時間価値の原則と割引率の関係
お金には「時間価値」があるという原則が割引率の根底にあります。現在の100万円を銀行に預ければ利息が付き、1年後には100万円以上になる可能性があります。逆に言えば、1年後に100万円を得るためには、現在それよりも少ない金額を投資すれば済むということです。
この時間価値を数値化したものが割引率であり、リスクフリーレート(無リスク資産の収益率)にリスクプレミアム(リスクに対する上乗せ分)を加えた構造になっています。国債のような安全性の高い投資の利回りを基準とし、そこに投資対象のリスクに応じた追加リターンを上乗せすることで割引率が決定されます。
割引率が企業価値に与える影響
割引率の設定は企業価値評価に大きな影響を及ぼします。割引率が1%変わるだけで、算定される企業価値は数千万円から数億円単位で変動することがあります。
例えば、毎年1,000万円のキャッシュフローを10年間生み出す企業を評価する場合を考えてみましょう。割引率が5%の場合と10%の場合では、算定される現在価値に大きな差が生じます。割引率が低いほど将来キャッシュフローの現在価値は高くなり、企業価値も高く評価されます。逆に割引率が高いと、同じキャッシュフローでも現在価値は低く算定されます。
| 割引率 | 10年間の現在価値合計 | 企業価値の差 |
|---|---|---|
| 5% | 約7,722万円 | 基準 |
| 10% | 約6,145万円 | ▲1,577万円 |
| 15% | 約5,019万円 | ▲2,703万円 |
この表からも分かるように、割引率の設定は慎重に行う必要があります。売り手側は割引率を低く設定したいと考え、買い手側は高く設定したいと考えるため、M&A交渉においても重要な論点となります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



割引率の主な計算方法
割引率の計算には複数の方法があり、評価対象企業の特性や利用可能なデータに応じて適切な手法を選択する必要があります。ここではM&Aで最も一般的に使用される計算方法を解説します。
WACC(加重平均資本コスト)による計算
WACCは企業が資金調達する際のコストを加重平均したもので、M&Aにおける割引率計算の最もスタンダードな手法です。株主資本コストと負債コストを、それぞれの資本構成比率で加重平均して算出します。
WACCの計算式は以下の通りです。
- WACC = (株主資本コスト × 株主資本比率)+(負債コスト × (1 – 実効税率)× 負債比率)
- 株主資本コストはCAPM(資本資産価格モデル)で算出
- 負債コストは借入金利や社債利回りから算定
- 資本構成比率は時価ベースで計算
例えば、株主資本比率60%で株主資本コスト8%、負債比率40%で負債コスト3%、実効税率30%の企業の場合、WACCは以下のように計算されます。
WACC = (8% × 0.6)+ (3% × (1 – 0.3)× 0.4)= 4.8% + 0.84% = 5.64%
この5.64%が割引率として使用されます。WACCは企業全体の資本コストを表すため、企業全体の価値評価に適していますが、個別事業やプロジェクトの評価には調整が必要です。
CAPM(資本資産価格モデル)による株主資本コストの算出
株主資本コストはCAPMを用いて計算するのが一般的です。CAPMは、リスクフリーレートに株式市場全体のリスクプレミアムとベータ値を乗じたものを加算して算出します。
計算式は以下の通りです。
- 株主資本コスト = リスクフリーレート + ベータ値 ×(市場リターン – リスクフリーレート)
- リスクフリーレートは長期国債利回りを使用(日本では0.5%程度)
- ベータ値は株価の市場全体に対する感応度(上場企業の場合は実績値、非上場企業は類似企業のベータ値を使用)
- 市場リターンは過去の株式市場平均リターン(日本では5~7%程度)
中小企業のM&Aでは、評価対象企業が非上場であることが多く、ベータ値の算定が困難なため、類似業種の上場企業のベータ値を参考にする方法が実務的です。ただし、企業規模や財務レバレッジの違いを調整する必要があります。
ビルドアップ法による割引率の設定
ビルドアップ法は、リスクフリーレートに各種リスクプレミアムを積み上げて割引率を算出する方法です。特に非上場の中小企業のM&Aでは、市場データが限られるため、この方法が有効です。
基本的な構成要素は以下の通りです。
- リスクフリーレート(長期国債利回り)
- 株式リスクプレミアム(株式投資一般のリスク)
- 規模プレミアム(中小企業特有のリスク)
- 個別企業リスクプレミアム(経営者依存度、顧客集中度など)
例えば、リスクフリーレート0.5%、株式リスクプレミアム5%、規模プレミアム3%、個別企業リスクプレミアム2%とすると、割引率は10.5%となります。この方法の利点は、評価対象企業の個別リスクを定量的に反映できる点ですが、各プレミアムの設定には評価者の主観が入りやすい点に注意が必要です。
割引率を用いた企業価値評価の簡単な実践
割引率を計算した後は、それを用いて実際に企業価値を算定します。M&Aで最も使用されるDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)を中心に、実践的な評価プロセスを解説します。
DCF法による企業価値算定の手順
DCF法は、将来のフリーキャッシュフローを予測し、それを割引率で現在価値に換算して企業価値を算定する方法で、M&Aにおいて理論的な評価手法として広く用いられています。まず3~5年程度の事業計画を基にフリーキャッシュフローを予測します。
フリーキャッシュフローは以下の式で計算されます。
- フリーキャッシュフロー = 営業利益 ×(1 – 実効税率)+ 減価償却費 – 設備投資 – 運転資本増加額
- 各年度のフリーキャッシュフローを予測
- 予測期間終了後の継続価値(ターミナルバリュー)も算定
次に、予測した各年度のフリーキャッシュフローを割引率で現在価値に換算します。第n年度のキャッシュフローの現在価値は、「第n年度のフリーキャッシュフロー ÷(1 + 割引率)のn乗」で計算されます。すべての年度の現在価値を合計し、さらに継続価値の現在価値を加えることで企業価値が算定されます。
継続価値(ターミナルバリュー)の計算式
DCF法では、詳細に予測できる期間(通常3~5年)の後も企業は存続し続けると考え、その後の価値を継続価値として一括で計算します。継続価値の算定方法には主に2つあります。
1つ目は永久成長率モデルです。予測最終年度のフリーキャッシュフローが永続的に一定の成長率で成長すると仮定し、「最終年度フリーキャッシュフロー ×(1 + 永久成長率)÷(割引率 – 永久成長率)」で計算します。永久成長率には、長期的な名目GDP成長率やインフレ率(日本では1~2%程度)を用いることが一般的です。
2つ目はマルチプル法で、最終年度のEBITDAなどの指標に業界平均の倍率を乗じて継続価値を算定する方法です。どちらの方法を選択するかは、業種特性や将来の成長見通しによって判断します。 継続価値は企業価値全体の50~70%を占めることも多く、その算定方法と前提条件は慎重に検討する必要があります。
感応度分析による評価の妥当性検証
割引率や成長率の設定には不確実性が伴うため、複数のシナリオで企業価値がどう変動するかを確認する感応度分析が重要です。割引率を±1~2%変動させた場合や、永久成長率を変えた場合に企業価値がどう変わるかを表形式で整理します。
例えば、割引率を8%、9%、10%と変化させ、永久成長率を1%、2%、3%と変化させた場合の企業価値をマトリクスで示すことで、評価のレンジが把握できます。この分析により、どのパラメータが企業価値に最も大きな影響を与えるかが明確になり、交渉における重点項目も特定できます。
感応度分析を通じて、楽観シナリオ、標準シナリオ、悲観シナリオの3つの企業価値レンジを設定し、M&A交渉における価格レンジの根拠とすることが実務的です。単一の評価額ではなく、レンジで考えることで、より現実的な交渉が可能になります。
他の評価手法との併用
実務のM&Aでは、DCF法だけでなく、マーケットアプローチ(類似企業比較法、類似取引比較法)やコストアプローチ(純資産価額法)も併用して、多角的に企業価値を検証します。各手法で算定された価値にばらつきがある場合は、その理由を分析します。
例えば、DCF法による評価額が純資産価額を下回る場合は、将来収益力が資産価値を下回ると判断されていることを意味します。逆にDCF法の評価額が類似企業比較法よりも大幅に高い場合は、成長予測が楽観的すぎる可能性があります。複数手法の結果を比較検討することで、より信頼性の高い評価レンジが得られます。
M&Aにおける割引率活用のテクニック
割引率の計算と企業価値評価の理論を理解した上で、実際のM&A取引でどのように活用するかが重要です。交渉戦略から価格調整メカニズムまで、実務的なテクニックを解説します。
買い手側の割引率設定戦略
買い手側は、買収後の統合リスクや予測の不確実性を考慮して、やや高めの割引率を設定する傾向があります。これにより算定される企業価値は保守的になり、買収後に想定外の事態が発生しても損失を抑えられます。
具体的には、標準的な割引率に以下のようなリスクプレミアムを上乗せします。
- 経営者依存リスク(キーパーソンの退任可能性)
- 顧客集中リスク(特定顧客への売上依存度が高い場合)
- 技術陳腐化リスク(IT業界など変化の激しい業種)
- 統合リスク(組織文化の相違、システム統合の難易度)
これらのリスクを定量化し、それぞれ0.5~2%程度のプレミアムとして割引率に加算します。 ただし、あまりに高い割引率を設定すると売り手側との交渉が難航するため、客観的根拠を示せるリスク項目に限定することが重要です。 デューデリジェンスで発見された具体的なリスク要因を根拠とすることで、売り手側の理解も得やすくなります。
売り手側の対応と交渉ポイント
売り手側は、買い手が設定する割引率の妥当性を検証し、過度に高い設定には反論する必要があります。自社のリスクが業界平均よりも低い点や、安定した収益基盤があることを示すデータを準備します。
例えば、以下のような要素をアピールすることで、割引率の引き下げを主張できます。
- 長期契約や安定した顧客基盤の存在
- 独自技術や特許による競争優位性
- 経営陣の継続コミットメント
- 過去の業績安定性と予測精度の高さ
売り手側が第三者の専門家による企業価値評価書を取得し、客観的な割引率の根拠を示すことも有効な戦略です。買い手と売り手で異なる割引率を前提とする場合は、両者の評価額の中間値を交渉の出発点とするケースも多くあります。
アーンアウト条項による価格調整
将来業績の予測が困難で、割引率や企業価値について買い手と売り手の見解が大きく異なる場合、アーンアウト条項を活用することが有効です。アーンアウトとは、買収後の実際の業績に応じて追加の対価を支払う仕組みです。
例えば、売り手は将来の高成長を見込んで高い評価を主張するが、買い手はそのリスクを考慮して保守的な評価をする場合、以下のような条件設定が可能です。
- 基本対価は買い手の評価額ベースで決定
- 買収後3年間の業績が目標を達成した場合、追加対価を支払う
- 追加対価の上限は基本対価の20~30%程度
この方法により、売り手は将来の成長による追加対価獲得の機会を得られ、買い手は実績に基づく支払いのためリスクを軽減できます。アーンアウトの条件設定においても、どの指標を基準とするか(売上高、EBITDA、純利益など)、達成判定の方法などを慎重に設計する必要があります。
段階的買収における割引率の調整
最初にマイノリティ持分を取得し、段階的に支配権を獲得していく場合、各段階で異なる割引率を適用することがあります。マイノリティ持分には経営支配権がないため、コントロールプレミアムを控除した割引率(つまり高い割引率)を用いて評価します。
支配権取得時には、コントロールプレミアムを反映した割引率(低めの割引率)を適用し、企業価値を高く評価します。この差分が支配権プレミアムとして価格に反映されます。段階的買収戦略では、各段階での割引率設定とそれに基づく価格設定を事前に計画しておくことが重要です。
割引率計算における注意点
割引率の計算と活用には様々な落とし穴があり、不適切な設定は企業価値の誤算につながります。実務で注意すべきポイントとリスク管理の方法を理解しておきましょう。
過度に楽観的な前提の回避
割引率を低く設定しすぎることは、将来リスクを過小評価することになり、買収後に期待したリターンが得られない原因となります。特に売り手側が作成した事業計画をそのまま採用し、低い割引率を適用すると、企業価値が過大評価されるリスクがあります。
過去の実績と将来計画の整合性を確認し、成長率の前提が現実的かを検証することが必要です。業界平均成長率や過去のトレンドと大きく乖離した計画には疑問を持ち、保守的なシナリオも準備すべきです。また、マクロ経済環境の変化(金利上昇、景気後退など)が割引率に与える影響も考慮する必要があります。
非上場企業特有の調整事項
中小企業のM&Aでは、評価対象企業が非上場であることがほとんどです。上場企業と比較して、流動性の欠如やガバナンス体制の脆弱性などのリスクがあるため、割引率に追加のプレミアムを加える必要があります。
一般的に、非上場企業の割引率には以下のような調整を行います。
- 流動性ディスカウント(非流動性プレミアム)として1~3%程度を加算
- 規模が小さいほど高いリスクプレミアムを設定
- 財務情報の信頼性が低い場合は追加プレミアムを考慮
- オーナー企業特有の個人的経費混入などを正常化
ただし、買い手が同業の戦略的買収者であり、シナジー効果が期待できる場合は、スタンドアローンベースの割引率から一部調整を行うこともあります。買収後の統合によるリスク低減効果を定量的に評価できる場合は、その分を割引率に反映させることも可能です。
為替リスクと海外企業評価
海外企業を買収する場合、為替リスクを割引率にどう反映させるかが課題となります。原則として、キャッシュフローと割引率は同一通貨で統一する必要があります。現地通貨ベースでキャッシュフローを予測し、現地通貨建ての割引率を用いて評価するのが標準的です。
現地通貨建ての割引率は、現地のリスクフリーレートと市場リスクプレミアムを用いて計算します。カントリーリスク(政治リスク、経済不安定性など)が高い国の企業を評価する場合は、追加のカントリーリスクプレミアムを加算します。算定された現地通貨建て企業価値を、現在の為替レートで円換算することで、最終的な買収価格を決定します。
専門家の活用と独立した検証
割引率の設定には高度な専門知識と経験が必要であり、重要なM&A案件では外部専門家の活用が推奨されます。公認会計士、M&Aアドバイザー、企業価値評価の専門家などに依頼し、独立した第三者評価を取得することで、評価の客観性と信頼性が高まります。
特に上場企業が買収を行う場合や、ファンドが投資判断を行う場合は、第三者評価機関による独立した企業価値評価書の取得が事実上必須となっています。これにより、取締役の善管注意義務の履行を示すとともに、株主に対する説明責任を果たすことができます。評価額の妥当性について後から疑義が生じた場合も、専門家による評価プロセスを経ていることが重要な防御となります。
まとめ
割引率はM&Aにおける企業価値評価の核心となる要素であり、その計算方法を正しく理解することが適正な買収価格の算定につながります。WACCやCAPM、ビルドアップ法など複数の計算手法があり、評価対象企業の特性に応じて使い分ける必要があります。
実務では、割引率の設定に買い手と売り手の見解の相違が生じやすく、客観的根拠に基づいた交渉が重要です。感応度分析により評価の不確実性を把握し、場合によってはアーンアウト条項などの価格調整メカニズムを活用することで、双方が納得できる取引条件を構築できます。
割引率の計算には専門的知識が必要であり、重要な案件では外部専門家による独立した評価を取得することで、評価の信頼性を高めることができます。適切な割引率設定により、M&A後の期待リターンを確保し、成功確率を高めることが可能です。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、豊富な実績に基づく企業価値評価と割引率設定のサポートを提供しており、お客様の戦略的M&Aの成功をお手伝いいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。