クラウンジュエルとは?M&A買収防衛策の特徴を事例と共に解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
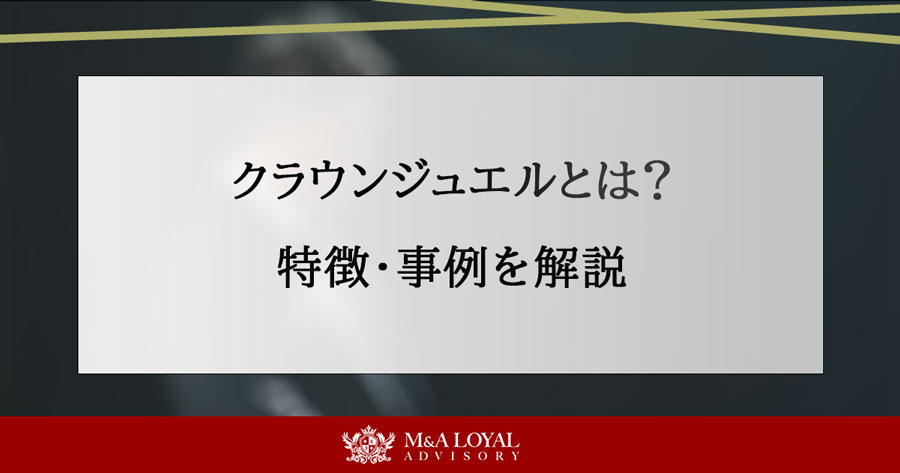
近年、M&A(合併・買収)は日本企業にとっても他人事ではなくなりました。成長戦略として歓迎される一方で、敵対的な買収に直面するリスクも現実味を帯びています。
王冠の宝石という異名を持つ買収防衛策「クラウンジュエル」は、特定の資産や事業を切り離すことで企業価値を意図的に引き下げ、買収の魅力を低下させる戦略として知られています。
本記事では、クラウンジュエルの基本的な情報からメリット・デメリット、類似する手段までを包括的に解説します。
目次
クラウンジュエルとは
まず、クラウンジュエルの基本的な知識について解説します。
企業資産またはその防衛手段のこと
クラウンジュエル(Crown Jewel)とは、敵対的買収を仕掛けられた企業が自社の中で最も価値のある資産(中核事業、ブランド、知的財産など)を第三者に譲渡または分社化することで、買収者にとっての企業価値を意図的に低下させる防衛策です。
なお、クラウンジュエルは企業にとって特に重要な資産そのものを指す用語としても使われますが、一般的には買収防衛策を指します。
クラウンジュエルの語源
「クラウンジュエル(Crown Jewel)」の語源は、英語で「王冠の宝石」を意味する言葉で、会社(王冠)の中でも特に価値のある要素(宝石)を指します。
敵対的買収が注目されるようになった1980年代のアメリカでは、買収者の主要な関心が被買収企業の価値ある資産に集中することから、これを切り離す防衛策が「クラウン・ジュエル・ディフェンス(Crown Jewel Defense)」と呼ばれるようになりました。そして現在では略称である「クラウンジュエル」が一般化しました。
クラウンジュエルの目的とは
クラウンジュエルによって、企業が持つ最も魅力的な資産を第三者に譲渡または分社化することで、自社の企業価値を意図的に低下させ、買収者にとっての投資メリットを失わせます。これにより、買収者が期待していた事業シナジーや資産活用の前提が崩れ、買収計画を断念させることが目的です。
この手法は、敵対的買収を仕掛けられた企業が自社の独立性を守るために講じる、最終的な防衛手段といえます。
スコーチドアース(焦土作戦)との違い
スコーチドアース(Scorched Earth)は、クラウンジュエル同様に敵対的買収に対する防衛策です。「スコーチドアースディフェンス」とも呼ばれる他、日本では「焦土作戦(焦土戦術)」という名称が一般的です。
クラウンジュエルよりも広範囲かつ徹底的な手段を取る点が特徴です。
クラウンジュエルが特定の価値ある資産の譲渡を通じて買収を妨害するのに対し、スコーチドアースは会社全体の価値を下げる手段を積極的に講じます。具体的には、多額の負債の引き受け、全社的な契約の解除、不採算事業への投資などを行い、買収者にとって企業全体を魅力のない存在にすることで、買収を思いとどまらせることを狙います。
企業財産としてのクラウンジュエルの種類
企業財産としてのクラウンジュエルは次のとおりです。
- 中核事業(コアビジネス)
- 収益性の高い子会社
- 不動産
それぞれについて解説します。
中核事業(コアビジネス)
企業の売り上げや利益の大半を支える中核事業がクラウンジュエルとして狙われることが多いです。例えば、飲料会社にとっての看板ブランドの製品群などが該当します。
こうした事業は、高い収益性以外にもブランド力や市場シェア、独自のノウハウなどを伴っていることが多いため、敵対的買収者にとって最も魅力的な資産とされます。
収益性の高い子会社
安定した収益を生む子会社は、企業グループ全体の財務基盤を支える存在であり、他社にとっても魅力的な投資対象です。
特にこうした子会社は、親会社とは異なる市場における事業展開や専門性を持つため、他社にとっては買収による即時的な収益貢献や事業シナジーが見込める極めて魅力的な投資対象です。
不動産
本社ビルや工場、物流拠点などの不動産は、資産価値としても高く、また事業運営に不可欠なインフラです。
地理的優位性や所有形態によっては、敵対的買収者にとって即時の売却益や事業運営への活用が可能なため、買収の大きな動機になります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



クラウンジュエルの手法
クラウンジュエルを実行する際は次の手法が採られます。
- 事業譲渡
- 子会社の譲渡・分社化
- 重要財産の譲渡・売却
それぞれについて詳しく解説します。
事業譲渡
クラウンジュエルの中でも最も重大な手段が事業譲渡です。会社が行う事業の一部または全てを第三者に移譲するもので、買収の動機となる中核事業を切り離すことにより、企業価値を意図的に低下させます。
会社法467条により、事業の全部または重要な一部を譲渡する場合には株主総会の特別決議(309条:出席株主の3分の2以上の賛成)が必要です。また、対象が「有機的一体として機能する財産」であると認定される必要がある他、株主の納得が求められるなど、実行までには高いハードルがあります。
子会社の譲渡・分社化
買収対象とされる収益性の高い子会社を第三者に譲渡することも有効な防衛策です。一般には子会社株式の譲渡によって行われ、買収者にとって魅力的な資源を意図的に排除することが目的です。
会社法467条および平成26年の法改正により、譲渡対象が重要子会社に該当する場合、株主総会の特別決議が必要です(議決権喪失、帳簿価額が総資産の5分の1超等が基準)。また、分社化により子会社化した上での切り離しも実務上用いられます。
重要財産の譲渡・売却
事業や子会社ほどではないものの、企業の競争力や資産価値に影響を与える重要財産(不動産、設備、知的財産など)の譲渡もクラウンジュエルの手段のひとつです。
会社法362条において、重要な財産の処分は取締役会の専決事項とされる場合がありますが、事業の全部または重要な一部を譲渡する場合など特定の条件下では株主総会の承認が必要です。スピーディな対応が可能である一方、何が「重要」かは敵対的買収に関わる企業の認識によって差があります。価格や資産構成比率、保有目的などを総合的に勘案して判断する必要があります。
クラウンジュエルのメリット
クラウンジュエルによって企業価値を毀損(きそん)してしまうため、メリットはないように思えますが、実は次のようなメリットがあります。
- 企業価値の保護につながる
- 資産の価値が上がる可能性がある
- 売却によって得られた資金を運用できる
それぞれについて解説します。
企業価値の保護につながる
クラウンジュエルによって敵対的買収を阻止することにより、企業の独立性と自律的経営を維持できます。これにより、自社の戦略に沿った中長期的な成長が可能となり、株主にとっても望ましい経営の継続が確保されます。
資産を短期的に手放すことで一時的な損失が生じる可能性はありますが、長期的には経営の安定性や継続性の確保による企業価値の保護は大きなメリットといえるでしょう。
資産の価値が上がる可能性がある
譲渡対象となる中核資産や事業は、他企業にとって極めて高い価値を持つ場合があり、適切な相手に売却することでその資産本来の価値が最大限に引き出されることがあります。
自社で抱えていた場合以上に高い価格での譲渡が可能となるケースもあり、クラウンジュエル戦略が資産の再評価と価値向上の契機となることもあります。
売却によって得られた資金を運用できる
クラウンジュエルの実行によって得た売却資金を、他の成長分野への投資や財務の健全化に活用することで、企業全体としての価値向上も可能です。
例えば、新規事業の開拓や研究開発投資、負債の圧縮などに資金を充てることで、経営の柔軟性と収益基盤が強化される可能性があります。単なる防衛策にとどまらず、戦略的な経営資源の再配分方法としても評価できます。
クラウンジュエルのデメリット・リスク
クラウンジュエルのデメリットやリスクは次のとおりです。
- 重要な資産を失う危険性がある
- 取締役の善管注意義務違反となる恐れがある
- 株主承認を得る難しさや反発を招く恐れがある
それぞれについて解説します。
重要な資産を失う危険性がある
クラウンジュエル戦略は、企業が敵対的買収を防ぐために、重要な資産や事業を売却することで、買収者にとっての魅力を削ぐ手段として用いられます。しかし、自社の中核事業や収益源となる子会社、知的財産を譲渡・分社化することは、企業が培ってきた価値ある資産を手放すことを意味し、これによって事業成長や市場での地位が損なわれるリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
買収を回避できたとしても、将来的に収益力や企業価値が低下し、結果的に株主や従業員などに不利益が及ぶ可能性が高く、最悪の場合には倒産にもつながりかねません。
取締役の善管注意義務違反となる恐れがある
会社法上、取締役には善管注意義務(第330条・355条)および忠実義務が課されており、企業の利益に反する意思決定は厳しく制限されています。
クラウンジュエルの実行によって明らかに企業価値が棄損された場合、その判断が合理性を欠くとして取締役の責任が問われる恐れがあります。特に株主からは、経営判断として不適切と見なされ、株主代表訴訟によって損害賠償責任を追及されるリスクもあります。
株主承認を得る難しさや反発を招く恐れがある
事業譲渡や子会社譲渡といったクラウンジュエルの主要手法は、会社法により株主総会での特別決議(3分の2以上の賛成)が必要です。しかし、企業価値を毀損(きそん)する恐れのある施策に株主が賛同するとは限らず、反発を招く可能性があります。
特に、株主が敵対的買収者に売却した方が利益になると判断すれば、逆に買収が加速されてしまうことがあります。取締役会としては、戦略の合理性と長期的利益を丁寧に説明し、株主の信任を得る必要があります。
クラウンジュエル以外の買収防衛策(予防的措置)
クラウンジュエル以外にもさまざまな買収防衛策があります。また、クラウンジュエルは他の防衛策と組み合わせることでより効果的になることも多いです。
予防的措置としての買収防衛策は次のとおりです。
- 株主名簿の管理
- ポイズンピル(ライツプラン)
- プット・オプションの付与
- 資産ロックアップ
- 黄金株(拒否権付種類株式)の発行
- ゴールデンパラシュート
- ティンパラシュート
- チェンジ・オブ・コントロール条項
- スタッガード・ボード
それぞれの特徴について解説します。
株主名簿の管理
まず、買収防衛の基本として、株主名簿の厳格な管理は極めて重要です。株主構成を常に把握することで、特定の株主が急激に持株比率を高めていないか、敵対的買収者が水面下で株式を取得していないかなどを早期に察知できます。
株主名簿に基づき、取締役会は状況に応じた迅速な対応策を講じることができ、クラウンジュエルをはじめとする他の防衛策を事前に整える上でも重要な役割を果たします。
株主名簿の適切な管理は、買収防衛の初動対応として不可欠であり、他の戦略を発動するための「監視体制の基盤」といえるでしょう。
ポイズンピル(ライツプラン)
ポイズンピル(ライツプラン)は、特定の条件下で既存株主に時価より安く新株を取得できる権利(新株予約権)を付与し、買収者の持株比率を希薄化させる防衛策です。日本語では「毒薬条項」とも呼ばれます。
例えば買収者が一定以上の株式を取得したときに、時価より著しく安い価格で新株を取得できる「新株予約権」を付与します。これにより、新たに発行される株式の数が大きくなり、買収者の持株比率が希薄化し、実質的に経営支配が困難になります。
ただし、新株予約権の発行により株式数が増加し、1株当たりの価値が希薄化するため、株価が下落する可能性や既存株主の利益を損なうリスクも存在します。また、導入には定款変更や株主総会の承認が必要な場合が多く、手続き面での整備と正当性の説明も欠かせません。
プット・オプションの付与
プット・オプションとは、特定の条件が生じた場合に、株主や債権者が株式の買い取りや債務の一括弁済を請求できる権利です。これを買収防衛策として活用する場合、敵対的買収が起きた際に株主が保有株式を会社に高値で売却できるよう設定し、買収後の資金流出リスクを高めることで、買収者の意欲を削ぐ仕組みです。
債権者にも同様に、一括弁済を請求できる条件を契約に組み込むことがあります。これにより、買収後に生じる潜在的な負債リスクが高まり、敵対的買収の経済合理性を低下させる効果が期待されます。
資産ロックアップ
資産ロックアップとは、企業の重要な資産を、買収後に譲渡・売却できないよう制限を設ける買収防衛策です。定款や契約で売却制限を明示することで、資産目的の敵対的買収を抑止する効果があります。
例えば、優良な不動産や知的財産を狙った買収に対して、ロックアップ条項を設定すれば、買収者にとって魅力のない取引となる可能性があります。ただし、資産の流動性が制限されるため、企業自身の経営の柔軟性も損なわれる恐れがあります。
黄金株(拒否権付種類株式)の発行
黄金株とは、種類株式の一種で、特定の議案に対して拒否権を持つ株式のことです。
正式には「拒否権付種類株式」と呼ばれ、通常の株主総会の議決とは別に、種類株主総会において黄金株の所有者の同意がなければ、特定の重要議案(事業譲渡や合併など)を成立させられません。
この仕組みによって、企業の重要な意思決定を一部の友好的な株主にとどめることで、敵対的買収者が過半数以上の株式を取得したとしても、支配権を行使できないようにする防衛策となります。
ただし、経営陣が黄金株を保有することは株主平等原則に反するため認められておらず、通常は信頼できる第三者や政府系機関に保有させる方法が一般的です。一方で、少数株主に強い権限を与える仕組みであるため、上場企業では導入に慎重な対応が求められ、企業統治の透明性や公平性の面でも議論の余地があります。
ゴールデンパラシュート
ゴールデンパラシュートとは、敵対的買収が行われた際に、企業の役員に対して多額の退職金や特別手当を支払う契約を事前に設定しておく買収防衛策です。
買収者が企業の支配権を握った後には、通常、経営陣を刷新し自社から新たな人材を送り込むことが多いため、既存役員の退任が前提となります。そこで、その退任に際し、通常の数倍にも及ぶ報酬を支払うことにより、買収に伴うコストを引き上げ、買収者の意欲を削ぐ狙いがあります。さらに、役員にとっても自身の将来に対する補償となるため、防衛策として導入しやすいという側面もあります。
ただし、この手法は企業の財務に与える影響が大きく、株主から「経営陣の保身策」として批判される可能性もあります。また、株主の承認が不要な場合でも、社会的な批判や企業価値毀損(きそん)のリスクを十分に考慮する必要があります。
ティンパラシュート
ティンパラシュートとは、従業員に対して退職金や一時金を通常より高く設定することで、敵対的買収者の負担を増やし、買収意欲を削ぐ手法です。すなわち、ゴールデンパラシュートの対象を一般従業員に広げた手法です。
敵対的買収後に従業員の整理や再配置を予定している買収者にとっては、退職に伴う費用が大きくなり、買収後の経営負担が増します。そのため、従業員の退職コストが重くのしかかることで、買収の経済合理性を低下させ、防衛効果を発揮します。
ただし、制度の設計や実行にあたっては、従業員との合意形成や労務管理の観点から慎重な対応が求められます。
チェンジ・オブ・コントロール条項
チェンジ・オブ・コントロール条項とは、企業の支配権が変更された場合に契約の解除や権利の制限を認める条項です。重要顧客との契約にこの条項が含まれていれば、買収後の売り上げ低下や業務停止が想定されるため、買収意欲を削ぐ効果があります。
例えば、「合併または株主構成の50%超の変更があった場合は、催告なく取引先会社との契約を解除できる」といった規定を契約に盛り込めます。これによって買収による経営権の変動が取引先の離脱や契約破棄を招くリスクとなり、敵対的買収者にとっては実質的な損失につながります。
契約自由の原則に基づく正当な規定である一方、実効性や発動条件には注意が必要です。
スタッガード・ボード
スタッガード・ボードとは、取締役の任期を複数年に分割し、毎年その一部のみを改選する制度です。これにより、株主総会において一度に全取締役を交代させられず、敵対的買収者が短期間で経営権を掌握するのを防ぐ効果があります。
M&Aの局面では、被買収企業が時間を稼ぎ、他の防衛策を講じる猶予を得るために用いられます。メリットとしては、経営の安定性や継続性の確保が挙げられる一方で、変革の遅れやガバナンスの硬直化といったデメリットもあります。
米国企業を中心に採用例が多く、日本では類似の防衛策として定款や役員任期の調整で実現されるケースがあります。
クラウンジュエル以外の買収防衛策(対抗措置)
クラウンジュエル以外の対抗措置としての買収防衛策は次のとおりです。
- ホワイトナイト
- ホワイトスクワイア
- 第三者割当増資
- ゴーイング・プライベート
- パックマン・ディフェンス
- ジューイッシュ・デンティスト
それぞれの特徴について解説します。
ホワイトナイト
ホワイトナイトとは、敵対的買収に直面した企業が、自社に友好的な第三者企業(ホワイトナイト)に株式を取得・TOBしてもらい、経営権を委ねることで買収を回避する手法です。
第三者の支援により、敵対的買収者よりも有利な条件での取引が可能となり、企業の経営方針や独立性をある程度維持しながら、買収リスクを回避できます。過去の実例としては、オリジン東秀がイオンをホワイトナイトとして迎えたケースが有名です。
ただし、最終的に経営権が第三者に渡ることになるため、自主独立経営を志向する企業にとっては慎重な判断が求められます。
ホワイトスクワイア
ホワイトスクワイアは、ホワイトナイトに似た手法ですが、買収防衛を目的に第三者に一定の株式を保有させる一方で、経営権までは与えないという点で異なります。
友好的な企業や投資家に一定比率の株式を持たせることで、敵対的買収者が経営権を取得するために必要な議決権の確保が難しくなり、買収が困難になります。経営の独立性を維持しつつ、株主構成を安定化できます。
ただし、友好的株主との関係性が崩れた場合には逆にリスク要因となる可能性もあり、導入時には慎重な株主選定が求められます。
第三者割当増資
第三者割当増資とは、企業が発行する新株を、友好的な企業や信頼できる取引先など特定の第三者に引き受けてもらう増資手法です。原則として、企業は新株の発行先と数量を自由に決定できるため、防衛目的での実施も可能です。
買収防衛策としては、敵対的買収者に対抗するために、新株を友好的な第三者に割り当てて支配権を分散させる、または敵対的買収者の持株比率を希薄化させることを狙います。しかし、過度な新株発行は株式価値を希薄化させ、既存株主の利益を損なう可能性があります。
そのため、株主の利益を著しく害するような不公正な発行については、株主による差止請求が認められる場合もあり、実施には法的な正当性や手続的な妥当性が求められます。
ゴーイング・プライベート
ゴーイング・プライベートとは、企業が株式を非公開化(上場廃止)することによって、敵対的買収を回避する戦略です。
この非公開化を実現する主な手段が、マネジメント・バイアウト(MBO)やエンプロイー・バイアウト(EBO)です。MBOは経営陣が自社株を買い取り、経営権を確保しつつ株式を市場から引き上げる方法です。EBOは従業員が出資して経営に関与するもので、内部からの支配体制を強化しながら買収防衛を図ります。
これらの手法は敵対的買収の回避だけでなく、事業承継や再編にも活用されます。株式非公開化後に譲渡制限付株式へ移行すれば、株式取得のハードルはさらに高まり、防衛効果は一層強化されます。
ただし、ゴーイング・プライベートには、既存株主との利害調整や巨額の資金調達、説明責任の履行といった課題が伴います。
パックマン・ディフェンス
パックマン・ディフェンスとは、敵対的買収を仕掛けてきた企業に対し、逆に買収を仕掛ける防衛策です。被買収企業が買収者の株式を大量に取得し、支配権を奪い返すという反転攻勢型の戦略で、名前はゲームの「パックマン」が敵を食べ返す様子に由来します。
買収側が保有する株式の4分の1を取得すれば、議決権を制限できる制度を利用することで、実効性を持ちます。
ただし、実行には巨額の資金が必要であり、防衛以外の経営効果が乏しいことから、実際に用いられるケースは少なく、現実的な手段とは言い難いです。
ジューイッシュ・デンティスト
ジューイッシュ・デンティストとは、敵対的買収を仕掛けてきた企業の社会的信用を低下させるための情報工作的な戦術です。語源は1980年代、ユダヤ系の歯科器具メーカーに対するアラブ資本の買収に反対したユダヤ人歯科医たちの運動が由来とされます。
具体的には、買収者に関するネガティブな情報(違法行為やコンプライアンス違反の疑いなど)をメディアなどに流布し、株主や世間からの信頼を失わせて買収意欲を削ぐことを目的とします。
現代においては名誉毀損(きそん)や風説の流布などの法的リスクが高く、実行はきわめて限定的ですが、買収防衛の心理・世論戦の象徴とされています。
クラウンジュエルの事例5選
クラウンジュエルによる敵対的買収の防衛が行われた事例を5つ紹介します。
ニッポン放送とライブドア(2005年・日本)
2005年、ライブドアはニッポン放送の株式を大量取得し、子会社のフジテレビを実質的に支配しようと試みました。これに対しニッポン放送は、クラウンジュエル戦略の一環として、フジテレビ株の売却や子会社ポニーキャニオンの譲渡を検討しました。しかし、最終的にはソフトバンク・インベストメントがホワイトナイトとして介入し、敵対的買収の回避に成功しました。
前田建設による前田道路の買収(2020年・日本)
2020年、前田建設は同業の前田道路に対して株式公開買い付け(TOB)を実施し、敵対的買収を仕掛けました。買収対象となった前田道路は、総額535億円の特別配当を発表し、企業価値を意図的に減少させる対抗策を講じました。
さらにホワイトナイトの導入も検討しましたが、最終的には前田建設によるTOBが成立し、子会社化されました。
ピルズベリーとグランドメトロポリタン(1988年・米国/英国)
米国の食品企業ピルズベリーは、英グランドメトロポリタンによる敵対的買収を受け、事業を売却するというクラウンジュエル戦略を採用しました。
この重要事業の売却により、ピルズベリーの企業価値は買収者にとって大きく低下し、グランドメトロポリタンは買収継続を断念しました。この事例は、重要資産の譲渡によって買収者の経済的動機を断ち切る典型的な成功例とされています。
クラウンジュエルに関するQ&A
最後に、クラウンジュエルに関するよくある質問とその回答を紹介します。
海外ではクラウンジュエルが頻繁に行われているか
欧米では過去に数多くの実例がありますが、近年は慎重な運用が主流です。1980〜1990年代のアメリカでは、敵対的買収が活発化した時期にクラウンジュエル戦略が多く採用されました。
ただし、資産を切り離すことで企業の本質的価値を損なうため、近年はより持続的なガバナンス重視の潮流により、発動は限定的です。
また、EU諸国などでは会社法・資本市場規制により、株主保護の観点からクラウンジュエルの実行に厳しい制約がある国も多く、実行には法的・倫理的な配慮が必要とされています。
クラウンジュエルの価値は誰がどうやって決めるのか
クラウンジュエルの価値は、財務・法務・事業部門の協働による内部評価と外部専門家の助言で判断されます。
クラウンジュエルとなる資産や事業の価値評価においては、収益性・成長性・他社との比較優位性・事業シナジー・ブランド価値などが検討材料となります。内部では財務部門が定量分析を、法務部門が権利関係や規制リスクの調査を、事業部門が戦略的価値を検討します。
加えて、M&Aアドバイザーやファイナンシャルアドバイザー、弁護士、会計士などが独立した立場から助言・価値算定を行うことも一般的です。
スピンオフとは何か
スピンオフとは、企業が特定の事業を新会社として分離しつつ、親会社が資本関係を維持する形で子会社化する手法です。新会社の株式は親会社が保有し続けるか、既存株主に割り当てる形で移転されるため、グループ内の一体性や協力関係は保たれます。
クラウンジュエル戦略としては、買収対象となり得る魅力的な事業を先に分離しておくことで、敵対的買収の魅力を削ぐ目的で使われることがあります。ただし、資本関係が残るため、買収側に完全な遮断効果を与える手段とはいえません。
スピンアウトとは何か
スピンアウトは、企業が保有する特定事業を新会社として切り出し、元会社との資本関係を断絶した上で独立させる方法です。これは、選択と集中の戦略や、グループ全体の効率化、あるいは将来的な買収・事業提携を見据えた再編の一環として行われます。
クラウンジュエル対策としては、買収者が狙う中核資産を先に外部に移転することで防衛ラインを築くことができ、買収の魅力を根本から損なう強力な手段となります。ただし、実行には株主や関係当局との調整、ステークホルダーとの信頼構築が不可欠です。
キラー・ビーとは何か
キラー・ビーとは、敵対的買収に際して企業を守る第三者のことを指します。
買収防衛のために雇われたM&A専門家や法律事務所、投資銀行などの外部助言者を意味し、企業が外部からの敵対的行動に対抗するための「刺す蜂(bee)」になぞらえた表現です。
キラー・ビーは、敵対的買収への反撃策(クラウンジュエル、ホワイトナイトの提案、ライツプランの設計など)を戦略的に立案・実行します。特にアメリカのM&A実務では、重要な役割を果たす存在として知られています。
グリーンメーラーとは何か
グリーンメーラーとは、株式を大量に取得して経営陣に圧力をかけ、高値での株式買い戻し(グリーンメール)を要求する投資家を指します。
経営権の取得を目的とせず、株式の売却益のみを狙う点が特徴で、M&Aや企業価値向上とは無関係の行動をとるため、対象企業にとっては敵対的買収者以上に厄介な存在とされます。
グリーンメーラー対策としてクラウンジュエルは適しません。主な防衛策としては、ポイズンピルの発動やMBOによる非上場化、パックマンディフェンスなど、株式の流通や影響力そのものを制限・排除する手段が挙げられます。
国内では敵対買収はリスクも高いため、実際には少ないですが、想定外の企業買収を回避するためのリスク対策としてクラウンジュエルやその他の手法を知っておくことをおすすめします。M&Aや事業承継に関するお悩みはぜひ一度、M&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。











