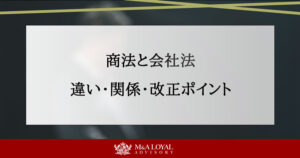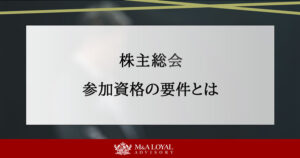利益相反取引とは?取締役が知るべき5つの承認手続きと実務ポイント
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
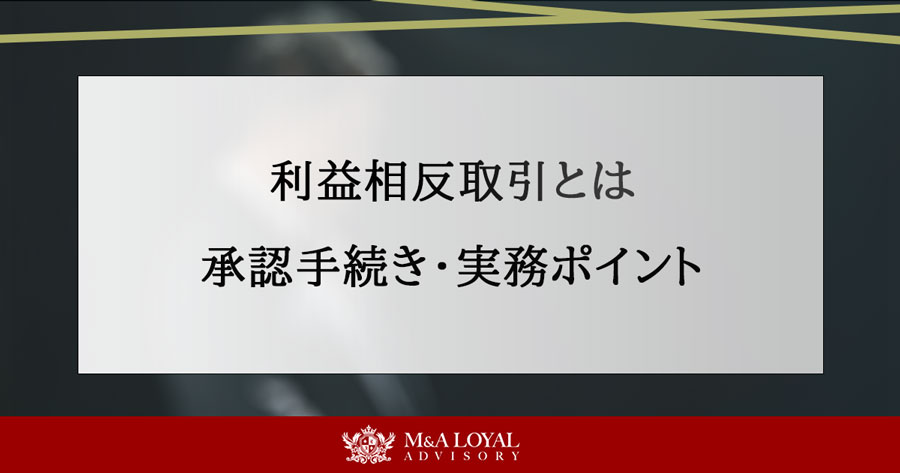
取締役が会社と取引を行う際、「利益相反取引」として特別な手続きが必要になることをご存知でしょうか。中小企業では、経営者が個人名義の不動産を会社に貸したり、関連会社との取引を行ったりするケースが日常的に発生しますが、適切な承認手続きを怠ると取引が無効となったり、取締役が損害賠償責任を負ったりするリスクがあります。
特に事業承継やM&Aを検討している企業では、過去の利益相反取引が問題となり、手続きが停滞する事例も少なくありません。しかし、利益相反取引の基本的なルールと正しい手続きを理解していれば、こうしたリスクを回避することができます。
本記事では、利益相反取引の基本的な仕組みから具体的な承認手続き、実務上の注意点まで、中小企業の経営者や法務担当者が知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。適切な管理体制を構築し、安心して事業運営を行うための実践的な知識を身につけましょう。
目次
利益相反取引とは?基本概念と会社法上の規制
利益相反取引とは、取締役が自身や第三者の利益を図るために、会社の利益と相反する取引を行うことです。会社法では、このような取引について厳格な規制を設けており、適切な承認手続きを経ない場合は無効となるリスクや、取締役の損害賠償責任が発生する可能性があります。
会社法における利益相反取引の定義と趣旨
会社法356条では、利益相反取引について「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」および「株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき」と定義しています。
この規制の趣旨は、取締役が会社の業務執行における地位を利用して、会社の利益を犠牲にしながら自己や第三者の利益を図ることを防止することにあります。取締役は会社に対して善管注意義務を負っているため、会社の利益を最優先に考えて行動する必要があります。
直接取引と間接取引の2つの類型
会社法は利益相反取引を「直接取引」と「間接取引」の2つに分類して規定しています。
直接取引(会社法356条1項2号)は、取締役が自己または第三者のために会社と直接契約を締結する取引です。例えば、取締役が会社から不動産を購入する場合や、取締役が代表を務める別会社が元の会社と売買契約を結ぶ場合が該当します。
間接取引(会社法356条1項3号)は、会社が取締役以外の第三者との間で契約を締結するものの、その取引により取締役にメリットが生じ、会社にデメリットが発生する取引です。代表的な例として、会社が取締役の個人的な借金について債務保証をする場合があります。
規制対象となる取引と規制対象外の取引
利益相反取引の規制対象となるのは、外形的・客観的に見て会社の利益と取締役の利益が対立する取引です。具体的には以下のような取引が規制対象となります。
- 会社と取締役間の売買契約、賃貸借契約、請負契約
- 会社による取締役の債務保証や担保提供
- 取締役が代表を務める他社との取引契約
一方で、規制対象外となる取引もあります。
- 無利息貸付:取締役から会社への無担保貸付
- 一般取引:通常価格での商品購入など
- 100%株主取引:株主と会社の利益が一致
- 全員同意:全株主が取引に同意している場合
これらは会社に損害が発生する危険性がないか、実質的に利害対立がないため承認手続きが不要とされています。 ただし、ケースバイケースで、特定の状況により、利益相反と見なされることもあるため、法的なアドバイスを受けることが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



直接取引として規制される具体例と判断基準
直接取引は、取締役が自己または第三者のために株式会社と取引を行う場合を指します。この直接取引には複数のパターンがあり、実務では「誰が契約の代表者となるか」によって利益相反取引への該当性が判断されます。適切な判断を行うためには、具体的なパターンと判断基準を理解することが重要です。
直接取引に該当する3つの基本パターン
直接取引として規制される取引には、主に3つの基本パターンがあります。
- 本人取引:取締役が契約当事者となる取引
- 代表取引:取締役が第三者を代表して行う取引
- 代理取引:取締役が第三者の代理人として行う取引
第1のパターンは、取締役本人が契約当事者となる取引です。例えば、取締役が会社から不動産を購入する場合や、会社が取締役に対して金銭を貸し付ける場合がこれに該当します。このような取引では、取締役が価格を自由に設定できる立場にあるため、会社に不利な条件で取引が行われるリスクがあります。
第2のパターンは、取締役が第三者を代表して会社との取引を行う場合です。取締役が代表取締役を務める別会社が元の会社と契約を締結するケースが典型例です。この場合、取締役は第三者(別会社)の利益のために行動するため、やはり会社の利益が犠牲になる可能性があります。
第3のパターンは、取締役が第三者の代理人として会社との取引を行う場合です。例えば、取締役が親族の代理人として会社と売買契約を結ぶような場合がこれに該当します。
契約当事者と代表者から見る判断基準
直接取引に該当するかどうかの判断で最も重要なのは、「誰が会社を代表して契約を締結するか」という点です。ここでいう「代表」とは、必ずしも代表取締役である必要はなく、当該契約について会社を代表する権限を持つ者を指します。
実務的には、契約書の署名捺印欄の記載を確認することで判断できます。例えば、A社の取締役BがB自身の会社C社とA社との間で売買契約を締結する場合を考えてみましょう。
契約書に「買主 株式会社A 代表者B、売主 株式会社C 代表者B」と記載される場合、BはA社とC社の両方を代表しているため、両社において利益相反取引の承認が必要となります。一方、「買主 株式会社A 代表者X、売主 株式会社C 代表者B」のように、A社を他の取締役Xが代表する場合は、BはC社を代表してC社の利益のために行動しているためB社の承認は不要ですが、A社については承認が必要となります。
この判断基準は、利益相反のリスクが「代表権の行使」という行為を通じて現実化するという考え方に基づいています。
直接取引に該当しない取引の見分け方
形式的には直接取引のように見えても、実際には利益相反取引の規制対象とならない取引があります。これらを適切に見分けることで、不要な承認手続きを避けることができます。
まず、会社に損害が発生する危険性がない取引は規制対象外です。取締役が会社に対して無利息・無担保で金銭を貸し付ける場合や、取締役が会社に無償で贈与を行う場合などがこれに該当します。これらの取引では、会社は利益を得るのみで損害を被ることがないためです。
次に、取締役が一般顧客として通常の条件で会社の商品やサービスを購入する場合も規制対象外です。この場合、取締役の地位を利用した不当な取引ではないため、利益相反の問題は生じません。
また、100%株主である取締役が会社との間で取引を行う場合や、全株主の同意がある場合も承認手続きが不要とされています。これらのケースでは、実質的に利害の対立が存在しないか、株主の利益保護という規制の目的が既に達成されているためです。
間接取引に該当する見落としがちな取引類型
間接取引は、会社と第三者との間で契約が締結されるものの、その取引により取締役にメリットが生じ、会社にデメリットが発生する取引です。直接取引と比べて該当性の判断が困難であり、実務では見落とされがちな取引類型でもあります。外形的・客観的に見て利益の相反が生じているかどうかが判断の分かれ目となります。
会社による取締役の債務保証・担保提供
間接取引の最も典型的な例は、会社が取締役の個人的な債務について保証や担保提供を行う場合です。
- 債務保証:取締役の借入金を会社が保証
- 担保提供:取締役の債務に会社資産で担保設定
- 債務引受:取締役の債務を会社が引き受け
- 多額借財:保証額が多額の借財に該当する場合
債務保証の場合、会社と金融機関等の債権者との間で保証契約が締結されます。この取引により、取締役は保証という経済的なメリットを享受する一方で、会社は保証債務というリスクを負担することになります。判例でも、このような債務保証は間接取引として承認が必要であることが確立されています。
担保提供についても同様です。取締役の借入金について会社が不動産に抵当権を設定する場合や、会社の預金債権に質権を設定する場合などが該当します。また、会社が取締役の債務を引き受ける債務引受も間接取引に該当します。
これらの取引では、取締役自身が契約当事者とならないため一見すると利益相反に見えませんが、実質的には取締役の利益のために会社がリスクを負担する構造となっているため、厳格な承認手続きが求められます。
なお、債務保証等が「多額の借財」に該当する場合は、利益相反取引の承認とは別に、取締役会決議が必要となる点にも注意が必要です。
取締役の親族・関連会社が関わる取引の該当性
間接取引として見落とされがちなのが、取締役の親族や関連会社が関わる取引です。
取締役の配偶者や子などの親族の債務について会社が保証を行う場合、形式的には取締役本人の債務ではありませんが、家族としての経済的利益の一体性を考慮すると、実質的に取締役が利益を享受していると評価される可能性があります。判例でも、このような親族の債務保証について間接取引に該当するとの判断が示されています。
関連会社との取引についても注意が必要です。取締役が全株式を所有する他の会社の債務を元の会社が保証する場合、その他の会社の利益は実質的に取締役の利益と同視できるため、間接取引に該当すると考えられています。
一方で、取締役が単に取締役を兼任しているだけで、実質的な支配関係がない会社との取引については、類型的に利益相反の危険性があるとは言えないため、間接取引には該当しないとする見解もあります。この点については、取締役の関与の程度や支配関係の実態を個別に検討する必要があります。
実務では、取締役と関連する人物や法人との取引について、形式的な関係性だけでなく、実質的な利益享受の有無を慎重に判断することが重要です。
利益相反取引の承認手続き|5つの必須ステップ
利益相反取引を適法に実行するためには、会社法で定められた承認手続きを正確に実施することが不可欠です。手続きを誤ると取引が無効となるリスクや、取締役の損害賠償責任が発生する可能性があります。以下の5つのステップに従って、確実に手続きを進めましょう。
ステップ1|該当性判断と承認要否の確認
最初のステップは、予定している取引が利益相反取引に該当するかどうかを正確に判断することです。直接取引と間接取引の定義に照らし合わせ、会社と取締役の利益が実質的に対立する構造になっているかを検討します。
該当性の判断では、取引の形式だけでなく実質的な利益享受の有無を慎重に評価する必要があります。取締役本人が契約当事者とならない場合でも、親族や関連会社を通じて間接的に利益を享受する可能性がある場合は規制対象となります。判断に迷う場合は、安全側に立って承認手続きを経ることが実務上の鉄則です。
また、100%株主である取締役との取引や全株主の同意がある場合など、承認手続きが不要とされる例外的なケースに該当するかどうかも確認します。
ステップ2|重要事実の整理と開示資料の準備
利益相反取引の承認を受けるためには、取締役会または株主総会において重要事実を開示する必要があります。重要事実とは、承認するかどうかを判断するために必要となる具体的な取引内容に関する情報です。
開示すべき重要事実には、取引の相手方、取引の目的・内容、取引条件(価格、支払方法、期間等)、取引の必要性・合理性、会社への影響(メリット・デメリット)などが含まれます。特に取引価格については、第三者間取引との比較や適正価格であることの根拠を明確にすることが重要です。
これらの情報を整理し、取締役会議事録や株主総会議事録に記載できる形で準備します。口頭での説明だけでなく、書面による資料も併せて用意することで、より丁寧な検討が可能となります。
ステップ3|取締役会での承認取得(特別利害関係者の除外)
取締役会設置会社では、取締役会において利益相反取引の承認決議を行います。この際、最も重要な注意点は、利益相反取引を行う取締役が特別利害関係者として決議に参加できないことです。
当該取締役は議決権を行使できないだけでなく、会社法第369条1項の規定により、決議の定足数を計算する際の母数となる「議決に加わることができる取締役」の数からも除外されます。このため、取締役の構成によっては、特別利害関係取締役を除くと残りの取締役の数が定足数を満たさなくなり、決議自体が不可能になる「定足数消滅」という事態に陥るリスクがあります。この実務上の重要なリスクを理解することが不可欠です。取締役会議事録には、特別利害関係者である取締役が決議に参加していないことを明確に記載する必要があります。
一方、取締役会非設置会社では株主総会での承認となります。この場合、当該取締役が株主であっても議決権を行使することは可能ですが、著しく不当な決議となった場合は取消事由となる可能性があります。
ステップ4|取引実行と適切なタイミングの見極め
承認決議を得た後、実際の取引を実行します。承認決議は取引実行前に行うのが原則ですが、重要事実の開示が事前になされていれば、承認決議自体は取引後でも有効とされています。
ただし、実務上は取引実行前に承認を得ることが安全です。特に不動産取引など登記が必要な取引では、登記申請時に承認決議の議事録を添付する必要があるため、事前の承認が必須となります。
取引実行時には、承認された内容と実際の取引内容が一致していることを確認します。承認時の条件と異なる取引を行う場合は、改めて承認を得る必要があります。
ステップ5|事後報告の実施と記録の保管
取締役会設置会社では、利益相反取引を実行した後、遅滞なく取締役会に対して重要事実を報告する義務があります。この事後報告は承認の有無にかかわらず必要であり、取引の概要、結果、会社への影響などを報告します。
事後報告も取締役会議事録に記載し、適切に保管します。利益相反取引に関する全ての記録(承認決議議事録、事後報告議事録、契約書等)は、後日の検証や監査に備えて整理・保管することが重要です。
これらの記録は、取引の適法性を証明する重要な証拠となるため、法定の保管期間にわたって確実に保管する体制を整えておく必要があります。
承認手続きの実務上の留意点
利益相反取引の承認手続きには、実務上注意すべき様々なポイントがあります。会社の機関設計や株主構成、取引の背景などによって対応方法が異なるため、個別の状況に応じた適切な手続きを選択することが重要です。特に中小企業では、形式的な手続きと実質的な判断のバランスを取りながら進める必要があります。
取締役会非設置会社では株主総会議事録を作成する
取締役会を設置していない会社では、利益相反取引の承認を株主総会で行う必要があります。この場合の手続きは取締役会設置会社とは大きく異なるため、特に注意が必要です。
- 議決権行使:利益相反取引を行う取締役も参加可能
- 議事録作成:作成者により押印する印鑑が異なる
- 印鑑証明書:個人実印または法務局届出印を使用
- 資格証明書:会社法人等番号記載で省略可能
株主総会での承認では、利益相反取引を行う取締役が株主である場合でも議決権を行使することができます。これは、株主総会では株主の地位で議決権を行使するためであり、取締役としての利害関係は直接的には影響しないとされているためです。ただし、その議決権行使により著しく不当な決議となった場合は、決議取消しの対象となる可能性があります。
株主総会議事録の作成では、議事録作成者の印鑑証明書や資格証明書の添付が必要となります。代表取締役が作成者となる場合は法務局届出印を、代表取締役以外が作成者となる場合は個人実印を使用し、それぞれの印鑑証明書を添付します。また、登記申請を伴う取引では、会社法人等番号の記載により資格証明書の添付を省略することも可能です。
100%株主・全員同意の場合は承認手続きを省略する
利益相反取引の規制は株主の利益保護を目的としているため、株主に不利益が生じない場合や株主が承諾している場合は、例外的に承認手続きが不要とされています。
最も明確なケースは、取締役が会社の100%株主である場合です。この場合、取締役の利益と会社の利益(≒株主の利益)が完全に一致するため、利益相反の問題が生じません。判例でも、このような取引について承認手続きは不要であることが確立されています。
また、利益相反取引について全株主の同意がある場合も、実質的に承認があったものと同視できるため、正式な承認決議は不要とされています。ただし、実務上は後日の争いを避けるため、全株主の同意書を作成するか、通常の承認決議を経ることが推奨されます。
完全親子会社間の取引は、株主が同一であるため実質的な利害対立がないとされ、利益相反取引の承認手続きは原則として不要です。しかし、この説明には「債権者保護」という重要な視点が欠けています。例えば、子会社の資産が不当に親会社へ流出するような取引は、子会社の債権者を害する可能性があり、その場合、子会社の取締役が善管注意義務違反等の責任を問われるリスクがあります。不動産登記では、承認決議議事録の代わりに完全親子会社関係を証する書面を添付することになります。
事業承継やM&A時には利益相反の洗い出しを徹底する
事業承継やM&Aを検討する際は、過去の利益相反取引について徹底的な洗い出しを行うことが重要です。これらの場面では、会社の法的リスクが詳細に検討されるため、承認手続きを経ていない利益相反取引が発見されると大きな問題となる可能性があります。
事業承継では、先代経営者が個人と会社の区別を曖昧にして取引を行っていたケースが多く見られます。不動産の貸借、資金の貸借、車両の使用、保証債務の提供など、様々な取引について利益相反該当性を検討し、必要に応じて事後承認の手続きを行う必要があります。
M&Aにおいては、買収監査(デューデリジェンス)の過程で利益相反取引の有無が精査されます。承認手続きを経ていない取引が発見された場合、取引価格への影響や、クロージング前の是正措置を求められることがあります。このため、M&A検討開始前に利益相反取引の総点検を行い、必要な手続きを完了させておくことが重要です。
また、将来的な利益相反取引についても、一定の範囲で包括的な承認を得ることも可能です。ただし、包括承認の場合でも、個別の取引内容や条件が承認時の想定と大きく異なる場合は、改めて個別承認を得る必要があります。包括承認を行う際は、対象取引の範囲、条件、期間などを明確に定め、定期的な見直しを行う体制を整えることが求められます。
承認を得ずに実行した場合の法的リスクと対処法
利益相反取引について適切な承認手続きを経ずに実行してしまった場合、様々な法的リスクが発生します。しかし、全てが致命的な結果に繋がるわけではなく、適切な対処によりリスクを軽減することが可能です。重要なのは、リスクの内容を正確に理解し、迅速かつ適切な対応を取ることです。
取引の無効リスクと相手方の善意・悪意の立証
承認を得ていない利益相反取引は、原則として無効となるリスクを抱えています。ただし、取引の無効を主張できるのは会社側のみであり、取締役や取引相手方から無効を主張することはできません。これは、利益相反取引の規制が会社の利益保護を目的としているためです。
直接取引で取締役本人が契約当事者となっている場合、会社は無効を主張することができます。一方、取締役が第三者を代表・代理して行った取引や間接取引の場合は、相手方の保護の観点から、会社が無効を主張するためには一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、会社が相手方に対して取引の無効を主張するためには、相手方が承認手続きを経ていないことを知っていた(悪意)ことを会社側が主張立証しなければなりません。相手方が承認の有無について知らなかった(善意)場合は、取引の安全保護の観点から、会社は無効を主張できないことになります。
この立証は実務上困難な場合が多く、特に相手方が一般的な企業である場合、会社内部の承認手続きの有無を知ることは通常期待できないため、多くのケースで取引は有効として扱われることになります。
取締役の損害賠償責任と免責の可否
承認を得ずに利益相反取引を行った取締役の損害賠償責任は、会社法上、取引の類型に応じて重さが異なる階層的な構造になっています。
階層1:任務懈怠の「推定」(会社法第423条3項)
利益相反取引によって会社に損害が生じた場合、関与した取締役は「任務を怠ったものと推定」され、自ら過失がなかったことを証明しない限り責任を負います。
階層2:「無過失責任」(会社法第428条1項)
さらに、「自己のために」直接取引を行った取締役は、過失がなくても損害賠償責任を負うという、極めて重い「無過失責任」が課されます。この責任は原則として一部免除も認められません。
事後承認による治癒の可能性と実務対応
承認手続きを経ずに実行された利益相反取引であっても、事後的に適切な承認を得ることで、取引を遡って有効にすることが可能とされています。この事後承認は、発覚したリスクを治癒する重要な手段となります。
事後承認を行う場合も、通常の承認手続きと同様の手続きが必要です。取締役会設置会社では取締役会決議を、非設置会社では株主総会決議を経る必要があります。承認の際は、既に実行された取引の具体的内容、会社への影響、承認の必要性などを詳細に説明し、十分な検討を経た上で決議を行います。
事後承認により取引は遡及的に有効となりますが、それまでの期間における法的リスクが完全に消滅するわけではありません。特に、既に第三者の権利が発生している場合や、取引の無効を前提とした法的措置が取られている場合は、事後承認だけでは解決できない問題が残る可能性があります。
実務的な対応としては、利益相反取引の可能性が発覚した時点で、速やかに該当性の検討を行い、必要に応じて事後承認の手続きを実施することが重要です。また、将来的な再発防止のため、利益相反取引に関する社内規程の整備や、定期的なチェック体制の構築も併せて検討する必要があります。
不動産登記など公的手続きを伴う取引の場合は、事後承認の議事録を速やかに作成し、必要な登記手続きを完了させることで、第三者への対抗要件を確保することも重要な対応となります。
まとめ|利益相反取引の適切な管理で法的リスクを回避
利益相反取引は中小企業の重要な法務リスクですが、適切な手続きを理解することで回避できます。最も重要なのは予防的対策であり、事前の該当性判断と5つの必須ステップに従った承認手続きの実施により、法的リスクを未然に防げます。
万が一承認を得ずに実行した場合でも、事後承認を得ることで取引が有効となる場合があります。特にM&Aや事業承継では過去の利益相反取引の洗い出しが重要となります。継続的な管理体制の構築により、健全な経営基盤を確立し、将来の事業価値向上に繋げることができます。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。