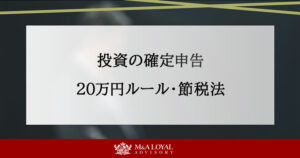総合課税と申告分離課税の違いやメリット・デメリットを徹底解説!
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
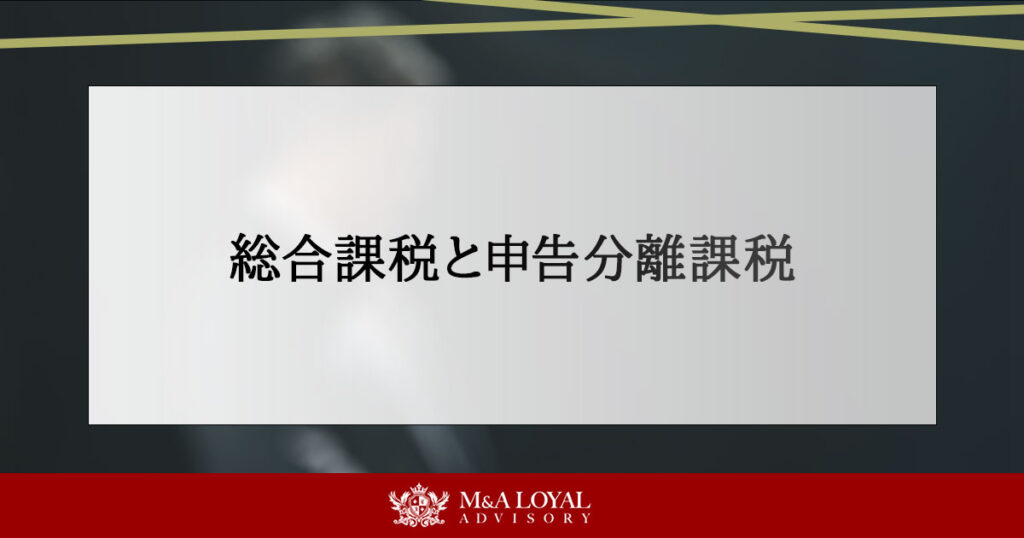
所得税の課税方式には大きく「総合課税」と「申告分離課税」の2種類に分かれ、どちらが適用されるかで税負担は大きく変わります。給与所得者でも株式投資やM&Aに関わる場合、この違いを理解することは節税や適切な税務処理において極めて重要です。特に中小企業の経営者や投資を行っている方にとって、課税方式の選択は手取り額に直結する重要な判断となります。本記事では、「総合課税」と「申告分離課税」それぞれの仕組みや対象所得、税率の違い、確定申告での選択ポイントまで、実務で活用できる知識を分かりやすく解説します。総合課税と申告分離課税を理解し、適切な税務戦略を立てるための参考にしてください。
目次
総合課税と分離課税(申告分離・源泉分離)の基本的な違い
所得税には大きく分けて「総合課税」と「分離課税」という2つの課税方式があります。この2つの方式は、所得の性質や政策的な配慮により使い分けられており、納税者の税負担に大きな影響を与えます。特に中小企業のM&Aや投資活動を行う際には、どちらの課税方式が適用されるかを理解することが、適切な税務戦略を立てる上で極めて重要です。
総合課税は所得を合算して税額を計算する仕組み
総合課税とは、1年間に得たすべての所得を合算し、その総額に対して超過累進税率を適用して税額を計算する仕組みです。給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得などが対象となり、これらの所得金額を足し合わせた後、各種所得控除を差し引いた課税所得金額に税率をかけて計算します。
例えば、給与所得が500万円、不動産所得が200万円ある場合、両方を合算した700万円から所得控除を差し引いた金額に対して税率が適用されます。総合課税では所得が高くなるほど税率も高くなる累進課税制度が採用されており、5%から最大45%まで7段階の税率が設定されています。
申告分離課税は個別に税額を計算する仕組み
申告分離課税とは、特定の所得について他の所得と合算せず、個別に定められた税率で課税する仕組みです。株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、先物取引による雑所得などが対象となり、それぞれの所得に応じて個別の税率が適用されます。
この制度が設けられている主な理由は、退職金や株式の売却益のように一時的に高額な所得が生じた場合、総合課税で計算すると税負担が過度に重くなることを防ぐためです。加えて、株式や不動産といった資産への長期投資を促すために安定した税率を設定することや、特定の所得(預貯金の利子など)については源泉徴収で課税を完結させ、徴税手続きを簡素化・効率化するといった政策的な目的もあります。
申告分離課税では所得の金額に関係なく一定の税率が適用されるため、高額所得者にとって税負担の軽減効果があります。確定申告での手続きが必要ですが、総合課税の他の所得とは分離して計算されます。
各課税方式の特徴を整理すると以下のようになります。
| 課税方式 | 税率 | 確定申告 | 損益通算 |
| 総合課税 | 5%~45% | 必要 | 可能(4種類の所得) |
| 申告分離課税 | 所得別に一定 | 必要 | 制限あり |
| 源泉分離課税 | 所得により異なる(預貯金利子等は20.315%) | 不要 | 不可 |
源泉分離課税は天引きで課税が完了する仕組み
源泉分離課税とは、所得の支払い時に一定の税率で所得税を天引きし、それで課税関係が完結する仕組みです。預貯金の利子所得、定期積金の給付補てん金、一定の保険の差益などが対象となり、支払者が所得税を源泉徴収して税務署に納付します。
源泉分離課税の最大の特徴は、確定申告が不要である点です。所得を受け取る側は、既に税金が差し引かれた金額を受け取るため、追加の手続きは必要ありません。税率は一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)が適用されることが多く、手続きの簡素化と確実な徴税を実現する制度として位置づけられています。
総合課税の対象となる8つの所得と税率
総合課税では、複数の所得を合算して税額を計算するため、どの所得が対象となるかを正確に把握することが重要です。国税庁の規定では所得は10種類に区分されており、そのうち退職所得と山林所得を除く8種類が原則として総合課税の対象となり、これらの所得金額を合計した総所得金額に対して超過累進税率が適用されます。
総合課税は給与所得・事業所得・不動産所得などが対象
総合課税の対象となる8つの所得は以下の通りです。給与所得は会社員の給料や賞与から給与所得控除を差し引いた金額、事業所得は個人事業主の事業による利益、不動産所得はアパートやマンションの家賃収入などが該当します。
・給与所得:会社からの給料・賞与・役員報酬
・事業所得:製造業・小売業・サービス業などの事業による所得
・不動産所得:土地・建物の貸付による家賃収入
・利子所得:源泉分離課税分を除く預貯金利子
・配当所得:確定申告を選択した株式配当
・譲渡所得:土地・建物・株式等を除く資産の譲渡
・一時所得:懸賞金・生命保険満期金など
・雑所得:年金・原稿料・講演料など
中小企業M&Aにおける事業譲渡による対価も事業所得として総合課税の対象となる場合があります。これらの所得は合算されて課税されるため、複数の所得がある場合は税負担が累進的に増加します。
総合課税は超過累進税率により5%から45%まで7段階で課税
総合課税では、課税所得金額に応じて税率が段階的に上昇する超過累進税率が適用されます。具体的な税率構造は以下の通りです。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
この仕組みにより、所得が高くなるほど実効税率も高くなり、高額所得者ほど重い税負担を負うことになります。例えば、課税所得が1,000万円の場合、最初の195万円部分は5%、次の135万円部分は10%というように、それぞれの所得区分ごとに該当する税率が適用されて計算されます。
住民税10%を加えると最大55%の税負担
所得税に加えて、住民税として一律10%(都道府県民税4%と市町村民税6%)が課税されるため、総合課税による実際の税負担はさらに重くなります。
所得税の最高税率45%と住民税10%を合わせると、最大の実効税率は約55%となります。より正確には、復興特別所得税は所得税額に対して2.1%が課されるため、[所得税45% + 復興特別所得税(45%×2.1%=0.945%)] + 住民税10% = 55.945% となります。
この高い税率は、特に中小企業のM&Aにおける事業譲渡や、短期間で大きな利益を得た場合に大きな負担となります。復興特別所得税(所得税額の2.1%)も加わるため、実際の税負担はさらに増加し、税務戦略の重要性が高まります。適切な事業承継や資産承継の計画を立てることで、この重い税負担を軽減することが可能です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



申告分離課税が適用される所得の種類
申告分離課税は、一時的な高額所得や特別な性質を持つ所得について、他の所得と合算せずに個別の税率で課税する制度です。特に投資や事業売却による所得に多く適用され、総合課税で計算した場合の過度な税負担を回避する目的があります。
申告分離課税の主な対象所得は以下の通りです。
・株式等の譲渡所得:20.315%の一律税率
・土地・建物の譲渡所得:所有期間により税率が変動
・退職所得:退職所得控除と1/2課税の適用
・山林所得:5分5乗方式による計算
・FX・先物取引の雑所得:20.315%の一律税率
これらの所得はそれぞれに特定の税率と計算方法が定められており、所得の性質に応じた適切な課税が行われます。
株式等の譲渡所得は一律20.315%で課税
株式等の譲渡所得は申告分離課税の代表例で、上場株式・非上場株式を問わず一律20.315%の税率が適用されます。その正確な内訳は、所得税15%、住民税5%、そして復興特別所得税0.315%(所得税額15%の2.1%)です。この税率の内訳は所得税15%、住民税5%、そして所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税0.315%(15% × 2.1%)であり.、譲渡益の金額に関係なく一定の税率となっています。
譲渡所得の計算は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」で行われ、株式の取得価額や売買委託手数料なども必要経費として控除できます。株式投資による利益が総合課税の対象となった場合、高額所得者では最大55%の税率となる可能性があるため、申告分離課税の恩恵は極めて大きいといえます。
※参照:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
M&Aによる株式譲渡も申告分離課税の対象
中小企業のM&Aにおける株式譲渡についても、申告分離課税が適用されます。会社売却により創業者や経営者が株式を譲渡した場合、その譲渡益に対して20.315%の税率で課税され、他の所得と合算されることはありません。
ただし、令和7年(2025年)分以降の所得からは「ミニマムタックス」制度が導入されます。これは、申告不要を選択した所得なども含めた年間所得から特別控除3.3億円を差し引いた金額に22.5%を乗じた額(最低所得税額)が、通常の計算による所得税額を上回る場合に、その差額が追加で課税される仕組みです。
この制度により、極めて高額なM&A取引では実質的な税率が27.5%まで上昇する可能性があります。
土地・建物の譲渡所得は所有期間で税率が変化
不動産の譲渡所得も申告分離課税の対象となり、所有期間の長さによって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定します。この時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得として税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、5年以下の場合は短期譲渡所得として税率39.63%(所得税30.63%、住民税9%)が適用されます。
マイホームの売却では3,000万円の特別控除や軽減税率の特例があり、所有期間が10年を超える居住用財産については6,000万円以下の部分に14.21%(所得税10.21%、住民税4%)の軽減税率が適用されます。これらの特例により、実際の税負担を大幅に軽減することが可能です。
※参照:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
FX・先物取引の雑所得も申告分離課税の対象
外国為替証拠金取引(FX)や商品先物取引による利益は、雑所得として申告分離課税の対象となります。税率は株式譲渡所得と同様に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が適用され、取引による損益を通算して申告します。
これらの取引では3年間の損失繰越が認められており、当年の利益と相殺しきれない損失は翌年以降に繰り越すことができます。ただし、損失繰越を適用するためには取引の有無に関わらず継続して確定申告を行う必要があります。
退職所得・山林所得にも分離課税が適用
退職所得は申告分離課税の対象となり、「(退職金-退職所得控除額)×1/2」で計算された課税退職所得金額に、総合課税と同じ税率表(速算表)を適用して税額を計算します。ただし、この「2分の1課税」には重大な例外があります。勤続年数5年以下の役員等が受け取る退職金には、この2分の1課税が一切適用されません。また、2022年分以降、勤続年数5年以下の一般従業員が受け取る退職金についても、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分には2分の1課税が適用されなくなりました。
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。
山林所得は5分5乗方式により計算され、「課税山林所得金額の1/5×総合課税の税率×5」で税額を求めます。これは山林の成長期間が長期にわたることを考慮した特別な計算方法で、一時的な高額所得による税負担の集中を緩和する効果があります。
※参照
・国税庁「No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)」
・国税庁「No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)(令和4年1月1日以後)」
総合課税と申告分離課税のメリット・デメリット比較
総合課税と申告分離課税には、それぞれ異なる特性があり、納税者の所得状況や投資戦略によってその影響は大きく変わります。適切な課税方式を選択するためには、両者のメリット・デメリットを十分に理解し、自身の状況に最適な選択を行うことが重要です。特に中小企業のM&Aや資産運用を検討している方にとって、この違いは将来の税負担に大きく影響します。
総合課税のメリット:損益通算による節税効果
総合課税の大きな特徴の一つは、特定の所得で発生した損失を他の所得と相殺(損益通算)できる点です。不動産所得、事業所得、譲渡所得(限定的な場合のみ)で発生した損失は、給与所得などの他の黒字所得と相殺することが可能です。ただし、損益通算にはいくつかの制限があり、以下のようなケースでは相殺が認められないことがあります。
- 土地の取得にかかる借入金の利子
- 生活用動産(家具や車など)の譲渡による損失
- 株式譲渡損失や山林所得など、分離課税対象の所得
例えば、事業所得で100万円の損失が発生した場合、給与所得1,000万円から100万円を差し引いた900万円が課税所得となり、税負担を軽減することができます。ただし、分離課税に属する所得(山林所得や株式の譲渡損失など)については、原則として損益通算の対象外であるため注意が必要です。また、控除しきれなかった損失については、一定の条件を満たせば翌年以降への繰越控除が可能です。
損益通算や繰越控除の適用条件は複雑な場合があるため、具体的な内容については税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
この損益通算の効果は、特に複数の事業を展開している経営者や不動産投資を行っている個人にとって非常に有効です。アパート経営による不動産所得の赤字を給与所得と相殺したり、新規事業の立ち上げ費用による事業所得の損失を他の所得から控除したりすることで、全体の税負担を最適化することが可能になります。
総合課税のデメリット:所得が増えると最大55%の税率
総合課税の大きなデメリットは、超過累進税率により所得が増加するほど税率が急激に上昇することです。所得税は5%から45%まで7段階に分かれており、住民税10%と合わせると最大55%の実効税率となります。課税所得が4,000万円を超える場合、所得税率45%に復興特別所得税2.1%も加わるため、実際の税負担はさらに重くなります。
この高い税率は、特に一時的に高額所得が発生する場合に大きな負担となります。事業が成功して利益が急増した個人事業主や、不動産売却により一時所得が発生した場合など、その年の所得が大幅に増加すると、税負担も比例して重くなるため、長期的な税務戦略を立てることが重要です。
申告分離課税のメリット:高額所得でも税率20.315%で一定
申告分離課税の最大のメリットは、所得金額に関係なく一定の税率が適用されることです。株式譲渡所得や不動産譲渡所得(長期譲渡所得の場合)の多くには、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の一律税率が適用されるため、譲渡益が1億円でも10億円でも税率は変わりません。これは、総合課税の累進税率と比較して、高額所得者にとって大きな税負担軽減効果があります。
また、特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、原則として確定申告が不要となり、手続きの簡素化が図れます。ただし、他の証券会社の口座との損益通算や、過去の譲渡損失の繰越控除を利用する場合には、確定申告が必要となることがあります。特定口座の源泉徴収により、投資による利益が年間を通じて20.315%で徴収されるため、複雑な計算や手続きから解放され、投資活動に専念できるメリットがあります。
申告分離課税のデメリット:他の所得との損益通算が不可
申告分離課税の主なデメリットは、総合課税の対象となる他の所得との損益通算ができないことです。ただし、同じ申告分離課税のカテゴリー内(例:上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得)での損益通算は可能です。株式投資で大きな損失が発生しても、給与所得や事業所得から控除することはできません。同じ申告分離課税内での損益通算は可能ですが、総合課税の所得とは完全に分離されているため、税務上の柔軟性が制限されます。
ただし、上場株式等の譲渡損失については3年間の繰越控除が認められており、翌年以降の譲渡益と相殺することが可能です。この制度を活用するためには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。また、配当所得について申告分離課税を選択すれば、株式の譲渡損失との損益通算も可能になります。
中小企業M&Aで申告分離課税を選択する税務上の利点
中小企業のM&Aにおいて株式譲渡を選択する場合、申告分離課税の恩恵は極めて大きくなります。創業者や経営者が長年経営してきた会社を売却する際、株式譲渡益が数億円から数十億円に達することも珍しくありません。この場合、総合課税であれば最大55%の税率が適用される可能性がありますが、申告分離課税なら一律20.315%で済みます。
例えば、株式譲渡益が5億円の場合、申告分離課税では税負担が約1億158万円(5億円 × 20.315%)となります。一方、仮にこれが総合課税の対象となった場合、所得税(復興特別所得税含む)と住民税を合わせた最高税率(約55.9%)が適用されると、税負担は約2億7,973万円((5億円×45%-479.6万円)×1.021 + 5億円×10%)となり、その差は1億7,800万円以上に達します。
ただし、2025年以降はミニマムタックスが導入されるため、極めて高額な譲渡益については実質的な税率が上昇する可能性があります。それでも申告分離課税の優位性は変わらず、M&Aを検討する経営者にとって重要な税務メリットとなっています。
さらに、株式譲渡では会社の資産や負債がそのまま承継されるため、事業譲渡に比べて手続きが簡素化され、従業員の雇用継続や取引先との関係維持も容易になります。税務面での優遇措置と合わせて、中小企業の事業承継において株式譲渡が選択される理由となっています。
確定申告で知っておくべき課税方式の選択ポイント
確定申告では、所得の種類によって適用される課税方式が決められている一方で、一部の所得については納税者が課税方式を選択できる場合があります。この選択により税負担が大きく変わるため、自身の所得状況と投資戦略を考慮した適切な判断が重要です。特に配当所得や投資による損失がある場合は、課税方式の選択によって数万円から数十万円の差が生じることもあります。
配当所得は総合課税と申告分離課税を選択可能
上場株式等の配当所得については、申告不要・総合課税・申告分離課税の3つの方法から選択できます。2023年分の所得税確定申告からは所得税と住民税で同一の課税方式を選択する必要があり、これまでのように「所得税は総合課税、住民税は申告不要」といった有利な使い分けはできなくなりました。
課税方式の選択基準は以下の通りです。
| 課税所得金額 | 有利な選択 | 理由 |
| 695万円以下 | 総合課税 | 配当控除により実効税率が低下 |
| 695万円超 | 申告分離課税 | 一律20.315%で税負担軽減 |
| 譲渡損失あり | 申告分離課税 | 損益通算による税額還付 |
総合課税を選択すると配当控除が適用され、課税総所得金額が695万円以下の場合は申告不要や申告分離課税よりも税負担が軽くなります。配当控除率は課税総所得1,000万円以下で所得税10%・住民税2.8%、1,000万円超で所得税5%・住民税1.4%となり、実効税率を大幅に下げる効果があります。
しかし、総合課税を選択すると合計所得金額が増加するため、配偶者控除や扶養控除への影響、国民健康保険料の増加なども考慮する必要があります。特に国民健康保険料への影響は重大で、総合課税で申告した配当所得は保険料の算定基礎に含まれます。所得水準によっては、配当控除による節税額よりも国民健康保険料の増加額が上回り、結果的に手取り額が減少するケースも少なくないため、申告前に必ずシミュレーションを行うことが極めて重要です。
申告分離課税を選択する最大のメリットは、株式の譲渡損失との損益通算が可能になることです。投資で損失が発生している場合、配当所得を申告分離課税で申告すれば、損失と相殺して源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
上場株式等の譲渡損失は3年間の繰越控除が可能
株式投資で発生した譲渡損失は、その年の配当所得等と損益通算した後、控除しきれない金額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。この繰越控除を受けるためには、損失が発生した年から3年間、毎年継続して確定申告を行う必要があります。取引がない年があっても申告を怠ると繰越控除の権利が消失するため注意が必要です。
繰越控除の対象となるのは、上場株式等の譲渡所得および配当所得(申告分離課税を選択したもの)です。損失の繰越は古いものから順次控除され、3年経過した損失は自動的に消滅します。例えば、2024年に100万円の譲渡損失が発生した場合、2025年から2027年までの3年間、この損失を譲渡益や配当所得から控除することが可能です。
特定口座(源泉徴収あり)内で発生した譲渡損失についても、確定申告をすることで他の口座の利益との損益通算や繰越控除が適用できます。複数の証券会社で取引している場合は、各社の年間取引報告書を確認し、損益を合算した上で最適な申告方法を選択することが重要です。
※参照:国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告が不要
特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、株式の譲渡益や配当所得について確定申告が不要となります。証券会社が自動的に20.315%の税率で源泉徴収し、年間を通じて損益通算も行うため、投資家の手続き負担が大幅に軽減されます。同一口座内で複数銘柄の売買を行った場合も、利益と損失が自動的に相殺され、最終的な税額が計算されます。
配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定すれば、配当金も特定口座で受け取ることができ、同一口座内の譲渡損失との損益通算も自動的に行われます。これにより確定申告をしなくても、効率的な税務処理が可能になります。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、他の証券会社での損失との通算や3年間の繰越控除を受けるためには確定申告が必要です。また、配当所得について総合課税で配当控除の適用を受けたい場合も確定申告が必要となります。投資戦略と税務上の効果を総合的に判断し、申告の要否を決定することが重要です。
M&A実行時は税理士への事前相談が重要
中小企業のM&Aを検討している場合、株式譲渡による税務影響は極めて複雑で専門的な判断が必要となります。特に2025年以降はミニマムタックスが導入されるため、年間所得から特別控除3.3億円を差し引いた金額に22.5%を乗じた額が通常の所得税額を上回る場合、追加課税が発生します。この制度により、高額なM&A取引では実質的な税率が最大27.5%まで上昇する可能性があります。
M&Aの税務戦略では、譲渡時期の調整、複数年での分割譲渡、事業承継税制の活用など、様々な選択肢があります。株式譲渡以外にも事業譲渡や会社分割などの手法があり、それぞれ税務上の取り扱いが異なるため、事前に十分な検討が必要です。また、買い手企業との交渉においても、税務効率を考慮した取引条件の設定が重要になります。
税理士への相談は、M&Aの検討段階から始めることが推奨されます。企業価値の算定、最適なM&Aスキームの選択、税務デューデリジェンスの実施、契約条件の税務的検証など、包括的なサポートを受けることで、税務リスクを最小化しながら最適な事業承継を実現することが可能になります。M&Aは経営者にとって一生に一度の重要な決断であるため、税務面での適切なアドバイスを受けることが成功の鍵となります。
まとめ|総合課税と申告分離課税を理解して適切な税務処理を
総合課税と申告分離課税は、それぞれ異なる特性を持つ重要な税務制度です。総合課税は各種所得を合算して超過累進税率(5%~45%)で課税する仕組みで、損益通算による節税効果が期待できる一方、所得が高くなるほど税負担も重くなります。これに対して申告分離課税は、特定の所得を他の所得と分離して一定の税率で課税する制度で、高額所得でも税率が一定である点が大きなメリットとなります。
中小企業のM&Aにおいて株式譲渡を選択する場合、申告分離課税の税率は一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)であるため、累進課税が適用される総合課税に比べて税負担を大幅に軽減できるケースが多いです。創業者や経営者が会社を売却する際の株式譲渡益は、原則として申告分離課税の対象となります。
ただし、非上場株式の譲渡益については、「事業承継税制」などの特例が適用される場合があります。これらの特例には厳格な条件があるため、事前に税務専門家に確認することが重要です。また、株式譲渡損失が発生した場合は、他の株式譲渡益や配当所得と損益通算が可能ですが、総合課税の所得とは相殺できない点に注意が必要です。
また、2025年以降に国際的な税制改正や国内税制の見直しが行われる可能性があり、極めて高額な譲渡益については新たな税負担が発生する可能性があります。そのため、事前の税務戦略を立てることが、譲渡益にかかる税負担を最小化するための重要なポイントとなります。
確定申告では、配当所得について総合課税と申告分離課税の選択が可能です。課税所得が695万円以下の場合は配当控除を活用できる総合課税が有利ですが、株式の譲渡損失がある場合は申告分離課税を選択して損益通算を行う方が効果的です。また、株式投資で発生した譲渡損失は3年間の繰越控除が可能ですが、これを活用するためには損失発生年から継続して確定申告を行う必要があります。
これらの税務制度を適切に活用するためには、自身の所得状況と投資戦略を総合的に判断することが不可欠です。特にM&Aを検討している中小企業経営者にとって、課税方式の選択は手取り額に大きく影響するため、早期の段階から税理士などに相談することを強く推奨します。適切な税務処理により、事業承継や資産運用の効果を最大化し、長期的な資産形成に繋げることが可能になります。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。