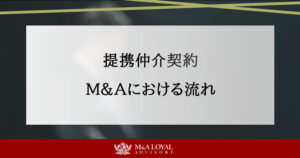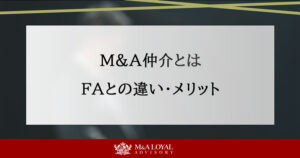M&Aアドバイザリー契約とは?報酬相場や締結時の注意点を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
M&Aを成功に導くためには、仲介会社やアドバイザーとの適切なアドバイザリー契約が不可欠です。しかし、具体的な内容や報酬相場、依頼時の注意点について詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、アドバイザリー契約の基本から、業務委託契約やコンサルティング契約との違い、さらに報酬体系や費用相場について詳しく解説します。
また、アドバイザリー契約締結時の直接交渉の禁止や秘密保持など、契約書に盛り込む条項についても触れていきます。M&Aにおけるアドバイザリー契約を正しく理解し、M&Aの成功率を高めましょう。
目次
アドバイザリー契約とは|基本をわかりやすく解説
アドバイザリー契約とは、企業が専門的な知識や経験を持つアドバイザーを雇い、その知見を活用して経営戦略や業務改善を図るための契約です。この契約形態は、特にM&A(企業の合併・買収)、資金調達、事業再編といった複雑なプロジェクトで広く活用されています。アドバイザリー契約を締結することで、企業は内部リソースだけでは対応が難しい専門的な課題に対し、外部の客観的な視点や高度なスキルを取り入れ、業務を円滑に進めることができます。
M&Aのアドバイザリー契約とは
M&Aのアドバイザリー契約とは、企業の合併や買収を円滑に進めるために、FA(ファイナンシャルアドバイザー)やM&A仲介会社と結ぶ契約のことです。この契約の主な目的は、M&Aを成功させるための戦略的なサポートを受けることにあります。アドバイザーは、M&Aプロセス全体で重要な役割を果たし、売却・買収戦略の策定、市場調査、適切な買い手や売り手の選定、交渉支援、デューデリジェンスの実施などを行います。
アドバイザリー契約を結ぶことで、企業は専門的な知見に基づくアドバイスを受けられ、複雑な手続きや法的リスクを軽減できます。さらに、アドバイザーは企業ごとのニーズに応じたサービスを提供し、M&Aの成功率を向上させることが期待されます。
M&Aアドバイザリー契約のメリット
M&Aアドバイザリー契約のメリットは、専門的な知見や広範なネットワークを活用して、取引を円滑かつ効率的に進められる点です。経験豊富なアドバイザーがプロジェクトをリードすることで、M&Aプロセス全体の効率が大幅に向上します。アドバイザーは市場動向や業界特性を的確に把握しており、戦略的に有利な条件での取引を実現するための支援を行います。
また、アドバイザーは豊富なネットワークを活用し、買収先企業や売却先企業のリストアップを迅速に行います。このネットワークの活用により、企業は自社に最も適したパートナーを見つけやすくなり、交渉の成功率が高まります。さらに、アドバイザーは法務や財務分野の専門知識を活かし、契約書のレビューやデューデリジェンスをサポートすることで、リスクを最小限に抑えながら取引を進めることが可能です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



アドバイザリー契約と他の契約形態の違い
アドバイザリー契約とは、他の契約形態とはどう違うのでしょうか。業務委託契約やコンサルティング契約、顧問契約との違いについて触れていきます。
アドバイザリー契約と業務委託契約の違い
アドバイザリー契約とは、企業が外部の専門家やコンサルタントに対して、特定の分野における助言や指導を依頼する契約形態です。アドバイザリー契約は、業務委託契約の一部に位置づけられます。
業務委託契約は大きく「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つに分かれ、責任の範囲や達成目標が異なります。アドバイザリー契約は、法的行為を含むことが多く、その場合は委任契約に該当します。法的行為を含まない場合は準委任契約となります。
企業はこの契約を通じて、外部の専門家の知識を活用し、戦略的な意思決定を行うことができます。つまり、アドバイザリー契約と業務委託契約の違いは契約内容の具体性と業務範囲にあります。
アドバイザリー契約とコンサルティング契約の違い
アドバイザリー契約とコンサルティング契約の違いは、支援の範囲にあります。アドバイザリー契約は通常、M&A成立に向けて専門的なアドバイスを提供し、数か月~1年ほどの中長期的な関係を築くことが一般的です。
一方、コンサルティング契約は通常、ITや組織経営など特定の分野や課題に対する解決策を提供します。コンサルタントは問題の診断、解決策の提案、そしてその実行支援を行います。これにより、企業は特定の問題に対する迅速な対応が可能となります。
M&Aの場面においては、アドバイザリー契約とコンサルティング契約は同じ意味で扱われることもあるため、契約の際には名称だけでなく、業務範囲の確認が大切です。
アドバイザリー契約と顧問契約の違い
アドバイザリー契約と顧問契約は、どちらも専門的な知識や経験を活かして企業の意思決定を支援する契約形態ですが、その目的や業務内容に違いがあります。アドバイザリー契約は、特定のプロジェクトや業務に対する具体的な助言やサポートを提供することを目的としています。
例えば、M&Aのプロセスにおける戦略的なアドバイスや、取引の実行に関する具体的な支援を行うことが一般的です。この契約では、結果を出すための具体的な目標設定がなされ、通常は短期的または中期的な関与となります。
一方、顧問契約は、企業の経営全般に対する継続的なアドバイスを提供することが主な目的です。アドバイザリー契約とは異なり、特定のプロジェクトに限定されることなく、経営に関する広範な助言を長期にわたって行うことが一般的です。顧問契約では、企業の長期的な成長や安定を目指した助言が重視され、具体的な業務遂行のための指示や実行支援は含まれないことが多いです。
さらに、報酬体系にも違いがあります。アドバイザリー契約では、プロジェクトの進行や成果に応じた成功報酬が設定されることが多いのに対し、顧問契約では、月額の固定報酬が一般的です。これにより、アドバイザリー契約は数か月~1年程での成果を重視し、顧問契約は長期的な関係構築を重視する傾向があると言えます。したがって、企業が求める支援の内容や期間に応じて、適切な契約形態を選択することが重要です。
M&Aにおける契約や交渉形態の種類
M&Aのアドバイザリー契約の契約形態や交渉形態についても触れていきます。まず、契約形態には「専任契約」と「非専任契約」があり、交渉形態には「アドバイザリー方式」と「仲介方式」があります。それぞれの違いについて解説します。
専任契約
専任契約とは、アドバイザリー契約の一形態で、特定の仲介会社やアドバイザーが対象業務を専属で担当する契約です。これにより、企業はアドバイザーが自社のM&Aプロジェクトに専念するという安心感を得られます。
専任契約は、特に複雑で高額な案件で効果を発揮します。アドバイザーはクライアントのニーズを深く理解し、個別にカスタマイズされた戦略を立案・実行できます。また、1社との契約であるため、非専任契約と比べて情報漏洩のリスクが低減され、プロジェクト進行中のリスクを最小化できます。
さらに、専任契約ではアドバイザーと企業の間に強固な信頼関係が築かれやすく、円滑なコミュニケーションが可能になります。これにより、アドバイザーの専門知識やネットワークを最大限に活用し、M&Aの成功率を高めることができます。
ただし、専任契約は一度契約を締結すると、アドバイザーへの不満があっても途中で変更が難しい点に注意が必要です。そのため、契約前にアドバイザーの実績や相性を十分に確認することが重要です。
非専任契約
非専任契約とは、特定の仲介会社やアドバイザーと専属契約を結ばないアドバイザリー契約で、企業が複数のアドバイザーと同時に契約することを可能にします。非専任契約により、それぞれのアドバイザーが持つネットワークや知識を活用できる点が特徴です。
非専任契約の大きなメリットは、その柔軟性です。企業は複数のアドバイザーから異なる視点の助言を得られるため、幅広いな情報や提案を活用できます。また、特定のアドバイザーとの相性が悪かった場合でも、他のアドバイザーに切り替えやすいため、ミスマッチのリスクを低減できます。
一方で、非専任契約には注意すべき点もあります。複数のアドバイザーに依頼することで、情報漏洩のリスクが高まる可能性があります。また、複数のアドバイザーを管理する必要があるため、情報管理が煩雑になり、プロジェクトの進行が遅れる恐れもあります。そのため、非専任契約を選ぶ際には、情報共有や管理体制をしっかり整備することが重要です。
アドバイザリー方式
アドバイザリー方式とは、M&A取引において売り手または買い手の一方と専属契約を結び、その当事者に対してサポートや助言を提供する契約形態です。例えば、売り手側と契約する場合、売却戦略の策定や潜在的な買い手の選定、交渉支援などを行います。一方で、買い手側と契約する場合は、買収ターゲットの評価や条件設定、交渉支援などを行います。
アドバイザリー方式の大きな特徴は、利益相反を避けやすい点です。アドバイザーはクライアント企業に専属的に対応するため、利益を最大限に考慮した最適なアドバイスが期待できます。また、クライアント企業と強固な信頼関係を構築しやすい点もメリットです。
しかし、アドバイザリー方式では、他方の当事者の意向や動向を把握しにくくなる場合があります。そのため、取引全体を俯瞰する視点を持つことが重要です。アドバイザリー方式は、特定の当事者に集中したサポートを期待できる一方、その特性を十分に理解し、適切に運用することが成功の鍵となります。
仲介方式
仲介方式のアドバイザリー契約とは、買い手と売り手の双方に対して中立的な立場から助言を提供し、取引を円滑に進める契約形態です。アドバイザーは両者と契約を締結し、それぞれのニーズや希望を考慮しながら、取引の成功に向けた交渉や調整を行います。この方式では、アドバイザーが双方の利益を調整し、公平な視点を維持することで、合意形成をサポートします。
仲介方式の主な特徴は、双方の立場を理解し、バランスの取れた解決策を提案できる点です。これにより、取引がスムーズに進行し、双方にとって最適な結果を導くことが期待されます。また、柔軟性の高いサポートを提供できるため、取引の複雑さに応じた対応が可能です。
一方で、仲介方式には課題もあります。アドバイザーが双方と契約するため、利益相反が懸念される場合があります。そのため、アドバイザーには高い倫理基準と透明性が求められます。また、双方の期待や信頼を適切に管理し、関係性を維持することも重要です。
仲介方式は、特に双方の利益をバランスよく考慮する必要がある取引で有効です。アドバイザーの専門知識や経験が取引の成否に大きく影響するため、適切なアドバイザーの選定が鍵となります。このように、仲介方式のアドバイザリー契約は、M&Aにおいて柔軟かつ公平な取引を実現するための有力な選択肢といえます。
アドバイザリー契約の報酬体系と費用相場
M&Aアドバイザリー契約で発生する報酬体系は依頼する仲介会社やアドバイザーによって異なります。ここではアドバイザリー契約の報酬体系と費用相場について解説します。
着手金
着手金とは、アドバイザリー契約締結時に支払う初期費用です。着手金はM&Aの成約の有無にかかわらず発生し、一度支払うと返金されません。 着手金は、M&A仲介会社が調査や書類作成、候補先企業の探索などの活動における初期コストをカバーする費用です。着手金の相場は案件規模によって異なりますが、50万円〜200万円程度が一般的です。
ただし、近年はM&A市場の競争激化により「着手金無料」を掲げる仲介会社も増えています。成功報酬のみでコストをまかなう報酬体系となるため、最終的な総コストの比較が重要です。
中間報酬
中間報酬とは、M&A交渉が一定段階まで進んだ時点で発生する報酬です。一般的には基本合意書の締結時に支払われ、成功報酬の一部を先払いする形となります。
中間報酬の金額は最終的な成功報酬の10%〜20%程度、あるいは定額で100万円〜250万円程度に設定されることが多いです。M&A仲介会社はこの段階で多くの工数を投入するため、途中で案件が破談になった場合のリスクヘッジとして中間報酬を設定しています。
着手金同様、近年は中間報酬を設定しない仲介会社も増えており、料金体系の簡素化が進んでいます。
月額報酬(リテイナーフィー )
月額報酬(リテイナーフィー)とは、契約期間中に毎月定額を支払う報酬です。売り手・買い手企業の分析や候補先の探索、面談などの活動費用として設定されます。中小企業の場合、一般的に月額50万円〜200万円程度です。M&Aの進行が長期化すればするほど総支払額も増加します。
M&A市場の競争激化により、近年では月額報酬を無料とする仲介会社も増えています。報酬体系を比較する際には月額報酬の有無と期間も考慮しましょう。
成功報酬
成功報酬とは、M&A成立時に支払う費用です。多くの仲介会社では「レーマン方式」と呼ばれる段階的な料率テーブルを採用しています。
一般的な料率は以下のとおりです。
- 取引金額が5億円以下の部分:5%
- 取引金額が5億円超〜10億円以下の部分:4%
- 取引金額が10億円超〜50億円以下の部分:3%
- 取引金額が50億円超〜100億円以下の部分:2%
- 取引金額が100億円超の部分:1%
例えば、取引金額が8億円の場合、成功報酬は「5億円×5%=2,500万円」と「3億円×4%=1,200万円」の合計3,700万円となります。
ただし、取引金額(報酬基準額)の定義は各社で異なります。主に以下の4つの方式があり、適用される方式によって成功報酬額が大きく変わることがあります。
- 株式価値基準:株式の譲渡価額のみを基準
- オーナー受取額基準:株式価額+役員借入金を基準
- 企業価値基準:株式価額+有利子負債-現預金等を基準
- 移動総資産基準:株式価額+負債総額を基準
通常、「株式価値基準」が最も報酬額が低く、「移動総資産基準」が最も高くなる傾向があります。ただし、報酬の計算基準や割合(例えば、レーマン方式での段階的手数料率)はアドバイザリー会社ごとに異なるため、一概には言えません。契約時には計算方式を必ず確認することが重要です。
中小M&Aガイドラインでも、M&A専門業者に対し、報酬の計算基準となる金額(譲渡額、純資産、移動総資産など)を事前に明確に説明することを求めています 。また、レーマン方式で計算した成功報酬額が一定額に満たない場合に適用される「最低手数料」が設定されている場合もあるので、この点も契約前に確認が必要です 。
アドバイザリー契約書の書き方と締結時の注意点
アドバイザリー契約締結時には契約書を交わしますが、この契約書の記載項目も非常に重要です。契約書の内容によって、M&Aプロセスの進め方や万が一のトラブル発生時の対応が大きく変わります。ここでは、アドバイザリー契約書の基本構成や必須項目、活用できる雛形、そして見落としがちな重要条項について解説します。
契約書の記載内容と基本構成
中小企業庁の中小M&Aガイドラインでは、アドバイザリー契約書に含めるべき重要項目とその内容を詳細に示しています。以下は、アドバイザリー契約書に含める基本項目です。
- 業務範囲・内容:アドバイザーに委託する具体的な業務範囲(候補先企業の調査・選定、交渉支援、書類作成支援など)
- 専任条項:他のM&Aアドバイザーへの依頼を禁止する旨と例外事項
- 直接交渉の禁止:候補先企業との直接交渉を禁止する規定
- 秘密保持義務:秘密情報の範囲と保持期間、違反時の罰則など
- 契約の有効期間:契約の期間と終了条件
- 報酬体系:着手金、中間報酬、月額報酬、成功報酬の金額・計算方法・支払条件
- 解除事項:契約解除が可能な条件と手続き
- アドバイザーの責任範囲:善管注意義務の範囲と免責事項
- 準拠法・管轄:紛争発生時の適用法と管轄裁判所
これらの事項は、M&Aプロセスを円滑に進め、両者の権利義務関係を明確にするために不可欠です。契約締結前に上記項目が適切に記載されているか、専門家の助言を得ながら慎重に確認することをおすすめします。
業務内容・範囲
アドバイザリー契約書に記載する業務内容と範囲には、アドバイザーがクライアント企業に提供する具体的なサービス内容を詳細に記載します。まず、業務内容には、提案書の作成、潜在的な買収先または売却先の調査、市場分析、企業評価、交渉支援、契約締結のサポートなどが含まれることが一般的です。これにより、アドバイザーがどの程度まで支援を行うのか、またどの時点で業務が完了するのかが明示され、誤解や期待値の齟齬を防ぐことができます。
次に、業務範囲は、アドバイザーの活動が及ぶ地理的、業種的、あるいは時間的な制限を設定することが求められます。これにより、アドバイザーが無制限にリソースを投入することを防ぎ、効率的な業務遂行が可能になります。また、業務範囲を明確にすることで、クライアントはアドバイザーに期待する成果を合理的な範囲内で設定することができます。
さらに、契約書には、業務内容や範囲の変更に関する手続きや条件も記載されることが一般的です。これにより、契約期間中に新たなニーズや状況の変化が生じた際に、迅速かつ円滑に対応することが可能となります。
専任条項
専任条項は、クライアントが特定のアドバイザーに対して独占的に業務を委託することを明確にするための項目です。専任契約の場合、他のM&Aアドバイザーへの依頼を禁止することで、情報の一貫性を保ち、スムーズなプロセス進行を可能にします。ただし、例外事項として特定の条件下では他のアドバイザーの関与が認められることもあります。これにより、クライアントが必要に応じて柔軟に対応できるよう、契約内容に一定の余地を持たせることが可能となります。
直接交渉の禁止条項
アドバイザリー契約書には、交渉の流れをスムーズに進めるために、直接交渉の禁止条項が含まれることが一般的です。直接交渉の禁止条項は、クライアントと第三者がアドバイザーを介さずに直接交渉を行わないように制限するもので、交渉プロセスの透明性と効率を確保する役割を果たします。直接交渉を禁止することで、誤った情報の伝達や交渉の行き違いを防ぎ、クライアントの利益を守ることが可能となります。
直接交渉禁止条項が無い場合、例えばM&A仲介会社が紹介した候補企業とクライアント企業が直接交渉を始め、仲介会社を介さずに契約を成立させてしまうと、仲介会社への成功報酬の支払いが曖昧になってしまいます。これは仲介会社やアドバイザーにとって大きな損害となるだけでなく、後のトラブルに発展し、場合によっては訴訟問題に発展する可能性もあります。
契約書には、直接交渉の禁止だけでなく、万一直接交渉が行われた場合の損害賠償額の算定方法や、契約終了後一定期間内に直接取引が成立した場合の報酬支払義務なども明確に定めておくべきです。
秘密保持義務
M&Aアドバイザリー契約において、秘密保持義務も重要な項目です。秘密保持義務は、取引の各段階において双方が提供する情報の機密性を保護することを目的としています。M&Aプロセスでは、企業の財務情報や戦略的計画、顧客リストなどの機密情報が頻繁に共有されるため、情報漏洩が取引に与える影響は甚大です。
秘密保持義務の条項には、どの情報が機密とされるか、情報の取り扱い方法、そして情報漏洩が発生した場合の責任について具体的に規定されていることが一般的です。また、通常この条項は、契約終了後も一定期間続くことが求められます。これにより、取引が終了した後も、当事者の秘密情報が不適切に使用されることを防ぎます。
契約の有効期間
契約の有効期間は、アドバイザリー契約がどのくらいの間有効であるかを定めるものであり、双方の当事者が明確にしておく必要があります。一般的に、有効期間は数ヶ月から1年程度に設定されることが多く、その間にアドバイザリー業務が遂行されます。
有効期間の設定においては、M&Aプロジェクトの規模や複雑さ、予想される交渉期間などを考慮に入れることが重要です。また、契約終了後も一定期間、特定の義務が続く場合があるため、これを契約書に明確に記載することが求められます。例えば、秘密保持義務や競業禁止義務などの条項が、契約終了後も一定期間続くことがあります。
さらに、有効期間の終了前に契約を更新するかどうかについても、事前に取り決めておくことが望ましいです。プロジェクトの進捗状況によっては、契約期間の延長が必要になる場合もあります。そのため、契約書には、更新や延長のための条件や手続きについての詳細を含めておくと、後々の交渉がスムーズに進むでしょう。
報酬体系・費用
M&Aアドバイザリー契約書において、報酬体系や費用の設定も大切です。前述した着手金や成功報酬などの費用項目のうち、どの費用がどのくらい発生するのかを明確に定めます。
支払条件についても、各報酬の支払い時期や方法を規定します。例えば、着手金は契約締結後直ちに、成功報酬は取引完了後一定期間内に支払われるなどの詳細が記載されます。これらの報酬体系は、契約書に明確に定められていることが重要であり、双方の合意に基づく透明性のある契約が求められます。
解除事項
解除事項は、契約の終了や解消に関する重要な項目です。契約の解除は、双方の合意または特定の条件が満たされた場合に行われます。解除事項には、契約不履行や当事者の一方が破産した場合、さらには重大な法令違反があった場合など、特定の解除事由が記載されることが一般的です。これにより、契約の継続が困難になった際の手続きや条件が明確化され、双方のリスクの管理が可能となります。
さらに、解除に際しての手続きや通知期間についても詳細に規定されることがあります。例えば、解除の意思を文書で通知しなければならない期間や、通知方法が指定されている場合があります。これにより、解除プロセスが透明で予測可能なものとなり、紛争の発生を未然に防ぐことができます。
また、解除後の義務や権利についても考慮されます。たとえば、解除後の情報の取り扱いや報酬の精算方法などが含まれます。これにより、契約終了後でも残る義務や権利を明確にし、後のトラブルを回避することが期待されます。
アドバイザーの責任範囲
アドバイザーの責任範囲は、取引の成功に大きく影響します。まず、善管注意義務とは、アドバイザーがクライアントの利益を最優先に考え、最善の注意を払って業務を遂行する義務です。この義務に基づき、アドバイザーは市場分析や買収候補の選定、交渉のサポートなど、専門知識を駆使してクライアントの意思決定を支援します。
しかしながら、アドバイザーがすべてのリスクを負うわけではなく、契約書には免責事項が設けられることが一般的です。免責事項により、アドバイザーは市場の変動や予測不可能な外部要因による損害について責任を負わないことが明記されます。契約締結時には、両者がこれらの内容を十分に理解し、合意することが重要です。
準拠法・管轄
M&Aアドバイザリー契約書における準拠法・管轄の項目は、契約の法的解釈や紛争解決において重要な役割を果たします。準拠法とは、契約の内容や履行に関する法律解釈をどの国の法律に基づいて行うかを定めるもので、これにより契約の有効性や違反時の救済措置が明確になります。特に国際的なM&A取引では、関係する国の法律が異なることが多く、適切な準拠法の選定がトラブル防止の鍵となります。
一方、管轄とは、契約に関連する紛争が生じた際に、どの国や地域の裁判所が訴訟を受け付けるかを決定する要素です。これは、紛争解決のプロセスを円滑に進めるために重要です。管轄地の選択は、裁判費用や手続きの迅速性、実務的な面での利便性に大きく影響します。契約締結時には、法律専門家の助言を仰ぎ、最適な準拠法と管轄地を選定することが望ましいです。
中小企業M&Aで使える契約書の雛形の活用
中小企業のM&Aにおいては、中小企業庁が公開している契約書サンプルが非常に参考になります。中小M&Aガイドラインの中で公開されている「M&A仲介契約/FA契約 重要事項説明書」のサンプルは、中小企業向けのアドバイザリー契約の雛形として最適です。
また、一般財団法人日本的M&A推進財団や一般社団法人M&A支援機関協会なども会員向けに契約書の雛形を提供しています。これらの雛形は実務経験に基づいて作成されており、中小企業のM&Aに特化した内容となっています。
雛形を活用する際の注意点としては、自社の状況や業界特性に合わせて適宜カスタマイズすることが重要です。特に、業務範囲や報酬体系については、M&A仲介会社との交渉結果を反映させる必要があります。雛形をそのまま使用するのではなく、弁護士などの専門家のチェックを受けることで、より安全な契約締結が可能になります。
中小企業庁のM&A支援機関登録制度のウェブサイトでは、中小M&Aガイドラインや契約書サンプルを含む関連資料が閲覧できますので、ぜひ参考にしてください。
委託先がM&Aガイドラインに遵守しているか確認する
M&Aアドバイザーを選ぶ際は、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」に準拠している業者を選ぶことが重要です。このガイドラインは、中小企業のM&Aが適切に行われることを目的に策定されたもので、M&A支援機関のサポートを均質化するための基本事項や行動指針が明記されています。
信頼できるM&Aアドバイザーかどうかを判断する方法としては、以下の2点の確認が有効です。
- 中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録されているか
- 「一般社団法人M&A支援機関協会」(旧:M&A仲介協会)に加盟しているか
M&A支援機関登録制度は中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために設けられた制度で、登録されるには中小M&Aガイドラインの遵守を宣言する必要があります。また、一般社団法人M&A支援機関協会は公正で安全なM&A仲介を推進する業界団体で、適正な取引ルールの徹底を掲げています。
これらの登録・加盟状況を確認することで、ガイドラインに準拠した信頼性の高いM&Aアドバイザーを選ぶことができます。
まとめ
M&Aは中小企業にとって事業承継や事業拡大の重要な手段ですが、その複雑なプロセスを成功に導くには、適切なアドバイザリー契約の締結が不可欠です。この記事で解説してきたように、アドバイザリー契約は単なる形式ではなく、M&Aの成否を左右する重要な要素です。
契約内容を適切に設計し、信頼できるM&Aアドバイザーを選ぶことで、M&Aに伴うリスクを最小限に抑えながら、自社にとって最大のメリットを引き出すことが可能になります。特に、専任契約の選択、適切な仲介方式の決定、重要条項の明確化、そして報酬体系の理解は、M&A成功への近道といえるでしょう。
最後に、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」に準拠し、M&A支援機関登録制度に登録されている専門家を選ぶことで、より安心してM&Aに取り組むことができます。適切なアドバイザリー契約を締結し、専門家の知見を最大限に活用することで、円滑なM&Aを実現することができるでしょう。 M&Aや事業承継に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。