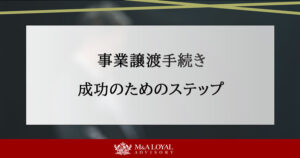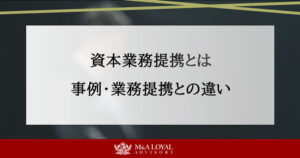業務移管とは?事業移管・事業譲渡の違いと進め方をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
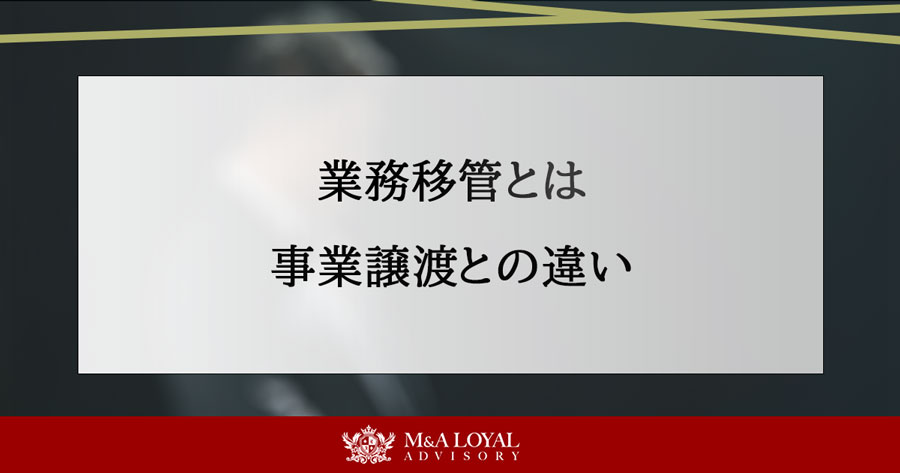
企業経営において、業務の効率化やコア事業への集中は重要な経営課題です。その解決策として注目されているのが「業務移管」という手法です。業務移管とは、企業内の特定業務を別部門や外部企業へ移す取り組みを指します。しかし、似た言葉である「事業譲渡」や「事業移管」との違いが曖昧で、業務移管とはどのように進めればよいかわからないという経営者も多いのではないでしょうか。
本記事では、業務移管とは何か、その定義から事業譲渡との違い、具体的な進め方まで、中小企業のオーナーにも分かりやすく解説します。
目次
業務移管とは?意味など基本をわかりやすく解説
業務移管とは、企業内で行っている特定の業務について、その管轄や実行権限を社内の別部門または外部企業へ移すことを指します。日常業務の一部を切り出して移動させるイメージであり、事業全体を売却するような大規模な取引とは異なります。業務移管は経営効率化の手段として、多くの企業で活用されています。
社内の別部門へ業務を移す場合は「社内移管」と呼ばれ、組織再編の一環として実施されます。一方、外部企業へ業務を移す場合は「アウトソーシング」や「オフショアリング」と呼ばれることもあり、専門性の高い企業に業務を委託することで品質向上やコスト削減を図ります。
業務移管と事業移管の違い
業務移管と事業移管は似た言葉ですが、移管する対象の範囲には明確な違いがあります。業務移管は特定の業務プロセスや作業のみを対象とするのに対し、事業移管は事業に関連する資産や人材、ノウハウなど、より広範な要素を含みます。例えば、経理業務の一部を外部の会計事務所に委託するのは業務移管ですが、経理部門全体を子会社化したり、他の企業に譲渡したりするような場合は事業移管に該当します。
事業移管では、業務に必要な設備や従業員、取引先との関係、契約など、事業を構成する要素が一体として移転します。そのため、法的手続きや従業員の処遇についても、業務移管よりも複雑な対応が必要になります。自社の状況に応じて、どちらの手法が適しているかを慎重に判断することが重要です。
業務移管と事業譲渡の違い
業務移管と事業譲渡は、経営効率化という目的では共通していますが、法的な性質や実務上の取り扱いが大きく異なります。以下の表で主な違いを整理します。
| 比較項目 | 業務移管 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 特定の業務プロセスや作業 | 事業資産一式(人材・設備・ノウハウ・顧客など) |
| 権限・責任 | 委託側に管理権限が残存 | 買い手に完全移転 |
| 対価の流れ | 委託側が受託側へ支払う | 買い手が売り手へ支払う |
| 法的手続き | 業務委託契約が中心 | 事業譲渡契約、株主総会の決議等が必要 |
| 従業員の扱い | 出向や業務指示の変更 | 転籍や承継が行われる |
事業譲渡では、対価を受け取って事業を売却するため、企業にとっては資産の現金化という側面があります。一方、業務移管は業務の実行を外部に委ねるだけで、事業そのものの所有権は移転しません。したがって、委託側は引き続き業務の管理責任を負い、受託側に対して業務委託料を支払う形になります。
また、事業譲渡は会社法で規定された法的手続きが必要であり、一定規模以上の場合は株主総会の特別決議が求められます。業務移管は基本的に業務委託契約の締結で完結するため、手続きは比較的シンプルです。ただし、労働条件の変更を伴う場合は労働法制への配慮が必要になります。
会社での業務移管の目的
業務移管を実施する目的は企業によって異なりますが、共通するのは経営効率の向上です。重複する業務を集約したり、不採算部門を立て直したりすることで、経営資源をより効果的に配分できます。また、業務移管によって社内のリソースをコア事業に集中させることができ、競争力の強化にもつながります。
特に中小企業においては、限られた人材や資金を最大限に活用することが経営の鍵となります。業務移管は、そうした経営課題を解決する手段の一つです。次に、業務移管の具体的な目的と、移管に適した業務について詳しく見ていきます。
業務移管の主な目的
業務移管を実施する目的として、まず挙げられるのが経営効率化です。複数の部門で類似の業務を行っている場合、これを一つの部門や外部企業に集約することで、業務の重複を排除し、効率を高めることができます。例えば、各部門で個別に行っていた経費精算業務を経理部門に集約すれば、処理時間の短縮やミスの削減が期待できます。
次に重要な目的がコスト削減です。業務を専門性の高い外部企業に委託することで、自社で人材を抱えるよりも低コストで業務を遂行できる場合があります。また、不採算部門を外部に移管することで、固定費を変動費化し、経営の柔軟性を高めることも可能です。
さらに、コア事業への経営リソース集中も重要な目的です。ノンコア業務を外部に移管することで、経営陣や従業員は本業に専念できるようになります。これにより、製品開発や営業活動などの付加価値の高い業務に時間と労力を割けるようになり、企業の競争力向上につながります。
業務移管に適した業務の種類
業務移管に適しているのは、マニュアル化や定型化がしやすい業務です。具体的には、単純な生産作業や伝票発行、経費精算などのバックオフィス業務が該当します。こうした業務は手順が明確で、外部に委託してもミスが発生しにくいという特徴があります。
コールセンター運営も業務移管に適した領域です。顧客対応のスクリプトやFAQを整備することで、外部の専門企業に運営を委託できます。専門企業は多数の顧客対応実績を持ち、高品質なサービスを提供できるため、自社で運営するよりも顧客満足度の向上を期待できます。
また、専門性の高い業務も外部移管の対象となります。例えば、情報システムの運用保守やデータ分析などは、専門企業に委託することで最新の技術やノウハウを活用できます。自社で専門人材を育成するには時間とコストがかかりますが、外部の専門企業を活用すれば即座に高度なサービスを受けられます。
以下に、業務移管に適した業務の例を整理します。
- 製造工程における単純作業や組み立て業務
- 経理部門における伝票処理や帳簿記帳
- 人事部門における給与計算や社会保険手続き
- 総務部門における施設管理や備品管理
- カスタマーサポートや問い合わせ対応
- ITシステムの運用監視や保守業務
- マーケティングデータの収集と分析

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



業務移管のメリット
業務移管とは、企業内外の別部門や外部企業に特定の業務を引き継ぐことを指します。適切に業務を移管することで、経営資源の最適化や業務効率化を実現でき、組織全体の生産性向上につながります。本章では、社内移管と社外移管それぞれのメリットについて詳しく解説します。
社内移管のメリット
社内の別部門へ業務を移管する場合、最大のメリットは手続きの簡素さです。外部企業との契約交渉や法的手続きが不要なため、短期間かつ低コストで移管を実現できます。また、同じ企業内での異動となるため、従業員の雇用契約を変更する必要もありません。
社内移管では、業務の引き継ぎもスムーズに進みます。同じ企業文化や情報システムを共有しているため、業務プロセスの理解が早く、移管後も円滑に業務を継続できます。さらに、部門間の連携が強化され、組織全体の効率が向上する効果も期待できます。
また、社内移管によって専門性の高い部門を形成できる点もメリットです。例えば、各部門で個別に行っていた経理業務を経理部門に集約すれば、経理部門の専門性が高まり、業務品質の向上につながります。専門部門の育成は、企業全体の競争力強化にも役立ちます。
社外移管のメリット
外部企業へ業務を移管する場合、社内の業務負担を大幅に軽減できます。移管した業務に携わっていた従業員を、より付加価値の高いコア業務に再配置できるため、経営資源の最適化が実現します。特に人手不足に悩む中小企業にとって、この効果は大きいと言えます。
外部の専門企業が持つ知識や技術を活用できる点も、社外移管の重要なメリットです。専門企業は多数の顧客対応実績があり、最新のツールやノウハウを保有しています。こうした専門性を活用することで、自社で業務を行うよりも高い品質と効率を実現できます。
不採算部門のリスク分散や再建も、社外移管によって可能になります。赤字が続く部門を外部に移管することで、固定費を削減しながら業務継続を図れます。また、専門企業のノウハウを活用して部門を立て直し、将来的には黒字化を目指すことも可能です。
業務移管のデメリット
業務移管には多くのメリットがある一方で、実施に伴うデメリットも理解しておく必要があります。まず、移管期間中の手間とコストが発生します。デューデリジェンスや契約交渉には専門家のサポートが必要であり、その費用は小さくありません。また、移行作業中は業務が一時的に停滞するリスクもあります。
人材流出のリスクも重要な課題です。業務移管に伴って従業員を出向させる場合、新しい環境への不満から退職を選択する従業員が出る可能性があります。また、出向先での処遇が良ければ、そのまま転職してしまうケースもあります。こうした人材流出は、企業にとって損失となります。
人材流出を防ぐためには、移管の目的や今後のキャリアパスについて、従業員に丁寧に説明することが重要です。双方向のコミュニケーションを重視し、従業員の不安や疑問に誠実に対応する姿勢が求められます。また、出向先での労働条件についても、可能な限り現状を維持するよう配慮することが望ましいです。
業務移管に必要な手続きと契約
業務移管を実施する際には、適切な法的手続きと契約の締結が必要です。移管の形態や対象業務によって必要な契約書類は異なりますが、基本的には秘密保持契約と業務委託契約が中心となります。これらの契約を適切に締結することで、移管後のトラブルを防ぎ、円滑な業務継続を実現できます。
特に外部企業への移管では、自社の機密情報が外部に流出するリスクがあります。したがって、秘密保持契約の締結は最優先事項です。また、業務委託契約では、業務内容や品質基準、責任範囲などを明確に定める必要があります。ここでは、業務移管に必要な主な契約について解説します。
秘密保持契約の重要性
秘密保持契約は、業務移管において最も重要な契約の一つです。業務を外部企業に委託する場合、必然的に自社の業務プロセスや顧客情報、技術ノウハウなどの機密情報を開示する必要があります。これらの情報が外部に漏洩すれば、企業の競争力が損なわれるだけでなく、顧客や取引先からの信頼も失ってしまいます。
秘密保持契約では、開示する情報の範囲と利用目的を明確に定めることが重要です。また、情報の管理方法や漏洩時の責任、契約終了後の情報返却・廃棄についても詳細に規定する必要があります。特に個人情報を扱う業務では、個人情報保護法に基づく適切な管理体制の構築が求められます。
秘密保持契約の締結は、業務委託契約の前段階として行われるのが一般的です。移管の検討段階から自社の情報を開示する必要があるため、早期に契約を締結することが望ましいです。契約書の作成にあたっては、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
業務委託契約の主な内容
業務委託契約は、業務移管の具体的な内容を定める中核的な契約です。この契約では、委託する業務の範囲や内容、納期、品質基準、対価などを詳細に規定します。曖昧な記載があると後々トラブルの原因となるため、できる限り具体的かつ明確に定めることが重要です。
業務委託契約に盛り込むべき主な項目は以下の通りです。
- 委託業務の具体的な内容と範囲
- 業務遂行の方法と手順
- 成果物の納期と品質基準
- 委託料の金額と支払い条件
- 再委託の可否と条件
- 損害賠償の範囲と責任
- 契約期間と更新・解除の条件
- 機密情報の取り扱い
- 知的財産権の帰属
また、業務の品質を維持するため、定期的な報告や監査の実施について契約に明記することも重要です。受託側の業務遂行状況を定期的にモニタリングし、問題があれば早期に改善を求める仕組みを構築することで、安定した業務品質を確保できます。
社内移管における手続き
社内の別部門へ業務を移管する場合、外部企業への移管のような契約締結は基本的に不要です。ただし、組織規程の変更や従業員の配置転換に関する手続きは必要になります。また、業務移管に伴って従業員の労働条件が変更される場合は、労働法制に基づく適切な手続きが求められます。
社内移管では、業務の引き継ぎを円滑に進めるための準備が重要です。業務マニュアルの整備や引き継ぎ期間の設定、移管後のサポート体制の構築などを計画的に進める必要があります。また、移管対象の従業員に対して、移管の目的や今後の業務内容について丁寧に説明し、理解と協力を得ることが成功の鍵となります。
業務移管の具体的な進め方
業務移管を成功させるためには、計画的かつ段階的に進めることが重要です。一般的に、業務移管には約10ヶ月程度の期間を要しますが、この期間は業務の内容や規模、関与する関係者によって異なることがあります。この期間を5つのステップに分けて、それぞれの段階で必要な作業を着実に実行していくことが求められます。急ぎすぎると重要な検討が漏れてしまい、逆に時間をかけすぎると関係者の負担が増大します。
ここでは、業務移管の標準的な進め方を5つのステップに分けて解説します。各ステップの目安期間や主な作業内容を理解し、自社の状況に合わせてスケジュールを調整してください。
ステップ1:スキーム検討
業務移管の第一歩は、移管の目的とスキームを明確にすることです。このステップには1〜2ヶ月程度を要します。まず、現在の業務内容を詳細に分析し、どの業務を移管対象とするかを決定します。業務の棚卸しを行い、各業務の工数や重要度、移管のしやすさなどを評価します。
移管範囲を決定する際には、業務間の依存関係や移管に伴うリスクを慎重に検討する必要があります。例えば、他の業務と密接に関連している業務を単独で移管すると、業務の断絶が生じて混乱を招く可能性があります。また、顧客との接点が多い業務では、サービス品質の低下リスクを十分に評価する必要があります。
このステップでは、業務移管と事業譲渡のどちらが適しているかも比較検討します。移管対象の業務規模が大きく、関連する資産や人材も含めて移転する場合は、事業譲渡の方が適しているケースもあります。専門家のアドバイスを受けながら、最適なスキームを選択することが重要です。
ステップ2:労務・法務確認とパートナー選定
スキームが固まったら、次は労務面や法務面の確認と、移管先のパートナー選定を行います。このステップには1〜3ヶ月程度を要します。まず、移管対象業務に従事している従業員へのヒアリングを実施し、業務の実態や課題を把握します。同時に、移管に対する従業員の意向も確認します。
法務面では、移管に必要な契約や許認可について確認します。特定の業務では行政の許認可が必要な場合があり、移管によって許認可の要件が変わる可能性もあります。弁護士や行政書士などの専門家に相談し、法的リスクを洗い出すことが重要です。
外部企業へ移管する場合は、パートナー候補の評価と選定を行います。候補企業の実績や専門性、財務状況などを多角的に評価し、自社の要求水準を満たす企業を選定します。複数の候補から提案を受け、費用対効果も含めて総合的に判断することが望ましいです。
ステップ3:具体的な準備作業
移管先が決まったら、具体的な準備作業に入ります。このステップは最も時間を要する段階であり、4〜6ヶ月程度の期間を見込む必要があります。まず、業務プロセスの詳細な文書化とマニュアル作成を行います。現場の従業員と協力しながら、業務の手順や判断基準、注意点などを細かく記録します。
業務マニュアルは、移管後の業務品質を左右する重要なドキュメントです。単に手順を列挙するだけでなく、業務の背景や目的、よくあるトラブルとその対処法なども含めることで、移管先での円滑な業務遂行が可能になります。また、図表や写真を活用して視覚的に分かりやすい資料を作成することも効果的です。
教育プログラムの準備も重要な作業です。移管先の担当者に対して、業務内容や自社の期待水準を正確に伝えるための研修計画を策定します。座学だけでなく、実際の業務を体験するOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)も組み合わせることで、理解度を高めることができます。
システム面では、移管先でも業務を継続できるよう、必要なシステムの移行や連携の準備を進めます。自社システムへのアクセス権限の設定や、データ移行の計画立案、セキュリティ対策の実施などを行います。特にクラウドサービスを利用している場合は、ライセンス条件の確認や、データのバックアップおよび復元手順の整備も必要です。
ステップ4:移管実施とフォロー
準備が整ったら、いよいよ実際の移管作業に入ります。このステップは7〜9ヶ月目に実施され、移管直後の稼働確認とフォローアップまでを含みます。移管は一度に全てを行うのではなく、段階的に進めることでリスクを低減できます。例えば、一部の業務から先行して移管し、問題がないことを確認してから残りの業務を移管する方法が有効です。
移管実施時には、元の部門と移管先の両方で業務を並行して行う移行期間を設けることが一般的です。この期間中は、移管先の業務遂行状況を細かくモニタリングし、問題があれば即座に対応します。また、移管先からの質問や相談に迅速に回答できる体制を整えることも重要です。
リカバリープランの準備も欠かせません。移管後に重大な問題が発生した場合に備えて、業務を元の状態に戻す手順を事前に検討しておきます。こうした備えがあることで、移管に伴うリスクを大幅に軽減できます。
ステップ5:継続的改善
業務移管は実施して終わりではありません。移管後10ヶ月目以降も、継続的に業務を改善していくことが重要です。定期的に移管先の業務状況をレビューし、課題や改善点を抽出します。また、当初設定した品質基準やコスト目標が達成できているかを評価し、必要に応じて契約内容の見直しも検討します。
移管先との定期ミーティングを設定し、双方の課題認識を共有することも効果的です。オープンなコミュニケーションを維持することで、小さな問題のうちに対処でき、大きなトラブルの発生を防げます。また、移管先から改善提案を受けることで、業務品質のさらなる向上も期待できます。
業務移管の効果測定も重要です。コスト削減効果や業務効率の改善度合いを定量的に評価し、移管の目的が達成できているかを確認します。効果が十分でない場合は、原因を分析して改善策を講じる必要があります。こうしたPDCAサイクルを回すことで、業務移管の成果を最大化できます。
まとめ
業務移管は、企業の経営効率化とコア事業への集中を実現する有効な手段です。特定の業務を社内の別部門や外部企業に移すことで、コスト削減や業務品質の向上、人材の最適配置などのメリットを得られます。一方で、事業譲渡とは法的性質や対象範囲が異なるため、自社の目的に応じて適切な手法を選択することが重要です。
業務移管を成功させるには、計画的な準備と段階的な実施が欠かせません。スキーム検討から始まり、パートナー選定、具体的準備、移管実施、継続的改善という5つのステップを着実に進めることで、リスクを最小限に抑えながら効果を最大化できます。特に業務マニュアルの整備や従業員とのコミュニケーションは、移管後の業務品質を左右する重要な要素です。
業務移管は単なるコスト削減策ではなく、企業の成長戦略の一環として位置づけるべきものです。移管によって生まれた経営資源を、新規事業の開発や既存事業の強化に振り向けることで、企業の競争力を高めることができます。経営効率化や事業再編をお考えの際は、業務移管という選択肢も視野に入れて検討されることをお勧めします。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、業務移管から事業譲渡まで、企業の経営課題に応じた最適なソリューションをご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。