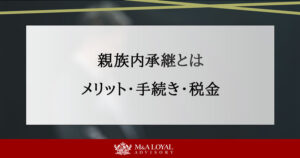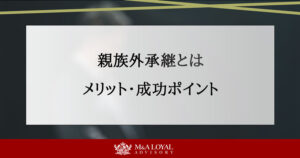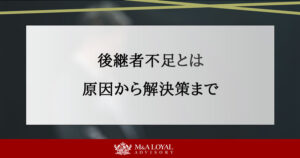跡継ぎとは?「後継ぎ」との違いや求められる能力や選び方を紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
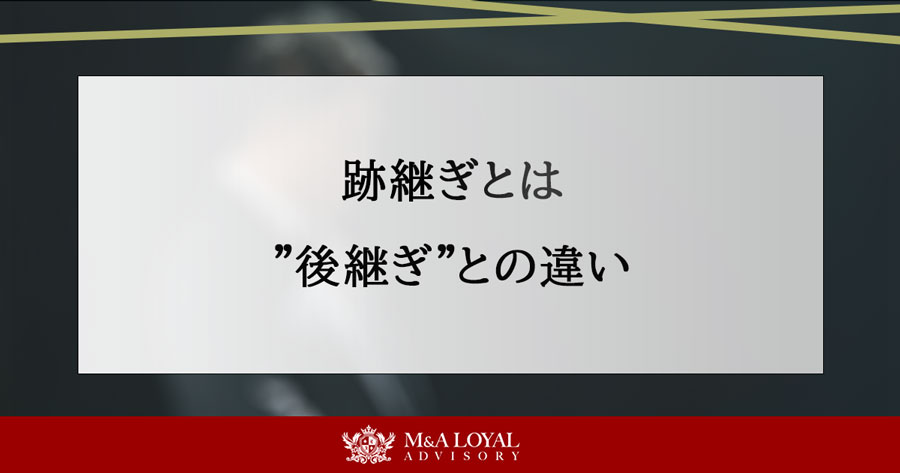
跡継ぎとは、企業や家業において次の世代に事業を引き継ぐ人のことを指します。日本の中小企業では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっており、適切な跡継ぎの選定が事業の継続に不可欠です。しかし、跡継ぎとは何か、その定義や役割について十分に理解していない経営者も多いかもしれません。
本記事では、跡継ぎとは具体的にどういうものか、意味や後継ぎとの違い、そしてどのような基準で選ぶべきかについて詳しく解説します。これから事業承継を考える経営者にとって、跡継ぎの選定は重要な課題であり、この記事が少しでもその助けになれば幸いです。
目次
跡継ぎとは何か?意味をわかりやすく解説
跡継ぎとは、家業や事業、財産などを前の世代から引き継ぐ人のことを指します。日本の伝統的な家族制度において、家督継承の考え方が根強く残っており、特に家業や事業の承継において重要な概念となっています。
跡継ぎの基本的な意味と由来
跡継ぎという言葉は、先代の残した事業や財産、権利関係を引き継ぐことを意味します。元々の意味としては、血縁関係で資産や家業を引き継ぎを行う際に使われ、特に一家代々で経営していた事業を長男が引き継ぐことを指すことも少なくありませんでした。こうした、現経営者の子などの身内に事業を継承させる「親族内承継」は昔からよく行われていた引き継ぎ方法であり、この考え方が現代の事業承継にも影響を与えています。
現代では、少子高齢化により、従来の血縁による跡継ぎ確保が困難になっています。そのため、親族以外への事業承継やM&Aによる第三者への承継も一般的になっており、跡継ぎの概念も多様化しています。
現代における跡継ぎの役割と重要性
現代の跡継ぎは、単に事業を引き継ぐだけでなく、企業の持続的成長を担う重要な役割を果たします。経営環境が急速に変化する中で、従来のやり方を踏襲するだけでは企業の存続は困難です。跡継ぎには、伝統を守りながらも革新を続ける能力が求められます。
また、跡継ぎは資産や権利だけでなく、従業員や取引先、地域社会に対する責任も負います。事業承継は単なる資産の引き継ぎだけでなく、ステークホルダー全体への責任も背負うため、跡継ぎの選定は慎重に行う必要があり、適切な準備期間と育成プロセスが不可欠です。
跡継ぎ問題と企業への影響
跡継ぎの有無は事業の将来に大きな影響を与えます。適切な跡継ぎが見つからない場合、企業は様々な課題に直面します。経営者の高齢化により判断力や体力の低下が起こり、事業の成長性や競争力が失われる可能性があります。また、将来への不安から優秀な人材の流出や取引先の離反が起こることもあります。
最終的に跡継ぎが見つからない場合は、事業の廃業を余儀なくされることもあります。これは企業自体の損失だけでなく、従業員の雇用や地域経済への影響も深刻です。そのため、早期から跡継ぎの確保と育成に取り組むことが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



跡継ぎと後継ぎの違いとは
跡継ぎと後継ぎは似た意味を持つ言葉として使われることが多いですが、実際にはニュアンスや使用される場面に違いがあります。事業承継を考える上で、跡継ぎと後継ぎの違いを理解することは重要です。
跡継ぎの特徴と使用場面
跡継ぎとは、主に家業や事業、財産の承継を意味し、血縁関係による承継や相続的な要素が強く、所有権の移転を伴う場合に用いられることが多いです。特に中小企業の事業承継や伝統的な家業の継承において使用されます。
また、跡継ぎには責任や義務といった重い意味合いが込められています。単に地位を引き継ぐだけでなく、先代が築き上げた事業や財産を守り、発展させる責任を負うことが期待されます。
後継ぎの特徴と使用場面
後継ぎとは主に役職や地位の承継に関して使用される言葉です。血縁関係に関係なく、前任者の後を引き継ぐことを意味し、企業の役員交代や組織のリーダー交代などで使用されます。後継ぎには、必ずしも所有権の移転は伴いません。
後継ぎという言葉は、より広い意味で使用されることが多く、政治家の後継や団体の代表者交代などでも使われます。跡継ぎに比べて、血縁や相続という要素は薄く、能力や適性による選定が重視される傾向があります。
実務上の使い分けと注意点
跡継ぎと後継ぎの違いは承継する範囲や血縁関係にあります。実務上では、事業承継や相続が関わる場合は「跡継ぎ」を使用し、単純な役職交代や地位の承継の場合は「後継ぎ」を使用するケースが多く見られます。しかし、実際にはこれらの意味が混合して使用されることも多いため、文脈から判断することが大切です。
跡継ぎと後継ぎの違いをまとめると以下のとおりです。
| 項目 | 跡継ぎ | 後継ぎ |
|---|---|---|
| 主な使用場面 | 家業、財産、権利など | 事業、学問、役職、地位など |
| 血縁関係の重要性 | 重要(特に伝統的には長男) | 関係なし |
| 選定基準 | 血縁関係+能力・適性 | 能力・適性中心 |
| 責任の範囲 | 財産・事業全体 | 役職・地位 |
「跡継ぎ」と似た言葉で「跡取り」という言葉もありますが、「跡継ぎ」と同じ意味で使用されるため両者に違いはありません。
跡継ぎに求められる能力
跡継ぎとは、事業承継において重要な要素であり、適切な跡継ぎを選定するためには、どのような能力や資質が必要かを理解することが重要です。経営環境が複雑化する現代において、跡継ぎに求められる能力は多岐にわたります。
経営能力と実務経験
跡継ぎには、事業を適切に運営するための経営能力が不可欠です。財務管理、人材管理、営業戦略立案などの基本的な経営知識に加え、現場での実務経験が重要な要素となります。理論だけでなく、実際に事業に携わることで得られる経験値が、困難な状況での的確な判断力を身につけます。
特に中小企業では、経営者自身が現場に近い距離で事業を管理することが多いため、各部門の業務内容を理解し、必要に応じて現場に入ることができる能力が求められます。また、財務数値を読み解く能力も重要で、売上や利益、キャッシュフローなどの財務指標を適切に読み取り、経営判断に活用できることが必要です。
リーダーシップと人間性
跡継ぎは組織のトップとして、従業員を導くリーダーシップが必要です。単に指示を出すだけでなく、従業員のモチベーションを高め、チーム全体のパフォーマンスを向上させる能力が求められます。コミュニケーション能力も重要で、様々なステークホルダーとの良好な関係を築くことができる人物である必要があります。
人間性も跡継ぎの重要な資質の一つです。誠実さや責任感、公平性などの基本的な人格に加え、困難な状況でも冷静さを保ち、適切な判断を下せる精神的な強さが必要です。また、従業員や取引先から信頼を得るためには、一貫性のある行動と発言が求められます。
変革への対応力と将来ビジョン
急速に変化する事業環境において、跡継ぎには伝統を守りながら改革を実行する柔軟性が求められます。デジタル化への対応や新しいビジネスモデルの導入など、積極的に変化を取り入れる姿勢が重要です。
また、明確な将来ビジョンを持ち、それを具体的な戦略に落とし込むことができる能力も必要です。5年後、10年後の事業の姿を描き、そこに向けた道筋を示すことで、従業員や関係者の共感と協力を得ることができます。
業界理解と専門知識
跡継ぎには、企業が属する業界の深い理解が必要です。業界の動向、競合他社の状況、顧客のニーズの変化などを常に把握し、それに基づいた経営判断を行う能力が求められます。また、自社の事業内容や強み、弱みを正確に理解し、それを活かした戦略を立案できることも重要です。
専門知識については、法務、税務、労務などの基本的な知識に加え、事業に特化した技術的な知識も必要です。全てを専門家レベルで理解する必要はありませんが、適切な判断を行うために最低限の知識は身につけておく必要があります。
跡継ぎの選び方
跡継ぎの人材を選定することは企業の将来を左右する重要な決断です。跡継ぎを探す方法として「親族内承継」「親族外承継(従業員承継)」「第三者承継(M&A)」が主な選択肢として挙げられます。これらの選択肢の中で、跡継ぎをどのような基準で選定するべきか理解することが大切です。
親族内承継における選定基準
親族内承継では、血縁関係がある親族に引き継ぐケースがほとんどですが、それだけで選定を行うのは適切ではありません。事業への関心と理解度、経営者としての資質、そして何より事業を継ぐ意欲があることが重要な選定基準となります。長男だから自動的に跡継ぎになるという考え方は現代では通用しません。
親族内の候補者を評価する際には、以下の点を考慮する必要があります。事業に対する理解度と関心の度合いです。幼い頃から事業に触れ、自然に事業内容を理解している場合もあれば、全く関心を示さない場合もあります。また、経営者としての適性も重要で、リーダーシップや決断力、責任感などを客観的に評価する必要があります。
従業員承継における選定基準
従業員承継では、既に会社で働いている人材の中から適任者を選定します。業務内容や会社の文化を深く理解していることが大きなメリットですが、経営者としての資質を持っているかどうかの見極めが重要になります。
従業員承継の場合の選定基準は以下の通りです。
- 現在の職務における実績と評価
- 他の従業員からの信頼度
- 経営者としての成長意欲と学習能力
- 会社の理念や文化への共感度
- 長期的に会社に貢献する意思
また、従業員承継では株式の取得資金や個人保証の問題もあるため、経済的な負担能力も考慮する必要があります。
第三者承継(M&A)における選定基準
第三者への事業承継やM&Aでは、より広範囲から適任者や買い手企業を選定することができます。この場合の選定基準は、事業の継続性と発展性を重視することが重要です。
M&Aによる跡継ぎ選定では、以下の要素を総合的に評価します。
- 買い手企業の財務的な健全性と安定性
- 事業に対する理解度と発展への意欲
- 既存従業員の雇用維持に対する姿勢
- 企業文化の適合性など
単に高い買収価格を提示するだけでなく、事業の本質を理解し、長期的な発展を考えている買い手を選定することが重要です。
選定プロセスと育成期間
跡継ぎの選定は短期間で行えるものではありません。適切な選定と育成には、短くとも3~5年、長いと10年以上の期間が必要です。まず候補者の洗い出しと初期評価を行い、その後段階的に責任ある業務を任せながら適性を見極めていきます。
選定プロセスでは、複数の候補者を同時に育成し、最終的に最も適任と判断される人物を選定することが理想的です。選定結果については候補者や関係者に適切に説明し、理解を得ることも必要です。
跡継ぎ選定における注意点
跡継ぎの選定には様々な課題や注意点があります。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、スムーズな事業承継を実現することができます。
相続税と資産承継の問題
親族内承継において最も大きな課題の一つが相続税の負担です。事業用資産や株式の評価額が高い場合、相続税の負担が跡継ぎの経済的能力を大幅に超えることがあり、事業承継自体が困難になる可能性があります。そのため、早期から税理士などの専門家と連携し、適切な相続税対策を講じることが重要です。
相続税対策としては、生前贈与の活用、事業承継税制の利用など、様々な手法があります。また、非上場株式の評価額を適正に下げる方法や、納税資金の確保方法についても検討する必要があります。これらの対策は専門的な知識が必要なため、早期から専門家のサポートを受けることが重要です。
家族内での合意形成
親族内承継では、跡継ぎ以外の家族の理解と合意を得ることが重要です。特に、跡継ぎに選ばれなかった兄弟姉妹や、配偶者の理解を得ることは、将来の家族間の対立を防ぐために必要です。事業承継は家族全体に影響を与える重要な決断であるため、十分な話し合いと合意形成が不可欠です。
合意形成のプロセスでは、事業の現状や将来性、跡継ぎ選定の理由などを明確に説明し、家族全員が納得できる形で進めることが重要です。また、跡継ぎ以外の家族への配慮も必要で、適切な財産分配や将来の生活保障についても検討する必要があります。
従業員や取引先への配慮
跡継ぎの選定は、従業員や取引先にも大きな影響を与えます。特に従業員にとっては、新しい経営者の下で働くことに対する不安や期待があります。事業承継の過程では、従業員への適切な説明と安心感の提供が重要です。また、取引先に対しても、引継ぎ後の事業の継続性や品質の維持について十分な説明を行うことで信頼関係を維持することが可能となります。
従業員への配慮としては、雇用の安定性の確保、労働条件の維持、キャリア形成の機会の提供などが重要です。また、取引先に対しては、契約条件の維持、サービス品質の継続、新たな取り組みへの理解を求めることが必要です。これらのステークホルダーとの関係維持は、事業承継の成功に直結する重要な要素です。
育成期間と能力開発の限界
跡継ぎに必要な能力や資質は、短期間で身につけられるものではありません。特に経営センスやリーダーシップなどの人間的な資質は、育成に長期間を要し、場合によっては十分な水準に達しない可能性もあります。そのため、育成計画を立てる際には、現実的な目標設定と代替案の検討が重要です。
能力開発の限界を認識し、不足する部分については外部の専門家やコンサルタントの活用、経営チームの強化などで補完することも検討する必要があります。また、育成期間中の評価と見直しも重要で、進捗に応じて計画を修正する柔軟性も必要です。
成功する跡継ぎ選定のためのポイント
跡継ぎの選定を成功させるためには、計画的なアプローチと総合的な視点が必要です。ここでは、成功確率を高めるための具体的なポイントを詳しく解説します。
早期からの計画的な準備
成功する跡継ぎ選定の最も重要なポイントは、早期からの計画的な準備です。理想的には現経営者が50代のうちから準備を開始し、時間をかけて段階的に進めることが推奨されます。この長期的なアプローチにより、候補者の育成、社内体制の整備、相続税対策など、必要な準備を十分に行うことができます。
準備段階では、まず事業承継の全体像を把握し、タイムスケジュールを作成します。その後、候補者の選定と育成計画の策定、法務・税務面での対策、資金面での準備などを並行して進めます。早期準備により、急な健康問題や市場環境の変化などの不測の事態にも対応できる余裕が生まれます。
複数候補者の同時育成
跡継ぎ候補は一人に絞るのではなく、複数の候補者を同時に育成することが重要です。これにより、最終的により適任な人物を選定できる可能性が高まり、また、第一候補が何らかの理由で承継できなくなった場合のリスクヘッジにもなります。
複数候補者の育成では、それぞれの特性や強みを活かせる分野での経験を積ませることが効果的です。営業、財務、製造など、異なる部門でのローテーション勤務を通じて、総合的な経営能力を身につけさせることができます。ただし、候補者間の競争が過度にならないよう、公平性と透明性を保つことが重要です。
外部専門家の活用
事業承継は法務、税務、財務など多くの専門知識が必要な複雑なプロセスです。そのため、税理士、弁護士、公認会計士、経営コンサルタントなどの外部専門家を適切に活用することが成功の鍵となります。
専門家の活用により、以下のようなメリットが得られます。
- 相続税対策や事業承継税制の適用など、税務面での最適化
- 株式譲渡契約や経営承継契約などの法務面でのサポート
- 事業価値の適正な評価と承継価格の決定
- 承継後の経営体制整備や成長戦略の策定
専門家との連携により、承継プロセスの効率化と成功確率の向上が期待できます。
段階的な権限移譲と実務経験
跡継ぎ候補者には、段階的に権限を移譲し、実務経験を積ませることが重要です。いきなり全ての経営権を移譲するのではなく、まず特定の部門や事業の責任者として経験を積ませ、徐々に責任範囲を拡大していくことが効果的です。
実務経験を通じて、候補者の適性や能力を客観的に評価することができ、また候補者自身も経営者としての自信と能力を身につけることができます。この過程では、現経営者がメンターとして適切なアドバイスとサポートを提供することが重要です。
跡継ぎ候補がいない場合の選択肢
親族や従業員に適切な跡継ぎ候補が見つからない場合、M&Aを活用した第三者承継が有効な選択肢となります。近年、この方法による事業承継が増加しており、多くの成功事例が報告されています。
M&Aによる事業承継のメリット
M&Aによる事業承継には多くのメリットがあります。まず、より広い範囲から適切な承継先を探すことができ、事業の特性や成長戦略に最も適した相手を選定できる可能性が高まります。また、買い手企業の経営資源や技術力を活用することで、単独では困難だった事業拡大や新規事業展開が可能になります。
現経営者にとっては、株式売却による対価を得ることができ、老後の生活資金や新たな事業への投資資金として活用できます。また、従業員の雇用維持や取引先との関係継続についても、適切な買い手を選定することで確保することが可能です。
M&A成功のための重要ポイント
M&Aによる事業承継を成功させるためには、以下のポイントが重要です。まず、事業の価値を正確に把握し、適正な評価を行うことです。財務面だけでなく、技術力、顧客基盤、人材などの無形資産も含めた総合的な企業価値評価が必要です。
次に、買い手企業の選定基準を明確にすることです。価格だけでなく、事業への理解度、従業員への配慮、長期的な成長戦略などを総合的に評価し、最適な相手を選定する必要があります。また、M&Aプロセスでは情報の管理と秘密保持が重要で、適切な手順で進めることが必要です。
M&Aプロセスの流れと注意点
M&Aによる事業承継のプロセスは、一般的に以下の流れで進められます。
- 事業価値の評価と売却戦略の策定
- 買い手候補の探索と初期接触
- 秘密保持契約の締結と詳細情報の開示
- 買い手による詳細調査(デューデリジェンス)
- 最終交渉と契約締結
- 統合プロセスの実行
各段階では専門的な知識と経験が必要であり、M&A仲介会社やアドバイザーの活用が重要です。また、プロセス全体を通じて、従業員や取引先への適切な情報開示と説明が必要です。
まとめ
跡継ぎの選定は企業の将来を左右する重要な決断であり、「跡継ぎ」と「後継ぎ」の違いを理解した上で、適切な基準と手順で進めることが大切です。求められる能力は経営能力、リーダーシップ、変革への対応力など多岐にわたり、長期的な育成が必要となります。
成功する跡継ぎ選定のためには、早期からの計画的な準備、複数候補者の育成、外部専門家の活用が重要です。親族内承継が困難な場合は、M&Aによる第三者承継も有効な選択肢となり、事業の持続的発展を図ることができます。適切な跡継ぎ選定により、企業の成長と雇用の維持、地域経済への貢献を実現することが可能となります。
事業承継でお悩みの経営者の方は、M&Aも含めた様々な選択肢を検討し、最適な跡継ぎ戦略を構築することをお勧めします。M&Aや経営課題に関するお悩みはぜひ一度、M&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。