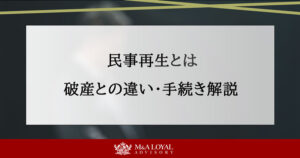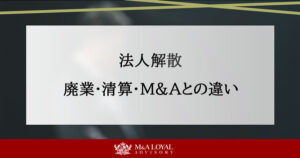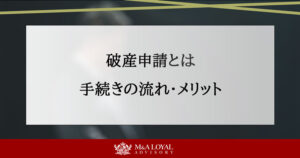特別清算とは?メリット・デメリットや破産との違い、流れを解説!
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
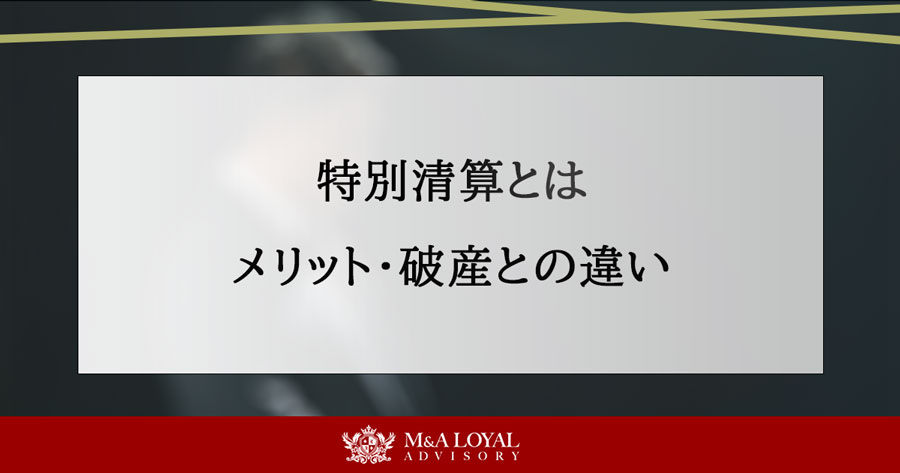
経営環境の変化や事業の不振により、会社の継続が困難になった際の選択肢として「特別清算」があります。特別清算とは、破産手続きと比較して信用毀損を抑えながら会社を整理できる制度として、中小企業でも活用されています。
しかし、特別清算の具体的な内容や破産との違い、利用できる条件について正確に理解している経営者は多くありません。手続きを選択する際は、それぞれのメリット・デメリットを十分に把握し、自社の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。
本記事では、特別清算とはどういうものか、その基本的な仕組みから実際の手続きの流れ、必要な費用、活用される具体的なケースまで、中小企業の経営者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。適切な事業整理の実現に向けて、ぜひ参考にしてください。
目次
特別清算とは
特別清算とは、解散して清算手続き中の株式会社が、債務超過の疑いがある場合などに利用する法的な清算方法です。通常の清算では会社の財産で全ての債務を完済できることが前提となりますが、特別清算は債務を完全に返済できない可能性がある状況でも会社を適切に整理できる制度として位置づけられています。
特別清算とは債務超過の疑いがある株式会社の清算方法
特別清算が最も多く活用されるのは、会社の財産だけでは負債を完全に返済しきれない債務超過の疑いがある場合です。通常清算では資産超過、つまり全ての債務を弁済してもなお財産が残る状態が必要条件となります。しかし現実的には、事業の不振や経営環境の変化により債務超過に陥る中小企業は少なくありません。このような状況で会社を適切に整理するために、特別清算という選択肢が用意されています。債務超過の疑いが判明した場合、清算人には特別清算開始の申立てをする法的義務が課されており、適切な法的処理を確保する仕組みが構築されています。
会社法に基づく裁判所監督下の手続き
特別清算は会社法第510条以下に規定された制度で、破産法ではなく会社法を根拠とする点に特徴があります。この手続きは裁判所の監督下で進められますが、破産手続きと比較すると裁判所の関与は後見的立場にとどまる場合が多くなっています。清算人が主体となって手続きを進行し、裁判所は必要に応じて監督や調査を行う構造となっています。また、株式会社のみが利用できる制度であり、合同会社や一般社団法人などの他の法人形態では利用することができません。
通常清算との決定的な違い
通常清算と特別清算の主な違いは、裁判所の関与と財産状態の前提条件です。通常清算は裁判所が関与せず、清算人が独自に手続きを進める一方、特別清算では裁判所の監督が必要で、債務超過やその疑いがある場合にも利用できます。
特別清算では、債権者集会で協定案を可決するか、個別の和解契約を締結することで債権者との調整を図ります。これにより、特別清算は債権者と協調しながら会社を整理する制度として機能します。
なお、通常清算は資産超過が前提ですが、実務上は債務超過でも行われる場合があります。ただし、債権者調整が必要な場合は特別清算が選択されることが一般的です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



特別清算とは破産とどう違うのか|手続きの比較
特別清算と破産はいずれも債務超過となった会社を清算する法的手続きですが、その進行方法や要件には大きな違いがあります。中小企業の経営者にとって、どちらの手続きを選択するかは会社の状況や債権者との関係性によって決まる重要な判断となります。
| 項目 | 特別清算 | 破産 |
| 手続きの主体 | 会社選任の清算人 | 裁判所選任の破産管財人 |
| 債権者の同意 | 出席した議決権者の過半数の同意、かつ、議決権を行使できる債権者の議決権の総額の3分の2以上の同意が必要 | 不要 |
| 利用できる会社 | 株式会社のみ | すべての法人・個人 |
| 予納金 | 5万円~(一般的な場合) | 20万円~ |
| 手続きの柔軟性 | 債権者ごとに条件設定可能 | 平等処理が原則 |
| 社会的イメージ | 計画的整理の印象 | 経営破綻の印象 |
以下、それぞれの違いについて詳しく解説します。
手続きを進める主体と裁判所の関与度
最も大きな違いは、誰が手続きを主導するかという点です。破産手続きでは、裁判所が選任する破産管財人が会社の財産管理処分権を握り、全ての手続きを主導します。破産管財人は通常、会社とは無関係の弁護士が選任されるため、経営者は会社の財産管理処分権を失い、手続きを主導することはできません。
一方、特別清算では会社が選任した清算人が手続きを主導します。多くの場合、代表取締役がそのまま清算人に就任するか、会社が信頼する弁護士を清算人として選任することがあります。裁判所の監督を受けつつも、会社側が主体的に手続きを進められる点が特徴です。ただし、裁判所は手続き全体を監督し、必要に応じて指示を出したり債権者集会を開催するなどの役割を果たします。債権者との調整が必要な場合には、裁判所の関与が強まることもあります。
債権者の同意要件と手続きの柔軟性
債権者の同意に関する要件も両者で大きく異なります。破産手続きでは債権者の同意は一切不要で、法的要件を満たせば強制的に手続きを開始できます。これに対し特別清算では、債権者集会での協定案可決が必要となり、議決権を行使できる債権者の議決権の総額の3分の2以上の同意を得なければなりません。
この要件により、特別清算は債権者との協調的な解決を前提とした手続きといえます。しかし同意が得られる場合は、債権者ごとに異なる条件での和解や協定が可能で、少額債権者への優先弁済など柔軟な解決策を図ることができます。破産では全債権者を平等に扱う必要があるため、このような柔軟性はありません。
費用面での大きな差と予納金の違い
手続きにかかる費用面でも両者には大きな差があります。破産手続きでは、東京地方裁判所の場合、最低でも予納金20万円に加えて申立手数料や官報広告費などを含めると約22万円程度の費用が必要となります。これに対し特別清算では、協定型で予納金5万円、和解型なら予納金約1万円程度で済む場合が多く、総費用は大幅に抑えることができます。ただし、事案が複雑な場合や債権者との争いがある場合は、特別清算でも予納金が高額になる可能性があります。また、特別清算では否認権がないため、破産管財人による財産の取り戻し手続きが不要である分、手続きが簡素化され、結果的に費用削減につながっています。
特別清算を開始するための3つの要件
特別清算を開始するためには、会社法に基づくいくつかの要件を満たす必要があります。例えば、会社が解散していること、債務超過またはその疑いがあること、株主総会での決議が行われることなどが求められます。これらの要件は、特別清算が適切かつ効果的に機能することを確保するために法律で定められています。中小企業が特別清算を検討する際は、これらの要件を正確に理解し、自社の状況と照らし合わせることが重要です。
要件1|債務超過の疑いがあること
最も一般的な特別清算開始事由は、債務超過の疑いがあることです。これは会社の資産をもって負債の全額を弁済することができない状態、または弁済できない疑いがある状態を指します。重要なのは「疑い」の段階で足りるということで、確実な債務超過状態である必要はありません。清算時の貸借対照表や財産目録から判断して、資産の処分価格では負債を完済できない可能性があれば、この要件を満たします。特に中小企業では、帳簿上の資産価値と実際の処分価値に大きな差がある場合が多く、このような状況で債務超過の疑いが生じることがあります。清算人が債務超過の疑いがあると判明した場合は、法律上、特別清算開始の申立てをする義務が課せられています。
要件2|清算の遂行に著しい支障を来す事情があること
特別清算は、通常清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合に開始される手続きです。例えば、債権者や株主が多数に上り利害関係が複雑な場合、財産関係が難解で清算手続きに時間を要する場合、清算人が誠実に清算事務を行わない場合などが該当します。また、清算人と債権者の間で債務内容について争いがある場合や、清算手続きに非協力的な債権者が存在する場合も、特別清算の開始事由となる可能性があります。中小企業においても、取引先や関係会社が多岐にわたる場合や複数の事業部門を抱えている場合など、清算手続きが複雑化するケースでは、特別清算が選択されることがあります。
要件3|特別清算開始障害事由がないこと
特別清算が適切に機能するため、会社法514条では開始を妨げる障害事由が規定されています。主な障害事由は以下の通りです。
- 予納金の未納付: 裁判所に必要な費用を納付していない場合。
- 清算結了の見込みがないことが明らか: 債務超過が深刻で清算が実現不可能と判断される場合。
- 債権者利益に反することが明らか: 特定の債権者が不当に優遇される場合や、債権者の公平な利益が損なわれる場合。
- 不当な目的での申立て: 強制執行の停止のみを目的とした申立てや、否認権行使の回避を意図した申立て。
債権者の同意が得られる見込みがない場合や、破産手続きによって債権者がより多くの弁済を受けられることが明らかな場合は、特別清算開始が認められません。また、強制執行の停止のみを目的とした申立てや、否認権行使の回避を意図した申立ても不当な目的として却下される可能性があります。
これらの障害事由は、特別清算制度の適正な運用と債権者保護の観点から設けられており、申立て前に十分な検討が必要です。
特別清算が活用される3つの典型的なケース
特別清算は理論上すべての債務超過の株式会社で利用可能ですが、実務上は債権者の同意が得られやすい特定の場面で多く活用されています。特に中小企業においては、会社間の関係性や事業構造の特徴を活かした戦略的な活用が行われています。ここでは、特別清算が効果的に機能する代表的な3つのケースについて詳しく解説します。
ケース1|子会社整理における親会社主導の清算
最も頻繁に特別清算が活用されるのが、親会社が子会社を整理する場面です。この場合、親会社が子会社に対して貸付を行い、外部債権者への債務を完済した後、最終的に残った親会社への借入金について特別清算で処理するという手法がとられます。親子関係にある会社間では債権者と清算会社の利害が一致しやすく、協定案への同意も容易に得られます。また、親会社としては破産という強いマイナスイメージを避けながら、子会社の債務を法的に整理できるメリットがあります。中小企業グループにおいても、不採算部門を別会社化した後にその会社を特別清算で整理するケースや、事業統合に伴い不要となった子会社の清算などで活用されています。この手法により、グループ全体の信用毀損を最小限に抑えながら事業整理を実現できます。
ケース2|事業譲渡後の旧会社の整理
事業譲渡を行った後の旧会社の整理でも、特別清算がよく選択されます。事業の中核部分を他社に譲渡した後、残った旧会社には主に負債と一部の資産が残されることになります。このような状況では、事業譲渡により得た対価と残存資産では負債を完全に弁済できないケースが多く発生します。しかし、事業譲渡先企業や関係する債権者の協力により、残債務の一部免除を含む協定を締結できる場合があります。特に中小企業では、長年の取引関係に基づく信頼関係から、債権者が協定に応じてくれることも少なくありません。この手法により、事業自体は継続させながら、旧会社の債務を適切に整理することが可能となります。また、事業継続により従業員の雇用も維持でき、取引先への影響も最小限に抑えることができます。
ケース3|不採算部門を切り離した新設会社の清算
企業再生の一環として、不採算部門を新設会社に移転した後、その新設会社を特別清算で整理するケースも見られます。これは会社分割制度と特別清算を組み合わせた手法で、収益部門と不採算部門を法的に分離することで、収益部門の事業価値を保護しながら不採算部門の負債を整理できます。新設会社には移転された不採算部門の資産と負債のみが計上されるため、債権者にとっても状況が明確で協定に応じやすい環境が整います。また、本体会社が新設会社に対して債権を持つ関係となるため、親子会社間の整理と同様に協定成立の見込みが高くなります。この手法は特に製造業や建設業などの中小企業で、事業部門ごとの収益性に大きな差がある場合に有効です。適切に実行されれば、企業の健全化と再生を同時に実現する強力な手段となります。
特別清算を選ぶ5つのメリット
特別清算を選択することで、破産手続きにはない多くの利点を享受することができます。特に中小企業においては、これらのメリットが事業整理の成功を左右する重要な要素となります。以下、特別清算を選択すべき5つの主要なメリットについて詳しく解説します。
破産による信用毀損を最小限に抑えられる
特別清算の最大のメリットは、破産と比較して社会的なマイナスイメージを大幅に軽減できることです。破産が引き起こす具体的な悪影響は以下の通りです。
・関連会社や取引先への深刻な不安
・グループ全体の信用不安の連鎖
・健全な会社の事業への悪影響
・金融機関からの警戒や取引条件の悪化
これに対し特別清算は「計画的な会社整理」という印象を与えやすく、ステークホルダーの理解も得やすくなります。事業譲渡後の整理や不採算部門の分離などの文脈で実施される場合は、むしろ経営の合理化として評価される場合もあります。この信用保護効果により、他の関連事業への影響を最小限に抑えながら会社整理を実現できます。
従来の経営陣による清算手続きの継続
特別清算では、会社法の原則に従い、取締役がそのまま清算人に就任することができます。これにより、事業の内容や取引先との関係を熟知した経営陣が直接清算手続きを進めることが可能となります。破産の場合は一般的に外部の破産管財人が選任されるため、会社の事情に疎い第三者が重要な判断を行うことになりますが、特別清算では経営陣の判断と経験を活かした効率的な手続きが期待できます(ただし、債務者の財産が極めて少なく、財産を換価してもそのなかから破産手続の費用も支出できないと確実に認められる場合は、破産管財人を選任せずに破産手続を終了することもあります)。また、債権者や取引先との既存の信頼関係を活用して協定への同意を取り付けることも容易になります。専門性が必要な場合は、会社が信頼する弁護士を清算人として選任することも可能で、経営陣の意向を反映した清算手続きを実現できます。
簡易迅速な手続きで時間とコストを削減
特別清算は、破産手続きと比較して柔軟かつ簡素化された手続きで進行します。破産では厳格な債権調査や配当手続きが必要ですが、特別清算では債権者との協定により迅速な解決が可能です。統計によると、特別清算の約70%が6か月以内に終結しており、破産手続きよりも短期間での処理が実現されています。特に和解型の特別清算では、債権者の同意が得られれば2~3か月で終結するケースもあります。
手続きの簡素化は、時間短縮だけでなくコスト削減にも寄与します。裁判所への予納金は破産の最低20万円に対し、特別清算では5万円程度から可能で、総手続き費用を抑えることができます。ただし、債権者の同意が不可欠であり、適切な調整が求められます。
債権者ごとの柔軟な和解交渉が可能
特別清算では、裁判所の認可を得れば債権者ごとに異なる条件での和解や協定が可能です。これにより、少額債権者への優先弁済、継続取引が重要な債権者への配慮、関連会社への特別な条件設定など、実情に応じた柔軟な解決策を図ることができます。破産手続きでは債権者平等の原則が厳格に適用されるため、このような個別対応は不可能です。中小企業では、長年の取引関係や地域社会との結びつきが強い場合が多く、画一的な処理よりも個別の事情に配慮した解決が望ましいケースが少なくありません。また、協定案の作成においても、債権者の理解と協力を得やすい条件設定が可能で、結果的に高い成功率を実現できます。
グループ会社への影響を限定できる
特別清算は、中小企業グループや関連会社を持つ企業にとって、他のグループ会社への悪影響を最小限に抑えるための重要な手段となります。破産手続きでは、その強いマイナスイメージが健全なグループ会社にまで影響を及ぼし、取引先や金融機関から警戒されるリスクがあります。一方、特別清算は計画的な事業整理としての位置づけで理解を得やすく、他のグループ会社の事業継続への影響を限定することが可能です。
親会社が子会社の特別清算を支援する場合、グループ全体の結束の強さを示すことで信用維持の効果も期待できます。このような信用保護効果により、一社の整理が引き金となってグループ全体が連鎖的に経営危機に陥るリスクを抑えることができます。ただし、これらの効果を最大化するためには、透明性を確保し、取引先や債権者との十分なコミュニケーションが不可欠です。
特別清算の3つのデメリット
特別清算には多くのメリットがある一方で、その活用には明確な制限とデメリットも存在します。これらのデメリットを理解せずに特別清算を選択すると、手続きが途中で頓挫し、最終的に破産手続きに移行せざるを得ない事態が生じる可能性があります。適切な判断を行うため、以下の3つの主要なデメリットについて詳しく確認しておきましょう。
株式会社のみに限定される利用制限
特別清算を利用できるのは株式会社のみに限定されており、他の法人形態では利用することができません。合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などの組織は、債務超過に陥った場合でも特別清算を選択することができず、破産手続きを選択するしかありません。近年増加している合同会社の場合、設立時の手軽さに対して清算時の選択肢が限定されることになります。また、株式会社であっても解散決議が前提となるため、株主総会での特別決議(総議決権の過半数の出席かつ3分の2以上の賛成)が必要です。株主が分散している会社や対立する株主がいる場合は、解散決議自体が困難となり、特別清算の利用ができない場合があります。このような制限により、法人形態や株主構成によっては、メリットが多い特別清算を選択できないケースが生じます。
債権者の3分の2以上の同意という高いハードル
特別清算では、協定案の可決に債権者集会での厳格な同意要件が課されています。
・出席した議決権者の過半数の同意
・議決権総額で3分の2以上の同意
この要件は破産にはない特別清算固有のハードルであり、一部の債権者が反対すれば手続きが成立しません。特に中小企業では、金融機関が大口債権者となっている場合が多く、金融機関の協力が得られなければ同意要件を満たすことができません。また、取引先が多数に上る場合や、債権額について争いがある債権者が存在する場合は、同意取得が困難となります。同意が得られずに協定案が否決されると、特別清算は終了し、破産手続きに移行することになります。この場合、特別清算にかけた時間と費用が無駄になるだけでなく、二重の手続き負担を強いられることになります。
否認権行使ができないことによるリスク
特別清算では破産手続きと異なり、否認権の制度が存在しません。否認権とは、債務者が倒産に至る過程で行った不適切な財産処分や偏頗弁済の効力を否定し、流出した財産を取り戻す権利です。破産手続きでは破産管財人がこの権利を行使して債権者への配当原資を確保できますが、特別清算では不可能です。このため、清算開始前に特定の債権者への優先弁済が行われていた場合や、会社財産が不当に安価で譲渡されていた場合でも、これらの行為を法的に取り消すことができません。中小企業では、経営悪化の過程で関係者への優先的な支払いや、経営者の関連会社への資産移転などが行われるケースがありますが、特別清算ではこれらの行為によって減少した財産を回復できません。この制約により、債権者が期待する弁済を受けられない可能性があり、結果的に協定への同意を得ることがより困難となる場合があります。
特別清算の手続きの流れと必要期間
特別清算の手続きは複数の段階を経て進行し、それぞれの段階で特定の作業と期間が必要となります。中小企業の経営者にとって、手続きの全体像と所要期間を理解しておくことは、適切な計画策定と関係者への説明のために重要です。以下、特別清算の具体的な流れと標準的な期間について詳しく解説します。
会社解散決議から清算人選任まで
特別清算の第一段階は、株主総会での解散決議と清算人の選任です。この解散決議には特別決議が必要で、議決権を行使できる株主の過半数の出席かつその3分の2以上の賛成が求められます。同時に清算人の選任も行い、通常は代表取締役がそのまま清算人に就任するか、法律事務や債権者との交渉が複雑な場合は弁護士を清算人として選任します。
解散登記は2週間以内に行う必要があり、この段階で会社は営業活動を停止し清算段階に入ります。清算人は就任後、直ちに会社の財産目録と貸借対照表の作成に着手し、株主総会での承認を得ます。また、債権者に対する債権届出の官報公告と知れたる債権者への個別催告を行い、債権者からの届出を受け付ける期間を設けます。この初期段階は、法律で定められた2か月以上の債権申出期間が必要となるため、一般的には3か月程度を要するのが一般的です。
特別清算開始申立てと裁判所の審査
清算人による財産調査が完了し、債務超過の疑いが判明すると、裁判所に対する特別清算開始の申立てを行います。申立書には会社の財産状況、債権者一覧、今後の清算方針などを詳細に記載し、必要な添付書類とともに提出します。裁判所は申立内容を審査し、特別清算の開始要件である「債務超過の疑い」または「清算の遂行に著しい支障を来す事情」の存在を確認します。同時に、開始障害事由(予納金の未納付、清算見込みの欠如、債権者利益への反などがないかも検討されます。要件を満たしていると判断されれば、特別清算開始決定が発令されます。この審査期間は通常1~2か月程度で、開始決定により会社は裁判所の監督下での清算手続きに移行し、債権者による個別の強制執行等は停止されます。
協定案作成と債権者集会での可決要件
特別清算開始後、清算人は会社財産の処分・換価を進めながら、債権者への弁済計画である協定案の作成に取り掛かります。協定案では、各債権者への弁済率、弁済期日、残債務の免除条件などを具体的に定めます。原則として債権者間での平等な取扱いが求められますが、少額債権者への優先弁済など一定の場合は例外が認められます。協定案の準備が整うと、債権者集会を招集して協定の可決を求めます。協定の可決には厳格な要件があります。
・出席した議決権者の過半数の同意
・議決権総額の3分の2以上の同意
可決されると、清算人は遅滞なく裁判所に協定の認可申立てを行います。この段階は債権者との調整や協議に時間を要するため、2~4か月程度の期間が必要となることが多くあります。なお、債権者が少数の場合は、協定に代えて個別の和解契約を締結する和解型の手続きも選択可能です。
6ヶ月から1年で完了する標準的な期間
司法統計によると、特別清算手続きの約70%が6か月以内に完了しており、約90%が1年以内に終結しています。協定の認可決定後は官報公告が行われ、2週間の即時抗告期間を経て認可決定が確定します。その後、協定に従った債権者への弁済を実行し、弁済完了後に特別清算終結の申立てを行います。裁判所による終結決定とその確定により、残債務は免除され会社の法人格も消滅します。和解型の特別清算では、事前に債権者の同意が得られている場合、2~3か月という短期間での終結も可能です。ただし、債権者との協議が難航する場合や、資産処分に時間を要する場合は1年を超えることもあります。中小企業においては、関係者が限定的で意思疎通が円滑な場合が多いため、標準的な6か月~1年での完了が期待できます。
特別清算にかかる費用の内訳と相場
特別清算を選択する際の重要な検討要素の一つが費用です。中小企業にとって、手続きにかかる総費用を事前に把握しておくことは、資金計画や他の選択肢との比較検討において不可欠です。特別清算の費用は大きく分けて裁判所に納める費用と専門家への報酬に分類され、破産手続きと比較して大幅な費用削減が可能です。
裁判所に納める予納金は5万円から
特別清算で裁判所に納める費用の中心となるのが予納金です。東京地方裁判所の場合の標準的な費用は以下の通りです。
- 予納金:協定型約5万円、和解型約1万円(裁判所の運用や会社の規模により異なる場合があります)
- 申立手数料:2万円(収入印紙)
- 郵便切手代:協定型約600円、和解型約500円(手続き内容により変動する場合があります)
- 官報公告費:数万円程度(公告内容により金額が異なります)
これらの金額は一般的な基準であり、実際の費用は裁判所や官報の発行元に確認することが重要です。
この予納金は清算手続きに必要な経費を賄うために事前に納付するもので、事案の複雑さや争訟性によって金額が変動します。比較的簡易な案件では最低額での納付が可能ですが、債権者が多数に上る場合や債権内容について争いがある場合は数十万円以上になる可能性があります。これらの裁判所関係費用の合計は、最も簡易な和解型の場合で約3万円、協定型でも約7万円程度となり、破産の約22万円と比較して大幅な費用削減が実現できます。
弁護士費用の相場と選び方のポイント
特別清算は法的手続きであり、適切な書面作成、債権者との協議、裁判所手続きへの対応が必要となるため、多くの場合で弁護士への依頼が行われます。弁護士費用は事務所や案件の複雑さにより大きく異なりますが、中小企業の標準的なケースでは着手金が50万円~100万円程度の範囲となることが一般的です。債権者数、負債総額、資産の種類と規模、争訟性の有無などが費用決定の主要な要因となります。成功報酬は設定しない事務所が多く、着手金のみで手続きを完了できる場合がほとんどです。清算人として弁護士が就任する場合の清算人報酬は、破産管財人報酬よりも低額に設定される傾向があり、事案の規模に応じて決定されます。弁護士選択の際は、企業法務や倒産処理の経験が豊富で、特別清算の実績を持つ専門家を選ぶことが重要です。初回相談を無料としている事務所も多いため、複数の事務所で相談して費用見積もりを比較検討することをお勧めします。
破産手続きとの費用比較で見る経済的メリット
特別清算の費用面での最大のメリットは、破産手続きとの大幅な費用差にあります。
破産手続きの場合:
・予納金:最低20万円(管財事件では70万円以上)
・総費用:200万円超のケースも多数
特別清算の場合:
・裁判所費用:3~7万円程度
・総費用:100~150万円程度で完了
約半額での手続きが可能です。また、
特別清算では、破産手続きにおける否認権がないため、破産管財人による財産回復手続きが不要となり、これに関連する調査費用や訴訟費用も発生しません。手続きが簡素化されることで弁護士の作業時間も短縮され、結果的に弁護士費用の抑制につながる場合があります。
ただし、特別清算では債権者集会で協定案の可決が必要となるため、債権者との協議が難航し協定が不成立となった場合、特別清算から破産へ移行する可能性があります。この場合、二重の費用負担が生じるリスクがあるため、事前の債権者との調整や同意取得の見込みを慎重に検討することが重要です。
費用面でのメリットを最大化するには、事前の準備と債権者との円滑な調整が不可欠です。経験豊富な専門家のアドバイスを得ながら、適切な手続き選択と効率的な進行を図ることで、手続きの成功率を高めることができます。
まとめ|特別清算で中小企業の適切な事業整理を実現する
特別清算は、債務超過に陥った中小企業が適切な事業整理を行うための有効な選択肢です。破産と比較して信用毀損を最小限に抑えながら、経営陣主導での柔軟な清算手続きを実現できる点が最大の特徴といえます。費用面でも大幅な削減が可能で、手続き期間も短縮できることから、条件が整えば中小企業にとって非常にメリットの多い制度です。
ただし、株式会社のみの利用制限や債権者の3分の2以上の同意という厳格な要件があるため、活用できる場面は限定的です。親子会社間の整理、事業譲渡後の清算、不採算部門の分離清算など、関係者の協力が得やすい状況で真価を発揮します。
事業継続が困難になった際は、早期に専門家に相談し、特別清算の可能性を含めた最適な解決策を検討することが重要です。適切な判断により、企業価値を最大限に保護しながら円満な事業整理を実現できるでしょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。