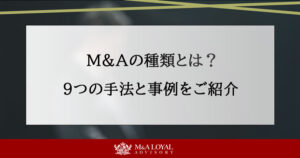退職所得とは?税制優遇の仕組みとM&Aでの活用ポイントを徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
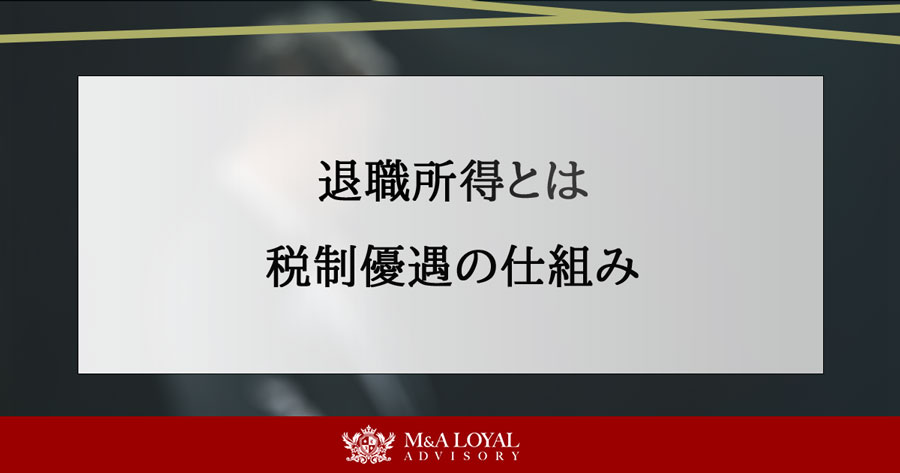
退職所得とは、退職時に勤務先から受け取る退職手当などの所得を指します。通常の給与所得とは異なり、税務上の優遇措置が設けられている点が特徴です。
また、M&Aの場面では、退職手当の支給が節税戦略として用いられることもあります。ただし、受け取り方や勤続年数、役職などによって課税の扱いは変わるため、正確な理解が求められます。
本記事では、退職所得の定義や課税方法、M&Aにおける活用方法までを網羅的に解説します。
目次
退職所得とは
まず、退職所得に関する基本的な知識について解説します。
勤務先から受ける退職手当などの所得のこと
退職所得とは、退職を理由として勤務先などから受け取る退職手当などの所得を指します。給与や賞与とは性質が異なり、長年の勤務に対する慰労や功労を目的とした支給です。
なお、退職所得として課税されるのは、退職しなければ支払われなかった金銭であり、退職に起因して一時に受け取るものである必要があります。
なお、他の従業員にも共通して支給される賞与などと同様の性質を持つ場合は、退職時の支給であっても退職所得ではなく給与所得として課税される点に注意が必要です。
退職手当と退職所得の違い
退職手当とは、従業員が退職する際に勤務先から支給される金銭のことです。退職金や退職慰労金とも呼ばれます。
一方、退職所得という言い方は、税務上の所得区分の一つです。退職手当は実際に支払われる金額の名称であり、退職所得はその金銭をどのように税務処理するかという観点で分類された所得区分です。
また、厳密には退職所得には退職手当以外も含まれます。
退職手当の定義
退職手当は法律上の支給義務はありません。ただし、多くの企業では就業規則や退職手当の規程を設け、一定の勤続要件を満たした従業員に対して退職手当を支給しています。これは長期的な勤続を促し、従業員のモチベーション向上につなげる制度的役割を果たしています。
なお、役員に対して支払われる退職手当は「役員退職慰労金」と呼ばれ、会社法や定款などに基づき支給されます。通常、株主総会の決議または取締役会の一任によってその金額が決定されます。
退職所得に該当するその他の一時金
退職所得に該当するのは退職手当だけではありません。例えば、確定給付企業年金法や厚生年金保険法などに基づき、退職に伴って支給される一時金も退職所得として扱われます。
さらに、法人税法上の適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金(自己負担分を除く)や、特定退職金共済団体による共済金のうち一定のもの、独立行政法人が支給する中小企業退職金共済金や小規模企業共済金なども該当します。
また、確定拠出年金における老齢給付金のうち一時金として支給されるものも同様です。いずれも共通しているのは、退職を直接の原因として支給される性質を持っている点です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



退職所得の税務上の取り扱い
退職所得の税務上の取り扱いについて解説します。
分離所得として税務上は優遇される
退職所得は税務上、分離課税の対象となり、他の所得とは合算せずに個別に課税されます。
この取り扱いにより、退職所得は大幅な税制優遇を受けられる仕組みとなっています。
具体的には、まず「退職所得控除」として、勤続年数に応じた金額が非課税とされ、さらに控除後の金額のうち半分のみが課税対象となります。このような制度設計は、退職が一時的に多額の所得を生じさせる点や、長年の勤務に対する功労の性質を考慮したものです。そのため、通常の給与所得などと比較して、実効税率は非常に低く抑えられる傾向があります。
退職所得に課される税金
退職所得には、所得税・住民税・復興特別所得税の3種類の税金が課されます。 給与などと同様に課税対象ですが、課税方法や控除制度が異なり、税務上は優遇されています。
所得税
退職所得には、所得税が課されます。ただし、その課税方法は給与所得とは異なります。
日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど税率も上がります。しかし、退職所得は「分離課税」の対象となるため、給与など他の所得と合算せず、独立して税額を計算します。また、退職所得控除が適用される上、控除後の金額の2分の1のみが課税対象となる仕組みです。
この優遇措置により、実質的な税負担は通常の給与所得よりも軽減されます。なお、退職手当が支給される際には、原則として「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、所得税は源泉徴収で精算され、確定申告は不要です。
ただし、この申告書が提出されていない場合や、支給額が特例の範囲を超える場合には、確定申告が必要となることがあります。また、医療費控除や寄附金控除を適用する際は、申告が必要となる場合があります。
住民税
退職所得には、所得税と合わせて住民税も課されます。住民税とは、個人の所得に対して地方自治体に納める税金で、都道府県民税および市区町村民税から構成されます。
住民税の所得割は全国一律で10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)となっており、所得税のように累進課税ではありません。これに加えて、均等割と呼ばれる定額課税(標準で年額5,000円)も併せて課されます。
退職所得については、退職所得控除後の課税対象額に対して住民税10%が適用されます。税額計算は地方税法に基づいて行われ、原則として会社側が源泉徴収するため、受給者が個別に申告する必要は基本的にありません。
ただし、確定申告を行う場合は、住民税の申告内容とも整合させる必要があります。
復興特別所得税
復興特別所得税は、平成25年から令和19年末までの間に限り、全ての納税者に課される臨時的な税金です。この税金は、東日本大震災からの復興費用を賄うことを目的として創設されたもので、基準となる所得税額に対して2.1%が上乗せされます。
退職所得に関しても、所得税が課される金額に応じて復興特別所得税が加算される仕組みとなっており、所得税と合わせて源泉徴収されることが一般的です。従って、退職手当に係る税金の総額は、実質的には「所得税 + 復興特別所得税」の合計額にあたります。
確定申告の必要がある場合は、復興特別所得税も併せて計算・申告・納付する必要があります。
退職所得の課税対象額の計算方法
退職所得の課税対象額は、退職手当などの収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1を課税対象とする特別な計算方式が採られています。具体的な計算式は次のとおりです。
- 退職所得の課税対象額 =(退職手当 − 退職所得控除額)÷ 2
例えば、退職手当が1,200万円で控除額が400万円の場合、退職所得の課税対象額は400万円です。ただし、勤続年数が5年以下の場合は、この「2分の1課税」が認められないケースがあるため注意が必要です。
また、年の途中で退職した場合も、月単位ではなく切り上げて年数計算されるため、正確な勤続年数の把握が重要です。 実務上は源泉徴収の段階で自動的に処理されますが、特例の適用要件や控除計算には注意が必要です。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額とは、退職手当に対して課税される金額を計算する際に控除される非課税枠のことです。
この控除額は、退職者の勤続年数に応じて定められており、勤続期間が長いほど控除額も増加します。計算式は勤続年数に応じて次のように異なります。
- 勤続年数が20年を超える場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数
ただし、どのような場合でも80万円を下回る場合には、一律で80万円が控除額とされます。例えば、勤続年数が1年であっても、40万円ではなく80万円が適用されます。
また、勤続年数に端数がある場合は切り上げて計算されるため、「10年2カ月」は「11年」として扱われます。
退職所得にかかる所得税の計算方法
退職所得にかかる所得税は、退職所得控除後の金額の2分の1に対して、所得税の速算表に基づいて計算します。
例えば、退職手当が1,800万円で控除額が1,150万円、退職所得が325万円の場合、税率10%、控除額97,500円となり、所得税は次のとおり求められます。
- 所得税:(325万円 × 10% − 97,500円)= 227,500円
さらに復興特別所得税(2.1%)が加算されるため、最終的な税額は次のとおりです。
- 復興特別所得税:227,500円 × 2.1% ≒ 4,777円
- 最終的な税額:227,500円 + 4,777円 = 232,277円
なお、課税される所得金額ごとの税率と控除額(所得税の速算表)は次のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:所得税の税率(国税庁)
受け取り方や在職年数による課税上の注意点
退職所得に対する税金は、受け取り方や在職年数などによって大きく異なります。
受け取り方による税務の違い
一時金として一括で受け取る場合
これまで解説したとおり、退職手当を一時金として一括で受け取る場合は、「退職所得」として扱われ、分離課税が適用されます。
計算方法は既に解説したとおりです。
年金として分割で受け取る場合
退職手当を年金として分割で受け取る場合は、「雑所得」として総合課税の対象に該当します。この場合、退職手当は他の年金収入(国民年金・厚生年金など)と合算して課税され、公的年金等控除を適用した後の金額が課税対象です。
控除額は年齢や受給額に応じて変動し、計算は一時金と比べてやや複雑です。例えば、年齢が65歳以上の場合は控除額が増えるため、同じ年金額でも税負担が軽減される場合があります。
分割受け取りの利点は、長生きすれば総受給額が増える可能性がある点ですが、税務面では一時金よりも不利になるケースが多いといえます。安定的な生活資金の確保を優先する場合や浪費を避けたい場合には、有効な選択肢です。
短期間で退職した場合の税務の違い
役員が短期間で退職したケース
役員が在職期間5年以下で退職した場合、退職手当は「特定役員退職手当等」として扱われ、通常の退職所得と異なる課税方法が適用されます。
最大の注意点は、退職所得控除を適用できる一方で、控除後の金額に対して「2分の1課税」が認められない点です。例えば、役員として4年間勤務し、退職手当が500万円だった場合、退職所得控除額は160万円(40万円 × 4年)となり、課税対象は340万円です。
また、「4年3カ月」や「4年6カ月」のような端数がある場合は、切り上げて「5年」として扱われるため、控除額が200万円となり、課税対象額が300万円に軽減されるケースもあります。
従業員が短期間で退職したケース
従業員が5年以下の短期間で退職した場合、支給される退職手当は「短期退職手当等」として分類されます。なお、2022年以降は課税計算に特例が設けられています。
退職手当から退職所得控除額を差し引いた後の金額が300万円以下であれば、通常どおり「差額 × 1/2」が課税退職所得です。一方、300万円を超える場合は「150万円 +(退職手当 −(300万円 + 退職所得控除額))」の式に基づいて課税されます。
例えば、退職手当1,000万円、勤続5年で控除額200万円の場合、課税退職所得は「150万円 +(1,000万円 − 500万円)= 650万円」です。この特例は過度な節税対策を抑制する趣旨があり、短期退職時の税負担が相対的に重くなる傾向があります。
退職所得と確定申告の関係
退職所得と確定申告の関係について解説します。
確定申告は原則不要
退職手当を受け取った際、原則として確定申告は不要です。多くのケースでは、退職時に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しており、その情報を基に会社が退職所得控除を適用し、適切な源泉徴収を行います。
この書類は、勤続年数に応じた退職所得控除の算定に必要なため、提出がなければ一律20.42%の税率で源泉徴収されます。申告書を適切に提出していれば、税額は自動的に精算され、通常は確定申告を行う必要はありません。
ただし、提出漏れや申告内容に誤りがある場合には、後日確定申告が必要になることがあります。
確定申告で税金が還付されることがある
退職後に年内で再就職しなかった場合や、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合は、確定申告によって税金が還付される可能性があります。
退職手当に対する所得税は、一律で20.42%が源泉徴収されることがありますが、勤続年数に応じた退職所得控除や分離課税の仕組みを反映すれば、本来の課税額はそれよりも軽減されることが多くあります。確定申告を行うことで、控除を適切に反映させ、過剰に徴収された税額の還付を受けられます。
また、退職後の年収が大きく減少した場合も、源泉徴収された税額が過大となることがあり、その際にも申告によって差額の還付が期待できます。確定申告が義務でないケースでも、税負担を見直す有効な手段です。
M&Aにおける退職手当を用いた節税手法
M&Aにおける退職手当を用いた節税手法について解説します。
退職金スキームと呼ばれ、活用が進んでいる
M&Aにおいて、株式譲渡の対価の一部を役員退職慰労金として処理することで、売り手側・買い手側の双方に税務上のメリットをもたらす手法を「退職金スキーム」といいます。
具体的には、売り手側の役員に対して退職手当を支給し、その金額を企業から事前に支出した上で、残額を譲渡対価として受け取る流れです。
買い手側のメリット
買い手側にとって、退職金スキームを導入する最大のメリットは、買収資金の圧縮と税務上の損金処理です。
このスキームでは、売り手側が株式譲渡の前に役員退職慰労金を支給します。その結果、売り手側の純資産は退職金の支出分だけ減少し、株式評価額も低下します。買い手側は退職金支給後の状態で株式を取得するため、買収価格を抑えられます。
また、退職金は売り手側が支出するため、退職金の分は株式譲渡対価から控除される構造となり、買い手側の実質的な手出し資金も減少します。
さらに、適正な金額で支給された役員退職慰労金は損金算入が可能であり、退職金が発生した年度の課税対象となる所得を減らす効果があります。加えて、退職金によって赤字となった場合は、一定の要件の下でその損失を繰越欠損金として翌年度以降に活用できる可能性もあります。
売り手側のメリット
売り手(譲渡側)の最大のメリットは、手取り金額の最大化です。通常、株式譲渡益には一律20.315%の税率が課されます。ただし、勤続年数が5年以上の場合は、退職手当として受け取った金額には退職所得控除および2分の1課税が適用されるため、税負担が大きく軽減されます。
勤続年数が長いほど控除額が大きくなるため、場合によっては課税対象が大幅に縮小され、実効税率が大きく下がる可能性があります。ケース次第ですが、退職手当として受け取ることで、株式譲渡よりも手取りが数百万円単位で増えることもあります。
また、M&Aに伴い経営から退く正当な理由があるため、退職手当の支給に対する税務上の合理性も確保しやすい点が特徴です。
失敗するとどうなるか
退職金スキームは節税効果の高い手法ですが、設計を誤ると多額の追徴課税や否認リスクが発生する可能性があります。特に注意すべきは、支給する退職手当の「金額の妥当性」です。
過大な退職手当と認定された場合、その一部または全部が損金算入できず、所得税や法人税の対象となるほか、譲渡所得として再評価される恐れがあります。
また、形式的には退職していても実質的に引き続き業務に関与していた場合など、税務署から「退職」とみなされないケースもあり得ます。慎重な設計と専門家の助言の下で進めることが求められます。
退職手当以外の節税方法
生命保険を活用する
生命保険を戦略的に活用することで、納税資金の確保や相続税の節税が可能です。経営者が法人契約で生命保険に加入し、死亡保険金を法人または後継者が受け取る形にすれば、現金化困難な自社株などを手放さずに納税できます。
法人税上も、一定条件の下で保険料を損金算入できるため、保険設計次第で法人・個人双方にメリットがあります。ただし、契約形態や受取人によって課税対象が異なるため、税務上の精査が大切です。
事業承継税制を利用する
事業承継税制は、中小企業の経営者が後継者に自社株を贈与または相続する際、贈与税や相続税の納税を猶予・免除できる制度です。
要件を満たせば100%の納税猶予が認められ、一定期間の代表就任などの条件を満たすと最終的に免除されることもあります。これにより、多額の納税負担による資金流出を防ぎつつ、円滑に事業承継を行えます。
ただし、事前認定や継続報告などの事務負担があり、制度の取り消しリスクもあるため、専門家の関与が推奨されます。
相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与において、2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。超過分には一律20%の税率が適用されますが、贈与財産は将来の相続時に合算されて相続税が課税されます。
2024年からは年間110万円の基礎控除も導入され、さらなる活用が可能です。ただし、一度選択すると撤回できず、他の特例との併用制限もあるため、慎重な検討が求められます。
不動産を購入する
事業承継の過程で法人が不動産を取得することで、減価償却費を活用して法人税の圧縮を図れます。
また、不動産は相続税評価額が時価より低くなる傾向があるため、相続や贈与における資産移転の手段として有利です。後継者への贈与においても、株式より税負担を抑えられる場合があります。
ただし、不動産取得税や固定資産税の負担、資産の流動性の低さなど、長期的な資産管理を前提に活用すべきです。
M&Aのスキームごとの退職手当の扱い
M&Aにおける退職手当の扱いについて、代表的なスキームである「株式譲渡」と「事業譲渡」に分けて解説します。また、それぞれのケースにおいて、「社員・従業員」と「役員・社長」で退職手当の取り扱いがどのように異なるのかを説明します。
株式譲渡
株式譲渡とは、売り手企業の株主が株式を買い手に譲渡することで、会社の経営権を移転するM&A手法です。法人格や雇用契約、各種契約関係は変更されないため、従業員の雇用や退職手当の制度にも直接の影響はありません。
一方、役員に対しては、譲渡と同時に退任する場合などに、株式譲渡対価の一部を退職手当として処理することで、節税効果も得られます。株主総会決議などが必要となるため、適切な設計が求められます。
社員・従業員
株式譲渡では会社の法人格に変更がないため、従業員の雇用契約はそのまま継続されます。
雇用条件や就業規則、退職手当規程も基本的に維持されるため、従業員にとって直接的な変化はありません。退職手当の支給も、従前の制度に基づいて、退職時に支給されます。
M&Aの実施自体が退職の原因とはならないため、退職手当が譲渡時に支払われることも通常ありません。ただし、経営方針の変更や配置転換などにより、将来的に退職を選択する従業員が出た場合には、従来の勤続年数を基に退職手当が算定されます。
役員・社長
株式譲渡により経営権が移転する場合でも、社長や役員が引き続き在任する限り、退職手当は支給されません。ただし、譲渡後に退任する場合や事業承継として社長が退く場合には、退職手当の支給が検討されます。
一般的には、譲渡前に役員退職慰労金として支給されることが多く、株主総会の決議が必要です。前述のとおり、退職手当を譲渡対価の一部として位置付けることで、売り手企業の節税、買い手企業のコスト圧縮にもつながるため、双方にメリットがあります。
なお、退職後に買い手企業の役員に就任する場合、再就任によって新たな在任期間が始まることから、旧会社での退職手当との分離管理が必要です。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を第三者に譲渡するM&A手法で、法人格は維持されるものの、対象事業に付随する資産・契約・人員などを個別に移転させる必要があります。
雇用契約も自動的に移行しないため、従業員は原則として一度退職し、譲渡先との再契約が必要です。この点が株式譲渡との最大の違いであり、退職手当の取り扱いにも大きく影響します。
社員・従業員
事業譲渡においては、売り手企業の従業員は原則として雇用契約が終了し、買い手企業との間で新たな雇用契約を締結する必要があります。この際、従業員の退職手当の取り扱いは次の二つに分かれます。
- 譲渡前に売り手企業が退職手当を精算する
- 買い手企業が売り手企業分を引き継ぐ
前者では売り手企業の退職手当制度に基づき支払われ、資金負担が生じます。一方、後者では退職手当の債務を買い手企業が承継し、譲渡金額から控除される形で調整されます。
どちらの方法を採用するかは、M&A契約時の交渉により決定され、従業員の合意や転籍同意書の取り交わしが必要です。退職手当の債務の引き継ぎ可否や譲渡後の処遇は、従業員との信頼関係にも影響するため、事前に丁寧な説明が求められます。
役員・社長
事業譲渡により会社の一部または全部の事業が売却される場合でも、社長や役員が退職しない限り、退職手当の支給は発生しません。しかし、譲渡を機に役員が退任する場合は、株主総会の決議を経て役員退職慰労金を支給できます。
事業譲渡の場合、買い手企業で役員として再任されるケースでは、売り手企業での退職が正式に成立するため、退職手当が課税対象です。金額は功績倍率などに基づき算出されますが、過大な支給は損金不算入とされるリスクがあるため、合理的な水準に抑える必要があります。
M&Aにおいて退職手当を取り扱うときのポイント
M&Aにおいて退職手当を取り扱うときのポイントは次のとおりです。
- 役員退職慰労金は適切な金額を算出する
- 退職手当の制度を速やかに統合・整理する
- 資金繰りを考慮して準備を進める
それぞれについて解説します。
役員退職慰労金は適切な金額を算出する
M&Aに際して役員退職慰労金を支給する場合、多くの企業では役員退職慰労金規程に基づいて算出され、株主総会の決議が必要です。規程がない企業もありますが、税務上の妥当性や透明性を担保するためには規程に従うことが原則です。
税務面では過大な退職手当は損金算入が否認される恐れがあり、「功績倍率方式」での算出が一般的です。これは「退職時の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」で計算され、倍率は役職や業務内容により設定されます。
妥当な金額を導き出すには、同業他社の水準や専門家の助言を参考にする必要があります。
退職手当の制度を速やかに統合・整理する
売り手企業と買い手企業では、退職手当の制度や支給基準が異なることが一般的です。
M&A後も複数の制度を併存させると、手続きの煩雑化や公平性の問題が生じやすいため、早期に制度統合を図ることが望まれます。買い手企業が制度統合を主導し、可能であれば売り手側で退職手当の制度を一度精算し、整理しておくと円滑です。
ただし、制度変更が従業員に不利益を与えることがないよう慎重に進める必要があり、説明会や個別面談を通じて理解と納得を得る努力が求められます。
資金繰りを考慮して準備を進める
退職手当は通常高額となるため、事前に資金繰りを確認し、無理のない範囲で準備を進めておくことが不可欠です。特に退職手当の積立が不十分なまま支給すると、売り手企業のキャッシュフローに深刻な影響を与える可能性があります。
M&Aスキームによって退職手当の扱いや支払タイミングは異なるため、買い手企業との交渉の中で、負担の所在や支払い方法を明確にすることが重要です。支払い原資の確保や、譲渡価格における退職手当の債務の控除などを念頭に、事前準備を徹底しておく必要があります。
退職所得に関するQ&A
最後に、退職所得に関するよくある質問とその回答を紹介します。
複数の会社から退職手当を受け取った場合、税金の計算はどうなるか
同一年中に複数の会社や基金などから退職金を受け取る場合、それらの金額を合算して課税対象額を計算する必要があります。
この際、最も長く勤めた勤務先の在職期間を基準とし、他の会社での重複しない期間も加算して通算勤続年数を算出します。
後から退職金を支払う会社は、先に受け取った退職金の金額や勤続年数を含めて源泉徴収税額を計算する必要があります。そのため、受給者は「退職所得の受給に関する申告書」と先の退職先の源泉徴収票を提出しなければなりません。
これを怠ると、正しい控除が適用されず、余分に税金が引かれてしまう可能性があります。
会社都合退職と自己都合退職の違いとは何か
M&Aや会社売却に伴う退職は、会社都合退職と自己都合退職に分けられます。
会社都合退職とは、解雇や退職勧奨など、労働者の意思によらず雇用契約が終了するケースです。一方、自己都合退職は、労働者が自らの判断で退職する場合を指します。会社都合退職と判断された場合、失業保険の給付が早期に開始され、給付額も増えるなどの保護が受けられます。
M&Aによって自発的に退職する場合、原則として自己都合退職とされますが、勤務地の大幅変更や賃金の著しい減額など労働条件の変更を理由に退職する場合には、会社都合退職と認定される可能性があります。
海外駐在員の退職所得にかかる税金はどうなるか
退職手当に対する課税は「居住者」と「非居住者」で取り扱いが異なります。居住者とは「日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある個人」のことで、非居住者は「居住者以外の個人」のことです。
非居住者に該当する駐在員が受け取る退職手当は、日本国内源泉所得とされる部分に対し20.42%の源泉徴収が課されます。また、役員退職慰労金は国内勤務分が全額が国内源泉所得とみなされます。
居住者が退職手当を受け取る場合には、申告書を提出することで大きな優遇措置を受けられ、税負担が軽減されます。これに対応するため、非居住者でも「退職所得の選択課税」制度を用いれば居住者と同様の税額計算が可能です。
制度利用により源泉徴収分の還付を受けられる可能性があります。ただし、制度を利用する際は確定申告が必要で、納税管理人を通じた手続きも求められます。
みなし退職金とは何か
みなし退職金とは、実質的に退職したとみなされる場合に支給される退職手当で、常勤役員が非常勤となるケースや、事業承継、M&Aによる退任時などで用いられます。
税制上は退職所得として扱われ、給与所得に比べて大きな優遇措置があり、節税対策として有効です。企業はこれにより退職給与引当金を計上でき、財務健全性の向上も見込めます。
適用にあたっては、就業規則や退職手当の規定との整合性を確認し、税務署の審査リスクも念頭に置く必要があります。なお、4年以内に別の退職手当を受け取っている場合、控除額が調整される点にも注意が必要です。
退職手当と役員報酬の違いは何か
退職手当と役員報酬は、いずれも法人から個人に支払われる金銭ですが、支給の目的と税務上の取り扱いが異なります。
退職手当は、過去の在職期間に対する功労や貢献に報いる性格のものであり、退職後に一括して支給されることが一般的です。
これに対し、役員報酬は在職中の業務に対する対価であり、定期的・継続的に支払われるものであるため、給与所得として総合課税の対象に該当します。
退職所得以外の課税所得とは何か
退職所得以外にも、税務上「課税対象」となる所得は多岐にわたります。
主なものに、給与所得(給料や賞与など)や事業所得(個人事業主の売り上げなど)、不動産所得(賃料収入)、配当所得(株の配当)、利子所得(預金利息)、一時所得(保険の解約返戻金など)などがあります。
退職所得と一時所得の違いは何か
退職所得と一時所得は、いずれも一時的に得られる収入ですが、税務上の取り扱いが大きく異なります。
退職所得とは、勤務先からの退職手当や功労金など、雇用契約の終了に伴って支払われる所得であり、大きな優遇措置が設けられています。
一方、一時所得は、労務の対価や資産の譲渡以外で、かつ継続性のない所得が対象となり、例えば懸賞金や生命保険の一時金などが該当します。一時所得には特別控除(最高50万円)があるものの、退職所得のような大きな優遇措置はありません。
分離課税と総合課税の違いは何か
所得税には「総合課税」と「分離課税」の二つの課税方式が存在します。
総合課税は、給与所得や事業所得など複数の所得を合算し、累進税率に基づいて課税される仕組みで、所得が多いほど高い税率が適用されます。給与所得や事業所得、不動産所得、一時所得などは総合課税の対象です。
一方で、上場株式の配当や譲渡益、一定の土地・建物の売却益などは分離課税に分類され、他の所得と切り離して別の税率で計算されます。
まとめ
退職所得は、退職時に受け取る特別な所得であり、税制上の優遇措置があるため、上手に活用すれば税金を抑えることができます。しかし、退職所得の税務処理は勤続年数や役職によって異なるため、誤解を避けるためにも事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
具体的なケースに応じたアドバイスを受けるためには、税理士や専門家に相談することをお勧めします。正しい情報を手に入れて、退職所得を最大限に活用しましょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。